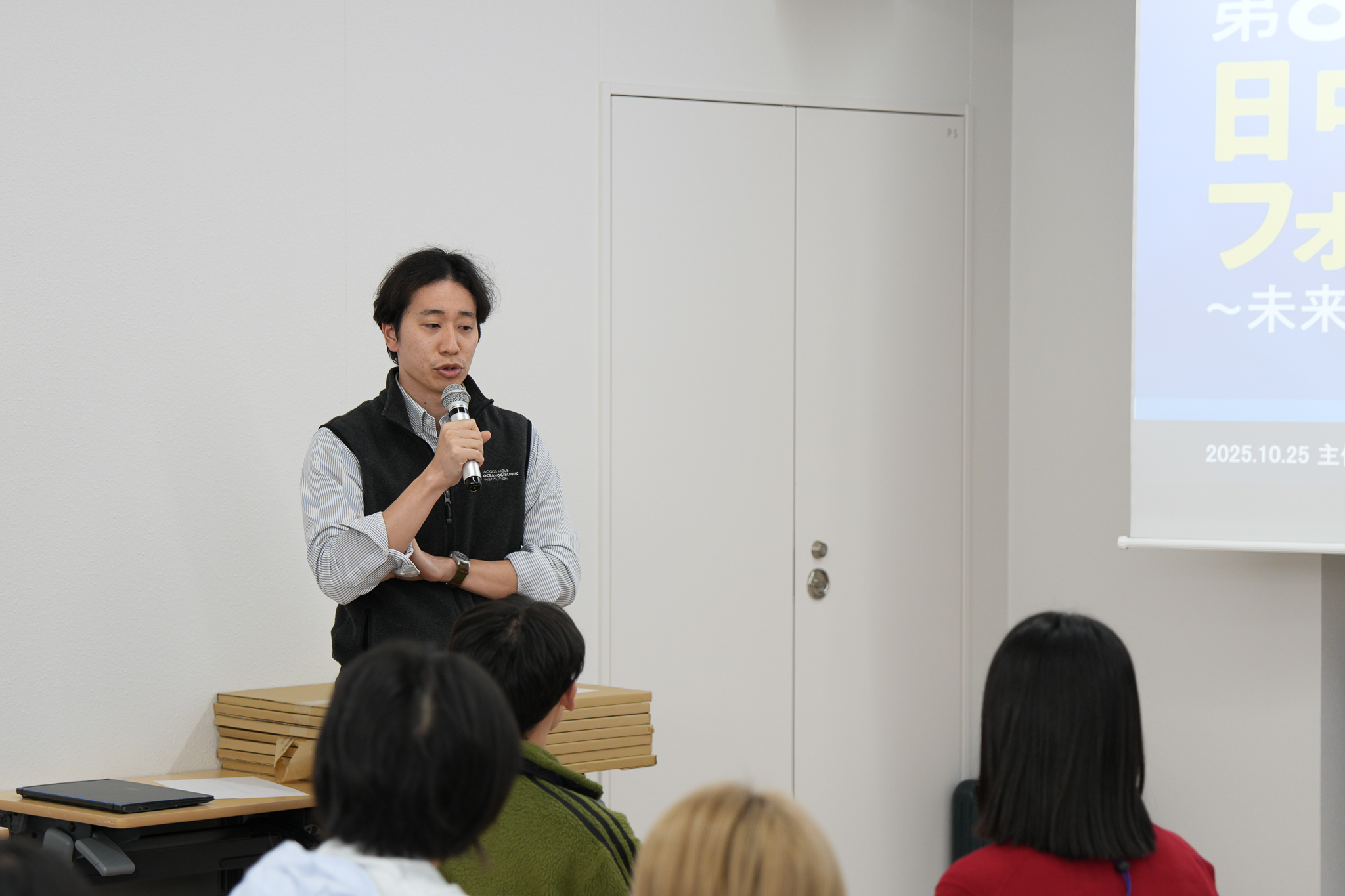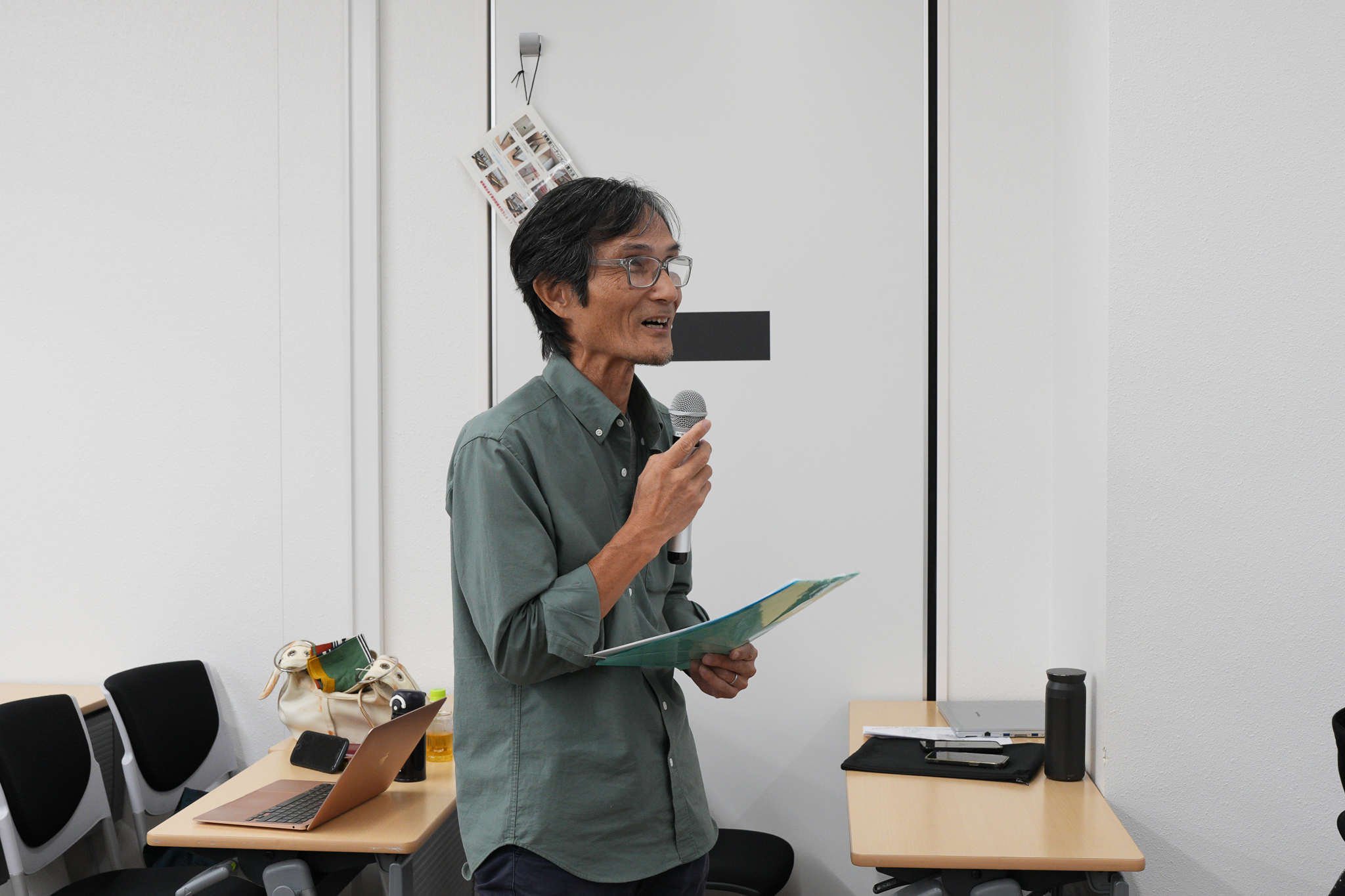2025年10月25日(土)、「日中未来創発ワークショップin福岡」が福岡市で開催されました。
このイベントは、笹川平和財団(理事長:角南篤氏)が、九州大学大学院農学研究院、日本科学協会、日中関係学会と、学生団体「茶話日和」「京論壇」「中国言語文化研究会」の協力を得て開催する交流型ワークショップです。
当日は、「未来の環境と私たち」をテーマに、専門家による講義、カードゲーム、グループワークなどを通じて、これからの社会で起こり得る変化を捉えながら日中の互いの視点や価値観を理解し合い、10年後の環境保全への関わりかたについてアイデアをまとめ、参加者全員で共有しました。参加したのは、日本人の高校生・大学生・大学院生、中国からの留学生など合計38名です。
開会にあたり口火を切ったのは、本イベントの総合司会を務める、于智爲さん。本日のねらいと1日のスケジュールを説明したのち、同財団の笹川日中友好基金 特任グループ長 尾形慶祐氏を紹介。壇上に立った尾形氏は本フォーラムの主催者代表として、このようにあいさつします。
尾形氏 今日は、皆さんにお会いできて大変光栄です。本フォーラムでは毎回、皆さんが自分自身の課題として捉えやすく、かつ日中双方に共通するテーマを選んできました。 本日は、「未来の環境と私たち」というテーマのもと、現在何が起きているのかをしっかり学びながら、これからの社会の姿をともに思い描き、今から未来に向けて私たちにできることを考えてみたいと思います。ディスカッションを通じて、自分と相手の考え方の違いに気づく場面もあるかもしれません。そのようなときには、相手の背景や立場にも思いを巡らせながら、お互いの理解を深めるきっかけとしていただければ幸いです。
参加者同士が自己紹介する時間が設けられたのち、さっそく基調講演が始まります。講師を務めたのは、名桜大学 国際学部の田代豊教授。『人と自然・環境の関わり―「美しい海の景観」を測る―』をテーマに、田代教授は「何のために自然を守るのか」と問いかけながら、自然を保護するための「美しさ」の測り方について、参加者に解説します。
田代教授 「自然を守ることは大切」とよく言われますが、何のためでしょうか。それは、自然界に生息する生き物のため、あるいは私たち人間の暮らしにも役立つ生態系サービスを守るためだけではありません。世界には圧倒されるような自然があります。それを目の当たりにしたとき、私たちは感動を覚えますし、この素晴らしさを守らなければ、という思いも芽生えるでしょう。つまり、私たちの精神にも影響を与えるものであることもまた、自然を守る一つの理由になり得るでしょう。
自然の美しさを守る取り組みの一つに、ユネスコの世界遺産があります。その認定を受けるためには守るに値する美しさがあるのかどうか、測る必要があります。その基準をどう決めるのか、いろいろな研究が行われています。たとえば、人工物をどの程度許容するのか、そのための指標をつくったり、アンケートを行ったりとさまざまです。
環境を守ろうと語るとき、生き物を中心にすることが多くあります。しかし、世の中の同調はあまり広がっていません。なぜなら、爬虫類や両生類が苦手な人に「生き物が大事」と話しても、さほど響かないからです。けれども、「水が透き通っていて綺麗だから」のように、人間の視点になることで守る意味が直接的に伝わってきます。
「景観」という形で現れた自然や環境の価値を、守ることは重要です。そのためには、その価値を明確にして共有できる社会にする必要があります。価値を理解しやすい形にし、声にすることが大事なのです。

田代豊教授(名桜大学国際学部)
「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲーム
続いて行われたのは、海洋ごみの削減に挑戦する『CHANGE FOR THE BLUEカードゲーム』です。
参加者全員が一つの町の住民になって、今後10年間(4ターム)でごみをどれだけ減らせるのかに挑戦します。
六つある各テーブルに配られたのは、「仕事カード」と「生活カード」の2種類。参加者はどのカードをいつ使うのかを話し合って決めます。選択したカードによって、町の状態は変化するのですが、同じカードであっても使うタイミングによって結果は変わります。町の状態は、①ゴミに対する住民の意識の高さを測る「市民意識」、②町にあるゴミを取り除くための「技術力」、③町の「便利さ」、④「ごみ・汚れ」の状況――の4つの指標で評価され、タームごとに数値で確認できます。
いよいよゲームがスタート。参加者は、「車に乗らない暮らし」「お買い物は自転車で」「洗剤を使わず洗濯しよう」などが書かれた生活カードを見比べながら、話し合いを始めます。一方、たとえば、木こりの仕事カードには、「森は大事だから木を切らない」「とにかくたくさん木を切ろう」のように、正反対のことが書かれていたりも。参加者は、カードに書かれた暮らしをときに想像しながら、1枚を選択。ごみを減らすことに成功したチームからは自然と拍手が沸き起こります。しかし、「市民意識」が上がるにつれ、「便利さ」が下がると、次のタームでは不自由さを訴える市民が出てきて、「市民意識」が下がる現象が起きてしまいます。すると、最終タームでは、「便利さを上げよう」という声が各テーブルからあがるなど、楽しみながら活動する様子が見られました。そして10年後、町の状態は、「市民意識」と「技術」が高まり、「ごみ・汚れ」を減らすことに成功。
この結果について、ファシリテーターを務めた石川千里さんは、このように講評します。
石川氏 皆さんのまちは、「市民意識」が高いので、非常に管理されている状況になっています。要は、ちょっと不便なんですね。実際に、ゴミ捨て用のシールは家庭ごとに年間何枚と決められていて、その数を超えてゴミを捨てる場合はお金を払わなければならない自治体も存在しています。ゴミや汚れがなくなるのはとても良いことですが、「この町に住みたいですか?」と聞かれたとき、「便利さはどうなのかな」と考えてしまうかもしれませんね。
今日の結果は皆さんの行動が生み出したものです。その行動は、皆さんの価値観、考え方に紐づいています。このゲームの「市民意識」とは、ゴミ問題の解決に向け、どんな行動が取れるのか、を表しているともいえます。しっかり学んだり感じたりすることが行動につながるのですが、仲間が増えるといろいろな対応ができるようになる。つまり、発展があることを示唆しているのです。まずは知ることから行動につなげてほしいと願っています。

石川千里氏(「CHANGE FOR THE BLUE」ゲームファシリテーター)
さらに、笹川和平財団 海洋政策研究所 研究員 田中広太郎氏は、プラスチック排出規制に関する国際条約のルール策定の過程に触れながら、他者理解の重要性を参加者に説きます。
田中氏 2022年の国連環境総会で、プラスチックの排出規制に関する国際条約をつくる方針が合意されました。しかし、政府間で話し合うもルールをまとめるには至りませんでした。なぜなら、排出管理だけじゃなく、つくる量も削減しようという意見に対し、産油国が難を示したりと、なかなか溝が埋まらなかったのです。もっというと、国際会議は全会一致が原則です。一人でも反対意見があるとそこで止まってしまいます。賛成している国だけで進めたとしても、問題の根幹には踏み込めないので実効性に疑問符が付きますし、みんなが賛成できるルールにすると、あっさりしたものが出来上がってしまい、意味あるものになるのか疑わしくもなってしまいます。
ここで私がお伝えしたいのは、ルールを決めることは「難しい」ということです。だからといって、相手を責めたり、考えの違いを嘆いたりするのではなく、それぞれの文化や経済や価値観を尊重し合うことが大切です。これは人同士もそうだし、国同士でもそうなのだと思います。

田中広太郎氏(笹川和平財団海洋政策研究所研究員)
このあとは午前の会場となった今津公民館からほど近い長浜海岸までフィールドワークへ。参加者は、「白い砂浜が続く美しい海岸線は、地域ボランティアによる定期清掃によって保たれている」と、事務局スタッフの説明を受けます。ここでは記念撮影も行われました。
午後は、九州大学伊都キャンパスに場所を移します。昼食を挟み、プログラムはグループワークへ。ここではまず、「未来の環境」についての課題をポストイットに書き出し、チームごとに課題をシェア。そのなかから一つのテーマを決め、発表内容を模造紙に表現していきます。
参加者は課題の概要や背景、解決策についてお互いに意見を交わしながら情報を整理。ときにスマートフォンを使って情報を補完しながら、自由に探究します。
こうして完成した各チームの発表内容は下記のとおりです。
グループ1:The Future of our Environment and Industries
工業による大気汚染、水質汚染、土壌汚染等は、健康被害や環境被害を招いています。これらの被害を防ぐためには三つの対策が考えられます。まずは、「国内の法律による制限」です。関係各省が意思統一を図り、工場から排出される有害物質を減らしていくこと、工業をより健康的なものにしていくことが日本の目指すところです。一方、中国の工業も監視体制の強化を図り、有害物質を出さないようにしていくことが求められます。続いて、「国際的なルール形成による制限」が挙げられます。たとえば、国境を越えて広がる大気汚染については、『ストックホルム条約』『パリ協定』を参考に、国際的なルールをつくることが未来の解決策の一つになると思います。最後は、「企業の努力」です。法令順守のための監督・監視体制の強化、代替エネルギーの導入、排ガスを処理するシステムの開発など、ステークホルダーの理解を得ながら工業を発展させていく努力が必要です。

グループ1の皆さん
グループ2:紙ストローに変えることで、環境負荷は本当に減るのか
紙ストローは、プラスチック削減を目的にリサイクルできる素材の利用、開発の視点から生まれ、日本では2019年、中国では2020年から使われています。しかし、あるコーヒーチェーンでは、「すぐにしおれて飲みにくい」などのクレームを受け、顧客の体験価値を守るためにプラスチック製に戻った経緯があります。
他方、紙ストローは環境にやさしい印象を持たれていますが、私たちは本当にそうなのか調べてみました。その結果、①マイクロプラスチックによる汚染を減らせるものの、温室効果ガスの排出量は増えている、②一部の紙ストローに含まれた有害物質は、環境中で分解されにくく、水質汚染によって水産生態系に影響を及ぼす可能性がある、③使用中に使えなくなることから使用量が増え、環境汚染のリスクが高まる可能性がある――ことが分かりました。
私たちは、環境保全について考えるとき、メリットとデメリットの両方を調査し、判断する必要があります。

グループ2の皆さん
グループ3:化石燃料に頼りすぎている
グループ1、2の課題が生まれる背景には、化石燃料への依存の高さがあると私たちは考えました。これらを解消するため、私たちは未来に何ができるのでしょうか。個人の取り組みとして考えられるのは、「環境負荷の低い公共交通の利用」です。短距離の移動であれば、飛行機ではなく電車や新幹線を利用するほうがよいと考えます。次に「節電」です。消灯意識の向上やエアコンの適正利用も大切です。三つ目は、「プラスチック製品の使用の減少」です。たとえば、マイバッグやマイボトルの利用、天然素材の衣服の選択や衣類のリサイクルは、プラスチックごみの減少に貢献できます。そして、「フードロス」に努めること、また生産地から消費地への輸送は、燃料やパッケージコスト、プラスチックごみの発生につながるため、「地産地消の推奨」も考えられます。
そして、社会としては、「クリーンエナジーの開発」に取り組むべきだと思います。水力発電や風力発電、太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電など、新しいエネルギーの研究が盛んに行われています。これらを専門に学ぶ学生の皆さんの活躍もぜひ期待したいです。

グループ3の皆さん
グループ4:環境への意識を上げる
私たちは、環境に対する人々の意識の低さが環境問題を解決できない主な原因ではないかと考えました。そのうえで、政府、企業、個人、研究機関の四つを巻き込むことで、人々の意識を上げられると考えました。たとえば、富裕層に向けた「環境保護課税制度」の導入、ゴミ拾いなど環境活動への参加を促す「教育や社会による働きかけ」をはじめ、「生分解性プラスチックの使用」「赤潮発生メカニズムの解明」「文書や資料の電子化」は効果があると考えます。
一方、教育の背景や暮らす環境の違いが、一人ひとりの意識の差を生み出しています。たとえば、砂漠に住んでいる人は水を大切にし、森に住んでいる人は動物の保護が大事です。社会全体の意識が変わるためには時間がかかりますが、今日のように人と人が交流できる場所に参加して、さまざまな意見があることを知り、お互いの理解が進めば、世界は良くなると思います。

グループ4の皆さん
グループ5:生物多様性を守る必要性
生物多様性には、「生態学的な価値」「科学的な価値」、そして「経済的・文化的な価値」の三つの価値があります。たとえば、暗闇に漂うホタルの光はとても美しいのですが、いまでは多くの人が見たことがありません。また、パンダは日中間の対話において非常に重要な役割を果たしています。すべての生き物は、それぞれが独自の生態系の中で大切な使命を持っているのです。しかし、ホタルもパンダも絶滅の危機に瀕しており、多くの機関や人々が種を守ろうと活動しています。これらはすぐに成果を得ることはできませんが、私たちには子どもたちやそのまた子どもたちのために、この活動を行う責任があります。
10年後には、世界から姿を消してしまう種がいるかもしれません。けれども、私たちはそれらを映像ではなく、直接楽しみ、触れ、感じられる機会を子どもたちに残すため、最善を尽くしたいと思っています。

グループ5の皆さん
グループ6:鳥から見る未来の環境
私たちが鳥をテーマにしたのは、かわいいだけでなく、人間にとって高い価値――生物多様性を守り、生態系のバランスを守る役割を持っているからです。たとえば、農地では害虫を食べて農作物を守ることで人類の食糧生産率向上に寄与していたり、無人島に種子を運んで森をつくったりもしています。鳥が好んで生息する場所とは、人類もよい生活を送れる場所であり、鳥を保護することは人間の生活や未来を守ることにもつながるのです。
私たちは鳥を守るための対策として三つを考えました。一つは、「ドローンの活用」です。人間に代わって地上から森や生態の状態を観測できるこの方法は、一部の希少種を守るためにも必要と考えます。二つ目は、「国立公園での生体保護」です。たとえば、香港の国立公園では鳥が幸せそうに生活しており、その姿を人間も楽しむことができます。三つ目は、「生物保護意識教育」です。老若男女問わず、この意識を育むことはとても必要だと思います。

グループ6の皆さん
以上、6グループすべての発表が終わり、参加者はファシリテーターから講評を受けます。
石川氏 たくさんのディスカッションから生まれた皆さんの提案ですが、これらを関係者にどうやって伝えていくのかが、皆さんの次の課題になるのだろうと思いました。日本語には「感動」という言葉があり、感じて動くことを表しています。一方、知るに動くと書いて、「知動」という言葉はありません。たとえば、どのぐらいの量のごみが海に流れているのかを知ったからといって、人は行動には移らないんです。それを知ったことによって、「それはまずい」「何かしよう」って感じたときに人は動きます。今日、感じたことを振り返り、次の行動に移していただけたのなら、このワークショップは本当に大きな成果を生むことになります。そうなることを期待しています。
田中氏 午前の活動を踏まえながら、メリットとデメリットの両方の視点や、異なるステークホルダーの立場で考えられた発表内容が、とても印象に残っています。なかでも、生き物にどのような価値を付けるかについての議論は興味深かったです。つまり、さまざまな価値を測るには、人間にとって有益なのか、それとも生態系にとって有益なのかのように異なる尺度が必要なんですね。そこはまさに科学の力が試される部分です。
今日は、異なる国と文化で育った皆さんが一堂に会しましたが、意見が一致した点、または違った点はありましたか? どんな話題が出たのか、私もとても気になります。
田代先生 私は、もっと人の考えに立ち入ったらいいのにと思いました。せっかくの機会なので、思ったことをもっと声にして、もっとディスカッションしたらいいと思うんです。それによって、私たちの社会が進んでいくのですから。加えて、今日の発表内容は、「未来の」解決策なのでしょうか。それとも「未来のために、いま行う」解決策なのでしょうか。なぜ、それがいま、できていないのかを次に考えてほしいと思います。できていない理由があるはずです。その一つの理由として、自分と社会は別のもの、という考えがあるように思います。社会、行政、企業、政府それぞれにやるべきことを考えたのはよいものの、「私たち」は何をするのか。誰が、その社会を変えるのか。皆さんが、いまこそ考え、ぜひ行動してほしいと思います。
その後、参加者は夕食を兼ねた懇親会で交流を深め、本フォーラムは終了。

主催団体の笹川平和財団より一人ひとりに修了証が授与されました
参加者からはこのような感想が届いています。
大学生 森楽歩さん
大阪で開催された「日中未来創発フォーラム」がとても印象に残ったので、今回は大学の後輩を誘って参加しました。カードゲームでは、チームのみんなと自分たちの行動が社会にどのような影響を与えるのかを考えながら、カードを選んでいく行程がとても楽しく、多くの学びがありました。また、大学で専攻している中国語を実践し、相手に通じたという成功体験がとても嬉しかったですし、中国人留学生と話せたことも純粋に楽しかったです。
大学院生 久保田智幸さん
グループワークでは、日中それぞれの文化的な視点から多くの学びを得ることができました。たとえば、日本と中国の「食べ残し」に対するマナーの違いに注目し、「フードロス」について文化的な背景から議論できたことは、とくに面白かったです。同じ問題でも、多面的な視点を持つことで結論が変わることを実感しました。この学びを明日から行動に移していきたいです。
大学生 李 昭雅さん
グループワークにおける初対面の人と関係をつくり、一つのテーマについて議論し、提案を模造紙にまとめるという一連の活動は、非常に貴重な経験でした。また、テーマである「未来の環境」については、国籍関係なく誰もが高い関心を持っていましたが、その対策案には文化や自国の発展度合いによる違いが見られ、とても興味深かったです。1日を通して、他の人の意見を聞き、別の視点を自分の中に取り入れる大切さを学びました。
大学生 田中俊行さん
グループワークをとおし、中国人留学生は環境保全について深く研究していることに感銘を受けました。また、母国語のみならず英語が非常に達者であり、いろいろな言語を通して交流できたことは、大きな刺激になりました。
参加者たちは、講義と実践的なグループワークを通じて、互いの文化や価値観に基づいた環境への関わり方を深く理解し合いました。本フォーラムは、日中両国の次世代を担う若者たちが、共に持続可能な未来を築くための確かな連帯を生み出す機会となりました。(執筆者:香川妙美)