2025冬休み特別企画「日本と中国の漢字を楽しもう!」開催報告
笹川日中友好基金は、沼津国際交流協会と共催で、小・中学生と保護者を対象とした「日本と中国の漢字を楽しもう!」ワークショップをぬまづ健康福祉プラザ内サンウェルぬまづ大会議室で実施しました。日本と中国の「漢字」をテーマに、クイズを交えながら漢字の伝来の歴史や漢字の特徴をワークショップ形式で学んだ後に、各自で考えた新しい「漢字」について発表しました。講師兼ファシリテーターは、元中国国際放送局アナウンサーの高橋恵子さんが務めました。


公益財団法人日本財団 理事長、笹川平和財団評議員 尾形武寿氏

中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官 杜柯偉氏

テーマ「環境」のファシリテーターを務めた山田典史氏(北京BC学院)

西島光洋さん

中島龍一さん

藤巻宇衣さん

テーマ「教育」のファシリテーターを務めた張玥(ちょう・ゆえ)氏(お茶の水女子大学講師)

梅河智博さん

何雨陽さん

二平凌吾さん

藤本拓也さん

テーマ「福祉」のファシリテーターを務めた豊嶋駿介氏

恩田侑紀さん、楊浩さん、劉菲さん

テーマ「文化」のファシリテーター兼イベント全体の司会進行を務めた于智爲(ゆう・じゅーうぇい)氏

大山千咲さん、任恒達さん

倉持和輝さん、尾崎そよかさん

唐歌天語さん

神田真帆さん、丁暁琳さん

呉詩妍さん

斉玉さん

発表会場の様子(虎ノ門AP)

成果発表終了後、参加者へプログラム修了証書を授与

公益財団法人日本科学協会理事、東京大学名誉教授 渡邊雄一郎氏

中国人民大学党書記 張東剛氏

笹川平和財団常務理事 安達一氏

テーマ「文化」の参加学生と高橋恵子先生(北京開催ワークショップの司会を担当)












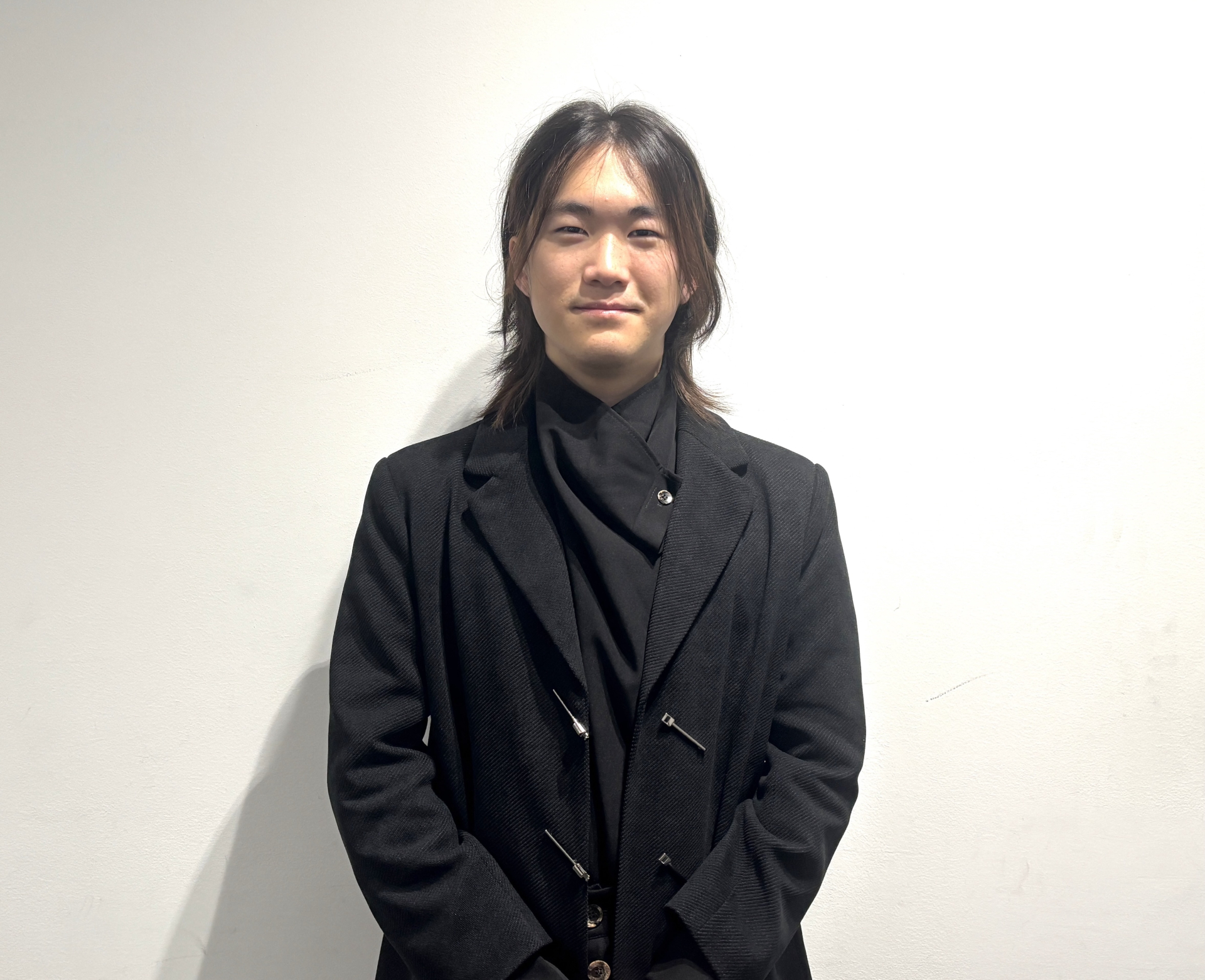
東京農業大学 応用生物科学部 1年 陳佳儀さん(環境)
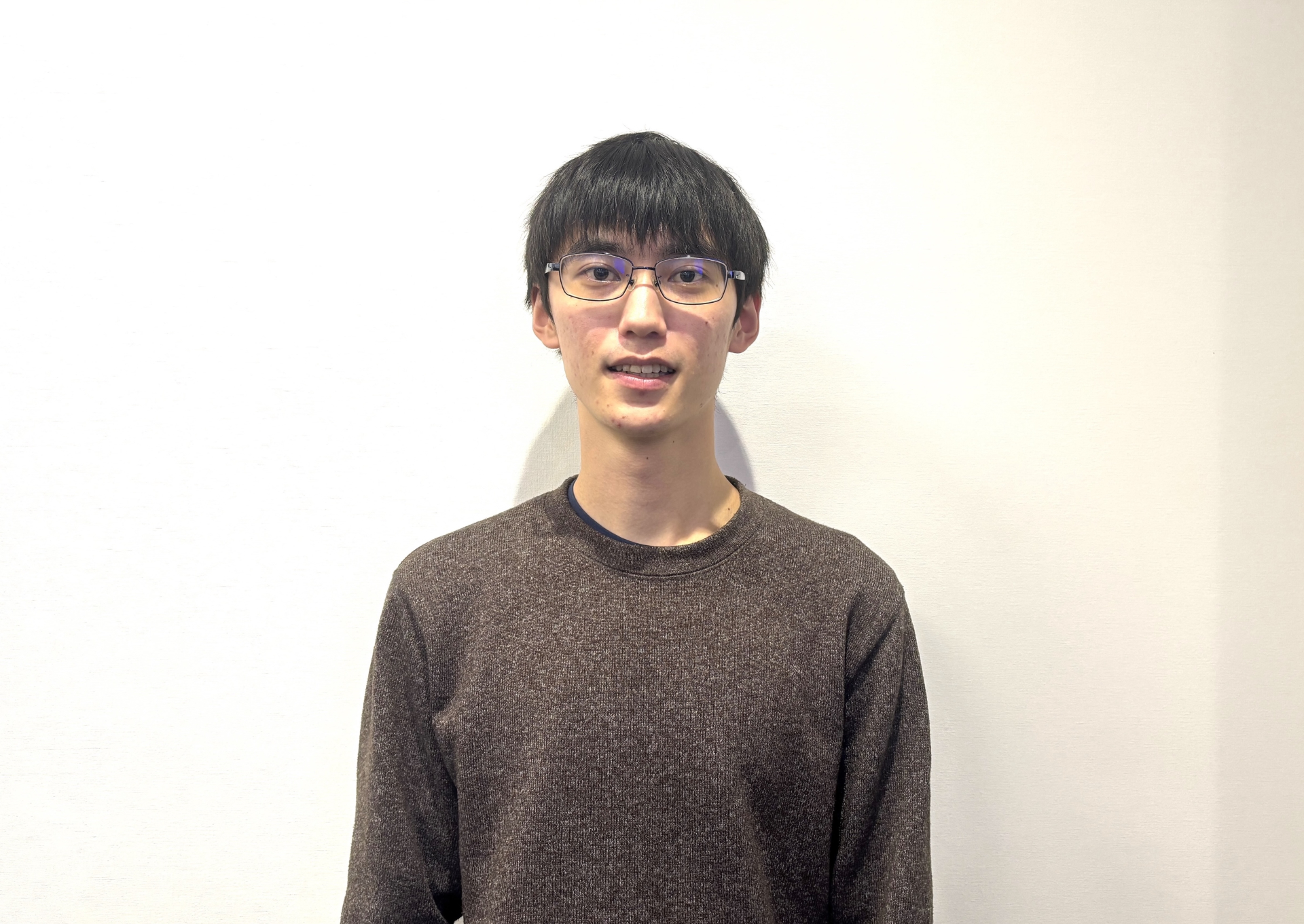
東京大学 文科二類 2年 平柳智明さん(教育)

日中学院 本科 2年 恩田侑紀さん(福祉)

中国人民大学 外国語学院 日本語学科4年 杜美楽さん(文化)