リビア平和研究所との協力分野を協議 角南篤理事長がリビア訪問 今年初めのMOU締結を受け
笹川平和財団の角南篤理事長らは2025年12月23日、リビアの首都トリポリを訪れ、アブドッラー・ラーフィー首脳評議会副議長、アブドッラー・ハーミド・リビア平和研究所(LPI)議長、アイマン・アル・マブルーク・サイフナスル代表議会(HOR)議員らの歓迎を受け、リビアの治安状況や停戦合意後初となる総選挙について意見交換しました。
笹川平和財団(東京都港区、理事長・角南篤)のアジア事業グループは2月26日、オンラインによる「責任ある企業行動のための対話救済フォーラム2021」を開催し、企業活動などで生じる人権侵害から労働者らを救済するための「グリーバンスメカニズム」(苦情処理・問題解決の仕組み・制度)の意義を中心に討議しました。
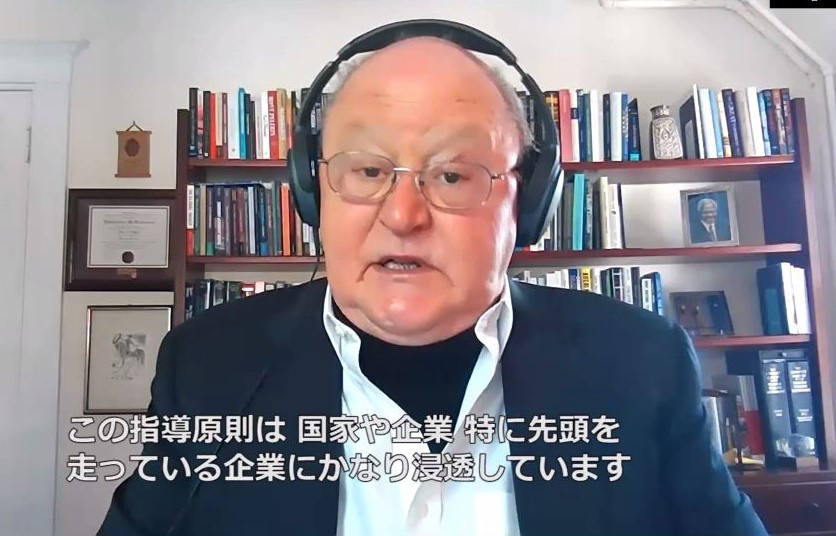
国連人権理事会は2011年、「ビジネスと人権に関する指導原則」を全会一致で承認しました。その柱は①人権を保護する国家の義務②人権を尊重する企業の責任③救済へのアクセス―の3つで、人権侵害が起こった場合には司法、行政、立法、その他の手段を通じ適切な救済措置が取られなければならないと規定しています。これに基づく救済するための仕組みや制度がグリーバンスメカニズムです。また、企業などが人権侵害を防止し、あるいは実際に侵害した場合に対処するための方策と計画を策定し、リスクの特定や、企業活動が人権に与える影響を評価することなどを「人権デューディリジェンス」と呼んでいます。日本企業が抱える人権問題は、生産の海外移転や国境を越えたサプライチェーンの拡大に伴って多様化するばかりです。
フォーラムは「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)」「ビジネスと人権ロイヤーズ・ネットワーク」「ビジネスと人権リソースセンター」との共催です。冒頭の挨拶で角南理事長は、「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認されて以降、この10年で「国別行動計画が策定されたほか、民間企業でもさまざまな取り組みがなされており、一定の進展があったことは歓迎すべきだ」としたうえで「しかし、特に日本企業の取り組みについては十分とは言い難く、とりわけ指導原則の3つ目の柱である救済アクセスについては、ほとんどの企業がまだ手を付けることにすら至っていない段階ではないか」と、懸念を表明しました。
こうしたことも背景に、笹川平和財団は「責任ある企業行動の促進」事業を推進しています。角南氏は「ビジネスと人権問題の解決へ向けた取り組みを積極的に進めていく」と述べるとともに、GCNJなどが2019年に発表した「対話救済ガイドライン」を用いることによって、「公平で実効的なグリーバンスメカニズムがさまざまなレベルで設置され、すべての人権被害者に救済の道が開かれる」ことへの強い期待感を示しました。
人権と多国籍企業に関する国連事務総長特別代表をかつて務め、ビジネスと人権に関する指導原則の「生みの親」ともいえるのが、国際政治学者で米ハーバード大学教授のジョン・ラギー氏です。第一部では、そのラギー氏がビデオメッセージを寄せ、指導原則を策定した経験などを踏まえ「企業は複雑な事業体であり、多くの企業はたいてい人権グループや部門を設置した時点で、人権問題は解決されたと考える。しかし、残念ながらそうはいきません。人権というものは人権派の人々によって侵されるのではなく、企業の経営陣によって侵されます。ですから人権グループが設立され人権ポリシーがあったとしても、これらが経営陣にアクセスできなければ意味がありません」と、くぎを刺しました。
そのうえで「経営陣が従業員にどのような影響を与えているか、企業がどんな悪影響を地域社会に与えているかは、対話をしてみなければわからない。対話は絶対に必要です」と強調しました。人権デユーディリジェンスについては、状況が変化するため「一度きりのものではなく継続的なものです」と指摘。さらに、グリーバンスメカニズムに言及し「企業ベースの救済制度や苦情処理の仕組みなどにおける最も重要な基準は、公正で真っ当な制度だと関係者が思えるものであること、アクセスしやすく、予測可能で、透明性が高いことです。企業ベースでは、第三者が(救済制度を)運営することが理想ですが、もし企業自身が運営するのであれば、オンブズマン制度のように、できるだけ独立した機関であることが望ましい」との見解を示しました。
ビジネスと人権ロイヤーズ・ネットワークの運営委員である蔵元左近弁護士は、今回のフォーラムの共催団体を中心とする「対話救済プロジェクト」が発足し、これは①「対話救済サポートプログラム」の開発を目的としている②サポートプログラムは、個別の企業や団体が受け付けた人権侵害の通報に対し、専門性をもった独立的な第三者が適正に判断し仲介する観点から開発する③2021年4月から2年間でプログラムを策定する―ことなどを説明しました。
一方、外務省の富山未来仁・人道人権課長は、政府が昨年10月に策定した「ビジネスと人権に関する行動計画」(2020–2025)に基づき、「横断的な事項」「人権を保護する国家の義務に関する取り組み」「人権を尊重する企業の責任を促すための取り組み」「救済へのアクセスに関する取り組み」など、関連する施策を整理して説明。企業に対する政府の期待として、企業活動における人権への影響を特定し、予防することなど人権デューディリジェンスを導入することを挙げました。
こうした見解の表明を受け、ニコラス・ハチェス(経済開発協力機構=OECD)、田中竜介(国際労働機関=ILO=駐日事務所)、四方敏夫(不二製油グループ)、銭谷美幸(第一生命)、指宿昭一(外国人労働者弁護団)の5氏がコメントしました。この中では第三者による仲裁の有益性や、労使対話を確保することの重要性、企業単独では対応が難しいとの認識から集団的なメカニズムへの期待、苦情処理の取り組みの遅れが日本企業にとりデメリットとなることへの懸念、ある企業が外国人の技能実習生に対する人権侵害で、対話を拒否し救済の道を閉ざしたことにより損害がもたらされた事例などが、披瀝されました。
第2部では「対話救済に関するプラットフォーム構築に向けて」をテーマに中尾洋三(味の素)、テオ・ジャエクル(エリクソン)、デボラ・アルバース(リスポンシブル・ビジネス・アライアンス)、佐藤暁子(ビジネスと人権リソースセンター)、パトリシア・ワグスタイン(インドネシア大学)の5氏が議論しました。
中尾氏は「グリーバンスシステム(の構築)は個々の企業ではハードルが高すぎ、中小企業には能力がない。公的な機関や業界団体を通じて、企業が参加できる仕組みを構築していただきたい」と政府側に要望。ジャエクル氏は「苦情を問題ではなくチャンスとしてとらえ、事態がエスカレートする前に処理する。グリーバンスプロセスは実効的である必要があり、対話と協力のプロセスが重要です」と述べました。
アルバース氏はスマートフォーンのアプリなどを使ったツールと取り組みを紹介。佐藤氏は日本と海外の「情報ギャップ」を埋める必要性を訴え、ビジネスと人権リソースセンターでは日本語のニュースレターなどで、ミャンマーといった諸外国の市民社会の動向に関する情報を発信していることを披露しました。ワグスタイン氏は 「東南アジアでは企業、NGO(非政府組織)、団体、政府が協力し救済メカニズムの構築を進めてきている」としたうえで、今後の課題として「人権問題をどのように定義するのか、人権を尊重しているような企業の場合でも労働基準を本当に順守しているのか、資金がない中小企業には例外を設けるべきか―。こうした疑問と議論がインドネシアやタイ、マレーシアなどで出てきている」ことを指摘しました。