リビア平和研究所との協力分野を協議 角南篤理事長がリビア訪問 今年初めのMOU締結を受け
笹川平和財団の角南篤理事長らは2025年12月23日、リビアの首都トリポリを訪れ、アブドッラー・ラーフィー首脳評議会副議長、アブドッラー・ハーミド・リビア平和研究所(LPI)議長、アイマン・アル・マブルーク・サイフナスル代表議会(HOR)議員らの歓迎を受け、リビアの治安状況や停戦合意後初となる総選挙について意見交換しました。
2019年8月27日—28日に、笹川平和財団海洋政策研究所(OPRI)は横浜で開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD 7)において、ブルーエコノミーおよびブルーカーボンに関する2つの公式サイドイベントを開催しました。TICADは、日本やアフリカ諸国における官民リーダー間の連携を強化し、持続可能な開発に向けて協力を促進することを目的に、日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行およびアフリカ連合委員会(AUC)と共同で開催されています。
2つのサイドイベントは、OPRIによる研究や取組みについて発信することに加え、海洋資源の保全および持続可能な利用を念頭に、世界の海が持つポテンシャルを活かすべく、日本とアフリカ諸国の政府、企業やその他ステークホルダーによるパートナーシップを強化していくことを目的として開催されました。各サイドイベントにおいて、登壇者はブルーエコノミーおよびブルーカーボンに関して協力していくことに大きなポテンシャルがあり、産学官および地域のステークホルダーによる協力体制を築いていく必要性があると強調しました。

ブルーエコノミーに関するサイドイベントの登壇者ら:(左から)OPRI渡邉敦主任研究員、東京海洋大学 和泉充教授、ケニア海洋水産研究所 ジェームズ・カイロ上席研究員、OPRI角南篤所長、ナミビア共和国 バーナード・エサウ漁業・海洋資源大臣、モーヴェン・M・ルスウェニョ駐日ナミビア大使、東京海洋大学 東海正副学長、OPRI小林正典主任研究員)
ブルーエコノミーは、海洋資源の経済的および社会的便益を享受すると同時に、世界の海洋環境を保全するための統合的な取組みを指す用語であり、近年の海洋政策および気候変動対策における議論の中心トピックとなっています。27日のサイドイベントではこの問題に関わる専門家と政府関係者を集め、アフリカのブルーエコノミーを促進する機会について議論しました。
イベント冒頭では、ブルーエコノミーをサポートする政策に対する国際的な関心の高まりを強調するコメントがありました。OPRIの角南篤所長は開会の挨拶で「ますます多くの国と企業が海洋経済、またはブルーエコノミーの可能性を検討しています」と述べました。また、ブルーエコノミーに焦点を当てた国際会議へのOPRIの広範な参加を概説し、ケニア・ナイロビで2018年に開催された「持続可能なブルーエコノミーに関する国際会合(Sustainable Blue Economy Conference)」の成果を強調しました。 角南所長は「アフリカのパートナーが示した熱意とリーダーシップに非常に勇気づけられた」とコメントしました。
このサイドイベントの司会をつとめたOPRIの小林正典主任研究員は、ナイロビでの会議の成功についても詳しく説明し、参加した代表団によって約束された持続可能なブルーエコノミーを推進する自発的なコミットメントは約1,720億米ドルであると述べました。また、OPRIとアフリカ諸国との継続的な協力への希望を表明しました。



ケニア海洋水産研究所のジェームズ・カイロ上席研究員
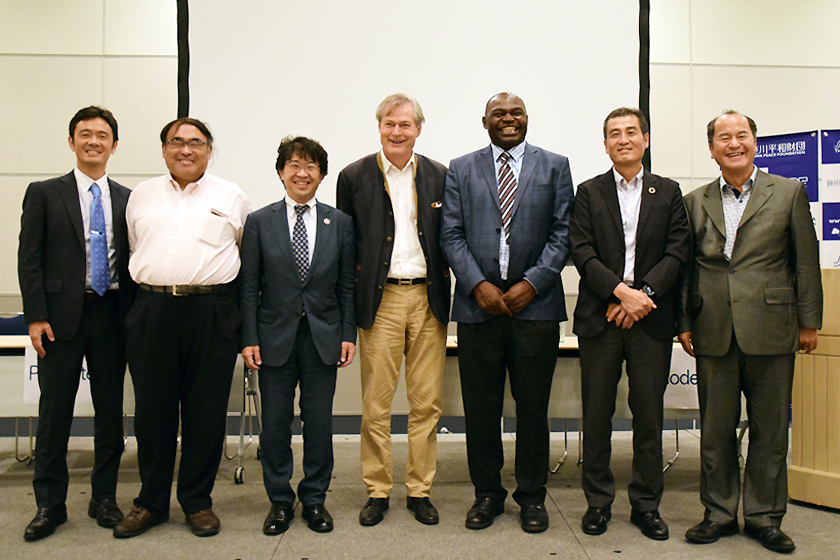
ブルーカーボンに関するサイドイベントの登壇者ら:(左から)OPRI渡邉敦主任研究員、東京海洋大学 藤田大介准教授、OPRI角南篤所長、ZERI Japan グンター・パウリ スペシャル・アドバイザー、ケニア海洋水産研究所 ジェームズ・カイロ上席研究員、横浜市温暖化対策統括本部 奥野修平副本部長、OPRI小林正典主任研究員)
28日のサイドイベントはブルーカーボンにおける最新の動向に焦点を当て、国際的連携の可能性について探ることがテーマとされました。パリ協定の実施に向け世界的な気温上昇を遅らせるための国際的コミットメントの勢いが増しているなか、大量の炭素を吸収し、固定する可能性のあるブルーカーボン生態系の保全は、ますます気候政策において重要な側面であると見られています。
サイドイベントの冒頭でOPRIの角南篤所長は「アフリカ諸国はブルーカーボンに大きな可能性を秘めている」とコメントしました。アフリカ諸国において広大なマングローブ、海草、海藻などの生態系がありながら、短期的な経済的利益を追求するための乱用と搾取が行われていることについても言及し、このような行為が保全の進捗を妨げていると説明しました。「ブルーカーボン生態系の持続可能な利用は、沿岸地域におけるコミュニティに利益をもたらすとともに、気候を調整する役割も果たす」とコメントしました。
前日に続いて本サイドイベントのモデレーターをつとめたOPRIの小林主任研究員は、2018年にポーランドで開催された国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(UNFCCC COP24)などのグローバルな政策対話へのOPRIの積極的な参画について説明しました。また、ブルーカーボンに関する近年のOPRIの活動について、岡山県日生市におけるアマモの再生活動などといった社会的・経済的利益をもたらしたさまざまな事例研究を紹介しました。

GEFの石井菜穂子統括管理責任者(CEO)兼任議長

ZERI Japanスペシャル・アドバイザーのグンター・パウリ氏