OPRI 特集ページ
新型コロナウイルス対応関連情報 - 対談 No.5
対談『OPRIリレーメッセージ』
「海から、新しい価値の創造を-ポストコロナ時代のNGO」
井植美奈子氏(一般社団法人セイラーズフォーザシー日本支局理事長)
新型コロナウイルス感染症の影響は世界に、日本に、そして海洋にどのような変化をもたらすのでしょうか。『OPRIリレーメッセージ』は、ポストコロナ時代を見据えて海洋の問題に造詣の深い専門家の方々にお話を聞くシリーズです。
今回は(一社)セイラーズフォーザシー日本支局理事長の井植美奈子さんに、海洋における持続可能性、NGOの役割などの視点からお話を伺います。
(聞き手:角南篤 笹川平和財団・海洋政策研究所所長)
*この対談は2020年6月11日にオンラインで行われたものです。
角南: |
今回は海洋分野の世界的なNGOであるセイラーズフォーザシーの井植さんにお越し頂きました。どうぞよろしくお願いします。井植さんは海洋や水産の問題について精力的に活動されていますが、海洋におけるコロナ危機と今後についてお伺いできればと思います。はじめに、セイラーズフォーザシーについてご紹介頂けますか? |
| 井植: | 今日はよろしくお願いします。「セイラーズフォーザシー」は、2004年にデイビッド・ロックフェラーJr.(注:「石油王」として知られるジョン・ロックフェラーの孫。実業家で慈善家。)により創設された海洋環境保護NGOです。2011年に日本支局を立ち上げ、2013年に社団化しました。海洋資源の持続可能な利用を啓発するための、サステナブルなシーフードを紹介する「ブルーシーフードガイド」の発行、ヨットやボートなどを利用して開催される各種競技やイベントがより海洋自然環境に配慮したものとなるようにするためのプログラム「クリーンレガッタ」の推進、海洋生態学に焦点をあてた環境教育の教材をオンラインで提供する取組み「KELP」が中心となっています。なかでも「ブルーシーフードガイド」が中心的活動で、サステナブルな漁業と水産物の消費を推奨しています。また2020年6月より、美容と健康に関心が高い方をターゲットに「ブルーシーフード・ビューティーブック」の公開も始めました。美容にも健康にも良いシーフードを紹介していますので、ぜひご覧頂きたいと思います。 |
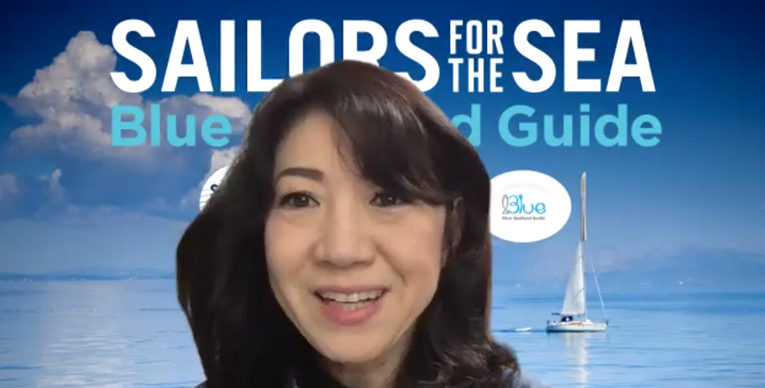
井植美奈子 氏 (一般社団法人セイラーズフォーザシー日本支局理事長)
新型コロナウイルス感染症の水産業への影響
角南: |
井植さんが感じておられる、新型コロナウイルスの感染拡大による水産業への影響についてお聞かせ頂けますか? |
井植: |
はい。新型コロナウイルスの影響により、魚が売れない、特に高級水産物が売れない、養殖魚が出荷できない、などの影響が出ています。一方で、魚が売れないため漁業者が自らオンライン販売を開始したところ即日完売する、といった変化も起こっています。こういった事例を見ると、サプライチェーンが変わっていくだろうという予感はありますね。個人のルートで情報を得る、個人が直接買う、という方式が、ニューノーマルとしてポピュラーになってきている。ここに付加価値としてサステナビリティ(持続可能性)をどう取り込んでいくか、いかにステークホルダーが協力していくかが重要と考えています。 また、この機会に天然魚の資源枯渇問題に取り組むことも重要です。改正漁業法(https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/kaikaku/attach/pdf/suisankaikaku-19.pdf)*1が2020年内に施行されます。さらに、漁業改革の推進に向けた後続の施策の検討が国会議員により開始されていますので、応援していきたいと考えています。 遠洋漁業については、出漁をあきらめたところが多いと思います。例えば、海外の漁港に寄港できないといったことに加えて、乗組員であるインドネシアの方々が国に帰れない、という話を聞いています。海外から入ってくる魚種のうちサプライが止まったものがあるなどの変化も生じてきています。国際的な漁業活動はこれからもリスクをはらんだものになるでしょう。こういった事例が国内自給率の低さや需給バランスの問題を考えるきっかけにもなりそうです。 |
角南: |
移動の自粛、国際的な移動の制限などにより、観光業界も大きな影響を受けています。海に関しても、クルーズ船などに影響が出ています。海に関する観光やレジャーの再生に向け注目している事例などありますか? |
| 井植: | 「ペスカツーリズム(Pesca-tourism)」という、ヨーロッパ発祥の観光の形態に着目しています。農村・農場で休暇を過ごす「アグリツーリズム(Agri-tourism)」の漁業版ですね。小船に乗って牡蠣を取って食べるような、自然のなかでのんびりとした時間とおいしいシーフードを楽しむ、イタリアで生まれた観光スタイルです。日本でも、広島県で牡蠣イカダを見学して、収穫した牡蠣を食べる、といった観光振興が動き出したところで、せっかく盛り上がってきたなかコロナ危機になってしまいました。ですが、動きが止まってしまったわけではありません。例えば最近では、北海道の漁業者がバーチャル漁業ツアー*2を始めました。オンラインの漁業体験プログラムに参加し、希望者にはその後自宅に実際に魚が届き、調理法はYouTubeで見られる、というものです。今後の展開が期待できると思っています。 |
セーリングへの影響
角南:
|
セーリングの分野でも環境保護の活動をされていますが、コロナウイルス感染症の影響はいかがでしょうか? |
| 井植: | 私たちの活動のひとつに「クリーンレガッタ」というプログラムがあります。レガッタとは、発動機を使わないボート競技のことで、こうした競技の実施団体や参加者に環境への配慮を求めるというものです。海外でもアメリカズ・カップやボルボ・オーシャンレースなどで導入されていて、環境配慮の取組みの度合いでプラチナ、ゴールド、シルバーなど等級付けもされています。参加者が自主的に目標を設定して、達成を目指すという仕組みになっています。ペットボトルを持ち込まない、といった身近なところから、マリーナのショップのハンガーなどでもプラスチックでなく紙製のものを利用、船からの排水規制など様々な取組みのステージがあります。参加者全員の意識改革が求められるもので、大きな国際レースではメディアを通した報道にも力が入れられており、啓発という意味でもインパクトは大きいと思います。神奈川県の葉山マリーナはセイラーズフォーザシーの年間パートナーとなり、このクリーンレガッタを支援してくれています。その葉山マリーナはコロナウイルス感染症の影響で残念ながらしばらく閉鎖されていましたが、3密を避けるという意味でプロセイラーも単独・ソロのヨット利用などを推奨しながら、徐々にヨットスポーツ再開の動きが出始めています。 こうした取り組みからも、世界で持続可能性が付加価値として認識されていくという期待が感じられます。新しい価値をどう創造していくかが、これからの課題だと考えています。 |
東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとは
角南: |
東京大会は来年に延期になってしまいましたが、井植さんは水産物調達基準についても熱心に取り組んでいらっしゃいましたね。 |
井植: |
「持続可能性に配慮した調達コード」(調達コード)の採用は、2012年のロンドン大会で始まりました。ロンドン大会組織委員会が調達コードを採用し、海洋管理協議会(MSC)認証あるいは海洋保全協会(MCS)の推奨魚種リストから水産物を調達するといった制度が導入されたものです。2016年のリオ大会では一歩進んで、MSCに加えて水産養殖管理協議会(ASC)認証を受けている水産物のみを提供することになっていました。 調達方針が持続可能なものになれば、大会のレガシーとしても残ります。日本もこのレガシーを踏襲していくべきだったのです。しかし東京大会の組織委員会の調達コードは、ロンドンやリオと比べると非常に緩い内容で、サステナビリティを担保するものではありませんでした。セイラーズフォーザシーでは、多くの賛同者と共に、水産物の持続可能性を高めるため、漁業法改正も受けた新しい漁業に対する考え方も反映されたものにするべきと組織委員会の担当に働きかけています。たまたま私のあるスピーチを聞いてくださっていた当時の文部科学大臣やIOCの持続可能性担当理事であるアルベール2世モナコ大公殿下も非常に関心を持って下さいました。そのおかげで改善が検討されたものの、決定権はあくまで組織委員会にあるとのことで、東京大会開催が改正漁業法の施行前であること、調達まで時間がないことなどを理由に、見直しを拒否されていました。その後、東京大会が延期になったため、社会情勢や調達現場が一変しました。レガシーとして残せるような調達コードに改善できるか、今後の展開が鍵を握ると思います。 |
角南: |
これはすべての関係者に考えてもらいたい課題ですね。東京大会を成功に導くには、国際感覚をもとにオリンピック全体のレガシーを創っていくという意識が必要だと思います。 |
| 井植: | 水産物の調達コードに持続可能性が取り入れられなかった理由は、複合的な要素があるため特定できません。ただ、水産物に限らず、「持続可能性に配慮した調達コード」に不備がありすぎることを指摘し改善を求める「街づくり・持続可能性委員会」の委員が複数いらっしゃることも確かです。一方、持続可能性検討委員会水産ワーキンググループにおいては、水産物の持続可能性の専門家が入っていないこと、持続可能性の議論が日本の魚を優先させる議論に押し負けていることが問題だと思っています。 |
アフターコロナ時代のNGOの役割
角南: |
やはりこういった課題を指摘していくNGOの役割は、ポストコロナ時代には加速していくのではないかと思っています。 |
井植:
|
はい、ますますNGOの役割は強化されていくと思いますね。海洋のNGOも、10年前と比べると存在感を増しています。政治家の皆さんによるNGOを交えた勉強会なども行われています。規制改革推進会議の委員として貢献したり、政策提言もしています。 また、私たちNGOの独自の視点からの情報発信も重要です。「ブルーシーフードガイド」などの幅広い層への周知のため、『みなと新聞』や業界紙だけでなく、『25ans(ヴァンサンカン)』や『フォーブス』などにも定期的に寄稿しています。今後はSNSも使ってさらに情報共有していきたいと思っています。SDGsが策定された2015年に比べれば現在の浸透率は著しいものですが、サステナビリティへの国民の意識は急速に高まっていますね。 |
| 角南: | 最近、SNSの声が政治を変えていくという動きが見られます。これまでの政治のやり方に対し、多くの人が問題を突き付けている結果だと思います。これからNGOに求められるのは、行政やコミュニティに働きかけて、政党を支えている20世紀の仕組みを変えていくことです。そういう影響力を持つ存在として、NGOが立場を確立できるかどうかが問われています。 今日、井植さんのお話を伺って、「新しい価値の創造」という言葉が浮かびました。高い付加価値をいかに作るかが今後の重要なポイントですね。そして、高いレベルの価値の頂点に持続可能性がある。これまで世の中は豊かでありラグジュアリーであることを求めてきましたが、ポストコロナの世界では、究極的な価値はサステナビリティになっていく。これは大きな転機です。ミシュランレストランガイドの星の評価も変わってくるという話もありましたが*3、食材へのアプローチが3つ星の判断基準になるかもしれませんね。この観点からも、セイラーズフォーザシーの活動はこれからますます重要になっていくことと思います。今日は興味深いお話をありがとうございました。 |

角南篤(海洋政策研究所所長)
井植美奈子氏:デイビッド・ロックフェラーJr.が米国で設立した海洋環境保護NGOのアフィリエイトとして2011年に一般社団法人セイラーズフォーザシー日本支局を設立。NGO経営と並行して京都大学大学院地球環境学舎博士後期課程在籍中。京都大学大学院非常勤講師、慶應義塾大学SFC研究所上席所員。
【参考】
*1: Ocean Newsletter 第449号「改正漁業法と持続可能な水産業」(小林史明衆議院議員)
*2: 落部ブルーツーリズム推進協議会
*3: 「ミシュランガイドに“サステナビリティ”の評価軸、新設された「緑のクローバー」マークが波紋」(WIRED 記事)
(海洋政策研究所 情報発信課 石島知美)