2025冬休み特別企画「日本と中国の漢字を楽しもう!」開催報告
笹川日中友好基金は、沼津国際交流協会と共催で、小・中学生と保護者を対象とした「日本と中国の漢字を楽しもう!」ワークショップをぬまづ健康福祉プラザ内サンウェルぬまづ大会議室で実施しました。日本と中国の「漢字」をテーマに、クイズを交えながら漢字の伝来の歴史や漢字の特徴をワークショップ形式で学んだ後に、各自で考えた新しい「漢字」について発表しました。講師兼ファシリテーターは、元中国国際放送局アナウンサーの高橋恵子さんが務めました。




テーマ:教育
発表タイトル:AIを活用した教育の未来:日中協力によるイノベーション戦略
発表の要旨:私たちのグループでは、教育分野においてAI技術が活用されている現状と課題を考察し、日中協力によるイノベーション戦略の提案を試みました。
AI技術には、学習内容を個別最適化したり、教員の業務負担を軽減したりするなどの可能性があります。一方で、倫理的な問題や、AIサービスを受けられないことによる教育格差の拡大への懸念、さらにはAIの過度な利用による思考力の低下など、いくつかの課題も指摘されています。
日中両国における教育分野でのAI活用状況を比較すると、中国では大学生のレポートや論文執筆への導入が進んでいるのに対し、日本では研究・教育分野でのAI活用は依然として限定的であることが分かりました。また、両国に共通する課題として、教員の業務負担に見合う賃金が支払われていない可能性が浮き彫りとなっています。
これらの課題に対応するためには、AI技術の導入によって教員の業務を補完するだけでなく、教育現場で安全に使用するための明確なガイドラインの整備や、教育的倫理をAIのプログラムに組み込む必要があります。加えて、学校施設や教材などの教育インフラの刷新も重要な課題です。日本と中国が技術協力や共同研究を通じて連携すれば、AIを活用した教育の可能性をさらに広げることが期待されます。さらに、教育分野でAI技術を導入するにあたっては、教育理念に基づき、「賢く使う道具」としてのAIの位置づけが不可欠です。今後はAI技術の進化に応じて、教育現場での活用方法も柔軟に発展させていく必要があります。そのためには、継続的な研究開発に加え、教育関係者同士による積極的な意見交換と経験の共有が重要な要素となる結論に至りました。


テーマ:生活
発表タイトル:AI・データベース活用と「百歳人生」
発表の要旨:私たちのグループは、AI技術やデータベースを活用した未来社会の人生設計について議論を進めました。医療の発達などによって人間の寿命は延びることが予想され、百歳までの人生を豊かに生きるための方法を検討しました。そのため人の一生を幼年期(0〜20歳)、青年期(21〜40歳)、中年期(41〜60歳)、老年期(61〜81歳以上)という年齢層ごとに分けて年代別の課題の抽出と技術導入によって得られる可能性を考えました。まず幼年期(0〜20歳)では、AI技術を活用した心と健康状況のモニタリングに適切な管理が可能になり、個人の学習レベルに合わせて最適化された学習支援などが提案されました。一方で、管理下におかけることによって運動不足になることへの懸念やプログラムにはない創造力を育むための学習方法などの方法を模索する必要があるといった課題も浮き彫りになりました。青年期(21~40歳)の世代では、今後もさらなる晩婚化や少子化が進むことを前提として場合においては、家庭生活全般に対する支援(家族の見守り、家事の分担、育児支援)や、働き方の柔軟化を実現するための支援(リモートワーク、副業など)が重要な課題になるため、これらを解決するAI技術の発展が期待されると考えました。中年期(40〜60歳代)では、子育てや介護と仕事の両立が大きな課題になり、AI技術の発展では経済的負担の軽減やキャリアの再設計に貢献できる可能性があると考えました。老年期(60歳以降)では、健康や介護への不安、社会的孤立、家族との意思疎通の困難といった課題があり、AIや地域コミュニティの力を活用した解決策が検討されました。このように、人生の各ステージにおいてAI技術が生活全般を支援する余地は非常に大きいという結論に至りました。 しかし一方で、生活の利便性や効率化を追い求めるあまり、AI技術の発展に過度に依存し、時間を生み出す手段として子どもたちの教育までもAIに任せてしまうことが、本当に「人間らしい生活」と言えるのかという疑問も提起されました。 むしろ、より人間らしく、心の健康を保ちながら幸福な生活を送るためには、過度な競争から距離を置き、家族や地域とのつながりを大切にすることが重要なのではないかという視点も示されました。


テーマ:文化
発表タイトル: ※以下の4つの視点から日中両国の違いについて意見交換しました。
発表の要旨: 1. 中国人と日本人の結婚しない考え方について 私たちは中国と日本における晩婚化・未婚化の背景を考察しました。中国では、選択肢として結婚を選ばない「不婚主義」や「恋愛はコスパが悪い」といった時間や費用をかける価値がないという考え方を持つ人の増加、高額な結納金、就職難などの経済的な理由が結婚を遠ざける理由にあることが分かりました。日本では、そもそも「1人がいい」といった価値観の多様化が進んでおり、2050年には独身世帯が人口の約半数を占める可能性があることが分かりました。日本と中国では仕事と家庭の両立に課題があり、伝統的な価値観に対する変化が徐々に進んでいるなどよく似た状況にあることが分かりました。将来的には、社会全体が多様なライフスタイルや価値観を尊重するようになり、「結婚すること」が必ずしも必要ではなくなる可能性があります。恋愛も従来の「結婚前提の関係」から、「自己実現や趣味の延長としての関係性」に変化していくのではないかと考えました。
2. 連絡頻度から見る中国の恋愛観 中国と日本のカップルを比較すると、中国ではお互いに連絡する頻度が非常に高い傾向にあることがわかりました。その理由として、恋愛に対する重要度が高いこと、WeChatが生活に密着していること、敬語がないため基本的にコミュニケーションがカジュアルであることなどが挙げられる。名古屋学院大学のデータによると、中国人は「将来の結婚相手を探すため」の手段として恋愛をしたいと考える傾向が強く、将来の「婚姻関係」を前提としたコミュニケーションであることを重視する傾向があります。対して、日本では、必ずしも恋愛に対する重要度は高くなく、また連絡頻度も中国と比較して少ない傾向があることがわかりました。
中国の社会では、個人の感情や自由を尊重した新たな恋愛スタイルや、パートナーシップの多様化を促進し、伝統的価値観と現代的価値観のバランスを取ることが望ましいとされていることがわかりました。日本の社会では、結婚や恋愛の価値観に多様な選択肢があることを推進し、若者や多様な生活スタイルの人々が安心して自己表現できる環境整備を進めていることがわかりました。両国は共に社会状況の変化に伴い、より柔軟で多様な恋愛観を許容する社会に進化していくことが予想されます。
3. 両国留学生の目に映る文化遺産 私たちは日中の留学生がお互いの国の文化遺産をどのように捉えているかを考察しました。中国の文化遺産は、故宮博物院や兵馬俑に代表される歴史的建造物など歴代の王朝時代の史跡を紹介するものが大半を占めています。国内外のたくさんの観光客が訪れる一方で展示物に対する説明がやや不足している傾向があるなどの課題があることがわかりました。日本の文化遺産は、金閣寺などの京都や奈良の寺社仏閣をはじめ、現代においても実際に使われている場所も多く、繊細で自然と調和が取れている印象がある。中国の留学生からは、寺社などを訪れると参拝やお守りを授かるなどの日本の特有の文化を体験することができとても興味深いという意見も多数みられました。両国共に国の文化遺産とは、過去を記録するだけでなく、過去の価値観を未来の世代に継承することで地域のアイデンティティ、教育に重要な役割を果たす効果があり、過去から現在を通じて未来をみる場所でもあるという共通点を見出しました。
4. 日中の公園から見る文化財保護 私たちは身近な公園に目を向けました。中国の公園は、大規模で人工の湖、彫像、伝統的な建築物が特徴。歴史や文化を守る目的で建設され、観光地としての役割が強い傾向にあります。一方、日本の公園は比較的小規模で多くは住宅街の近くにあり、ベンチ、トイレ、遊具など基本的な設備を備えています。日常的なリフレッシュや散歩、子どもの遊び場として、住民の憩いの場としての役割が強い傾向にあります。日中の公園を比較することで、社会における公園の位置づけや文化財の保護に対する考え方に違いがあることがわかりました。日本と中国は共に文化財の保護には、観光・教育・地域住民の三者の視点をバランス良く取り入れた取り組みが必要になります。伝統と現代の価値観を融合し、保存・活用を進めることが、文化財保護の鍵になることがわかりました。
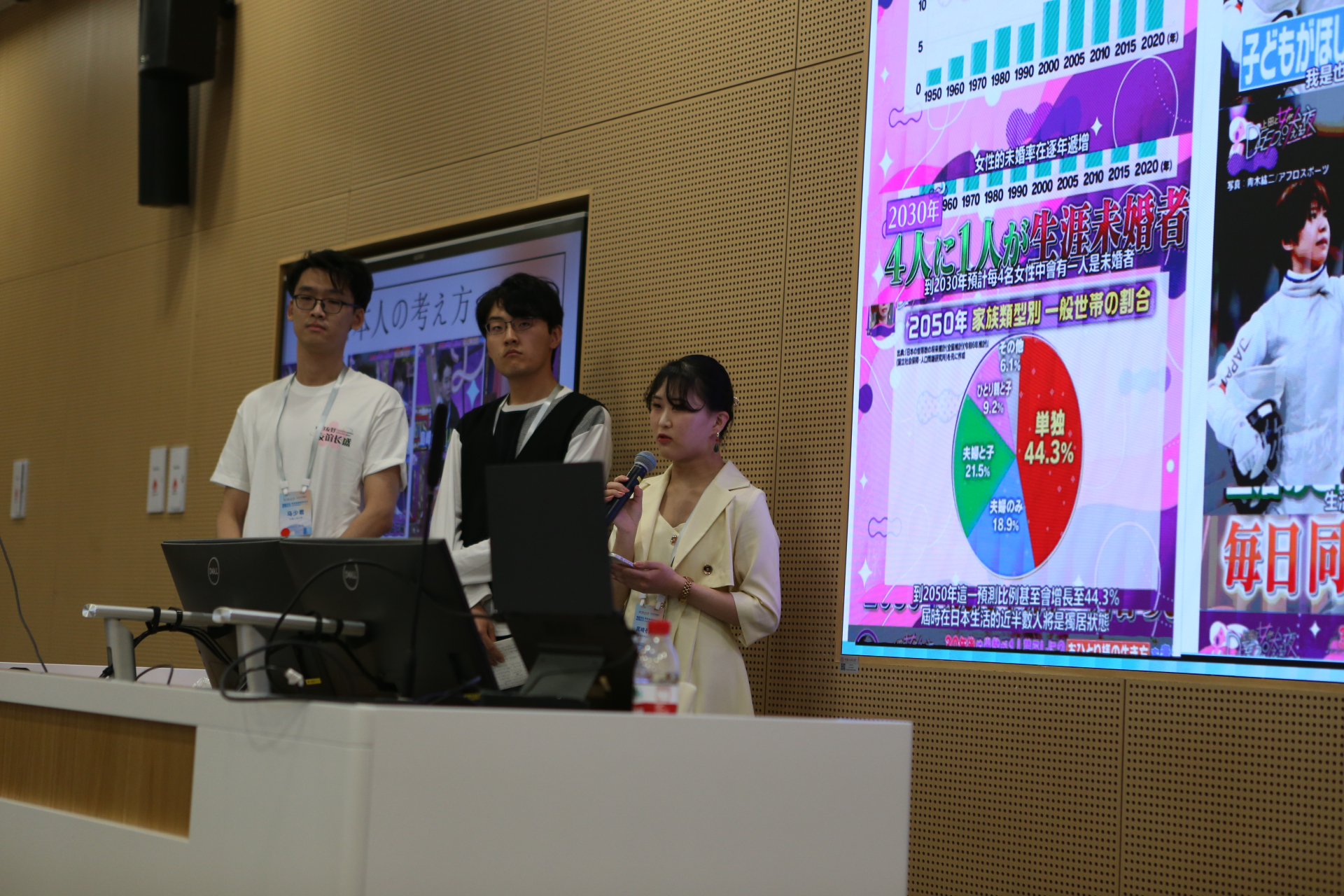

閉幕式には、フォーラムに参加した大学生のほか、来賓に中国人民大学の張東剛党委員会書記、朱信凱常務副学長、日本財団の尾形武寿理事長、佐藤英夫常務理事、日本科学協会の顧文君常務理事、中国人民大学の教職員等が出席し、司会は中国人民大学外国語学院の陳方院長が務めました。
日中の学生代表によるスピーチでは、中国人民大学外国語学院日本語学部3年生の呉昀謙さんは、「中国には”新しい友がひとりできれば、また道がひとつできる”という言葉があります。両国の友好に携わってきた先生方の意思を引き継ぎ、新たな友情をつくっていきたいと思います。何年かあとにこれから植える桜の木が花を咲かせるときにぜひ家族とともに再会したいと思います」と語り、未来への希望と交流の継続を願いました。
日本人留学生の清華大学大学院の伊藤雪乃さんは、「日中両国の言語は異なりますが、学生たちの未来や社会に対する考え方には共通点が多く、新たなインスピレーションを得ることができました」と述べ、国境を越えた若者同士の理解と共感の深まりを実感していました。




閉幕式を終えた後は、新校舎の一角にある庭園の「双櫻園」に移動し、このフォーラムをきっかけに、日中両国の世代を超えた友情が末永く続くことを祈念して、桜の木の植樹式が行われました。
