尖閣諸島
島嶼研究ジャーナル
第15巻1号
2025年11月30日
第15巻1号では、世界各地で次々に勃発する海洋と島嶼の問題を、幅広い視点で取り上げている。 論説は2本を掲載。『トランプ政権下のグリーンランド買収企図を巡る内外情勢分析』では、世界の安全保障に重要な立ち位置であるグリーンランドと、その米国による買収問題を世界情勢に通暁する著者が分析・考察している。将来の選択肢として米国との「自由連合」(Free Association)を、また、日本・グリーンランド協力の一環として氷床下の大規模天然食料・医療品保管庫建設構想を提言している。 『実務的デカップリング-2025年の日露関係』では、少しずつ日本に対し外交的圧力を強めているロシアとの間にある北方領土問題、ロシア産エネルギーの問題への対処方法を論じ、最終的には日露のデカップリングを目指し、日本の外交・経済資源は、インド太平洋秩序を共に支える力と意志を持つ国々に再分配すべきであると論じている。 インサイトは3本を掲載。『仲裁裁定9年目の南シナ海-中国に対するフィリピンの2つの革新的対応措置を中心に-』では、2016年7月、南シナ海仲裁裁判所においてフィリピンがほぼ全面勝訴したにもかかわらず、中国は裁定をあらゆる意味で受け入れないと表明し、9年目の今も南シナ海で妨害行為や威圧的行動を続けている。フィリピンが中国に対抗するために始めたのが「積極的透明化キャンペーン」であり、本論ではその内容や評価、また日本との関係について論じている。 『「ブルー・エコノミー」の認知度拡大に伴う今後の課題』では、外交・安全保障の文脈で提唱された「ブルー・エコノミー」という概念は、流行語のようになって拡大解釈され、主に自然環境・経済の観点からのみ語られるようになってしまっているが、著者はアフリカや中南米の例を挙げて、本来の「ブルー・エコノミー」について具体的に論じている。 『歴史的観点から台湾の地政学的・経済的・文化の地位を考える』では、台湾について、歴史的な観点から東アジアでの立ち位置について考察し、軍事衝突・IT通信機器・米国でのロビー活動・投資の4点において台湾には強みがあり、独立を貫けると論じている。 コラムでは『竹島問題啓発パネル展「出張竹島資料室in浜田」について』を掲載した。「竹島資料室」は島根県が2007年に竹島問題の啓発を目的として開設した。以来、竹島関係資料収集、研究会活動などを続け大きな成果を上げている。本稿では同資料室の啓発活動の具体例を取り上げ、特に島根県水産試験場の竹島周辺調査の歴史を解説している。
島嶼研究ジャーナル
第14巻2号
2025年03月31日
第14巻2号の論説では、緊張を高める世界情勢のなか、日本の島嶼領土である尖閣・竹島の現在においての問題を提言し、解決を論じる2本を掲載した。 『緊急提言:いま実行すべき日本の尖閣諸島防衛策』では、尖閣諸島の主権に対し執拗かつ周到な現状変更を企て続ける中国に対し、守勢のみの日本政府に即時行動を促し、可能かつ有効な手段を論じる 『韓国の「国史」教育の変遷と独島/竹島』では、韓国が、小学校から高等学校に至るまでのすべての教科書に、竹島主権についての韓国側の主張のみをあたかも真実であるかのように掲載し国民に偏向教育を続けている事実を提示し、この歴史教科書問題には日本側の積極的な対処が必要不可避であると論じている。 インサイトは3本を掲載。『琉球大航海の尖閣航路-西表島から飛鳥時代に遡る』では、尖閣諸島の近代以前の歴史について、かつて八重山諸島に在った貿易航路「尖閣航路」から、首里(琉球王国)とは異なる八重山の貿易勢力の存在を提起し、従来の中国史観のみでは論じられない歴史の可能性を示唆している。 『多元的脆弱性指標とその政策的意味合い 小島嶼開発途上国における対応力強化と持続可能な開発に向けて 』では、小島嶼開発途上国の社会的脆弱性に対策するため、2024年に国連総会で採択された「多元性脆弱性指標(MVI)」について、評価指標である、環境(気候変動)、社会経済、国際制度的枠組みについて、パラオ、モルジブ、バハマ等を取り上げて具体例を考察している。 『フィリピンの海洋安全保障の概念』では、フィリピン大学法学部教授である著者が、フィリピンにおいて「海洋安全保障」という用語についての認識について、「国家安全保障・行動アジェンダ」「国家安全保障」「フィリピン沿岸警備隊法」「国家警察海洋グループ」などに触れて解説している。 コラムでは『対日平和条約第2条が世界に及ぼした影響』を掲載した。日本が直面している「尖閣・竹島・北方領土」の島嶼領土問題は、ほぼすべて第2次世界大戦の講和条約である「対日平和条約第2条」に起因している。この条項はこうした重大な島嶼領土問題のほかにも、日本の国連加盟、自衛隊の法的地位、南極における活動、南シナ海の島嶼領有権問題なども発生させている。
島嶼研究ジャーナル
第13巻2号
2024年03月31日
第13巻2号は、日中関係と海洋秩序をテーマに、台湾、尖閣諸島をめぐる問題を論じている。 論説は、日本政府が台湾を国家として承認した場合、その行為は1972 年日中共同声明 3 項に反するのかどうかを明らかにする『1972年日中共同声明3項の意味』、また、2023年6月に中国の全国人民代表大会で採択された対外関係法が、第2次世界大戦の終結以降の国際秩序を自国の思惑通りに修正しようという中国の法律戦の一例であることを、新法の条文の一部を検証しつつ論じている『中国の新たな対外関係法―中国独特のルールに基づく国際秩序の変革』の2本を掲載している。 インサイトでは、尖閣石垣島航路の開始年代を14世紀中期以前と推測し、琉球貿易と尖閣航路について論じた『鎌倉時代の尖閣航路から室町時代の波照間南洋大交易へ』、また、2010年の尖閣諸島沖で海上保安庁巡視船が領海侵犯の中国漁船に体当たりされるという事件を取り上げ、日本の対応にあまりにも多くの問題があったことを、国際法の視点から指摘する『尖閣諸島沖中国漁船船長逮捕事件について』、さらに、島嶼研究ジャーナル13巻1号に掲載された論説『韓国の竹島不法占拠と新聞報道』の追補である『別表「竹島問題に関する記事一覧」』の3本を掲載した。 コラムでは、『国際判例紹介(17)サイガ号事件(1977 年及び1999年国際海洋法裁判所判決)』を掲載した。サイガ号事件とは、西アフリカの国家「ギニア」のEEZ 内で、カリブ海の島嶼国「セント・ビンセント及びグレナディーン諸島」の洋上給油船サイガ号が他国漁船へ給油したことを、ギニアが国内法違反であるとして船を連行し、乗員を抑留、積荷を没収した行為について、セント・ビンセントが国際海洋法裁判所に提訴した事件である。
島嶼研究ジャーナル
第13巻1号
2023年12月27日
第13巻1号は、国際関係と海洋秩序をテーマに、日本海、東シナ海、南シナ海、太平洋、インド洋、地中海、エーゲ海、カリブ海と地球を一周する広大な海域を扱っている。 論説は、日本と中国の関係を考察しつつ東アジア全体の海洋地政学について論じた『日本、中国、南シナ海と東シナ海における領有権問題』、また、竹島の自然や日本人の活動を撮影した、波乱の来歴を持つ映像資料の解析と検証『1940年に竹島で撮影された8ミリフィルムの検討』を掲載した。 インサイトは4本、韓国による竹島の不法占拠を新聞記事から考察した論説、エーゲ海係争地域でのドイツの海洋調査活動を取り上げた論説、また、EUによるインド太平洋への海軍派遣と海洋安全保障問題の論説、さらに、東地中海でのトルコなどによる海洋境界画定問題の論説を掲載。 コラムでは、カリブ海の島嶼問題を通して、海洋利用に関する公海・領海問題を論じた『カリブ海の島嶼国とパトリモニアル海』を掲載した。
島嶼研究ジャーナル
第12巻2号
2023年05月12日
本号は太平洋地域、地中海、東シナ海、南シナ海、エーゲ海における島嶼の問題を取り上げている。いずれの島嶼問題も国家主権との関係で解決が難しく、諸国は外交政策を尽くして領有権の主張と発信を繰り返している。 論説では、南太平洋諸国の外交姿勢、特に対中国について解説した『太平洋の島嶼地域情勢―中国の思惑と島々の心情を読む』と、スペイン、モロッコ間の島嶼紛争を概説した『2002年のペレヒル島「危機」について』を掲載。 インサイトはエーゲ海におけるトルコとギリシャとの間の島嶼問題について論じた3点を掲載。また南太平洋地域(メラネシア、ポリネシア、ミクロネシア等)に眼を向けるべきという提言も掲載した。 島嶼問題コラムには、昨年12月に公開された「領土・主権の内外等の発信に関わる有識者懇談会」の成果報告書とともに、日本政府による尖閣諸島調査活動紹介の後半を掲載した。また前号に引き続き尖閣諸島調査に参加した筆者による記録・写真をまとめた『魚釣島・南小島・北小島での日本政府の利用開発可能性調査のあらまし』を収録した。
島嶼研究ジャーナル
第12巻1号
2022年12月14日
今号の論説では、竹島について言及がなされている明治初期の外交資料について検討した『朝鮮国交際始末内探書再考』、史実であるヴァージン諸島購入やイースター島売却提案をもって売買による領土の取得について論じた『国家間における島の売買と国際法』を掲載した。 インサイトではテレビのドキュメンタリー番組などで写された有名な竹島の写真について出典を解き明かした『1965年の朝日放送番組「リャンコ─竹島と老人の記録─」と『橋岡アルバム』─竹島アシカ猟写真の拡散の検証』。海洋および漁業に関して国際組織と台湾の関わり方を検討する『「漁業主体」台湾の国際的な枠組みへの参加―かつお・まぐろ類地域漁業管理機関を素材として―』。また、『失地回復主義的中国の2021年から2024年までの海洋作戦?』では、中国現政権の構想する海洋戦略について概説している。 島嶼問題コラムは、1979年に実施された国による尖閣諸島調査に実際に参加した筆者による記録『魚釣島・南小島・北小島での日本政府の利用開発可能性調査のあらまし―魚釣島・南北小島はどんな島なのか―』を記録写真とともに収録した。
島嶼研究ジャーナル
第11巻2号
2022年04月01日
『島嶼研究ジャーナル』は本号よりフルカラー印刷となった。鮮明な図、地図、写真の掲載が可能になり、より読みやすい誌面になったと自負している。 今号の【論説】は、ロンドン大学教授(海上自衛隊幹部学校(JMCSC)客員教授でもある)による、中国の海洋戦略を解説した『戦略が「グレー」ではなく「ハイブリッド」である場合』を掲載している。また、竹島問題に関する韓国の主張のうち、サンフランシスコ平和条約における部分について論じた『竹島問題に関する1996年の韓国の主張について』を掲載。 【インサイト】では、河川の中にある島(中州、川中島)の領土問題について、コンドミニウム(共同領有)であり、かつ主権が入れ替わる「交代式」である例について考察した『世界唯一の「交代式」コンドミニウムとしての会議島』。また、撮影時期や出典が不明だった竹島におけるアシカ猟写真について、詳細を解き明かした『1941年の撮影と判明した竹島でのアシカ猟師の集合写真』を掲載した。 【島嶼問題コラム】では、尖閣諸島、また九州南端から台湾へと続く「琉球弧」の諸島が、中国の海洋進出の標的とされている現状を説く『尖閣諸島と中国の戦狼外交』を掲載している。
島嶼研究ジャーナル
第11巻1号
2021年04月23日
今号の論説では、米国の研究者の視点から、尖閣諸島の主権問題を論じた『尖閣諸島に及ぶ日本の主権に関する米国の認識』、また、南シナ海をめぐるフィリピンと中国の紛争に関して、国連海洋法条約に基づいて設立された仲裁廷が2016年に下した判断とその後について論じた『中国による南シナ海での違法な人工島建設の法的結果』を掲載した。 インサイトには、若手研究者による『気候変動が島嶼等に与える影響 ―国際法からのアプローチを中心に―』。『島をめぐる係争水域の共同開発に関する一考察』『2020年から2021 年にかけて登場した韓国の竹島海上警備策の特徴』『インド洋島嶼国セーシェル共和国とモーリシャス共和国の領土問題とブルー・エコノミーの役割』の4本を掲載している。 コラムでは、『島嶼領土に対する日本政府の基本的認識』として、北方領土、竹島、尖閣諸島に関わる日本政府の認識を紹介し、日本は領有主張の根拠を国際法に置いていることを解説している。
島嶼研究ジャーナル
第10巻2号
2021年04月23日
今号の論説では、ヨーロッパの研究者の視点から、日本の抱える3つの島嶼領土の問題を論じた『高慢と偏見-北東アジアにおける海洋紛争』、また、尖閣諸島問題の歴史を振り返り、同諸島における日本の主権を確認する『尖閣諸島問題の歴史と課題』の連載を開始した。 インサイトには、国際法用語としての「実効支配」を解説しマスコミの誤用を指摘する『「実効支配」とは何か?』。さらに『南シナ海のある事件』では、オーストラリアの研究者が、中国の漁船団及び海警局とNATO軍艦との、南シナ海上での事件を仮定し、そのif事件シナリオを国際法で評価する試みを行っている。 また、今回の国際判例紹介では、国際仲裁裁判所の裁定とローマ法王の仲介を経て、島嶼領土問題の平和的解決に至った「ビーグル海峡事件(アルゼンチンVSチリ)」を取り上げている。
島嶼研究ジャーナル
第9巻2号
2020年04月10日
今号の論説は、中谷和弘東大教授によるアラブ首長国連邦(UAE) とイランとの領土紛争について考察した『アブムーサ島に関するイラン・シャルジャ間の了解覚書についての国際法上の考察』、下山憲二海上保安大学校准教授による遠隔地の帰属に関する先占基準の適用と沈黙が黙認となるのかを論じた『遠隔地に対する実効支配と関係国による沈黙の効果―尖閣諸島を題材として―』そして、第7巻2号から4回に渡って連載してきた、北方領土の法的諸権利を論じる『北方領土問題の歴史と諸権利(4)』が完結した。 インサイトでは、篠﨑正郎航空自衛隊幹部学校教官による英国の島嶼領土であるフォークランドの防衛についての考察『イギリスの防衛政策にとってのフォークランド紛争―本土防衛と島嶼防衛の均衡―』、第9巻1号から3 回に渡って連載予定のクラスカ米海軍大学教授による『虎の口に頭を突っ込む―領海内の潜水艦による諜報―(2)』では平時における潜水艦の諜報活動と海洋法について豊富な例を挙げて検討・分析を行っている。 コラムでは、2020年3月、虎ノ門に新設された内閣官房の発信事業「領土・主権展示館」について紹介する。

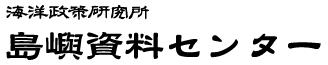
情報ライブラリ
日本の島嶼領土
尖閣諸島 Facts & Figures
竹島 Facts & Figures
北方領土 Facts & Figures
小笠原諸島 Facts & Figures
沖ノ鳥島 Facts & Figures