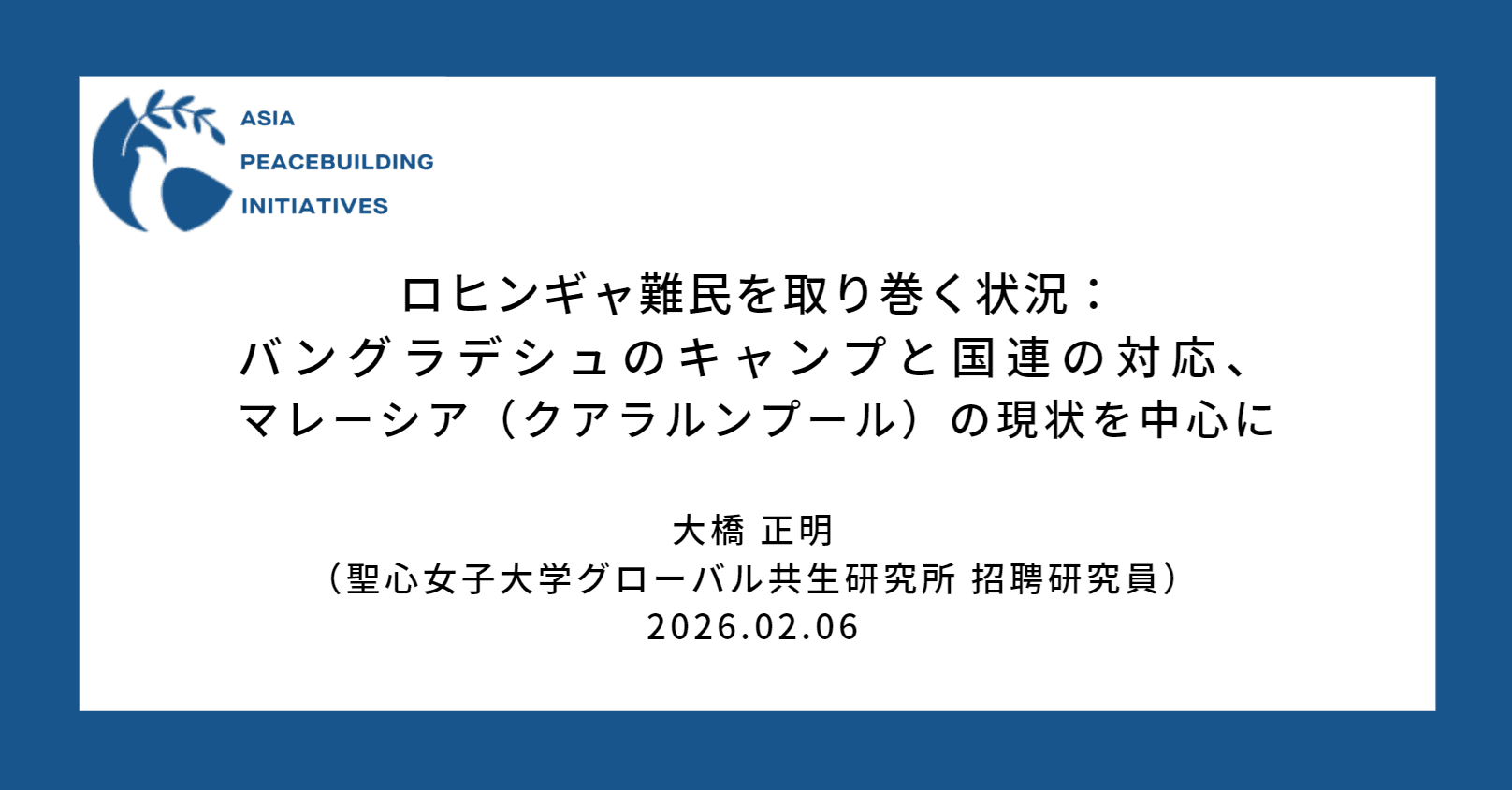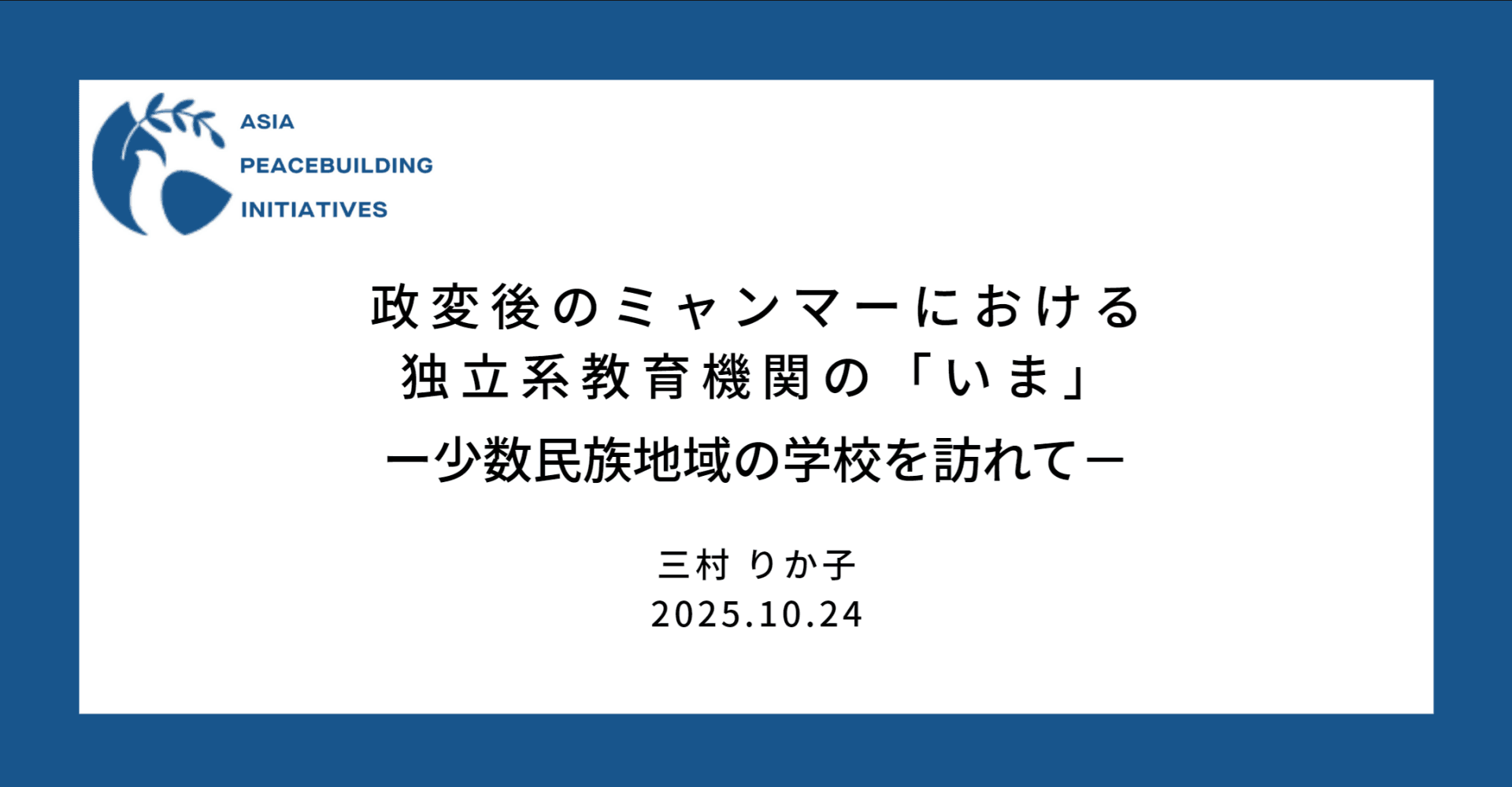-
2026.02.06
ロヒンギャ難民を取り巻く状況:バングラデシュのキャンプと国連の対応、マレーシア(クアラルンプール)の現状を中心に
本論考は、支援縮小が続く中でロヒンギャ難民が直面している現実を、バングラデシュのキャンプとマレーシアでの生活状況を軸にわかりやすく整理しています。難民の暮らしを支えてきた仕組みが揺らぐ今、国際社会がどんな課題に向き合うべきなのかを考える手がかりとなる内容です。
-
2025.10.24
政変後のミャンマーにおける独立系教育機関の「いま」 ―少数民族地域の学校を訪れて―
本レポートは、政変後のミャンマーで教育を守ろうとする独立系学校に焦点を当てます。政府系や武装勢力系に属さない中立的な学校は、少数民族地域で数少ない選択肢となっています。筆者は約1か月間の現地滞在を通じて、資金難や安全の不安、徴兵制など若者を取り巻く課題を記録し、内戦下で教育を続ける意義と希望を考察します。
-
2025.10.17
【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (3) ―バングラデシュからの海外を目指す―
本エッセイ(第3回/全3回)は、ロヒンギャ人をめぐる国籍問題と、ミャンマー・バングラデシュ両政府の対応を考察します。ミャンマー政府はロヒンギャ人を「移民」として国籍を認めず、バングラデシュ政府も自国民としての統合には否定的です。こうした制度の狭間で、ロヒンギャ人は「どの国にも属さない存在」として扱われています。筆者は現地調査を通じて、国境や国籍に縛られた近代国家の枠組みが、難民の尊厳や人権にどのような影響を与えているのかを問い直します。シリーズの締めくくりとして、制度の限界と人間の尊厳をめぐる根本的な問いに迫ります。
-
2025.10.10
【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (2) ―ラカイン州政治情勢に翻弄される難民たち―
本エッセイ(第2回/全3回)は、バングラデシュ側のロヒンギャ人難民キャンプで暮らす人々の声を通じて、彼らの生活実態を描きます。筆者は現地調査の一環として家庭を訪問し、若者や女性たちから教育や労働、家族の喪失、将来への不安などについて聞き取りを行いました。難民キャンプでは支援団体による雇用のほか、非公式な労働も広がっており、現地のベンガル人との関係性も複雑です。一方で、治安の悪化や勢力争いも報告されており、難民たちは不安定な環境の中で暮らしています。現場の声を通じて、制度の限界と人間の尊厳を問い直します。
-
2025.10.06
【動画】ドキュメンタリー「バングラデシュ:政変と少数民族」予告編のご紹介
独立から53年を迎えたバングラデシュでは、先住民族・少数民族が今もなお、アイデンティティと権利をめぐる課題に直面しています。2024年の政変後も状況は改善されず、土地問題や生活基盤の脆弱さが続いています。特に若い世代は、多数派社会への適応と自文化の保持のはざまで揺れ動き、「変化の波に取り残されるのではないか」という不安を抱えています。本トレーラーでは、先住民族・少数民族の人々が、自らの将来とこの国への期待をどのように語るのかを描いたドキュメンタリー作品をご紹介します。 本トレーラーでは、先住民族・少数民族が自らの将来とこの国への期待をどう語るのかを描いたドキュメンタリー作品をご紹介します。
-
2025.10.03
【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (1) ―現地のベンガル人と隔絶されつつも隣り合って暮らす難民たち―
本エッセイ(第1回/全3回)は、ミャンマーからバングラデシュへ逃れたロヒンギャ人難民の現状を、2024年11月の現地調査をもとに描いています。筆者はタイ=ミャンマー国境の専門家で、今回初めてバングラデシュ側の難民キャンプを訪問。ロヒンギャ人は現地のベンガル人と外見や言語が近いにもかかわらず、有刺鉄線で隔てられた生活を送っています。支援の縮小や労働規制の中、難民たちは日々の暮らしを模索しています。本シリーズでは、国境を越えて生きる人々の姿から、近代国家の制度が抱える限界と難民の尊厳をめぐる課題を考えます。
-
2025.08.29
第2次トランプ政権の大統領令がミャンマー難民キャンプに与える影響(後編):トゥーサーが過ごした数年間を振り返って
本稿(後編)では、タイ・ミャンマー国境の難民キャンプで暮らす一人の男性の数年間を追います。米国への第三国定住の再開に希望を託しながらも、政策の急転によってその夢は断たれました。家族とともに移動を繰り返し、非正規滞在者として不安定な生活を送る中で、彼が直面した現実とは何か。個人の視点から、国際援助と難民政策のはざまで揺れる人々の姿を描きます。
-
2025.08.25
第2次トランプ政権の大統領令がミャンマー難民キャンプに与える影響(前編):米国への第三国定住を中心に
本稿(前編)は、タイ・ミャンマー国境の難民キャンプを舞台に、第2次トランプ政権の大統領令がもたらした影響を検証します。2025年1月の政権発足後、米国への第三国定住プログラムは全面停止し、医療や食料などの基本支援も大幅に削減されました。こうした政策転換が、長期化する難民生活や人々の将来にどのような影響を与えたのか。現地調査を踏まえ、国際援助に依存する構造の脆弱性と、難民たちの希望が断たれる過程を明らかにします。
-
2025.06.20
紛争後スリランカで進むPVE(暴力的過激主義予防)活動
本論考では、内戦後のスリランカにおける暴力的過激主義予防(PVE)活動に焦点を当てます。スリランカでは2009年のLTTE(反政府武装組織)制圧後、宗教対立が先鋭化しました。さらに2019年の連続爆破テロにより社会分断が深刻化する中、国際NGOと地元団体が若者向けの予防プログラムを展開しています。こうした状況を踏まえ、現地調査を通じてこれらの実践とその効果を明らかにし、多民族・宗教共存というグローバルな理念を現地に適応させる際の課題と可能性を考察します。
-
2025.03.21
我々はタリバンとどう向き合ったらよいのか? ― ウズベキスタンの実利的関与を手がかりに
本論考では、タリバン支配下のアフガニスタンをめぐる国際関係を分析し、特にウズベキスタンの実務的アプローチに焦点を当てます。貿易拠点設立や教育支援を通じたウズベキスタンの関与は、欧米の制裁政策とは対照的です。アフガニスタンの孤立回避と自立支援の重要性から、変動する世界秩序における日本の役割を考察します。
-
2025.02.07
イエメン内戦概況解説 ―「紛争のリンケージ」に着目して―
本論考では、2015年以降続くイエメン内戦を「国際化した内戦」と位置付け、その基本構造を整理するとともに、ガザ紛争後のフーシー派の行動変化やイエメン内戦への影響を考察します。また、フーシー派の国際的な存在感の高まりや、ロシアとの連携強化を「紛争のリンケージ」として分析し、今後の和平の展望を検討します。
-
2024.11.15
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(3):海民ウラク・ラウォイッの〈先住民〉運動
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(3)では、1974年にタルタオ国立公園に指定されたことがウラク・ラウォイッの集住と観光客増加に与えた影響を考察しています。
-
2024.11.01
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(2):海民ウラク・ラウォイッの定住
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(2)では、ウラク・ラウォイッが1900年頃にリペ島に定住した経緯を探ります。
-
2024.10.18
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(1):タイ南部の「秘境」
「アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題」は、アンダマン海のタルタオ国立公園内に位置するリペ島とその周辺の土地問題を探る全3部作です。
-
2024.04.03
行き詰まるウガンダの難民支援 ―食料支援プログラムの見直しと難民の窮状―
-
2024.03.25
パレスチナ人民の自決権〜国際的枠組みの根本に立ち返る
ガザの惨劇は長年力でもって無理に無理を重ねてきた結果である。原点に立ち返って考え直すしか方法はないと思う。それは困難なことだし、不可能と言う人も多いだろう。シオニズム運動の誕生からほぼ130年、中東戦争の勃発から80年近い。時間の経過が生んだ不可逆的な部分もある。しかし、このままでは和平の展望は開けない。短期的に事態を収拾するだけでは、いつかまた破綻する。
-
2024.03.20
【エッセイ・映画評】 人間が獣のように吠える時〜 ~『この都市を失って』(『負け戦でも』)
近年ミャンマー人監督によるドキュメンタリー映画が数多く作成され、日本をはじめ国外でも上映機会が増えている。国際映画祭などで選出されることも稀ではない。これは以前には見られなかった現象である。2023年にはミャンマー人による作品(『この都市を失って』(『負け戦でも』))が山形国際ドキュメンタリー映画祭のアジア部門(「アジア千波万波」)で最高賞(小川紳介賞)に選ばれた 。 本エッセイでは、ミャンマーのドキュメンタリー作家が2021年クーデター後に直面する課題を論じた上で、『この都市を失って』(『負け戦でも』)がいかに新境地を切り拓いたかを示したい。
-
2024.03.11
難民支援におけるHDPネクサス :日本のODAはバングラデシュでこれをどう実現できるのか?
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、何らかの理由で故郷を追われ国内外に避難を強いられている人の数は2023年5月現在1億1千万人で、18年末の7,080万人からわずか4年間で4千万人も増加した。現下の国際情勢を見れば、この数はその後も大きく増加していると思われる。なおこのうち3,640万人が国外に逃れた難民で、その 69%が低・中所得国、とりわけ20%が特に貧しい後発開発途上国(以下LDC)に逃れており、しかも66%が滞在期間5年以上の長期難民 であり、それらの国々での受け入れ負担は大きい。
-
2024.03.08
仏教徒とムスリムの関係:ミャンマーでの反ムスリム運動の背景を考える
現在、反ムスリムの動きは少なくなり、2021年のクーデターの影響で、マイノリティ全体に対する風向きが少しだけ良い方向に変わりつつあるように見える。しかし、反ムスリムの動きが全くなくなったわけではない。ミャンマーの人々が抱く反ムスリムの感情は民主化後に急激に高揚したようにも見えるが、実際には民主化以前は顕在化していなかっただけの状態であった。本稿ではミャンマーで多数を占める仏教徒と、マイノリティであるムスリムの関係について、少し時代をさかのぼって考えてみたい。
-
2024.02.29
【エッセイ】ミャンマーの民主闘争と国内避難民 (3)―越境支援の現場から―
本連載はこれまで、私がマンダレー滞在中に見た国内避難民の様子を描いてきた。第三回目の今回は、舞台を隣国タイの国境地帯に移したい。私はマンダレーに数週間滞在した後、タイに飛んだ。タイでは10日間ほど滞在し、ミャンマーとの国境地域を調査した。とりわけ本稿で伝えたいのは、国境を通して実施されるミャンマー人たちによる同胞への支援の様子である。
新着記事NEW
ARTICLES
-
2026.02.06
大橋 正明バングラデシュ新着ロヒンギャ難民を取り巻く状況:バングラデシュのキャンプと国連の対応、マレーシア(クアラルンプール)の現状を中心に
本論考は、支援縮小が続く中でロヒンギャ難民が直面している現実を、バングラデシュのキャンプとマレーシアでの生活状況を軸にわかりやすく整理しています。難民の暮らしを支えてきた仕組みが揺らぐ今、国際社会がどんな課題に向き合うべきなのかを考える手がかりとなる内容です。
-
2025.10.24
三村 りか子新着ミャンマー政変後のミャンマーにおける独立系教育機関の「いま」 ―少数民族地域の学校を訪れて―
本レポートは、政変後のミャンマーで教育を守ろうとする独立系学校に焦点を当てます。政府系や武装勢力系に属さない中立的な学校は、少数民族地域で数少ない選択肢となっています。筆者は約1か月間の現地滞在を通じて、資金難や安全の不安、徴兵制など若者を取り巻く課題を記録し、内戦下で教育を続ける意義と希望を考察します。
-
2025.10.17
岡野 英之バングラデシュ新着【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (3) ―バングラデシュからの海外を目指す―
本エッセイ(第3回/全3回)は、ロヒンギャ人をめぐる国籍問題と、ミャンマー・バングラデシュ両政府の対応を考察します。ミャンマー政府はロヒンギャ人を「移民」として国籍を認めず、バングラデシュ政府も自国民としての統合には否定的です。こうした制度の狭間で、ロヒンギャ人は「どの国にも属さない存在」として扱われています。筆者は現地調査を通じて、国境や国籍に縛られた近代国家の枠組みが、難民の尊厳や人権にどのような影響を与えているのかを問い直します。シリーズの締めくくりとして、制度の限界と人間の尊厳をめぐる根本的な問いに迫ります。
-
2025.10.10
岡野 英之バングラデシュ新着【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (2) ―ラカイン州政治情勢に翻弄される難民たち―
本エッセイ(第2回/全3回)は、バングラデシュ側のロヒンギャ人難民キャンプで暮らす人々の声を通じて、彼らの生活実態を描きます。筆者は現地調査の一環として家庭を訪問し、若者や女性たちから教育や労働、家族の喪失、将来への不安などについて聞き取りを行いました。難民キャンプでは支援団体による雇用のほか、非公式な労働も広がっており、現地のベンガル人との関係性も複雑です。一方で、治安の悪化や勢力争いも報告されており、難民たちは不安定な環境の中で暮らしています。現場の声を通じて、制度の限界と人間の尊厳を問い直します。
-
2025.10.06
バングラデシュ新着【動画】ドキュメンタリー「バングラデシュ:政変と少数民族」予告編のご紹介
独立から53年を迎えたバングラデシュでは、先住民族・少数民族が今もなお、アイデンティティと権利をめぐる課題に直面しています。2024年の政変後も状況は改善されず、土地問題や生活基盤の脆弱さが続いています。特に若い世代は、多数派社会への適応と自文化の保持のはざまで揺れ動き、「変化の波に取り残されるのではないか」という不安を抱えています。本トレーラーでは、先住民族・少数民族の人々が、自らの将来とこの国への期待をどのように語るのかを描いたドキュメンタリー作品をご紹介します。 本トレーラーでは、先住民族・少数民族が自らの将来とこの国への期待をどう語るのかを描いたドキュメンタリー作品をご紹介します。