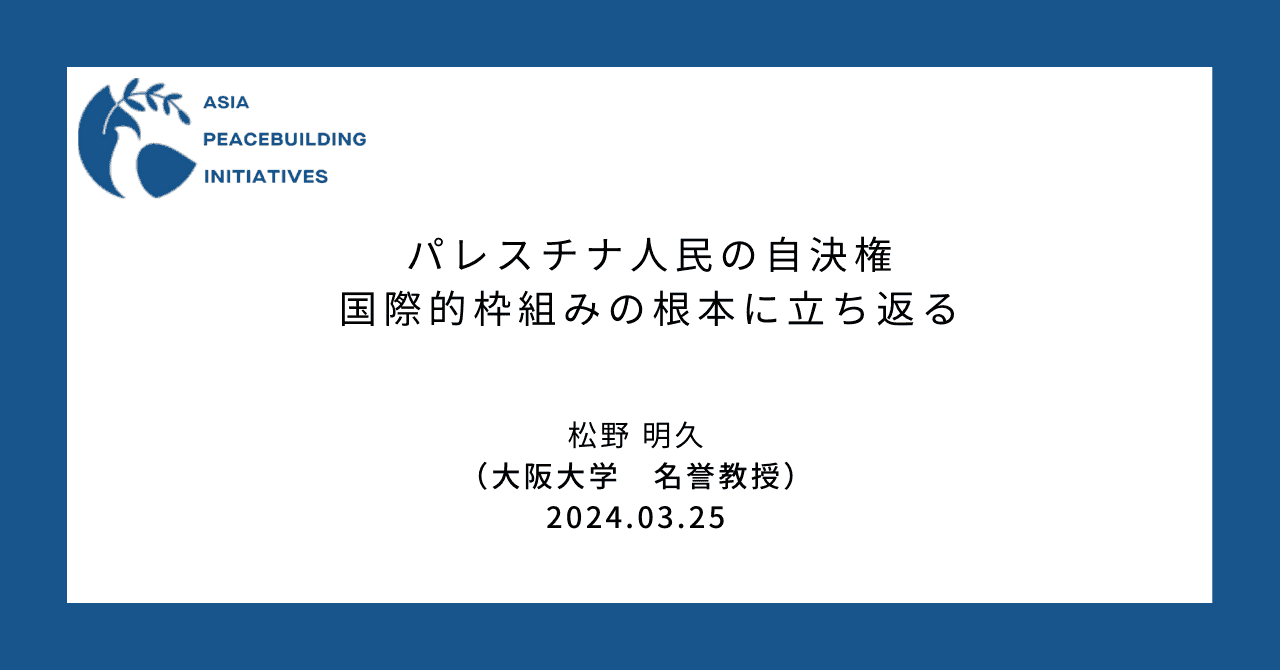- 松野 明久
- 平和構築全般
パレスチナ人民の自決権〜国際的枠組みの根本に立ち返る
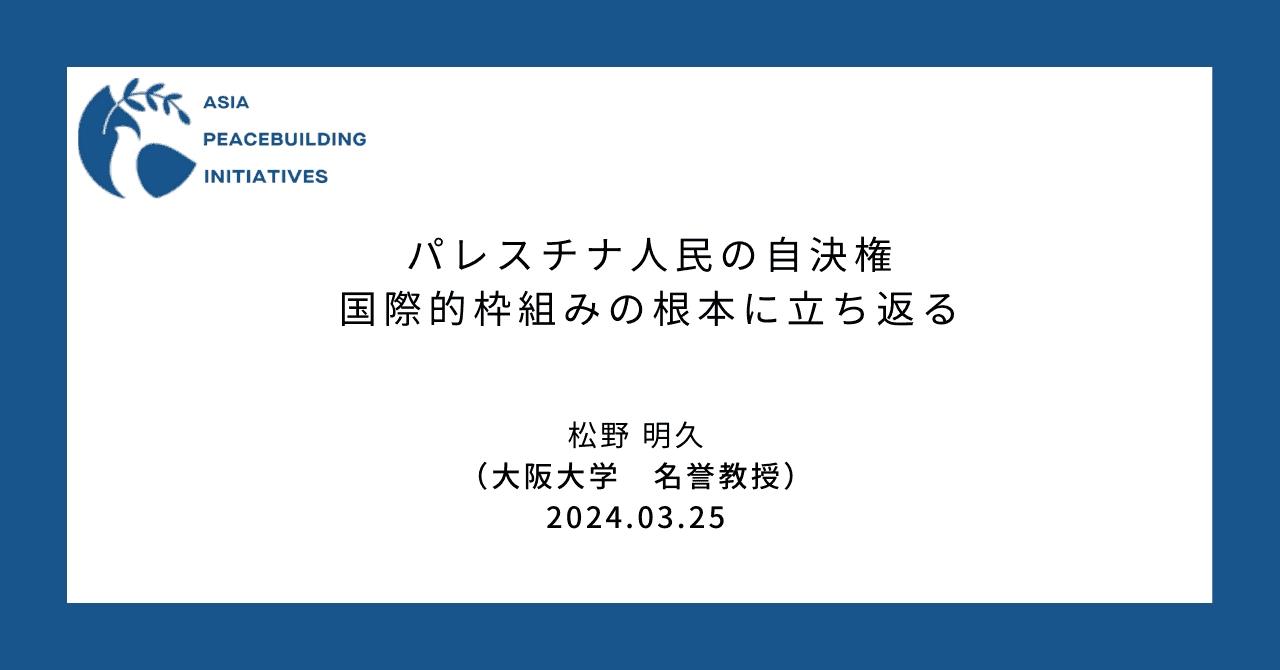
※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。
グローバル・ガバナンスと自決
ガザの惨劇は長年力でもって無理に無理を重ねてきた結果である。原点に立ち返って考え直すしか方法はないと思う。それは困難なことだし、不可能と言う人も多いだろう。シオニズム運動の誕生からほぼ130年、中東戦争の勃発から80年近い。時間の経過が生んだ不可逆的な部分もある。しかし、このままでは和平の展望は開けない。短期的に事態を収拾するだけでは、いつかまた破綻する。
問題の根本はパレスチナ人民の自決であり、彼らの自決権が侵害されていることである。第一次世界大戦後の世界構想に関して民族自決原則を掲げたウッドロウ・ウィルソン大統領の14ヵ条(1917年)は民族自決原則の確認であったし、国際連盟の委任統治制度は極めて不十分ながら人民の自決の援助を使命とした。国際連合は憲章の第1条で自決の原則を謳う。自決権は国連総会決議1514 (XV)「植民地独立付与宣言」(1960年)で再確認され、2つの国際人権規約(1966年)で人権として認められた。こうした歴史的経緯が示しているのは、人民の自決は国際社会がそれを保証しなければならないということである。自決を行う人民が弱小であればなおさら国際的枠組みが重要となる。
国際連盟とパレスチナ
国際社会のパレスチナへの公的な関与は、1922年、国際連盟がパレスチナの統治をイギリスに委任したことを始まりとする。そのとき国際連盟は、パレスチナにユダヤ人の民族郷土を建設するという1917年の英シオニスト機構宛英外相書簡、イギリスの二枚舌外交と批判されるいわゆる「バルフォア宣言」に国際的承認を与えた。これが最初のボタンの掛け違えとなる。
国際連盟はパレスチナ人の自決を援助するどころか、ユダヤ人の国家建設を進めようとした。表向き、バルフォア宣言も委任統治も「現地非ユダヤ系住民の市民的、宗教的権利を侵害しない」という条件を付けていたが、ユダヤ人の民族郷土とはユダヤ人が統治し、アラブ人は従属的な存在となるというユダヤ人国家に他ならない。バルフォアは後継となる外相宛のメモに「列強4ヶ国はシオニズムに約束した。シオニズムは、正しかろうと間違っていようと、良かろうと悪かろうと、長い伝統に根ざし、今日必要なものであり、将来における希望なのだ。それは古の土地に住む70万の住民の願望や権利よりはるかに重要だ」などと書き残していた[1]。
一方、国際連盟は規約の第22条で、未だ自立できない人民の福祉と発達を計ることは文明の神聖なる使命であると謳い、オスマン帝国下のいくつかの民族は独立国として仮承認を受けられるほどに発達しており、受任国は彼らが独立するまで助言・援助を与えると述べた。イギリスのパレスチナ政策はこの第22条と矛盾していた。イギリスの構想を懸念したアメリカはパリ講和会議で現地住民の意見を聴取する委員会の設置を提案した。意見聴取に後ろ向きなイギリスとフランスがサボタージュする中で、アメリカ主導のキング・クレーン委員会が意見聴取を行った。委員会が受け取った請願の72%がシオニストの計画に反対であり[2]、委員会はパレスチナへのユダヤ人移住は自決に対する重大な侵害にあたると結論した[3]。しかし、アメリカは国際連盟に入らず、ウィルソン大統領も病気で倒れ、イギリスとフランスの思惑に歯止めをかける勢力はなかった。
[1] United Nations, The Right of Self-Determination of the Palestinian People: Prepared for, and under the Guidance of, the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, New York, 1979, p. 16.
[2] Encyclopedia Britannica, "King-Crane Commission", https://www.britannica.com/topic/King-Crane-Commission.
[3] John Quingley, "Self-determination in the Palestinian Context," in Susan M. Akram, Micheal Dumper, Michael Lyink, and Iain Scobbie (eds.), International Law and the Israeli-Palestinian Conflict: a rights-based approach to Middle East conflict, Routledge, 2011, p. 220.
国際連合とパレスチナ
国際連合憲章は明確に自決の原則を謳う。しかし、1947年、国連パレスチナ特別委員会(UNSCOP)は、連盟の判断を踏襲するとして、パレスチナ人民に自決原則を適用しないと決め、分割案を提示した。UNSCOPは「アラブ人とユダヤ人の領土的主張はともに有効であるが和解不可能で、分割案が最も現実的で実行可能な解決策だ」と説明した。もちろん委員会にはこれに反対する少数派がいたが、多数派が少数派を制した。総会は11月29日この分割案を決議181 (II)として採択する。アラブ諸国は決議を拒否し、イスラエルは1948年5月14日イギリスが撤退すると同時に建国を宣言。アラブ6ヶ国がイスラエルを攻撃し、ここに第一次中東戦争が始まった。
国連総会決議がパレスチナ人の自決権に言及したのは1969年のことである。文言は「パレスチナ人民の不可分の権利を再確認する」[4]。つまり、権利をもつのは歴史的パレスチナに居住する人民であり、それは彼らが本来持っている権利であり、すでに一度は確認された権利だということである。
国際司法裁判所がパレスチナ人民の自決権に言及した分離壁に関する2004年の勧告的意見はよく知られている。勧告的意見は、パレスチナ人民の存在はもはや議論の余地ないものであり、彼らがもつ正当な権利の中に自決権も含まれるとした。そして、分離壁はパレスチナ人の自決権を著しく侵害するものだと結論した[5]。
[4] United Nations General Assembly Resotluion 2535 (XXIV), 10 December 1969.
[5] International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004.
フェアーな国際的枠組みの構築
国際社会による自決の保証といっても、当の国際社会が一枚岩ではない。国連総会はパレスチナに同情的であるが、決定権をもつ安保理でアメリカが拒否権を行使する。パレスチナ問題をめぐる国際的枠組みも決してフェアーではない。
冷戦が終結し、湾岸戦争が終わった1991年、アメリカとソ連が中東和平会議(マドリード会議)を共催した。それはアラブ諸国11ヶ国と27ヶ国が参加する一大マルチステークホルダー会議であった。マドリード会議はイラクのフセインを封じ込めたアメリカが、アラファト率いるPLOの弱体化をチャンスと見て、中東での覇権強化の意図をもって開催したものであり、またパレスチナ代表団は独自の代表団ではなく、ヨルダンの派遣団の一部として参加を許されたにすぎない。パレスチナ人民の自決を議論するのにフェアーな枠組みではなかった。
しかし、マドリード会議がうまくいかないからとしてオスロ秘密交渉にシフトした結果、和平はイスラエルとパレスチナの当事者の直接交渉に委ねられることになり、そうなると両者の力関係がストレートに交渉を規定した。言うまでもなく両者には圧倒的なパワーの差があり、直接交渉という枠組みは著しくアンフェアーであった。案の定、1993年のオスロ合意は、画期的と言われたが、実際にはパレスチナ側が歴史的な譲歩をしたのであり、さらなる直接交渉で1993年に合意されたオスロIIに至っては、パレスチナが致命的とも言える不利な条件を吞まされることになった。結局、オスロ和平プロセス崩壊の理由のひとつはオスロ合意そのものにあったと言わざるをえない。こうなった責任は、むしろ国際連盟以来、人民の自決を国際社会が保証する原則を歪め、パレスチナ人民の自決権をないがしろにして来た国際社会にこそある。憎悪と暴力の連鎖などといった論理で当事者に責任を転嫁してはならない。
オスロ和平プロセスの破綻が明らかになり、2002年にアメリカ、ロシア、国連、EUの4者によるパレスチナ和平推進を目的としたカルテットが設置された。和平に向けたロードマップを作成したものの、カルテットは事実上機能不全に陥っている。カルテットの重要な柱の一つはイスラエルとパレスチナの直接交渉であり、その交渉実現のためにパレスチナ側が一本化されるのを国際社会は待っている。パレスチナ人が団結できないでいるのを責めるのはたやすい。しかし、パレスチナ人にしてみれば、団結したところで、イスラエルとの直接交渉という到底対等ではありえない自決権実現の枠組みに向き合わなければならないとしたら、そこには国際社会に対する不信と失望しかない。国際社会がやるべきことをやると覚悟を決めるしか、出口はないと思う。

大阪大学 名誉教授