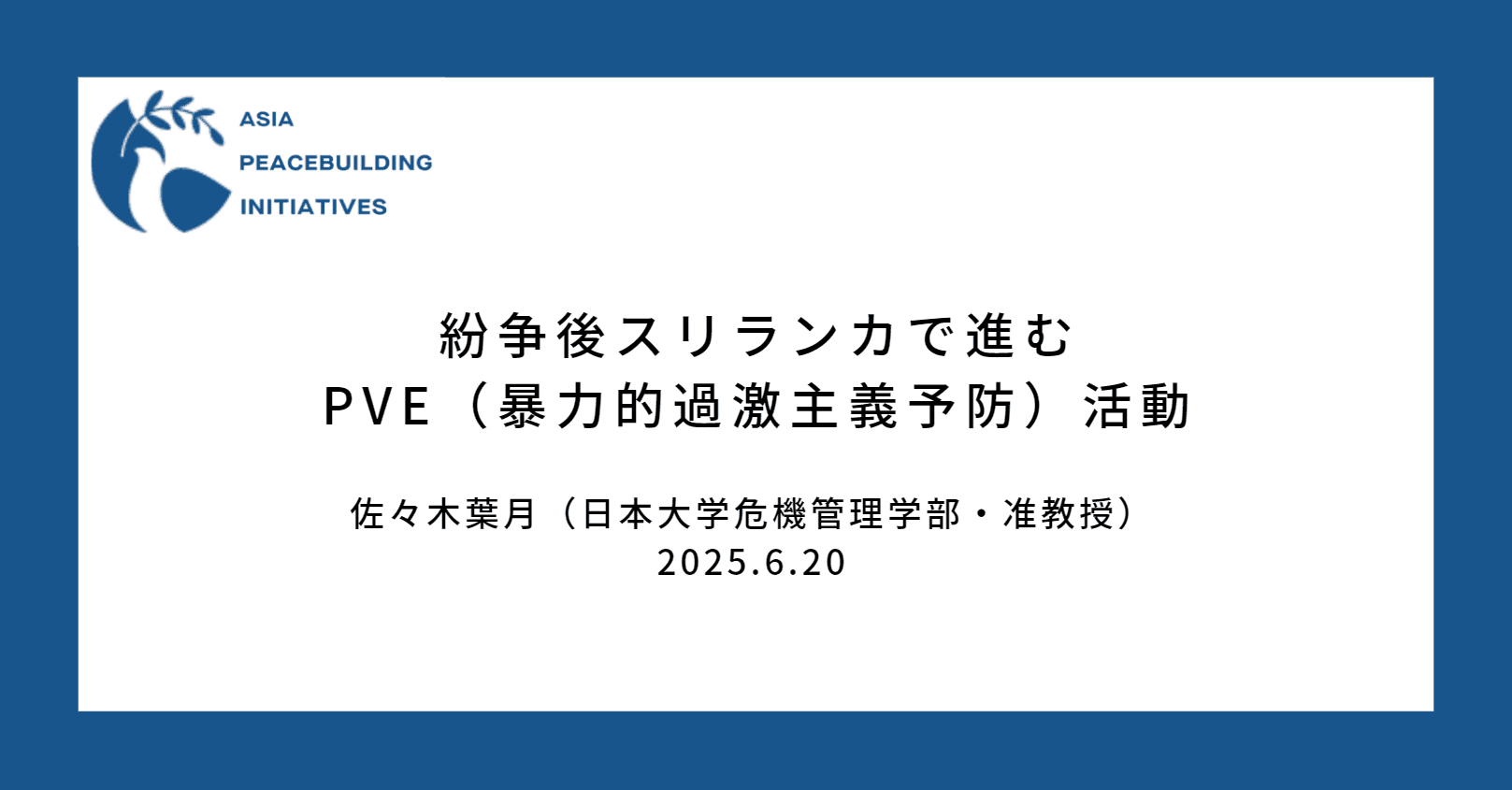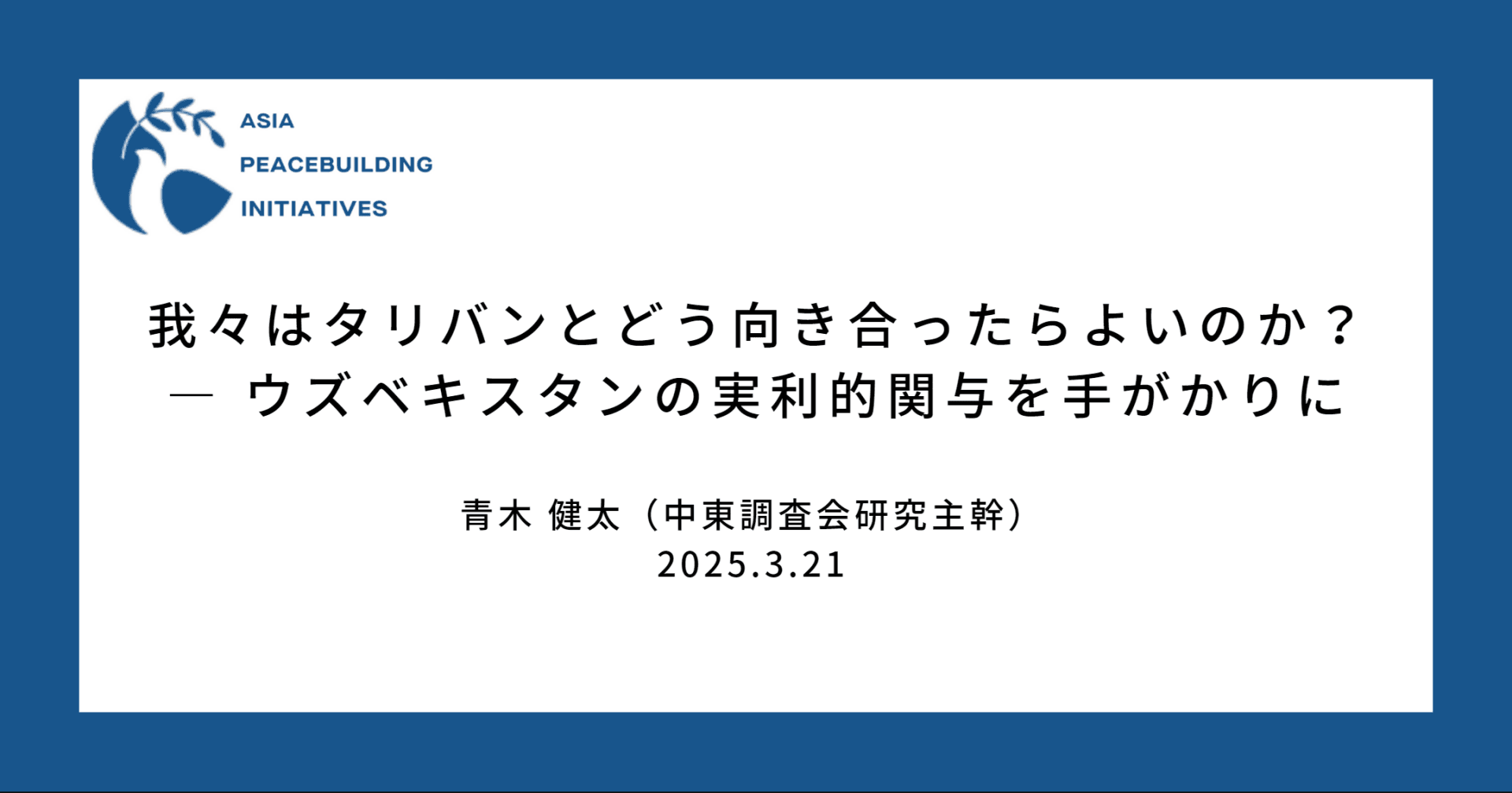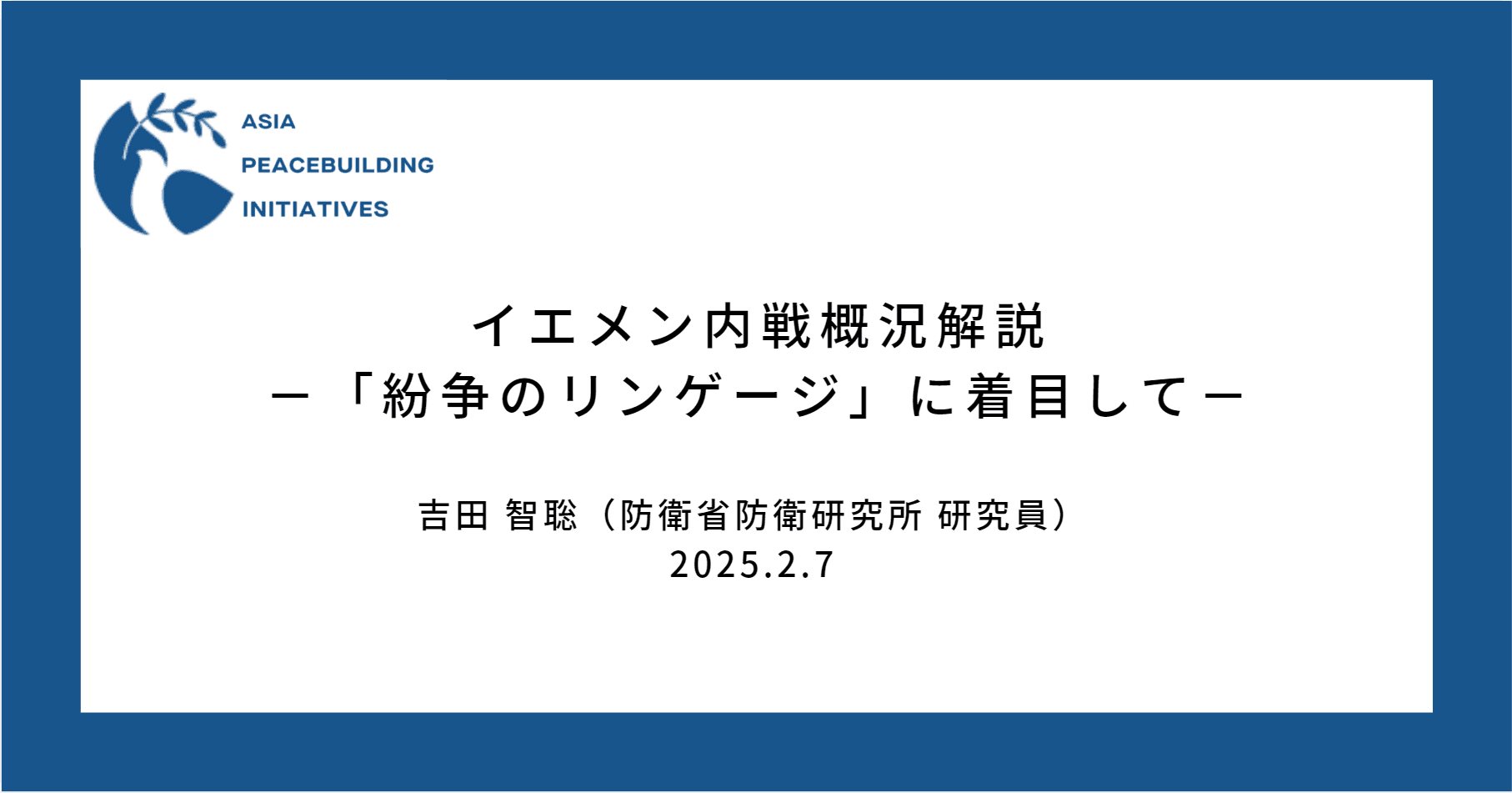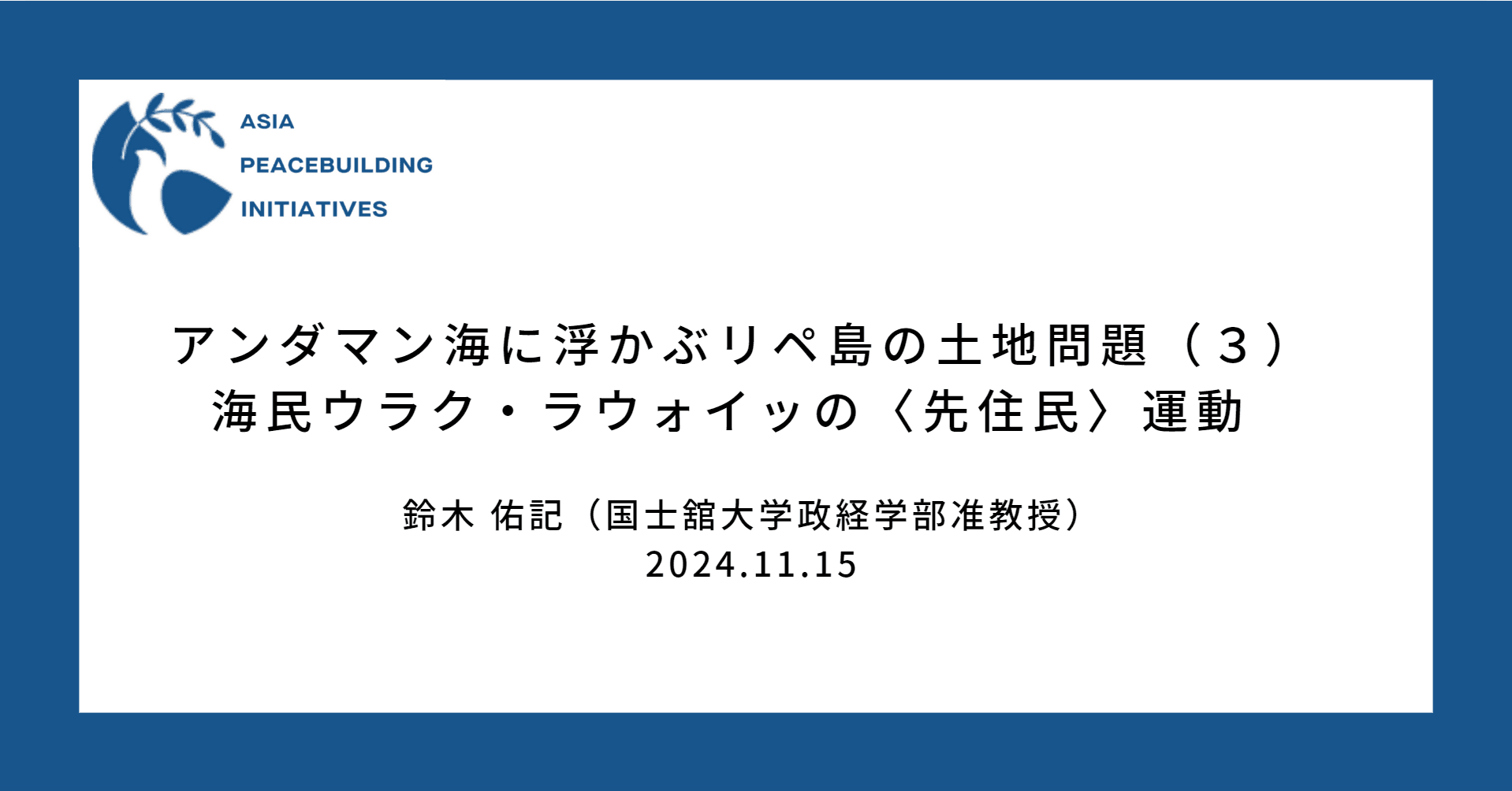- 平和構築全般
北アイルランド和平プロセスの今

〜 パワーシェアリングの機能不全と埋まらぬ両者の溝 〜
「成功事例」の危機
1998年4月10日、北アイルランド紛争を終わらせる和平協定が締結された。一般にはベルファスト協定と呼ばれるが、その日が復活祭前の聖金曜日(Good Friday)であったことから聖金曜日協定とも呼ばれている。これによって、イギリスとの連合維持を望むプロテスタント系住民とアイルランド共和国との統一を望むカトリック系住民の対立から発展した武力紛争は終わった。協定では、北アイルランド自治政府内閣のポストを選挙で獲得した議席に応じて配分するパワーシェアリング(権力分有)方式が採用された。このような異なる民族集団の共同統治をコンソーシエーショナリズム(consociationalism)というが、北アイルランドはその数少ない「成功事例」として語られてきた。
しかし、協定から18年たった2016年11月、北アイルランド自治政府は「再生可能熱インセンティブ(Renewable Heat Incentive)」というエネルギー政策の失敗で巨額の赤字(約5億ポンド)を出してしまい、内閣は解散に追い込まれてしまった。環境政策の失敗と北アイルランド紛争の構図との間に本質的な関係はない。しかし、対立するグループが失敗を弁護する側/追及する側に分かれて闘うとなると、話はちがってくる。この問題では、政策決定時エネルギー相であった第一首相がプロテスタント系急進政党(DUP)の党首であり、その第一首相の失政を追及するカトリック系急進政党(シン・フェイン党)に属する第二首相が抗議の辞任をしたことで、発足後8ヶ月で内閣が崩壊したのである。2017年3月の再選挙に向け両者のレトリックは激しくなり、北アイルランドのコーンソーシエーショナリズムは危機に瀕しているとまで言われるようになった。
そんな情勢の中、私は2017年2月半ばに北アイルランドを訪れた。3月の再選挙に向けたキャンペーンの中でエスカレートする対立の様子をみながら、さまざまな人びとの話を聞いて回り、和平プロセスの現状について考えた。以下にそれを報告したい。
紛争の構図
北アイルランドの人口は約180万人(2011年センサス)である。宗教についてみるとカトリックが約74万人、プロテスタント諸派(長老派、アイルランド教会、メソジストなど)が約75万人で、残りは他の宗教や信仰宗教なしか無回答となっている。スコットランドやイングランドからの移民及びその子孫はほとんどがプロテスタントであり、先住のアイルランド人はほとんどがカトリックである。紛争の争点はこの領域をイギリスとするかアイルランドとするかという帰属の問題であり、それぞれの立場をユニオニスト(イギリス連合派)、ナショナリスト(アイルランド統一派)と呼ぶ。さらに英国王・女王を元首として戴くか否かといった違いもあるので、ユニオニスト急進派をロイヤリスト(loyalist)、ナショナリスト急進派をリパブリカン(republican)という。ただ、先に述べた背景から、紛争はいきおい宗派的対立へとシフトしやすい。紛争のそうした側面に言及する際、宗派的(セクタリアン)という形容詞を使う。
対立の歴史的ルーツをたどれば、16世紀に進んだイギリスによるアイルランドの植民地化に遡る。北アイルランドでは9年戦争(1603年終結)で敗北したゲール領主たちが逃亡した後、イギリスがその土地を取り上げて多くをプロテスタント系植民者に分配した。その後名誉革命(1688-89年)がおき、それによって即位したプロテスタントのウィリアム3世(オランダから招かれたオレンジ公)が、革命で追放されたカトリックのジェームズ2世を最終的にダブリン北部の「ボイン川の戦い」(1690年7月12日)で負かし、アイルランドにおけるプロテスタント優位を決定的なものとした。
「ボイン川の戦い」はプロテスタントにしてみればそれまで抑圧されていた自分たちを解放した戦いであった。例えば1641年のアイルランド蜂起では数千人のプロテスタントが殺されるという事件があった。そのため今でも毎年7月12日はその勝利を祝う日になっており、プロテスタント系結社「オレンジ・オーダー」が北アイルランド各地で「オレンジ・パレード」を行う。オレンジはプロテスタントのシンボルカラーなのである。彼らは名誉革命とウィリアム3世を讃える。しかし、カトリック系住民にとって「ボイン川の戦い」はその後の長く暗い抑圧を決定的にしたできごとであって、それを祝うパレードはプロテスタントの示威行動としか映らない。7月12日は暴力事件がおきやすい。
北アイルランドの帰属問題は、イギリスがアイルランドの独立運動を受けるかたちで1921年にアイルランドを南北に分割し、南側(のちのアイルランド共和国)を独立に向かわせた一方で、スコットランドやイングランドからの移民が多かった北側をイギリス領内にとどめる決定をしたことに端を発する。アイルランドは分断され、北アイルランドのカトリック系住民はイギリスからの離脱を求める武装闘争を継続した。
北アイルランド内の住民同士の対立がエスカレートしたのは1960年代、アメリカの公民権運動に触発され、カトリック系住民が住宅配分や雇用における差別撤廃を要求し始めた頃である。カトリック系住民の権利伸張を快く思わないプロテスタント系住民による妨害が相次ぎ、双方の武装組織(パラミリタリー)による暴力の応酬へとエスカレートした。カトリック系のIRAはそのテロ活動によって悪名高いが、プロテスタント系の武装組織もそれに負けないほど残虐であり、さらにはイギリス軍・警察がプロテスタント側に肩入れするといった状況もあって、紛争は複雑化し、90年代までに3,500人の犠牲者が生まれていた。それが一気に解決へと向かうことになった理由は1997年にブレア政権が誕生したからであった。ブレア首相はクリントン米大統領の支援を受け、北アイルランド紛争の解決に力を入れた。
ピースウォールの現状
行く前から気になっていたのはピースウォールである。ベルファスト観光の「名所」にすらなっているピースウォールは、市西部にあるカトリック系住民とプロテスタント系住民の居住区の境界に設置された分離壁のことである。設置したのは行政で、和平後も住民間の和解が進まない証として知られていた。入り口には鉄の門があって夜11時には閉められるという。戦争・紛争の跡をたどる観光をダーク・ツーリズムというが、ハイヤーでめぐる1時間半のツアーのルートになっているので誰でもそこを訪れ、運転手から説明を受けることができる。この壁の北側の居住区にはシャンキル通り(Shankill Road)があり、プロテスタント系労働者階級の住宅区であることから、リパブリカン武装組織IRAに対抗するUDAやより過激なUDF 、UFFといったロイヤリスト武装組織の活動拠点だったことで知られている。紛争中は酒を飲んでここに迷い込んだカトリック系労働者がリンチにあって殺されるといった事件があった。一方、ピースウォールのカトリック系住民居住区側では、紛争で犠牲となった人びとのために小さな公園がつくられており、今でも花を捧げに来る人があとをたたない。

ピースウォールは境界線に沿ってつくられているが、延々とあるわけではなく、多少迂回すれば双方からの行き来は可能である。しかも閉鎖されるのは深夜だけなので、壁の必要性を疑問視する声もある。ただ、アンケート調査では付近の住民の多くが壁の撤去には消極的だとの結果が出ており、まだ不安が除去されたわけではないことを物語っている。というのも、暴力事件はほとんどなくなったものの、上に述べたような双方の武装組織は完全に解散したわけではなく、武器も完全に押収されていないとみられているからである。
この地区にはそれぞれの主張を描いた「壁画(mural)」が多く、それもまた観光の対象になっている。例えば、ナショナリスト側では、1981年獄中でハンガーストライキをして亡くなったIRAのメンバー、ボビー・サンズ(Bobby Sands)の肖像があり、ユニオニスト側では白馬に乗ったウィリアム3世の勇姿や「トップガン」の異名で知られるUDAのメンバーで数々の暗殺事件に関わったスティーヴィー・マッキーグの肖像が描かれている。唯一救いと思えたのは「女たちのキルト」と題された壁画で、「万人のための平等」「強く、正直に」といったセクタリアニズムを諫めるようなスローガンを掲げていた。



「オレンジ」の旗の下に〜ユニオニストの歴史観〜
ベルファスト東部には、芝生が美しく刈られ、瀟洒な戸建て住宅が建ち並ぶ住宅区が広がる。ここは典型的にプロテスタント系住民の居住区であり、ユニオニスト系政党の強力な地盤でもある。この地区に2015年6月にオープンしたばかりの「オレンジ・ヘリテージ博物館」がある。EUの平和構築資金をえて建設され、プロテスタントの歴史観と彼らの結社であるオレンジ・インスティテュートの変遷を展示している。入るとすぐに名誉革命の展示があり、続いて白馬に乗った等身大のウィリアム3世の人形があらわれる。彼らの物語(ナラティブ)によると、名誉革命時、北アイルランドではカトリックがプロテスタントを(1641年のように)虐殺するという噂が広まり、プロテスタントは当時プロテスタントの拠点となっていた北部の城塞都市デリーに逃げ込んだ。そこをジェームズ2世(カトリック)が攻撃しようとした際、彼らは城塞の門を閉じて籠城し、飢餓に直面しながら援軍をまった(「デリー籠城」という)。そして105日間の封鎖に耐え、ウィリアム3世の武装した船の到来でデリーは解放された。
博物館には「ボイン川の戦い」でカトリック軍側が使ったとされる銃が無造作にテーブルの上においてあり、子どもたちが手に触れたりできるようになっている。こうしたミリタリスティックなセンスはいかがなものかと思うが、EUの平和構築の考え方はそれぞれの文化的伝統を表現することは相互理解につながるというものである。この点、イギリスの政治学者メアリー・カルドーが、90年代の民族紛争の解決において(エスニック)民族主義者の言い分を聞きすぎて彼らをエンパワーしすぎた、その結果民族分断が返って固定化したと批判していることが思い起こされる(メアリー・カルドー『新戦争論』)。
ところで、ベルファスト東部はまったくもってナショナリスト系政党が議席をとれない選挙区であるが、今回の選挙ではユニオニスト系政党も支持を落とした。この地区で5議席中トップ2議席を獲得したのはアライアンス党だった。この政党はユニオニスト・ナショナリストいずれにも与しないが、歴史的にはスコットランド系プロテスタント住民のリベラル層を代弁している。パワーシェアリングに対しては民族的分断を固定化するとして反対の立場をとり、イギリスのEU離脱には反対し、LGBTやマイノリティの保護を掲げる。北アイルランド議会90議席中アライアンス党が獲得したのは8議席で、4番目の勢力しかもたない。しかしその躍進は和平の進展にとってはプラスと考えていいだろう。
平等な権利を求めて〜ナショナリストの物語〜
「デリー籠城」で知られるデリーの町は、ベルファストから電車で2時間のところにある。正式な名称はロンドンデリーであるが、当然のことながら、アイルランド系の人びとにとって「ロンドン」は余計であって、単にデリーと呼ぶことが多い。鉄道路線図や電車内のアナウンスは「デリー、ロンドンデリー」と必ず並べることになっている。
デリーの歴史は北アイルランド植民地化の歴史そのものである。先に述べたように、9年戦争(1603年)に勝利したジェームズ1世(プロテスタント)は北アイルランドの植民地化を進めるためここに城塞都市を建設した。そして「名誉アイルランド協会(The Honorable The Irish Society)」という東インド会社に相当するロンドン市による連合会社の設立を促し、この地への植民を担わせた。彼らにカトリックの領主たちから奪った土地を分配し、イングランドからの移民にそれを耕作させたのである。このことを「アルスター・プランテーション」と言う。アルスター(Ulster)とはほぼ現在の北アイルランドに重なる地域の呼び名で、もっぱらイギリス史においてはここはそう呼ばれてきた(北アイルランドという呼称はやはりアイルランドの一部であることを含意してしまうので、ユニオニストはあまり好まない)。プランテーションとは植民地化の別な呼び名にすぎない。
こうしたあからさまな植民地化の歴史をもつデリー周辺(とくに西部)はカトリックが多い地域で、したがって選挙でもナショナリスト系政党が強い。そうしたことを反映してか、「名誉アイルランド協会」が建設したギルドホールという建物は今は博物館となっていて、その歴史展示のコーナーは「プランテーション」以降アイルランド人がいかに抑圧されたかを描いている。
また、デリー市は北アイルランド紛争史上もっとも有名な事件、「血の日曜日事件(Bloody Sunday)」が起きたところでもある。それは1972年1月、イギリスの弾圧に抗議するデモ隊に対して軍が発砲し、14名の死者を出した事件である(1名は4ヶ月後に死亡)。その場で死亡した13名のうち8名は20才以下だった。事件発生現場には記念碑が立てられている。私がそこを訪れた時、まだ新しい花がいくつも捧げられていた。そして、この記念碑の近くには「自由デリー博物館(Museum of Free Derry)」がある。EUの援助をえて2007年にオープンしたこの博物館は弾圧の歴史、公民権運動、血の日曜日事件などについて展示しており、ベルファストの「オレンジ・ヘリテージ博物館」と対照をなす。ただ、ほとんど来訪者がいなかった「オレンジ・ヘリテージ」に比べ、こちらは高校生グループや一般市民等、多数の来訪者で賑わっていた。「ボグ・サイド(沼地側)」と呼ばれるかつては劣悪な環境だったこの地区はカトリック系住民の居住区であり、ここでも多数の壁画がみられた。

ところで、町中を歩いていたら「Ex-POP Outreach Program(元囚人アウトリーチプログラム」という看板の店があったので入ってみた。どうやらここはリプブリカン系武装組織「アイルランド民族解放軍(INRA)」(IRA左派)をやっていた人たちの店のようで、彼らの歴史を展示し、元囚人たちがつくった雑貨・工芸品を販売している。「自分たちはシン・フェイン党ではない」と案内してくれた男性は説明してくれた。(彼らは「アイルランド共和社会党(IRSP)」の軍事部門だったとされる。)
町中ではシン・フェイン党や社会民主労働党の看板が目立った。シン・フェイン党のスローガンは「平等を求める」で、そうした要求自体はしごく当然のことであり、実現に向けた努力がなされなければならない。しかし、プロテスタント系住民の懸念は、そうして平等な権利を与えるとやがて彼らが多数派になった時、セクタリアン的な要求を次々と実現し、最後にはこの地をアイルランド共和国の一部にしてしまうだろうというものである。マイノリティに転落する不安が頑ななユニオニズムを支えている。実際、ベルファスト協定では、北アイルランド住民が将来多数でもってアイルランド共和国との統一を選択した場合、イギリス・アイルランド両政府はそれを受け入れなければならないと定め、将来帰属が変わる可能性を排除していない。そしてこのところのトレンドではカトリック系住民の人口が増加しており、それがプロテスタント系住民の人口を超える日がいつか来ることを予感させるところがある。
さらにはイギリスのEU離脱問題が対立に陰を落としている。ベルファスト協定によって北アイルランド生まれの住民はイギリスまたはアイルランド共和国のいずれのパスポートも請求できることになった。ただパスポートはアイデンティティの問題であって市民としての暮らしに影響はないらしい。しかし、イギリスがEUから離脱することになり、アイルランドパスポートを請求している人が増えるだろうと予測されている。さらに、これまでパスポートチェックもなく自由に往来できたダブリンとの間に国境線が引かれるとなると、大変不便なことになるし、現実問題として長い陸の国境線を管理するのは不可能に近い。(やったら膨大なコストとなって跳ね返ってくる。)北アイルランド住民のイギリス離れが進むのではないだろうか。
紛争中の人権侵害〜見えない政府の「やる気」〜
「血の日曜日事件」から38年、ベルファスト協定から12年たった2010年、イギリス政府は事件の犠牲者の遺族たちに謝罪した。ブレア首相が1998年に命じた事件の調査結果が、やっとキャメロン首相の時代に出たのである。報告を受け、キャメロン首相は議会において次のように述べた。
「私は愛国主義者であり、世界で最もすばらしいと信じるこの国の軍隊の行動を問題としたくはない。しかし、報告書の結論は明白である。血の日曜日事件は正当化されることはなく、またそうすることのできないものだった。それはまちがっていた。(中略)事件から40年もたった今首相が謝罪することの必要性について疑義をもつ人もいるだろう。しかし、これは起きてはならないことだったのだ。(中略)わが国の兵士がまちがったことをした。一国の軍隊がしたことの責任は政府が負わなければならない。したがって、政府を代表し、そしてこの国を代表し、私は深く謝りたい。」[1]
キャメロン首相の議会演説をギルドホールの広場に設置された大スクリーンで見て歓声を上げるデリー市民の様子が、「自由デリー博物館」で上映されていた。それを見た私もシンプルだが明確なことばで謝罪したキャメロン首相の姿に感動を覚えたほどである。
しかしながら、北アイルランド紛争中におきた人権侵害についてイギリス政府の態度は必ずしも明確ではない。今回私はベルファストにあるアルスター大学移行期正義研究所やNGOである「正義の執行についての委員会(Committee on the Administration of Justice)」を訪れ、その辺りの事情について話を聞いた。紛争中の人権侵害で処理されていない大きな問題に軍人・警官によるものがある。欧州人権裁判所や国連人権メカニズムの勧告にもかかわらず、イギリス政府の真相究明の動きは鈍い。鈍いどころか、調査の進展を意図的に妨害すらしていると批判されている。イギリス政府が躊躇する背景には、軍人・警官とユニオニスト系武装組織との共謀関係が明るみに出ることに対する懸念がある。軍・警察が武器を横流ししたり、ユニオニスト系武装組織メンバーであれば殺人を犯しても取り調べを甘くしたり、調書をとらなかったり、不起訴にしたりなどしたという。また、軍・警察はイギリス国内の他の地域であれば試みないような新手の拷問を北アイルランドで実験していたと言われている。こうした疑惑について調べようにも、政府は記録がないと答えるか、あっても国家安全保障を理由に開示しないといったことが続いている。
ブラジルの真実委員会によると、1970年代、イギリスはブラジルの独裁政権に対して洗練された拷問(跡を残さない心理拷問など)を教えていた。ブラジルの軍人たちは尋問方法を学ぶのにアメリカ、ドイツ、フランス、パナマにも行っていたが、中でもイギリスが「一番よい方法をもっていた」そうだ。イギリス軍は北アイルランドで方法に「磨きをかけていた」[2]。
現在、メイ首相はイギリス軍兵士が作戦中の行動について人権侵害で責任追及されないための法改正を考えている。選挙期間中、ユニオニスト系急進政党のDUPは、イギリスの軍人・警官が北アイルランドでとった行動について「時効」を適用するよう提案していた。カトリック系住民にとって移行期正義の問題はイギリス政府がどれだけ自分たちをまっとうなイギリス国民として扱ってくれるかということを計る試金石になっているため、彼らのイギリス残留に対する態度の選択に微妙な陰を投げかけている。イギリス政府が北アイルランドを引き留めたければ、彼らを平等に扱うことが不可欠となる。
選挙の結果を考える
北アイルランド議会の選挙は3月2日に行われた。議席はそれまでの108議席から90議席に減っており、その分選挙戦は激しさを増した。解散前の議席は次の通りである。DUP(民主アルスター党)38、シン・フェイン党28、UUP(アルスター統一党)16、社会民主労働党12、アライアンス党8、緑の党2、その他4。
シン・フェイン党はIRAを軍事部門にもつ急進的なナショナリスト系政党(一般にはリパブリカンと呼ばれる)であり、DUPは和平交渉にシン・フェイン党が呼ばれたことに抗議して交渉から撤退し、ベルファスト協定反対の立場をとり続けてきたユニオニスト系急進派である。和平合意は、当時主流派であったUUPと社会民主労働党という双方の穏健派が手を結んだことで実現した。1998年のノーベル平和賞を共同受賞したのもその穏健派二政党の党首たちである。しかし、皮肉なことに、協定後の北アイルランドの選挙では急進派が躍進し、急進派同士が連立内閣を構成するという事態になっている。コンソーシエーショナリズムにもとづくパワーシェアリングが急進派の台頭を招き、分断を深めるという現象は他の地域でも指摘されており、紛争解決の即効薬としてよく使われるパワーシェアリングの強い副作用として議論されている。北アイルランドもまさにそうなっていると言えそうである。
今回の選挙結果は次の通りである。DUP 28、シン・フェイン党27、UUP 10、社会民主党12、アライアンス党8、緑の党2、その他3。結果は、DUPとUUPの大敗北、すなわちユニオニストの大敗北だった。一方、シン・フェイン党と社会民主労働党は全体の議席数が減った中で議席を維持したという意味で善戦したと言える。今回の選挙でユニオニストとナショナリストはほぼ同議席になり、ユニオニストの優位は崩れた。これは和平協定後初めての現象であり、非常に大きな変化をもたらすことになると予想される。ちまたでは、DUPとシン・フェイン党の連立はもやはありえず、デッドロックに陥ってロンドン(イギリス政府)による直接統治が復活するかもしれないという予想すら出ている。今回会った人たちは一様に紛争に戻ることはないだろうという楽観論を述べていた。私も基本的にはそうした見方が正しいだろうと思うが、選挙の結果には少し驚かざるをえない。
とくに頑ななのはDUPである。DUPは1960年代に噴出したカトリック系住民の公民権運動をことごとく妨害してきた。それまで差別されてきたカトリック系住民は住宅の不平等な配分や就職差別について改善を訴えてきた。強硬なユニオニストたちはカトリック住民が自分たちの領域に入ってくるのを極端に嫌う。したがって、そうした状況をつくりだす平等化政策そのものを快く思っていない。今回の選挙でもDUPのシン・フェイン党に対する激しい憎悪キャンペーンがかえって有権者の離反を招いたのではないかと思われる。加えて、DUPがイギリスのEU離脱を強力に支持したというところが有権者に疑問を抱かせた部分もあるだろう。DUPはEU離脱の国民投票に際しては、北アイルランドを除くイギリス国内で「EU離脱賛成」の新聞広告を出していた。それに要した4,000万円近い資金はどこから得たのか。党首はマスコミの追及にも資金提供者を明かさなかった。こうした疑惑もDUPに対する反発を生んだと思われる。
今回の選挙ではユニオニスト系の票、とくに若い人たちの票が多くアライアンス党や緑の党に流れたと推測されるが、おそらくその辺に希望を見いだすことができるかもしれない。とくにアライアンス党はプロテスタント系住民の支持を集めているが、EU残留を支持し、両者の共存と和解を掲げている。DUPとシン・フェイン党が第一党・第二党を維持したわけなので、政治の両極化(ポラリゼーション)は変わらない。むしろシン・フェイン党が強く出られるようになった分、DUPの拒否反応が強まり、対立が激化する可能性が高い。それに対して共存派が世論をバックにどれくらい攻勢をかけられるかが、和平プロセスの今後を左右することになるだろう。
(2017年3月)

[1] BBC. 15 June 2010. Bloody Sunday: PM David Cameron’s full statement.
http://www.bbc.com/news/10322295
[2] BBC. 30 May 2014. How the UK taught Brazil’s dictators interrogation techniques.
http://www.bbc.com/news/magazine-27625540

(大阪大学大学院教授)