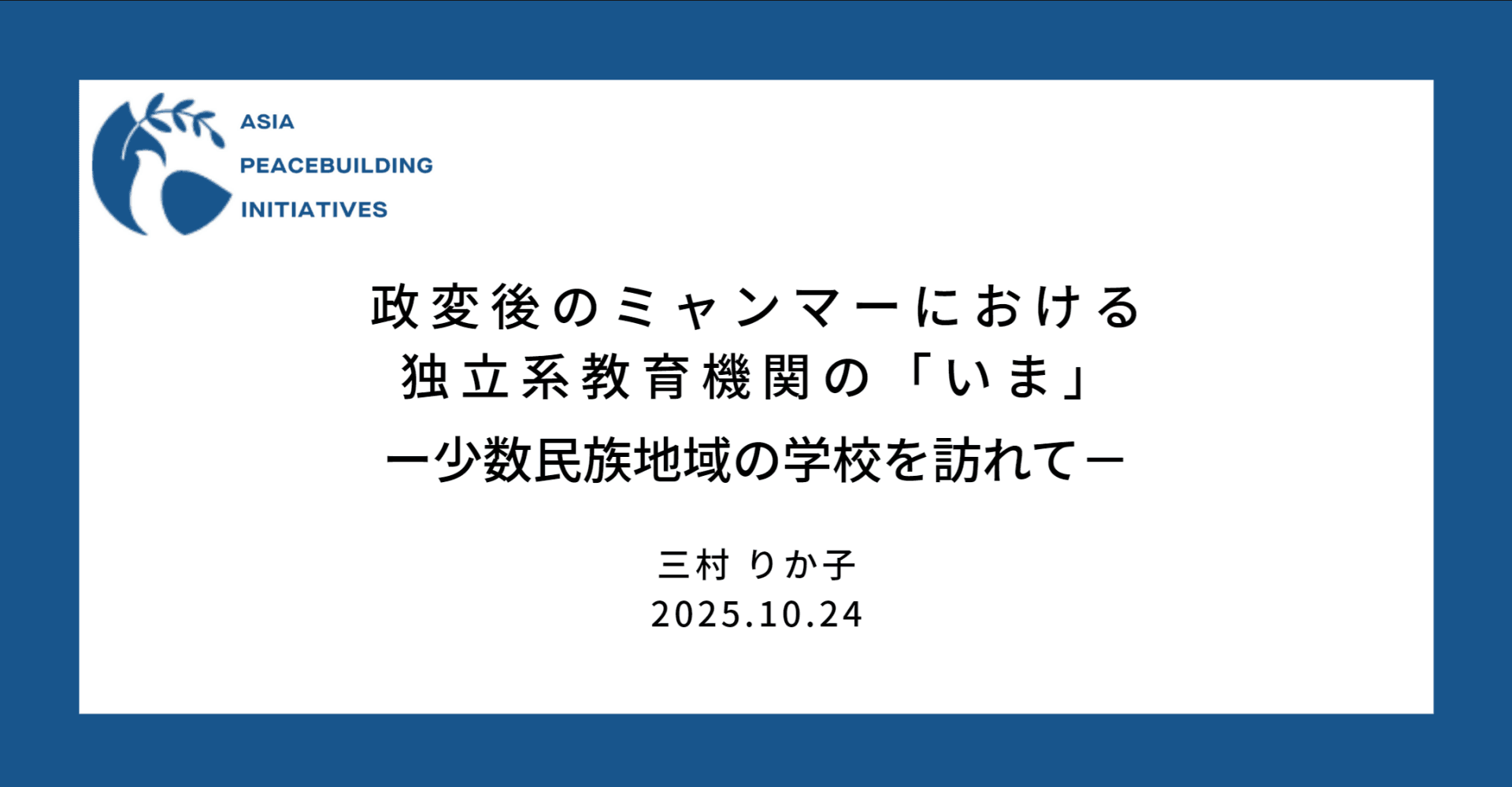- 岡野 英之
- ミャンマー
【エッセイ】ミャンマーの民主闘争と国内避難民 (3)
―越境支援の現場から―
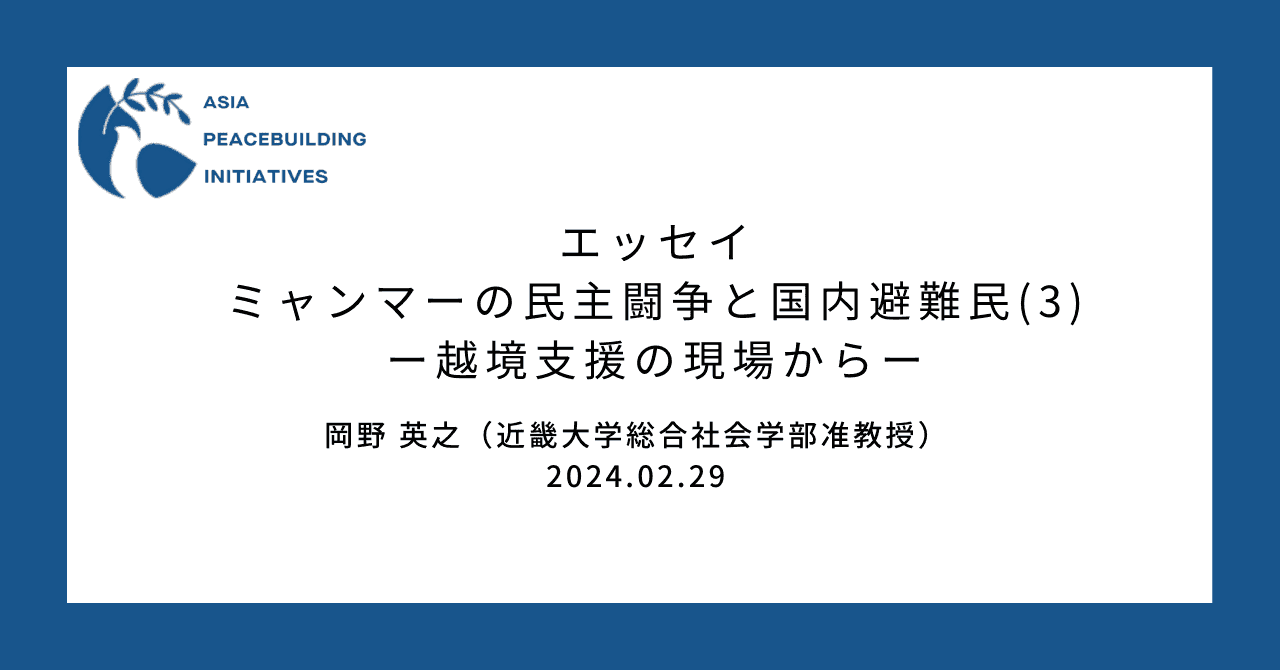
本連載はこれまで、私がマンダレー滞在中に見た国内避難民の様子を描いてきた。第三回目の今回は、舞台を隣国タイの国境地帯に移したい。私はマンダレーに数週間滞在した後、タイに飛んだ。タイでは10日間ほど滞在し、ミャンマーとの国境地域を調査した。
とりわけ本稿で伝えたいのは、国境を通して実施されるミャンマー人たちによる同胞への支援の様子である。私が滞在したタイ側の町メーソットは、ミャンマー国内にいる人々に越境支援をするためのハブとして機能していた。様々な組織がそれぞれの形で支援をしていたのだ。
その支援は、国内避難民などの困窮した人々へ届けられるものもあれば、民主派勢力という暴力の担い手に届けられるものもあった。
国境の町メーソット
私が滞在した町メーソットは国境交易の拠点となっており、幹線道路上にはコンテナをけん引するトラックが行き交う。メーソット市内をかすめる幹線道路は、タイの首都バンコクとミャンマーの最大都市ヤンゴンを結ぶ最短ルートなのだ。その幹線道路はメーソットから数キロメートル先でミャンマー国境でもあるモエイ河にぶつかる(注1)。そこに設置されている国境ゲートをくぐれば、その先はミャンマーである。このあたりの国境線はモエイ河と重なっており、上述の幹線道路はそれを横切る形で両国を結んでいる。川幅は、さほど広いものではなく、渡ろうと思えば簡単に渡れる。私はミャンマーとタイの両方で調査をするため、国境ゲートを何度も通ってきた。
メーソット周辺には、ミャンマーからの安い労働者を当てにして、多くの工場が誘致されており、そこで働こうとするミャンマー人が1990年代から国境を越えてやってくるようになった。とりわけ繊維産業が盛んである。さらには周辺の農村でも、ミャンマーからの安い労働力に頼った農業がなされている。このあたりでは不法労働者に依存した経済構造が作られているといえよう。こうした状況から、この町の周辺では、人口の半数以上がミャンマー出身者という状況が生まれている。彼らの中には不法滞在も少なくないのだが、警察や行政もそれに目をつぶっているというのが現状である。なぜなら、タイ側としては安い労働力が必要であるし、汚職を通してカネをせしめる金づるでもあるからだ(Balčaitė 2019; Tsuda 2022; 渡邊 2023)。
私は、クーデターが発生するまでメーソットで調査をしたことはなかった。コロナ禍が落ち着き始めた2022年8月、はじめて調査に入った。今回は2回目の調査である。その調査からは、ミャンマーでクーデターが発生したことで、メーソットおよびその周辺(ミャンマー側も含む)が大きく変わったことがわかってきた。
ミャンマー側の安全地帯
2021年2月にクーデターが発生して以降、この国境地域の対岸、すなわち、ミャンマー側には、軍事政権「国家統治評議会(State Administration Council: SAC)」による弾圧を受けた人々にとっての安全地帯が作られた。クーデター後に成立した軍事政権SACは、民主主義の復権を訴えるデモ隊に対して弾圧を加えた。
その手法のひとつが、逮捕者のスマートフォンに保存されているデータ(例えば、写真やSNS、通話履歴)から情報を得ることで、芋づる式にデモ参加者を探し出すというものであった。ゆえに知り合いのデモ参加者が逮捕されると自分にも捜査が及ぶ恐れが生じる。そうした場合、家を離れて身を隠す必要があった。その受け皿として安全地帯が作られたのである。ある30代の女性は大都市ヤンゴンから逃げたときの経験を次のように語った。
〔デモ活動をしていた〕ある時、自分の仲間が捕まりました。そこで家を離れ、友達の家に転がり込むことにしたんです。そのあとは友人の家を転々としながら過ごしました。そんな中、国境地帯に弾圧から逃れる人々のための安全地帯があることを知ったんです。すでにそこにいた友人から教えてもらいました。そこでその友人と連絡を取り、そこに向かうことにしたんです。長距離バスでミャワディ〔メーソットの対岸にあるミャンマー側の町〕まで行き、そこからは知り合いに向かえに来てもらいました。
(2022年8月メーソットにて聞き取り)
安全地帯には、この女性のように弾圧から逃げてきた人々がかくまわれた。
この安全地帯を作り上げたのは、ミャンマー政府と対峙する武装勢力「カレン民族同盟」(Karen National Union: KNU)であった。KNUはカレン人を主体とする武装勢力である。KNUは1948年にミャンマーが独立した直後に武装蜂起しており、少数民族勢力の中でも最も歴史が長い(注2)。KNUは自治を求めて(かつては分離独立を求めて)武装闘争を継続しているものの、主要民族ビルマ人(人口の七割を占める)と敵対しているわけではない(山本 1996)。KNUは2012年に停戦合意を結び、当時の政権と政治的な解決に向けた対話を始めた。ただし、武装解除や支配地域の受け渡しには応じておらず、あくまでも話し合いを持つための停戦である(同様の停戦合意はミャンマーでは珍しくない)(Brenner 2017)。
安全地帯となったのは停戦合意後に国内避難民の定住プログラムの一環として作られた「難民帰還村」である。便宜的にA村としよう。A村はKNU支配地域の中の、政府支配地域に隣接する場所に建設された。KNUの支配地域でありながらも、ミャンマー政府の行政制度が導入された。この村は「平和の象徴」として扱われ、国際援助機関から多額の援助が流れ込んだ。とりわけ、A村には日本政府からの支援も大量に投入されている(Irrawaddy 2021)。私は、その事業を実施する日本のNGOに随行して、クーデター前に村を見学させてもらったことがある。新たな住宅が数多くつくられ、新興住宅街のようだと思った。その時にはミョーさん(=連載1~2回に登場した女性)の通訳で何人かに話を聞いた。この村では家族の誰かがタイ側に出稼ぎに出ており、その収入に頼って暮らしている世帯が少なくないという話が印象的であった。
A村にはクーデター後、弾圧を逃れたビルマ人が大量に流入することになった。その安全地帯には、デモ隊に参加した者たちだけではなく、政府高官や国会議員など軍事政権SACに拘束される恐れのある重要人物も逃れてきた(Frontier 2022)。A村の存在は、弾圧を逃れる人びとの間に広まった。「タイ=ミャンマー国境地帯に安全地帯がある」。そんな噂がSNSやメッセージ・アプリを使って、多くの人に知れ渡った。先に着いた者が後から来た者を呼び寄せる形で、A村には、どんどん人が増えていった。
安全地帯で行われた軍事訓練
問題なのは、A村で軍事訓練の志願者が集められていたことである。クーデター後、KNUの指導部は停戦合意を維持しようとしていたものの、この地域の各地に散らばるKNUの部隊の中には、国軍との間で戦闘をはじめるものが現れた。A村に弾圧を逃れたビルマ人たちをかくまったのも、A村の行政を担う一部の者が勝手に始めたことだともいわれる。さらには一部の部隊がビルマ人志願者たちに軍事訓練をしたことで、KNUはなし崩し的に反軍事政権の立場へと引きずり込まれていった(Ye Myo Hein 2022: 54-58)。
軍事訓練を志望する者はA村から別の場所へと移され、そこで軍事訓練を受けていたという。そうした軍事訓練を受ける場所は、KNUの支配地域に点在していたと語る者もいた。訓練にあたったのは軍事経験を持つカレン人勢力KNUの関係者である(Ye Myo Hein 2022: 54)。A村で数か月過ごした50代の男性は、軍事訓練の様子を周りの若者たちから聞いたという。
訓練は毎日、ジョギングで始まるそうです。そのあと、100メートルくらいの幅がある河にロープがかけてあって、ロープを伝って向こう岸に渡らないといけない。それで向こうに置いてある石を持って帰ってくるんだそうです。そうでないと朝ごはんを食べられないとのことです。実際に軍事訓練の現場を見たこともあります。〔スマホの写真を見せながら〕この女の子、AK47かM-13か知らないけど銃を持っているでしょ。銃と同じくらいの身長なんですよ。立って撃てないから、座って撃つように指導されていた。それでもちゃんと真ん中にあたっているんです。ものすごい集中力でした。
(2022年8月、メーソットにて聞き取り)
こうした軍事訓練を受ける者の多くが都市部からやってくる若者たちである。中には、つらさに耐えきれず逃げる者もいる。メーソットで出会った元・大学生は軍事訓練から逃げてきたという。「あれはつらかった。僕には無理です」と語った。無理はない。都市部で勉強にあけくれる生活が、ジャングルでの生活へと一変するのである。
ミャンマー当局からの捜査が入る
A村にいた人々は、2021年12月に発生した戦闘でこの地を追われた。きっかけは12月14日、A村にミャンマー当局の捜査が入ったことである。軍事政権側がこの安全地帯へと乗り込んだのも、わからなくはない。上述のように、弾圧から逃れる人々の間で「国境地帯に安全地帯がある」という情報が出回っていた。軍事政権SACが気付くのも時間の問題であった。
12月14日の午後、武装をしたミャンマー軍兵士約200名が4つの分隊に分かれ、A村を取り囲んだ。その後、村へと侵入し、家々に乗り込んでは取り調べを繰り返した(Irrawaddy 2021)。それ以降の数日間で60名以上が逮捕されたという。その中には2名の国会議員も含まれていた(Frontier 2022)。捜査が戦闘に転じたのは、KNUの一部が武力で抵抗をはじめたからである。数日の間に本格的な戦闘に発展した。国軍による応戦は空爆を含めた大規模なものとなった(Frontier 2022)。
それによりA村に暮らしていた人々は避難を余儀なくされた。都市部における弾圧から逃げ数カ月ほどA村で暮らしたビルマ人女性は、あるメディアに対してこう語っている(Frontier 2022)。
その夜、私たち数千人はタウンイン河〔筆者注―モエイ河のビルマ語名称〕を越え、タイへと入りました。私たちは急いでいたためボートを待っている余裕はありません。〔夫が〕大きなプラスチックの桶に私を乗せ、押してくれたんです。武器もないので兵士も難民も違いはありません。
この戦闘の後、A村はミャンマー国軍に占拠され、そこに住んでいた人々は住処を奪われることになった。その数は2万人以上にのぼるとの推計もある(Shwe Zin 2022)。その中にはカレン人の姿も含まれているし、安全地帯に逃げ込んだビルマ人活動家の姿もあった(Eleven 2021)。
離散するA村の住民たち
では、こうしてA村を追われた人々はどうなったのであろうか。この戦闘の後の数カ月で、彼らが取った選択肢は大まかに3つに分かれた。
第一に、多くの者が国境沿い(すなわち、モエイ河沿い)に作られた国内避難民キャンプに住むことになった。タイ当局は避難民が長期に滞在することは許可しないものの、数日間くらいであればタイ側で戦闘をしのぐことは認めている。実際、2021年12月から1月の間にタイ当局はA村からの越境避難民を一時的に保護している。しかし、戦闘が収束すれば追い返した(Eleven 2021; Quinely 2022; Shwe Zin 2022)。とはいえ、避難民たちにとっては、何かあればタイに逃げられるという選択肢は確保しておきたい。その結果、すぐにタイ側へと渡れるモエイ河沿いに国内避難民キャンプが点在することになった。
第二に、軍事訓練を志した者は戦闘員になる道を選んだ。そのまま本格的な武装闘争へと突入したのである。その結果、KNUの支配地域およびその周辺を拠点に、カレン人司令官がビルマ人の若者たちを率いる民主派勢力が活動することになった(藤川 2022; BNI 2023; Frontier 2022)。現在、この地域で軍事政権SACに対抗する勢力は3万人規模だといわれている。そのうち約2万人が「カレン人勢力」、そして、1万人が民主派勢力だという(Ye Myo Hein 2022: 57)(注3)。
第三に、金銭に余裕がある者はタイ側へと流れた。メーソットでは不法滞在は黙認されているが、その条件として警察に毎月定額(約1200円)の賄賂を払わなければならない(Tsuda 2022)。タイでの生活はカネがかかるのだ。難民帰還村に住んでいる人でも、比較的お金がある者はタイに渡って生活をすることにした。彼らの中には、支援機関からの援助や先進国に住む親類からの送金に頼る者もいれば、労働者としての生活も選ぶ者もいた。レストランや小売店を開く者もいた(Amporn 2023)。
文化人類学者アンポーンは、メーソットへと流れてきた者を対象に調査を行った。そのうちの一人は生活が苦しいながらも、支援が受けられない現状について次のように語ったという。
お金は武器を買うのに必要です。そのことを私たちはわかっていますから〔支援が受けられないのも我慢します〕。武器を買って戦闘をすることが、私たち〔の側〕が戦争に勝つための唯一の道です。
(Amporn 2023: 25)
メーソットからの支援
この戦闘が発生して以降、メーソットは支援のハブとしての様相を呈していった。もともとメーソットにはたくさんのミャンマー人が住んでいることから、多数の支援団体が事務所を構えていた。こうした支援団体の例をいくつか挙げると、ミャンマー人移民のための学校、移民労働者の権利を守る団体、カレン人の住む地域へと援助を届ける人道支援団体などがある。こうした団体の多くは1990年代以降、国際的な支援を受けながら、ミャンマー人の手で運営されてきた(山本2016)。クーデター後、彼らが国境を越えた支援を実施することになったのである。
ミャンマー情勢を研究する研究者、渡邊康太はこの頃、メーソットに住み込んで調査を重ねていた。彼によると「〔メーソットで〕訪問したミャンマー・コミュニティのほぼすべてが、何らかの形で新規避難民への支援に取り組んでいた」という。ふだんの生活がままならない日雇い労働者たちも少額の寄付をして避難民の支援に貢献していたという(渡邊2023)。実際、私の調査でも、対岸の国内避難民キャンプに食糧支援をしたり、メーソットにやってきた新規の越境避難民に金銭や食料などの支援をしたりする団体の話はいくつも耳にした。
そうした支援の中には、国内避難民に対する支援なのか、武装闘争を志す民主派勢力に対する支援なのかが明確にわかれていない支援をするものもある。例えば、ある団体では、対岸で活動する民主派勢力に食料や日用品を届けることと、国内避難民キャンプにこれらの物資を届けることを同時にしているという。この団体はメーソット市内で食料や日用品を買い付け、市内からある程度離れたところから、その物資をミャンマー側に渡す。私がこの団体のオフィスを訪ねた際、普段はミャンマー側にいるという民主派勢力の兵士がいたので話を聞いた。休憩がてら1週間ほどタイ側に滞在するのだという。彼は物資の運搬という後方業務にあたっているとのことだった。
私は週一回提供されるタイ側からの物資を国内避難民キャンプや、PDF〔本稿でいう民主派勢力〕に配って回っています。PDFには受け渡しポイントがあるのでそこに持っていきます。何か必要なもののリクエストがあれば、携帯電話で連絡が入ります。彼らはタイの電話番号を持っているし、電気がないところでもソーラー式の充電器などで対処しています。活動のアピールのためには動画撮影や写真撮影も必要ですから、スマートフォンの他に、Go Pro〔スポーツやアウトドアの動画配信でよく使われる小型のカメラ〕を持っている人もいますよ。
このように民主派勢力と国内避難民キャンプの両方に支援をしているのも、わからないでもない。なにせ両者ともA村から逃げてきたことには変わりはないからである。この人物自身もA村に滞在し、軍事訓練を受けた経験があるという。さらにA村からタイ側に逃げた人たちの中にも民主派勢力を応援している人がいることを考えると、こうした支援が実施されているのは当然のことといえよう。
無論、こうした支援を行っているのは、この団体だけではない。メーソットにはミャンマー人を主体とする数多くの支援団体があり、それらの団体には世界各地のミャンマー人から支援金が送られてくる。それらの支援金はメーソットを介してミャンマー側に流れている。そうした資金がどこに流れているのかを把握することは不可能に近い。
ただし、タイ側のミャンマー人が実施している支援すべてが国内避難民と民主派勢力の区別なしに行われているというわけではない。武装闘争に反対する人たちも少なくないし、純粋に困っている国内避難民に対して支援する団体も多い。しかし、その区別なしに支援を行う団体や個人もいるというのが現状である。
ここまで見てきたようにメーソットにおける調査からは、現場レベルでの「同胞による同胞への支援」は、国内避難民に対する支援なのか、民主派勢力に対する支援なのかが、あいまいなまま実施されているものもあることが浮かび上がってきた。こうした状況が突き付けるのは、国際的な支援団体はどのように支援を実施すべきかという問題である。一般論として国際援助機関―すなわち、国際機関や二国間援助機関(先進国からの援助を実施する政府機関)、NGO―は、ローカルな団体を実施機関としたり、自発的に活動を行っている現地の団体に資金援助を提供したりすることで業務を遂行している。当然のことながら、その援助は暴力の主体に益することはあってはならない。それは “Do No Harm”(害悪を及ぼしてはならない)というフレーズとして語られ、国際社会に共有された規範となっている(木場 2017; Anderson 1999)。しかし、メーソットで見られるローカルな状況を考えると、どの団体がどこまで民主派勢力という「暴力の主体」に関与しているのかがわからない。
無論、これはミャンマーに限った話ではない。国内避難民や難民が存在するところには、同様の問題が存在する。すなわち、国内避難民や難民は、彼ら自身が支援を必要としている存在でもある一方、故地を追われた人々として武装勢力を支援する存在でもある、という話は往々にしてある(岡野 2017; Lischer 2005)。外部の者はそれが見えにくい。過去には、そうした見えない部分に気づかずに援助した結果、思わぬ被害をもたらしたこともある。このような中で支援をどのように実施するのかを、国際援助機関は問われているといえよう(緒方 2017; Keen 1994; Lischer 2005)。
本連載では3回にわたり、クーデター後のミャンマー情勢を伝えてきた。その内容は、現実に起こった出来事を正確に周知しなければならないという「モノ書き」としての役割と、“Do No Harm”の原則とのバランスを鑑みて決めたものである。個人的には、研究者であれジャーナリストであれ、モノ書きにも“Do No Harm”の原則は共有されなければならないと考えている。書くことで誰かの不利益を招くことは倫理に反する。その一方、何かを書くことは、その問題を広く一般に周知することでもあり、その際に誰かの立場に偏ってはならない。ゆえに本連載では、民主派勢力にとって不利になるようなことにも言及したし、軍事政権SAC側を理解するという姿勢を取った箇所もある。ただし、私が知り得たものの、どこかに不利益を与えるかもしれないと思った内容は記していない。ミャンマーの現実を伝える文章を書こうとする身として、ミャンマーの人々やミャンマーに関わる人々、そして、平和構築に関わる人々に対して本連載で伝えたことが何らかの形で益することを願っている。
(注1)
モエイ河(Moei River)とは、タイ語由来の名称である。英語でも同河川はMoei Riverと表記されているため、「モエイ河」という表記を用いた。ビルマ語での名称に従えば「タウンイン河」(Taung Yin River)となる。
(注2)
ミャンマーでは70年以上にもわたり少数民族と中央勢力の対立が続いている。少数民族は複数あり、ミャンマー政府の公式見解では135に上るという。その一部が武装勢力を作っている。離合集散を重ねているため、ひとつの少数民族に複数の武装勢力があることも少なくない。ゆえに全国規模で見ると多数の武装勢力がおり、主要な武装勢力だけでも50を超えると指摘する研究者もいる(中西 2022: 111)。後述するようにKNUは民主派勢力を支援しているが、その他にも民主化勢力を支援している少数民族武装勢力がいる(岡野2021)。
(注3)
KNUではなく「カレン人勢力」と書いたのは、煩雑さを防ぐためである。ビルマ人の志願兵の増加に伴い、KNUから分派して独立した部隊が現れた。さらには、カレン系の別の勢力もビルマ人志願兵を吸収することで傘下の民主派勢力を創設している。詳細はYe Myo Hein (2022)、藤川 (2022)を参照。
参考文献
緒方貞子 (2002)『私の仕事―国連難民高等弁務官の10年と平和の構築 ―』草思社。
岡野英之 (2017)「リベリア―国境と紛争―」木田剛・竹内幸雄編『安定を模索するアフリカ』ミネルヴァ書房、198-223頁。 岡野英之 (2021)「なぜ市民による抵抗運動はエスカレートしたのか――クーデター後のミャンマーを分析する」シノドス、11月11
日 、https://synodos.jp/opinion/international/27483/
木場紗綾 (2017)「援助の国際規範:Do No Harm(害悪を及ぼしてはならない)」同志社大学政策学部、3月2日、
https://policy.doshisha.ac.jp/keyword/2017/0302.html
中西嘉宏 (2022)『ミャンマー現代史』岩波新書。
藤川大樹 (2022)「ミャンマー南東部の戦況に影響? 国軍と70年戦う少数民族武装勢力に若者主体の大隊結成」『東京新聞』10月3
日、https://www.tokyo-np.co.jp/article/205904
山本宗補 (1996)『ビルマの大いなる幻影―解放を求めるカレン族とスーチー民主化のゆくえ―』社会評論社。
山本博之 (2016)『倒せ独裁! アウンサンスーチー政権をつくった若者たち』梨の木舎。
渡邊康太 (2023)「隣国のミャンマー・コミュニティとの連携を推進」『国際開発ジャーナル』793号、30-33頁。
Anderson, Mary B. (1999) Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War, Lynne Riener.
Balčaitė, Indrė (2019)“Flows Making Places, Borders Making Flows: The Rise of Mae Sot–Myawaddy Hub in the Thai–
Burmese Borderland,” John Garrard and Ekaterina Mikhailova (eds.) Twin Cities: Urban Communities, Borders and
Relationships Over Time, Routledge, pp. 301-312.
Brenner, David (2017) “Inside the Karen Insurgency: Explaining Conflict and Conciliation in Myanmar’s Changing
Borderlands,” Asian Security, doi: 10.1080/14799855.2017.1293657
Eleven (2021) “Thai Authorities Look after Displaced Villagers Fleeing from Lay Kay Kaw Fighting,” Eleven, December 17,
https://elevenmyanmar.com/news/thai-authorities-look-after-displaced-villagers-fleeing-from-lay-kay-kaw-fighting
Frontier Myanmar (2022) “‘Peace Town’ to Ghost Town: Lay Kay Kaw, One Year On,” Frontier Myanmar, December 17,
https://www.frontiermyanmar.net/en/peace-town-to-ghost-town-lay-kay-kaw-one-year-on/
Irrawaddy (2021) “Myanmar Junta Forces Raid KNU-Controlled Town; Democracy Activists Feared Arrested,” Irrawaddy,
December 14, https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-forces-raid-knu-controlled-town-democracy-
activists-feared-arrested.html
Keen, David (1994) Benefit of Famine: A Political Economy of Famine and Relief in Southwestern Sudan, 1983-1989,
Princeton University Press.
Lischer, Sarah Kanyon (2005) Dangerous Sanctuaries: Refugee Camps, Civil War, And The Dilemmas Of Humanitarian
Aid , Cornell University Press.
Quinely, Caleb (2022) “Myanmar refugees receive little relief at Thai border,” Al Jazeela, 21 January,
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/21/myanmar-refugees-face-little-relief-at-thai-border
Shwe Zin (2022) “Displaced on the Border,” Irrawaddy, January 12, https://www.irrawaddy.com/factiva/displaced-on-the-
border.html
Tsuda Tomoko (2023) “Lack of Support Leaves Myanmar Refugees in Thailand Isolated,” The Japan News, September 13,
https://japannews.yomiuri.co.jp/world/asia-pacific/20230913-136288/
Ye Myo Hein (2022) “One Year On: The https://elevenmyanmar.com/news/thai-authorities-look-after-displaced-villagers-
fleeing-from-lay-kay-kaw-fightingMomentum of Myanmar’s Armed Rebellion,” Asia Program, Wilson Center, available at:
https://www.wilsoncenter.org/publication/one-year-momentum-myanmars-armed-rebellion

近畿大学総合社会学部准教授