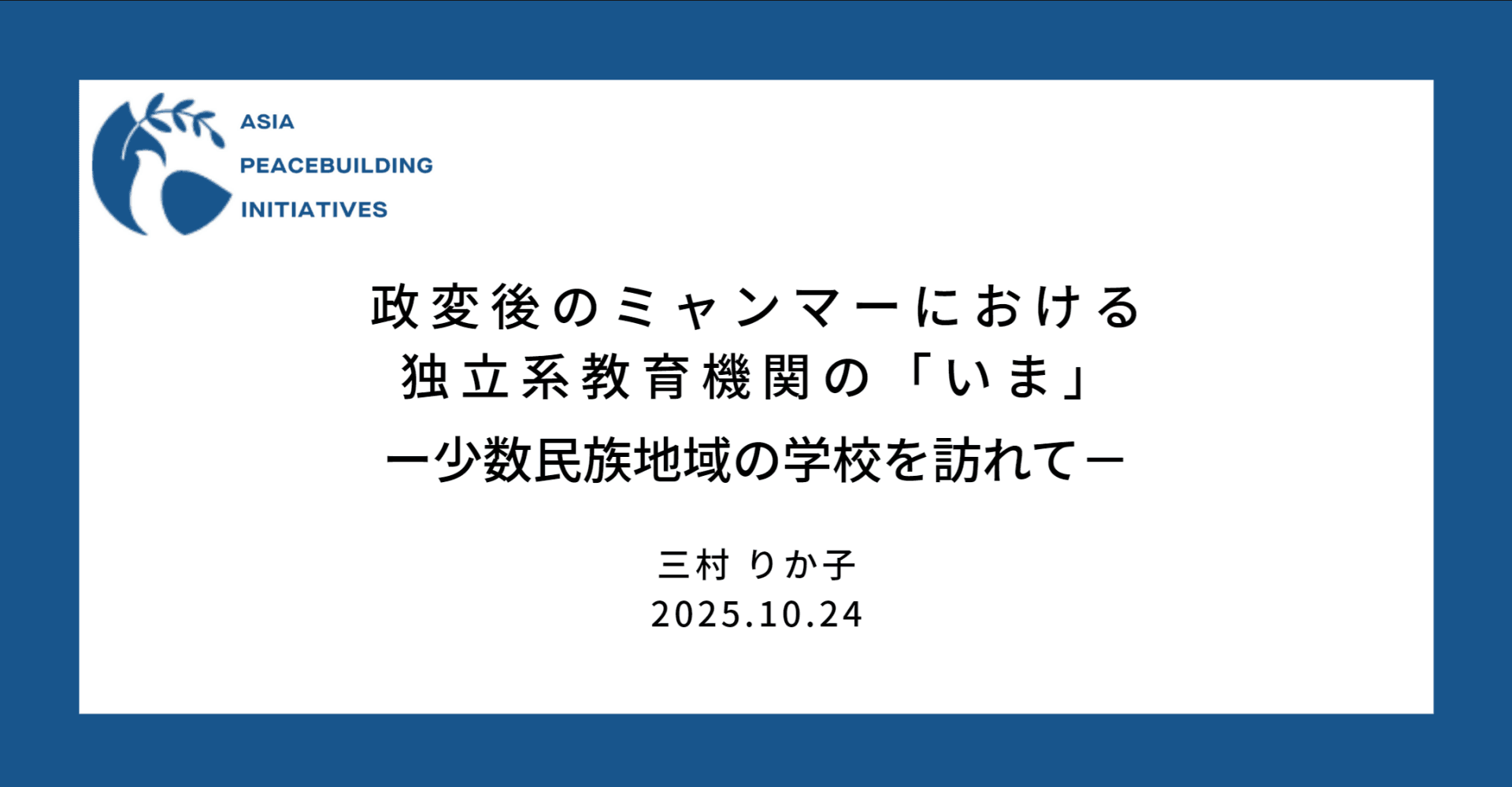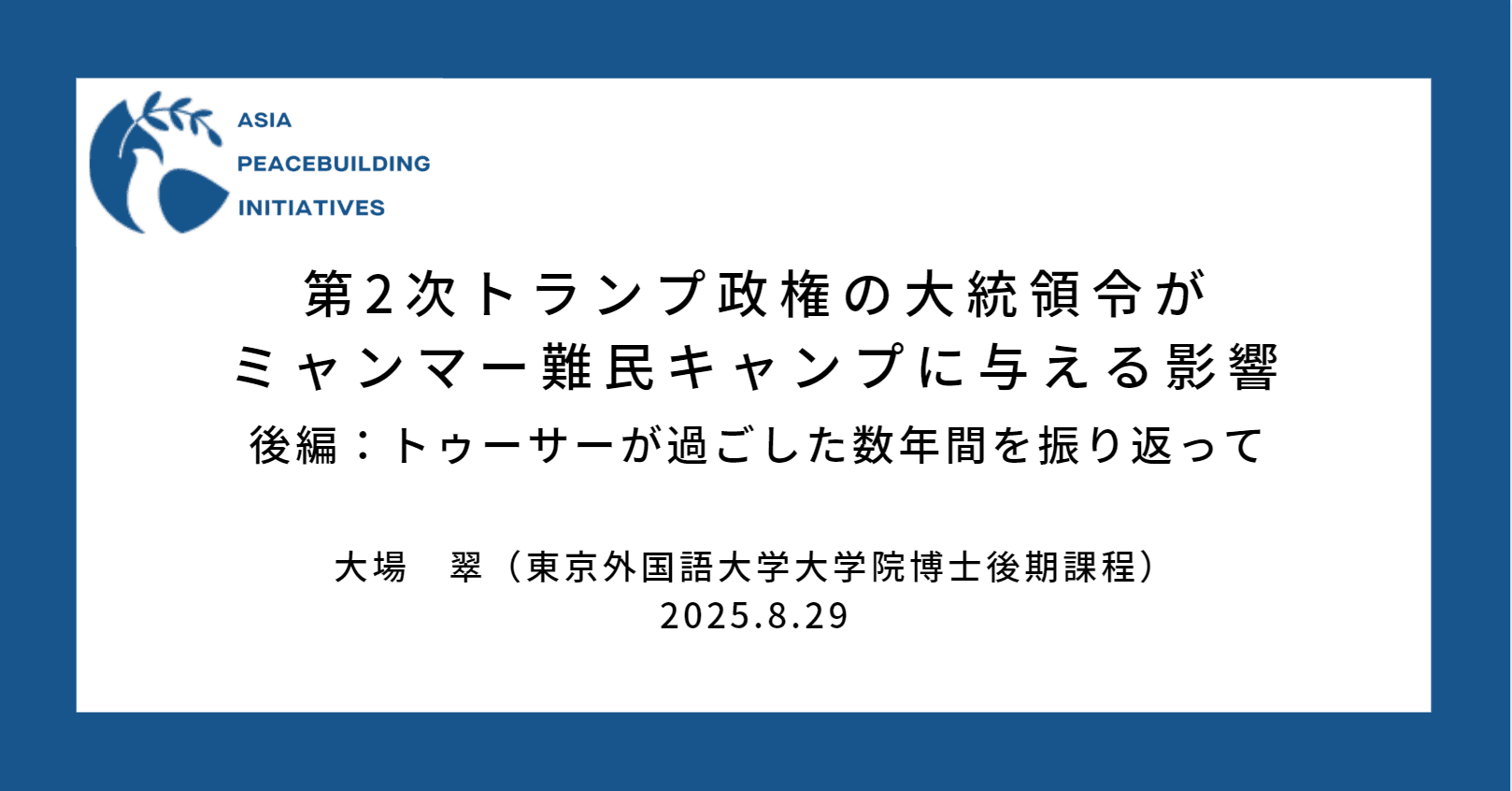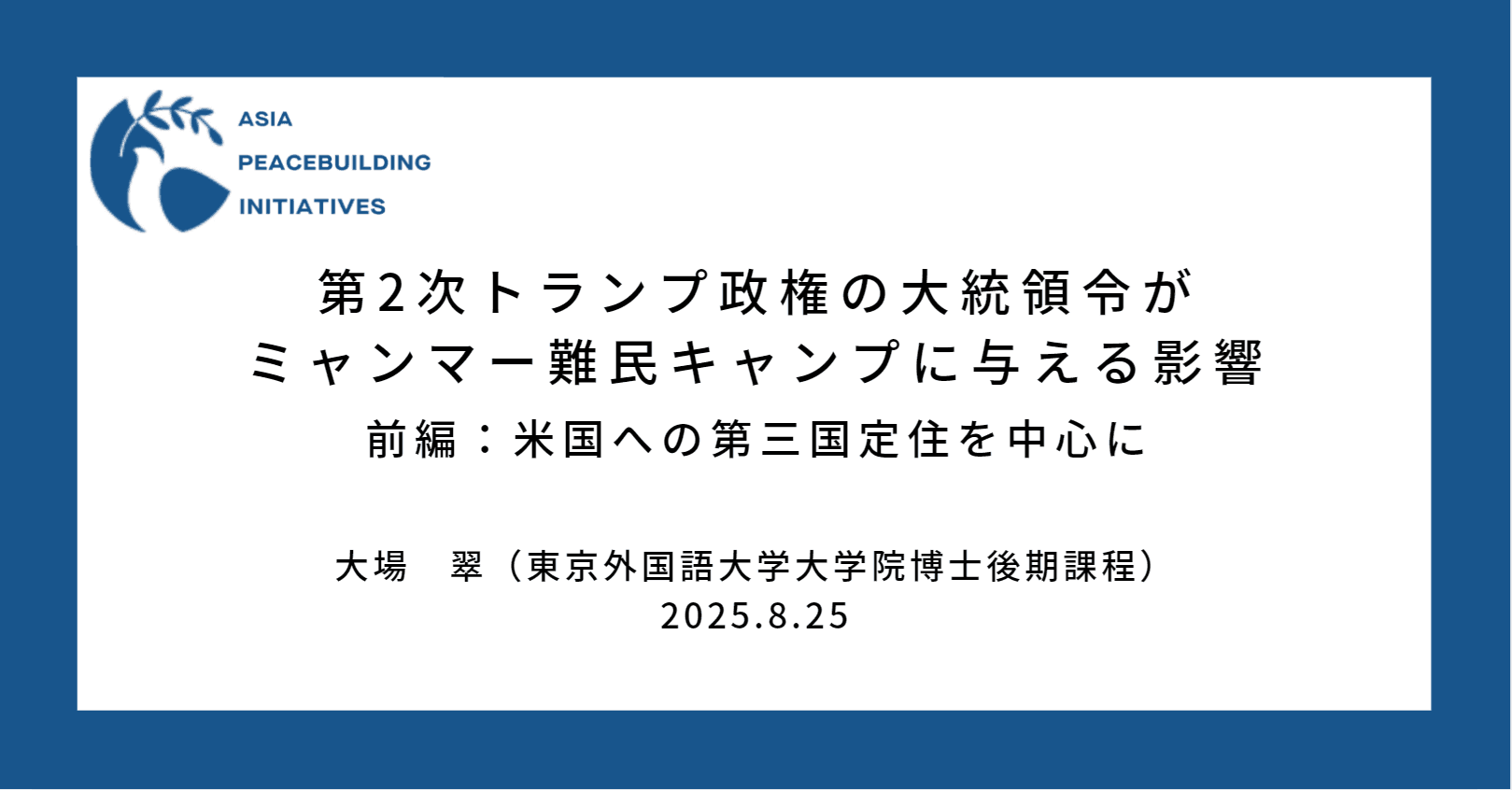- 今村 真央
- ミャンマー
【エッセイ・映画評】
人間が獣のように吠える時〜〜
『この都市を失って』(『負け戦でも』)
ミャンマー/2023/23分 監督:匿名

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。
「人民がいなくて、何が都市だ?」
〜ウィリアム・シェイクスピア『コリオレイナス』より〜
近年ミャンマー人監督によるドキュメンタリー映画が数多く作成され、日本をはじめ国外でも上映機会が増えている。国際映画祭などで選出されることも稀ではない。これは以前には見られなかった現象である。2022年には『ミャンマー・ダイアリーズ』がベルリン国際映画祭パノラマ部門に選出され、ドキュメンタリー賞を受賞した。2023年にはミャンマー人による作品(『この都市を失って』(『負け戦でも』))が山形国際ドキュメンタリー映画祭のアジア部門(「アジア千波万波」)で最高賞(小川紳介賞)に選ばれた[1]。ミャンマー人監督の作品が最高賞に選ばれたのは、アジア最古にして最大のこのドキュメンタリー映画祭で初めてのことだ。本エッセイでは、ミャンマーのドキュメンタリー作家が2021年クーデター後に直面する課題を論じた上で、『この都市を失って』(『負け戦でも』)がいかに新境地を切り拓いたかを示したい。
[1] 山形映画祭では『負け戦でも』という題が付けられたが、ビルマ語の原題(「ピャアウソンチンディミォピャ」)により近い「この都市を失って」という邦題を本エッセイでは用いる。ビルマ語の原題についてはピーピョミッ氏から教えていただいた。
質量ともに存在感が高まる、ミャンマー・ドキュメンタリー
ミャンマー映画による今日の目覚ましい躍進は、2010年代に始まった言論の自由化の産物である。2000年代以前、ミャンマーでドキュメンタリー映画を作成することはほとんど不可能といえるほど困難であった[2]。外国人による作品は散見されたが、ミャンマー人が政治問題を正面から扱うドキュメンタリー映画は皆無であった[3]。のちにパイオニア的役割を果たすヤンゴン・フィルム・スクールは2005年に開校していたが規模は小さく、また作品公開の場も限られていた[4]。
しかし、2011年に発足したテインセイン政権のもとで言論の自由が大幅に拡大されると、ミャンマー国内での映画制作も一気に活気づいた。ちょうど世界的にも、デジタルカメラやスマートフォンといった機器が安価で流通するようになった時期である。若者は言論の自由と新しい映像機器に敏感に反応し、ミャンマーの映画は新たな時代に突入し、2010年代後半には国際的にも認知されるようになる[5]。その台頭の経緯を、山形国際ドキュメンタリー映画際の上映作品を通して手短に追ってみよう。
山形映画祭でミャンマー映画が初めて選出されたのは2015年(『船が帰り着く時』<2014年制作>)であるが、その後は毎回ミャンマー映画がコンペ作品(評価対象作品)として上映されている。2017年から2023年までの計4回で選出作品を並べてみると、ミャンマーが舞台の映画のみならずミャンマー人監督による作品の増加を確認することができる[6]。
2017年上映の『翡翠之城』(2016年制作)は、シャン州出身の華人で、台湾に帰化した趙德胤(チャオ・ダーイン/ミディ・ジー)が北部カチン州の翡翠鉱山で撮影したものである。2019年上映の『山の医療団』(2019年制作)はイタリア人監督が国境地域で潜入撮影したものであった。2021年以後にミャンマー人監督の台頭が目立つようになる。『心の破片』(2021年)は、ナンキンサンウィンという、東部カヤー州出身の若手女性女性監督による短編作品であった。2023年は3本のミャマー映画がコンペ作品として選ばれたが、そのうち2本はミャンマーに住む、ミャンマー人の若手監督がミャンマーで撮影・編集したものである[7]。この二人はいまだにヤンゴンに暮らしている。
2023年の山形映画祭にはミャンマーから計14作品の応募があった[8]。その理由が2021年の軍事クーデターにあることは指摘するまでもないだろう。実際コンペに選出された3作品も全てクーデターを取り上げている。ミャンマー人監督による作品、『この都市を失って』(『負け戦でも』)と『鳥が飛び立つ時』は全編においてクーデターが主題である。2021年2月のクーデターによって、ミャンマーの民主化は突如幕切れとなり、軍事政権が復活した。自由を奪われた市民は、デモや不服従運動という形でクーデターに異議を申し立てたが、国軍は抵抗運動を徹底的に弾圧。多くの命が奪われた。この国民的災難をミャンマーの映画作家が避けることはできない。
[2] アウンミン監督がインタビューでミャンマーの映画史を簡潔に論じている。Aung Min, 2012, “The Story of Myanmar Documentary Film” https://www.guggenheim.org/articles/map/the-story-of-myanmar-documentary-film (2024年3月6日に閲覧)。アウンミン, 2015年,「日本とミャンマー映画」https://asiawa.jpf.go.jp/culture/features/aungmin/2/(2024年3月6日に閲覧)。
[3] Lindsey Merrison監督のFriends in High Places(2001年)はこの時期につくられた民族誌的映像の傑作である。Merrison監督は、清恵子氏と共に2000年代からミャンマーでの独立系映画制作の始動に寄与した。
[4] 2000年代の状況については東京芸術大学のプロジェクトTMOP2020での清恵子氏のインタビューが貴重な情報を提供している。清恵子, 2021,「CONVERSATION #4」, https://tmop.geidai.ac.jp/conversation/conversation4keikosei/ (2024年3月6日に閲覧)
[5] 2011年にヤンゴンで始まったワッタン映画祭はこの時代の輝かしい象徴であった。Thai Dhi & Thu Thu Shein, 2021,「CONVERSATION #2」https://tmop.geidai.ac.jp/conversation/conversation-02/ 2024年3月6日に閲覧)
[6] 山形映画祭は隔年開催であり、西暦の奇数年に催される。
[7] 3本目の作品は、韓国系アメリカ人エミリー・ホンによる長編ドキュメンタリー『地の上、地の下』である。
[8] 若井真木子氏および樋爪かおり氏との私信。
クーデターの後で映像作家が直面する困難:敗者が映像を持つ時
しかし、ミャンマーのクーデターを主題にドキュメンタリー映画をつくることには二つの種類の困難が伴う。まず初めに、いうまでもなく、クーデターに対して批判的な作品を世に出すことには政治的危険が伴う。「国境なき記者団」によれば、クーデター後に軍政が逮捕したジャーナリストやメディア関係者は150人を超える。そのうち60人以上がいまだに拘束されたままである[9]。日本人のジャーナリスト北角裕樹氏と映像作家久保田徹氏、そして日本育ちのミャンマー人映像作家モンティンダン氏もヤンゴンで逮捕・投獄されたことは記憶に新しい[10]。
もう一つの困難は、政治状況に関わらず、監督が作家もしくは表現者として直面する難題である。2021年のクーデターに関してはすでに、目撃者や当事者による記録映像が大量にある。クーデターは無名市民が撮影した数多くの画像や動画にすでに収められている。よって、これらの動画を越える作品をつくりあげることが映像作家に求められる。しかし、市民による現場からの映像を超えることは容易ではない。
2021年のクーデター時に無名市民が撮影した動画は真に衝撃的であった。2月1日にクーデターが突如起きた時、国会議事堂に入っていく一群の車を偶然撮影したのは、エアロビクス・インストラクターの自撮り動画であった。彼女は意図せずに、歴史的事件をカメラに収めてしまったわけだ。続いて、ヤンゴンをはじめ各地から抵抗する市民の映像が世界を駆け巡った。クーデターに対して異を唱える無数の一般市民たち。カラフルなコスチュームに身を纏った若者たち。大通りを埋め尽くす群衆。不服従運動を始めた医療従事者の集合写真。しかし、2月中旬からミャンマー軍の徹底的な弾圧が始まると、痛々しい映像ばかりが連日送られてくるようになる。兵士に蹴り飛ばされる救助隊員。トラックの上の兵士からいきなり銃撃を受け、自転車から墜落する若者たち。動かない子供の体を抱きながら、「俺の子が!俺の子が!」と叫ぶ父親。棺桶に顔を伏せて震える母親。膝をつき、両手をあげ、「もう撃たないで」と兵士たちに懇願する修道女。泣きながら3本指を立てると遺族と友人たち。そういった映像が半年ほど絶え間なくミャンマーから世界中に送られた。
ミャンマーから届いたこれらの映像の大半は、プロの映像作家によるものではなく、その場に居合わせた目撃者が自分のスマホで撮影したものだ。建物の窓や上階からこっそりと隠し撮りしたものも多数あった。スマホを握る手が震えている動画も目立った。撮影者の悲鳴が録音されていることもある。また、兵士や警察官が「扉を開けろ」「撮影を止めろ」と撮影者に向けて怒鳴っている映像もあった。こういった動画の撮影者はもはや事件の目撃者であるのみならず被害者であり当事者である。
被害者が多数の映像を持っているという点で、2021年のクーデターは現代史の中でも例外的な事件である。大島渚が「敗者は映像を持たない」と指摘した通り、弾圧の被害者はまず映像記録を有していない。例えば、2017年だけでも数万という規模で殺害されたロヒンギャ市民は、その暴力を映像に収めることができなかった[11]。パトリシオ・グズマンの『チリの闘い』(1975, 77, 79)や、ジョシュア・オッペンハイマーの『ルック・オブ・サイレンス』(2014)でも、創造的な手法で「敗者の映像」をつくりあげることでドキュメンタリー史上に輝く名作となった。しかし、ミャンマーの2021年 クーデターでは、(少なくとも一部の)被害者が映像を残している[12]。監督が映画を作る前に、すでに当事者による無数の動画が巷に溢れている。「敗者による映像」がすでに世界に衝撃を与えた後で、ドキュメンタリー作品に何ができるのか。 2021年のクーデター後に、ミャンマーのドキュメンタリーが直面したのはこの問いである。
[9] Reporters Without Borders, 2024, Asia, https://rsf.org/en/country/myanmar (2024年3月6日に閲覧)
[10] DocuAthan, https://www.docuathan.com/about-docu-athan (2024年3月6日に閲覧)
[11] 私が知る限り、国軍兵士の殺害を写した唯一の映像は、ロイター通信が発表した数枚の写真のみである。国軍側の人物が撮影した写真をワローン記者とチョーソーウー記者が入手したが、彼らには国家機密法違反で禁錮7年の有罪判決が下った。スーチーもこの判決を擁護し、二人の記者は500日以上に勾留された。
[12] 大島渚、 1975年、「敗者は映像を持たない」『大島渚著作集 第2巻 敗者は映像を持たず』(2008年、現代思潮新社)収録
映像作家が吠える時:極限状態からの声
この問いに対する答えを、私はこれまで二本の作品に見出すことができた。一本は、NHKスペシャル『緊迫 ミャンマー 市民たちのデジタル・レジスタンス』であり、もう一本が前述の(『この都市を失って』(『負け戦でも』))である。
『市民たちのデジタル・レジスタンス』は、クーデターのわずか2ヶ月後に放映された作品だが、ミャンマーの無名市民による動画を積極的に用いるという新たな方法を徹底することで生まれた傑作である。NHKというプロの番組制作集団が、市民による映像の証言的価値を追求するという斬新なアプローチであった。ミャンマーから届いた映像は衝撃的であったが、それらの映像には証拠としての価値がいったいどれだけあるのだろうか。『市民たちのデジタル・レジスタンス』は、現場に偶然居合わせた市民による映像を唯一無二の証拠映像として分析した。インターネットで誰もがアクセスできる(オープン・ソースの)映像も含めた無数の映像を法医学的視点から検証するという新たな手法を通して、記録映像の定義そのものを変える視点を提示した。このNHKスペシャル取材班は、ドキュメンタリー番組を作成すると同時に、一般市民による映像を積極的に収集・保存する「ミャンマーで何が起きているのか」というサイトも開設した[13]。これら一連の作品と行動は、SNS時代のドキュメンタリーの課題を認識した上で、新たな可能性を示した。
『この都市を失って』(『負け戦でも』)もまた、SNS時代にドキュメンタリーには何ができるかという根源的に問いに対する答えを提示している。その答えとは、一言で言えば、大事件(クーデター)そのものを対象にするのではなく、クーデター以後の日常に焦点を合わせ、当事者個人の内面を描くことである。
この短編作品に劇的な映像は一切ない。報道からも物語からもあえて距離を取ることで、暗澹たる日常に焦点を合わせている。全編において、カメラは監督が暮らすアパートの外に出ることすらない。3名の人物(監督と彼の家族と思われる)が現れるが、顔は露わにされない。アパートには大きな鳥(インコ?)が飼われている。この鳥は羽を大きく開いて羽ばたくが、飛ぶことはない。髪の長い女性がバイオリンを弾く映像と、監督(と思われる男性)がチェロを弾く映像が短く挿入されるが、そこで聞こえるのは断片的な音に過ぎず、音楽が旋律として流れるわけではない。これらの断片的な映像と音声は何らかのストーリーを物語るわけでもなく、行く先を見失った日常を表しているようだ。
映像を一つの作品としてまとめているのは、監督の声によるナレーションである。ナレーションによれば、この若き監督は、クーデター後にデモに参加したことで逮捕され、投獄された。彼はやがて釈放されたが「釈放後の方が精神的に辛い」と語る。「刑務所では皆で一緒に生き延びた。でも僕が釈放されても皆は拘束されたままだ。」監督は頭からは、まだ獄中に残っている友人たちのことが離れず、彼は自身の無力と罪悪感に打ちひしがれている。「どこにも逃げ場がない」。映画が進むにつれて絶望が深度を増していく。監督のナレーションは「今や僕が好きだったヤンゴンは刑務所と化した/どこにも逃げ場がないように感じる/僕が生まれ育ったヤンゴンはもうここにはない。」という絶望と喪失の表明で終わってしまう。
しかし、我々が監督の声を聴くのはそれが最後ではない。静かなナレーションが終わり、映画も終わると思いきや、監督はなんと獣のように吠えはじめる。巨大な敵に追い込まれ、命の危険を感じた犬が、ここで死ぬものかと必死に吠える、そういう吠え方だ。この刑務所で人の道を歩むことはもはや難しい、獣に身を堕とすことでしか生きながらえる方法はない。吠え声が伝えているのは、そういう極限状況である。
映画館でこの映画を視聴した私は、突然の咆哮に驚きながらも、「吠える」という詩を思い出した。1950年代にアメリカ合衆国をマッカーシズムという狂気が襲った時、ある若き詩人が書いたものだ。その冒頭はとりわけよく知られている。「ぼくは見た、ぼくの世代の最良の精神たちが、狂気に破壊されたのを」[14]。ヤンゴンの若い芸術家も見てしまったのだ、彼の世代の最良の精神たちが狂気に破壊されたのを。私はそう受けった。
クーデター後にミャンマー詩を精力的に日本語に訳した詩人の四本康祐は、「人はなぜ危機の中で詩を書くのか?」と問い、以下のように答えている。「自由を奪われ、愛するものを殺された人々の絶叫が、詩という壜に詰められて、時空の海原へ投じられているのだ」と[15]。人間は、大声で叫んだり、吠えるしかない危機的状況に追い込まれることがある。極限状況で発せられた叫び声をなんとか言語化したものが詩である、と。四本の詩論に沿えば、『この都市を失って』(『負け戦でも』)という作品は極限状況で発せられた咆哮を映像化した作品であるといえるだろう。監督自身はすでに釈放され、自宅で静かに暮らしているが、彼の生はトラウマと恐怖に支配されている。羽ばたいてももう飛べない、もはや獣になりそうだ。ミャンマー人の苦悩をここまで深く表現した映像作品を私は他に知らない。
『この都市を失って』(『負け戦でも』)はまた、ヤンゴンという一つの地にのみ焦点を合わせているという点でもクーデター後を扱うドキュメンタリー作品の中で例外的である。「ヤンゴン、ぼくらが育ってきた街」と言うナレーションで始まる映画は、ヤンゴン以外の地には言及せず、「ミャンマー」という国を語ることもない。これは、クーデター後につくられたドキュメンタリーのなかで異色の設定だ。というのも、軍事政権下のミャンマーを描く映画では国全体が主題であることが強調され、しばしば舞台が辺境(「解放区」)や国外に移る。ミャンマーの軍政を批判的に描く映画では、中央部で国軍の攻撃を受けた登場人物が辺境や国外に逃れ、「辺境からの救済」を暗示するという対比がほとんど定型句になっている[16]。救済への場を辺境や国外に位置づけることで、視聴者に希望を与える結末を設けられるからである。
しかし、こういった辺境の表象は外部からの一方的な期待にもとづいていることもしばしばだ。匿名監督は自分の街ヤンゴンのことしか語らない。「ミャンマー全土のことを語るにはまだ早い」と判断したのだろうか。それは「ミャンマー」の代表・表象がいかに困難かを知る作家の倫理的な判断なのかもしれない。
この映画が我々視聴者に一抹の希望を与えるのは、ヤンゴンの若き芸術家が優れた映像作品をなんとか作成し、そして国外の映画祭に送ってくれたという事実である。彼の国では芸術家が映画を作りたくても作れないという状況が続いている。カメラを自宅の外に持ち出すことすらも危険な街で、ドキュメンタリー映画作成は命懸けの行為である。2023年10月には著名なドキュメンタリー監督シンデーウェー監督が逮捕され、先月(2024年1月)に終身刑が宣告された[17]。作家たちが自由に作品をつくれる日が一日も早く戻ってくるために自分にはいったい何ができるのか。我々の都市を取り戻すにはどうすればよいのか。この匿名監督は問い続けている。
*本映画評を執筆する上で、樋爪かおり氏、北角裕樹氏、岩井真木子氏および査読者から貴重なアドバイスをいただいた。感謝申し上げたい。
[13] 2022年に出版された、『NHKスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる』に番組作成の詳細が説明されている。NHKミャンマープロジェクト、2022年、『NHKスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる』(講談社)。
[14] アレン・ギンズバーグ、2020年、「吠える」『吠える その他の詩』柴田元幸訳(スイッチパブリッシング)
[15] 四元康祐、2021年、「Dah Poetryクロニクル 人はなぜ危機の中で詩を書くのか?」『現代詩手帖 特集 ミャンマー詩は抵抗する』(2021年11月号、思潮社、p.60)
[16] 国境地域を救済の空間とする表象は、長年ミャンマー軍政との闘いを描く映画の定型になっている。『ラングーンを超えて』(1995)でも、『ランボー 最後の戦場』(2008)でも、『ビルマVJ 消された革命』(2010)でも、軍政が支配する中央に対して、隣国からの越境活動に希望を抱かせるという構図になっている。
[17] Human Rights Watch, 2024, “Myanmar Filmmaker Sentenced to Life in Prison”
https://www.hrw.org/news/2024/01/12/myanmar-filmmaker-sentenced-life-prison シンデーウェー監督の作品は2018年の恵比寿映像祭で上映されたこともある。

山形大学 人文社会科学部 教授