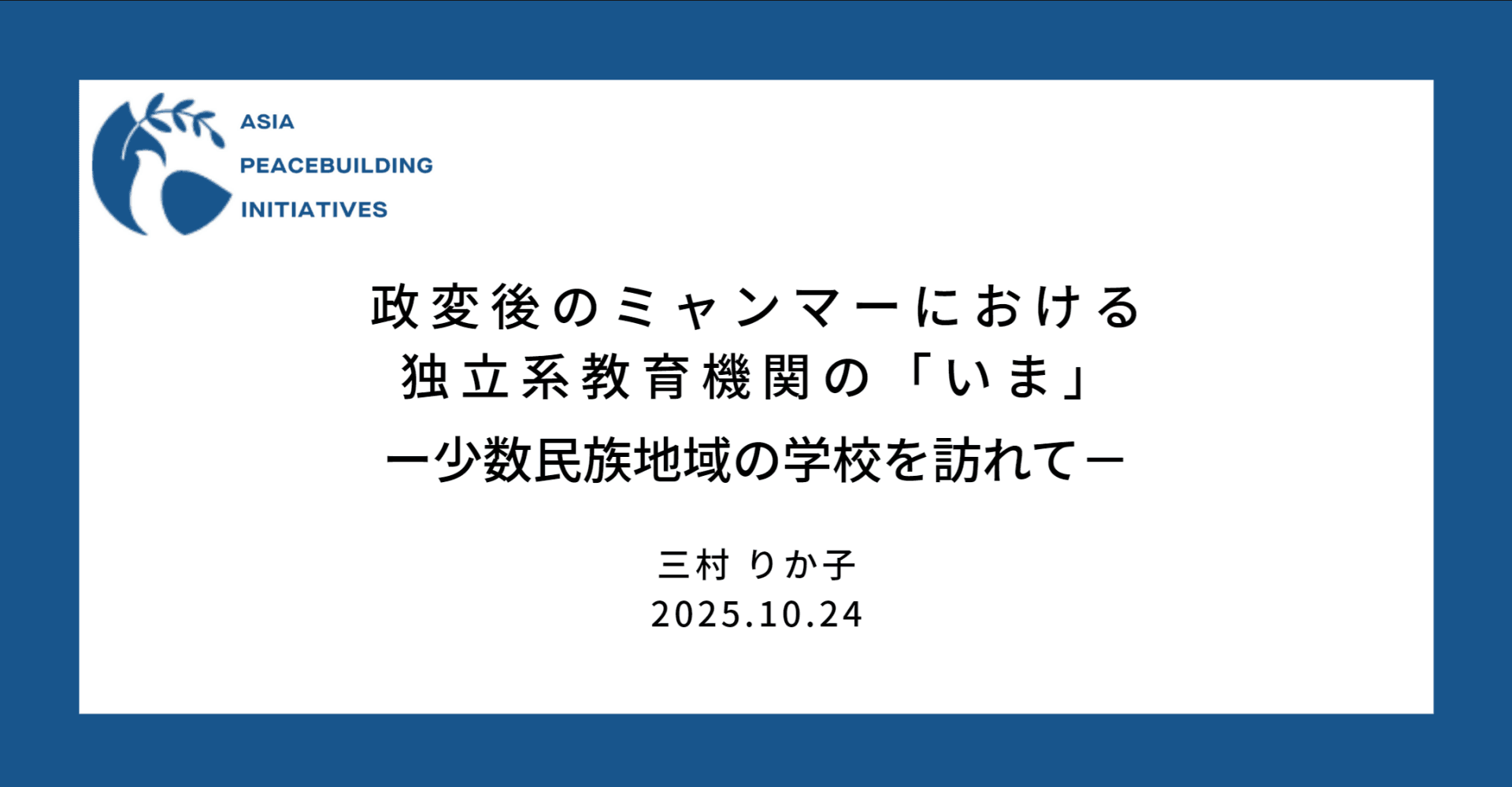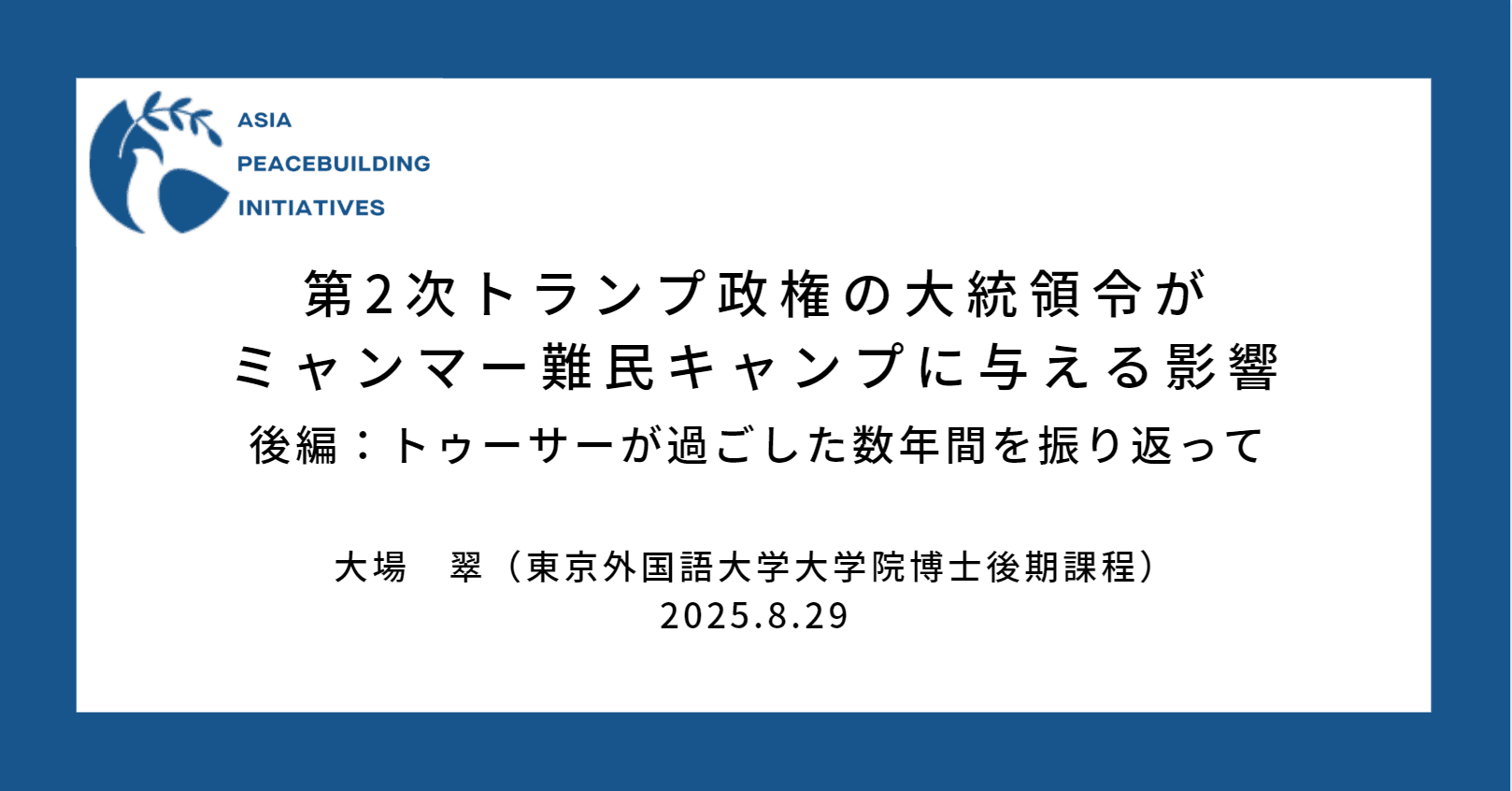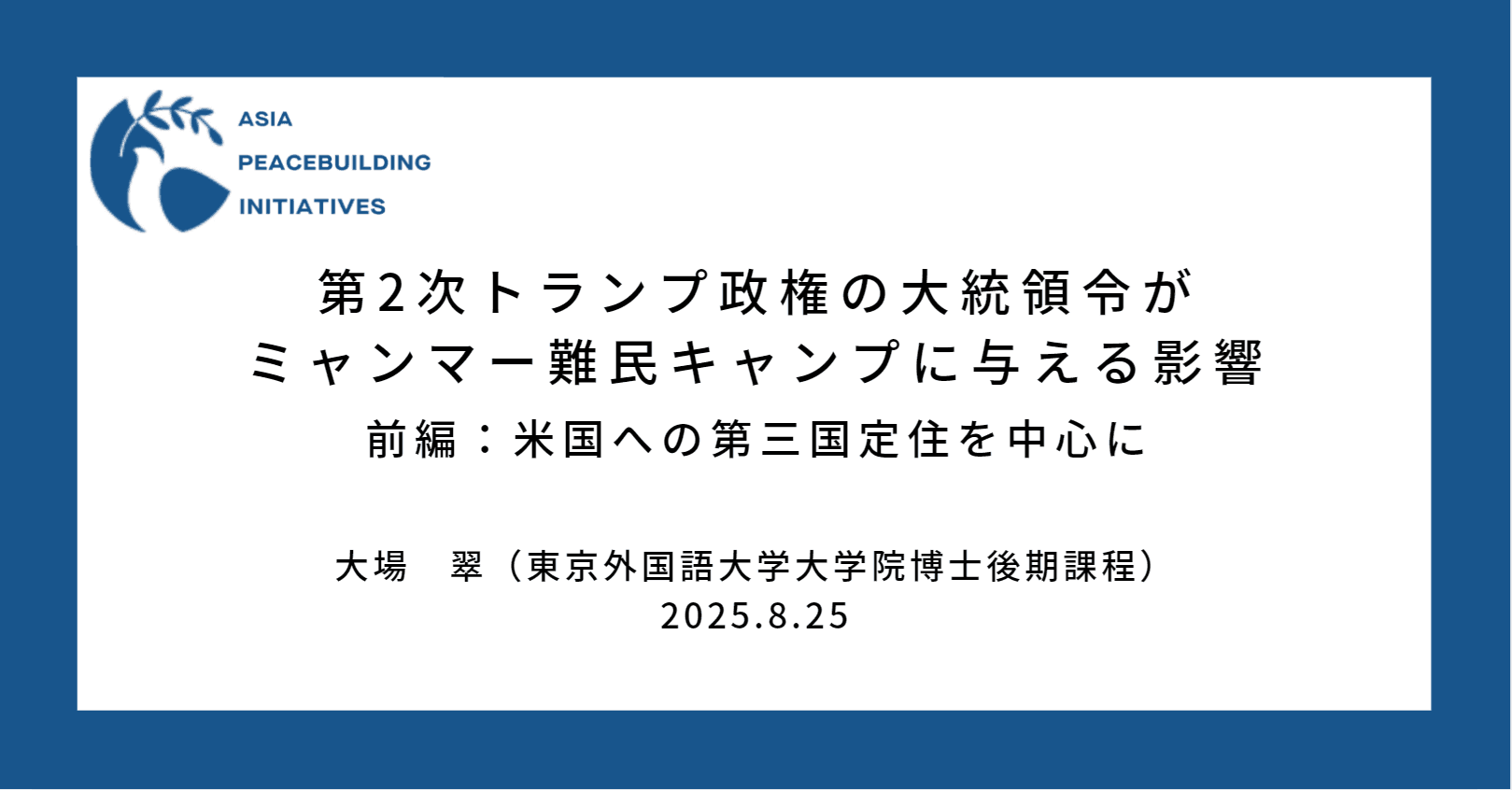- 斎藤 紋子
- ミャンマー
仏教徒とムスリムの関係
ミャンマーでの反ムスリム運動の背景を考える
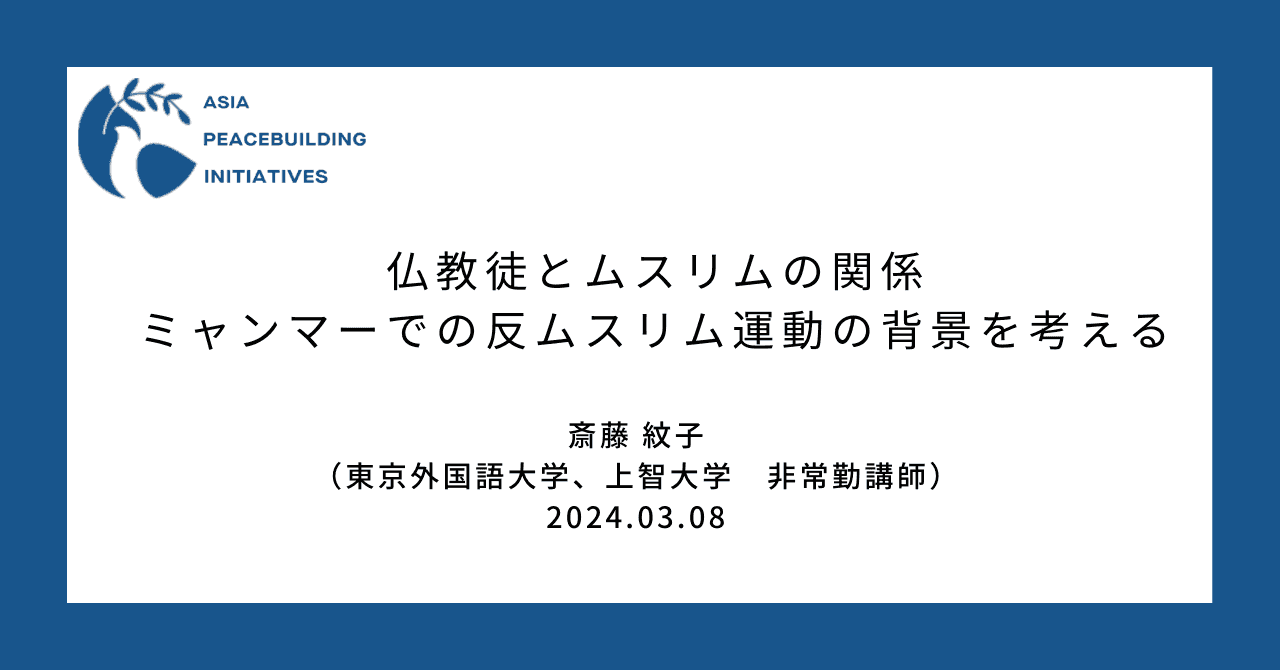
※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。
1. はじめに:反ムスリム運動は突然発生したのか
ミャンマー・ラカイン州でムスリム(ロヒンギャ)による仏教徒ラカイン女性に対する暴行として報道された事件をきっかけに、大規模暴動が発生したのは民主化後1年ほどたった2012年6月であった。その後、全国で反ムスリム運動が高揚、2013年から2014年にかけて各地で大規模なものも含め暴動が多数発生した。小規模な暴動は2016年までみられ、その後も小競り合いが発生していた。2012年の暴動のきっかけはロヒンギャと関係があったが、それ以降の反ムスリム運動はロヒンギャの枠を超えて国内全体のムスリムに向けられた。
現在、反ムスリムの動きは少なくなり、2021年のクーデターの影響で、マイノリティ全体に対する風向きが少しだけ良い方向に変わりつつあるように見える。しかし、反ムスリムの動きが全くなくなったわけではない。ミャンマーの人々が抱く反ムスリムの感情は民主化後に急激に高揚したようにも見えるが、実際には民主化以前は顕在化していなかっただけの状態であった。本稿ではミャンマーで多数を占める仏教徒と、マイノリティであるムスリムの関係について、少し時代をさかのぼって考えてみたい。
2.イギリス植民地時代:インドからの移民増加との関係
反イスラーム/ムスリム感情の発生時期をさかのぼるのは難しい[1]。植民地時代を見ると、1930年代にはヤンゴンで反インド人暴動が2回発生している。これについてはすでに拙稿[斎藤2012:17]で扱っており、1回目の暴動はヤンゴン港でのビルマ人労働者とインド人労働者の荷役作業をめぐる争いであり、宗教は直接関係していない。さらに1938年の2回目の暴動については、植民地政府が暴動調査委員会を発足させ、報告書も出されている。ムスリムが書いた『イスラーム礼拝導師と瞑想修行者文書』という本が発端となった暴動であったが、報告書では特にムスリムのみに問題を見出すことはなく、結婚の問題以外はインド人全般に対する反感やナショナリストの扇動を問題の原因としていた。
ただし、報告書の最後には付録として、暴動に関して1938年7月26日にシュエダゴンパゴダで行われた青年僧侶組織主催の会合のアジェンダと解決策が掲載されており、こちらでは先の本の著者と出版者などへの強い抗議と、ビルマ人仏教徒女性の婚姻について法律制定の要求をしている。特に、本の執筆や出版等にかかわったムスリムに対し要求通りの処罰を行わない場合、ムスリムを仏教徒コミュニティと仏教を侮辱する第1の敵とみなす、という強い表現が取られている[The Final Report 1939:ix-x]ことから、ビルマ人社会でのムスリムへの反感は非常に強いものであったことは明らかである。
上記の政府報告書以外にも、ビルマ人ナショナリストであったテインペーの書いた「インド人とビルマ人の争い」という本が出されている。こちらも当時のビルマ社会に存在したインド人に対する不満が書かれ、一方で宗教については結婚に関すること以外では触れられていない[斎藤2012:17-18]。テインペーの本では先の報告書の付録のような強い言葉は使われていないが、不満は具体的に描かれている。ただ、インド人を「カラー」[2]と表記し、結婚問題でムスリムだけを指す場合も「カラー」と表記しているので、信仰による反感ということではなく、インド人全体に対する反感が強かったとも推測できる(「カラー」については次節でも扱う)。
一方ムスリムの側では、植民地時代にインドからミャンマーに入ってきたインド人ムスリム以外に、王朝時代からミャンマーに暮らしていたムスリムの子孫がおり、彼らは「ムスリム」としてひとくくりにされることをすでに気にしていた。1930年代にはバマー・ムスリムの歴史に関する本が2冊出版されており、当時の社会の中での自分たちムスリムの立場に関することも叙述している[斎藤2012:13-14]。「バマー・ムスリム」というのは王朝時代からミャンマーに暮らし、社会の中で仏教徒ともかかわりがあり、ミャンマー文化を受容していると自認してきたムスリムの自称である。この2冊の歴史書の中で、彼らはムスリムであることによって「インド人」とひとくくりにされ「ビルマ人」と認められないことに不満を抱いている。ただし、これは「インド人」として差別されているという意味ではなく、他の多くのビルマ人と同じ立場(植民地での被支配者としての立場)であり、先に述べたような当時の社会でのインド人への反感に対し、自分たちは「ビルマ人」と扱われるべきだとの認識であった。
もう一点、前述の1938年の暴動に関する報告書に、結婚に関してムスリムと仏教徒女性の間で問題が生じていたと書かれていたが、1930年代にはすでに仏教徒女性と(インド人)ムスリム男性との結婚についての小説が現れている[3]。1930年代のこうした小説は元々ヘイトを意識して書かれたものではないと思われるが、後述する内容を含む類似の作品を集めれば、ムスリムに対する反感を煽るには十分なものとなっていたのが事実である。実際に独立以降長期にわたって、同じような内容の小説がまとめられた本が、アンダーグラウンドで出回っていた。筆者はこうした書籍を旧軍政期(1988-2011)の国家平和発展評議会(SPDC)政権下の2002年以降に入手している。この当時、ミャンマーにおいては映像や音楽、出版物に対して検閲制度があり、民族・宗教対立を煽る内容は検閲が通らないために未検閲のまま密かに売られていた。
例えば、『知るようにしなさい。愚かではならない』(著者、出版年不明)という本には三つの小説が掲載されている。最初の小説は「メーミャ」と題され、1938年に出版された民族教育行政官ポーチャーによるノンフィクション小説集からのものとされている。残りの二つは著名な作家ピーモーニンによるもので、「ナンとインド人(カラー)」(1934年12月7日発行「ランニュン・ジャーナル」第2巻第62号から)、および「車に乗せて」(1958年出版「ピーモーニン短編小説集」から)というように原版についても記載がある。ピーモーニンは1940年に亡くなっているので、つまりこの二つの小説はそれ以前に書かれたものと考えられる。小説の内容で共通の点は、ムスリム男性の暴力性や女性に対する性的搾取、金銭による仏教徒女性誘惑、複数の妻、仏教徒であった妻に対するイスラームへの強制的改宗、などである。
1930年代にこのような内容の小説が出ており、一つはノンフィクション小説集からのものということで、当時このような事例が実際にあったと推測することは可能であろう。ただし、元々別の媒体で発表されたものを一つにまとめ、それをのちの時代にアンダーグラウンドとはいえおそらく意図的に流通させていた状況にあるため、著者の意図しないところで利用されることになったともいえる。上述のものを含め、ムスリムに対する嫌悪を増幅させるような出版物が複数存在したことはいくつかの本でも指摘されており(例えば[Selth 2003:9-10][Fink 2001:225-226]など)、拙稿でもこれら書籍の内容を扱っている[斎藤2015:193-196]。ここでは内容についてこれ以上詳述しないが、こうした書籍が反ムスリム感情の醸成に関係していた可能性は否定できないといえる。
[1] 1930年代より前の状況について、例えばルードゥ・ドー・アマーによる『クジャクの羽ペンエッセー』 という本には、マンダレー在住のバマー・ムスリムが1911年に発行したヤダナボウン・メガゼインという雑誌について書かれている。雑誌はビルマのムスリム向け記事のほか、一般読者向けに新年の占い、ビルマの新年を詠んだ詩、人口統計関連の記載もあり、広く読者啓蒙の目的をもって編集出版されたと推量できるという[Ludu Daw Ahmar 1975 =1994:130-131, 136]。これだけで当時の社会の状況を明確にはできないが、民族・宗教間関係に大きな問題はなかったと推測できる。
[2] 次節でも述べるが、「カラー」は通常、宗教に関係なく南アジアの人々全般、あるいは西アジア地域の人までを含めての呼称であるが、ムスリムのみを意味している場合もある。呼ばれる側は差別的と感じることが多い。
[3] これらの小説について、ほぼ同時代に出されている暴動調査委員会の報告書、テインペー著「インド人とビルマ人の問題」、およびバマー・ムスリムに関する歴史書2冊のいずれにも言及はない。
3.独立後の仏教徒とムスリムの関係
植民地時代に出版された上述の2冊の歴史書には、ビルマ民族/仏教徒とムスリムとの間に問題が発生しているというような記述は特にみられない。一方で、1938年の反ムスリム暴動の政府報告書やナショナリストが書いた本からはムスリムに対する不満が出ていたことがわかり、また同時代に発表されたムスリム男性と仏教徒女性の関係を描いた小説からはムスリムへの反感がすでに生まれていたことが窺える。
その後植民地からの独立を果たし、1951年[4]にはピンサルーパン・ウー・カ[5](以下ウー・カ)というムスリムによって『ビルマ人とムスリムの民族宗教問題』という本が出版されている。読み物形式になっている本の内容は、あるムスリムの結婚式に向かう際の列車の中でなされた会話が結婚式参列者の間で話題になり、その話題に関する疑問点を、元郡長をしていたバマー・ムスリムを中心に数人の登場人物が解説していく、というものである。「カラー」という呼び方、なぜそう呼ばれたくないのか、カラーとムスリムは同じか、イスラームの教えにはどのようなものがあるか、など解説されている内容は多岐にわたる。読み物の中の登場人物に解説させることで、著者であるウー・カがどのような問題意識を持っていたのか、また独立後に仏教徒とムスリムの間にどういった問題があったのかということがこの本に示されている[6]。
ウー・カのこの本の中では、カラーという呼称について次のような発言がある。例えば「『カラー』と呼んだだけで怒り傷つく理由は自分たち(ビルマ人仏教徒)にはわからない」「服装の違いで自分たちと違うことは明白である」「呼称が『イスラーム人』『ムスリム人』『モハメダン人』『カラー混血』『ザーバディ(ゼルバーディ)』『パディ人』と多岐にわたるため自分たちは簡単に『カラー』と呼んでいるだけで、わざと傷つくような呼称を使っているのではない」[Kha 1952: 5]といったものである。
この呼称について、例えば、地図にあるイギリスという国で生まれて「イギリス人」と呼ばれるのはわかるが、「カラー国」がないのに「カラー人」はいるのだろうか[Kha 1952: 40-41]と疑問を投げかけている。さらに、キリスト教宣教師ジャドソンが作成した辞書によれば「カラー」は外国人あるいは海を渡ってきた人とあり、バマー・ムスリムは外国人ではなく、海を渡るどころか海なるものを見たこともない人がほとんどなので、「カラー」という呼称にはあたらない [Kha 1952: 42-43]、また、混血が進み生活習慣などがミャンマー文化に近くなり、言葉もビルマ語を使うようになり名前もビルマ名で呼ばれ、それなのに「カラー」とは言われたくない[Kha 1952: 43-45]とも述べられている。
読み物はビルマ人仏教徒に対してもムスリムに対しても、互いに混乱している点をわかりやすく説明するというのがウー・カの意図するところと思われ、仏教徒に一方的に説明するのではなく、ムスリムも質問をし、説明を聞いて初めて理解したなどの受け答えを入れている。上述の「カラー」という呼称についてと同様、宗教と民族が混ざって考えられているという点に関しても、仏教徒もムスリムも宗教と民族を同一視してしまうことが多く混乱している状況を何度も述べている。例えば、モハメダンというのはカラーという意味か、という質問に対しては、カラーは民族を指しておりモハメダンは宗教(信徒)のことである[Kha 1952: 21]と答え、また、バマーだと主張するのになぜカラーのモスクに行くのか、という質問には、「カラーの」モスクではなく、ムスリムであれば誰でも行くことのできる礼拝の場所がモスクであるのでカラーのモスクという言い方は適切でないと説明している[Kha 1952: 60-61]。
この読み物に挙げられているような呼称の問題や、民族と宗教を区別できないという問題、ムスリムの文化や習慣に対する疑問は、おそらく現在でもよく理解できていないという人が多いのではないかと推測できる。ビルマ民族であり仏教徒である人々が多数を占める中で、マイノリティを知る機会があまりないということも関係するのではないだろうか。この1冊だけですべてを知ることにはならないが、独立後の状況のなかですでにこうした問題があると捉えられていたことは注目に値するといえよう。
[4] 筆者は1952年出版の第二版を入手したが、第一版は1951年9月出版[Aung Zaw n.d.: 72] 。
[5] 著者ウー・カは1885年生まれでマンダレー出身、編集や印刷の仕事をし、植民地時代にはミャンマーの人々の教養を高める必要性や正しいものの見方について見解を発表していた。また1950年代にはイスラーム関連の雑誌に、バマー・ムスリムが新聞や雑誌を軽視している状況への批判や、礼拝の仕方、死に対する考え方などの解説を掲載している[Aung Zaw n.d.: 65-67]。
[6] 第二版前書きには、「ビルマ連邦の国民である仏教徒とそこで生まれたムスリムの間には、民族や宗教に関してややよそよそしい場面がみられるが、お互いに正しく理解していけば平和な連邦が築かれるという希望をもって、自分の見方をここに記述した」とある[Kha 1952: 1-2]。
4.おわりに
本稿では、仏教徒とムスリムの関係を植民地時代、独立後の時代にさかのぼって考えてきた。さらにさまざまな資料を探索する必要があるものの、今回扱った資料からは、直接的に現在の反ムスリム感情、反ムスリム運動に結び付くようなものは見られなかった。しかし、植民地時代に出された一部小説は、その後のアンダーグラウンドでの反ムスリム感情増幅に利用されており、現在の問題は植民地時代後半に一部その萌芽がみられたと言える。
1950年代の資料に挙げられていたような相互理解の不足という点は近年も変わっていない。2021年のクーデターを挟んで、今後のミャンマー社会では若者を中心に多様性を重視、尊重することを望む声が多くみられ、相互理解は必須である。現在の軍政と民主派側の闘いがいつまで続くか不明だが、今後の国造りのなかでも引き続き仏教徒とムスリムの関係、さらには民族的宗教的マジョリティとマイノリティの関係に注意を払う必要があるだろう。
参考文献
Anonymous. n.d. Si Aung Lup Kra, Ma Nyam Kra Nai.(『知るようにしなさい 愚かではならない』)n.p. (未検閲書籍)
Aung Zaw, Pamaukkha Dr. n.d. Tuingyang Mwatcalang Capru Cahcui Puggui Kyau Mya. Dutiya Twai. Accalam Cacany Ahmat(60).(『土着ムスリム有名著述家の人々』第2 巻.イスラームシリーズNo.60)Yangon: Accalam Sasana Yeya Kaungci
Htana Hkyup.
The Final Report, The Final Report of the Riot Enquiry Committee. 1939. Rangoon: Supdt., Govt. Printing and Stationery.
Fink, Christina. 2001. Living Silence: Burma under Military Rule. London: Zed Books.
Hbo Chey, Hsaya U. 1939. Bama Mwatcalang tui i Hrehaung Athtuppatti (『バマー・ムスリムの古い記録』), Sagain Myo: Mya Than Ca Pumhniptuik.
Kha, Pyinsa Rupan, U. 1952. Bama hnang Mwatcalang lumyui basa pyassana. (“Facts on Burman & Muslim”) Second Edition. Prome, The Pyinsa Rupan Press.
Ludu Daw Ahmar. 1975. Shwe Daung Taung Hsaungba-mya. Mandalay.(『ビルマの民衆文化―語られたパゴダと微笑みの
国』土橋泰子訳. 新宿書房. 1994.)
Mya (1), Asoya Sheinei U. n.d. Bama Mwatcalang Samuing Akyanyhkyup (『バマー・ムスリムの歴史概要』) Mandalay.
Selth, Andrew. 2003. Burma’s Muslims: Terrorists or Terrorised? Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, The
Australian National University.
Thein Pe, Maung.〔1939〕. Kala Bama Tuikpwai.(『インド人とビルマ人の争い』)Rangoon: Nagani Caoup sang.
斎藤紋子 2012.「ミャンマーにおける『バマー・ムスリム』概念の形成 : 1930年代ナショナリズム高揚期を中心として」『東南アジア. 歴史と文化』41号 pp.5-29
斎藤紋子2015.「ミャンマー社会におけるムスリム -民主化による期待と現状-」工藤年博編『ポスト軍政のミャンマー ―改革の実像
-』pp.183-204 日本貿易振興機構アジア経済研究所

東京外国語大学、上智大学 非常勤講師