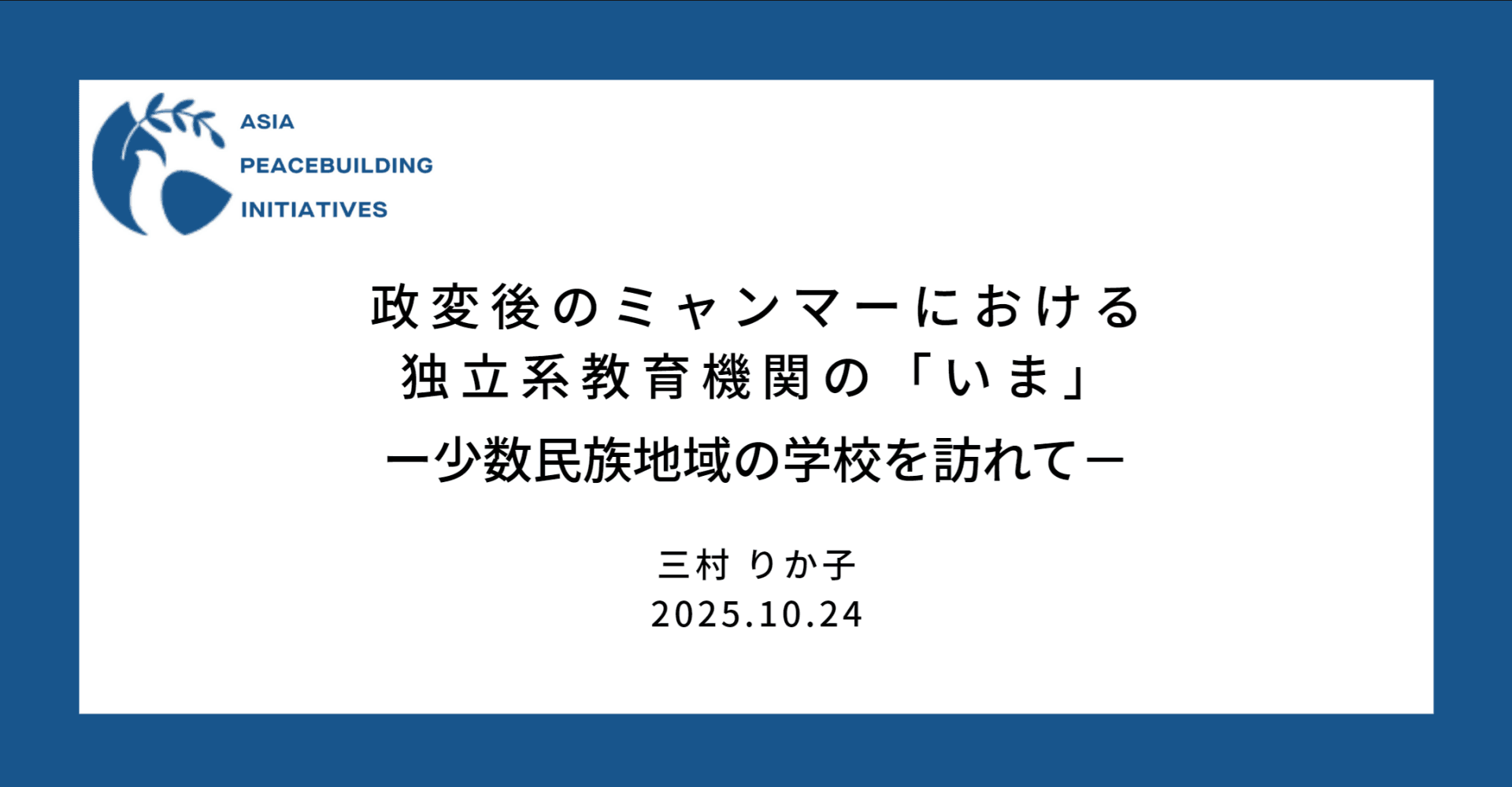- 岡野 英之
- バングラデシュ
【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (2)
―ラカイン州政治情勢に翻弄される難民たち―

このエッセイはロヒンギャ人難民を紹介する3回シリーズの第2回目である。筆者は、朝日新聞の笠原真記者やその通訳である田中志歩さん、そして、バングラデシュ研究者の日下部尚徳さんとともにロヒンギャ人難民キャンプを訪問する機会を得た。第1回目のエッセイではバングラデシュに逃れたロヒンギャ人難民が、現地に住むベンガル人のコミュニティと隣り合って住んでいることを紹介した。難民キャンプは有刺鉄線で囲われ周囲と隔てられてはいるものの、ベンガル人の住むコミュニティのすぐそばにあり、キャンプへの出入りも比較的自由であった。
難民キャンプが点在する地域を回った翌日、すなわち、2024年11月27日、私たちは難民キャンプのひとつを訪問する機会を得た。今回のエッセイでは、その訪問時に聞き取った難民たちの声を紹介したい。難民キャンプでは、この頃、ロヒンギャ人武装勢力による強制徴兵が多発していた。若者たちは兵士になってミャンマーに送られるか、強制徴兵を逃れるために海外を目指すという選択肢を迫られているという。本エッセイでは、難民たちの声を紹介すると同時に、彼らの置かれた状況を理解するために、2024年11月時点でのミャンマー情勢、とりわけ、バングラデシュと隣接するラカイン州の状況を見ていきたい。端的に述べるならば、この1年ほど前、ロヒンギャ人を主体とする武装勢力が、これまでロヒンギャを迫害をしてきたミャンマー国軍と手を組んだ。その上で、ラカイン人の武装勢力「アラカン軍」(Arakan Army: AA)と戦闘をしている。その背景にはロヒンギャ人とラカイン人が対立してきた歴史がある。
難民キャンプにおけるロヒンギャ人武装勢力の強制徴兵
コックスバザールから車で1時間。約100万人がひしめく「世界最大の難民キャンプ」には、山あいにへばりつくようにシートや木でできた家屋が広がっていた。店が並ぶ表通りは人で埋め尽くされている。
この日について笠原さんはこう書いた(笠原2024)。私もまったく同じ印象だ。キャンプに着くや否や通訳である田中さんは、いろんな人に話しかけた。田中さんの気さくさと通訳の腕前もあるのだろうが、いろんな人が応じてくれた。ロヒンギャ人はわりとオープンな人たちらしい。興味を持った人がゾロゾロとやってきて周りを取り囲まれる。中にはついてくる人もいる。キャンプの中では学校を訪れたり、支援の現場を見たりしたが、それは笠原さんの記事に譲ろう(笠原2024)。本エッセイでは最近のキャンプの治安悪化、ならびに、ロヒンギャ人武装勢力ARSAやRSO(後述)による強制徴兵の話に焦点を絞りたい。
第1回のエッセイの冒頭で登場した男の子たちを覚えているだろうか。私たちは難民キャンプの訪問時、ひとつの家にお邪魔し、10代の男の子2人に話を聞くことになった。彼らからは「18歳になったら武装勢力に徴兵されるかもしれない」、「徴兵を避けるためにも外国へと出稼ぎに行くしかない」という深刻な話を聞いた。彼らからは1時間近く話を聞いたが、強制徴兵については次のように話してくれた。
彼らは18歳になると迎えにきます。ミャンマーで兵士にさせられるんです。このあたりはRSOの陣地で、迎えに来るのはRSOの関係者です。RSOとの関連で殺された人についてもよく聞きます。
難民キャンプはRSOやARSAなどの縄張りに分かれており、それぞれの縄張りでは武装勢力が若者を兵士にするために徴兵をしている。難民キャンプの区長もリスト作りに加担せざるを得ない。すなわち、武装勢力は難民キャンプのコミュニティ・リーダーにも協力を求め、徴兵に適した人物がいないかを探していたのである。こうした強制徴兵の状況を理解するためにも、近年のラカイン州の情勢や、ロヒンギャ人武装勢力が現れた経緯を記すことにする。
ミャンマー国軍と繋がるロヒンギャ人武装勢力
私たちがバングラデシュ側にある難民キャンプを訪問した時、ミャンマー側では、ラカイン人の武装勢力 AA、すなわち、アラカン軍がラカイン州のほぼ全域を掌握しつつあった(アラカンとはラカイン人の別名)。とりわけ我々が難民キャンプを訪問する2024年11月までの半年間、ラカイン州では軍事政権「国家行政評議会」(Sate Administration Council: SAC)(すなわち、国軍)とAAとの戦闘が繰り返された。その戦闘に国軍側としてロヒンギャ人武装勢力が加担した。
ミャンマーでは、2021年にクーデターが発生し、軍事政権SACが成立した。それ以来、ミャンマー各地で反SACを掲げる武装勢力の活動が増えた。ラカイン人武装勢力AAも例外ではなく、軍事政権SACに対する戦闘を繰り返し、2024年までにラカイン州のほぼ全土を掌握した。ここ数年は、ラカイン州で支配地域を広げるAAがロヒンギャ人を迫害しており、新たな難民が流出していた。そもそも仏教徒であるラカイン人は、20世紀半ば以降、ムスリムであるロヒンギャ人としばしば衝突を繰り返しており、この迫害もその延長といえる。AAが支配地域を拡大するに伴い、ロヒンギャ人の武装勢力は、それまでロヒンギャ人を虐待していた国軍(すなわち、SAC側)と協力してAAとの戦闘に参加する。その結果、難民キャンプでは強制徴兵が頻発した。若者が武装勢力関係者により強制的に連れ去られ、ミャンマーで兵士にさせられた(ICG2025)。
ロヒンギャ人の武装勢力として代表的なものが「アラカン・ロヒンギャ救世軍」(Arakan Rohingya Salvation Army: ARSA)である。ARSAが現れたのは、2012年以降にロヒンギャ人とラカイン人の対立が激化したことに深く関係している。同年5月28日、仏教徒の女性がムスリムの男たちにレイプされて殺されるという事件が発生した。それをきっかけにラカイン人とロヒンギャ人の対立が再燃し、ラカイン州各地で暴力的な衝突が相次いだ。その衝突ではお互いに村を焼き払い、人びとを追い出したという。双方の民族が被害を受けたが、国内避難民になったのはロヒンギャ人の方が圧倒的に多かった。2014年8月時点でラカイン州では13万7000人以上が国内避難民となっており、そのほとんどがロヒンギャ人であったという。ラカイン人側はロヒンギャ人避難民に対して支援を与えないよう支援団体を襲撃したり、支援団体のスタッフがホテルに泊まったり家を借りたりできないようにホテルや家のオーナーに脅しをかけたりしたという(ICG2014)。
こうした対立はミャンマーの民主化が後押しをしたと指摘されている。ロヒンギャ人とラカイン人の衝突が発生した2012年とは、ミャンマーが民政移管をして間もない頃である。ミャンマーでは2011年の民政移管をきっかけに、選挙という民主的な制度が導入され、これまで強権的な政権の下で制限されてきた表現の自由やインターネットの使用も解禁された。その後のスマートフォンの普及は著しく、5年もたたないうちに日常に不可欠な道具となった(深沢2022: 37-59)。こうした変化の中でラカイン人の間にはムスリムに対する危機感が共有された。
ムスリムは出生率が高く、バングラデシュからも次々やってくる。その一方でラカイン人は海外へと出稼ぎに行くために人口が減っている。選挙も導入されたこともあり、人口が増えた彼らは、やがてラカイン州を乗っ取るのではないか。(ICG2014に基づき筆者が要約)
そんな言説が政治集会や仏教の説法会を通して共有され、インターネットでも拡散された。さらに反イスラームの感情はラカイン人以外の仏教徒にも広がっていく。ミャンマーでは主要民族ビルマ人(人口の約7割を占める)の大半が仏教徒であり、数ある少数民族にも、仏教徒が多数を占める民族が少なくない。それを合わせるとミャンマーの全人口のうち9割弱が仏教徒だということになる。彼らの中でも急進的な考えを持つ者がムスリムの商店に対する不買運動を訴えかけたり、反イスラームを訴えた集会をしたりした。その代表的な例ともいえるのが、仏教僧ウィラトゥ師(Wirathu)である。ウィラトゥは説法において「(ベンガル人ムスリムが)過剰に増えると、我々を圧倒し、我々の国を乗っ取って邪悪なムスリムの国へと変えてしまうだろう」などと訴え、仏教徒の反イスラームの感情を煽った(中西2021:130)。そうした説法はFacebookやYoutubeによって共有されることで、さらに多くの人の目に触れることになった。反イスラームの感情が国内に広がる中、ロヒンギャ人の中には自らも武装をしようとする人々が現れた。
武装勢力ARSAは、そうした潮流の中で活動を始める。ただし、ARSAの創設者はミャンマー出身というわけではない。ARSAの指導者アタウッラー・アブ・ジュヌニ(Ataullah abu Jununi)はパキスタンの最大都市カラチで生まれた。父がラカイン州北部出身であり、アタウッラーが生まれる前にバングラデシュへと逃れ、その後、カラチに移住したのだという。アウタッラーがラカイン州の情勢に関心を持ったのは2012年に発生した「民族対立」がきっかけであった。彼はパキスタンなどでイスラーム系武装勢力による軍事訓練を受けた後、バングラデシュに渡り、武装勢力を結成した。当初の組織名は「信仰運動」を意味するアラビア語、ハラカ・アル・ヤキン[Harakah al-Yaqin]であり、英語の報道や学術論文ではHaYと略される。ラカイン州では2016年あたりからHaYによるものとみられる住民殺害事件が見られ始め、同年10月には350人ほどの集団が国境警備隊の拠点を複数襲撃し、銃数十丁と弾薬を強奪した(その後の国軍による捜索に伴い約10万人のロヒンギャ人がバングラデシュへと逃れており、2017年につながる難民流出となった)(高田2019:37-41;中西2021:136-141)。その後、ARSAと名を変えた同組織は2017年8月に大規模襲撃を実行する。
その攻撃はロヒンギャ人の村人たちも動員して実施された。ARSAおよびARSAに率いられた村人は、2017年8月24日深夜から数日間、ラカイン州北部の国境警察や国軍の施設を同時多発的に襲撃した。その数は30カ所以上に上るという。ARSAの兵士とみられる者は小銃で武装していたものの、村人たちはナイフやナタ、古い小銃など粗末な武器しか持っていないかった。彼らは政府施設を数百人で取り囲んだ。そうした施設には治安要員が常駐していたものの数百人に立ち向かうには数が少なすぎた。襲撃者たちはこうした施設から自動小銃や短機関銃、スタンガン、弾倉、手りゅうを略奪していったという(中西2021: 142-144)。武器が略奪されたことは、さらなる治安悪化の可能性を高める。国軍は危機感を強め掃討作戦に乗り出した。その掃討作戦で国軍は、ARSAの兵士が隠れる場所をなくすために、ロヒンギャ人の村々を次々と焼き払った。こうした掃討作戦が70万人以上という数の難民流出につながり、国境であるナフ河周辺は2㎞ほどの無人地帯ができあがった(日下部2019:20;高田2019: 41)。2017年の難民大量流出によって、ARSAの兵士もバングラデシュ側に流れた。それによりARSAの活動拠点はバングラデシュ側に移った。ARSAは2017年以降、難民キャンプの若者を徴兵してバングラデシュ領内で軍事訓練を行っていたとされる(中坪2019: 355-358)。
その一方、上述したもう一つの武装勢力RSOが台頭したのは、2021年にミャンマーでクーデターが発生した後のことである。クーデター後、ロヒンギャ人難民キャンプでは新たな勢力が台頭し、ARSAとの間で縄張り争いを始めた。そのうちの代表的なものがRSOである。RSOとは「ロヒンギャ連帯機構(Rohingya Solidarity Organisation)」のことで、この名前を持った組織は、もともとは1982年に結成され、1990年代には弱体化し消えたはずであった(結成は第三回エッセイで紹介する国籍法改正がきっかけであった)。そのRSOと同じ名を名乗る勢力が2021年クーデター後に現れ、軍事政権SAC(すなわち、国軍)と戦うことを表明した。旧RSOと新たに現れたRSOとの関係は明らかになっていない(ICG2025; Irrawaddy 2021)。その他にもいくつかの勢力が台頭したものの(ICG 2025)、ここではARSAとRSOだけを覚えておいてほしい。難民キャンプでは2023年あたりからARSAとRSOの抗争とみられる暴力事件が多発した。
2024年に入るとARSAやRSOは軍事政権SAC、すなわち、国軍と協力関係を結ぶようになる。このタイミングはラカイン人武装勢力AAが、ロヒンギャ人が多く住むラカイン州北部へと支配地域を広げようとしている頃であった。ラカイン州においてAAとの戦闘を続ける中、ミャンマー国軍は、そもそも国民とはみなされないロヒンギャ人を徴兵し、戦闘に動員した(国内にはまだロヒンギャ人が残っていた)。当初は強制徴兵が多かったものの、AAによる迫害が繰り返されたことで自主的に加わる者も増えたという(AAは支配地域を広げる中でロヒンギャ人に対する人権侵害を繰り返し、20万人のロヒンギャ人がバングラデシュへと流出した)(ICG2025: 4-6)。この頃、ARSAやRSOも国軍と協力するようになり、若者をミャンマーへと送り込むために難民キャンプでの徴兵を繰り返すようになった(ICG2024)。
我々が難民キャンプを訪れた2024年11月はそうした強制徴兵が横行している頃であった。10代の子供たちが「彼らは18歳になると迎えに来ます」といったのは、そうした背景があったのである。
強制徴兵によってキャンプに治安が悪化する
私たちが男の子たちに強制徴兵の話を聞いていたら、他の人たちも強制徴兵について話してくれた。家の中で話を聞いていたものの、その中には入れ代わり立ち代わり誰かがやってくる。家人もいるが、外国人がいることを聞きつけて覗きに来た人もいるようだ。そのうちの一人は強制徴兵について次のような語った。
徴兵を断って殺されたという話はよく聞きます。もうかなりの数の人が徴兵されてますよ。徴兵に適した人がいると、彼らは銃や武器を持って呼びに来るんです。
さらには徴兵がらみで親族が殺されかけたという者もいた。その親族は別のところに住んでおり、その者が目撃したわけではない。彼は聞いた話だといいながら、その時の様子を次のように語ってくれた。
家にARSAがやってきてたそうです。何人かで来ました。兵士になってミャンマーに行ってもらうと話したそうです。しかし、彼は「俺はやらない」と断固として断ったそうです。すると「じゃあ首を切ってやる」と脅されて刃物が出てきました。そしてどこか連れて行かれたそうです。もう少しで殺されるところだったそうです。幸い、隙を見て逃げだすことができたそうです。その後、「キャンプにいると殺されかねない」と彼はキャンプの外に住むことにしたんです。いまはキャンプの外で暮らしています。キャンプの中は危険だけれど、キャンプの外は安全です。
その前日、キャンプの外でベンガル人に話を聞いている時、キャンプ内では治安が悪化していると聞いたが、そういうことかと納得がいった(第1回のエッセイを参照)。強制徴兵に関わる暴力事件が増えているのだ。難民キャンプに住む若者だってやすやすと徴兵に応じるはずがない。
さらに治安の悪化にはARSAやRSOといった複数の勢力が縄張り争いをしていることも関わりがあるようだ。キャンプには、雑貨屋や軽食店、野菜や肉を売る店、ビンロウ屋などがある(ビンロウとは実を噛んで覚醒作用を得る嗜好品でミャンマーではよく見かける)。こうした店は難民たちがインフォーマルに運営しているものであり、難民キャンプの運営側に正式な許可を得ているわけではない。とはいえ新鮮な野菜や肉、ビンロウといった嗜好品などを難民たちが消費することを考えると公的な支援だけで暮らせるわけではないので、こうした商売は黙認されている。こうした店は、そのエリアをウラで支配する武装勢力に「みかじめ料」を支払っているという。縄張りは現金獲得につながるため武装勢力の縄張り争いも激しいものになる。それが治安の悪化する理由のひとつにもなっているという。


ちなみに難民への支援は基本的にはEバウチャー(カードにチャージする)で支給されており、公的な支援が現金でなされることはない。しかしながら、こうした店でのやりとりは現金のみである。難民たちも国外からの送金や、難民キャンプ外での労働で現金を得ている。
※ ※ ※
RSOやARSAなど武装勢力の状況を見ると、難民たちは隣国に逃れたからといって本国の政治と無縁になったわけではないことがわかる。2021年のクーデターによってミャンマーでは軍事政権が成立し、それに反対する勢力との間で戦闘が続いている。ロヒンギャ人難民たちはそうしたミャンマーの国内事情に翻弄されている。
男の子たちによると、キャンプでは、徴兵を逃れるためにも海外へと出稼ぎに出る者も少なくないとのことだった。「自分も徴兵をされないためには海外に行きたい」、彼はそう続けた。海外を目指すことは彼らにとって難民キャンプの生活から逃れる現実的な選択肢はひとつである。ただし、海外に渡るということは密航船に乗ることに他ならない。次の第三回目のエッセイでは、海外へ目指すロヒンギャ人たちについて記していきたい。
参考文献
International Crisis Group (ICG) (2014) Bangladesh/Myanmar: The Dangers of a Rohingya Insurgency, Brussels: International Crisis Group.
―― (2024) Breaking Away: The Battle for Myanmar’s Rakhine State, Brussels: International Crisis Group.
―― (2025) Bangladesh/Myanmar: The Dangers of a Rohingya Insurgency, Brussels: International Crisis Group.
Irrawaddy (2021) “Rohingya Armed Groups Active Again in Western Myanmar,” Irrawaddy, 20 September, https://www.irrawaddy.com/news/burma/rohingya-armed-groups-active-again-in-western-myanmar.html
笠原真 (2024) 「迫害逃れ、待っていたのは次の窮状 ロヒンギャ難民キャンプを歩いた」朝日新聞、12月4日、https://www.asahi.com/articles/ASSD20QXMSD2UHBI018M.html
日下部尚徳 (2019)「ロヒンギャ問題再燃をめぐる地政学」日下部尚徳・石川和雅編『ロヒンギャ問題とは何か』明石書店、14-36頁.
高田峰夫 (2019)「ロヒンギャ問題とアラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)」日下部尚徳・石川和雅編『ロヒンギャ問題とは何か』明石書店、37-62頁.
中坪央暁(2019)『ロヒンギャ難民100万人の衝撃』めこん.
中西嘉宏 (2021)『ロヒンギャ危機―「民族浄化」の真相―』中央公論新社.
深沢淳一 (2022)『「不完全国家」ミャンマーの真実』文眞堂.

近畿大学総合社会学部准教授