昨年12月、自衛官を退官して民間人となって初めて北京を訪問する機会を得た。今回の訪問は、日中国交正常化から半世紀を経てもなお、安全保障分野における日中間の認識ギャップがいまだに多く存在することを再認識する機会となった。ここにその一部を紹介したい。
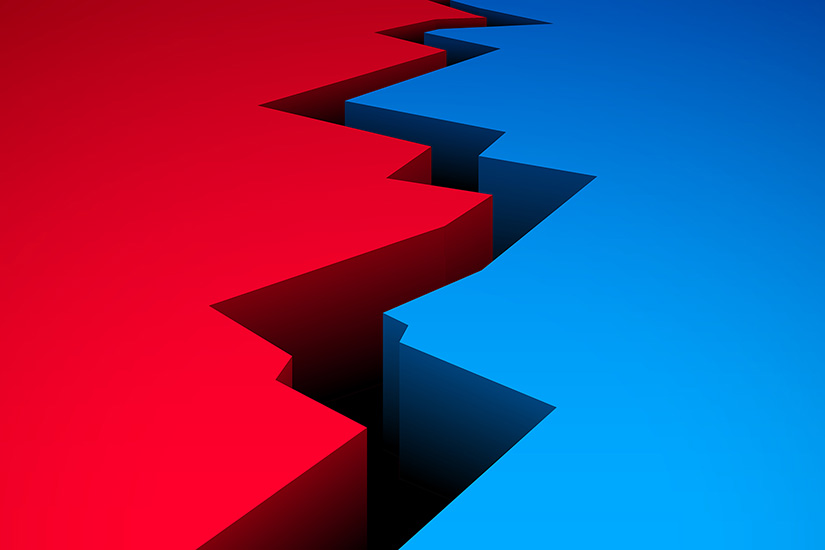
学会ではない中国国際戦略学会
今回の訪中は、笹川日中友好基金[1]が中国国際戦略学会(China Institute for International Strategic Studies, CIISS)から招請を受けたことに端を発したものである。
中国国際戦略学会は、各国の国防相や参謀総長等の参加を得て中国が実施している「中国版シャングリラ・ダイアログ」とも呼ばれる「北京香山論壇(シャンシャン・フォーラム)」[2]の主催団体の一つであり、地球規模の安全保障問題を取り扱う民間戦略研究団体と自称している[3]。
日本にも「国際安全保障学会」、「戦略研究学会」、「日本防衛学会」などCIISSと類似した名称の学会が存在する。そのため我々日本社会に暮らす者からするとCIISSもそれらと同様にその分野の研究者自身の運営によって学術研究活動を行う研究者の自発的組織であるに違いないと早合点しそうな組織ではある[4]。しかし、その実態が人民解放軍に付属する機関の一つであることはあまり日本では知られていない。CIISSのホームページを一見すれば明らかであるが、この組織は人民解放軍の現役の将軍が組織幹部を、管理スタッフ及び研究スタッフの大半を現役の人民解放軍将校が務める事実上の中央軍事委員会・聯合参謀部(旧総参謀部)の一機関である[5]。
CIISSは前述の「北京香山論壇」などを通じて外国の安全保障シンクタンクとの意見交換などの交流を主たる任務とする一方で、駐在武官等として国外に赴任予定の、あるいは帰任後、対外関係に携わる人民解放軍将校が国際情勢や戦略を学ぶ場としての役割を担っている。研究スタッフのほとんどが駐在武官等を経験した国外勤務経験者であり、各国の国防軍研究組織や退役軍人コミュニティとの窓口的役割も果たしている。
彼らは自身の機関が人民解放軍の一部であることを隠しているわけではなく、我々に正々堂々とかつ誇らしくその役割を紹介してくれる。このように明らかに人民解放軍に付属した機関であっても「民間の学術団体」であると自称できるところからも、中国は日本とは異なる価値観を有しており日中間には用語に対する認識ギャップがあることを窺い知ることができる。
「平和的解決」は恫喝によっても成就する
今回の訪中では、CIISSにおいて、総参謀部第3部長(いわゆる情報部長)や駐露、駐北朝鮮武官を経験した将軍、駐米や国連代表部を経験した将軍、軍備管理を専門とする駐イスラエル武官を経験した将軍などと議論した。またCIISSの仲介により国防大学では戦略教育研究部門の将軍などと議論した。
筆者は、これら議論を通じて「平和的解決」という用語に対して日中間に大きな認識ギャップがあるということを実際に認識することとなった。
南シナ海における沿岸諸国に対する中国の挑発的な行為や、台湾海峡周辺における軍事演習など攻勢的な中国の活動について我々から問題提起したところ、中国の行動態様が中国の目指す「平和的な解決」と何ら相反しないことを彼らは異口同音に繰り返した。
我々日本を含む国際社会の多くからみれば、自国の沿岸警備隊艦船に船体を衝突させるような中国海警艦[6]の攻撃的な行為[7]や、他国の排他的経済水域内にミサイルを撃ち込むような演習[8]は暴力的な恫喝であって決して「平和的」なアプローチであると看做すことはできない[9]。

しかし中国では、中国人民解放軍の中でも国際社会に明るい彼らでさえ、「軍事力を背景とした演習や強硬な姿勢を中国が示すことによって、相手が会議の席について解決を図ること」も「平和的解決」の一つであると考えていることが今回の議論を通じてあらためて明らかになったのである。
日本語では“deterrence”を「抑止(力)」と訳している。日本社会において安全保障の分野で「抑止」や「抑止力」からイメージするものは「攻撃されるのを予防する」[10]ために備えること、つまり侵略の未然防止であり「守り」の姿勢、平和的で防衛的な概念だと考えることが一般的である。一方の中国では、“deterrence”を「威懾(威嚇)」と訳している。今回、彼らの言から得たそのイメージは、防衛的であることばかりではなく、より攻撃的で恫喝的な概念をも含意していることが窺える。まさに “deterrence”を「威嚇」と訳す中国の姿を現していると言えよう。
2022年、岸田政権が新たな「国家安全保障戦略」及び「国家防衛戦略」によってスタンド・オフ防衛能力など、日本への侵攻そのものを抑止するために、いわゆる「反撃能力」を保有することが策定された。その際、中国はこのような能力を日本が保有することを「世界の反ファシズム戦争(第2次世界大戦のこと)の(連合国側の)勝利に対する甚大な破壊であるばかりか、歴史に対する尊厳と地域の平和に対する重大な侵害だ」[11]と厳しく批判した。
日本は侵略を未然に阻止するための「抑止力(deterrence)」だと思っているこの反撃能力を、おそらく中国は日本がこの反撃能力によって中国を「威嚇(deterrence)」するのだと考えたのだろう。“deterrence”に対する中国の行動の鏡、中国自身の行動態様に照らせば中国としては至極当然な帰結と言えるのかもしれない。
まとめに代えて
ミサイルの発射や相手の艦船への衝突など軍事力を使用して「威嚇」することも“deterrence”であり、そのような「威嚇」によって相手が中国の意図に従うことも「平和的解決」であると理解している中国と、そうした行動を「平和的解決」の手段であるとは理解できない我々との間には大きなギャップがある。
中国自身はまだ「平和的解決」の段階にあると考えて実施した行動が、相手には恫喝と映り、それが軍事力の行使(又はその直前)であるとの認識に基づく反応を招く状況は容易に発生しうる。我々から見れば、中国がエスカレーション・ラダーを上げたと映り、中国は我々がエスカレーション・ラダーを上げたと非難するだろう。相手の意図を読み間違えて戦争に至った悲劇は人類の歴史上数えきれない。
2007年に安倍総理と温家宝首相との合意によって協議が始まった「日中海空連絡メカニズム」において[12]、2023年にようやく日中防衛相間のホットラインによる初めての通話が行われた[13]。双方の意図を誤解なく理解してこのような認識のギャップを埋める必要性が高いことも実効性あるホットラインの運用が待たれるゆえんである。
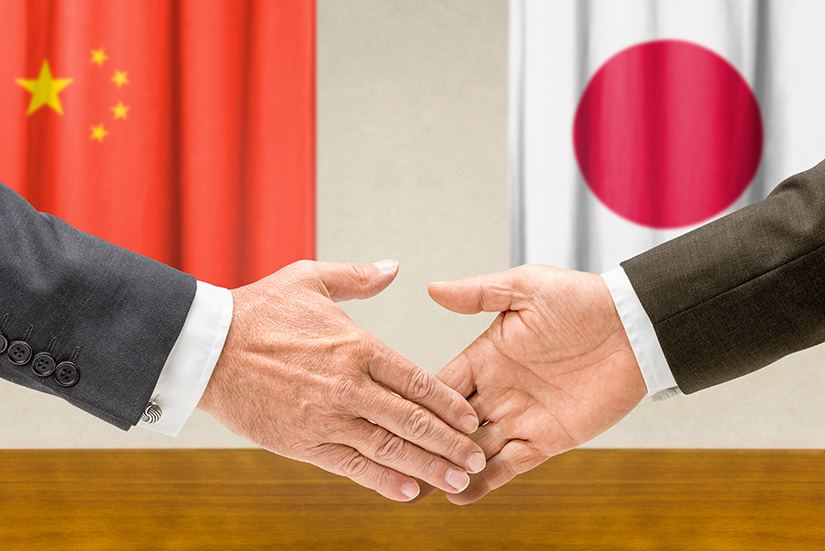
(2025/02/19)
脚注
- 1 笹川日中友好基金は、笹川平和財団の主要部門の一つであり、自衛隊と中国人民解放軍の次世代を担う現役佐官級に交流と対話の場を継続して提供し、相互理解を図るために2001年より防衛省と中国国防部の協力を得て「日中佐官級交流」事業を推進している 。 「日中佐官級交流事業:自衛隊佐官級訪中プログラムを実施」、笹川平和財団、2024年12月9日。
- 2 北京香山論壇(旧称香山論壇)は、アジア太平洋地域の安全保障に関するトラック2対話プラットフォームとして、2006年に中国軍事科学学会によって開始された国際会議であり、 2014年の第5回から1.5トラックに格上げされ、レベルと規模が大幅に拡大した。参加者はアジア太平洋地域内外の関係国の国防省や軍事指導者、国際機関の代表、元軍人や政治家、著名な学者などに拡大されている。 2015年の第6回以降は中国国際戦略学会が共催者に加わった。「论坛简介(論題紹介)」北京香山论坛、2025年2月17日アクセス。
- 3 「性质与宗旨(性質と設立趣旨)」中国国际战略学会、2025年2月17日アクセス。
- 4 日本における学術団体については「日本学術会議協力学術研究団体」日本学術会議、2025年2月17日アクセスを参照のこと。
- 5 「组织机构(組織機構)」中国国际战略学会、2025年2月17日アクセス。 名誉会長には現職を離れた元中央軍事委員会聯合参謀部副参謀長(大将、中将級)が、会長及び副会長には現職・元職の聯合参謀部参謀長助理または聯合参謀部情報部長(少将級)が充てられており、人民解放軍の作戦系の外郭機関であることがわかる。なお、中国では、現職を離れた、いわゆる定年退職した高級将校(退休軍人)は、現役当時に準じた礼遇と待遇及び必要に応じて軍服の着用などが認められている。
- 6 日本では中国海警の艦船を「中国海警船」や「中国公船」と呼ぶことが多い。しかし中国自身は、中国海警を軍隊(武警)の一部であり、中国海警の艦船を「〇〇艦」つまり軍艦(warship)と自称している。本稿では中国の主張に沿って「中国海警艦」と記述している。詳細は、拙稿「中国海警も中国共産党の軍隊である」国際情報ネットワーク分析IINA、2022年11月17日を参照のこと。
- 7 こうした行動については、たとえば、「フィリピン 中国と南シナ海で高まる緊張 防空能力も強化へ」NHK、2024年10月12日。
- 8 排他的経済水域は、領海とは異なる地位にあるため、他国の排他的水域を含む国際海域で実弾演習を含む軍事活動をすること自体が国際法に反しているわけではない。
- 9 たとえば、拙稿「中国ミサイル、日本のEEZ落下」が示す日本の盲点」東洋経済オンライン、2022年8月10日。
- 10 高橋杉雄「<視点>抑止力の意義」『令和6年版防衛白書』、2024年。
- 11 「日本构建“反击能力” 破坏地区安全(日本は地域の安全保障を破壊する「反撃能力」を構築)」中国军网、2022年12月9日。
- 12 “Japan-China Joint Press Statement (Provisional Translation),” Ministry of Foreign Affairs, April 11, 2007.
- 13 「日中防衛相間における『日中防衛当局間ホットライン』による初回通話の実施」防衛省、2023年5月16日。
