はじめに
「中国が6年以内に台湾へ侵攻する可能性が高まっている」[1]とフィリップ デービッドソン(Philip Davidson)前米国インド太平洋軍司令官が、今年(2021年)3月上旬の米国連邦議会上院軍事委員会公聴会で述べたことで、世界に衝撃が走った。その衝撃は、10月4日、中国が一日のうちに軍用機56機を台湾の防空識別圏(ADIZ)に侵入させた[2]ことで、現実を帯びているとの認識に至り、米、仏、欧州連合(EU)及びバルト3国の各議員団などによる台湾訪問が相次いでいる。また、日米を中心とする各シンクタンクなどが、台湾海峡有事を想定した事例研究やシミュレーションを行うなど議論が活発化している[3]。その事例研究、シミュレーション及び議論の軍事的安全保障に係る具体的な兵力分析は、ミサイル、空母、フリゲート、水陸両用艦艇、戦闘機・爆撃機、海兵隊などであり、機雷戦が登場する議論はほとんどない。議論にあったとしても「バシー海峡及び台湾海峡を機雷敷設と艦艇・潜水艦により封鎖する」程度である。第二次大戦後のほとんどの戦争及び紛争で機雷が登場している事実がある一方で、一般にはその認識は薄い。
そこで、本論考では、(前編)と(後編)の2回にわたり、(前編)では、なじみの薄い機雷戦の戦史を概観するとともにその特徴について述べ、(後編)で前編での考察を踏まえた台湾有事における機雷戦及びその機雷戦が日本に及ぼす影響について考察する。

1.機雷戦とは
機雷戦は、機雷を敷設する作戦である「機雷敷設戦」と、機雷を排除あるいは除去または回避する作戦である「対機雷戦」に大別されている。また、「対機雷戦」はさらに、機雷が攻撃対象としている船舶の発する様々な要素(音(スクリュー音やエンジン音など)、磁気(金属で建造されている船体の磁気)、水圧(航行することによって生じる水圧の変化)など)を感受して発火する武器であることを利用し、あたかも攻撃対象船舶が発するものと同じ要素を模擬して発することで機雷を騙して作動させる方法で処分する「機雷掃海」と、機雷を積極的にソーナーで探知し、無人水中ビークル(UUV : Unmanned Undersea Vehicle)、水中ロボット、および水中処分員などにより爆破処分する「機雷掃討」に分類されている。なお、2015年に成立、2016年に施行された平和安全法制関連2法の国会審議で使用されていた「機雷掃海」の用語は、ここで言う「機雷掃海」ではなく、「対機雷戦」を意味している[4]。
2.機雷戦史概観―近世から現代まで―
機雷の歴史は、16世紀、欧州において火薬をボートに搭載して使用したことが起源とされている。実際に水中で爆発した最初の例と言われているのは、米独立戦争時の1777年、米軍がフィラデルフィア沖に停泊していた英国艦隊に対して、火薬を詰めた樽を放流し、英国軍艦に当たり爆発、損害はなかったものの心理的な恐怖を抱かせたものである[5]。
機雷の組織的な使用が初めて行われたのは、日露戦争(1904∼1905年)と言われており、露軍の機雷により、日本は、戦艦「初瀬」、「八島」の沈没をはじめ多くの被害を受けた。一方の露軍も日本軍が敷設した機雷に触雷し、戦艦「ペトロパヴロフスク」が沈没、乗組員約500人とともに露軍太平洋艦隊司令長官のステパン・マカロフ中将も殉職した。この戦い後の1907年に機雷戦に関する唯一の国際法である「自動触発海底水雷ノ敷設ニ関スル条約」(ハーグ第8条約)が成立している。この条約は、今日、科学的・技術的能力が向上した機雷が現存するにも関わらず、成立以来114年経過してもなお改正や議定書の追加がなされていない[6]。これには、機雷の使用制限に係る修正・追加を避けようとする主要各国の思惑が伺える。仮にそうだとするならば、機雷を保有する主要国は、現代においても機雷を使用する意図が大いにあることを意味する。
第一次及び第二次大戦においても多くの機雷が使用され、例えば、終戦直前の日本近海には、日本軍による防御用機雷約5万5千個と米軍のB-29爆撃機及び潜水艦により敷設された約1万個の機雷が存在した[7]。戦後、連合国軍最高司令部(GHQ:General Headquarters)一般命令第一号には、日本に対する日本近海の危険海面を開放するための機雷位置等の完全かつ詳細な情報の提供と機雷除去の実施命令も包含されていた[8]。そして、一般命令第二号により、「日本国および朝鮮水域における機雷は、連合軍最高指揮官所定の海軍代表の指示により掃海を行うこと」[9]とされ、1950年10月4日、米国極東海軍司令官から日本の運輸大臣あて「日本の掃海艇による朝鮮海域での掃海に使用」の指令が下された[10]。なお、この対機雷戦により、日本の掃海艇1隻が機雷に触雷し沈没、乗組員1名が殉職(行方不明)している[11]。また海上自衛隊創設後の最初の任務は、日本近海の機雷の除去であった。
第二次大戦後においても、朝鮮戦争(1950∼53年)、ベトナム戦争(1965∼75年)、第三次・第四次中東戦争(1967・1973年)、印パ戦争(1971年)、イラン・イラク戦争(1980∼88年)、フォークランド戦争(1982年)、湾岸戦争(1991年)、イラク戦争(2003∼11年)をはじめ、国際法の議論を呼び起こしたコルフ海峡危機(1946年)、各国の内戦であるカンボジア内戦(1974年)、ニカラグア内戦(1984年)、クロアチア内戦(1991年)、スリランカ内戦(1991∼97年)、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦(1992年)、また、テロ的な敷設がされたスエズ湾・紅海触雷事件(1984年)、NATOの常設対機雷戦グループ(SNMCMG1/2:Standing NATO Mine Countermeasures GROUP ONE/TWO)創設のきっかけとなったアドリア海投棄兵器類の除去に従事したハーベスト作戦(1999年)など、多くの戦争、紛争及び内戦、テロ活動において機雷は使用されている。さらには、機雷を実際に敷設しなくても、機雷の敷設予告・宣言によって海上交通路等航行に混乱または影響を与えた米国ミシシッピ川での愛国スクーバダイバー危機(1982年)、イラン海軍司令官ホルムズ海峡封鎖発言(2011年)などがある。第二次大戦後の米国の具体的な被害状況について見ても、第二次大戦後の米海軍艦艇の全戦闘被害の75%は、機雷によるものであるとされている[12]。その代表的な例として、1988年のミサイルフリゲート「サミュエル・B・ロバーツ(USS Samuel B. Roberts:FFG58)」、1991年のイージス巡洋艦「プリンストン(USS Princeton:CG59)」及び揚陸艦「トリポリ(USS Tripoli:LPH10)」の触雷被害などがある。そして、今現在も約45か国が機雷を保有、約20か国で機雷を製造、約10か国が機雷を輸出するなど[13]、世界には100万個以上の機雷が存在すると言われている。また、その機雷を除去する対機雷戦兵力も海なし国を含め100か国以上の国が保有している[14]。

3.機雷戦の特徴
機雷戦史から伺える特徴については、「1.機雷戦とは」において述べた機雷戦のカテゴリーごとに、以下のとおり指摘できる。
(1) 機雷敷設戦
a. 費用対効果が大きい。
代表例として、米海軍ミサイルフリゲート「サミュエル・B・ロバーツ」の場合、機雷価格対艦の修理費は、1,500ドル対95ミリオンドル(約18万円対114億円)と言われている[15]。
b. 破壊効果が大きい。
ミサイルなどの空中武器に対して、機雷、魚雷などの水中武器は、衝撃波、バブル効果(膨張と収縮)及びジェット効果(ジェット衝撃)があり、破壊効果が極めて大きい。
c. 戦略的効果も期待できる。
機雷が敷設されているという情報のみによって海上交通路が遮断されるなどの心理的効果がある。また、実際に機雷が敷設された場合、海上交通が遮断されるなど経済への打撃も与える。そして、機雷敷設海域の海上交通が遮断されることにより、あたかもそこに陸地があるようなシー・ディナイアル(Sea Denial)を構築することができるなど、戦略的な効果が期待できる。
d. 柔軟性に乏しい。
機雷敷設後は、固定され、潜水艦のように海中を自由に動き回ることができないことから、柔軟性に乏しい。また、敷設後は、敷設前に設定した諸元(センサーの感度、航過係数、自滅時間など)から変更できないなどコントロール下から離れることとなる。
e. 敷設位置に制約を受ける。
機雷の性能、水深、潮流などにより敷設位置に制約が生じる。特に潜水艦を目標とする機雷敷設を除き、水上艦艇を目標とする場合、水深がある程度浅い海域に限定される。
(2) 対機雷戦
a. 海上交通の安全確認のため多くの労力と時間を要する。
機雷を排除、除去しなければ、艦艇を含む船舶の安全確保ができない。そして、最終的には、機雷がないことを確認できなければ、機雷の情報海域を迂回しなければならず、多くの労力と時間を要する。
b. 厳密な位置精度が要求される。
2メートル前後の機雷を処分するため、特に海底に埋没している場合はソーナーに反応する範囲は限られることから、1メートル以内の単位での位置精度が求められる。
c. 気象、海象の影響が大きい。
千メートル単位の機雷掃海具(ケーブル)または、機雷掃討のための水中ロボットなどを運用しなければならず、気象、海象に大きく左右される。
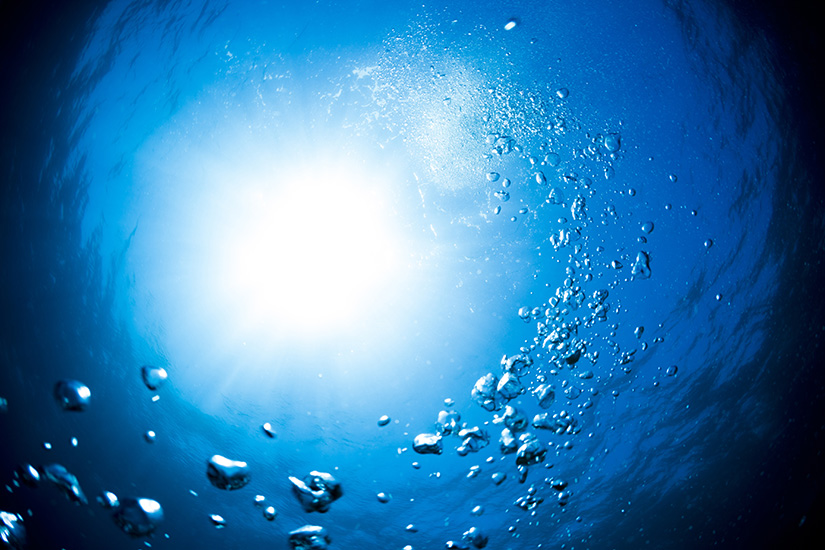
4.台湾有事における機雷敷設戦シナリオ
一般に刊行されている台湾有事における中国による機雷敷設戦に関しては、米海軍大学中国海洋研究所が2009年に発刊した「中国の機雷戦(Chinese Mine Warfare)」[16]が代表的である。この中で、中国が台湾に対して機雷を敷設する地理的選択肢として、港湾などを除き台湾本島の西側および北側としている。その理由として、台湾本島の南側と東側は、沿岸から急激に水深が2000mに達することから、機雷敷設に適さず、係維機雷と沈底機雷[17]は、通常、水深200m以浅で使用するから、としている[18]。
上記の選択肢に同意できる。その理由は、先の理由に加えて、台湾本島の南側から東側にかけては、黒潮の流れが速く、特に係維機雷の敷設には適さないからである。したがって、中国は台湾本島西側の台湾海峡の南北入口付近に機雷を敷設して、台湾及び台湾を支援する各国艦艇の侵入を阻止する機雷原を設定するとともに、台湾本島の西側及び北側に台湾軍艦艇の撃破を企図した機雷原を設定すると推察できる。一方、台湾は、台湾海峡を挟んで西側の金門島などの島々の付近及び台湾本島の西側及び北側の沿岸海域に防御機雷原を設定する可能性が考えられる。
この中台機雷敷設戦による日本への影響については、後編で考察する。
(2021/12/15)
*こちらの論考は英語でもお読みいただけます。
Mine Warfare in a Taiwan Contingency — Scenarios for Naval Mine Use and Its Impact on Japan
脚注
- 1 United States Senate Committee on Armed Services, “Open/Closed : United States Indo-Pacific Command,” Tuesday, March 9, 2021.(最終閲覧日:2021年11月25日).
- 2 「中国軍機の進入増批判「繰り返し地域の平和侵害」―台湾行政院長」時事通信社、2021年10月5日(最終閲覧日:2021年12月13日)他。
- 3 例えば、門間理良「第6章 台湾海峡有事における課題と方策」武田康裕編著『在外邦人の保護・救出―朝鮮半島と台湾海峡有事への対応―』東信堂2021年、227‐252頁。日本戦略研究フォーラム「台湾政策研究会政策シミュレーション(TTX:Table Top Exercise):徹底検証:台湾海峡危機 日本はいかに抑止し対処すべきか」2021年8月14・15日TTX開催。Chris Dougherty, Jennie Matuschak,Ripley Hunter, “The Poison Frog Strategy –Preventing a Chinese Fait Accompli Against Taiwanese Islsnds-,” CNAS, October 2021.(最終閲覧日2021年12月8日).
- 4 今後の国会審議等においては、「機雷掃海」ではなく、「対機雷戦」もしくは「機雷排除」、「機雷の除去」などの用語の使用が望ましい。
- 5 “Naval Mine Warfare,” Naval History and Heritage Command, 22 July 2007.(最終閲覧日2021年11月26日).
- 6 機雷に関する国際法の現代的考慮については、永福誠也「機雷の開発と使用に必要な考慮―国際法上の観点から―」防衛研究所『安全保障戦略研究』第1巻第1号、2020年(8月)。(最終閲覧日:2021年11月26日);塔筋一生「機雷戦に係る武力紛争法の適用法規に関する考察~ハーグ第Ⅷ条約は規制枠組みとして十分か~」防衛大学校安全保障研究科修士論文、2019年などがある。
- 7 掃海OB等の集い世話人会編『航路啓開史』改訂版、2012年、11頁。(最終閲覧日2021年11月26日)。なお、米軍敷設の機雷は、戦中に触雷あるいは日本軍が排除し、戦後残っていた機雷は、約6千5百個とされている。本史は、太平洋戦争終戦時から昭和 35 年 3 月 31 日までの日本における航路啓開の歴史を記したものであり、防衛庁海上幕僚監部防衛部において編纂され昭和 36 年 2 月 1 日に発刊された原本を書写し、再編集したものである。
- 8 Office of the Supreme Commander for the Allied Powers, “General Order No.1,” 2 September 1945,(連合国最高司令官総司令部 一般命令第一号 1945年9月2日)pp.5・6.(最終閲覧日2021年11月25日)
- 9 Office of the Supreme Commander for the Allied Powers, “General Order No.2,” 3 September 1945,Part2(Japanese Armed Forces 12∼14.)(最終閲覧日2021年11月29日).
- 10 掃海OB等の集い世話人会編『朝鮮動乱特別掃海史』改訂・追加版、2012年、13頁。(最終閲覧日2021年11月29日)。本史は、朝鮮動乱勃発から概ね 10年を経た時期に防衛庁海上幕僚監部防衛部において編纂され、昭和 36年 2月 1日に発刊された原本(発刊当時は「秘」に指定されていたが、2009年の指定解除により情報公開された。)を書写、改定・追加したものである。
- 11 同上、49-57頁。
- 12 Peter C Chu, “Unmanned undersea vehicle (UUV) for Navy’s science/technology and operations,” Naval Postgraduate School, November 2010,p.7.(最終閲覧日2021年12月13日); Committee for Mine Warfare Assessment Naval Studies Board, Division on Engineering and Physical Sciences National Research Council,“Naval Mine Warfare –Operational and Technical Challenges for Naval Forces (2001)-,”The National Academies Press,2001,pp19-24.
- 13 HIS,“Jane’s YaerBook Mines & EOD Operational Guide 17/18,”2018などを参考に筆者が算出。
- 14 HIS,“Jane’s YaerBook Fighting ships 17/18,“2018. などを参考に筆者が算出。
- 15 Peter C Chu, “Unmanned undersea vehicle (UUV) for Navy’s science/technology and operations,”p.8,(1ドル120円で計算).
- 16 Andrew S. Erickson, William S. Murray, Lyle J. Goldstein,”Chinese Mine Warfare: A PLA Navy' Assassin Assassin's Mace' Capability,” China Maritime Studies, No.3, China Maritime Studies Institute, U.S. Naval War College, 2009, pp.51-55,90-93.(最終閲覧日2021年11月30日)
- 17 係維機雷とは、海底に設置した錘(アンカー)からワイヤーなどを伸ばして浮力のある機雷缶(センサー、炸薬あり)を係止している機雷である。通常、目標とする船舶の船底を狙うため、水面下で船舶の喫水の深さに調定されている。例えば、水深200mの場所で喫水10mの船舶を狙う場合、ワイヤーの長さは190m程度となる。潮流がある場合には、さらに調定が難しくなると同時に、ワイヤーが切れて機雷が浮流する可能性も高くなる。また、係維機雷は深々度の水深においても敷設可能な機雷も存在すると言われている。沈底機雷とは、海底に鎮座させた機雷である。したがって、水上船舶を目標とする場合、ある程度水深が浅くなければ、威力を発揮しない。
- 18 Erickson, Murray, Goldstein, ”Chinese Mine Warfare,”pp.90-93.
