歯止めのかからない感染増
1年前の総選挙で圧勝し、続投を決めたインド・モディ政権が大きな試練に直面している。新型コロナウイルス感染症への対応が遅れたというわけではない。むしろ対応は早く、過剰ではないかとみられたほどであった。3月半ばまでにはすべての外国人の入国を停止する措置をとり、3月25日には、全土のロックダウンを発表した。感染者数がまだ536名にすぎなかったにもかかわらずだ。
ロックダウンは諸外国と比較しても、きわめて厳格に行われた。にもかかわらず、これ以降、インドの感染者数は増加の一途を辿る[1]。ロックダウンはなんと3度にもわたって延長され、ようやく6月から段階的に解除されたものの、このときにはすでに感染者数は19万人に達していた。その後の経済活動の再開とともにその数はさらに増え、6月半ばの時点で40万人超となり、世界で4番目の感染国となってしまっている。政府が主張するように、たしかに13億人という人口規模の大きさに鑑みれば、感染者数も死者数も欧米に比べると抑制されているようにはみえる。しかし人口あたりのPCR検査率は、日本と同様に低く、実際にはもっと多くの感染者が潜んでいるものと推測される。もともと「ソーシャル・ディスタンス」とは無縁の社会であることや、ひとびとが密集して生活するスラムの存在を考えれば、ロックダウンの効果にはおのずから限界があった[2]。
しかも2カ月以上の長期にわたるロックダウンは、もともと低迷気味であったインド経済に深刻な打撃を与えた。世界銀行は2020年度のインドの経済成長率予測を、5.8%からマイナス3.2%にまで、大幅に引き下げた[3]。
イスラーム教の集会でクラスターが発生したとされたことを受けてヒンドゥー・ムスリム間の宗教対立が深まったほか、デリーやムンバイなどの出稼ぎ労働者のほとんどが職を失い、社会不安も広がっている。

45年ぶりに犠牲者を出した印中国境問題
このモディ政権を襲ったのが、先に新型コロナを「制圧」したとする中国の攻勢である。世界がコロナ対策に追われるなか、習近平政権が、香港、台湾、東シナ海、南シナ海で、その自己主張を強め、強硬姿勢や軍事行動を活発化させていることは知られているが、それだけでなく、5月に入るとインドとの陸上国境でも同様の動きを見せ始めた。印中間では1962年に国境戦争が戦われたように、陸上国境のおよそ半分近くの領有権問題が解決していない。両国間では、1993年に実効支配線(LAC, Line of Actual Control)の尊重と現状維持を図る合意が成立し、その後さまざまなレベルでの信頼醸成措置(CBMs)が積み重ねられてきた。その結果、印中間では、相手の「侵入」行為を非難し合ったり、双方の部隊が対峙するなどの、小競り合いが起きるといったことはあったものの、武力紛争に至ることはなく、「管理されたライバル関係[4]」が続いてきた。インドのもうひとつの敵対国パキスタンとの間で、カシミールの管理ライン(LoC, Line of Control)を挟んで銃撃戦と死傷者が日常的に繰り返されてきたのとはまったく対照的である。
ところが、今回、6月に起きた衝突は45年ぶりに死者を出す事態にまで発展した。まず5月上旬、インドのラダック連邦直轄領、ならびにシッキム州が中国側と接するLAC沿いの数カ所で、両国の兵士が殴り合うなどの小競り合いが立て続けに発生し、双方に負傷者が出ていることが報じられた[5]。しかしこのレベルの「喧嘩」であれば、これまでにもなかったわけではない。双方がCBMsに基づき武器を用いないことで、いずれ解決し、エスカレーションは避けられるものと考えられた。
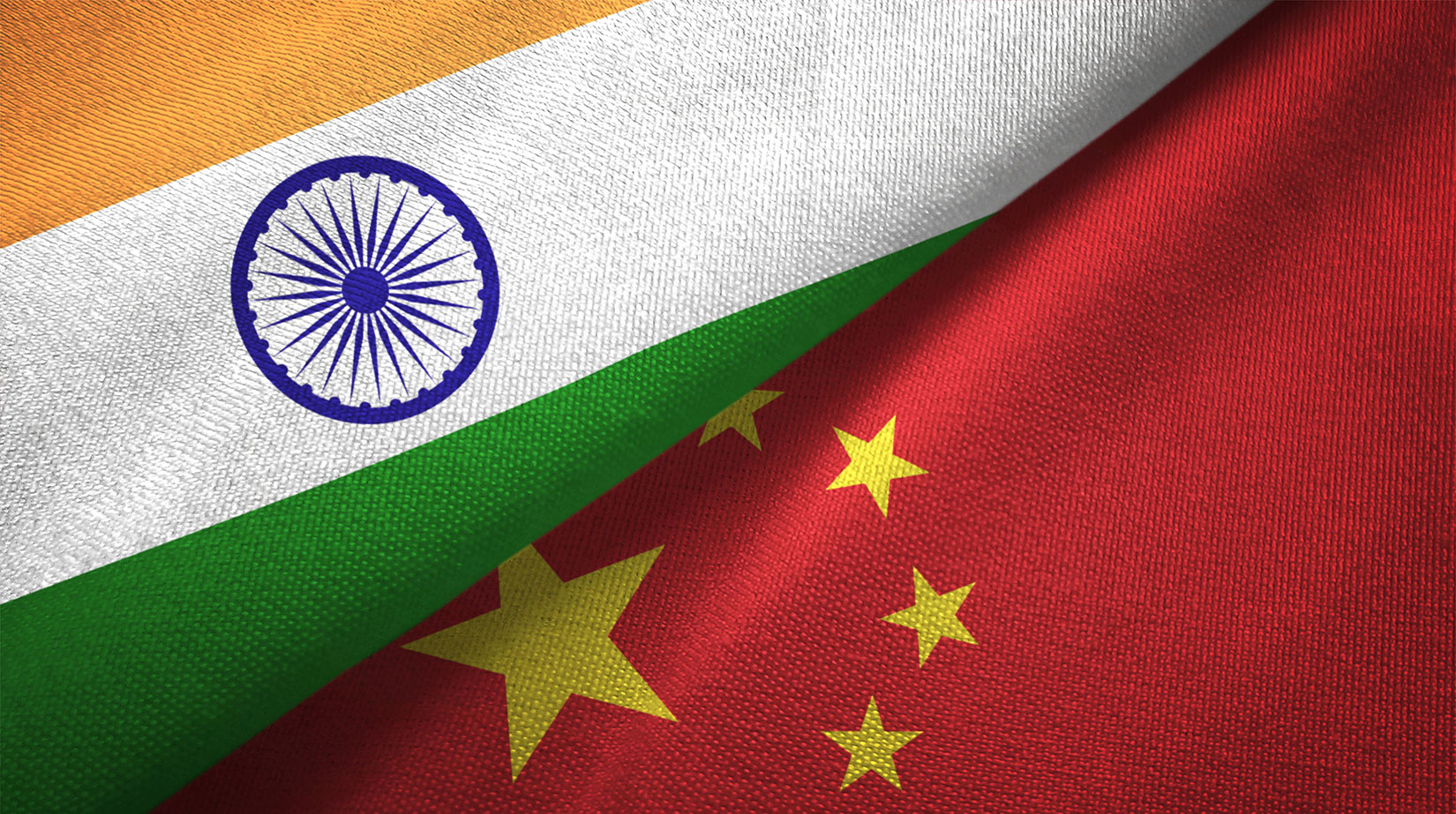
実際のところ、インドのラージナート・シン国防相は、いわゆる「侵入」行為はLACに対する双方の「認識の違い」に起因するものだという従来の政府の立場を表明して、緊張をプレイダウンする意思を明確にした。そして対話による解決を探っていることを強調した。6月上旬には外務省局長級、軍中将級の協議などが立て続けに開かれ、前線からの「部分的な撤退」に双方が合意したと報じられた[6]。
しかしこうした事態沈静化に向けたハイレベルの合意にもかかわらず、「認識の違い」のあるLACをめぐる現場での「せめぎ合い」は、いくつかの地点では、もはや抜き差しならないほど激しいものになっていたようだ。事件の舞台となったのは、インドのラダックと中国が実効支配するアクサイチンの間の、ガルワン渓谷である。6月15日の夜から16日未明にかけて発生した同地の双方の部隊の衝突で、インド側の死者数は20名に達した[7]。当局はいっさい公表していないが、中国側にも犠牲者が出た模様である。発砲はなかったとされているにもかかわらず、なぜこれほどの惨事となったのだろうか。インド国内のこれまでの報道を総合すると、今回の衝突は部隊の撤退過程で、インドの部隊が中国側の撤退状況を監視していたところ、中国の部隊が石や棒をもって、さらにはせき止めていた小川を一気に放水して襲撃してきたという。多くの兵士は渓谷に投げ出され、発見と救援が始まったのは明朝以降になってからであった。ガルワン渓谷はヒマラヤの標高4300メートルに位置する高地で、この時期でも夜の気温は氷点下近くになるという。こうした事情が、被害を大きくしたと考えられている。

中国はなぜいまインドに攻勢をかけるのか?
インドの有識者は中国側の攻勢の真意を測りかねているようにみえる。従来からの「貿易戦争」だけでなく、新型コロナウイルスの起源と拡散の責任、香港問題などをめぐって米中関係がいっそう悪化し、「新冷戦」へ向かいつつあるともいわれるいま、中国は普通に考えればインドを敵には回したくないはずである。国境問題で事を荒立てれば、インドを日米豪などを軸とする「インド太平洋」の側に追いやり、「中国包囲網」の形成を許すことになりかねない。そんなことは誰しも想像がつく話だからである。現にこの危機の最中、米国務省のアリス・ウェルズ国務次官補代理(南・中央アジア担当)は、印中の緊張について中国側が脅威を突きつけていると明言するとともに、コロナ後の世界では各国が脱中国を図り、サプライチェーンを多様化しようとするため、インドに大きなチャンスがあると述べた[8]。トランプ大統領も秋に延期された米国でのG7サミットにモディ首相を招きたいなどと秋波を送った[9]。オーストラリアのモリソン首相も、モディ首相とのテレビ首脳会談で両国の関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げ、日米との間で始めたのと同じ閣僚級2プラス2を設置すること、相互の基地へのアクセスを可能にする相互後方支援協定などを結んだ。
それでも中国がインドに対し、国境問題であえて攻勢をかけるのはなぜなのか。もちろん、根底には、LAC沿いのインフラをめぐる双方の警戒感がある。モディ政権は、これまで中国側と比べて立ち遅れていた道路建設を積極的に進めてきた。それは有事の際の前線への動員を容易にするものであり、双方とも相手の建設は阻止したいと考える。政治・外交的には、昨夏、モディ政権が発表したジャンムー・カシミール州の憲法上の特別な地位の停止と同州の2分割・直轄統治領化に対して、パキスタンだけでなく中国も係争当事国として、「一方的な現状変更」に抗議していた。さらには、強化されつつある「日米豪印」枠組みへの反発もあったであろう。しかしこれらの要因は、なぜ「いま」なのかを説明するものではない。
シャム・サラン元外務次官は、中国の行動の背景には、コロナ禍で米国の力が衰退するのに対し、自らのほうが早く回復し、世界における影響力を拡大できるチャンスだという過剰なまでの自信と、新型コロナを世界に蔓延させた責任を世界から問われかねないという不安感が、その強硬な姿勢につながっており、インドに対しても例外ではない、と論じる[10]。またネルー大のハッピモン・ジェイコブは中国が米国からの圧力に耐え、そのなかでも自らがインドに圧力を加える手段をもっているというメッセージを印米に伝える狙いではないかとの見方を示している[11]。いずれにせよ確証はないものの、インド国内では、計算し尽くされた中国の戦略的な行動とする見方が支配的であり、「偶発的」事件とは受け止められていない。中国製品へのボイコットなど反中感情は、メディアにおいても新型コロナに対する政府批判の声をかき消すほどにまで高まっている。今後モディ政権は中国企業の締め出しなど、経済的な「報復措置」を強めるものと思われる。

インドはどうすべきか?
そこでインドとしては、コロナ後の世界も睨んで日米豪などと連携をいっそう強化すべきだという声が強まるのは当然であろう。英印で活躍する戦略家のハルシュ・パントは、インドとしては民主主義陣営の側につくべきだと明言する[12]。しかし「伝統的」思考様式も依然根強い。前国民会議派政権で国家安全保障顧問を務めた経験をもつM.K.ナラヤナン、ジヴシャンカール・メノンは、米中対立の悪化を予測しつつも、インドがどちらかの側につくことは得策ではなく、安易に中国叩きに乗るべきではないと警鐘を鳴らしている[13]。しかし、インドが今後も米中間で「スイング国」として振る舞い、その「戦略的自律性」を維持し続けることができるかどうかは、モディ政権が今回のコロナ危機で露呈した国内の社会経済矛盾を克服し、再び成長軌道に乗せることができるかどうかにかかっている[14]。直面する新型コロナ問題と中国の攻勢という2つの危機にどう対処するのか、インドは岐路に立たされている。
(2020/06/25)
*この論考は英語でもお読みいただけます。
India at a Crossroads – Combatting the Coronavirus and the Chinese Offensive
脚注
- 1 法的強制力のあるロックダウン措置をとった10カ国のうち、1カ月後に新規感染者数が減少に転じなかったのは、インドとロシアだけであるという。しかもオックスフォード大学の研究によれば、インドのロックダウンは10カ国のなかで最も厳格なものであったとされている。
Shreya Raman, “Within a Month of Lockdown, New COVID-19 Cases Dipped in 8 Countries, But Not India,” The Wire, May 3, 2020. - 2 Jyoti Shelar, Ajeet Mahale, “Coronavirus in Dharavi | When a virus finds space in India’s largest slum,” The Hindu, May 9, 2020.
- 3 Gaurav Noronha, “India's economy to contract by 3.2 per cent in fiscal year 2020-21: World Bank,” The Economic Times, June 8 2020.
- 4 T.V.Paul,“Explaining Conflict and Cooperation in the China-India Rivalry,” in T.V. Paul ed., The China-India Rivalry in the Globalization Era, Orient Blackswan, 2019, p.6.
- 5 Dinakar Peri, “Indian, Chinese troops face off in Eastern Ladakh, Sikkim,” The Hindu, May 10, 2020.
- 6 “LAC row with China | Efforts on to resolve situation at earliest, says India,” The Hindu, June 11, 2020.
- 7 Dinakar Peri, Suhasini Haidar, Ananth Krishnan, “Indian Army says 20 soldiers killed in clash with Chinese troops in the Galwan area,” The Hindu, June 16.
- 8 “Post-coronavirus world provides window of opportunity to India: Wells,” The Hindu, May 21, 2020.
- 9 Kallol Bhattacharjee, “Donald Trump invites Narendra Modi for G-7 summit in U.S.,” The Hindu,” June 2, 2020.
なお、トランプ大統領はおそらくは、反中国、インド支持を打ち出す趣旨で、5月27日にツイッターで印中の「仲介」を申し出て、その後、モディ首相からも中国との関係に苦慮していると言われたとまで明かした。しかしこれは逆にインド側を当惑させる結果となった。印外務省は、そもそもこの危機が始まって以来、モディとトランプの接触は電話を含めてまったくなかった、と発言内容を完全否定した。 - 10 Shyam Saran, “China’s aggression against India, Hong Kong, US comes from sense of siege on pandemic origin,” The Print, June 1,2020.
- 11 Happymon Jacob, “In Himalayan staredown, the dilemmas for Delhi,” The Hindu,, June 4, 2020.
- 12 Harsh Pant, “The China challenge: In the evolving geopolitical dynamic after Covid, India should side with democracies,” The Times of India, June 16, 2020.
- 13 M.K. Narayanan ,“Remaining non-aligned is good advice,” The Hindu, June 16, 2020.Nayanima Basu, “Covid-19 different from Tiananmen, China won’t be able to tide over crisis: Ex-NSA Menon,” The Print, May 7, 2020.
- 14 Pranay Kotasthane, Akshay Alladi, Anirudh Kanisetti, and Anupam Manur, “Executive Summary: Takshashila Discussion SlideDoc: India in the Post COVID-19 World Order,” The Takshashila Institution, May 7, 2020.
