はじめに
インド太平洋地域では、多国間安全保障の制度的枠組みが構造的に未成熟なままである。欧州では、NATOによる集団的防衛体制と、OSCEの危機管理・信頼醸成が連携する多層的な安全保障アーキテクチャが確立されている。一方で、この地域では米国との二国間同盟が軸となる「ハブ・アンド・スポーク型」の安全保障構造が長らく続いており、複雑化する地域の脅威に多国間で対応する制度は不十分である。
ASEAN地域フォーラム(ARF)[1]は信頼醸成に貢献しつつも、合意形成依存と実行権限の欠如により限界がある。QUAD(4か国戦略対話)も戦略的整合性はあるが、非拘束的・非制度的であり、実務レベルとの間にギャップが残っている。
このギャップは、北朝鮮に対する国連安全保障理事会決議(UNSCR)[2]の履行において特に鮮明である[3]。2006年以来続く制裁にもかかわらず、北朝鮮は瀬取り(STS)[4]や船舶の識別情報の偽装といった手口で制裁をくぐり抜けている。これら海洋上の慣例に反する行為は、地域的な制度的執行体制の欠如と、既存の多国間枠組みの運用上の権限の制限を巧みに利用している。
この課題に対応するため、同志国群(日本、米国、韓国、豪州など)は、横須賀にECC(Enforcement Coordination Cell)を設置した[5]。2018年に米海軍ブルーリッジ(USS Blue Ridge)[6]艦上で始まり、2022年に常設の機関として本格化したECCは、機能的ミニラテラリズム(functional minilateralism: FM)[7]という新たな協力モデルの実践例といえる。このモデルは、法的拘束力を伴わない、一般に正式な多国間枠組みよりも小規模な[8]、柔軟かつ実利的な協力形態を意味する。
ECCは現在、12の加盟国(日本、米国、韓国、豪州、欧州諸国等)から構成されているが参加国数に上限はない、柔軟な構造を有している[9]。類似の事例として、シンガポールの情報融合センター(Information Fusion Centre)[10]やスールー海におけるインドネシア・マレーシア・フィリピンによる三国合同パトロール[11]があるが、ECCは常設の多国籍海軍司令部へ組み込まれ、国連制裁執行という明確な課題への特化という点で際立っている。
ECCはリトアニア国防大臣の2025年4月の訪日を機に再注目された。この訪問では防衛省や米第7艦隊司令部での意見交換[12]も行われ、同時期にリトアニアは太平洋海洋安全保障交流(PSMX)[13]への参加を果たし[14]、ECCが地域の海洋秩序において重要性を高めていることを示した。
本稿では、ECCがどのように正式な条約や協定なしにリアルタイム協力を可能にし、既存の制度的空白を効果的に補完する運用上の革新性を発揮しているのかを分析し、海上制裁執行への貢献と、インド太平洋における他の多国間枠組みとの補完関係における将来的価値を探る。

運用枠組み
ECCは、法的拘束力を持たないものの、実務的な制裁執行調整の中核として機能している。国連安保理決議(UNSCR)1718[15]、2270[16]、2375[17]、2397[18]などは、北朝鮮への武器、贅沢品、精製石油製品の輸出を禁じているが、海上における制裁執行は断片的であり、各国が自発的に対応しているのが現状である。
このギャップを埋めるために、ECCは、日米韓豪などがリアルタイムで海上監視情報を共有し、哨戒スケジュールや艦艇等の展開を調整できる仕組みを提供している。哨戒任務は通常運用と制裁監視を兼ねることもあり、専用部隊を必要とせず、各国が効率的に貢献できる体制となっている[19]。これにより、限られた資源でも効果的な制裁監視が可能となっている。
ECCは、米海軍第7艦隊司令部(横須賀)に拠点を置き、広域的には米インド太平洋軍(INDOPACOM)の傘下に位置づけられているものの、中央集権的な運用権限は持っていない[20]。各国は、共有情報に基づいて行動するか否かの主権的判断を保持しており、超国家的な命令系統は存在せず、あくまで自主的な調整と情報共有を基盤としている。
ECCの活動は、多国間制裁監視チーム(Multilateral Sanctions Monitoring Team:MSMT)による取り組みによっても補完されている[21]。MSMTは制裁違反の最前線監視と報告の統合を担っており、ECCとの間に公式な制度的連携は明文化されていないものの、メンバーと目的が重複していることから、機能的な相乗効果が生まれているといえる[22]。
さらに、ECCは大量破壊兵器拡散防止構想(Proliferation Security Initiative: PSI)の一環であるPSMX演習の計画および行動調整にも主要な役割を果たしている[23]。これらの演習は、相互運用性の向上、手順の検証、実務的協力の強化を目的としており、ECCの調整機能の制度化をさらに後押ししている。
制度的意義
ECCは、FMの一例といえる。これは、能力を持ち、少数の同志国による、目的重視の安全保障協力の枠組みを指す。NATOのような条約に基づく正式な同盟や、ARFのような対話中心のメカニズムとは異なり、ECCは法的拘束力を伴わずに、実務的な制裁執行の成果を生み出すことを目的に構築された。本モデルには以下の3つの制度的な強みがある。
1. 実利的な柔軟性
参加国は自発的に関与し、各国の優先順位に応じて能力を提供する。これにより、厳格な制度的手続きに縛られることなく、海上監視や制裁執行において柔軟かつ段階的なアプローチが可能となる。
2. 運用重視
多くの地域枠組みが対話や信頼醸成に重点を置くのに対し、ECCは日々の調整や共同監視といった実務活動を軸としている[24]。この運用面での基盤は、言葉だけの約束に留まらず、実際の共同活動を通じて信頼を醸成し、説明責任の強化にもつながるものである。
3. 補完性
ECCは既存の多国間枠組みを代替するものではなく、それを補完する役割を果たす。特に、より広範な枠組みではマンデートや運用能力が不足しがちな海上での国連制裁執行という機能的なギャップを補っている。
こうしたECCの非公式な制度設計は、新規加盟国や新たな運用手法の柔軟な受け入れも可能にしている。例えば、リトアニアが最近PSMX枠組みに加わり、ECCに関与を深めた事例は、たとえ域外国であっても海上制裁の実務に貢献できることを示している。
このような柔軟性は、地理的近接性よりも共通の機能的必要性に基づいて連携が形成される傾向が強まるインド太平洋の安全保障環境に合致しており、ECCの制度設計がその動的変化に適応していることを示している。
具体的成果と戦略的インパクト
ECCは設立以来、海上監視の強化と集団的モニタリング支援を通じて、北朝鮮に対する関連安保理決議の制裁執行努力に具体的な成果をもたらしてきた。中でも、多国間による監視活動および情報共有を通じた海洋状況把握(Maritime Domain Awareness:MDA)の向上は、最も顕著な成果のひとつである。防衛省によれば、ECC参加国は、2023年以降、STSによる違法行為が疑われる船舶を対象とした継続的な監視活動を実施している[25]。
1.日本主導による国際協力の推進
日本は、ECCとの連携のもと、P-1哨戒機[26]や海上保安庁の巡視船[27]を展開し、監視活動を主導してきた。また、衛星画像の分析でも情報の集約・配信における中核的な拠点としての役割を果たしている。こうした基盤の上に、英独仏加などの参加国が人員や装備を提供することで、ECCの活動範囲と国際的な支持拡大が推進されている。
2.国連専門家パネルに対する間接的な支援を通じた監視活動の信頼性向上への寄与
ECCで得られた情報が、2024年4月に解散した国連の北朝鮮制裁専門家パネルの年次報告書に活用されていた点がある。STSの違法行為や、北朝鮮関連船舶による船籍偽装(アイデンティティ詐欺)といった事例の多くは、ECC主導の監視活動によって初めて認知された。こうした証拠は、制裁回避手段への国際的認識を高め、関与船舶を知らずに受け入れている国々への外交的働きかけにも活用されている。
3.柔軟なモデルによる地域・超地域的な連携強化への波及的影響
ECCの枠組みは、当初の想定を超えた国際連携の促進にも寄与している。たとえば、リトアニアがECC主導のPSMX演習に参加し、日本との外交的関与を深めた事例は、ECCが地域横断的な協力の触媒として機能しうる可能性を示している。
総じて、ECCは単なる制裁回避監視の実務的枠組みにとどまらず、国際規範の形成、連携の拡大、大量破壊兵器の不拡散体制への情報支援といった戦略的側面でも重要な役割を果たしている。

課題と今後の展望
本章では、前章で述べたECCの制度的特徴と運用上の成果を踏まえ、現行体制の限界を明らかにするとともに、将来に向けた改善の方向性を提示する。ECCは運用面・戦略面で顕著な成果を挙げてきたものの、制度的および地政学的な課題から制約が存在する。ECCを信頼性のある制裁執行メカニズムとして維持・拡張し、将来的な多国間協力のモデルとするためにはこれら課題への対処が不可欠と言える。
-
1. 負担分担の偏りと資源コミットメントの限界
ECCの最大の課題の一つは、情報収集や装備展開において日本・米国への依存が強い点である。NATOのような中央集権的な枠組みがないため、ECCは自主的な協力に基づいて運用されており、他国の人的・政治的貢献があっても運用面での非対称性が共同所有意識や持続可能性を損なう恐れがある。これに対しては、NATOの「スマート・ディフェンス」構想 を参考に、輪番制の監視や技術支援を含む柔軟な資源共有の枠組みを導入し、参加国全体の関与を促すべきである。
-
2. 係争海域における法的・政治的曖昧性
ECCには法的権限がなく、参加国は外交的圧力や軍事的嫌がらせのリスクに晒されている。中国によるECC関連哨戒活動への監視・追尾[29]や、北朝鮮との海洋取引を通じたロシアによる制裁回避行動がその一例である[30]。こうした状況には、ECCの機動性を保ちつつ正統性を高めるため、匿名報告の発出や国連制裁監視機関との非公式連携が有効であり[31]、Track 1.5やTrack 2の静かな外交も摩擦緩和に寄与し得る。
-
3. 政治的意志と制度的継続性の脆弱さ
ECCは条約に基づく制度がなく、参加国の政治的意志に強く依存しているため、政権交代などで支持が揺らぐ可能性がある。この脆弱性への対応として、年次閣僚会合や共同声明などの柔軟な運営体制の導入が望まれる。また、PSMXとの統合により継続性を確保しつつ、QUADとはMDAなど特定分野での協調を検討すべきである。
-
4. より広範な地域協力への潜在力の未活用
ECCは先進民主主義国中心で、東南アジアやグローバル・サウスとの関与が限定的である。しかし、制裁執行には地域の港湾・空域の協力が不可欠であり、ASEAN諸国などとの連携強化が重要となる。能力構築や技術交流を通じたアウトリーチの拡大に加え、パートナー国・オブザーバー国枠の導入により、地域的包摂を促進できる。
結論
ECCは、北朝鮮制裁の「執行ギャップ」に対応する柔軟な協力モデルとして注目されており、同盟の形を取らずとも信頼と共通目標に基づき、課題特化型の枠組みで成果を挙げている。直接的な取り締まりよりも、海洋状況把握の向上や国連監視支援など戦略的な貢献を主要な役割としており、これはFMの成功例といえる。
今後は、参加国拡大や主導国依存の軽減、持続可能な制度設計が課題であり、QUADやARFを補完する柔軟な運用プラットフォームとしての役割が期待される。さらに、IUU漁業[32]や大量破壊兵器不拡散など非伝統的安全保障分野への応用も可能であり、ECCはインド太平洋のルール形成に資する重要な協力枠組みとなり得る。
総じてECCは現代の複雑な安全保障環境に適応した、柔軟で成果思考のミニラテラリズムの稀有な例と言える。その今後の深化は、自由で開かれた、ルールに基づくインド太平洋の構築を目指す政策立案者・研究者などにとって、注目に値する動向といえるだろう。
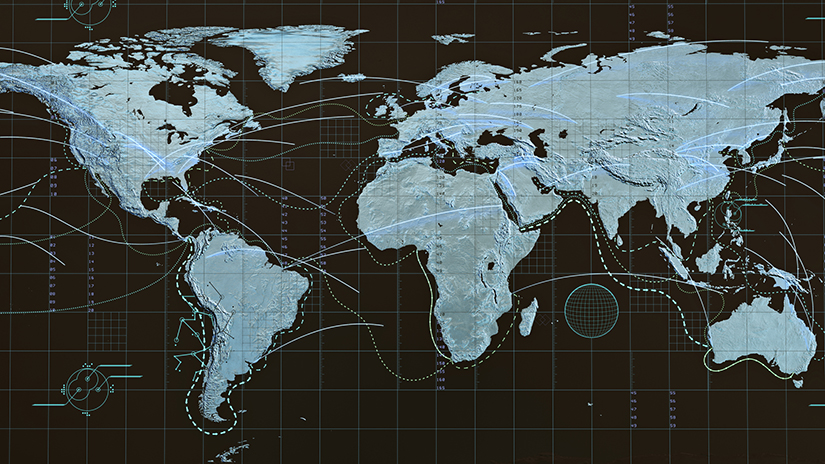
(2025/09/05)
*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。
Bridging Sanctions Gaps: The Enforcement Coordination Cell (ECC) in Yokosuka and Minilateral Maritime Cooperation
Notes
- 1 松卓馬「インド太平洋における信頼醸成の背骨:ARFは地域緊張を緩和できるか?」笹川平和財団IINA、2024年3月28日。
- 2 国連安保理決議1718(2006年)は、北朝鮮の核実験に対応して武器および贅沢品の貿易を禁止する初の制裁を導入した。United Nations Security Council. “Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006).” Accessed June 13, 2025.
- 3 これらの制裁は、北朝鮮の弾道ミサイル発射および核活動に対する対応であり、その核・ミサイル開発を抑止することを目的としている。
- 4 Reza Kapo. “Ship-to-Ship Transfer Operations: Safety and Emergencies.” Seably, Accessed June 13, 2025.
- 5 ECCは、米海軍横須賀基地内に設置されている。
- 6 ブルーリッジ(LCC-19)は、横須賀を拠点とする米第7艦隊の旗艦である。
- 7 この用語自体は、特定の既存の資料から逐語的に引用されたものではないが、インド太平洋における新たな安全保障の実践に関する著者の概念的な解釈を反映している。See also Bhubhindar Singh and Sarah Teo (eds.), Minilateralism in the Indo-Pacific, Routledge, 2020, pp. 3–6. Yirga Abebe Damtie, “From Multilateralism to Minilateralism,” Wilson Center, October 16, 2024.
- 8 タン・シー・センは、ミニラテラリズムが通常は少数の国家(例えば3〜5か国)による枠組みを指すものの、固定された数があるわけではないと論じている。Singh and Teo, Minilateralism in the Indo-Pacific, pp. 3–6.
- 9 ECCには、現在12か国(米国、日本、豪州、韓国、フランス、ドイツ、カナダ、英国、オランダ、イタリア、ニュージーランド、リトアニア)が参加している。Burns, Shannon. “U.S. 7th Fleet ECC Visits Partner Nations, FS Tonnerre.” Commander, U.S. 7th Fleet, June 16, 2021.
- 10 IFC(インフォメーション・フュージョン・センター)は、シンガポール海軍が運営する海上安全保障の地域拠点である。Information Fusion Centre (IFC), “About Us,” IFC Official Website.
- 11 Vincent Wee, “Indonesia, Malaysia and the Philippines launch joint patrols…” Seatrade Maritime News, June 19, 2017.
- 12 Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania. “Minister of National Defence D. Šakalienė Departs for Japan and Singapore.” kam.lt, June 14, 2025.
- 13 PSMX(太平洋海上安全保障交換)は、北朝鮮制裁違反の監視を目的とした情報共有枠組みである。U.S. Department of State. “Pacific Security Maritime Exchange.” Bureau of International Security and Nonproliferation.
- 14 Ministry of National Defence Republic of Lithuania. “Lithuania and Japan expand defence cooperation.” May 29, 2025.
- 15 UNSCR 1718 (2006), op. cit.
- 16 国連安保理決議2270(2016年)は、石炭、鉄、航空燃料の輸出禁止を含む分野別制裁を導入した。United Nations Security Council. “Resolution 2270 (2016).” Adopted March 2, 2016.
- 17 国連安保理決議2375(2017年)は、原油供給の上限設定と繊維製品の輸出禁止を導入した。United Nations Security Council. “Resolution 2375 (2017).” Adopted September 11, 2017.
- 18 国連安保理決議2397(2017年)は、石油製品の上限をさらに厳格化し、北朝鮮船舶の臨検を承認した。United Nations Security Council. “Resolution 2397 (2017).” Adopted December 22, 2017.
- 19 2020年1月、海上自衛隊の補給艦が北朝鮮籍タンカーのSTS疑惑事案の発見にも関与している。防衛省 「北朝鮮船籍タンカー「CHON MA SAN(チョンマサン)号」と船籍不明の船舶による洋上での物資の積替えの疑い(令和2年1月12日)」 2020年6月12日。
- 20 Australian Department of Defence. “Front-row seat on Indo-Pacific security.” Defence News, May 21, 2025.
- 21 Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT). “About MSMT.”
- 22 MSMT, Field Surveillance Update, Report No. S_2025_340-EN, June 20, 2025, p. 4.
- 23 U.S. Department of State. Proliferation Security Initiative (PSI).
- 24 外務省「北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い」 2025年6月9日。
- 25 防衛省「「瀬取り」に対する関係国による警戒監視活動(令和7年6月9日更新)」。
- 26 防衛省「北朝鮮船籍タンカー「NAM SAN 8(ナムサン8)号」と船籍不明の小型船舶による 洋上での物資の積替えの疑い(令和元年12月16日・17日)」。
- 27 首相官邸HP「内閣官房長官記者会見」2018年1月25日。
- 28 António Eugénio, “Smart Defense: Overcoming Hurdles and Passing Batons,” George C. Marshall European Center, Occasional Paper No. 25, Dec 2013.
- 29 2025年1月、PLA海軍がカナダ艦を追尾している。Radio Free Asia. “PLA Navy Vessel Enters Canadian Warship’s Path in East China Sea.” Jan 9, 2025.
- 30 北朝鮮とロシア間の武器取引は、鉄道から海上輸送へと移行しつつある。MSMT. Unlawful Military Cooperation including Arms Transfers between North Korea and Russia, May 29, 2025, pp. 16, 18.
- 31 国連の北朝鮮制裁専門家パネルは2024年4月に解散された。The UN Panel of Experts on DPRK sanctions was disbanded in April 2024.
- 32 Food and Agriculture Organization of the United Nations. “What is IUU fishing?” Accessed June 13, 2025.
