はじめに
2025年9月25日にトランプ大統領が提案したガザ紛争包括的終結計画(以下「和平計画」)[1]は、イスラエルおよびハマス当事者双方の合意を得て、10月10日イスラエル軍の撤退開始とともに同計画の第1段階が始まった。その後、生存していた20人のイスラエル人人質とイスラエルに収監されていたパレスチナ人約2000人が返還され、10月13日には、エジプト・シャルムッシェイクにおいてトランプ大統領は、「中東の新しい夜明け(new ‘dawn’ in Middle East)」を宣言した[2]。
しかし、ガザ停戦から1週間、和平計画の第1段階の合意に基づく停戦は概ね維持されているが、停戦発効後72時間以内に返還されなければならないとされていた人質遺体の返還は遅れており、停戦維持の上での火種となっている[3]。また、ハマスは、ハマスに抵抗するガザの武装組織や部族に対する攻撃を行い、ガザ内部を掌握しようとしている模様であり[4]、20項目提案中のハマスの武装解除及びガザ統治からの排除に向けて障害になり得ると考えられる。
和平計画は、トランプ大統領の仲介によりイスラエル、ハマス双方が受入れて2023年10月7日から続くガザ戦争を一旦終結させたという意味で大きな意義をもつ。他方、第2段階実施が可能か否かは、未だ不透明である。そこで本稿では、まず、20項目提案にイスラエル、ハマスが合意に至った背景を探り、次に第2段階へ進む上での課題を整理する。さらに、トランプ大統領の和平計画発表までほぼ関わってこなかった日本がこの過程で如何なる役割を果たしたらよいか議論する。
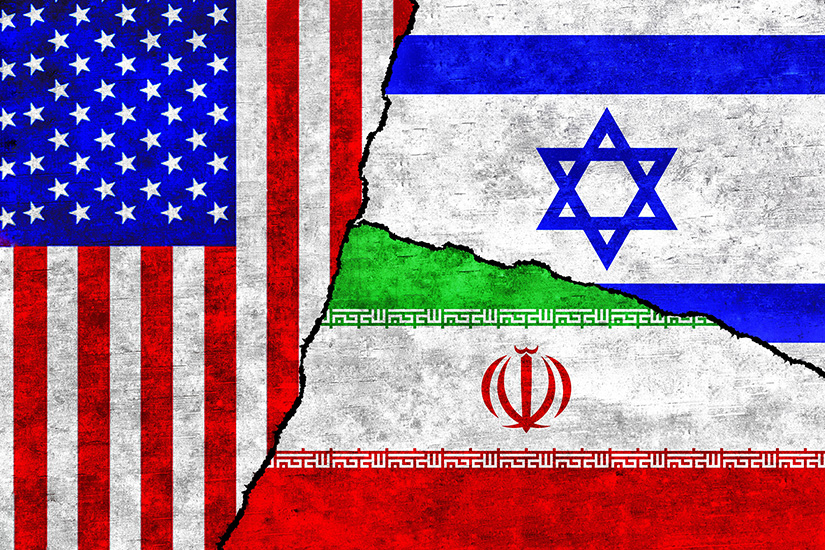
合意の背景
合意の背景として、①岩盤支持層を含むアメリカ国民によるイスラエル支持が低下、②湾岸アラブ諸国に対するアメリカの威信と信頼を回復する必要、③イスラエルの孤立、④ハマスの弱体化があると思われる。
トランプ大統領の和平計画は、国際社会においてイスラエルが孤立し、かつ同国がアメリカ軍基地のあるカタールのハマス幹部宅を攻撃するという「ミス」を犯したタイミングで提案された。カタールのハマス幹部宅攻撃は、トランプ大統領に対するカタールを始めとするアラブ諸国の信頼を低減させ、ある意味で同大統領は面子をつぶされた。また、本年になってイスラエルに対するアメリカ国民、特にトランプ政権の岩盤支持層である福音主義キリスト教徒の支持率が急減しており、トランプ大統領としてはガザ戦争終結に向けてイスラエルの反対があっても動かざるを得ない条件が整っていた。
これまで筆者の論考で繰り返し述べてきたように[5]、イスラエルとパレスチナを含むアラブ諸国との間で和平を生み出すには、アメリカの持つイスラエルへの影響力が必要である。しかし、昨年末より続く中東地域におけるイスラエルの「一強」状況の中、イスラエルがガザ地区、シリア、イランに対し自由に軍事行動を起こすとともに西岸地区ではユダヤ人入植と入植地の併合を進めたのに対して、アメリカは黙認ないし支援するという姿勢であった。結果として、ガザ地区においては飢餓を含む危機的人道状況が現出し、これがアメリカを含む全世界に伝わった。
エコノミスト誌の調査によると、アメリカ国内においては、パレスチナ問題に関しイスラエルを支持するアメリカ人の割合は、過去25年来の低さだという。2022年に反イスラエルの意見をもつ成人アメリカ人の割合は43%であったが、今は53%と報じられている。この傾向は、民主党支持者は言うに及ばず、共和党支持者の間でも生じている。2018年~21年までの30歳以下の福音主義キリスト教徒のイスラエル支持の割合は69%であったが、現在は34%であると言われている[6]。福音主義キリスト教徒がパレスチナ問題だけでトランプ政権を支持するかを決めるとは思われないが、政権からすれば由々しき事態ではないだろうか。
トランプ大統領は、2025年1月の第二期政権発足当初、ガザ戦争を直ぐに終わらせる旨表明し、アメリカのガザ地区所有と同地区のリビエラ風再開発を打ち上げたが、イスラエルのガザ攻撃は継続する一方、同地区の危機的人道状況は深まるばかりであった。そのような中、トランプ大統領は「12日間戦争」を自分が終わらせたとは言うものの、イスラエルに引きずられる形でイラン核施設攻撃を行った。さらに、冒頭で言及した通り、9月に入り、イスラエルは、中東におけるアメリカ軍最大の基地のあるカタールのハマス幹部拠点を攻撃した。トランプ大統領はこれを非難はしたが、カタールを守るうえでさらなる行動は起こさなかった。カタールと同様に安全保障をアメリカに依存する湾岸アラブ諸国に対するアメリカの威信と信頼はかなり低下したと考えられる[7]。トランプ大統領としては面子を取り戻す必要があった。
アラブ諸国は、バイデン政権時のアメリカ軍のアジアシフトの頃より、アメリカに対する信頼感が低下してきていた。アメリカによるイランの核施設攻撃の際は、カタールのアメリカ軍基地が報復の対象とされた。その上でのイスラエルのカタールのハマス幹部拠点攻撃である。カタールのみならず、エジプト、ヨルダン、GCC諸国からなるアラブ穏健派諸国は、アメリカに対する信頼が著しく下がるとともに、アメリカが仲介するイスラエルとの国交正常化について二国家解決を下げられない条件とすることができるようになった。
イスラエルは、中東における軍事的フリーハンドを持ったと同時に国際社会における孤立化も進んだ。フランスとイギリスおよびそれに続くカナダ、オーストラリア等によるパレスチナ国家承認は、二国家解決進展にはつながらなかったが、欧州諸国を中心に多くの国の反イスラエルの姿勢につながった。国連の専門家パネルによる、イスラエルがガザ地区においてジュノサイドを犯しているという非難、イスラエルの欧州サッカートーナメントやユーロヴィジョン歌唱からの排除、EUとの貿易協力協定の見直しなどが起こっている[8]。イスラエル社会にとってこれは痛みを伴うものである。後ろ盾であったアメリカが、これ以上ガザ戦争を継続するイスラエルを支援できない、和平計画を受け入れるよう求めれば、断ることはできなかったと推測される。
一方、ハマスは、昨年末までに、政治的及び軍事的指導者をイスラエルによって殺害され、また軍事行動を行なえるレベルの軍事組織を失い、幹部レベルの統率力が弱まっていた。また、ハマスは、アラブ諸国の多くからテロ勢力と認識されており、自らを受け入れるカタールによる助けがなければ、生き延びられない状況である。ハマスは、人質を保持することで生き延びようとしていると言われていたが、結局人質全員解放、武装解除及びガザ地区政治への不介入を受け入れざるを得なかったと考えられる。
まとめれば、トランプ大統領は、イスラエルを戦争から和平へと向かわせるためのアメリカの国内的支持を得られる見込みの下、アラブ諸国の二国家解決の要望を受入れつつ、20項目に和平計画をまとめ上げ、国際的に孤立したイスラエルと弱体化したハマスにこの和平計画を受け入れさせたものと観ることができるのではないかと考えられる。
第二段階へ進む上での課題
和平計画について、フィナンシャルタイムス紙のアンドリュー・イングランドは、始まりに過ぎず、戦争を終わらせるにはトランプ大統領は引き続きイスラエルとハマスの間の交渉を押し進める必要がある、としている[9]。一方で、エコノミスト誌のカバーストーリーでは、オスロ合意と違い、実践的なアプローチをとる新しい始まりであるとしている[10]。ここで見て取れるのは、和平計画は、イスラエル・パレスチナ和平の新しい枠組みをつくるものと考えられるが、実践的アプローチを行うにしても、イスラエルとパレスチナの交渉にはアメリカの強い働きかけが必要であるということであろう。
和平計画は、第1段階としてイスラエル軍は合意された地点まで撤退し、ハマスは生死に関わらず全人質を、イスラエルは250人の終身刑者と2023年10月7日以降に拘禁した1700人のガザ地区のパレスチナ人を返還することになっており、遅れている人質の遺体の返還を除き、実施された。また、和平計画では、合意がなされれば、ガザ地区への人道支援物資搬入がすぐさま行われることになっている。これらは国連とその専門機関及び国際赤十字により行われ、開始されている[11]。
これに対し、第2段階は、今後のガザの統治、治安、及び復興・開発に関する具体的な施策が綴られているが、どの施策にしても、アメリカの強力な指導力がなければ、進まないものと考えられる。また、イスラエルとハマスがどれだけ協力するか、或いはアメリカの指導を受容するかが鍵となる。これを踏まえて以下に第2段階実施における課題を整理してみる。

統治
パレスチナ自治政府に引き渡されるまで、非政治的なパレスチナ人と国際的専門家テクノクラートからなる暫定移行委員会が、トランプ大統領がトップで議長を務める平和会議に監督されつつ、日々の行政を担う。この平和会議の構成員はトニー・ブレア元イギリス首相を含む国家指導者等であり、この会議体がガザの再開発の枠組みをつくり、資金を集め活用する。しかし、これだけ頭でっかちの会議体を動かし、テクノクラートの暫定移行委員会の的確な監督を行うには、国家指導者クラスでも単なるテクノクラートでもない両者を効率的に結びつける人物あるいは人物のグループが必要ではないか。更にガザ復興・開発のためのトランプ経済開発計画の策定や特別経済地区の設置などについてもそれぞれを指導する人材が必要となるであろう。人材をどのように適正・的確に集め、配置していくかについてもアメリカの指導力が必須である。
治安
ハマスとその他の派はガザ地区の統治に役割を持たない。非武装化・兵員退役・社会復帰(DDR: Demilitarization, Decommissioning, and Reintegration)が独立したモニターの監視の下で行われ、トンネルや武器製造所を含む軍事的・テロ関係・攻撃的インフラはすべて破壊されるとされている。また、アメリカは、アラブ及び国際的パートナーとともに、国際安定化部隊(ISF)を創設しガザ地区に配置する。ISFはガザ地区警察を訓練し、支援することになっている。更にISFは国境地帯の治安につきイスラエル及びエジプトと協力をする。アメリカは200名の部隊を送ってISFと撤退するイスラエル間の連携を円滑にする役割を担う。
ハマスは、DDRを実施され、ガザ地区の統治に役割をもたないとされているが、冒頭で述べたようにイスラエル軍撤退後すぐにガザ地区の人々を掌握しようとする行動に出ているとの報道がある[12]。ハマスの武装解除が円滑に行われるのかも極めて疑問である。アフガニスタンでDDRを担った日本の経験からすれば、敵対勢力でない武装組織の圧力が必要であるが、計画の趣旨から推し量ればISFがそれを担うことになるだろう。ISFは、イスラエル撤退後の地域の治安を引き継ぐことになっているが、ISFがハマスを武装解除させられなければ、イスラエルの撤退に影響を与えるかもしれない。ここにおいてもアメリカの指導力と力が必要である。
復興・開発
和平計画の中に、ガザ地区を再興させ元気づけるトランプ経済開発計画が言及されている。前述したように、これも統治においてアメリカがどのように指導力を発揮するかにその成否がかかっているが、トランプ大統領肝いりの計画であるので、アメリカ政府関係者が具体化していくと予想される。その際、アメリカ国際開発庁(USAID)が解体された今、これまでのODA的手法の復興開発は脇に追いやられ、民間資本を中心とした投資が行われる可能性がある。また、アメリカの資金は民間からで、インフラ整備等民間資金が適合しない分野については、アラブ産油国や欧州・日本等に資金提供の要請がなされることも大いに考えられる。
ガザ地区の復興・開発においては、開発計画を最初に策定すべきである。これはアメリカが主導するのであろうが、USAIDの関与が期待できないのであれば、世界銀行の協力を得るしかないであろう。
日本がとるべき姿勢
和平計画の発表までにアメリカはアラブ穏健派諸国、トルコ、インドネシア及び欧州諸国とは協議してきた。一方で、日本の姿は見えなかった。日本は、オスロ合意においては、アメリカ、EU及びサウジアラビアとともにパレスチナ自治の立上げに大いに協力した。2009年までに10億ドル以上の支援を行い、母子保健、地方行財政、廃棄物処理・管理及び農業技術の普及などの技術協力も実施した。また、「平和と繁栄の構想」を提唱し、和平を下支えする包括的な支援も行っている[13]。90%の建物が破壊されたガザ地区の復興開発に今回もしっかりと協力するべきである。このためには、トランプ大統領の訪日の機会を捉えて、日本のガザ支援を表明し、日本を協力パートナーとして認めてもらう必要がある。その上でアフガニスタン復興支援を含む日本の経験を活かした協力策を策定していくべきである。

追記
イスラエルは、10月28日夜、ガザ地区への空爆を行った。ガザ保健当局によればこれにより104人の死者がでたが、イスラエルは停戦合意違反によるものとハマスを非難した[14]。アメリカのヴァンス副大統領はガザで攻撃が再燃しているものの停戦は維持されているとの見解をしているとされている[15]。しかし、この状況が続けば、アラブ諸国等からアメリカの指導力に対する疑問符がつけられるようになる可能性もあり、第二段階に進みこれを実行する上でも、イスラエル、ハマス双方に対するアメリカの指導力が求められていると思われる。
(2025/10/31)
脚注
- 1 “Donald Trump’s 20-point Gaza peace plan,” BBC, October 9, 2025.
- 2 “Trump declares a new ‘dawn’ in Middle East. It could be a false one,” The Washington Post, October 15.
- 3 「ガザ停戦、遺体返還が火種に 発効1週間、先行きは不透明」『東京新聞』2025年10月16日。
- 4 “Hamas reasserts control in Gaza after ceasefire with Israel,” The Washington Post, October 15, 2025.
- 5 拙稿「イスラエル「一強」下の中東情勢-国際社会に何ができるのか」国際情報ネットワークIINA、2025年1月10日。
- 6 “How Israel is losing America,” The Economist, September 18, 2025.
- 7 “Israel’s Qatarstrophic error,” The Economist, September 11, 2025.
- 8 “Trump goes mainstream on the Middle East,” Financial Times, September 29, 2025.
- 9 Andrew England, “‘Donald Trump’s Gaza breakthrough is just the start,” Financial Times, October 9, 2025.
- 10 “A new beginning for the Middle East,” The Economist, October 9, 2025.
- 11 「イスラエル、ガザ支援物資の制限を国連に通告 人質遺体の返還遅れで」CNN、2025年10月15日。
- 12 “Hamas reasserts control in Gaza after ceasefire with Israel,” The Washington Post, October 15, 2025.
- 13 外務省「パレスチナ概況」2009年3月。
- 14 「イスラエルがガザを空爆、死者100人以上 停戦合意にハマスが違反したと非難」BBC NEWS Japan、2025年10月29日。
- 15 同上。
