拙稿「「もがみ型護衛艦」の開発経緯とその強み――オーストラリア政府はなぜ導入を決めたか」では、「もがみ型護衛艦」の建造の背景、具体的な性能面について分析し、オーストラリア政府が新型「もがみ型護衛艦」を選定した理由について論じた[1]。本稿では、新型「もがみ型護衛艦」を事例に、今後の日本の防衛装備移転の可能性と課題を検討し、その安全保障政策への影響について分析する。
安全保障政策の転換と防衛装備移転
日本の防衛装備移転の経緯は、1967年に武器輸出三原則が定められ、その後1976年に「武器」の輸出を事実上禁止する政府見解が示された[2]。しかし、2014年に「積極的平和主義」を掲げ、これまでの原則が変更され、国家安全保障戦略に基づく防衛装備移転三原則が策定された。これにより防衛装備に関し一定の条件付きで海外移転が認められるようになった[3]。さらに2022年、改定された国家安全保障戦略に「防衛装備移転の推進」が明記され[4]、国際共同開発への対応、より積極的な平和への貢献や国際協力推進のため、2023年3月にはその運用指針が改定され、次期戦闘機の第三国移転が認められた[5]。
さらに2024年10月、オーストラリア政府が次期汎用フリゲート艦の候補を日本とドイツの2か国に絞り込み、新型「もがみ型護衛艦」を最終候補の1つとしたことを受け、同年11月、日本は国家安全保障会議(NSC)において、防衛装備移転三原則の適用案件について議論を行い、オーストラリアの次期汎用フリゲートの共同開発・生産に関して、海外移転を認め得る案件に該当するということを確認している[6]。
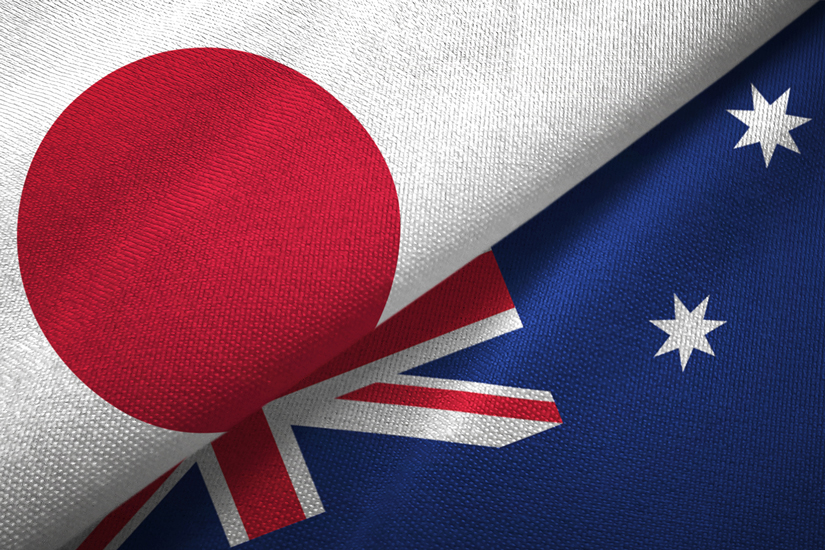
新型「もがみ型護衛艦」の移転とその可能性
日本とオーストラリアはこれまで、日豪ACSA(物品役務相互提供協定)や日豪情報保護協定、日豪防衛装備品・技術移転協定、日豪RAA(円滑化協定)といった協力の基盤を強化してきた[7]。その日本が官民協力し本格的に防衛装備移転に取組み、日豪協力基盤の強化と相まって、新型「もがみ型護衛艦」が選定されたと見ることができる。
今後も日本の高い防衛開発・技術力と運用能力を基底として、二国間における協力基盤を整えれば、オーストラリアへの新型「もがみ型護衛艦」を例とする防衛装備の移転は、インド太平洋地域への拡がりが期待できる。さらにはオーストラリアだけでなく、他の英連邦諸国(ニュージーランド、カナダなど)への新型「もがみ型護衛艦」などの防衛装備移転へとつながる可能性がある。
このような防衛装備移転の結果として安全保障連携が高まり、これまでの米国を中心としたハブ・アンド・スポークスの関係から、米国を中心としながらも有志国間連携(スパイダーウェブの関係:米国を蜘蛛の巣の中心としながらも横の連携がなされる状態)への転換が期待できる。
そして、防衛装備移転がさらに他国へ広まれば、日本がインド太平洋地域の安全保障の中心的役割を担う契機ともなりうる。これは2025年5月に開催されたシャングリア・ダイアローグにおいて、中谷防衛大臣が提唱したOCEAN(One Cooperative Effort Among Nations)構想として述べた「OCEANの下で各国が手を携え、対話を重ね、「ルールに基づく国際秩序」の溶解ではなく回復をなし、アカウンタビリティの無視ではなく実現をすること、国際公共益の棄損ではなく増進を図っていくべきである。そして、日本はその中心であり続けることの約束」[8]にも大きく貢献するものとなる。
さらにはインド太平洋に位置するいわゆる西側各国の造船業の復活へとつながるものとなる。2024年の世界の新造船建造量は、中国が約3,900万総トンでシェアが55%、韓国がシェア28%、日本がシェア13%(3か国で96%、因みに米国のシェアは1%)となっている[9]。現在、米国やオーストラリアほかの艦艇建造能力の低下が著しいことから、本防衛装備移転は同志国の造船業復活のための出発点にもなる。そして「もがみ型護衛艦」のファミリー艦を持つ各国で修理に関する協定などを結べば、インド太平洋地域を中心にどこにおいても補給、修理が可能となる。これにより艦艇の活動範囲の拡がりと活動期間の長期化が期待できる。

具体的な安全保障への影響として、オーストラリアへの防衛装備移転が成功した場合、将来、少なくとも日豪合わせて35隻程度の「もがみ型護衛艦」のファミリー艦が連携しながら東シナ海、南シナ海、そしてインド太平洋海域を中心に活動することとなる。つまり同じコンセプトで建造、戦力化された相互運用性の高い艦艇が共同してプレゼンスを示し、また活動が可能となることで、結果として、力による一方的な現状変更を試みる権威主義国家の抑止とともにインド太平洋地域の安定にもつながる。これがさらにASEAN諸国、インド、他の英連邦諸国まで広がれば、抑止と安定の度合いはさらに増す。
新型「もがみ型護衛艦」の事例から見える防衛装備移転の課題
ここまで防衛装備移転についてのさまざまな可能性について述べてきたが、日本の防衛装備移転の課題も明らかになってきた。
第1に、国外での建造に係る課題である。オーストラリアに移転する最初の3隻の日本国内での建造については、「もがみ型護衛艦」の建造実績がある2社(3造船所)で建造できることから、その納期に関して問題はないものと見積もられる。ただし、4隻目以降のオーストラリアのオースタル造船における建造については、建造能力、特にスチール材を使用したステルス技術に関しての経験が少なく知識と経験についての継承が重要な課題となる[10]。この対策の一例としては、1~3番艦建造時、オースタル造船の技術者・現場職員を日本に研修派遣させ、また4番艦以降の建造時に日本の技術者・現場職員を派遣することなどが考えられるが、日本の防衛造船企業は海外での指導経験が少ないことや言語の壁も大きな課題である。
第2に、造船所現場職員および同艦乗員の秘密保全の問題である。オーストラリアにおける適正管理や目的外使用の禁止および第三国移転に係る事前合意をオーストラリア政府に義務付けることとされているが[11]、就役後も含めた現場での保全に関しても適正に管理されているかなどをどのように担保するのかが課題となる。
第3に、継続メンテナンスに係る課題である。就役した艦の故障部品の補給や技術力を必要とする損傷個所の修理、突発的修理所要や更には有事における修理と技術・部品をどのように指導・補給するのかなどの課題がある。この場合日本版FMS(Foreign Military Sales:有償援助)での装備品の有償提供などの検討も必要となる。
第4に、戦力化教育や教範の移転を含む乗員に関する教育である。通常の約半数で運用する新型「もがみ型護衛艦」は、通常のフリゲートの運用とは異なること、そして省人化から高度の教育、訓練も必要となる。諸外国でも武器等の海外輸出における技術指導や運用指導をその分野を専門とする退役軍人が実施している。新型「もがみ型護衛艦」においても保全・技術資格を備え、かつ豊富な経験を有する自衛隊OBを活用することは、日本および装備移転国にとっても大きなメリットとなる。この点においても米国からのFMSには、装備・武器のほか、技術指導も含まれている。これを参考とする日本版FMS(技術指導)の活用が考えられる。

おわりに
本稿では、新型「もがみ型護衛艦」のオーストラリアへの移転から、日本とオーストラリアを軸とした防衛協力の可能性について具体的に論じた上で、見えてきた防衛装備移転の課題についても検討してきた。
オーストラリアへの防衛装備移転はあくまでも一つの事例であるが、高い技術力と運用能力、アフタケア力を持っている日本が、本格的に防衛装備移転を実施する可能性は大きい。そうした場合、日本のインド太平洋地域における安全保障上の責任も当然大きくなる。これに対する準備もしなければならないことも自覚しなければならない。そのためには、防衛装備移転の際に発生する建造やその際に求められる情報保全、継続的なメンテナンス、乗員に対する教育などの課題なども考慮しつつ、防衛装備移転を含み現在検討されている「防衛産業戦略(仮称)」[12]やインド太平洋地域における日本の安全保障に関する責任の拡がりをも含め、次期「国家安全保障戦略」に取り入れることが必要となってくるのではないだろうか。
(2025/09/29)
*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。
Possibilities and Issues in the Defense Equipment Transfer of the New Mogami-Class Frigates―― Impact on Japan’s Security Policy
脚注
- 1 拙稿「「もがみ型護衛艦」の開発経緯とその強み――オーストラリア政府はなぜ導入を決めたか」国際情報ネットワーク分析IINA、2025年9月24日。
- 2 「武器輸出三原則等」外務省、2025年9月21日アクセス。
- 3 「防衛装備移転三原則」内閣官房、2014年4月1日。
- 4 「国家安全保障戦略」内閣官房、2022年12月16日、20頁。
- 5 「防衛装備移転三原則の運用指針」内閣官房、2024年3月26日一部改正。
- 6 「豪州次期汎用フリゲートの共同開発・生産を我が国が実施することとなった場合の令和6年度型護衛艦の移転について」外務省、2024年11月28日。
- 7 それぞれの協定の概要は、『令和7年度防衛白書』防衛省、2025年8月、359頁を参照のこと。
- 8 「中谷防衛大臣の第22回IISSアジア安全保障会議への出席及び各国国防大臣等との会談等について(概要)(令和7年5月30日~6月1日)」防衛省、2025年9月21日アクセス。
- 9 「造船関係資料」日本造船工業会、2025年3月、1頁。
- 10 オーストラリアのオースタル造船所の建造船舶は、高速船舶が主体であり、そのほとんどが軽くて高速力を発揮できるアルミ船体である。また、ステルス性を追求した艦船の建造実績は少ない。
- 11 「防衛装備品及び技術の移転に関する日本政府とオーストラリア政府との間の協定」外務省、2014年。
- 12 「我が国の防衛産業と装備移転」防衛省、2024年10月、31頁。
