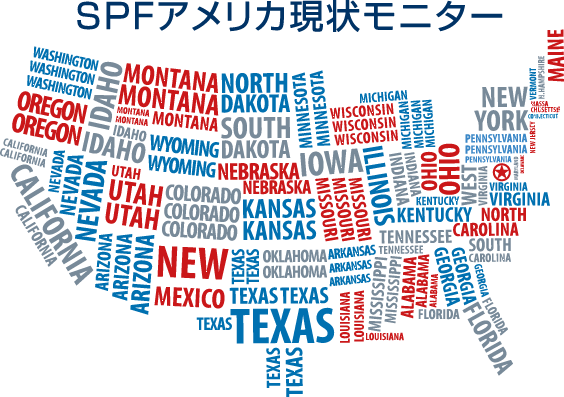【特別転載】
アメリカのエスニック「部族主義」
ハリスとオバマともうひとつの人種問題

渡辺 将人
雑誌『ひらく』5巻2021年6月 p.55-63 より出版元の許諾を得て転載しています。
2021年1月20日、大統領就任式で司会のエイミー・クロブシャー上院議員が宣誓に臨むバイデン政権の副大統領をこう紹介した。
「初のアフリカ系、アジア系、そして初の女性副大統領のカマラ・ハリスを祝福します」
アフリカ系と共に「アジア系」という文言が入ったことは、小さいようで大きな進歩だった。ハリスがインド系移民一世の娘でもあることが、黒人社会に動揺を与えていたからだ。かつてバラク・オバマにかけられたのと同じ嫌疑、すなわち「十分に黒人か(ブラック・イナフ)」という問いが一部黒人社会では首をもたげた。筆者はバイデン政権がこの「マルチレイシャル(多人種)」問題をどう扱うのか固唾を飲んで見守ってきた。
オバマは母親が白人だった。黒人の血が一滴でも入ると白人に見做されることはない。オバマは青年期まではハワイとインドネシアで「無人種」的な感覚で過ごし、大学進学で本土に移ってからは「黒人」に覚醒していった。それに対して、両親が共にマイノリティのハリスは、両親の人種ルーツに平等に価値を見出してきたことが窺える。連邦議会が刊行する『アジア系政治家名鑑』にはアジア系として登録している1。これはアジア系の政治関係者に流通している刊行物で、アジア系献金筋やロビイストには仲間意識を与える一方で、黒人や一般有権者の目には触れない。だからこそハリス事務所は掲載を許していた。ハリスはアジア系の間では紛れもなく「インド系の上院議員」だったのだ。
実際、ハリスはインド系の母親に育てられた。ジャマイカ系の父親と母はハリスが七歳で離婚し、ハリスと妹は母親に引き取られている。食べ物から習慣まで、(多分にアメリカナイズされていても)インド系の環境で育った。少なくとも典型的な黒人料理ではない(これはオバマも同じで、家庭の味がソウルフードになったのは結婚以降で、それまで黒人との同居経験がない)。また、ハリスの父方のカリブ海系のルーツも黒人社会では微妙な問題をはらむ。アメリカの黒人社会には独特の「主流」「亜流」定義がある。今でこそジャマイカ系にはコリン・パウエル元国務長官、NBC気象キャスターのアル・ロカなどセレブリティも多いが、奴隷制や公民権運動をめぐる共有体験の濃度では、彼らは南部黒人奴隷の子孫とは異質とされる。近年増加するアフリカからの自由移民も、白人とアメリカ黒人の双方から疎外される「二重の差別」を受けてきた。
それでもハリスの「人種」が2020大統領選まで問題視されなかったのには以下の複数の理由が介在している。第一に「黒人大学」のハワード大学に進んだこと、第二にカリフォルニア州というアジア系の多い多文化的地域を地盤としていたこと、第三にジェンダー(女性)という別の重要なマイノリティ記号の前景化、第四に外見上は褐色でさほど黒人として違和感がなかったことだ。外見は「名指し」を支配し、「名乗り」にも影響を与える。顔の造形で多人種ルーツが周囲に推測されれば、本人にも異なるアイデンティティが形成される。ハリスの場合、10年以上の長い付き合いの黒人の仲間が誰も彼女のアジア系のルーツを想像しなかったという。カメレオン的に属性の違う友人ごとに違う顔を見せてきたのはオバマとも共通する処世術である。
単一属性の「名指し圧力」をめぐる「二重差別」
アメリカでは、人種、民族など属性ごとの分断を彼ら自身が自ら強める歴史が繰り返されてきた。ハリスはオバマと同様、そうした中では属性横断的な異端の存在だ。ハリスの夫はユダヤ系の白人であり、黒人社会に根強い同人種間の結婚の慣習にもとらわれなかった。その意味では、アジア人や白人との恋愛を繰り返しながらも、ミシェルを選び「黒人家族」を営むことにしたオバマと違う。筆者と共同研究歴のある黒人政治学者は「白人の女性を家に連れてきてはいけない」と母親に躾けられたと述懐する。「母はどんな女性でもいいと言っていたのに、白人だけは別で、黒人が白人に何をされたか忘れてはいけないと繰り返していた」という。ジム・クロウ法の時代ではなく、1990年代から2000年代にかけての逸話だ。白人が混血を差別したことで、彼らは黒人側に包摂された。全てに優先する属性としての「血の一滴」の原則は、黒人自身のプライドとも共鳴したのだ。
異人種と結婚すると子どもは多人種になる。アメリカではこれが意外に厄介だ。双方から仲間と認めてもらえない「二重差別」の温床になる。ハリスも「十分に南アジア系ではない」「十分に黒人ではない」との不満の声を浴びせられた。オバマはしっかり「黒人になる」ことだけに集中すれば済んだが、ハリスは2つの集団を満足させる重荷を背負ったのだ。
多民族社会アメリカではどれか一つの属性に属さないといけない。国籍の下にもう一層「看板」が必要になる。白人アングロサクソン系のワスプには「看板」が不要でも、マイノリティであれば「アメリカ人」だけでは済まない。勿論、ハワイのような例外はある。先住民と中華系、日系と白人など異人種間結婚の歴史と表裏一体のハワイでは多人種をハワイ語で「ハパ」と呼び、これ自体が一つのエスニシティ区分の扱いに近い。しかし、本土では西海岸でもニューヨークでもそれは許されない。エスニックな多様性が強い都市ほど「何系なのか」を常に問う。
政治家ハリスが公式に黒人アイデンティティを優先することに不満を持つアジア系は少なくない。インド系ジャーナリスト、ニーシャ・チタルもその一人である。両親は1980年代に移民しシカゴで育った二世のチタルは「黒人か南アジア系を二者択一で選ぶ必要はない」とした上で、本質的な問題は「アメリカ社会がいまだにマルチレイシャルの人をどう扱っていいか分からないことにある」と言う。国勢調査に基づく予測では、アメリカでは現在約7%の多人種ルーツの市民が2060年までに3倍になる。だが、それ自体は単一属性を自明視する社会的な「名指し圧力」からの解放を少しも約束しない2。
アメリカ社会は多様である。しかし、社会全体が多様であることは、その社会の構成員が多様性に寛容であることや、他の属性に詳しいことまで保証するものではない。寛容さを持ち合わせていても、他の属性への関心や理解まで兼ね備えているわけではない。筆者がかつて米民主党のエスニック集団別の集票戦略にニューヨークで携わった際に驚愕したのは、徹底した蛸壷性だった。黒人のことは黒人にしかわからない、アジア系のことはアジア系に任せる。寛容さは持ちつつも、首を突っ込んではいけない。アメリカの選挙運動に関しては、政治学者による数々の選挙実験で、対象の有権者と人種やエスニシティが同じ運動員による動員・説得活動が効果的であることが実証されている3。有権者と接しない陣営本部内のスタッフですら、黒人部門に黒人以外が関与するのはご法度だった。
アジア系の場合、困るのは「アジア太平洋諸島系」が単なる国勢調査区分でしかないことだ。言語も宗教も異なる集団を仮想的に一つにまとめている。しかもアメリカ国内で地域特性が激しく、「主流」から「亜流」は見えにくい。日系の大きな分断はハワイ派か本土(メインランド)派かだ。ハワイからは違いが見えるが、本土派はハワイのメンタリティがわからない。この差異区分に限定して言えば、本土の黒人はアメリカの「主流」である。オバマは離島から「主流」に混ざったが、いつしか「説明してもどうせわかってくれない」と感じるようになった。シカゴや黒人社会でハワイのことを語っている形跡がない。共有しているのはミシェルだけだ。そのミシェルもインドネシアについてはお手上げだ。文化的にはインドネシアに同化していたオバマの母親とミシェルの間にはわずかな邂逅しかなかった。
政治における「人種」を避け続けた、帰国子女のオバマ
2020年11月、オバマの大統領回顧録『A Promised Land』が刊行された(邦訳は2021年2月刊『約束の地 上・下』集英社)4。注意しなければいけないのは、これは私人としてのオバマ自伝ではなく、あくまで合衆国大統領の記録だということだ。青少年期は早回しで飛ばして選挙戦の回顧に突入する。『Dreams From My Father(邦題『マイ・ドリーム』)』というオバマの自著が既に存在し、回顧録と同書の整合性は難題だった。オバマの文学仲間やデイヴィッド・レムニックが述べている通り、上の既刊書は自伝風の創作作品だからだ5。この本は、シカゴでの住民活動で黒人社会に感化されて書き上げられたものだ。当時、オバマの夢はまだ作家だった。執筆過程で多くの人物名は仮名にされ、統合された架空のキャラクターにされた。時系列も不正確で、黒人問題に収斂しない出来事や人物は省かれている。第三者が同書の記述に過度に依拠してオバマ史を編むのは危険だ。
全米の書店の「アフリカ系文化」の書棚にひっそりとあった同書が、オバマの著名化で燦然と輝き「自伝」として一人歩きを始めた。この本でオバマを知った有権者や翻訳に親しんだ外国人は、オバマの精神的な根源が黒人問題だけに収斂していると解釈した。『Dreams From My Father』を単一のテキストにオバマ論を深めることに警戒を発する一人にハワイ時代のオバマの恩師の日系人のエリック・クスノキがいる。氏によれば、とりわけ問題なのはレイという仮名で出てくるキース・カクガワの問題だ。母が日系、父が黒人だったカクガワは「多人種」ではあったが、本土からの移住者で純粋なハワイの「ローカル(地元民)」ではなかった。本土流の「マイノリティ」としての防衛本能を身につけていたカクガワは攻撃的で、何か指摘すると常に「人種差別だ」と牙を剥いたという。インドネシアとハワイで育ったオバマにはそのような意識はなかった。オバマ史については「文脈」なしの「断片」には、念入りの注意を要する。
オバマは母方のダナム家の子である。幼少期はシングルマザーの白人の母親と暮らし、途中インドネシア人の継父との再婚生活を挟むが、オバマはハワイに戻され、中高時代は母方の白人の祖父母が親代わりで面倒を見た。母親はインドネシアで人類学の研究や開発の仕事に邁進していたからだ。オバマはケニアの苗字を名乗るが、父親は一時滞在していた外国人留学生で、移民でもアメリカ人でもない。この辺りが「バーサー」運動など陰謀論の根になった。母方の苗字であるダナム姓を名乗っていれば疑われるリスクは少なかったがそうはしなかった。オバマ自身がアフリカ文化への回帰を大学時代以降に求め、「父親探し」のような青春期を送ったのは事実だからだ。要するにアイデンティティクライシスである。
オバマは最愛の母や妹と黒人意識を共有できない悩みを抱え続けた。オバマの母はオバマの父を人間として愛したのであって、アフリカに関心があったわけではない。文化として惚れ込んだのはインドネシアだった。インドネシアはオバマの母の人生そのものだった。だからオバマのインドネシアへの敬意は母が愛した国への敬意だ。妹のマヤは継父と母の子である。妹はインドネシア姓「スートロ」を名乗り、母はダナム姓なので親子3人の苗字が違う。古いアメリカン・ファミリーを逸脱した「国際的」家族を象徴していた(ただ、インドネシアの現地校名簿でオバマは「バリー・スートロ」だった)。
古矢旬・東京大学名誉教授の指摘するようにオバマとトランプは、アメリカ外交の超党派的な合意から離反する「アウトサイダー」大統領という共通点があった6。付言すれば、オバマはワシントンの「アウトサイダー」であるだけでなく、文化的にもアメリカの「アウトサイダー」であった。そのため2008年の大統領選挙では、バラク・オバマが白人とのバイレイシャルであることや、インドネシアのアジア文化で育った「帰国子女」であること、「国際結婚」の子どもであることなどは無視された。隠されたわけではないが伏せられた。
バラク・オバマが大統領選挙で勝利したとき、まるでアメリカの人種問題が終わったかのような楽観論も飛び交った。だが、アメリカの人種問題は少しも解決していない。そもそもオバマは人種問題を避けてきた。オバマが目指した人種問題の解決の仕方は「人種を論じない」アプローチだったからだ。それは彼の独特の生い立ちがそうさせた部分と、政治戦術的に周囲がそう強いた面との2つがある。選挙参謀たちはオバマに人種を語らないように指導した。オバマは回顧録で以下のように記している7。
「プラフもアックス(アクセルロッド)もギブズも、人種についての不満表明であるとみなされそうな問題、有権者どうしを人種で線引きしかねない問題、私を〝黒人候補者〟という枠に押し込めてしまいそうな問題についてはことさらに取り上げる必要はなしとして譲らなかった」
「公民権や警官の職権濫用、その他黒人に特有の問題ばかりに焦点を当てすぎると、より幅広い有権者層から、反感とまではいかずとも不信感を持たれてしまうと懸念していたのだ」
白人の支持を得ることが黒人候補として勝利の要だった選挙だったからだが、オバマ政権の問題は政権発足後もこの人種ニュートラル戦略を貫いたことだった。現実問題として度重なる人種差別を見れば、差別が終わっていないのは自明で、ポストレイシャル(脱人種)論は、人種差別はすでに終了したという白人の主張に悪用されかねない。
選挙が増幅する「部族主義」と内向きの人権
アメリカの多様性はサラダボウルのままだ。サラダの野菜は種別ごとに蛸壺に収まっている。しかも、他の属性に触れないだけならまだしも、ステレオタイプや印象の固定化も促されている。固定化にはアメリカ特有の二つの要因が作用している。
一つは選挙だ。2年ごとに連邦レベルの選挙があることは、アメリカのデモクラシーの根幹ではある。その度に人種・エスニシティ、信仰、セクシャリティ別にアウトリーチを繰り返してきたことは、非主流のマイノリティを政治参加に巻き込んでいく意味で民主化に大きな貢献をした。しかし、集団ごとに壁を作る「部族主義(tribalism)」を固定化する副作用を伴った。オバマ政権の元黒人高官は「部族主義」の問題について政権終了間際、トランプ政権の幕開け前に次のように筆者に語っていた。
「黒人やラティーノが候補者ならば彼ら(少数派有権者)は投票に行く。だが、オバマが候補者ではないと途端に投票しない。こうした態度はレイシストを利するだけだ。我々は部族主義の犠牲者だ。この部族主義をどう払拭するかに対してあまりに関心がなさすぎる。黒人は2016年に共和党の嘘を信じた。それはヒラリーもトランプも違いはなく、共和党も民主党も違いはないという嘘だ。黒人が候補者でないのならば、もう投票する意味はないと考えた。黒人をこういう思考にさせてしまったのは民主党の戦略的な過ちだ。民主党はこの代償を抱えていかねばならない。1万いや10万以上の黒人がトランプ政権下で虐げられるだろう」
一連のトランプ政権下における人種ヘイト事件への予見も含んでいたが、問題は民主党がトランプ批判に忙しく、マイノリティ内部の問題には目を向けなかったことだ。選挙における属性別集票のアウトリーチ戦略の最大の副作用のひとつと言える。
固定化要因のもう一つは、他の「部族」に対して無知なまま過剰な「政治的正しさ」だけを追求する傾向だ。「政治的に不適切」と思われたくないために、とりあえずダイバーシティを尊重しておくという棚上げ的な姿勢がリベラルでは定着した。他の「部族」に詳しくなる「部族」間の相互交流を臆病にさせている。LGBTQについて、メキシコ系について、外国人によるイノセントな質問は文脈次第では許されても、アメリカ人同士ではそれは政治的に致命的だ。お互いに無知なまま、別属性の集団の併存だけを形式的に尊重する行為が「部族主義」を深めた。アメリカは多民族国家である以上に、最大の「移民」国家である。世界中に別のルーツを持つものが集まる土地では「統合」の理念も必要だ。そこでは異なる集団の背景への過剰な関心や自己ルーツの誇示は「統合」の阻害要因にもなる。しかし、同じ「部族」にしか関心を持たない、評価しない、投票しない、という政治的な反射神経は、アメリカの視野をますます狭くする。
たとえば、一見無関係のように見えて2019年夏に香港島で勃発し、香港全域に拡大した香港民主派のデモは一つの試金石だった。超党派で米議会が民主派を公聴会に招いた。活動家の若者は米メディアに熱心に出演して、自由をめぐるダム決壊の臨界点にあることを英語で訴えた。天安門事件30周年のデモを契機に拡大した運動で、十分に国際的な人権運動の含意があった。SNS時代らしい関心の広がりも見せた。それだけに、公民権運動を経験し、フェミニズム運動第二波や数々の市民運動を牽引してきたアメリカの左派の関心の限定性は意外感も伴った。香港民主派がトランプ政権に向けて星条旗を振ったことが反トランプの左派には不満だったし、中国と対峙する案件は共和党の「反共」イシューだとの固定観念が古い世代の民主党リベラルにある。だが、若年層に関しても、アジアの人権問題に関心を向ける層が、香港移民の子弟や台湾系などの中華系民主派を除き、国際的な人権団体以外では広がりを見せず、抗議活動も小規模にとどまった。
もちろん不幸も重なった。コロナ禍とトランプ政権下の分極化である。コロナでアメリカは内向きになった上に、中国をスケープゴートにするトランプの言動は、単なる票狙いの利己的な排他主義と解釈された。政権はアジアの民主主義を擁護する政策も打ち出したが、その価値を部分的に超党派で承認できないほど大統領選挙下でトランプ憎悪は燃え上がった。中国に関する人権問題に触れることはトランプの政治ゲームへの加担になるとの空気を醸成した。トランプが「チャイナウイルス」と叫べば、アメリカのリベラルは頑なに「COVID」と唱和した。
2020年初夏、中国の全国人民代表大会における香港の国家安全維持法の可決に先立ち、ミネアポリスで白人警官が黒人男性の首を押さえつけて死亡させる事件が発生した。反差別デモの広がりで、「ニューヨークタイムズ」や「デモクラシーNOW!」など香港に関心を寄せていた人権派メディアも報道を止めた。国内問題とりわけ黒人問題は特別の優先事項だからだ。結果、アジアのデモクラシーにコミットする政治家は「左」のペローシ下院議長のように天安門事件時代の古い人権派か、「右」のルビオのような反共キューバ系しか残存していない。議会の同僚議員は彼らの情熱に歩調を合わせているだけだ。ジュディー・チュー下院議員など中華系もその役目は担えない。選挙区に増える大陸系移民や親族のしがらみが複雑だからだ。 黒人が奴隷以来舐めてきた辛酸は凄惨だ。「移民国家」で先住民と黒人奴隷は例外的存在であり、アファーマティブアクションの含意も違う。しかし、アメリカの関心を内向きに収斂させることは看過されるべきなのか。オバマの悩みもここにあった。むしろ黒人と公民権活動家こそ、自由と人権の価値を誰よりも知り、共感の連帯を主導できる存在ではないか。2019年12月、ある黒人政治関係者は筆者との対話で香港のデモへの強い共感を吐露していた。
「香港のデモをテレビで見ていると黒人の公民権運動を思い起こさせられる。自分の母も運動で逮捕され続けた。それでも立ち向かうのは政治的にリスクがある。生活もおかしくなる。しかし、母親の逮捕がなければ自由は達成できなかった」
BLMが象徴する新世代黒人が提起するもの
明るい兆しもある。黒人の新世代の若手が変質し、黒人運動による「部族主義」を自己改革していることだ。旧世代黒人は敬虔なキリスト教徒で、同性婚に拒絶感があった。黒人層は総じて社会争点では極めて保守的で、白人や保守派と信仰ではむしろ結びついていた。だが、SNS時代の新世代は同世代の白人や異人種との人種横断的な交流を深めている。BLM(ブラック・ライブズ・マター)運動創設者の3名の黒人女性のうち2名がクィアを公言している8。中心人物アリシア・ガーザはトランスジェンダーの結婚相手の姓を名乗って活動している。BLMが古い意味での黒人運動ではないことを物語る。創設者はLGBTQ運動以外に労働運動にも関与していて、関心事は狭義の黒人の公民権ではない9。バーニー・サンダースは人種を区別せず、これが旧世代の黒人には面白くなかった。しかし、特別視しないことは軽視ではなく、むしろ経済的窮境にある黒人を具体的に救う情熱の表れだと解釈した黒人若年層が共鳴し、サンダース支持にも流れた10。新世代の黒人が共感性を人種横断で拡大することは、黒人の伝統を揺るがしかねない地殻変動だ。LGBTQは「名指し」よりも「名乗り」を重視した、「選ぶものとしてのアイデンティティ」であり、運命的かつ外見的な「名指し」に依拠した人種アイデンティティの再検討に繋がるからだ。
アメリカのエスニックをめぐる「部族主義」が1枚でも2枚でも脱皮できるとき、オバマ的な存在の意味が回顧される。そのときまでオバマは引き続き猫を被り続けて、「アメリカ黒人」として振る舞うだろう。オバマは白人家庭に育った子にして文化的にはアジア太平洋で、自ら貧困地域での活動や結婚を通して「黒人」になった。それこそ肌の色なんてたまたまのことでしかない。社会は肌の色で「名指し」することをやめないだろうが、それに従い「名乗り」の選択の多様性に歯止めをかける社会であれば、アメリカの多様性は窮屈な「部族主義」の代名詞でしかなくなる。
オバマの人生はある時期から、ひたすら「どうしたらアメリカ黒人になれるか」でもがく人生だった11。オバマ本来の複雑さをオバマ自身がどれだけ誇りに思っても周囲はそう捉えない。だからこそオバマは属性を一つ選ぶことにした。また、アメリカ社会で真に影響力を持つために、既存の縦割り属性内で認めてもらう必要性もあった。多民族社会アメリカに「どの属性にも当てはまらない」という属性が存在しない窮屈さを意味しているが、組織的には属性の認証がなければ、政治的に力を持つことはできない。精神的にも、どこかの属性の仲間にならなければ、心から受け入れられる心の安らぎを得られない。ジェイムズ・クロッペンバーグは記す。「世界のほとんどの場所で、バラク・オバマは、混合人種だとみなされている。アメリカでは、彼は、黒人であり、そして、その単純な事実と、それが含意するすべての事態の結果として、他者が彼に帰属させたり押しつけたりしているあらゆることから逃れられない」12
だから、オバマはアメリカの「黒人初」の大統領になったし、回顧録が政権記録としては「正史」にあたる。しかし、私人オバマとしての前半生は、筆者が『評伝バラク・オバマ』『大統領の条件』(集英社)で跡付けたように複雑な物語に満ちている。言い換えれば「アメリカからはみ出す」ことをめぐるマイノリティの息苦しさだ。選挙アウトリーチに象徴される「多様性の政治」は、既存のカテゴリーの縦割り強化の上塗りに陥り、既存の縦割りを越境するカテゴリー横断的な性質を持つ人間の本来の個性を否定する。ロナルド・サンドストロムが警鐘を鳴らすように、逆説的に「内なる排外主義」につながりかねない。サンドストロムは哲学者で黒人研究を専門にするが、自身も黒人、フィリピン系、白人の多人種ルーツを持ち、「周囲の期待が負担」だったと述べる。サンドストロムは、「十分に黒人か」という審査は「彼らは十分にXではないので、彼らはアメリカ人ではない」というゼノフォビアに転じていると警告する13。
オバマが象徴する人種問題とは、この縦割りカテゴリーの「建前の多様性」の偽善と矛盾のことであり、白人至上主義や人種差別の超克の問題だけに収まらない。それをほんの少しだけであるが、ハリス時代の黒人の新世代は前進させた。初の女性副大統領の人種属性を「黒人」だけに固定化せず、「南アジア系」との融合を認めたのである。無論、全ての多文化性が受け入れられたわけではない。アメリカの岩盤ともいえる、「ガラスの天井」としての壁は、人種ではなく宗教にある。ムスリムあるいは無神論者の大統領が誕生したら、それはもはやアメリカではないと考える保守的な市民もいる。
だが、漸進的な変化はある。オバマもトランプも信仰には敬虔ではなかった。オバマは組織的宗教の社会的な必要性を認めながらも、個人の信仰には冷めた目線を持っていた。トランプにとってのキリスト教は票田だった。
「多様性」のジレンマ
マイノリティ文化の中に「主流」と「亜流」が存在する構造は少数側にいないとわかりにくいが、善意の多様性の副作用は、アメリカの世界との接点にも顔をのぞかせることがある。アメリカ特有の「癖」に、海外をアメリカ国内の移民社会の延長で理解する思考がある。公民権に敏感な民主党やリベラル派に顕著で、逆に農村の保守派は新移民との接触機会が少ないので移民と外国が意識上は断絶しがちだ(しばしば排外主義の根にもなる)。本稿で引用した黒人の元オバマ政権高官の警句に戻れば、「部族主義」の弊害といえよう。
白人や他の先行移民に対抗するためにアジア系は「アジア太平洋諸島系」という国勢調査上の架空のエスニシティを政治的にはあてがった。本当は中華系ひとつとっても、清末の初期広東移民、中華民国期の移民、台湾アイデンティティの強い移民、大陸留学生の天安門事件による亡命者、非合法の労働移民、中国強国化後のエリート層など複雑であるし、西海岸でもサンフランシスコとロサンゼルスでは流派が違う。台湾移民は二重国籍と投票権を維持し、
2021年2月、駐大阪・神戸アメリカ総領事館が「春節2021」と旧正月を祝うツイートをしたことが一部で物議を醸した。
たしかにアジアでは旧暦の正月は広範に祝われる。ベトナムでもモンゴルでも旧正月を祝う。だが他方で、「春節」という表現は中華圏特有のものだ。しかもこれは大陸風の表現で、香港では「農暦新年」、台湾でもやはり「農暦年」「舊曆年」などと表現し、祝いの言葉も「恭賀新禧」「恭喜發財」で「春節」は滅多に使用しない。無論、総領事館のツイートはあくまで、「ダイバーシティ」への配慮を示したもので、その意図は「民族的背景を問わず、旧正月を祝う人々が日本や世界中にいることを認識」しているという総領事館の説明通りだ。良かれと思ってしたことが思わぬ反発を招いて途方に暮れている館員の姿が想像され気の毒だった。
世界には様々な暦があるが、網羅するならば内部の運用差にも習熟する必要が派生する。アメリカ国内で大掴みに「アジア系」に敬意を示す上では合格の表現も、域内文化に細かく照らせば「優遇」と「冷遇」に思わぬ政治的な含みを持たせかねない。英語ではChineseではなくLunar New Year(太陰暦)としていたことは幸いだった。
真のダイバーシティには、白人・男性・キリスト教徒とそうでない層との均衡だけでなく、マイノリティの中での多様性も鍵になる。オバマはそこまで一足飛びに超越しようとして空回りに終わった。アメリカ人には常に「属性」と「立場」が生じる。既存の「属性」に帰依して特定の都市に住めばそれがその人の「アメリカ」になる。地に足のついたリアルな当事者経験だが、俯瞰には適さない限定性がある。ユダヤ教のシナゴーグとカトリックの教会に同時に通うアメリカ人はいないし、結婚式以外で異人種、異教徒の行事を網羅的に経験することもない。保守系とリベラル系は互いの地域や家庭を知らない。英語の下にある家庭使用言語の多言語地層も深い。
しかし、外国人ならば別だ。複数の属性に来訪して観察することが許される。越境的な観察者としての外国人の地域研究の意義もここにある。外国人研究者としてアメリカに接してきた筆者が、オバマに妙な親近感と共に哀しみの感情を抱くのは、彼が何を黙ることにしているか理解できる気もするからだ。オバマは今でも、「アウトサイダー」のままだ。
結語にかえて
アメリカは世界で最も多様な人種や民族の共存という社会実験を現在進行形で行なっている。奴隷の子孫と先住民と共に、悲劇を抱きしめながら「統合」を目指してきた。これだけの規模の共存に挑戦している社会の諸問題を、同様の経験を有しない社会の物差しで断罪することには慎重であらねばならない。差別や対立の問題は、総じて当該社会の歴史や文脈によって意味づけられているからだ。
ホワイトハウスの住人になった「黒人」が2名続けて、バイレイシャルだったことは偶然だろうか。ピュアなアメリカ黒人は白人に脅威を与えるからか。それとも複数の異文化を内に秘めた政治家は、「名指し」と「名乗り」に敏感だから、自己ブランディングや演説に得意になるからか。運命的に黒人になった人物と違って、自ら掴みとった「名乗り」の「黒人性」への覚悟は、宿命としての政治への責任感をより焚きつけるのかもしれない。
オバマとハリスのホワイトハウス入りをもってしても、真の黒人大統領・副大統領いまだ誕生せずと考える黒人はいる。だが、古い意味での「真の黒人」を飛び越えて、多人種系の黒人が代表に選ばれたことの価値をむしろ噛み締めてみたい。「血の一滴」が入っていれば、黒人側を選ぶ選択肢しかないし、公民権運動を支持したジョンソン政権以降、黒人の民主党支持は自動化されている。仮に、黒人とのマルチレイシャルなのに黒人属性を単一で名乗らず、それでも「脱人種」的ではなく人種差別と先頭で闘う候補が現れたとして、その人物をマイノリティの有権者が率先して抱擁したら、そのときこそアメリカの人種問題は次の出口に到達するに違いない。
しかし、しばしばアメリカで起きる白人警官による暴力事件で、人種差別の根深さに直面するたびに、その選択もまだ遠い未来のことになるのだろうと悲観的な思いにもさせられるのだ。
(了)
- Asian and Pacific Islander Americans in Congress: 1900-2017, U. S. Government Publishing Office (January, 2017) (本文に戻る)
- Chittal, Nisha, “The Kamala Harris identity debate shows how America still struggles to talk about multiracial people: Identity is complicated, and she shouldn't have to choose just one", Jan 20, 2021, Vox, <https://www.vox.com/identities/2020/8/14/21366307/kamala-harris-black-south-asian-indian-identity>(本文に戻る)
- 渡辺将人『現代アメリカ選挙の変貌―アウトリーチ・政党・デモクラシー』名古屋大学出版会(2016年)(本文に戻る)
- Obama, Barack, A Promised Land, New York: Crown, 2020.(『約束の地 上・下』集英社2021年)(本文に戻る)
- 渡辺将人『評伝バラク・オバマ―「越境」する大統領』(集英社2009年)、Remnick, David, The Bridge: The Life and Rise of Barack Obama, Knopf, 2011.(石井栄司訳『懸け橋:オバマとブラック・ポリティクス』白水社2014年)(本文に戻る)
- 古矢旬『グローバル時代のアメリカ:冷戦期から21世紀シリーズ アメリカ合衆国④』(岩波新書2020年)(本文に戻る)
- Obama, Barack, A Promised Land, New York: Crown, 2020.(『約束の地 上・下』集英社2021年) 2024.(本文に戻る)
- 川坂和義「全ての人が自由になるまで誰も自由にはなれない:クィア・ムーブメントと人種とジェンダー・セクシュアリティの交差」『現代思想』2020年10月臨時増刊号総特集=ブラック・ライヴズ・マター」、58-65頁。(本文に戻る)
- Sony Salzman, “From the start, Black Lives Matter has been about LGBTQ lives—Two of three Black Lives Matter founders identify as queer.” abc news, June 21,2020, <https://abcnews.go.com/US/start-black-lives-matter-lgbtq-lives/story?id=71320450> (本文に戻る)
- David Frum, “Bernie Can’t Win—But unless other Democrats take a page from his book—stressing the practical over the theoretical, the universal over the particular—they won’t prevail either.” The Atalantic, January 27,2020, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/bernie-sanderss-biggest-challenges/605500/>> (本文に戻る)
- 渡辺将人「オバマ時代に凍結された「人種」という難題:『評伝バラク・オバマ』執筆から11年目の「取材後記」として」『現代思想』2020年10月臨時増刊「総特集=ブラック・ライヴズ・マター」、292-298頁。(本文に戻る)
- 古矢旬・中野勝郎訳『オバマを読む─アメリカ政治思想の文脈』岩波書店2012年(本文に戻る)
- Sundstorm, Ronald R., “Kamala Harris, multiracial identity, and the fantasy of a post-racial America” Vox, Jan 20, 2021 <https://www.vox.com/first-person/22230854/kamala-harris-inauguration-mixed-race-biracial>
Lim, Dion, “Being mixed-race in America: From Kamala Harris to Tiger Woods, experts explain meaning of identity” ABC 7 News, <https://abc7news.com/race-mixed-race-identity-how-do-you-identify/6441954/>> (本文に戻る)