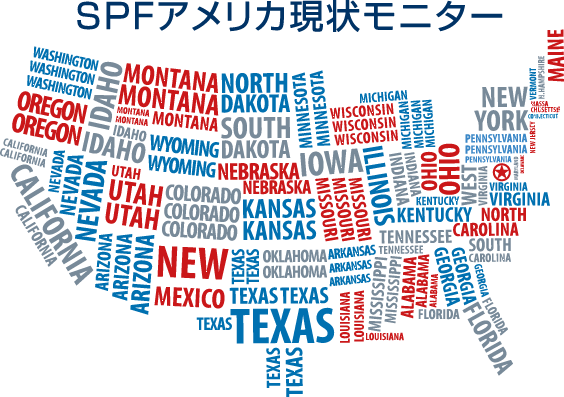2024年、予備選はあってなきが如し?:
本選は異例の「大統領」同士のリマッチ(再対戦)に

渡辺 将人
現職再選年でも「ドラマ」があった過去の予備選挙
アメリカの大統領選挙には「面白い年」と「面白くない年」が明確にある。もちろん「面白い」の定義にもよるが、同時代的な高揚感をもたらす候補者の意外性、そして(アメリカの選挙の真骨頂は党内バトルに凝縮されているので)予備選で多数の候補が接戦を繰り広げるかも基準になる。
現職が2期目を狙う再選選挙年は、現職側の政党ではシリアスな挑戦者が出て来ずほとんど予備選がない。1990年代以降の再選選挙は1992(ブッシュ父再選失敗)、1996(クリントン再選)、2004(ブッシュ息子再選)、2012(オバマ再選)、2020(トランプ再選失敗)。いずれも、現職側の予備選挙は無風に等しかった。
しかし、片方側だけでも十分に「ドラマ」はあった。
1992年民主党予備選では不倫から徴兵回避までスキャンダルの雪だるまになったビル・クリントンがしぶとく「カムバック」する過程はドラマに満ちていた。しかも、この年は第三候補のロス・ペローが民主党予備選に並行してメディアを賑わした。
1996年共和党の候補は重鎮ボブ・ドール上院議員で本選は予定調和的なつまらなさを象徴した選挙だったが、共和党予備選では『フォーブス』誌創刊者の孫スティーブ・フォーブス、右派イデオローグでトランプ派の精神的な起源でもあるパット・ブキャナンなどが大暴れした。
2004年民主党予備選ではバーモント州知事の左派ハワード・ディーンが初戦のアイオワ党員集会に向けて、オバマ陣営が後に真似た黎明期のSNS草の根組織を初めて構築した。いわばオンライン選挙技術史的に転換点になった予備選である。
2012年共和党予備選は、ティーパーティ旋風後最初の大統領選で、ミシェル・バックマンやロン・ポールなどティーパーティ派やリバタリアンが台頭し、ポールは3位につけた。隠れテーマはモルモン教(ミット・ロムニー)への反発というキリスト教内の宗教対立で、だからこそキリスト教右派に近いリック・サントラム元上院議員が「反モルモン/反ロムニー」票を集めて2位と大健闘した。財政保守、社会保守の双方にとって、ポスト9/11の「保守運動元年」的な予備選で、トランプ運動の源流が生まれた選挙年だ。
2020年民主党予備選は左派反乱の年で、バーニー・サンダースとエリザベス・ウォーレンが2巨頭的に善戦し、中道派は壊滅状態だった。バイデンに至ってはアイオワで最下位をウロウロし、中道派の強引な一本化工作とサンダース派への泣き入れの「手打ち」で辛勝した。
どの選挙も、予備選にこそドラマがあり、その予備選での勝ち方・負け方、指名の獲得の仕方が、本選での勝敗やと政権運営上の方向性や制約などのあり方に影響を与えた。その意味で言えば、2024年ほどつまらない選挙はない。2024年は事実上「予備選挙はあってなきが如し」であったという気すらする。
予備選挙が盛り上がらなかった3つの理由
2024年予備選挙にあっという間にけりがついたのは3つの理由によるだろう。
1:アイオワの共和党党員集会で、特定候補(トランプ)が早々に単独過半数をとってしまった。緒戦のアイオワとニューハンプシャーで勝者が割れ、その後も戦いがもつれ込むのが常で、いずれの年でもアイオワで単独候補が50%以上を獲得することはなかった。初戦でここまで特定の候補に独走されることに後続州の有権者は慣れていない。票を分散させる動機すら失せてしまう。
2:共和党候補に撤退者が続出し、候補者数が早々に絞られてしまった。トランプは後述するように「事実上の現職候補」である。「現職」に刃向かうハードルは高い。ハードルが高ければ撤退を誘発する。撤退して候補者が少なくなれば、単独候補の過半数が生まれやすくなる。そもそもが、今回の共和党予備選を通常のオープンな戦いとして論評するのは間違いであり、(一度お休みしている)「現職」が再選を目指している選挙と捉え直せば、諸現象がクリアカットに見えてくる。
3:民主党側で分裂が起きず、大統領への手強い内部挑戦者が出なかった。民主党側でバイデン下ろしが本格化すれば、民主党側で予備選が混戦化した可能性はあるし、それが共和党側に甚大な影響を与えたはずだ。バイデンが2期目を目指せなくなれば、バイデンとセットの「ハリス大統領」誕生も現実味を失った。バイデン再選より共和党が怖れるのは、不測の事態の繰り上がりでリーダーシップに問題があると彼らが考える人間が大統領になることだ。共和党穏健派が渋々トランプを許容するのはバイデン=ハリス阻止が課題だからでもあった。また、民主党候補が先手で「若返り」をすれば、トランプだけが高齢候補になり、共和党にも若返りの切迫感が生まれた。しかし、パレスチナを擁護する反戦デモの広がりにもかかわらず、民主党内での挑戦は起きなかった。間接的にトランプの勝利を支えたのは、バイデンの無風勝利を許した民主党だとも言える。
「1期大統領」で終わることの不名誉とトランプ
今年は事実上の「現職対決」だ。トランプは厳密には現職ではないが、大統領職ではバイデンの1つ先輩である(ホワイトハウス経験は副大統領を2期務めたバイデンが先輩であっても)。
トランプの敗北は、近年1期で敗北したカーターや父ブッシュとは異なり、勝利して選挙人を獲得できると見込んでいたいくつかの州では比較的僅差だった。それらの州の多くで「何らかの不正があった」とトランプと支持者が考えているならば、むしろ再出馬で勝利することで正当性を証明しようとするのは自然だ。
1期敗北を受け入れられるかは性格の問題もある。再選に失敗した大統領に国民は冷たい。1期目の否定は、すなわち「間違った人間を大統領にしてしまった」という国民の後悔の審判として刻印される。この不名誉は元大統領の威厳すら相殺する力がある。だから、アメリカの大統領は、1期大統領と2期大統領の間には、権威的に大きな質的差がある。「〜時代」と名がつくのも通常2期務めた場合からだ。
カーターと父ブッシュは伝統的な政治家で、1期でお払い箱にされた日陰者の「身の処し方」を自覚していた。だが、トランプは実業家である。ワシントンの慣習に沿って「1期大統領は消えゆく身」で終わることを潔しとしなかった。2期目で何をやるかではなく、B級カテゴリーにされる1期大統領で終わりたくない、という強い執念を感じさせる。
民主党側もバイデンが「1期大統領」の腹を決めていれば、政局になっていた。民主党内でカマラ・ハリスをそのまま無風で大統領候補に望む勢力は皆無と言ってもいいからだ。ハリスの支持基盤になるべき女性、黒人、アジア系がそもそも彼女を一枚岩で支持していない。女性団体に至ってはハリス攻撃の震源である。
しかし、側近らが引退説得に失敗し、バイデン本人が2期目を目指すと言い出したことで、民主党内で刃向かうのは異色の第3候補的な候補に限定され、本命に近い候補は出馬を控えた。しかも、トランプが再出馬した上に共和党で勝利したことで、サンダース派や「スクワッド」派(女性4人組の新世代左派下院議員)などが反乱を起こせなくなった。ケネディJr.の挑戦は面白いが、ああいう人物は既存政党の指名を獲得できない。アメリカの現行制度では難しい。
こうして、歴史的にも極めて珍しい、「大統領職の経験者同士の対決」が発生した。
有権者心理として、4年前に「我が英雄」を抹殺した敵を倒すために「我が英雄」が再出馬するのであれば、支持熱は高まる。英雄に2期目を与えたい情熱以上に、英雄から勝利を「盗んだ」憎き相手への仕返しだ。相手がバイデンだからこそ復讐心は燃えたぎる。民主党の選択がトランプ熱をむしろ焚き付けている。
今年の共和党候補者には不運でしかないが、トランプが再出馬を表明し、バイデンが再選の意向を固めた時点で、ある意味では予備選はかなりの程度終わってしまった。決定打になったのは次回以降の寄稿で言及するイスラエルとハマスの衝突で、これが「ゲームチェンジャー」となり共和党内のトランプ収斂が加速した。
1892年以来初めての大統領経験者同士の「リマッチ」
さて、今回の本選には3つの異例がある。
第1に、大統領選に再出馬する元アメリカ大統領は歴史上存在するが、数はそう多くはないことだ。過去に6名。ヴァン・ビューレン、フィルモア、グラント、クリーブランド、セオドア・ルーズベルト、フーバーである。トランプ以前では84年前(1940年)のフーバーの挑戦まで遡らないといけない。元大統領の再挑戦の勝率は芳しくなく、6名のうちクリーブランドだけが再び大統領になることに成功し、 他のほとんどは政党の指名獲得にすら失敗している(一部は第3党的な政党で指名獲得)。
第2に、同じ座組での対戦すなわち「リマッチ」であることの珍しさだ。直近でも約70年前のアイゼンハワーの対戦に遡る。「トランプ対バイデン」(2020年、2024年)以前は以下の6つのケースがあった。
- ジョン・アダムズ vs. トーマス・ジェファーソン(1796年、1800年)
- ジョン・クインシー・アダムズ vs. アンドリュー・ジャクソン(1824年、1828年)
- マーティン・ヴァン・ビューレン vs. ウィリアム・ヘンリー・ハリソン(1836年、1840年)
- グローバー・クリーブランド vs. ベンジャミン・ハリソン(1888年、1892年)
- ウィリアム・マッキンリー vs. ウィリアム・ジェニングス・ブライアン(1896年、1900年)
- ドワイト・D・アイゼンハワー vs. アドレイ・スティーブンソン(1952年、1956年)
19世紀当時は参政権が今ほど拡充しておらず、移民の多様化以前、さらにテレビもなかった。今はエスニシティも多様なら、テレビどころかネットもある。こういう時代に大統領職の経験者同士が同じ顔ぶれで「リマッチ」する。有権者心理も選挙キャンペーンの方法も何もかもが前代未聞である。
2名の「1期大統領」が2期目を争う異様な構図の功罪
トランプとバイデンには、もうあまり語ることがない。だからこそ、トランプになったらどうなる、バイデンが再選されたらどうなる、という「先読み」に報道が集中していると言える。本来であれば、候補者同士のキャラクター問題ではなく、政策論争を深める最大の機会でもある。しかし、実際にはそうはなっていない。
事実上両党「無風」の予備選(スーパーチューズデーで本格的な特番や特集を組む必要がないほど「無風」加減が際立っている)。同じ顔ぶれのしかも大統領経験者どうしの「リマッチ」。この耐え難くつまらない大統領選は、このままつまらないまま終わるのだろうか。
今回は面白さの質がいつもと違う、と前向きに見てみても良い。通常の大統領選挙では片方が「自分が大統領になれれば」という演説をする。しかし、今回は両方が「現職の再選」を目指す演説をする。1期目の成果・失政への原罪や攻撃を受ける脛の傷も同じだ。通常は「俺が大統領をやらせてもらえれば」「お前には務まらない」の応酬になるのに、「俺の政権ではこうだった。それに比べてお前の政権は」と「大統領(元・現)」同士がディベートする異様な光景になる。
この状況で議論を深めるには、両者への質問の当て方やメディアの議題設定の仕方を、大統領同士の戦いにシフトさせないといけない。しかし、トランプ叩きとバイデン叩きしか能がないワシントンの党派的な米メディアは、あいも変わらず、同じいつもの競馬レースとスキャンダル取材を繰り広げている。両方の候補者に「大統領としての失敗」の責任を問える珍しい選挙なのに、これではせっかくの異例のリマッチがいい試合にはならない。
無論、予備選挙は終わったようで終わっていない、という見方もある。この予備選結果のままで本選が行われるか、不確実性が例年とは桁違いだからだ。起訴されたり、健康状態に不安説があったり、党大会までに「何か」が双方で起きれば、指名争いは白紙に戻る。その意味でも「面白くない」ことも含めて、何もかもが異例の年である。
混乱の民主党シカゴ党大会の再現になるのか:「ベトナム反戦」のような空気感?
異例の年を更に複雑にしている最新の変数が、全米各地の大学キャンパスでイスラエルのガザ攻撃に対する抗議デモが相次いでいることだ。これは民主党を分断させ、痛手となる可能性がある。
一つの鍵はガザ攻撃には嫌悪感を抱くが大学デモには両手をあげて賛同していない遠巻きの「民主党内一般市民」と無党派層だ。この種のデモが社会で起きると、デモは参加もしないし、メディアのインタビューで意見表明もしないが、心の中では密かに応援している層も必ずいる。しかし、例えば大学以外の場にデモが拡大した場合、空港、地下鉄などインフラを危険な「戦闘の場」にされたりバリケードを張られたり、日常や商業活動を妨害されて一般市民の生活を不便にする抗議方法に拡大すれば、デモに対する「見えない共感層」も離反することがある。
デモ参加者だけがマージナルな存在として疎外されていく場合、民主党の主流政治家は彼らが民主党で中心的な勢力とならないように排除の論理を働かせるだろうが、「民主党内一般市民」と無党派層への影響を見極めるのは難しい。
バイデン陣営は「反トランプ」一致結束で、左派離反を抑え込んだものの、夏が過ぎても抗議活動が続くようであれば、ベトナム反戦運動の活動家が乱入して大混乱になった1968年大会と同じくシカゴ開催になる民主党大会が荒れるのではないか、との懸念も民主党内部にある。この動きに戦々恐々しているのは、バイデンに「何か」あった場合に名乗りをあげる構えのカリフォルニア州知事のギャビン・ニューサムらである。反戦デモで党内分裂状態の民主党を引き継いでも、支持を固められる保証がない。
ベトナム反戦運動当時との違いにも留意が必要だ。
第1に、真ん中不在の分極化が先鋭化している政治状況だ。ベトナム戦争当時の左派は、活動家としては活発に組織化されていても、議会民主党など党内レベルではあくまでフリンジ(中心ではない縁)だった。今では主流を動かす影響力を持っている。フリンジが動きを起こしても、それは「押さえ込む対象」でしかなかったが、今はその活動のエネルギーが政党全体を乗っ取るだけの力を持ち得る。左派の英雄的な政治家が公に後押しすれば運動自体が党内分断の火種として残る。バイデン政権、バイデン陣営には頭の痛い問題になる。
第2に、ソーシャルメディア時代に起きるデモの影響の派生形の違いだ。2000年代半ばのイラク反戦運動は、初めてのネット時代の大規模な反戦運動だった。しかし、SNSスマホ時代の反戦運動となると今回が初めてである。相互の罵り合い、現地の凄惨な画像・動画、「偽情報」含め入り乱れる。キャンパスでの学生や教員の逮捕動画も報道されているが、同情のリポストと同時に、デモを揶揄する書き込みでコメント欄はすぐ埋まる。
ベトナム戦争は戦場の様子もデモも、メディア報道で断片的に全米の視聴者は目撃した。しかも、ベトナム戦争報道はフィルムを東京に運びそこからニューヨークに送るという手間のかかり方で戦場の映像はかなりの時間差で伝わった。現代の「この瞬間に爆撃が起きている」という同時共有感とは違う。
さらに戦争やデモへの賛否まで今はコメントで目に入る。SNSは基本的には違う意見に触れにくい原理を帯びてはいるが、たまに異論に触れても「これは一理ある」と自説を修正する前向きな機会になる作用は稀だ。むしろ、同じ現象や動画を見てもこんな真反対の反応をする人が同じアメリカ人にいるとは信じ難いという嫌悪感を増幅し、それがまた相手側への憎悪や対立感情を掻き立てる。戦争報道や一部の学生のデモ映像をメディアが流して、それをただ「鑑賞」していた時代とは違う。現場の一般撮影の動画がSNSに流れ、コメント込みで消費は膨らんでいく。上記のように一般市民の戦争自体への賛否と、大学デモへの賛否は微妙に違う。「場外戦」込みで対立意見が拡散し、自説や自らのポストに冷静さを欠いたコメントが付けられれば反感が湧くし、熟議なきままに分断だけが深まる。それは当然、様々な海外勢力を利する分断にもなる。選挙年なら尚更である。
第3に、今回のデモにはアメリカ国内のエスニック対立が絡んでいることだ。単なる「反戦」あるいは「反テロ」を訴えるものではなく、親イスラエル(デモへの反発)・親パレスチナ(デモ応援)の分断が色濃く、「反ユダヤ主義」をめぐる問題などポリティカル・コレクトネスも絡む。ジェノサイド批判や停戦がメッセージではあるが、パレスチナの旗とパレスチナにシンパシーを示すコスチュームがセットになり、反対側もイスラエルの旗を振る。UCバークレー、ウィスコンシン大学マディソン校など全米にはリベラルで学生が政治的な大学は山ほどある。しかし、今回の大学デモがコロンビア大学とニューヨーク大学という、2つのマンハッタンの大学で中心的に先鋭化したのは、これほどまでに凝縮された近い範囲でパレスチナ系、ユダヤ系、キリスト教徒やそれ以外のエスニック集団が量的に大規模に存在し、普段からある種の緊張関係にある地域はアメリカで他にないからだ。これは「反戦デモ」である以上にエスニック対立であり、海外ルーツ元の代理言論戦である。その意味で極めてアメリカ的でもある。また、これも付随的ではあるが、大学が警察を招き入れたことで警察官をめぐる賛否も分断の象徴になっている。黒人を含む現場の警官の職務執行を応援する立場と、マイノリティへの過剰暴力事件を定期的に起こす警官を悪魔化する声がますます分断を煽る。
「反トランプ」での結束を促すだけで、バイデン陣営と民主党連合がもつのか。予断を許さない状況が続く。
(了)