「イスラエルに未来はあるのか?」
―ガザ紛争をめぐる国内対立を克服するために―

山岸 敬和
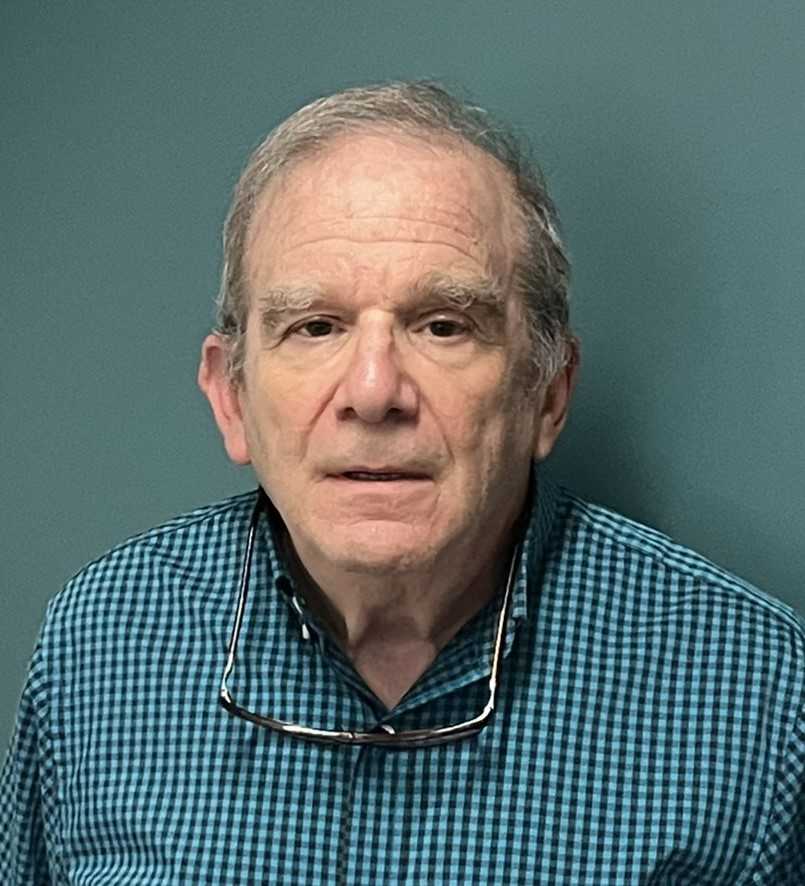
Steven David ジョンズ・ホプキンス大学教授
1981年から40年以上にわたってジョンズ・ホプキンス大学で政治学を教えてきた Steven David1。安全保障研究、発展途上国の政治、アメリカの外交政策、中東研究が主な研究対象である。彼はユダヤ系アメリカ人の教授でありながら、2016年から「Does Israel Have a Future? (イスラエルに未来はあるのか?)」というクラスを教え、その中でイスラエルの存在を批判的に議論する機会を学生に提供してきた2。そのクラスは特にガザ紛争が勃発してから米国内で話題となった3。ガザ紛争は、アメリカの大学において停戦を求めるデモを引き起こし多くの逮捕者を出した。さらに、親パレスチナ運動の広がりに対抗する形で親イスラエルのデモも起こり、両者間の暴力事件も起こるほどに対立は激化していった。特に反ユダヤ人感情の高まり、それに伴うユダヤ人に対する暴力行為はアメリカのみならず日本でも報道されている。
本コラムは、2024年10月31日に現地で行われたこのSteven Davidへのインタビューを基に構成されている4。まず、Davidから見た今回のガザ紛争の歴史的意味についてまとめる。そして、現在彼が教えている上記のクラスについて、その目的と、ガザ紛争がクラスの内容に与えた影響についての話をまとめる。最後に、ガザ紛争のような社会を分断する争点に直面した時に、大学としてどのような役割を果たすべきかについて論じたい。
イスラエルが置かれた政治環境
Davidはイスラエルの国家安全保障戦略について、その変化の背景を国内と国外の両面から見てきた。インタビューでは、過去40年間研究してきて、どのようなことが予想外であったのかについてまず聞いた。彼は国内的要因について以下のように答えた。「イスラエルの国内政治が右に急速に偏っていったことは予想外でしたし、とても残念に思っています。パレスチナ自治区にあるイスラエル人による入植地の住民の支持を基盤とした政党や、ユダヤ教の宗教団体からの影響が大きくなっています」(1967年の第3次中東戦争でイスラエルが占領した地域には、イスラエル人が入植しており、その数は約72万人となっているが、この入植は国際法違反であると指摘されている)5。
Davidはこの右傾化の動きはイスラエルの国としての本質に変化をもたらすと警告を鳴らす。「これはイスラエルの民主主義に危険をもたらすと思います。イスラエルには憲法がありません。その意味では、個人の自由や権利は司法府が守っていたと言えます。しかし急進的右派勢力は司法の力を減退させてきました。多くのイスラエル人はこれに抵抗していますが、この動きが続けば神権政治に陥ってしまいます。そうなれば本当に危険です」。
次にイスラエルの国家安全保障戦略を取り巻く国外要因について予想外の出来事だったことは何か聞いた。「今回のハマスの攻撃が一番大きな驚きだったことは間違いありません。ハマスはイスラエル南部を襲撃し、民間人を中心に1200人以上が殺害され、また約250人が拉致されました。この出来事が、イスラエルの民主主義を取り巻く環境に甚大な影響を与えました」。
続いてDavidは、アメリカ国内の対イスラエル政策をめぐる政治状況について話した。「アメリカ国内のユダヤ人コミュニティを見れば、全体的にイスラエルへの支持は弱まってきていると言えます。民主党は少しずつイスラエルに対して批判的になってきていますが、共和党は一貫して親イスラエルです。これは皮肉なことです。なぜならば、70%のユダヤ人が民主党支持だからです。大多数のユダヤ人がイスラエルに対する厳しい姿勢を強めている政党に与しているからです」。
これに続いて、Davidはユダヤ人についてのアメリカにおける誤解について言及した。「多くの人々はユダヤ人の影響力を過大評価し過ぎていると思っています。人口比で言えばたった2.4%で、7%を超えるアジア系と比べるととても少ないのです」。
Davidは続けてイスラエルの国としての特殊性を強調する。「イスラエルは、その存在自体、国として存在すべきかどうかを常に問われる世界の唯一の国であると言えるのではないでしょうか。アメリカはイラクに侵攻し、ロシアもウクライナに侵攻し、これらは「悪事」だと言えるでしょう。しかし、アメリカやロシアは存在すべきでなかった、存在すべきではないという議論になりません。他方で、イスラエルが悪事をはたらくと、イスラエルは存在する権利がないという議論になります」。
「イスラエルに未来はあるのか?」という科目
以上のようなイスラエルの国としての特殊性も念頭に置きながら、Davidは「イスラエルに未来はあるのか?」というクラスをジョンズ・ホプキンス大学で教え始めた6。彼自身は、イスラエルは国として存在する権利があるという明確な立場を持っている。そこで、そのようなバイアスを持った教員が教えることの難しさはないのかを聞いた。「私がユダヤ人であることはクラスの最初に明確に伝えます。私にも偏見や自分の見解がありますが、私の意見に反対だからと言ってペナルティを課すことはないと明言しています。授業では私が完全に同意しないような主張を行う論文等も読みます」。
イスラム教徒、ユダヤ人、アジア系、その他世界各国からの留学生もこのクラスを履修するという。Davidにこのクラスを教えてみて感じたことを聞いた。「学生は政治運動に参加する時には互いにスローガンを叫びあっていますが、自分が話していることについてほとんど知らない学生が多いと思います。特に問題の歴史的背景については無知であることが多いです。どのような経緯で現在に至っているのかを知るために歴史を学ぶことは重要で、さらに歴史を通じで様々な見方があることを知る必要があると思います」。
今回のガザ紛争によって議論が過激化することはなかったのかも聞いてみた。「クラスの中で泣いてしまった学生は複数人いました。このクラスでは学生がとても感情的になることがあり、普通の政治学のクラスではありません。ガザで戦闘に加わっているイスラエルの兵士を親戚に持つ学生がいましたし、家族がガザに住んでいる学生もいました。彼らはクラスの中で特に感情的になりますが、それ自体私は良いことだと思っています。イスラエルやガザに全く関係を持たないアメリカ人、そして留学生たちが、そのような人々の感情に接するというのはとても貴重なことだと思います。誰もクラスの中で大声を出しませんし、クラスメートを侮辱するようなこともしません。ネタニヤフ政権やハマスを批判すること自体はいいですが、それがイスラエル人は嫌いとか、イスラム教徒は嫌いだとか、そういうことにつながってしまったら、それはもう人種差別だと言えます」。
政治的対立を埋めるために大学ができること
Davidのクラスでは、一週間ごとにテーマを決めて、その問題についてさまざまな角度で議論した文献を学生に読ませる。例えば「イスラエルの正当性を否定するような国際的な動きは不公平で反ユダヤ主義的である」というテーマもある。学生はテーマについての文献を読み、授業時間までに賛否どちらの立場を取るのかを決めておく。Davidはクラスの冒頭に学生がとる立場を聞き、学生には敢えて反対の立場に立たせてディベートのような議論を進める。そうすることで、相手の立場についての理解を深めることができるのだという。
Davidが教える「イスラエルに未来はあるのか?」のような野心的なクラスはアメリカ国内にあまり存在しないだろう。学生が指摘するように、ジョンズ・ホプキンス大学のホームウッドキャンパスは学部生約5,000人と小規模で、メディカルスクールに進学する学生が多いこともあり、政治的活動があまり活発でないと言われている。だからこそDavidのクラスが可能なのかもしれない。また、そもそも過激な意見を持つ学生はこのようなクラスは取らないだろうという、参加学生の指摘もある程度合っているだろう7。
しかし、明確な分断を生み出す争点についても、一定の期間に毎週顔を合わせて一緒に勉強するという機会は分断を修復する試みをする上で重要である。Davidの口から何度も「civil(市民的な、礼節を重んじて)」という言葉が出てきた。学生が感情を持ちそれを表現するのは良い。しかしそれが「hostility(敵意)」になってしまったらいけない。どんなに難しい政治問題であっても、大学という組織は、「civil」に議論するための空間、時間、知識を提供するために重要な存在なのである。
アメリカの総合大学ではたいてい政治学科があるが、日本では政治学科を持っている大学は限られている。またアメリカでは自国の政治について学ぶクラスが必修科目になっている大学が多い。だからこそアメリカのキャンパスで学生による政治活動が活発になるのだろうが、他方で大学は分断を埋めるための機会も生まれやすい環境なのだと思う。トランプ政権二期目では、再び高等教育に対する政治的攻撃が強まることが予想される。トランプ主義が今後も続くことが明白である中、政治的分断に対して、大学という組織がどのような役割を果たしていくのかについては注目していきたい。
(了)
- 経歴や業績については以下を参照。Johns Hopkins Krieger School of Arts and Sciences,” Department of Political Science,” <https://politicalscience.jhu.edu/directory/steven-david/>, accessed November 10, 2024. (本文に戻る)
- Aleyna Rentz, “Johns Hopkins Professor, Students Debate Israel’s Future,” Johns Hopkins University Hub, May 16, 2024, <https://hub.jhu.edu/2024/05/16/steven-david-qa/?fbclid=IwY2xjawGQe69leHRuA2FlbQIxMAABHVnVRPXNIZ-5arDCzv_TrLEBojWmi9uANEcK74e574C0eSusbzYU3Zagcg_aem_NnApj9yz7F84jluEZAwRrw>, accessed on November 10, 2024.(本文に戻る)
- Beth McMurtrie, “Debating Israel’s Future, One Week at a Time,” The Chronicle of Higher Education, April 30, 2024, <https://www.chronicle.com/article/debating-israels-future-one-week-at-a-time>, accessed on November 12, 2024. (本文に戻る)
- Steven Davidへの聞き取り調査は、2024年10月31日にジョンズ・ホプキンス大学のメインキャンパスであるホームウッドキャンパスで行われた。同キャンパスはメリーランド州ボルティモア市にある。ボルティモア市には医学部や公衆衛生学部が入ったメディカルキャンパスが別にある。その他にも高等国際関係大学院(SAIS)が入るワシントンDCキャンパスがある。(本文に戻る)
- 真野啓太「イスラエル入植地とは—『国際法違反』の批判にも止まらぬ拡大なぜ」『朝日新聞』2024年5月24日、<https://digital.asahi.com/articles/ASS5J3H0NS5JUHBI00YM.html>、accessed on November 13, 2024.(本文に戻る)
- 日本では「政治学」「社会学」など、汎用性がある科目名がつけられることが多いが、ジョンズ・ホプキンス大学や多くの大学では、特に上学年向けのクラスでは、クラスの内容が明確にわかる科目名が付けられていることが多い。(本文に戻る)
- Beth McMurtrie, “Debating Israel’s Future, One Week at a Time.”(本文に戻る)


