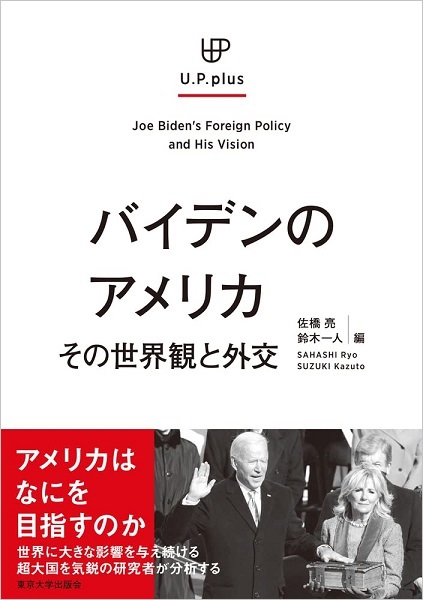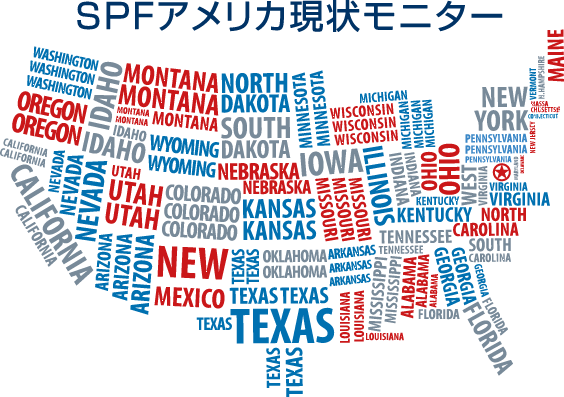追悼:中山俊宏教授が拓いたアメリカ政治「3つの往復」

渡辺 将人
今年5月に急逝された中山俊宏慶應義塾大学教授を偲ぶ会が、関係者を招いて9月11日にしめやかに行われた。「中山俊宏とアメリカ」と題された記念シンポジウムでは、中山教授のお仕事やお人柄に親しんできた関係者から、中山先生の広範かつ奥の深い業績が多角的に共有され、貴重な機会となった。中山教授が座長として牽引された本プロジェクト「アメリカ現状モニター」のメンバーも複数登壇した。モデレーターとして森聡慶應義塾大学教授、パネリストとして渡部恒雄笹川平和財団上席研究員および筆者が登壇した。
本稿は、渡部恒雄著「故中山俊宏教授が示した日米同盟における価値観とは?」(『アメリカ現状モニター』No.123)に続く、中山先生を偲ぶ追悼の寄稿であるが、非公開式典の性格と諸般の事情により関係者へのプライバシー等に配慮する形で、筆者のシンポジウム報告に一部修正を加え改稿した。
******
中山教授はご専門のアメリカ政治をめぐる「3つの往復」に尽力された先駆者であった、というのが筆者の中山先生の業績をめぐる所感である。
1:内政と外交の往復:統合的に政権の「思想」を知覚するアメリカ政治分析
第1に内政と外交の往復である。
中山先生は、内政と外交を横断的にダイナミックに手掛けることでアメリカ政治の「地殻変動」を探求された研究者だった。中山先生のアメリカ政治への関心は、狭義の内政と外交の形式的な分類にはおよそ収まりきらないものであったが、歴史や思想を土台に、政治を動かす為政者の脳内に入り込んでいくことで人間像を根底から解き明かす手法でもあり、筆者も多大な影響を受けた。先生は筆者の政治家評伝を有難いことに面白がってくださったが、それは中山先生の手法に学んでいる筆者の中にご自身との類似性をご覧になったからではなかったかと今では思っている。
トランプ政権期以降、ますます「外交の内政化」「内政要因の外交への拡張」が日常化している。バイデン政権においても労働者利益を重視した外交を謳う「中間層外交」が掲げられている。いわば外交分析と内政分析における事象の過程と要因をめぐる境界が、従来の外交と内政の枠を乗り越えているような現状にあって、アメリカ政治外交の研究者の役割も変容を迫られている。内政を見ないと外交を明らかにできず、外交を視野に入れねば内政研究も深められない。本プロジェクトのメンバーを務める森聡教授とも別のシンクタンクで意見交換した問題意識であった。無論、専門領域や方法論に誠実で慎重であれば抑制的になる部分であるが、アメリカ共産党の研究で博士論文を書かれている中山先生は最初から「内政」「外交」という峻別に馴染むアメリカ政治研究を志向しておらず、いわば内政と外交の往復におけるロールモデル的な先駆者だったのではないだろうか。今年4月に刊行された『バイデンのアメリカ』(鈴木一人・佐橋亮編、東京大学出版会、2022年)に所収された中山先生論文「バイデンの非・世界観外交」が中山先生の遺作となったが、ここでも先生は外交と内政の地続きを前提にバイデン政権に潜む性格の「絵解き」を披露された。
筆者にとっても中山先生と最後の共著となった。
その中山先生のスタイルが如実に現れた先駆的な業績が、NTT出版から2012年に刊行された『オバマ・アメリカ・世界』という、中山先生と久保文明先生と筆者の3人の論考と鼎談をミックスしてオバマ政権1期目の性格を占う異色の共著であった。
久保先生と中山先生と筆者は1956年、67年、75年生まれでちょうど10歳ぐらいずつ離れていたこともあり、中山先生は『オバマ・アメリカ・世界』を「三世代鼎談」と銘打っていた。1日がかりの泊まらない合宿のような会合を何度も「缶詰め」で開催し、アメリカ政治についてこれでもかと議論したが、学会でも学生とのゼミでもあんなに長時間、本音で少数の研究者同士で話す機会は珍しく、末席の筆者としては、久保先生が監督される中山先生のゼミにたった一人で参加する「私塾」のような贅沢を味わわせてもらった。ゲラ校正の土壇場で2011年3月11日の東日本大震災が起き、日米関係と東北の震災を論じ直したりもした。この著作で特筆すべきは、中山先生がいち早くオバマ政権の性格をオバマの人物像から言い当てていたことである。政治を担うオバマの脳内に入り込み、ある種成り代わって語る分析の凄まじさが以下のように披露されている。
1つはオバマの保守性に関する分析である。
もう1つは分断の起源をトランプ政権以前のオバマ政権に見通していたことだ。
- 「皮肉なことにオバマ政権下においてはこの分断が完成したといってもいいほど、亀裂が深く悪質なものに変容していってしまった」 (p. 264)
- 「オバマは意図せずして政治的座標軸を浮き上がらせ、『オバマに抵抗する運動』を生み出してしまった」 (p. 265)
中山教授は、トランプ政権以前からオバマが引き込んだ分断の顕在化を予見していた。
ちなみに余談ではあるが同書には秘話がある。当初の企画では、編集の強い意向で「写真集」が口絵でつく予定だった。プロのカメラマンが来訪し、久保先生と中山先生と筆者の写真を撮影したのだが、研究者の著者近影の顔写真撮影の域を明らかに越えていた。キュービクルの中で佇んでいる横顔とか、非常階段の踊り場で腕を組んで斜め上を見上げるような、まるで昭和の刑事ドラマのオープニングのような撮影まであり、筆者は「モデルでもないので恥ずかしい」と撮影後に躊躇感を編集者に伝えていた。すると完成した本には帯にも口絵にも大量に撮影したはずの写真がなくなってしまった。
筆者が尻込みしなければ写真の口絵が挟みこまれたのか、何か別の理由で中止になったのかは不明だが、読者に中山先生の写真をお届けできなくなった責任の一端を感じている。周知の通り中山先生はスーツの洗練された着こなしで知られ、ファッション文化の伝統にも独特の哲学をお持ちであった。出版社やカメラマンの方の手元に一部でもネガやデータが残っていれば、中山先生のお写真だけでも何らかの形で共有していただける機会があればと願っている。
2: 臨床と理論の知の往復:現実と実務に照らした想像力
第2に臨床と理論の知の往復である。
中山先生は、実務で体得するアメリカ政治外交の現場感覚を大切にされていた研究者だった。先生はメディアと政治外交の2つの実務経験をお持ちだった。大学院修士課程で学ばれた後、まずワシントンポスト極東総局で記者として、その後は博士課程の研究を進めながら1996年から2年間、国際連合ニューヨーク本部の日本政府代表部で専門調査員として活躍された。双方ともに「現場」を大切にする中山先生の臨床の知にはなくてはならない経験だったが、とりわけニューヨークでの実務経験はその後の研究に深く関係していたと思われる。当時の国連大使は小和田恒大使で、中山先生は大使のステイトメントの草稿の起案にも参画していた。
このように、中山先生は大学人になる前に実務を先に経験された。そのためなのか、先生は「外交官」なのではないかと強く感じたことが多々ある。海外の少人数での調査旅行をよくご一緒した。久保先生と中山先生と共に鼎談本の面々でワシントンの議会やシンクタンクを回ったことがあるが、先方との小規模の会合での頼れる、安心できる立ち居振る舞い、情報をスマートに掴み取る姿は、まさに外交官のそれであった。
ところで、中山先生も国連で経験した外務省専門調査員制度は日本の国際政治学者・地域研究者育成の鍵になっている。これは海外にあまりない日本独自の興味深い制度で、外務省が若手研究者などを採用して全世界の在外公館で専門的な調査に従事させる仕組みだ。日本の国際政治や地域研究の研究者の多くは何らかの在外公館や代表部で現地調査をしていた経験がある。翻ってみれば、文科省ではなく外務省の予算で形を変えた国費留学として国際政治学者を育ててきたとも言える。筆者も専門調査員ではないものの、シカゴ留学時代に在シカゴ日本総領事館に短期間勤務していた経験があるので、同制度の価値を現場で理解している。
専門調査員は「日本政府の人物」として現地の外交コミュニティで信頼を得られるし、他方で「在外研究中の一個人の研究者」としてフィールドにも出られる。いわば2つの「顔」を持つ存在である。アメリカ研究の若手が現地に深く食い込むことは、総領事館の本務上も有意義な貢献になることが少なくない。思想を扱われていた中山先生からは意外感があるかもしれないが、先生は向学心のある若い人にはなるべく「現場」に触れさせたいという研究者教育の哲学をお持ちだった。国際政治や地域研究で、この「土地勘」みたいなものが、定性研究ではいうまでもなく、定量研究であっても間接的に生かされると中山先生は考えていた。
中山先生は大学院で指導している学生に対しても、躊躇なく在外研究の一つのチャンスとしてこの制度を勧めていた。ある教え子の若手研究者が論文作成中に研究途上で在米の総領事館に行くチャンスを得たときも、中山先生は「行った方がいい。研究がいったん停滞しても、それは長い目でみたら研究にもすごく大きなリターンになる」と背中を押した。ご自身の若い頃を重ねていたのかもしれない。研究を一時離れても専門の地域で現場を経験できることは、政治・外交への想像力を豊かにすると信じていた中山先生は、臨床と理論の知を往復して地域に寄り添う根っからの地域研究者でもあった。ところで、先生は、実務界から招かれる大学教員を「実務家教員」とする近年の分類法を超えた「往復する」研究者の価値を見据えておられたように記憶している。これはある意味では「実務経験豊富な研究者」を想定していない呼称で、すなわち「研究者には本格的な実務家がいるはずがなく、実務家には本当の研究者はいないはず」という「分離」を暗黙の前提としている表現だからだ。「往復」が片方の立場の信頼性を毀損するものであるべきではなく、双方の価値をむしろダブルにするものであるべきだと中山先生は考えておられた。
3:大学とメディア / シンクタンクの往復:公的知識人(public intellectuals)としての知の還元
中山先生は津田塾大学、ご出身の青山学院大学、そして慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスという、それぞれ異なる魅力と学風に満ちた大学で広範囲に多様な学生を育て、大学運営にも縦横無尽に貢献されたが、他方で大学とは不思議な距離感のある独立研究者のような顔もお持ちだった。海外英字紙記者とアメリカでの外交実務経験を経て、研究者キャリアをシンクタンクからスタートさせた「シンクタンカー」でもあった。「シンクタンカー」としての中山先生については慶應義塾大学だけでなく日本国際問題研究所の同僚でもあった神保謙・慶應義塾大学教授が当時の貴重な詳細を記している1。
筆者の中山先生とのご縁も元々は学会ではなくシンクタンクであった。筆者が政治部の外交記者だった2000年代初頭頃に先生の知遇を得て、国際問題研究所のオフィスに外交談義にお邪魔していた。取材という意識はまるでなかった。ただ、先生と話すのが楽しかったのだ。中山先生は筆者のことを研究者のような記者だと仰られ、筆者は中山先生を大学教授のようなシンクタンカーだと感じており、共に「往復」を是とする精神から馬が合った。中山先生の部屋の書棚には思想や歴史の英語原書が溢れており、ワシントンの政策シンクタンクの研究員オフィスとも雰囲気が違いまるで大学の研究室だった。それも人文系の思想や哲学を専門とする研究者のそれを彷彿とさせる佇まいだった。中山先生はシンクタンク常勤から程なくして大学に移られたが、シンクタンクと大学の間に垣根を感じていなかった。大学では若い人を育てる教育に没頭しつつも、肝煎りの「仕掛け」はシンクタンクで実践された。中でも論争を呼びそうな少しリスクのある提言や主張は、メディアではなくシンクタンクの論考で試すことにされていて、SPF「アメリカ現状モニター」を自由に書ける「思想の実験工場」として、とても大切にされていた。
中山先生とのプロジェクトで未完の作業になってしまったものに2012年に開催された東京財団の「パブリック・インテレクチャルズ(public intellectuals)研究会」があった。パブリック・インテレクチュアルとは、大学知識人とは違う形で公に知を問いかける担い手で、アメリカでは政治思想の分野では無視できない存在である。未完の共著で中山先生の「はしがき」に「趣旨」として盛り込まれたであろう2012年1月9日付「研究企画書(案)」と題された文章から引用したい。
日本で論壇の凋落が語られて久しい。その原因としてはいくつかの要因が考えられる。そもそも論壇を支えた総合誌がかつてのような影響力を失ったこと、知識の専門化によって「総合知」といった観点から時局を分析することが困難になり、それに伴って知識人が「大学人化」していったこと、さらに論壇を成立させるイデオロギー的な対立軸が曖昧になっていることなどが上げられるだろう。3.11後、瞬間的に「ものを考える人たち」の「考えようとする衝動」が、論壇を活性化させたかのようにも見えるが、その持続性は危うい。このようなわが国の状況と対比させると、アメリカでは「論壇」と形容されうる「場」が、分散的ではあるが機能しているように思われる(ちなみに英語では「論壇」に相当する言葉はない)。日本では、インターネットの普及は論壇にとっての「脅威」として語られることが多いが、アメリカではその反対に公的な議論を活性化させる効果をもった。かつては、アメリカでもある種の党派性をもった雑誌が論壇を支える中心的な媒体だったが、いまや紙媒体と並んでネット上の言論が米論壇の重要な一要素を構成しているといえよう。
(中略)
アメリカの事例は、知識人の公的な役割を考える事例として大いに参考になる。言論の使い手としての知識人が公的な役割を担わないことは、社会にとっては大変な損失であろう。無論、知識人が発言すれば、社会が活性化するなどという単純な構図が成立するわけはないが、議論を洗練された言葉で整理し、公衆が参加しうるような場を提供する役割を期待することは過剰ではないだろう。アメリカにおいて、今日、「論壇」を成立させている要件について考察し、それをわが国の論壇がおかれている状況と照らし合わせて研究をすすめていくことは極めて実践的な研究であると考えられる。
中山先生はご自身もパブリック・インテレクチュアルであろうと、実践されていた。だからこそシンクタンクで初の「座長」を務める研究会では同テーマを仕込みたいのだと筆者に内に秘めていた大志を語って下さった。まさにライフワークであった。「自分はアメリカのコラムニストやパンディット(メディアに出演する政治評批評家)のような存在として、政治分析を言葉で、コラムなどで、世の中に還元していくことにやりがいを感じている」と。リチャード・ローティ、マイケル・ウォルツァー、ファリード・ザカリア、ピーター・ベイナート、デイビッド・ブルックス、ウィリアム・ガルストンのような存在、あるいはジョージ・ウィル、ウイリアム・バックリー、タッカー・カールソンのような、政治分析をメディアで還元していく存在に魅力を感じ、日本における「理想」とされていたように感じる。そしてオンラインが論談を成長させる可能性に多大な関心を持ち、自らもTwitterでインフルエンスを発揮されていた。
アメリカの公的知識人とは、大学に籍を持たないか、あるいは大学で教えもするけれども大学だけにいるわけではない。シンクタンクの研究者が支える政策分析から、雑誌やメディアを立ち上げてコラムニストやパンディットを務める役割まで、広範な活動を担う。こうした大学とは違う軸の知性のインフラが、アメリカの民主主義の底力であると、中山先生は公的知識人の役割をとても尊重されていた。この伝統を日本の政治研究の世界に持ち込むことを切望され、自ら国際問題研究所など数々のシンクタンク、また各種のメディアで発信され、その先駆者となられてきた。デモクラシーの知的なインフラにご尽力された方であった。
中山先生は大学とメディアの間も軽やかに往復されていた。ただ、専門と無関係な番組への関与や専門外のコメントはしない原則を貫かれ、共演者との馴れ合いも拒まれていた。数多くご一緒した共演や対談の中で一つだけ忘れられない番組は『NHK BS1スペシャル:分断されるアメリカ』(2012年11月6日放送:司会は元TBSの渡辺真理キャスター)である。中山先生が保守側、ジャーナリストの堤未果氏がリベラル側の草の根政治を事前に現地ロケで取材し、そのVTRにスタジオで筆者が解説を加え、3名で議論する2時間特番だった(生放送ではなく収録)。番組半ば過ぎ、医療保険制度の議論の中で、堤氏がアメリカの医療保険制度の改革に絡んで「医療保険業界からの献金をあるポイントで規制するしかないと思う。何十億、何千億ドルという選挙献金があった利益団体に対して、それをこう全部排除するのはできないと思いますね」と企業献金の問題を指摘した。中山先生はすかさず、献金が政治表現の一つであるアメリカにおける規制へのハードルの高さを説明した。
特定の業界をターゲットに献金を廃止するのは難しいでしょうね。それからアメリカにおける政治とお金の関係は、額そのものの問題になりますけれども、基本的に献金は言論の自由の文脈で捉えられるわけですよね。ですからそれを規制するのは非常に難しいという現実も一方であると思うんです。
(中略)
形式的に言うとオバマキャンペーン自体は(献金を)もらってないんです。オバマキャンペーンを応援する団体がもらっている。その団体に対する資金提供を禁止するのはやっぱり言論の自由に抵触してしまう、どうしても。
これに対して堤氏は「そこが難しいですよね」と受け止め、政治献金論のキャッチボールがさらに続いた。中山先生は堤氏とは一部の認識を異にしていたが、堤氏の本質的な問題提起は番組で深く受け止めて掘り下げる価値のある重要論点だとして尊重していたからこそ安易な同調もしなかった。緊張溢れる空気を周囲は懸念したが、中山先生の「反論」によりアメリカの特質を文化面と併せて浮き彫りにできた。筆者はカットの可能性もあると感じたが、NHKはこの応酬をそのまま放送した。堤氏と中山先生の間での仲裁的な調整役が、NHKが解説に加えて筆者に依頼していた、スタジオ本番での「もう1つの任務」だったが、その「もう1つの任務」の必要性は杞憂に終わった。中山先生は、視点や主義主張に関係なくアメリカを本気で論じる論客との討論を心から楽しまれていた。筆者にとって先生との共演の中でも決して忘れられない、清々しい後味の仕事である。
これら3つの「往復」こそが、中山先生の個性であり核心でもあった。残された私たちは大きな宿題を貰ったと感じている。研究、教育における「中山先生イズム」を末長く継承し、そして大きく育てていかねばならない。そのような使命感を改めて噛み締めている。
中山先生、どうぞ安らかにお眠りください。
(了)
- 神保謙「追悼 中山俊宏 孤独な探究心を持ったヒューマニスト」『中央公論』2022年8月号(ウェブ版は、https://chuokoron.jp/international/120833.html)。神保教授は中山先生を「孤独な探究心」を持った人と絶妙に形容する。なるほど中山先生は「研究は孤独な作業で、孤独に耐えられなければならない」と繰り返していた。(本文に戻る)