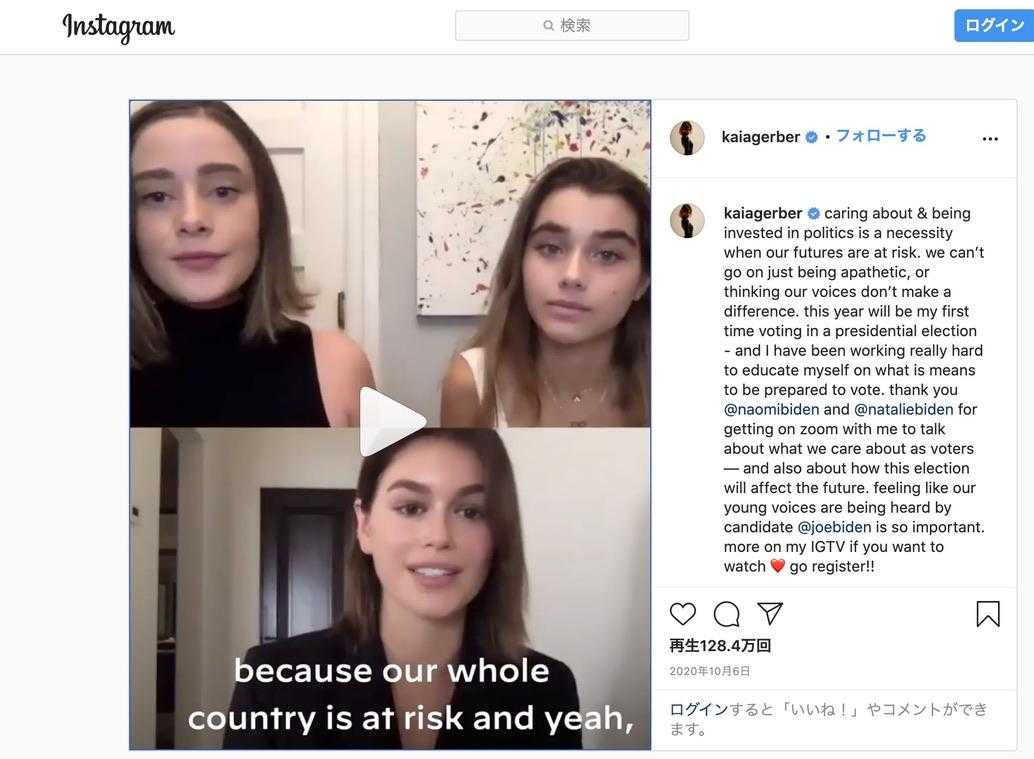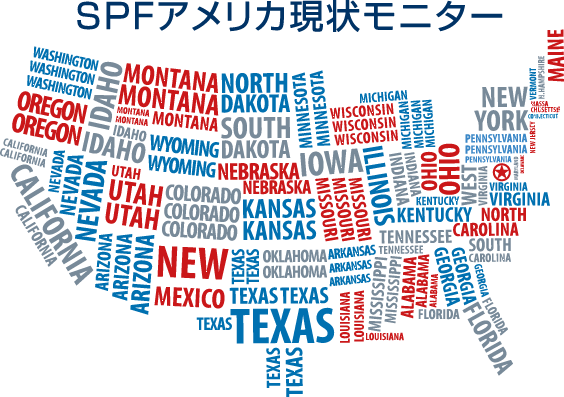デジタル技術と政治の新潮流(前編)
インフルエンサー選挙とは何か

渡辺 将人
政治における「インフルエンサー」利用
アメリカの選挙に起きている地殻変動のひとつにデジタル技術の日常化による選挙運動の質的変化がある。かつて選挙運動にネットが導入され始めた頃、陣営内でオンライン戦略は独立した新分野だった。1990年代以降、議員事務所でも「システム・アドミニストレーター」にネット業務は丸投げで、テレビ広告全盛期を生きてきた陣営幹部も、オンラインのことはシリコンバレーから参加しているヒッピー的な集団に「ギーク部屋」を与えて自由に任せる発想だった(2012年オバマ再選陣営のビッグデータ選挙ですら幹部スタッフ内にそうしたデジタルをめぐる意識の分断が存在した)。しかし、コロナ禍以前から私たちの日常生活がそうなっているように、今やオンラインに何も関係しない活動領域がむしろ少数になっている。「地上戦」「空中戦」「オンライン戦」と分けられていた選挙運動も、現場では統合的な再編の転換点にある。草の根組織作りも旧来のメディア戦略もオンラインと無関係ではあり得ない。2010年代以降、マスメディアの購買数と視聴率の減少に伴い、読者や視聴者が接する記事や映像はネットのプラットフォームを介して伝わるものに変質しつつある。そこでは匿名コメントや一般ユーザーが編集する「まとめ記事」とごちゃ混ぜに記事が消費され、ネット空間の「再解釈」に委ねられる。マスメディアの編集権の独占が、ある意味では「民主化」された一方、副作用として「フェイクニュース」問題も浮上した。
その流れが選挙現場にも押し寄せている。主流メディアだけでアジェンダ設定を支配できた時代は過去になりつつある。ソーシャルメディアでは「ミーム」と呼ばれる映像加工などがコラージュ風に拡散されることもあるし、放送や記事を紹介する「紹介者」の恣意的解釈でメッセージは簡単に歪む。今も昔も変わらないのは人物を介した「紹介」「解説」をオーディエンスが好む傾向で、「メッセンジャー」としてテレビ時代にアンカーに求められた役割だ。アメリカのYouTubeには報道機関のチャンネル(49%)と独立系チャンネル(42%)が併存するが、コンテンツではなく出演者の人物誘引(Personality-driven)の番組が半分近く(YouTuber 29%、公的著名人15%)を占めており、独立系チャンネルの7割が人物誘引で視聴習慣を確立している1。
こうした傾向やコロナ禍の対面活動が制約される環境を受け、2020年選挙サイクルから加速したのがソーシャルメディアでフォロワーへの独自の影響力を持つ「インフルエンサー」を活用した戦略だった。インフルエンサーを利用した商業マーケティングは2010年代前半から広く浸透している。市場調査のフォーカスグループの政治転用と同様、マーケティング技術の政治への応用は一定のタイムラグを経て概ね実現してきた2。しかし、一般的な商品と「候補者や政策」の売り込み、消費者と「有権者」の需要や判断基準にはいうまでもないが質的な違いが多々あり、経営学の知見の全てが政治現場にそのまま転用可能なわけではない。政治現場に馴染む技術のアレンジには試行錯誤が繰り返されてきた。そのため応用には一定のタイムラグを要した。マーケティングを選挙や政策過程に流し込んでも効果が得られないか逆効果になる問題は、技術上の瑕疵というよりも政治文化に起因することが少なくなく、アメリカの政治家がマーケティング技術に長けたコンサルタントを一部で利用しながらも、選挙区に土地勘のある政務スタッフの判断を重用する要因でもあった3。
「メガ」は空中戦? 「ナノ」は地上戦?
インフルエンサー選挙の研究はアメリカでも始まったばかりで実証的な研究は蓄積途上にある。だが、包括的で具体例も豊富で参考になる先駆的な研究はサミュエル・ウーレイがディレクターとして率いるテキサス大学オースティン校(メディア・エンゲージメント研究所)のプロパガンダ研究のプロジェクトの成果であろう。2020年大統領選挙でインフルエンサー戦略を担った政治戦略家に14回にも及ぶ聞き取りを実施し、InstagramやTikTokなどの詳細な観察も行なった。彼らの研究が明らかにしたのは、「ナノ・インフルエンサー」と呼ばれる小規模のインフルエンサーの効果だった。政治インフルエンサー(Political-Influencer)に関して、最も効果的なアプローチは、「普通の人(everyday people)」と呼ばれる小規模のインフルエンサーを、特定候補者への支持取り付けではなく、何かの「大義」のために動かすことで、彼らの個人的な物語で感動を増す「演出のない(authentic)」コンテンツ(content)創造の手助けをすることにあるという4。
このテキサス大学の先行研究のほか、アメリカの選挙現場の試行錯誤を試論的に筆者なりにまとめ直すと、インフルエンサー選挙は「空中戦」型と「地上戦」型に分別できる。「空中戦」型とは100万人以上のフォロワーを誇る「メガ・インフルエンサー」を利用した戦略である。ワンランク規模を落とすと「マクロ・インフルエンサー」(10万〜100万フォロワー)になる。ハリウッド俳優などのセレブリティを代理人にしたり、大物政治家に支持してもらったりする戦略と同趣旨だ。「空中戦」的なテレビ広告のロジックである。「メガ」の利点は圧倒的に知名度で、弱点は有権者との距離感だが、それでもテレビと比べてソーシャルメディアでは繋がりに親近感を与えられる。2020年バイデン陣営の試みでは、Instagramで612万人のフォロワーを誇るモデルによるバイデンの孫娘2名とのライブ配信が特に話題となった。ライブ配信は編集済みの動画アップロードとは違う一体感を醸し出す。
インフルエンサーのカイア・ガーバー(下段)のInstagram(2020年10月6日)。上段はバイデン孫娘のナオミとナタリー。Instagramのライブ機能を用いた配信風景。(引用元:Instagram @kaiagerber)
ただ、ある意味では「メガ・インフルエンサー 」現象を牽引したのは共和党だったとも言える。慶應義塾大学の中山俊宏教授の言葉を借りれば「トランプが最大のインフルエンサー」だったからだ5。2016年大統領選挙以降、候補者自身がソーシャルメディアで「インフルエンサー」として有権者に直接リーチするようになった。インフルエンサーの利用は、選挙後も政権の政策の売り込みに応用されている。バイデン政権の新型コロナ対策法案では、「財テク教育」系インフルエンサーの「The Budgetnista」ことティファニー・アリーチェと「The Money Coach」ことレネット・カファルファニ=コックスらに法案支持を代弁させることで幅広い世論の支持を固めた。ホワイトハウスが直接リーチできない層に満遍なく考えを浸透させるには、大統領が日曜朝の番組のインタビューを梯子で受けるよりも、インフルエンサーに彼らのフォロワーの質問に答えさせる方が効果的だという広報戦略の部分的変容である。
「地上戦」型とは、1万人から10万人のフォロワーを持つ「マイクロ・インフルエンサー」を活用するもので、誰もが知っているわけではないが特定分野での知名度や影響力がある人物が、限定された対象にメッセージを伝える。上で紹介したテキサス大学の先行研究で効果が強調されている分類だ。人種や信仰や利益団体などでセグメント化されたアウトリーチに最適である。さらに細分化されたコミュニティで支持されるフォロワー1万人以下の「ナノ・インフルエンサー」は普通の一般市民ではあるが、教会関係者など地域指導者や学校の同窓会の中心人物など、対等の仲間同士によるピアツーピア(P2P:Peer to Peer)で、特定のローカルの集団内で隣人や友人へ限定的だが深い影響を与える。彼らは「メガ」と違って無名で、世代や趣味が異なるとほとんど誰だか分からない。「芸能人」ではないからだ。あらゆる世代や属性が知る人物には「マイクロ」や「ナノ」としての価値はむしろない。「感覚」を共有する一定の閉じられたサロン的コミュニティ内での繋がり意識が「メガ」との違いだ。「国民的有名人」が減少し、世代別のヒーローが分断されている現代のメディア環境も関係する。陣営幹部がリーチ対象であるインフルエンサーのリストを見ても、自分の世代や属性に合致している人以外は、誰が誰だか分からないことがほとんどで、対象抽出には多様な判断が要る。民主党は外部委託を活用している。「マイクロ」や「ナノ」の効果は戸別訪問や友人への電話説得と類似している。振り返れば、2004年大統領選挙で民主党ハワード・ディーンの選挙戦を指揮したジョー・トリッピが提唱し、陣営に参加していた部下たちが後に2008年オバマ陣営で具現化したのが、ピアツーピアの概念でもある。アイデア自体は目新しくない。だが、スマートフォン普及やライブ配信向けの通信環境などインフラ充足とインフルエンサーの相対的な影響増大、それにコロナ禍が重なり、デジタル技術を活用した「もうひとつの地上戦」が発掘されるに至っているのが現状である。
集票効果の条件とアウトリーチ戦略の新たな可能性
インフルエンサー選挙は、集票効果に関する古くて新しい問題も問いかけた。アメリカの選挙研究者の間では、そもそも「キャンペーンは効果があるのか?」に始まり(Thomas M. Holbrook, Do Campaigns Matter?, SAGE, 1996)、戸別訪問など戦略別の効果論は主要な研究上の問いの1つだった。2016年大統領選挙直後は、トランプ勝利のショックから従来の「玄人政治」を否定する偏向的な言説も米ジャーナリズムには散見された。2017年9月の「アトランティック」誌は、「ほとんどのキャンペーン・アウトリーチは有権者に影響を与えない」という刺激的な見出しを立てている6。なるほど紹介されている2人の政治学者が49の連邦選挙と地方選挙で行なったフィールド実験では、戸別訪問、電話接触などで効果が見られなかった。しかし、記事の元論文を読むと、対象は本選挙の「説得」に限った結論であることがわかる(アメリカの選挙戦略分類では、既存の支持者を確実に投票させるのが「動員」で、新規に支持者になってもらうのが「説得」)。党派性が作用しない予備選挙や議題別投票への効果には肯定的で、持続性こそ短いが緒戦での「説得」効果も認めている。候補者の資質や思想、キャンぺーン全体の「メッセージ」の影響力、有権者登録、GOTV(直前動員)、説得への最適な選挙資金配分との関係もまだ未解明だとされている7。記事の見出しは研究成果を歪曲した「煽り」の色彩が濃かった。
オール・オア・ナッシングの白黒結論を避けながら、先行研究と選挙現場の双方の過去の知見を概観すると、メッセージの内容そのものもさることながら、「誰が」「どのような関係性で」アクセスするかがどうやら重要だということは共通理解として浮き彫りになる。確かに、他州からアイオワ州やオハイオ州にピストン輸送されてきた赤の他人のボランティアが人海戦術で押しかけるよりも、あるいは湯水のようにテレビ広告を垂れ流すよりも、たった一人でも地域の信頼できる仲間からの言葉が大きな力を持つし、候補者名の連呼による投票の押し売りではなく、何らかの「単一争点」への情熱の共有が結果として効果的だ。戸別訪問なら運動員がわざわざ足を運んでくれたことへの印象効果はあるが、親しい仲間のオンライン説得の方が、赤の他人の戸別訪問よりメッセージ効果は強い。「関係性」すなわち対話者間の「文脈」こそが効果を決める。「誰が」「どのような」関係性の中で語るかの重要度に比べれば、オンラインか対面かは二次的になるかもしれない(対面の方が望ましいという前提ではあるが)。
ターゲットを絞った有権者分類に即した集票を行うアウトリーチ戦略では従来から、民族別に言語も変えてキャンペーンをしている。例えば、中南米系にはスペイン語でキャンペーンをしており、その効果は先行研究でも実証済みだ。だが、人種や民族や宗教が同じという程度では同族意識の幅は広すぎる。チャイナタウンの商工会で尊敬されるある実力者を介して、広東語で、広東移民系の中華系に、しかも候補者名連呼ではなく「人権」「地域経済」など特定の争点でアプローチし、さりげなく候補者を示すような方法であれば効果がある。そうした意味で、同族の信頼関係原則の細分化や争点重視のメッセージ作りは、マイノリティのアウトリーチの分野ではすでに開発されている。だが、それがソーシャルメディア上の人物の発信でランダムに行なわれることは、アウトリーチ戦略にとっても新たな現象だ。特定のエスニック集団や信仰の属性への帰属意識が強い有権者、あるいは争点指向の有権者には、インフルエンサー活用は強い動員効果を発揮する可能性がある。しかしその効果を期待するには、「メガ」ではなく「マイクロ」、できれば「ナノ」が最善だ。そして、広告的な演出性の薄い自然な「コンテンツ」である方が望ましい。テキサス大学の研究報告は、PAC(政治活動委員会)や政治戦略ファームに配備されるインフルエンサーの多くが何らかの報酬を得ていることを示唆しているが、それをインフルエンサーは滅多に明かさない。明かせば訴求効果が薄れてしまう。
インフルエンサー利用はかつて巨額の選挙資金がテレビ広告に注がれたように、資金力がものをいう「デジタル人工芝」(digital astroturfing)の育成競争になってしまうのか。アウトリーチの細分化により、多民族社会の声を政治に反映するダイバーシティ促進の魔法の杖になるのか。「後編」でアメリカに学びつつ独自のデモクラシーを育む台湾の事例を参考にしてみたい。
(了)
■「後編」はインフルエンサーの政治利用で先進的な台湾の現場の事例を紹介します(後編「台湾の選挙現場との比較から」へ)。
- 2020年1月6-20日調査。YouTubeチャンネルの集計は2019年11月から12月時点の番組が対象。Galen Stocking et al., “Many Americans Get News on YouTube, Where News Organizations and Independent Producers Thrive Side by Side,” Pew Research Center, September 28, 2020, <https://www.pewresearch.org/journalism/2020/09/28/many-americans-get-news-on-youtube-where-news-organizations-and-independent-producers-thrive-side-by-side/> accessed on October 28, 2021. (本文に戻る)
- Philip Kotler and Neil Kotler, “Political Marketing: Generating Effective Candidates, Campaigns, and Causes” in Bruce I. Newman ed., Handbook of Political Marketing (Thousand Oaks CA: SAGE, 1999). フィリップ・コトラーが商業マーケティング理論を公共セクターに応用する研究に踏み込んだことで、選挙がマーケティング関連業界の関心を集めるようになった。候補者が有権者に対して「公約」「政策提案」「人格」などを売り込み、他方で有権者が「票」「ボランティアとしての労働力」「献金」などを提供するという「取り引き」は、構図上は商業モデルに類似しており、消費者調査などで応用が進んだ。しかし、選挙の現場が経験的に知っているように応用には限界がある。自分のビジネスのマーケティングでは成功を収め、最高のマーケティング専門家集団を自社に抱えているはずのアメリカを代表する経営者が、大統領選挙に出馬してはその都度敗退を繰り返してきた。多くは予備選過程初戦のアイオワにたどり着くこともできなかった。(本文に戻る)
- 渡辺将人『現代アメリカ選挙の集票過程 アウトリーチ戦略と政治意識の変容』(日本評論社、2008年)の特に第1章参照。政治応用の調整はマーケティング専門家へのコンサルタント依頼の増加ではなく、マーケティング的発想に親和的な政治スタッフが増えることでことではじめて実現した。(本文に戻る)
- Anastasia Goodwin, Katie Joseff, and Samuel C. Woolley, “Social Media Influencers and the 2020 U.S. Election: Paying ‘Regular People’ for Digital Campaign Communication,” Center for Media Engagement. October, 2020, <https://mediaengagement.org/research/social-media-influencers-and-the-2020-election/> accessed on September 1, 2021.(本文に戻る)
- 中山俊宏慶應義塾大学教授のSPFアメリカ現状モニター研究会での指摘より。(本文に戻る)
- Emma Green, “Most Campaign Outreach Has Zero Effect on Voters,” The Atlantic, September 30, 2017, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/09/campaigns-direct-mail-zero-effect/541485/> accessed October 28, 2021.(本文に戻る)
- Joshua L. Kalla and David E. Broockman. “The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments,” American Political Science Review 112, no. 1. (2018): pp. 148-166.(本文に戻る)