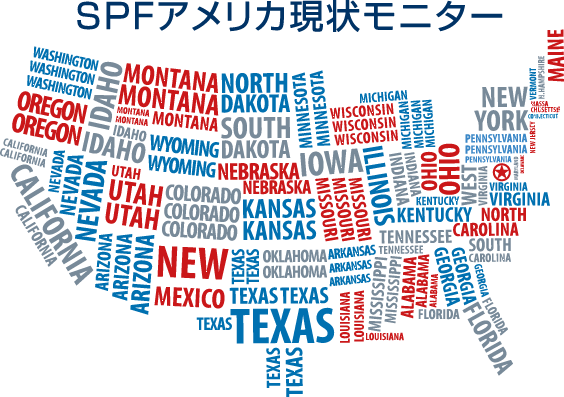諸外国と「文化」言及のジレンマ
オバマ回顧録論⑤

渡辺 将人
オバマ回顧録論の5回目は、外国について回顧録が言及する含意について、日本を事例に振り返りながら、大統領一家の外国語学習論にも視点を広げて考察する(「政権の『公式写真集』として オバマ回顧録論④」より続く)。
閣僚回顧録との相互牽制
上司の大統領が回顧録を出すまで、閣僚や補佐官が政権回顧録を出してはいけないというルールは厳密にはない。元部下は次々と本を出す。「裏切りの書」も大統領在職中に出る。大統領が、威厳を維持した堂々とした回顧録の出版を無事に成功させるには、元部下の誰がどの時期にどのようなスケジュールで回顧録を出そうと画策しているか、把握し尽くさなくてはならない。
また、上司の大統領とライバル関係にあった元閣僚にとって、大統領回顧録よりも先に回顧録を出して、事実描写を誘導したり、記述の方向性を牽制したりするのは、最後のささやかな「争い」だ。
そこで付随的に浮上するのは、ある政権の内政・外交の足跡を理解するときに、大統領回顧録に単体でどのような意味があるのかという問題だ。例えば、政権の外交を多面的に理解したいのであれば、実際には国務長官や国防長官の回顧録と併読しないと、政権の全体像は浮かび上がりにくい。無論、大統領回顧録には「元大統領がどう考えていたのか」を知れることに価値がある。要は、目的をはき違えなければよいだけだ。大統領回顧録1冊に依存して、ある政権を描き出すことに意味がないだけである。
元大統領と元閣僚は、それぞれの回顧録を書く上で、明確な役割分担や編集の打ち合わせをするわけではない。先に出した方が影響を与え、「引き算」の発想を後続の著者に生じさせる。特にオバマ政権1期目の外交のディテールは、前回紹介したヒラリー回顧録でそれなりに語り尽くされているところがある。オバマが『約束の地』で外交に過度に頁を割いていない間接的な理由は、国務長官の方が最前線の外交に詳しい記録を先に残してしまったことも関係する。ヒラリー本の内容を個別に否定すれば政権を掌握していたはずの指導力に傷がつくし、全てを肯定しても二番煎じになる。
これでもかと、凄まじい数の訪問国、世界の要人との出来事を羅列的に書き込んだヒラリーの回顧録との「張り合い」を避け、オバマはあえて文学的描写と達観的な政治観の提示で独自性に走った。その意味で、オバマ回顧録にオバマ政権の外交記録を求めるのは正しい読み方ではなく、国務長官回顧録を併読されることを前提とした開き直りが滲む。すべての国や首脳に平等に文字数を割くことに過度な期待はできない。しかし、羅列的ではない限定記述であるがゆえに、なおさら元大統領の記述対象国とそのトーンに深い意味が伴うとも言える。
「ニュース化」と「翻訳」の狭間:日本の事例から
大統領回顧録が刊行され、各国のプレスが最初に行うのは自国がどう言及されているかを記事にすることだ。就任演説、一般教書演説、党の綱領などの文書と同じだ。日本の報道関係者も「Japan」という文字を探す。今回の回顧録では鳩山由紀夫総理(当時)についての言及が波紋を呼んだ。
ただ、各国プレスが自国に紹介する場合の目的は一義的には「翻訳」ではなく「報道」である。すなわち何か「ニュース」を探して、「見出し」を立てる必要性から逃れられない。自国や自国の指導者が言及されている個所を見つけて「ニュース化」する際、それがポジティブかネガティブかの価値解釈に引きずられるのはそのためだ。しかしそれだけに、一部分を抜き出して国内に紹介する上で、ミスリードへの緊張と責任も背負う。Kindleもネットもなかった1980年代までならば、報道機関がそう書いてしまえばそのまま受け入れられることがほとんどだったが、裾野の英語力も増し、SNSで疑問が広がる現代では異論が噴出することもある。
オバマ回顧録は、2020年11月の原書発売を受け、日本の報道各社も内容を紹介した。以下の原書477頁(邦訳版下巻218頁)にある日本に関する記述は、2009年の7日間のアジア歴訪の最初の訪問地として「外遊録」的に登場しており、日本単体を深掘りして論じたものではない。
A pleasant if awkward fellow, Hatoyama was Japan’s fourth prime minister in less than three years and the second since I’d taken office - a symptom of the sclerotic, aimless politics that had plagued Japan for much of the decade. He’d be gone seven months later.
この箇所を紹介する報道が話題となった理由は、A pleasant if awkward fellowをどう訳すかという問題と、鳩山総理を「迷走した日本政治の象徴」とまで言い切れるかどうかの問題だった。すでに各方面で論じ尽くされているので、重要な指摘を紹介する形で問題を整理しておきたい。
まず、前者に関して翻訳家の鴻巣友季子氏の指摘は説得力があり実に的を射ている1。A if Bと書かれている場合、if以下のBの部分が付属的な言及で、Bという点はあるのだが、それでもAだと理解するのが自然だからだ。鴻巣氏がいみじくも指摘しているように、この「順番」が決定的に重要だ。『約束の地』集英社訳では、「話し上手ではないが感じのいい」と訳している。この訳を土台にAとBの順番を試しに入れ替えると、「感じはいいが話し上手ではない」となる。こうなると俄然、ニュアンスがネガティブになる。
英日翻訳に20年近く細々と関与してきた筆者にも他人事ではなく、さらなる良訳への向上心を込めてなのだが、単語の訳出そのものには多様な表現があり得るもので、これは訳の個性の範囲である。日本語の豊かな表現の範囲内で、pleasantは「感じが良い」のような「あたりの良さ」を表すポジティブな含意の様々な訳が想定でき、awkwardは「やりにくい」「話しにくい」などネガティブな含意の様々な訳があり得る。日本語論としてどのような訳語が著者の意図に近いかの議論も可能だが、それ以前の前提として、どちらに著者の比重があるかのAとBの順番は読み違えてはいけないとの指摘は妥当だろう。
他方、鳩山総理を日本政治の迷走の「象徴」とまで言い切れるかの問題であるが、これは多様な視点が存在するようだ。symptomは「症状の1つ」で「全体を象徴」しているとまでは言えないという見方ももちろんできる。しかし、「顕在化」「反映」であることも事実なので、静的に翻訳に徹するならば踏み込むべきではないかもしれないが、「ニュース」にするならば、「回顧録でオバマ前大統領が日本政治についての否定的な認識を盛り込んだ」と原稿化する意図は理解できる。ただ、揶揄の対象が鳩山総理個人に限定されていない点は注意が必要だ。
集英社訳は「話し上手ではないが感じのいい鳩山は、日本ではここ3年足らずのあいだで4人目の首相であり、私が就任してからは2人目だった。これは、過去10年にわたって硬直し、迷走していた日本の政治を象徴していた」(邦訳版下巻218頁)となっており、「象徴」と訳して踏み込んだ解釈をしている。しかし、「これは」として、象徴の対象として揶揄しているのは、鳩山氏個人ではなく、総理が次々と変わる日本の政治との理解だ。比較的バランスの良い訳だろう。「過去10年にわたる硬直」には政権交代前の自民党も含まれるからだ。
いずれにせよ言えることは、オバマの「日本政治」への記述は決して肯定的ではないことだ。鳩山総理への個人攻撃ではないのだが、安定しない日本政治への不満の事例にされてしまったのは事実だ。オバマが鳩山氏を、政治を変革する「チェンジ仲間」と認識したならば、日本政治では例外的な存在として積極的に評価する書き方をしたはずだからだ。これもオバマ特有の間接的な文章表現の特徴で、現象と個人のどちらへの批評なのか分かりにくい手の込んだ言い方をあえて好む。日本政治への不満が主題でも、それを鳩山氏との邂逅に混ぜてくるのは、失望や期待外れを人物にも絡めて示すオバマ流のポライトな皮肉表現だ。
とりわけ鳩山氏は政権交代直後の総理だった。オバマがそのことに一切触れていないのはやや気になる点だ。日本の当時の政権交代そのものを無価値と理解していたのか、外交安保における日米関係の安定性の方が重要だと考えていたのか。例えば、同じ民主党大統領だったビル・クリントンは細川護煕総理(当時)を以下のように回顧録で記述している。
「日本の新しい指導者、細川護煕首相とは充実した時間を過ごせた。自由民主党の政権独占を崩し、経済的には従来どおり開かれた日本を推進していく改革派だ」(邦訳版『マイ・ライフ:クリントンの回想』下巻149頁)
オバマと同じく「チェンジ」を1992年大統領選のスローガンにして勝利したクリントンが、日本の総理を政権交代に絡めて紹介した回顧録のこのくだりを覚えている人には、時代背景が違うとはいえ、対照的に感じられたはずだ。その意味で、冷泉彰彦氏の論考2にあるように、オバマ回顧録の記述が「手厳しい批判」だったことは大筋では間違いはなく、特に同氏も指摘するように普天間基地移転問題が絡んでいたことは否定できないだろう。オバマはあえてこの箇所の直前で、鳩山総理との会談内容として「沖縄の海兵隊基地の移転案」と明示している。一般のアメリカ人は理解できないだろうが、当時の混乱を覚えている日本人や日米外交筋にはピンとくる、分かる人には分かる書き方だ。作家オバマのやんわり匂わせつつ刺激的な毒をさりげなく混ぜる文章は、ストレートにネガティブな評価が伝わらない筆致なのだ(回顧録論⑦で紹介する中国論でも同じ手法を用いている)。
「文化」言及をめぐるオバマ流の抑制
ただ、その後段の当時の天皇皇后両陛下への親愛の情は、素直なものと読める。型通りの敬意ではなく、両陛下の心を察した独自の言い回しに踏み込んでいるからだ。その関連で「お辞儀事件」に自ら触れているのも興味深い(陛下の前で直角に近い角度でお辞儀したことが米メディアで批判された一件)。
ハワイで生まれ育ったオバマは明治元年以降に移民してきた日系移民の恩師や親友に囲まれて育ち、天皇陛下の存在について耳学問ではあるが一般のアメリカ人とは異なる敬意を抱いて育った。日本人の作法としてお辞儀は深いほど謙遜を示すという断片知識が少し歪んだ形で肥大化していただけで、不器用だが精一杯の特別な敬意の示し方だったと言える。「自分は日本文化にも近い位置で育った『アジア太平洋人』である」という、アメリカ国内派への差異化の自負心が咄嗟に頭をもたげたのかもしれない。
オバマの青少年期の関係者に話を聞けば聞くほど、背後に上記のような複雑な心理も部分的には介在した可能性を感じさせる一方、オバマ自身は回顧録で、「お辞儀批判」は純粋に保守派からの言われのない攻撃だとして、分極化の下での政争による中傷として片付けた(邦訳版下巻 219頁)。
アメリカ国内にアジア文化論を説明しても理解されないことをオバマは知っている。文化的にアメリカの理解の範囲に収まらないことは、概ね保守とリベラルの分極化のせいにして共和党を叩けば、民主党読者はそれで納得してくれる。アメリカの国内政治の二項対立を内側(民主党内)に向けて演じ、自らの多文化性の表現の抑制に努めるのは、オバマ流のアメリカ政治の遊泳術である。
たしかに文化ネタは、外交上も余計なシグナルの原因となりかねない。文化を外交に持ち込むことはハイリスクである。何がその国や地域の固有の文化かへのコンセンサスの境界が微妙なことがあるからだ。特にアメリカ人は、他の人種エスニシティへの尊重が転じて、自分が属さないグループについては政治現場でも「アジア系」「中華系」と輪切りにして片付けがちだ。
イラク戦争で急落したアメリカの尊敬回復の任を担ったオバマ政権は、政権発足直後、「異文化に寛容なアメリカ」への息吹を感じさせられるネタを貪欲に用いた時期がある。アジア言語を娘が学んでいることは格好の素材だった。ホワイトハウスは、オバマの下の娘のサーシャが中国語を勉強していることを公にして、2011年の胡錦濤訪米時にサーシャが中国語で挨拶をしたことを「文化交流」ネタにもしていた。だが、時系列上はビンラディン殺害前で記述範囲のはずのこの一件は『約束の地』には出てこない。
2008年の大統領選挙戦の遊説で、「アメリカ人も何か1つ外国語を学ぼう」とオバマは訴えた。オバマは米大統領としては例外的にアジア言語を理解する逸材だ(インドネシア語で4年間初等教育を受けた。インドネシア訪問ではインドネシア語を話して聴衆を沸かせたが、アメリカ国内では政治的な事情からインドネシア語は「忘れた」ことになっており、回顧録でもそう記している)。
選挙戦での訴えは、英語だけで通用する世界に安穏とした「内向きアメリカ」への叱咤だった。だが、外交では指導者の家族の特定の外国への留学、言語学習は思わぬメッセージ性を伴う。例えば、大統領の子どもや夫人が揃って日本語を学び、日本に留学することなどを想像すればわかりやすい。その国際的な絆感の印象は圧倒的だ。
「外国語アピール」のジレンマ:外交・文化交流・移民社会
ビル・クリントンは回顧録で娘のチェルシーが外国語をサマーキャンプで学んでいたエピソードを披露している。ミネソタ州の施設で2〜3週間のあいだ、グループごとに特定の言語だけで生活する。中国語や日本語も選択できたそうだが、チェルシーはドイツ語を選んだ。夏の恒例行事だったという(邦訳版『マイ・ライフ』上巻688頁)。
ドイツ語ならばさほど問題も起こりにくいのだが、多様性の代名詞のようなアジア文化は深入りするには複雑な問題もある。アメリカの「アジア太平洋諸島系」は、地域的、言語的、宗教的に雑多な出身地からの寄せ集めの「国勢調査用語」でしかない。とりわけ中華圏は多様だ。中国語は文字や方言に広範囲の多様性があり、それが少なからず現代の対立関係とも重なり政治的な含意も伴う。文字や方言や地域の歴史学習を並列して扱わないと、余計な意味を生じさせてしまう。
特に、移民社会アメリカの場合難しいのは、お膝元に大規模な中華系アメリカ人社会を長年抱えていて、ここでの主流が外交上の米中関係とは一致しないことだ。アメリカの政治家にとっての中国語の扱い方には、どの種の中国語を第二外国語教育の基準にするかといった日本での問題などとは、まるで異質の事情がある。中華系アメリカ人は歴史的に広東移民が源流かつ大多数で、映画やあるいはエスニックジョークを繰り出す中華系のコメディなどでも、長年「中国語」として浸透しているのは広東語である。台湾系拠点では北京語も浸透し、近年大都市では福州語など多様な方言も浸透しているが、北米のチャイナタウンは文字に関しては共通して繁体字を受け継いできた(ここ数年で急速に簡体字も浸透しつつある:拙著『メディアが動かすアメリカ―民主政治とジャーナリズム』)3。
移民社会の延長で海外を理解する傾向のあるアメリカでは、コミュニティの感情的にも、政治家の家族が移民の主流ではない方言や文字の学習をメディアで誇示することは、やや複雑な問題を引き起こす。「足元の中華系の伝統にもサーシャは目を向けて欲しかった」と、筆者と旧知のニューヨーク民主党の中華系の面々は寂しがっていた。オバマ周辺は良かれと思って「多文化理解」を示したのに、予期せぬ落とし穴だったと政権関係者は吐露する。外国語を披露したり民族衣装を褒めたりという行為は、完全に偏りのない配慮は難しく、どこかに誤解を与えかねず、結果メリットよりもリスクが大きい。筆者もかつて従事したニューヨークの選挙の集票広報では、南アジア系の多言語に配慮していたら、広報物のデザインが翻訳例文集のようになった挙げ句、ヒンディー語とパンジャブ語とウルドゥー語とベンガル語の順番1つでも揉めに揉めた。
この手のことは外交では頻繁に起こる。例えば、アジアではベトナムでもモンゴルでも旧暦の正月が広範に祝われるが、表現には地域性がある。「春節」は中華圏特有、しかも大陸風で、香港では「農暦新年」、台湾でもやはり「農暦年」「舊曆年」などと表現する。日本では旧正月は祝わない。大掴みに「アジア系」に敬意を示す意図でこの種の表現を使う場合、域内文化に細かく照らせば思わぬ「優遇」と「冷遇」の政治的含みを持たせかねない。Chinese New YearかLunar New Year(太陰暦)かの微妙なニュアンスも同様だ。一般ではそこまで神経質になる必要はない。だが、超大国の大統領家族であれば、そうはいかない窮屈さがある。
オバマの娘の中国語学習の話題自体は、当時多くの台湾人や香港人に、大統領の娘が中国語に関心を持ってくれて嬉しいと好意的に受け止められていた。一方、中国語教育を文化戦略の柱の1つにしている中国の動きは俊敏で、国営新華社通信系の映像メディアが、「オバマの娘も学ぶ中国語」として、アメリカでの北京語教育熱を学習者の若者へのインタビュー取材で大々的に報じていたこともある。誰かが進言したのか、オバマ家の中国語学習の話はその後あまりホワイトハウスから出てこなくなった。贅沢にも胡錦濤主席(当時)を相手にサーシャが中国語練習の胸を借りたという、あの微笑ましいエピソードは『約束の地』には記されていない。オバマがインドネシア語はもう忘れたと回顧録で繰り返し強調するのも、「文化」が不可避的にはらむ政治的含意の面倒さから距離を取りたい感情の発露かもしれない。
- 鴻巣友季子「日本メディアの『オバマ回顧録』の翻訳、その訳文がはらむ『危険性』を考える」『現代ビジネス』2020年11月29日 <https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77813?page=2>(2021年5月25日参照)。(本文に戻る)
- 冷泉彰彦「【オバマ回顧録】鳩山元首相への手厳しい批判と、天皇皇后両陛下への『お辞儀』の真実」『ニューズウィーク日本版』2020年11月19日 <https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2020/11/post-1201.php>(2021年5月25日参照)。(本文に戻る)
- 渡辺将人「メディアの見えない地域性:デジタル時代の米中の事例から」『Journalism』2021年6月号(朝日新聞社)(本文に戻る)