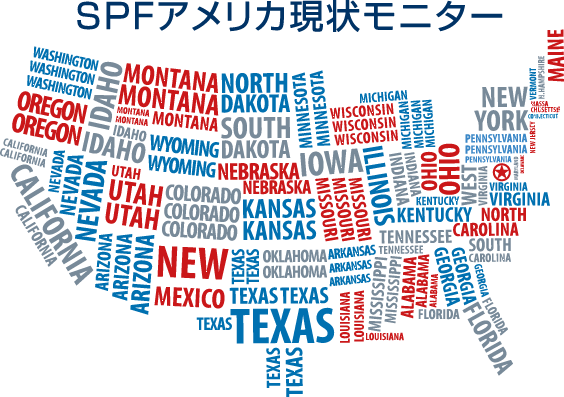作家オバマの「文学作品」として オバマ回顧録論②

渡辺 将人
オバマ回顧録論の2回目は、本書に漂う文学的性格の起源について考察する(「アメリカ大統領回顧録とは オバマ回顧録論①」より続く)。
スピーチライター任せにできない本音の滲ませ方
本書にはオバマ元大統領本人にしか書けないか、少なくとも本人の許可がないと踏み込めない際どい記述が多数盛り込まれている。それが魅力の一つとなっている。ゴーストライターの関与度の判別ポイントは書籍のジャンルで多様だが、共通しているのは2点だ。構成と文章である。
資料や短時間の口述インタビューだけで、第三者がゴーストとして書く場合、過去の著作や演説から引用や繰り返しが増え、エピソード選びも無駄のない整然とした構成になりがちだ。『約束の地』は、わりと構成が「でこぼこ」している。そもそも前編・後編シリーズの時間差刊行で、前編を1期目の途中で中途半端に区切ることからして異例だ。前半生の記述の薄さの反面、選挙戦を詳細に扱う比重など、内容からもオバマ個人の思惑が浮き彫りになる。
そして、美しく個性的な文章だ。オバマ回顧録は、無味乾燥な記録とは一線を画した筆致に満ちている。過剰に詩的で感傷的なわけではない。しかし、一つひとつのシーン描写に遊び心を持ち込んだ独特のメタファーが満載である。スピーチライターの権限だけでは不可能な、オバマの印象に悪影響を与えかねない、超大国の責任者としては少し「傍観者」過ぎと思われかねない表現にも及んでいる(原書の英語もぜひ機会があれば目にしていただきたいが、翻訳の日本語も、読みやすさとオバマの文章の個性の再現の両立に成功している。なお、鳩山元総理をめぐる記述も話題になった翻訳問題については次回以降で言及する。以下、引用箇所の頁数は原書ではなく邦訳の頁)。
首脳会議の集合写真やセレモニーの揶揄は印象的だ(下巻6-7頁)。
「首脳全員がずらりと整列してぎこちない笑顔を浮かべる、小学校3年生のクラス写真によく似たあれだ」
「ひたすら自席で時差ぼけと戦いながら、自分を含めた円卓の面々が議題を問わず入念に用意された原稿に沿って代わる代わる味気ない発言をしているあいだ、いかにも熱心そうな顔つきを必死で保つことになる」
「会議に書類仕事や何か読むものを持ち込んだり、誰かがマイクに向かっているあいだに他の首脳にそっと声をかけてちょっとした職務上の話をしたり」
プラグマティストのオバマは「無駄」が嫌いだった。特に形式を重視する外交の儀典礼を冷めた目線で捉えていた。会談や会議は事前に事務方同士でサブスタンスの多くを詰め終えている。発言要領に沿うことがオバマには退屈だった。とりわけ2者会談で常用される逐次通訳を時間の無駄として感じていた。首脳会談では双方の国が通訳者を用意するが、正確なニュアンスを重視する必要上あえて同時通訳を避ける。しかし、逐次には2倍の時間がかかる。30分なら首脳の実際の発言は15分しかない。理由がある外交の慣習なのだが、オバマはそれを「無駄」と考えて改善を望んだ最初のアメリカ大統領だった(結局は外交の慣習に従った)。デバイスの普及と政権期間が重なったこともあるが、ブラックベリーやスマートフォンによる「内職」に寛容な大統領でもあった。現代的と言えば現代的、効率重視のビジネスマン的な人物だった。
このことは回顧録に書かれているわけではなく、筆者が複数の日米関係筋から聞き及んでいる話だ。だからこそ、上の鉤かっこで引用した部分(邦訳下巻冒頭)を読んで、これぞ「オバマ節」だと確信した。筆者にとってオバマ回顧録は「答え合わせ」の様な経験でもあったが、案の定、多国間のサミットを記念撮影以上の価値がない場と考えていたとの誤解を与えかねない描写も繰り出されて興味深い。ここは意外にもトランプ元大統領と共通する点でもある。
多くの実務家は、日常として内在化されている自分の職業風景には興味を持たない。首脳会談の様子を「内職」の技術まで茶化してあれこれ記述するのは、明らかにジャーナリストや作家の目線だ。ワシントンや外交エリートたちの振る舞いを遠目で観察する「アウトサイダー」であり、部外者感が溢れているとも言える。
「等身大の大統領一家」描写と外交儀礼の狭間
見栄を張らない正直な描写は面白いが、相手国に失礼ならないかとこちらが心配になるシーンもある。ブラジル訪問時のオバマ一家の逸話は特に目を引く。リオデジャネイロでオバマ夫妻と娘2名を乗せた大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」が巨大なキリスト像のあるコルコバードの丘上空にさしかかった際、オバマは娘2名に体を寄せながら指差して「ほら・・・・あそこに今夜行くんだよ」(下巻474頁)と言うのだが、家族が一切関心を持たない。
「だが2人の娘はiPodを聴きながら、ミシェルが持ってきた雑誌をぱらぱらとめくり、私の知らない晴れやかな有名人の写真を目で追っているだけだ。2人の注意を引こうと手を振ると、2人はようやくイヤホンを外して、同じように窓のほうへ顔を向けた。しかし、私のきげんをとるかのように一瞬そこに目をとめ、黙ってうなずくと、また耳にイヤホンを詰め込んでしまった。ミシェルはやはりiPodを聴きながらうたた寝しているらしく、何も言ってくれない」
「私は、2人のそれほど興味のなさそうなようすを見て、少々心を傷つけられた」(下巻474頁)
この家族内の会話は南米外交にも政策にも関係ない。しかし、筆者はとても正直で面白い箇所だと感じた。外交では訪問国に最高の敬意を払うし、テレビは大統領や首相、王族が現地国の文化に魅了されている姿を映す。オバマ本人も「訪れた場所の歴史や文化、人々に対する興味を示すようにした」(下巻178 頁)と述べ、報道されるような観光を外交日程に組み込むことに大統領自ら気を配った。イラク戦争後、「傲慢なアメリカ」の修正を担わされた彼らしい。だが、家族はそうはいかない。
また、人種マイノリティ内での経済格差、教育格差にもオバマは正直な筆運びをする。オバマは自分の娘たちにはアファーマティブアクション(積極的差別是正措置)は不要だと早期から発言し、人種格差を軽視する「脱人種」的にすぎると黒人指導者から誤解を受けてきた。オバマは経済的に恵まれている娘たちが黒人だからと優遇を受ける必要はないと考えていただけだが、ニュアンスを間違えると人種政治的にはリスクがあった。
オバマは外遊先で自国の音楽とゴシップ雑誌で時間潰しをする自分の妻と娘をダシにする「家族自虐」という手法で、セレブリティ家庭の自然体の日常とアメリカの「内向き」を表現することに見事に成功している。パパの仕事のせいでホワイトハウスの自室からそのままどこか知らない国に「連れてこられた感」がよくでている。カメラに映っていない時間の正直な描写だ。四六時中、相手国の言語や伝統工芸の予習をしているほうが偽善的だ。世界の文化に均等に関心があるはずもない。海外に関心がないことだってあり得る。
ミシェル夫人は長旅で疲れていただけかもしれない。しかし、「象徴的な建造物よ。しっかり見なさい」と国務省のレクチャーのようなことを言わないのも、夫に同調して娘をたしなめないのも、ある種ミシェルらしいし、リアリティがある夫婦のやりとりだ。王族のいないアメリカでは大統領一家は神格化されがちだ。彼らを俗物に見せかねないこうしたエピソードは、部下のライターの権限では盛り込めない。オバマ本人の手によるものだ。そもそもブラジルに失礼だ。国務省の南米担当は嫌がるにきまっている。
これが日本の例えば京都上空だったらと想像するとわかりやすい。「ほら、あれが大文字焼きだよ。むかし、ここに都があったんだよ」と話しかけても、iPodのイヤホンを外さずジャスティン・ビーバーを眺めていたとでも回顧録に書かれようものなら、日本のオバマのアンチとファンの増減になんらかの影響を与えたかもしれない。外交的にはアウトであることは自明だ。退任後も影響力に責任がある元大統領は、何でも自由に書いてもよいのかには議論がある。無責任に見える向きもあるだろう。だが、回顧録にこうした本音を散りばめるのは面白い細工で、等身大の大統領一家の空気感を醸し出す、元大統領にしか書けない文章だ。これは「大統領回顧録とは何か」と、元大統領に表現の自由がどこまで無制限に認められるのか、とに絡む問題でもある。
『約束の地』には、こういう政権の政策そのものと無関係な描写が散見される。そこにオバマが行間に滲ませたがっているメッセージが透ける。オバマにとって回顧録は明らかにただの「政権記録」ではない。「作家が大統領職を体験取材した」かのようなこの独特の空気感は一読の価値がある。オバマは見栄っ張りでええカッコしいと思われがちだ。今でもそういうエリート的な雰囲気は抜けていないが、文章表現においては「自虐」で自分や身内をピエロ化する技を駆使する余裕を見せている。
「作家オバマ」が抑制された3つの理由
コミュニティ・オーガナイザー出身の政治家にはしては、文章やレトリックにやたら凝っていると思われるかもしれない。日本語の翻訳でもそれは十分に味わえる。だが、それもそのはずで、オバマは作家だからだ。「作家志望だった文学青年」というよりも、「作品を発表して一度デビュー」したが違う道に進んだ「元作家」と言ったほうが正確だ。オバマの文章を読む際に、「読み方」を変えてしまいかねない情報であると同時に、期待値をむやみに高める先入観にもなる。しかし、この経歴を避けてオバマの文章を吟味するのは、むしろ不誠実になるだろう。そんな経歴聞いたことがない、と思われるかもしれない。たしかに今回の回顧録『約束の地』にもそのことはほとんど書かれていない。私たちが「作家オバマ」の顔にさほど馴染みがないのは、オバマ大統領の略歴上、明らかに情報の抑制を余儀なくされてきたからだ。その理由は大別して3つある。
第1に、元作家ないしは作家志望の元文学青年という経歴が、超大国の指導者にして最高司令官としては望ましくなかったことだ。元軍人や法律家が、繊細な芸術家的な才能もたまたま持ち合わせていて後年それを発揮したというのとはわけが違う。オバマのどこか白黒つけない、優柔不断にも見える、真理を求め、なんでも物事の両面を見て大所高所から傍観者的に観察する感覚は、作家としては素晴らしい才能だが、リーダーシップと決断が仕事の大国の指導者には向かないかもしれない。慶應大学の中山俊宏教授は、回顧録の読後感として「ドストエフスキーの『地下室の手記』風に絶えず自分に問いかけ、信念を持ちつつ疑い続けるオバマの気質」が伝わってくると語り、「おそらくこういう人は大統領には向いてないんだろう」とも指摘した。実に言い得て妙である。だからこそオバマ側近たちは政治家オバマのブランディングに「文学」が表面化しないように細心の注意を払ってきた。
白人と留学生との交流と文学:オクシデンタル・カレッジ
第2に、オバマが進学したオクシデンタル・カレッジという大学での活動や交友関係が、作家オバマの核心だったことだ。オバマの学歴で有名なのはハーバード大学ロースクールだ。3年からコロンビア大学に編入する前に通っていたロサンゼルス郊外のオクシデンタル・カレッジはよく知られているわけではない。しかし、拙著『評伝バラク・オバマ』1で描いたように、オバマが演説や文章の決定的な才能の開花を経験したのは大学時代だった。オバマはもともと創作への関心と素養があり、ハワイのプナホスクール時代に優れた詩を校内雑誌に掲載している。大学で彼が選んだサークル活動は文芸の会だった。趣味のバスケットボールをやめたわけではないが、大学では小説や詩の創作に没頭した。そしてオバマは文学仲間と一緒にニューヨークに進出する。
2008年大統領選挙前後、コロンビア大学時代のオバマを覚えている学友がほとんどいないことが陰謀論的に論じられたことがある。それは彼が大学では最低限の授業に出る以外は、新規の交友を拡大せず、西海岸から共に越してきた仲間と文学に没入していたからだ。日本でもそうだが、大学は低学年時代にできる友人が核になる。オバマもコロンビア大学で新しい友達を作るよりも、オクシデンタル時代の仲間と4年間付き合いを継続した。オバマの大学生活はサークル活動と交友関係上は4年間ずっと「オクシデンタル時代」であった。コロンビア大学の同年卒業生に聞き取りをして足跡が出てこないのは当然だ。
アメリカでは入学や中退は学歴にならず、学位だけが履歴書に記される。知名度があるコロンビア大学とハーバード・ロースクールが、政治家オバマのブランディングとしては優先され、人間オバマの核心を形成したオクシデンタルは容赦無く抑制された。今回の回顧録でもオクシデンタル時代の知的営みについては、女性の気を引くことばかりに関心があったような自虐的な謙遜表現に終始している。しかし、オバマに文章創作の場を与え、競作や批評会を通じて、オバマの才能を開花させたのは、まぎれもなく同カレッジ時代の文学サークルだった。オバマが自分で筆を入れた過去の演説草稿を研究する上でも、当時の文学仲間への取材は必須だが、そこに関心を及ばせた米メディアは僅かだった。それはオクシデンタル時代の文学仲間が、ほとんど白人と外国人留学生だったことに起因する。
オバマはハワイ、インドネシア時代は、人種アイデンティティとしては「無人種」に近かった。白人のシングルマザー、インドネシア人の継父と異父妹、白人の祖父母の家庭で育ち、ミシェル夫人と結婚するまでオバマは黒人と生活したことがない。その上、ハワイは日系人が多数派のアジア系を筆頭に多人種が混ざり合う島だった。カリフォルニア進学で黒人の友達ができて徐々に黒人意識に目覚めるのだが、コアの仲間や恋人は白人や外国人だった。オバマが黒人性に覚醒したのはシカゴ黒人街での住民活動を通してで、厳密に言えばミシェル夫人との邂逅以降だ。シカゴの住民活動時代の上司や同僚も全員が白人だった。そのため、文学に没頭していた頃のオバマの話は、黒人政治家オバマの立志伝としてアピールしないどころか矛盾感も与え、政敵への攻撃材料になりがちだった。
オクシデンタルの学友らは「文学の聖地」ニューヨークを同時期に目指して、彼ら同士で下宿を共にしたり誰かの家に常に集まったりした。手塚治虫や藤子不二雄などの大漫画家を輩出した日本の「トキワ荘」のようなものをイメージしていただければよいだろうか。課題図書の批評会を兼ねた酒盛りも開かれた。オバマには創作のライバルがいた。同じアパートに住み、シカゴでオーガナイザーになった後も郵送で作品を交換して批評しあった仲間だ。オーガナイザー時代のある上司は、オバマがシカゴでの活動をモデルにした小説の執筆途中、生原稿を借りて読んだ。それがのちの『ドリームズ・フロム・マイ・ファザー』である。オーガナイザー経験ですら文学の素材だったとの見方もできる。作家オバマ青年の前半生は、私小説を書くためにあったのだ。
カリフォルニア時代、ニューヨーク時代、オーガナイザー時代を含む、ハーバード入学までの青年期の全時期を貫く交友関係が、オクシデンタルの文学仲間であり創作活動だった。しかし、彼らは皆、白人や留学生だった。アメリカ国内の黒人と無関係の交流歴は、コスモポリタン的な視野の広さを感じさせても、「アメリカ黒人」魂や愛国心の証明には逆行する。
「自伝」として一人歩きした文学作品
そして第3に、『ドリームズ・フロム・マイ・ファザー』という本の存在だった。政治家の「キャンペーン本」ではなく、作家オバマの作品だった。文学仲間は仲間の作家デビューを喜んだ。だが、政治家オバマの本としては不都合な面もあった。オバマの著名化とともに「自伝」だと思われてしまったことだ。オバマの名誉のために言えば、彼はこれが自伝だと一度も言っていない。原書の副題にもそう書いていない。メディアや海外の翻訳版の版元が勝手に判断したことだ。
デイビッド・レムニックはこう書く。
「多くのジャーナリストはDreams from My Fatherを読み、学術的もしくはジャーナリスティックな真実性の基準に則って本を書いていないことに失望した。実際、他の自伝作家と違い、オバマは読者に彼の本の柔軟な事実の扱いについて警告している。「作家に都合のいいように出来事に脚色する誘惑」と「都合よく記憶が欠落する」ことに自覚的であるとしている。純粋に事実を表現している振りはしておらず、フィクションのツールをいくつか適用している」
「登場人物は実際の人物の合成だ。(家族と著名人以外)名前は変更され、時系列も話の通りをよくするために変えたとオバマは認めている」2
回顧録『約束の地』でオバマは、『ドリームズ』刊行前までの前半生については最小限しか記載していない。これは回顧録前に別の自著がある他の元大統領達と同じ理由に見えて違う。彼の場合は前半生について述べる必要がなかったからではなく、へたに忠実な記載をすると小説仕立てだった『ドリームズ』との矛盾が生じて、世界的に混乱を招くからだ。オバマが本気で自分の前半生を正確な史実で振り返れば、それはそれで興味深い、ハワイ論、インドネシア論、コミュニティ・オーガナイザー論が期待できる。50番目の州の離島出身大統領というだけで「亜流」なのにインドネシアからの「帰国子女」で、文学青年の青春を駆け抜け、住民運動で世界を変えることに早々に2年半で幻滅して弁護士資格の必要性に目覚める。
このオバマの一番面白い部分が回顧録ではこれ以上はない薄味の早回しで飛ばされている。親友や恩師の固有名詞は出てこない。『ドリームズ』はフィクション仕立てで架空の名前だったので、オバマに決定的な影響を与えた親友や恩師の実名が、結果としてオバマ自身の手による書物に記載されずに終わってしまった。それもこれも私小説『ドリームズ』が勝手に自伝として一人歩きしたことのブーメラン効果だ。
オバマは必ずしも筆が速くない。凝り症なのだ。完璧主義でもある。演説もそうだが、草稿を夜通しあれこれ納得するまでいじくる。『ドリームズ』の刊行が実現した頃、すでにオバマはハーバード大学ロースクールを卒業し、若き講師としてシカゴ大学で憲法論を講じていた。法律家の顔が社会的には主役だった上に、ミシェル夫人と出会っていた。自分のアイデンティティクライシスを解決するための精神治癒のような創作だった『ドリームズ』への黒人社会の好意的な反響で、オバマは「十分に黒人(ブラック・イナフ)」になれた手応えを感じ、政治家を志すようになる。この頃から文学仲間とも疎遠になっていく。
今回、回顧録の感想をオバマの旧友ら取材先に順に聞いて回ったが、案の定、最も評価が辛口だったのは文学仲間たちだった。オバマをプロとして見ているからでもあるし、彼ら自身の多くが作家やジャーナリストとして大成していることも関係しているが、それだけではない。オバマが文学や知に目覚めたあの時代、それを手助けした恩師や仲間がいたのだが、そのことを照れ隠しもあってか、『約束の地』では詳述せずに親交が深かった仲間たちをむしろからかうような描写をしたことに複雑な反応が入り混じった。
『ドリームズ』がなければ政治家オバマは生まれなかったが、前半生の史実を回顧録で深く書きこめない曖昧なままで終わる弊害を伴った。これは大統領史家やアメリカ政治研究者にとっても凄まじく大きい含意である。未来のオバマ時代の総括書にも影響を与える。オバマ評伝の著者として、筆者は回顧録での「答え合わせ」を心待ちにしていた。正面から自分史を語り直すことを期待していたからだ。ところがオバマは前半生を詳述しない手法を採った。それは、まだオバマには様々な「しがらみ」があることを示唆する。『ドリームズ』は嘘偽りない、オバマの黒人論であり人種物語だが、それが自伝ではないとすれば「黒人としての覚醒」は嘘だったのか?と悪ノリする政敵もいるからだ。『ドリームズ』は、政治的事情から今後もなんとなく自伝と勘違いされたまま回顧録と併せて読まれていくだろう。もちろん、オバマはまだ若い。回顧録とは別に彼の幼少期についての単著をいずれ記す可能性はある。いずれにせよ、世界のオバマ伝記作家の前半生部分の「答え合わせ」は、先延ばしになった。
さて、これで「前提」は整っただろう。オバマの演説が詩のような独特な流麗さとリズムを伴っていて、深遠な比喩に満ちた非凡なのもであったのも、今回の回顧録の不思議なトーンも、すべてオバマが作家であることに由来する。彼は回顧録でそれを発揮したいと待ち望んでいた。世界中の人に読んでもらえる大統領回顧録という「舞台」を用いて、心の中ではまだ作家でもある著者が、思う存分作品に凝りたいのは自明だ。オバマの欲求は流麗なレトリックや比喩を駆使した文学創作だ。オバマ回顧録でもそれを発揮したいと腕まくりして機会を待ち望んでいた。その意味で、他の大統領回顧録と並列することに適さない。
しかしながら、オバマの「文学性」は諸刃の剣にもなっている。本質を突いた観察眼を働かせた文章に表れるオバマの深い思索と俯瞰的目線は、政党や超大国の指導者としてはある種の弱さの表れでもあるのは事実だからだ。次回以降、内政と外交の記述を具体的に検討する中でそれを確認したい。
PDFファイル(333.2KB)