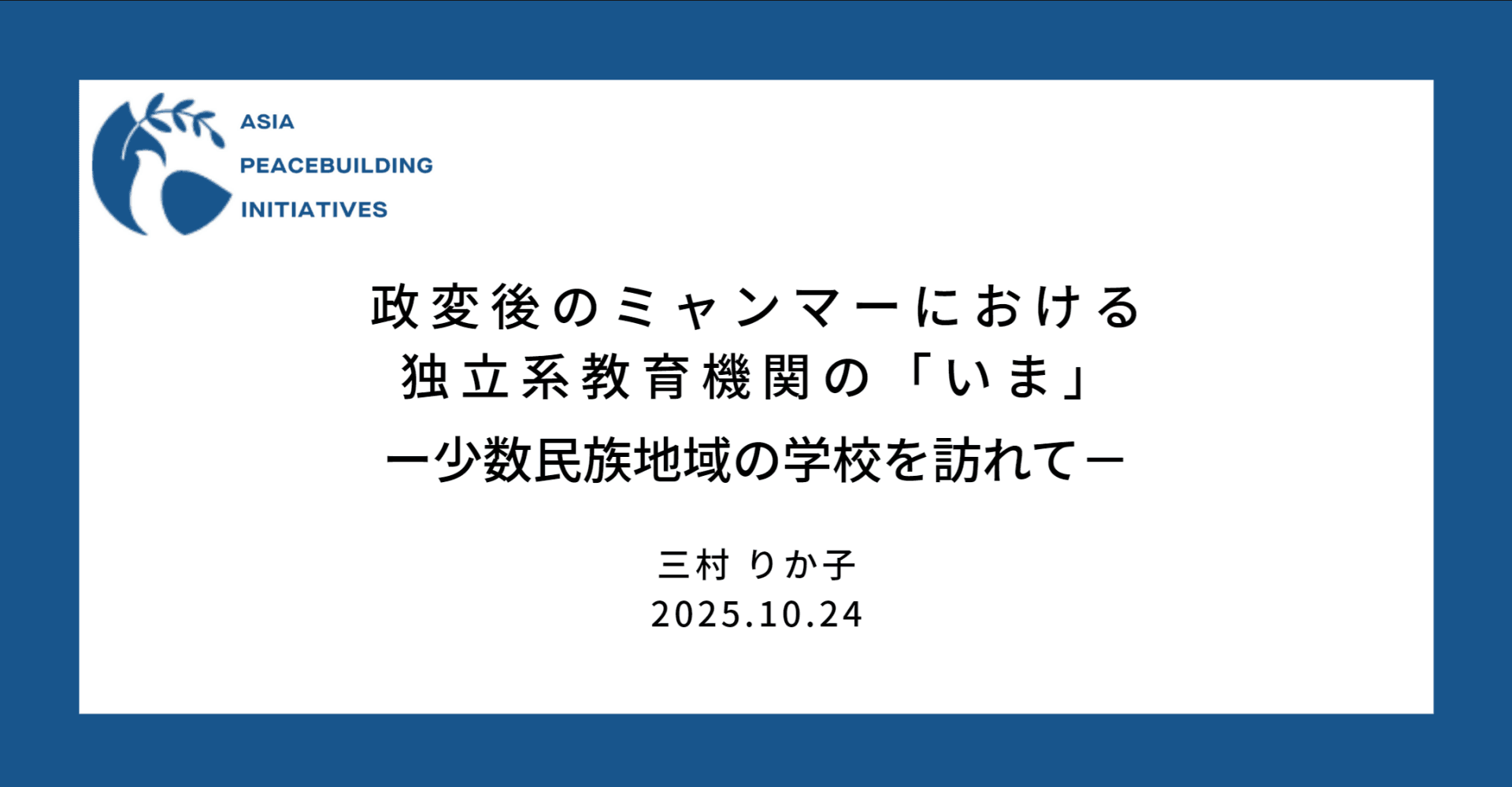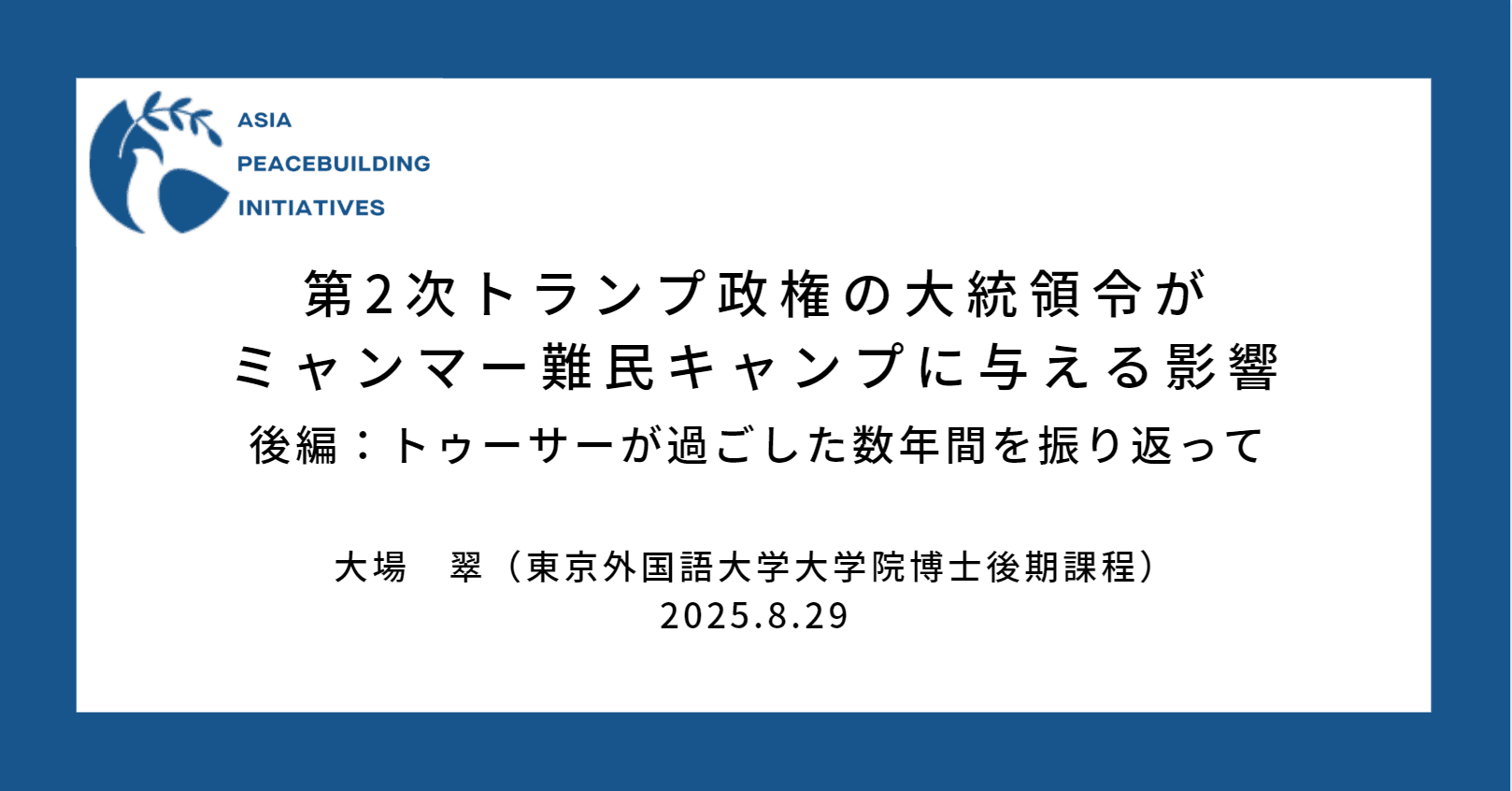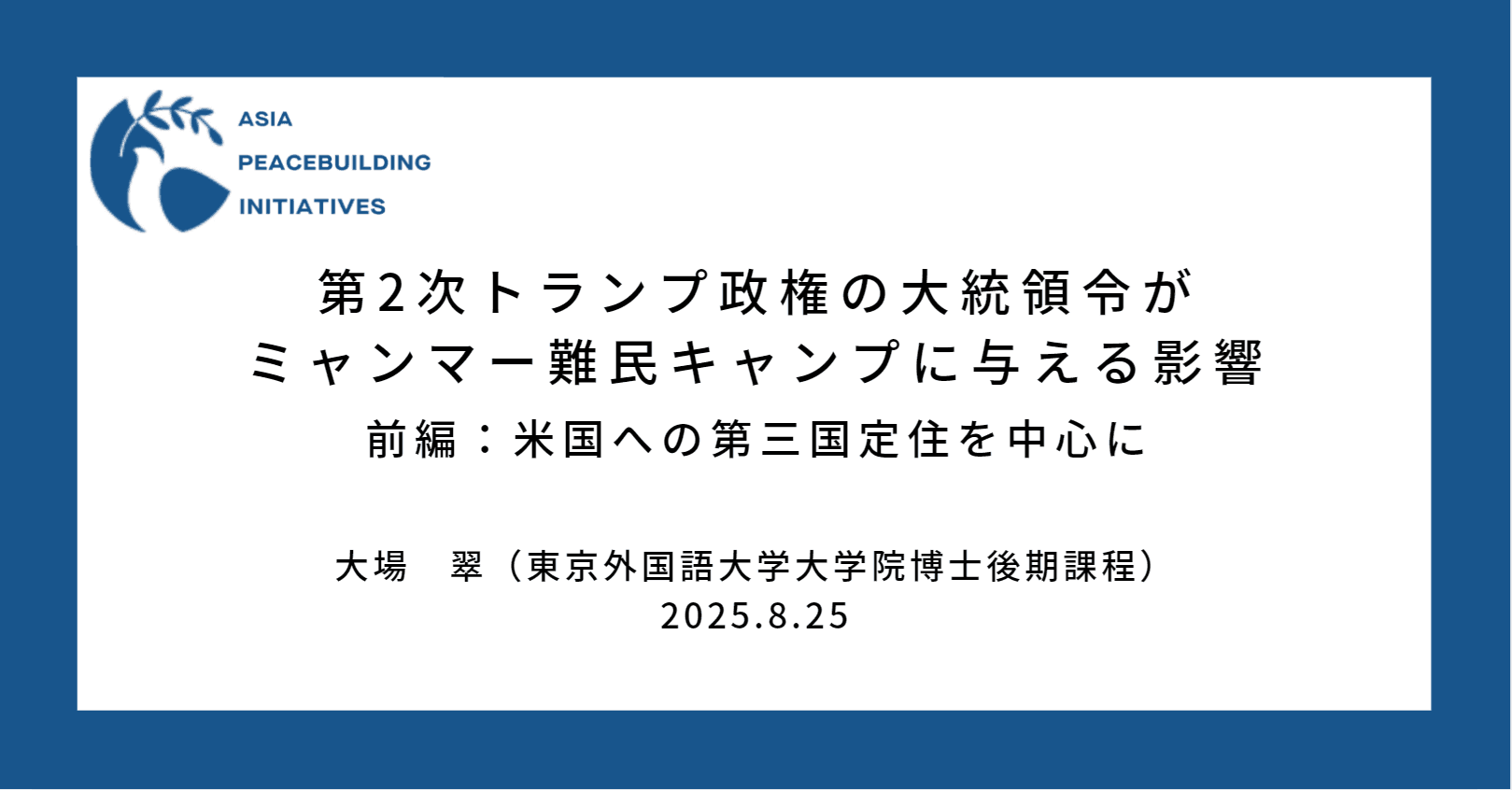- ミャンマー
ミャンマーにおける最近の宗教的暴動: ビルマ・ムスリムの現状

すっかり定着していた軍事独裁政権から民主主義誕生へというミャンマーの変革のストーリーは多くの観測筋を驚かせた。しかし、2012年の秋から2013年末にかけて発生した仏教徒によるムスリムへの暴力的攻撃がこの前向きな動きに影を投げかけている。
現在起きている仏教徒とムスリム間の紛争は、ラカイン州で仏教徒の女性がレイプされ殺害された2012年に始まった。この事件に対する非難の矛先がロヒンギャ民族に向けられ、ラカイン民族仏教徒は報復としてバスを攻撃し、10名のムスリムを殺害した。仏教徒とロヒンギャ民族との衝突は瞬く間に広がり、暴動と集団暴行の大きな波を引き起こした。双方に死傷者が出ているものの、多くの観測筋では、ロヒンギャ民族側の方が過度に人命や財産を失っているとの見方で一致している。250名以上が殺害され、更に多くの人々が負傷し、25万人のムスリムが住む場所を追われたが、その多くはラカイン州に住んでいた。この紛争によって追われた人々は、今も仮設キャンプに暮らす。
2013年3月の終わり、メティラ県の中心部で暴徒たちが3日間にわたり、ムスリムの住居、店舗、モスクを焼き払うという凶行におよび、40名ほどが殺害される結果となった。ムスリムが所有していた店舗の残骸には「969」という番号がスプレーで書かれていた。3桁の数字「969」は仏教における「三宝」を意味する。最初の「9」は、仏の9つの偉大な特性、「6」は法(仏の真理)の6つの偉大な特性、二つ目の「9」は、僧(僧侶)の9つの偉大な特性を表わしている。「969」の基本的なメッセージは、ミャンマーは仏教徒、特にビルマ民族の仏教徒のものであり、他の民族のものではないということである。
それからほどなく、僧侶たちが旅をしながら「969」のイデオロギーを説いて回った後、バゴー地域で暴動が勃発した。加えて、ヤンゴンの北にある街、オッカンでも新たな衝突が起き、少なくとも1人が死亡している。暴力の終わりが見えない中、暴動によって行き場を失った何千人ものムスリムが、現在難民キャンプに閉じ込められたままになっている(リンク1)。反イスラム感情は仏教徒が多数派を占めるこの国に蔓延しており、ミャンマーの北東、中国との国境に近く、商業の中心都市ヤンゴンから約700キロ離れた山深い辺ぴな場所でも暴力は発生している。そして2013年10月の始め、ミャンマーの西部、サンドウェーの仏教徒住民とムスリム住民との間で衝突が生じ、再び人命が失われる結果となった。5名のムスリムが死亡し、多数の住居が破壊された。
「969」運動とビルマナショナリズム

多くの観察筋は、仏教徒ナショナリストが先導する「969」運動が、ミャンマーの大部分で起きている暴力を含め幅広い反ムスリム運動を煽っている、または少なくともその背後にあると考えている。それは、マンダレーを拠点とする有名な僧侶、アシン・ウィラトゥが率いるナショナリストの反ムスリムキャンペーンの旗印になっている。
アシン・ウィラトゥは、マンダレーに近い彼の地元で反ムスリム暴動を扇動したとして、2003年に逮捕されているが、この暴動では仏教徒が10名のムスリムを殺害している。アシン・ウィラトゥには、25年の刑が宣告されたが、2011年の恩赦の一部として釈放された。一番最近の国内反ムスリム運動が急激な高まりを見せたのはそれからすぐのことだった。それ以来、アシン・ウィラトゥは、急速に大きくなる「969」運動の急先鋒に立って多数のスピーチを行ない、仏教徒に対し「969を掲げる店だけで買い」、ムスリムの店をボイコットするように呼びかけている。この運動のイデオロギーには、仏教徒の宗教的狂信に強いビルマナショナリズムと僅かとは言えない民族的排外主義が取り入れられている。当然ながらこのレトリックは、国の人口の三分の二を占めるビルマの主要な民族グループであり、特にイラワジ川流域の低地においてその存在が顕著なビルマ民族の共感を呼んだ。ビルマ民族の大部分が上座仏教徒である。
また、969にはムスリムのシンボルである786という数字に対抗する意図があるとの見方もある。786は、コーランの冒頭の一節をアラビア文字の記数法で数字化したものに由来する。ミャンマーや南アジアの各地でシンボルとして使われており、特にイスラムのハラルレストランで見られる(根拠のない、しかしミャンマー内に広く知れ渡っているうわさでは、各桁を合計すると21になる786は、ムスリムの秘密のコードであり、21世紀のミャンマーあるいは世界を乗っ取ろうとする欲望を示しているという)。
反ムスリム暴動がミャンマーを揺るがすと、テイン・セイン大統領は、大虐殺を「政治的日和見主義者と宗教的過激派」のせいにした。そして異なる信仰を持つ人たちへの憎悪をかき立てることで、高尚な宗教の教えを私利私欲に悪用した者たちに向けて警告を発した。2013年10月4日、テイン・セインは、ミャンマー西部のサンドウェーでムスリム住民と仏教徒住民間の衝突の勃発を画策した「よそ者」を非難し、それが彼の紛争地域への初めての訪問を貶めるための計画的な行動であることを示唆した。しかし、その「よそ者」が誰なのかを明確にはしなかった。
事件は仕組まれたのか?
ミャンマーの人権に関する国連特使であるトマス・オヘア・キンタナ氏は、国軍の関与を疑っている。
目の前で残虐行為が行なわれている間、軍、警察、その他の民間の法執行部隊はずっと待機していたという例があげられる、と彼は言った。こうした行為には、たまたま仏教徒である国粋主義者が周到に計画した暴力も含まれる。これは、そうした行為に対する国家のある部門による直接的関与、あるいは間接的な共謀や支援を意味する可能性を示している。
新たな組織、イラワジパブリッシンググループを設立したジャーナリストのアウン・ザウが、ニューヨークタイムズ紙に書いたところによると、暴力に加担するよう政府内の派閥が僧侶たちをけしかけていると考えられるという。彼は破壊的な反ムスリム暴動は、偶発的なものではなく陸軍の強硬論者によって画策されたものであり、ミャンマーの国内改革と外部世界への開放を妨げていると述べている。
強硬論者のヘイトスピーチは、ミャンマーの多くの普通の仏教徒たちに影響を与え、彼らをムスリムへの暴力へと駆り立てている。その一方で、仏教の僧侶たちは、暴力に対してうわべだけの立派な態度を取っている。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの客員研究員でミャンマーからの亡命者のマウン・ザルニ博士は、ミャンマーでの最近の暴力に対する準民間政府であるテイン・セイン政権の役割を注意深く精査した。彼は、政府が関与した多数のあからさまな反ムスリム活動について挙げているが、これにはロヒンギャに対する暴力への後ろ盾やビルマ軍隊からのムスリムの「一掃」から、反ムスリム出版物の承認やアシン・ウィラトゥ自身が躍進するための支援まである。
とはいえ、グリフィス大学のアンドリュー・セルスが述べたように、ミャンマーにとって宗教的不寛容は今に始まったわけではなく、政権が自らの失敗から注意をそらすために、2011年以前からいくつかの反ムスリム暴動をけしかけたとされている。彼は、問題なのは単なる治安部隊の戦略ではなく、ミャンマーの差別的な政策と地域社会の態度であり、それはつまり反ムスリムの動乱が再発する可能性が高いことを意味すると指摘している。この問題に真剣に取り組もうとしていると見られるミャンマーの政治家はほとんどいない。
暴徒たちと政府との間に暗黙の協調があると見てとる観測筋もおり、強硬論者たちがアウン・サン・スー・チーの信用を失墜させようとしていると疑っている。ミャンマー専門家で作家のベルティル・リントナーが語っているが、政府はスー・チーが指揮をとる支援を非常に恐れているという。彼らはロヒンギャに肯定的な発言をせざるを得ないような立場に彼女を追い込みたいのである。そうすれば、反ムスリム感情を抱いている者が多いミャンマーの仏教徒の間で人気が高い彼女を貶められる。多くのビルマ人が仏教を保護するという名目のもと、暴力を認めているように見える。一方で、彼女がこの問題について沈黙を守れば、人権に対して毅然とした立場をとる彼女を支援する人々を失望させることになる。
さまざまな方向への指摘があるが、ミャンマーにとってその多くが、最近の騒動は誰かがまたはあるグループが意図的に扇動しているものであると認めているように見える。
メディアの役割
ミャンマーにおいて始まったばかりの情報文化の役割も、「ヘイトスピーチ」を煽りたてる悪意のあるうわさの広まりに責任がありそうである。2012年8月に終わりを告げたばかりの国による検閲はいまだに残っており、ほんの一握りのミャンマー国民しか独立系メディアソースのニュースや東南アジアの至るところで使われているオンラインソーシャルメディアへのアクセスを持っていない。確かな情報ソースによれば、およそ6千5百万人の人口のうち、フェイスブックのアカウントを持っているのはわずか80万人程である。週刊の新聞を読んでいるミャンマー国民が30万人いる一方で、最も人気のある出版物の中にはムスリムに対する偏見を見せるものもある。更に、ミャンマー国民の大多数が口コミ、家族、友人、近隣の人々、僧侶から政治情勢を聞いているが、どれも信頼性のあるニュースソースとは思えない。しかし、最近の宗教的紛争を起こしている更に深い原因のダイナミクスを理解するためには、検討されるべき政治的、および文化的状況のニーズをもっと綿密に調べる必要がある。

ビルマムスリム:ビルマ仏教徒との不穏な関係
ムスリムが中央アジアや東南アジアの他の地域から、初めて今日のミャンマーに交易商人としてたどりついたのは、11世紀初頭だった。現在のミャンマーにおけるムスリム人口には、パガンで成立した初めてのビルマ王朝以来からの最も古い移住者であるインド系のパシス、パシュ(マレー系)、パンディーとして知られる中国系、ロヒンギャ(北部ラカイン)、カマン(南部ラカイン)、そして系統の混じり合った多くの人々がいる。またビルマ民族ムスリムもいるが、それは婚姻あるいは改宗によるものである。しかし大多数のビルマ民族と過去の政権から見れば、彼らはムスリムになってビルマ民族をやめた者たちであり、恐らくビルマ民族ムスリムあるいは単なる外国人に対する蔑称である(もともとは、どのような宗教に属しているかにかかわらずインドからの移民に対して用いた)カラーとして分類されるのだろう。
1930年代、経済的苦境と反植民地運動により暴動が引き起こされたが、それは概して、インドからの移住民に対して向けられた。1938年の暴動は反植民地的である一方、ムスリムも標的にしていることがよりはっきりしていた。しかし、1962年、軍事独裁政権が成立した後は、ムスリムが標的であることに疑問の余地がなかった。
半世紀にわたる軍事支配の間、反ムスリム暴動は何度も起きた。暴動には多数の僧侶が関与していたという事実にもかかわらず、多くの人が、事件は軍指導者が準備したもので、経済的苦境や政策の失敗から人々の注意をそらし、ナショナリストの感情を刺激するためだと考えていた。軍首脳部には人々の暮らしを良くすることができなかったため、ムスリムが国民の怒りから彼らを守るための都合のよい身代わりになったというわけである。
更に、ムスリムは明らかにビルマ軍、政府高官や国の多くの名のある地位から締め出された。また高等教育を受ける機会も阻害された。結果として多くのムスリムが高等教育を必要としない、あるいは政府との繋がりの必要がない、小さな商売に従事した。多くの公式あるいは非公式なルールや規定が導入され、ムスリムを抑圧した。陸軍士官学校や公務員研修でのプログラムにはカリキュラムの一部に反ムスリム洗脳があった。市民権にかかわらず、ムスリムを二級の市民あるいは非市民として扱うことが、政府関係機関の中で当たり前となった。要するに、ムスリムは自身の母国において抑圧され虐げられた人々であった。
ビルマ民族ムスリムは暴動の標的にされ、差別を受け、軍によって抑圧され続けたが、それでも軍事政権の初期にはビルマ民族仏教徒と健全で調和の取れた関係を維持することができていた。はるか昔には数百年にわたり、ミャンマーの仏教徒とムスリムが平和に共存していた。ビルマ民族仏教徒はビルマ民族ムスリムのイスラム教への信仰に敬意を表わし、娘や姉妹がビルマ民族ムスリムの男性と結婚することも許し、結婚後に彼女たちがイスラム教へ改宗しても反対しなかった。同様に、穏やかな信仰心を持つ大多数のビルマ民族ムスリムは、仏教徒の宗教的行事にも参加した。実際、多くのビルマ民族ムスリムの生き方や文化的アイデンティティは、ビルマ民族仏教徒のものと大きく異なるというものではなかった。しかしながら、軍指導者のビルマ民族ムスリムに対する政策は、二つのコミュニティを多くの面で分断させるように計られていた。
イスラムの国際的影響力とビルマムスリム
あらゆる政敵を排除しようと躍起になっていた軍の独裁者たちは、ビルマ民族の社会にうまく融合していた穏健派のムスリム指導者と違い、民主化運動にはほとんど関心のない極めて保守的なムスリムグループを気づかぬうちに擁護していた。彼らの思想はデオバンド派、タブリーグ派、ジャマート派、ワハビー派の運動が混ぜ合わされた学派に厳密に従っている。昔から宗教的に穏健なビルマ民族ムスリムとは大いに異なるその思想は、宗教的慣習の中でゆっくりと確実により保守的で厳格になってきている。多くの人が洋服の着こなし方を典型的なビルマスタイルから、デオバンドスタイルに変え、あごひげを生やし、インド人やベンガル人に非常によく似た洋服を着る。新しい形の宗教指導者はまた、多くの宗教的見解を押し付けたため、ビルマ民族ムスリムがビルマ民族仏教徒と調和の取れた社会的関係を維持することを難しくした。
軍事独裁政権の閉鎖的社会主義経済と誤った国家運営、および仏教をゆがめた政治的パラノイアに駆り立てられた過激なナショナリズムによって、ミャンマーは1987年までに東南アジアの後発発展途上国の一つになった。かつては地域において前途有望な国の一つだったが、今や蔓延する貧困、雇用不足、希望のない将来に直面している。こうした状況によって、総じて多くのビルマ民族が、合法的あるいは非合法的に、祖国を捨てざるを得なくなっており、隣国で不法就労者となる危険を冒している。ムスリムが多く占める国であるマレーシアへ行くが、中東のアラブ諸国へと向かい単純労働者として働く者もいる。
こうした国からはミャンマーの不法就労者が不当に扱われているとしばしば報告されている。これが多くのビルマ民族ムスリムを、迎えてくれるムスリムとの連帯意識の中で、より一層信心深くしている。過去に経験してきたビルマ民族ムスリムに対する差別と、危機に際して彼らが国からの庇護に頼ることができなかったという事実を考えると、ミャンマーのビルマ民族ムスリムが宗教的慣習においても社会的交流においても内向きになってしまったことは理解できる。多くのムスリムグループが、自身の宗教的コミュニティを超えて積極的に慈善活動行なってきているのに、非ムスリムの間では、イスラムコミュニティは偏狭であり、イスラム教の宗教的なしきたりは内輪的でうさんくさいと感じられている。こうした認識はまた、 世界的に語られている「テロとの闘い」にも影響されている。そこでは、あらゆるモスクやマドラサ(訳注:イスラム教の神学校)が武装駐屯地かテロリストのトレーニング場のように思われ、イスラムの攻撃性という国際メディアでのよくある描写によって固定された印象がある。ワハビー派の振興と結びついたイスラムの国際的影響力のインパクトによって、ビルマ民族ムスリムは、忠誠心を祖国からイスラムの連帯へと移すことを余儀なくされている。
ビルマムスリム:1982年国籍法により国籍を持たず

市民権は、さまざまな国際的人権協約の中で定められている。しかし、多くのミャンマー観測筋がミャンマーの1982年国籍法は、世界人権宣言や、国際条約に基づくビルマの法的義務に適合していないと言っているが、これは元独裁者であるネ・ウィン大将の統治下で発布されたものである。加えて、国籍法は自由裁量でミャンマーの多くの人々から、そのほとんどはビルマ民族のムスリムであるが、市民権を奪えるとも述べている。
以前の1948年国籍法の第4条では、「少なくとも2世代の祖先が連邦の領内のいずれかに居を構えており、両親および自身がそうした領内で出生している者を、連邦の国民とみなすものとする」としていた。しかし、ミャンマー(当時はビルマ)が独立した1948年に導入されたこの以前の国籍法とは違い、1982年国籍法が市民権を保証しているのは、その家族がミャンマーに少なくとも3世代暮らしていることを証明できる者に対してのみである。公認されている135の民族には市民権が認められているが、そこに含まれているのは主要な民族である、ビルマ、ラカイン、チン、シャン、カレン、モン、カレニである。国籍法の第2章第3条は、これらの民族グループと1823年以前にビルマに定住した者たちのみにビルマの市民権が与えられると謳っている。誰かが1823年以前に定住したかどうかを証明するのは難しいことが多く、仮になんとか証明することができても、大抵の場合、相手がムスリムであることが分かると出入国審査官がその証拠を却下する。
1982年国籍法には、帰化した場合の市民権獲得のプロセスもあるが、この市民権は他の多くの国での帰化と同じではない。ミャンマーでは、帰化国民に国民と同等の権利を与えていない。そればかりか、これは国民になるための中間の段階でさえない。帰化国民は、専門職に就く機会が平等に享受できず、選出公職にも立候補できない。更にビルマ法では、「国家に不満や不忠を表明した」「不道徳行為を伴う違反を犯した」などさまざまな理由で帰化国民の資格を取り消すことができる。ビルマ民族ムスリムに対する市民権問題が適切に対処されない限り、ミャンマーの将来とあらゆる改革プロセスが確実なものとならないことは明白である。
国際社会は、ミャンマー政府に圧力をかけ1982年国籍法を改正させ、国内の資格要件を満たしたすべての人が平等に市民権にアクセスできるようにし、民族や宗教を理由として差別を受けないようにしなければならない。
ティン・ウィン・アクバル
在日ビルマ市民労働組合 代表
https://observers.france24.com/content/20130424-muslim-burmese-refugees-camps-fear
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strange-numerological-basis-for-burmas-religious-violence/274816/
http://www.nytimes.com/2013/04/25/opinion/will-hatred-kill-the-dream-of-a-peaceful-democratic-myanmar.html?ref=opinion
TRACKBACKS & PINGBACKS
境域に生きる:南アジア系の人々とミャンマーの時空間 | Asia Peacebuilding Initiatives

在日ビルマ市民労働組合 代表