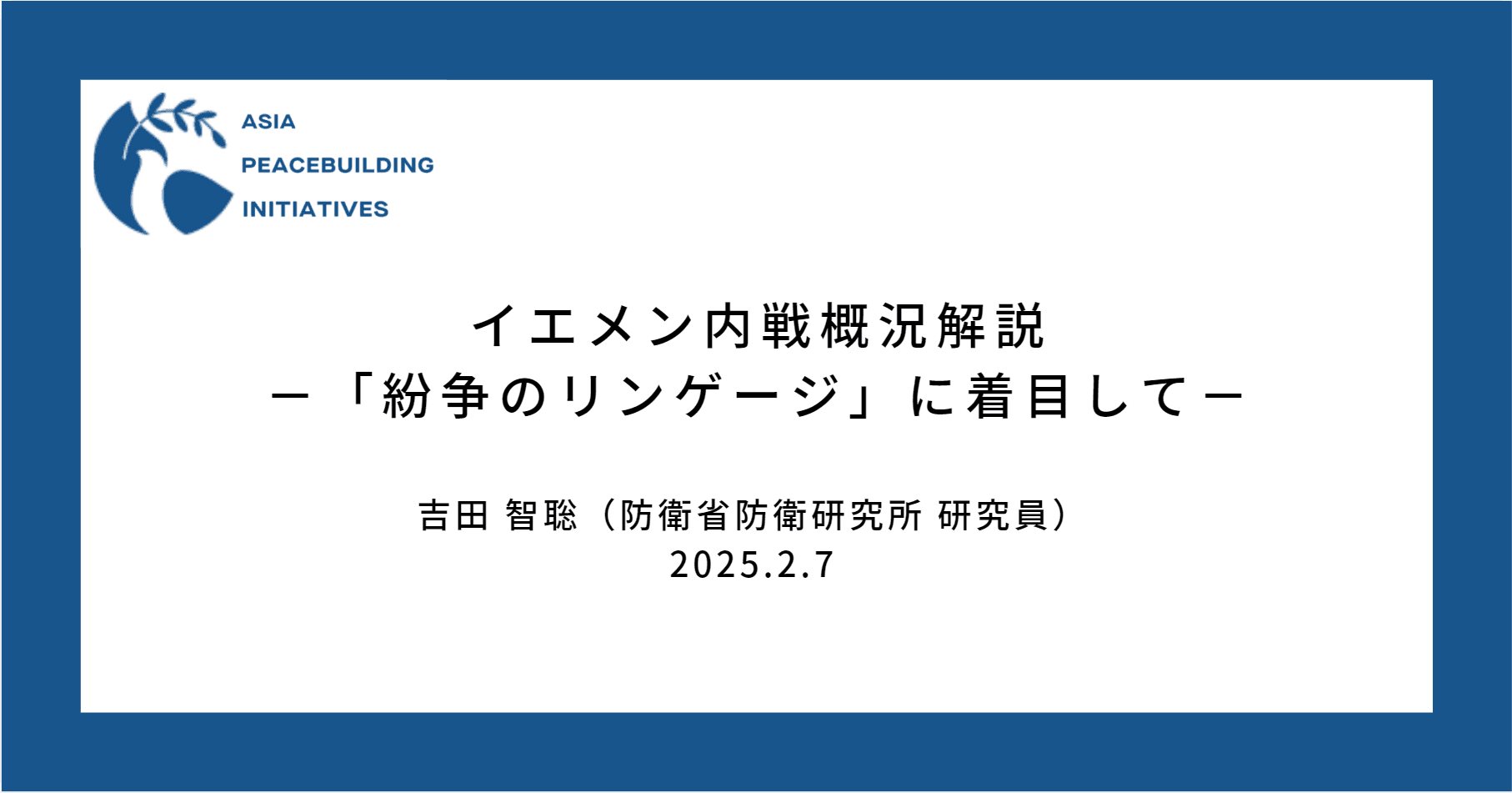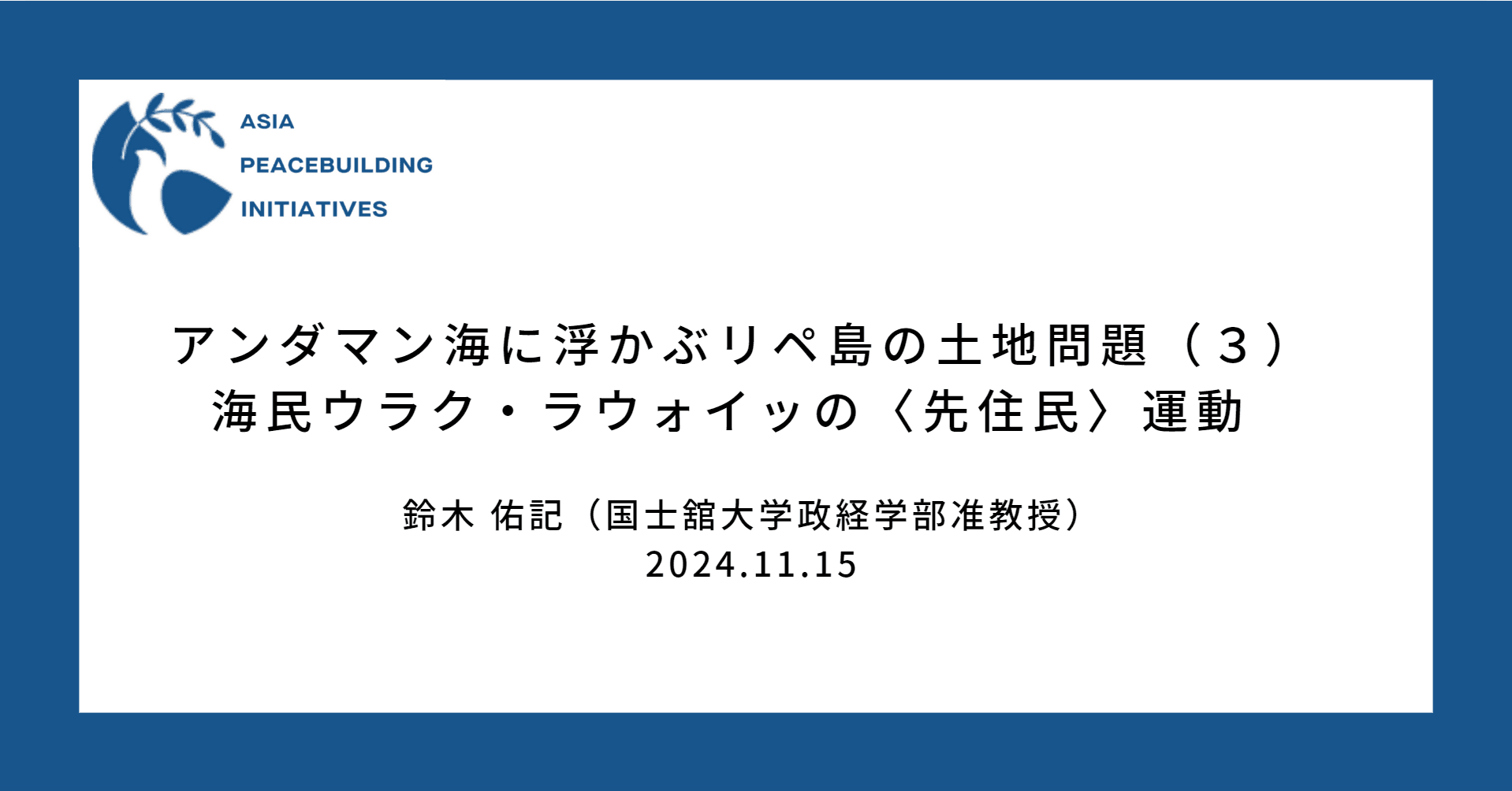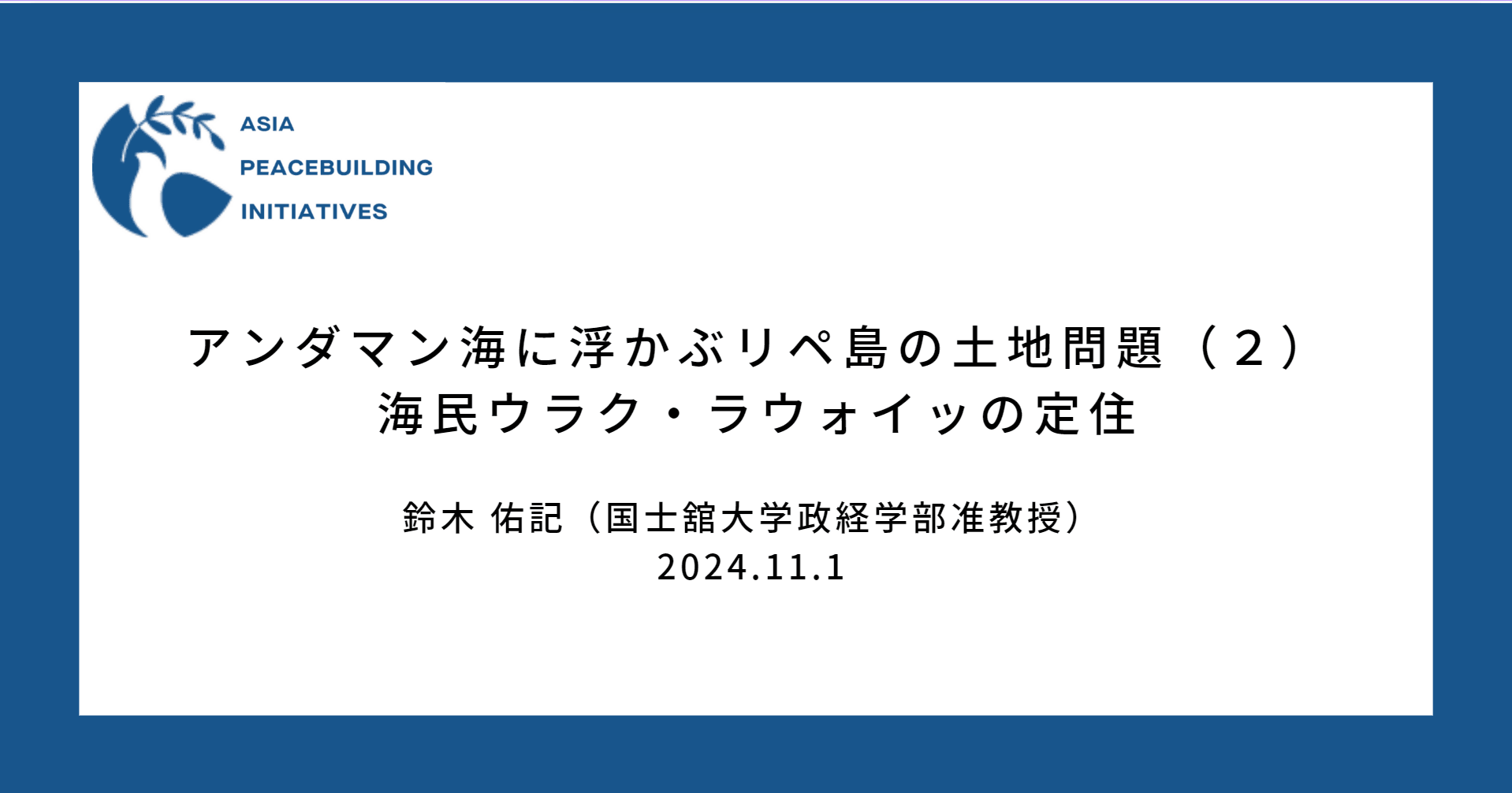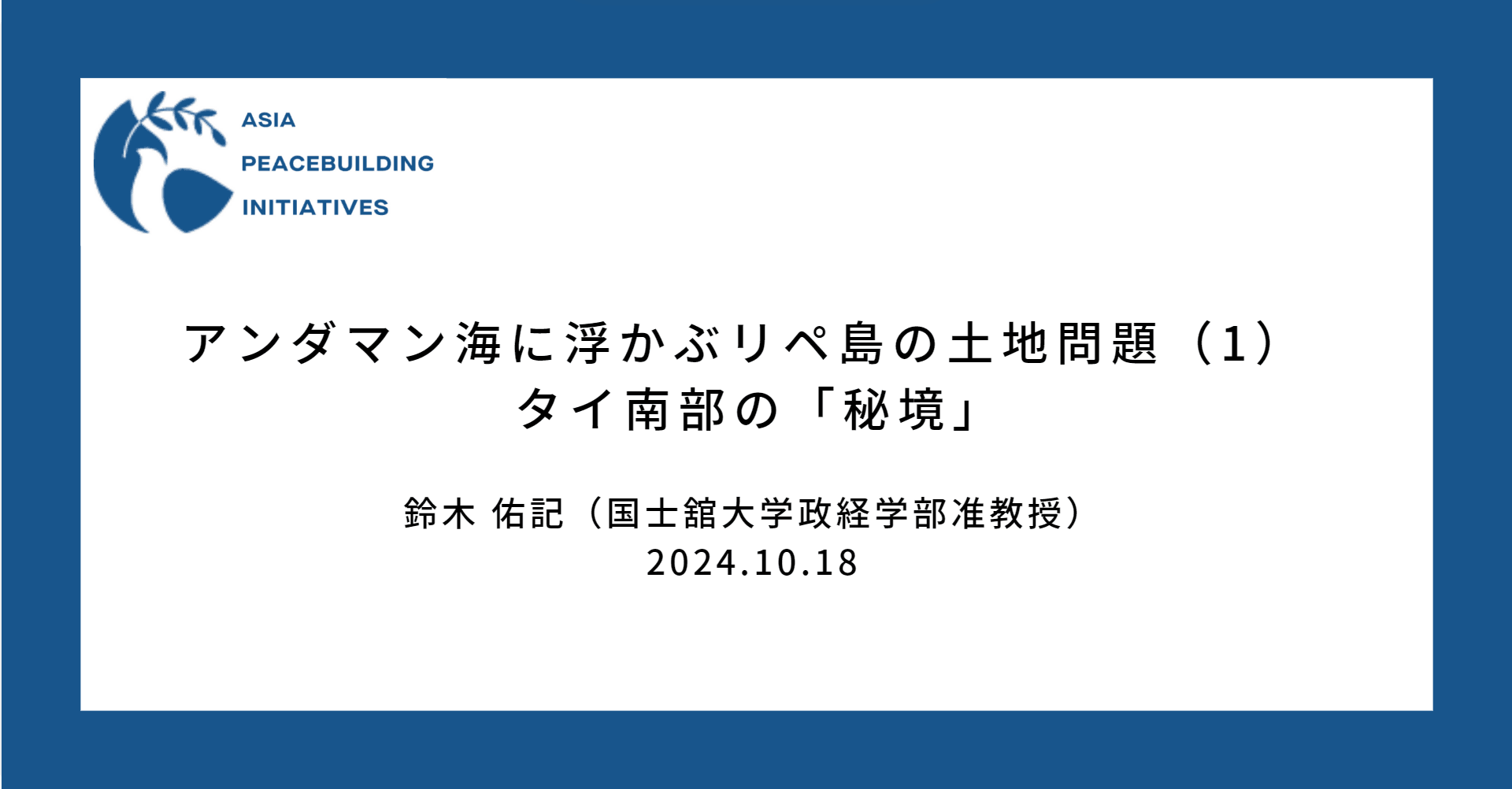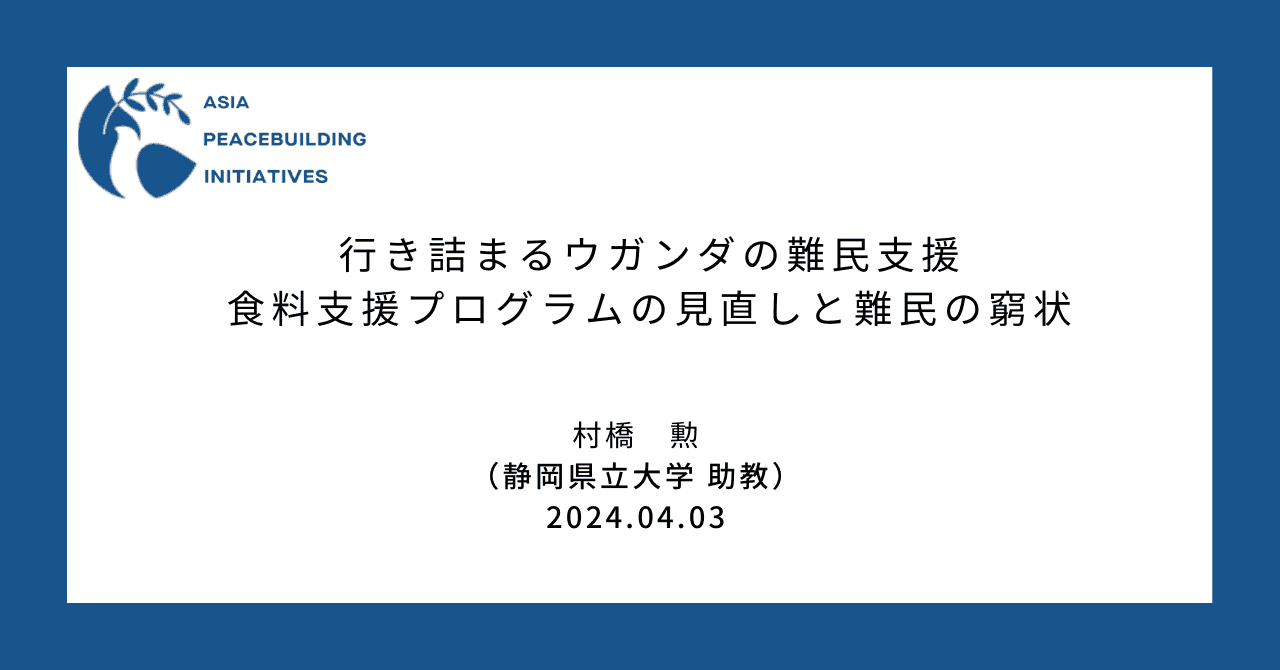新着記事NEW ARTICLES
-
2025.02.07
吉田 智聡平和構築全般新着イエメン内戦概況解説 ―「紛争のリンケージ」に着目して―
本論考では、2015年以降続くイエメン内戦を「国際化した内戦」と位置付け、その基本構造を整理するとともに、ガザ紛争後のフーシー派の行動変化やイエメン内戦への影響を考察します。また、フーシー派の国際的な存在感の高まりや、ロシアとの連携強化を「紛争のリンケージ」として分析し、今後の和平の展望を検討します。
-
2024.11.15
鈴木 佑記平和構築全般新着アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(3):海民ウラク・ラウォイッの〈先住民〉運動
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(3)では、1974年にタルタオ国立公園に指定されたことがウラク・ラウォイッの集住と観光客増加に与えた影響を考察しています。
-
2024.11.01
鈴木 佑記平和構築全般新着アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(2):海民ウラク・ラウォイッの定住
アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(2)では、ウラク・ラウォイッが1900年頃にリペ島に定住した経緯を探ります。
-
2024.10.18
鈴木 佑記平和構築全般新着アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(1):タイ南部の「秘境」
「アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題」は、アンダマン海のタルタオ国立公園内に位置するリペ島とその周辺の土地問題を探る全3部作です。
-