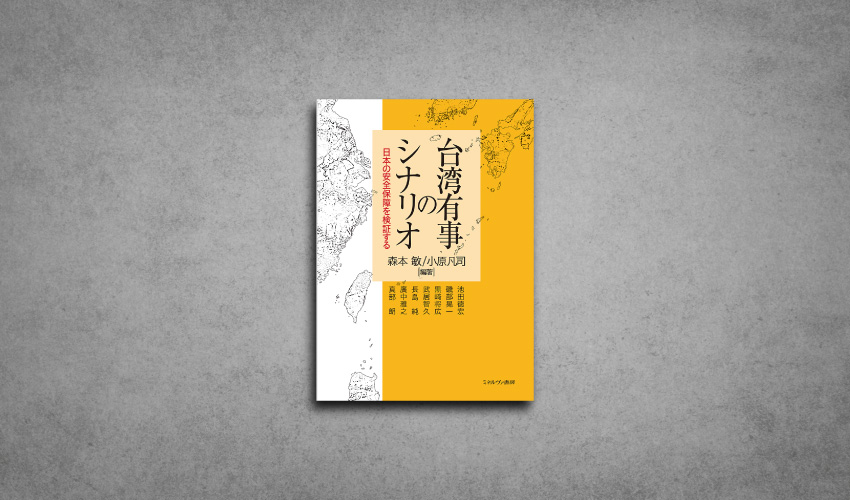ABOUT PROJECT
日米同盟の在り方研究
プロジェクトとは
「新冷戦」とも言われる米中対立の構造の中で、地域および国際社会の「公共財」としての日米同盟の在り方を再検討し、新たな日米同盟における日本の安全保障上の役割を定義し、日本の安全保障政策を提言するための研究を行っています。
プロジェクト
日米研究会
地域および国際社会の「公共財」としての日米同盟の意義と、日本の防衛体制を再定義することを目的とし、国際情勢にあわせて実施する具体的な日米連携分野について考察します。日本の国内法、地理的な制限、現状のパワーバランス等の枠組みに縛られることなく、「公共財」としての日米同盟の在り方を探究し、軍事革命や軍事技術革新の急速な進展なども含めたアセスメントを基に、包括的な安全保障戦略・政策の提言を目指しています。
具体的には、米国ヘリテージ財団との共同研究、米国海軍大学ストックトン・センターとの連携などを実施しています。
具体的には、米国ヘリテージ財団との共同研究、米国海軍大学ストックトン・センターとの連携などを実施しています。
米国の他の同盟国などとの協力
中国が国際秩序の変更を試みる現在、米国と同盟国の関係をネットワーク化する必要があります。日本が日米同盟の中で貢献できる役割について考察するとともに、中国が欧州への入り口と位置付ける中央ヨーロッパ諸国との協力を強化するために、同地域のシンクタンク(ハンガリー、チェコ、スロバキア)と共同研究等を実施しています。
机上演習(TTX:Table Top Exercise)
日米研究会などの研究成果を検証し、新たな課題を抽出するために政策決定過程を模擬した机上演習を米国のヘリテージ財団と共催で実施しています。2022年度は、「台湾有事シナリオ:低烈度ハイブリッド戦からのエスカレート」をテーマとして実施しました。過去の成果物はこちらをご参照ください。
過去の活動内容
※無断転載禁止
政策提言書
※無断転載禁止
| 2022年12月9日 | 提言 日米両政府によるウォーゲーミングの定例化 |
|---|
論考
※無断転載禁止
| 2023年12月27日 |
NATOウォーゲーミング・ハンドブックの一考察 松 卓馬(笹川平和財団研究員) |
|---|---|
| 2023年12月26日 |
【エッセイ】日本の政策シンクタンクにおけるウォーゲーミングとは ―部内ウォーゲーミング研究会の前期活動を終えての所感― 阿久津 博康(笹川平和財団特別研究員/平成国際大学法学部教授) |
| 2023年12月25日 |
SPFウォーゲーミング研究会の終了報告 松 卓馬(笹川平和財団研究員) |
公開フォーラム
最新動画
第2回 中国『海警法』の問題点と日本の対応
2021年1月23日に中国『海警法』が成立し、同2月1日から施行されました。日本の報道には、中国海警局に武器使用の権限が付与されたことに注目するものや、中国が、国際法として認められていない様々な措置の根拠として国内法を定めるなどの措置を行っているといったものがあります。しかし、『海警法』の何が問題なのかについて明確な回答が示されているとは言えません。また、日本がいかに対応すべきかについての議論も始まったばかりです。本公開フォーラムは、運用の視点と国際法の視点から『海警法』を分析し、その問題点と日本の対応について議論を行いました。
2021年9月9日(木)公開フォーラム(英語のみ)
テーマ:Exiting Normal: EDTs (Emerging Disruptive Technologies) and their Impact on Military Operations and Equipment
日本と欧州の安全保障面での協力の可能性について、さらに議論を深めることを目的として、「新興破壊的技術(Emerging Disruptive Technologies)が、安全保障政策・戦術・軍事装備に与えるインパクト」をテーマに、日本と欧州の軍事関係者とコンサルタントの間で、活発な議論が繰り広げました。