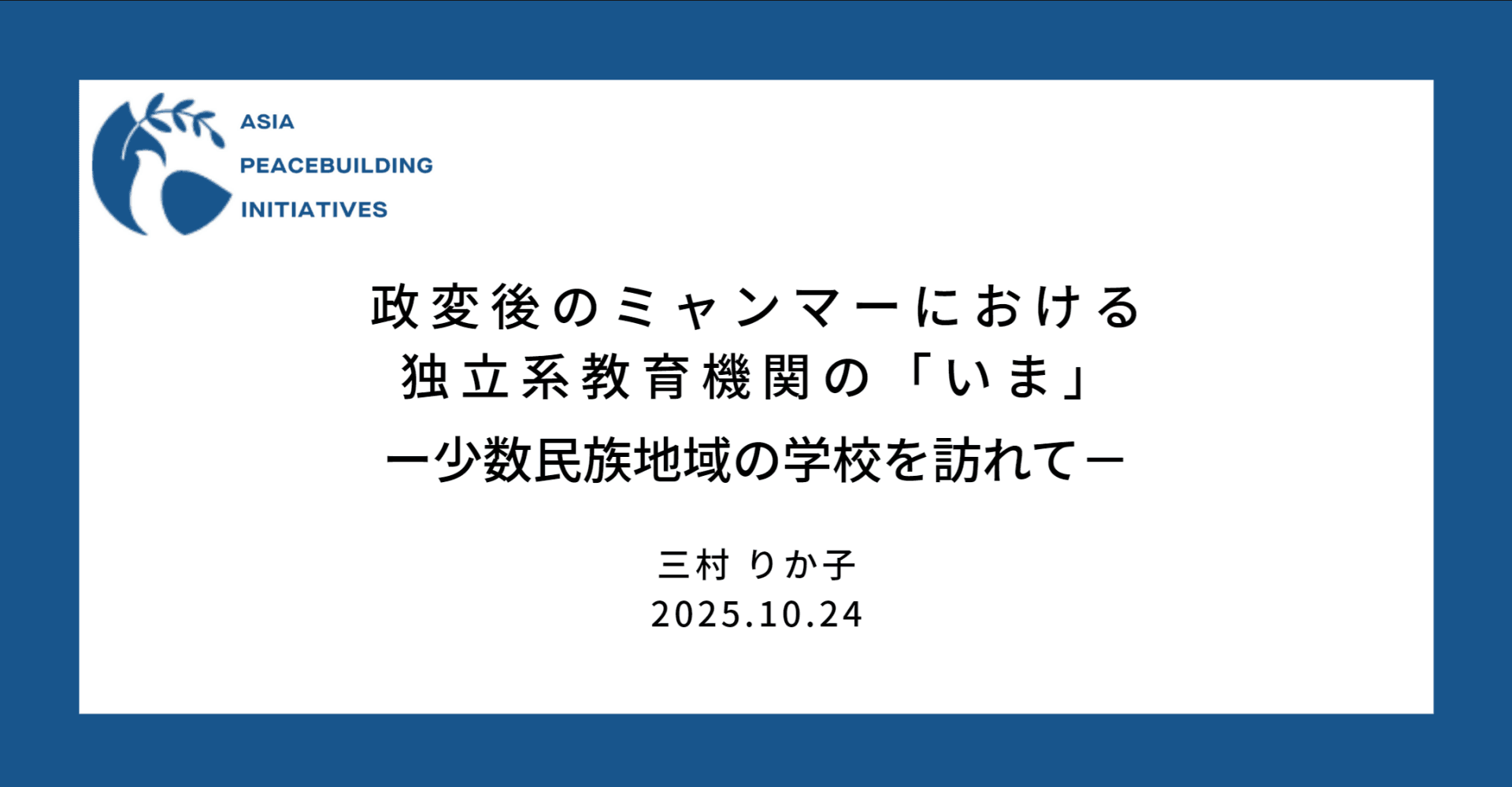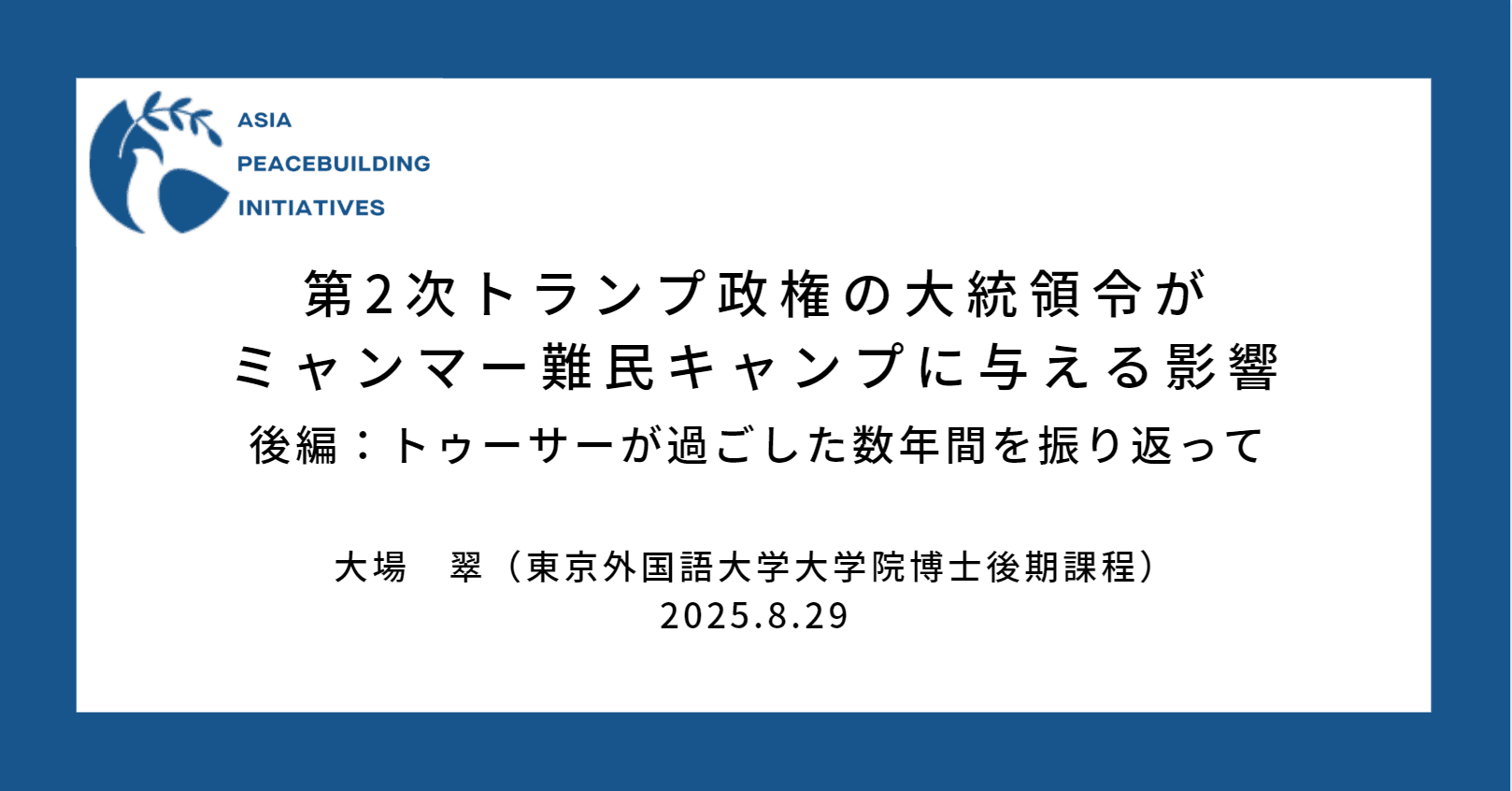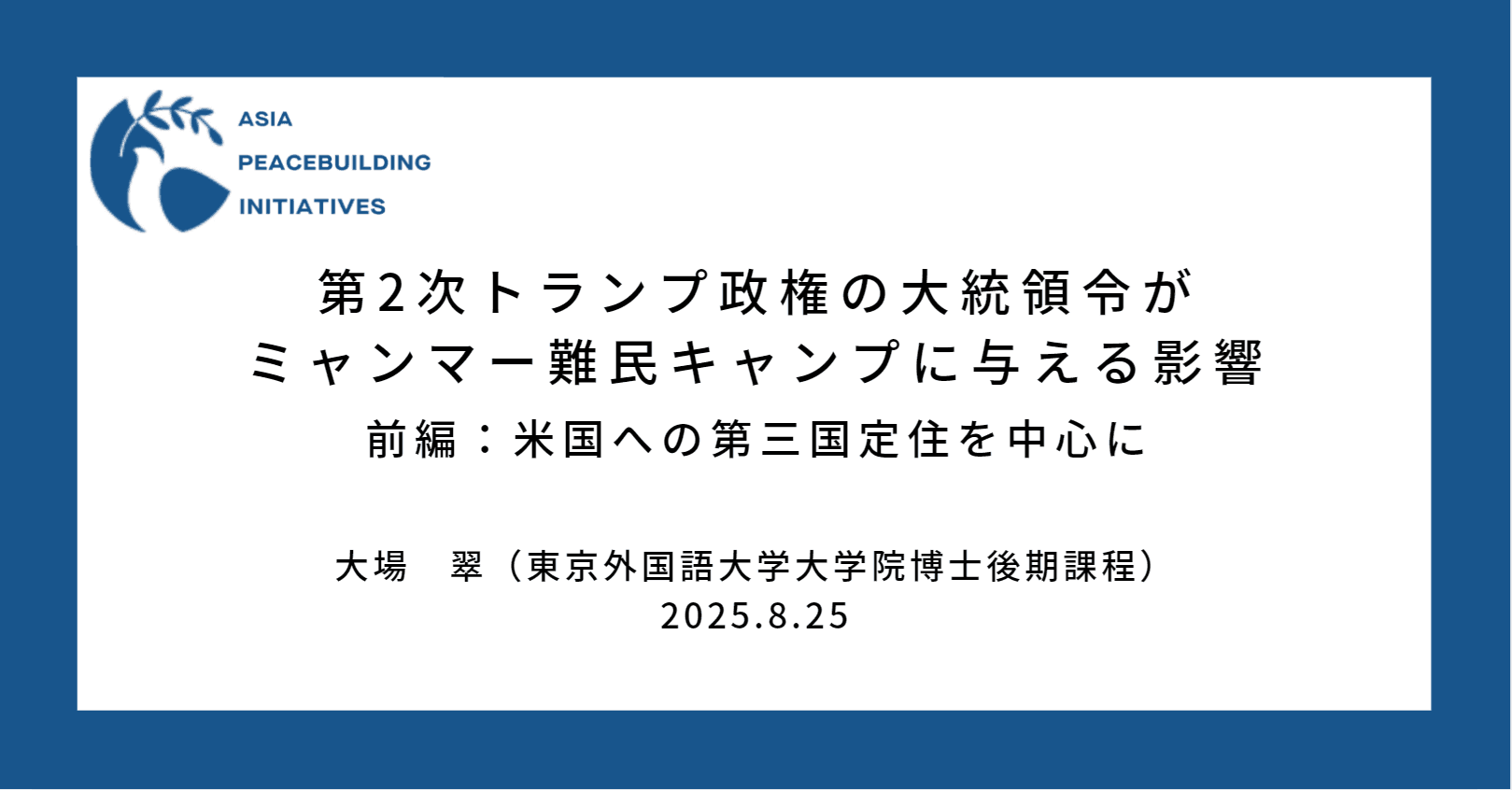- ミャンマー
ミャンマー全土停戦と国内和平の行方~少数民族問題の解決に向けた現状と課題~

はじめに
2015年8月18日付のミャンマー(ビルマ)国営紙に政府と少数民族武装勢力との間で最終合意した全国規模停戦協定(Nationwide Ceasefire Accord、以下、「全土停戦協定」)の全文が掲載された。国内和平の実現を最優先課題の一つとして取り組んできたテインセイン政権が、停戦協議が大詰めを迎えていることを国民にアピールする狙いがあったとみられている。実際に、2013年11月から正式交渉が続いてきた全土停戦は、2015年10月、一部武装組織との間で協定署名を実現した。
多民族国家のミャンマーでは1948年の独立直後から最大民族ビルマ族中心の中央政府に対し、自治権拡大や民族間の平等を求める少数民族の武装闘争が続いてきた。2011年の軍事政権からの民政移管でテインセイン大統領が就任した後も、戦闘は北部カチン州や北東部シャン州などで断続的に起きてきた。全土で戦闘がやむような状況になれば、ミャンマー独立史上画期的な出来事となり、内戦状態から恒久和平に向けて大きく前進することになる。
ところが、現状では文字どおり「全国」で停戦が実現するかは不透明な情勢になっている。政府側がシャン州北東部で戦闘状態にある少数民族コーカンなどの一部武装組織の協定への参加を認めておらず、その問題での対立から、署名式に参加したのが政府が武装組織と認める17組織のうち8組織だけだったからである。国軍のミンアウンフライン最高司令官は8月の筆者とのインタビューで、全土停戦協定署名後のコーカン族武装組織「ミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)」への対応について、「彼ら次第だ。彼らが攻撃をしてくるなら、反撃せざるを得ない。我々は彼らを(交渉相手としても)認めていない」と述べ、MNDAAとの戦闘が続く可能性を否定しなかった。
それでもこの協定に意味があるのは、少数民族側が切望してきた将来の連邦制のあり方を話し合う「政治対話」を始めることが盛り込まれているからである。ほぼすべての武装組織を包括する形で、自治権拡大や真の連邦制の実現といった少数民族側の実質的な要求に対する話し合いの場が持たれるのは初めてのことになり、そこでの議論が少数民族問題解決のためには極めて重要になってくる。ただ、この政治対話は総選挙後のさらなる民主化へのプロセスを複雑にする可能性も秘めている。
テインセイン政権は和平を呼びかけてから全土停戦の実現が目前になるまで4年以上を費やした。政権側の当初の見通しよりも大幅に時間がかかった。全土停戦に向けた交渉は何度も中断を余儀なくされた。本稿ではこれまでの政府と少数民族側の和平交渉プロセスを中心に振り返り、全土停戦協定署名後の国内和平に向けた課題を考えたい。
テインセイン政権の和平プラン
民政移管で大統領に選出されたテインセイン氏は、就任から5カ月後の2011年8月19日、民主化運動指導者アウンサンスーチー氏と首都ネピドーで初めて会談した。この会談を機にミャンマーでは民主的な改革が一気に進むことになるが、その前日の18日付でテインセイン氏は少数民族武装勢力に対しても「和平交渉への招待」という声明を出して国内和平の呼びかけを行っていた。声明は「国の発展のためには和平が必要だ」として、和平に応じる組織には政府に連絡をとるよう求めた。軍政時代のミャンマーでは、軍政と民主化勢力、少数民族武装勢力との間で長年対立が続き、それに伴い国内経済は停滞した。テインセイン氏は両勢力との対立の解消に取り組む姿勢を相次いで表明した形になった。
国内和平の実現に向けてテインセイン政権はまず各武装組織と個別に停戦を結ぶ方針をとる。これは軍政下で結ばれた停戦協定が、軍政末期に「無効」になったからである。軍政は1989年以降、主要組織ではカレン民族同盟(KNU)を除く大小15を超える武装組織との間で停戦を実現していた。民主化運動を抑圧したことで先進国からの援助が止まったため、中国など近隣諸国との外交・経済面での結びつきがより重視されるようになり、国境地帯の安定が求められるようになったためである。これによって各武装組織は武器を保持したまま支配地域を管理し続ける状況が続くことになった。
ただ、停戦は進めたものの、軍政は少数民族側が求める実質的な要求に関する話し合いには、自分たちが暫定政権であることを理由に応じなかった。そのため、少数民族側の不満は高まっていった。軍政は2008年に民政移管に向けた憲法を制定すると、同憲法338条の「連邦のすべての軍隊は国軍の指揮下にある」という規定に基づき、各武装組織に戦闘部隊の「国境警備隊(BGF)」への編入を要求する。これに少数民族側は反発し、2010年9月の期限までに大半の組織が応じなかった。軍政は「これまでの停戦は無効になった」と一方的に宣言し、武装組織との間で緊張が高まっていた。
こうした状況にあったため、テインセイン政権はまず停戦の結び直しを始める。2011年中に国内最大兵力を持つワ族のワ州連合軍(UWSA)など4つの組織と合意し、翌12年には独立直後に蜂起して以降、一度も停戦に応じてこなかったKNUをはじめ9の組織との間で停戦を実現した。政権発足から2年足らずでおもな少数民族武装組織16組織中13の組織と停戦できた最大の要因は、政府側が国境警備隊への編入問題を棚上げにしたためだ。少数民族側にも資金難や内部対立による弱体化があり、軍政時代にいったん結んだ停戦を再び確認することには大きな抵抗がなかった。
テインセイン政権は個別停戦後の和平プランを当初次のように考えていた。第1段階である個別停戦が実現したら、第2段階として武装組織に連邦からの離脱をしないと確約させたうえで、2008年憲法を受け入れて政党をつくって合法的な政治活動を行うように促す。そして、最終段階として国会で恒久的な和平合意に署名する。つまり、テインセイン政権は少数民族武装勢力を武装解除させてうえで、政党として憲法の枠内で活動させることを目標としていた。だが、こうした方針は少数民族側の考えとは相いれず、和平プロセスは2012年後半に入ると一時停滞することになった。
少数民族側の和平方針
国境警備隊編入問題で国軍との緊張が高まったことを受け、少数民族側には連帯の機運が生まれた。軍政下で国軍は兵力を40万人にまで増強したが、少数民族側は3万人の部隊を有するとされるUWSAを除けば軍政時代に弱体化し、北部カチン州や北東部シャン州の一部を勢力下に置くカチン独立機構(KIO)でも最大1万人規模で、なかには兵力数百人という組織もある。個別に国軍と向き合えば、不利なのは明らかだった。2010年11月にKNU、KIO、新モン州党(NMSP)など6組織が連邦緊急委員会を設立した。同委員会は翌年2月にさらに5つの組織を加えて、統一民族連邦評議会(UNFC、本部タイ・チェンマイ)へと発展した。
UNFCはテインセイン大統領が少数民族武装勢力に国内和平を呼びかける直前の2011年8月15日、大統領宛てに書簡を送る。書簡は少数民族側に対する攻撃を停止する「全国規模での一時停戦」を政府が一方的に宣言するように求め、UNFCと少数民族問題の解決に向けた「政治対話」を始めるよう要請した。つまり、UNFCは真の連邦制実現のための話し合いこそがなによりも先だという立場だった。こうした要求の背景には軍政時代に停戦に応じたにもかかわらず、実質的な要求に関する交渉を軍政側に反故にされ続けた苦い経験がある。少数民族のリーダーたちは軍政下で制定された2008年憲法は中央集権的として受け入れない姿勢を示しており、連邦制実現のためには、現憲法の改正か新憲法の起草が必要だと訴えている。
政府側は当初、UNFCの要求には応じず、個別停戦の交渉を進めた。UWSAやシャン州南部で勢力が強いシャン州復興評議会(RCSS)などUNFCに加盟しない組織があるというのが理由だった。だが、2013年に入っても和平プロセスが停滞し、KIOなど残り3つのグループとの停戦交渉もなかなか進展しないなか、政府側は方針の転換を図る。少数民族側が求める政治対話の開始という妥協をちらつかせた形での全土停戦の模索である。
和平プロセスと国軍
テインセイン政権が国内和平を訴える一方で、国軍と一部少数民族武装組織との戦闘はやまなかった。特にミャンマー北部ではKIOとの間で大規模な戦闘が繰り返されることになった。国軍とKIOとの関係は国境警備隊編入問題で悪化した。2011年6月に国軍がKIOの実効支配線を越えて部隊を進め、KIOが国軍の補給路にある複数の橋を破壊したことで1994年に軍政と結ばれていた停戦は実質的にも破棄されることになった。
戦闘再開で2012年末までには約10万人が避難民になった。テインセイン大統領は国軍に戦闘をやめるよう指示したが、国軍は同年末、KIOの本拠地ライザへの空爆を開始した。攻撃は1月下旬まで続いた。双方は停戦協議に入り、2013年5月には衝突を減らすよう努力するとの合意文書に署名したが、その後もカチン州やシャン州北部では断続的に戦闘は続いた。国軍がKIOとの戦闘を継続した理由は定かではないが、軍政時代にいち早く停戦し、勢力を温存してきたKIOを弱体化させる狙いがあったと考えられる。
戦闘はパラウン族の未停戦組織タアン民族解放軍(TNLA)との間でも続いたが、RCSSやカレン族の民主カレン慈善軍(DKBA)といった停戦グループとの間でも散発的に繰り返された。これは国軍がテインセイン大統領の和平路線を支持しながらも、軍事戦略的な観点からは独自に動いていることの証である。武装組織と向き合う上で戦略的に重要な拠点の確保や武装勢力支配地域の縮小をめざした軍事作戦は、たとえ停戦が結ばれた後でも実行に移された。
全土停戦協定交渉の展開
テインセイン大統領は2013年1月にあったミャンマーの開発を支援する国際会議の開会式で和平について触れ、「近い将来、停戦をした武装組織と政治対話を始める」と明言した。この頃から全土停戦の実現とその後の政治対話の開始という方針が出てくる。政府が全土停戦を掲げ始めた背景には、2014年の東南アジア諸国連合(ASEAN)議長国就任前に国内和平の実現を内外に示したい思惑があった。さらには、懸案となっていたKIOとの停戦をめぐって、すでに停戦を結んだ大多数の武装組織とともに交渉のテーブルに着かせることで、KIOを和平プロセスに引き込みたいとの狙いもあったと考えられる。
当初、少数民族側はこの全土停戦案に警戒感を示す。停戦協定を結んだ後に政治対話を始めるという約束を政府が破った場合のことを心配したのだ。2013年9月にあった政府とUNFCとの協議で、政府側は全土停戦への参加を求めたが、UNFC側は態度を保留した。少数民族側は同年10月末から11月初めにかけ、UNFC非加盟を含めた17組織がKIOの拠点ライザで対応を協議したが、最終的に応じることを決め、交渉団である「全土停戦調整チーム」を組織した。
ライザでの協議を経て、同年11月にカチン州の州都ミッチーナで全土停戦をめぐる第1回の公式協議が開かれた。ここでは全土停戦をめざすことでは一致したが、政治対話にどのような政治勢力からどれだけの人数が参加するのかなどの枠組みや各組織の戦闘部隊の今後の扱いをめぐって意見の隔たりが明確になった。交渉は2014年に入り、旧首都ヤンゴンで繰り返し開かれた。途中、国軍による2014年11月のライザ砲撃などが原因で数カ月に渡って中断したが、翌15年3月の第7回協議で協定草案の合意に至った。その後、6月に少数民族側から一部文言の修正要求が出されたが、8月の第9回協議で最終合意した。
合意に至った背景には同年11月に予定される総選挙があると考えられている。テインセイン政権としては、全土停戦協定を実現することで、総選挙で少数民族地域の支持を集めたいとの意向があったとみられる。一方の少数民族側としても、国軍が交渉プロセスに参加しているテインセイン政権のうちに、政治対話開始の段取りを付けておきたい思いがあったとされる。
だが、協定の署名をめぐって政府と少数民族側との間で意見対立が生じることになった。2015年2月にシャン州北東部のコーカン地区で、MNDAAのリーダー、ポン・チャーシン議長率いる部隊が同地区の制圧をめざして攻撃を仕掛けたことがきっかけだった。突然の攻撃で多数の国軍兵士が戦死したため、政府側はMNDAAとは徹底抗戦の構えをみせ、MNDAAに協力したTNLAとアラカン軍(AA)も含めて、全土停戦協定への署名を拒否すると主張した。これに対し少数民族側はすべての武装組織を包括しなければ署名はしないと訴えた。これによって、協定の草案ができたのにもかかわらず、署名ができないという事態が続くことになった。もっとも2015年8月に、KNUやRCSSなど4組織が全土停戦協定へ署名する意向に転じ、少数民族側に足並みの乱れが出ている。結局、10月に8組織が先行署名する形になった。

協定内容実現の見通し
MNDAAなど一部武装組織が全土停戦協定から取り残される見通しになっていることで、停戦が実際に「全国規模」になるかどうかが疑わしいということは先に指摘した。それでは、協定に署名する武装組織と国軍との間の停戦は守られることになるのだろうか。ここからは協定の中身をみていきたい。
停戦の実効性を確保するのに不可欠なのが停戦監視メカニズムである。実際、ミャンマーでこれまで結ばれた停戦では、このメカニズムがなかったために国軍と武装組織の間で戦闘が散発的に起きてきた。これについて、協定は停戦共同監視委員会の設置を定めている。委員会には政府と少数民族側の代表などが加わり、全国、州、地区の3つのレベルでそれぞれ委員会を組織するとしている。外国や国際機関のメンバーもアドバイザーなどの形で参加できるとしてはいるが、原則的には国連の平和維持活動(PKO)などの関与はなく、当事者同士が代表を出し合って停戦監視を行う方式になっている。
そのため、委員会にどのような権限を与えるのかが極めて重要になってくるが、これについては協定署名後に話し合うことになっている。持続的な停戦を実現できるかは、今後の双方の協議にかかっているということになる。委員会が十分に機能するような形にならなければ、停戦を担保することは難しくなる。
一方、少数民族側が望んでいる政治対話について、協定は署名後60日以内に枠組みを決め、90日以内に開始すると規定している。署名式は10月15日だったので、2016年1月13日が政治対話開始の期限になる。なお、枠組みとは先に述べたように、どのような資格の人たちをどれだけ参加させるかという会議の参加者に関する事項を含む。政治「対話」と言っても最終的に物事を決める際には多数決になると想定され、どういう人がどれだけ参加するかは議論の行方を左右する重要事項である。ある少数民族の指導者によると、全土停戦交渉の過程で少数民族側は「政府」、「少数民族武装勢力」、「政党」の3つのカテゴリーから同数の代表を参加させるべきだと主張したが、政府側は「政府」、「国軍」、「国会」、「政党」、「少数民族武装勢力」の5つのカテゴリーから代表をそれぞれ選ぶべきだとの見解を示したという。少数民族側の案では「政党」のカテゴリーにも少数民族政党が存在することから、少数民族勢力が議論を主導することができそうだ。一方で、政府案は与党と軍人議員で多数を占める「国会」や「国軍」もいわば政府側となるので、政府に有利な形になりそうだ。
テインセイン大統領は政治対話の結果に基づいて、憲法改正についても検討していくべきだとの意向を示している。国の仕組みを大きく変えうる重要な協議の枠組みについて、政府と少数民族側が2カ月ほどの間に合意できるかどうかはかなり不透明だ。仮に期限内に合意できなかった場合にどうするのかについて協定に規定はない。停戦監視メカニズムと含めて、停戦署名後の極めて重要な協議課題となっている。
おわりに~政治対話と憲法改正
今後最も順調なシナリオ通りに政治対話が始まり、10月には署名しなかった残りの武装組織も協定に加わってくるとすれば、少数民族問題の解決に向けた大きな一歩となる。ミャンマー独立以降の政権は少数民族武装勢力の要求にしっかりと向き合ってこなかった。非合法組織とされてきた少数民族武装勢力が参加する会議で、将来の連邦制のあり方や国の仕組みについて議論されることは歴史的なことである。そこでは少数民族が求める真の連邦制を実現するための憲法改正が重要議題として話し合われることになるだろう。
だが、ここで一つ不安が生じる。それは政治対話と国会の関係である。11月8日に投票された総選挙ではアウンサンスーチー氏率いる野党・国民民主連盟(NLD)が圧勝した。2012年の補欠選挙で獲得した41議席を大幅に上回る約390議席を獲得した。NLDはさらなる民主化のために、国軍の政治関与を定めた憲法の改正を公約に掲げている。国会議席の20%超の133議席を獲得すれば単独で改憲案を国会に提出できる。憲法改正は国会でのみ発議が可能で、全議席の75%超の賛成が必要である。もっとも、国軍最高司令官が任命する軍人議員が議席の25%を占めており、国軍がNLDの改憲案を廃案にすることは可能である。それでも、NLDが改憲を国会審議のテーブルに乗せることはできることになる。
ここで憲法改正を主導するのは政治対話か国会かとの問題が生じる。憲法上は国会でしか改憲はできないが、少数民族武装勢力との全土停戦の成果として実現した政治対話がより重要だとの考えもありえなくはない。仮にNLDが総選挙で圧勝した場合、「NLDだけで決めてしまえる国会よりも、すべての政治勢力を包括する政治対話の方が全国民の意思を反映している。国会での改憲審議は政治対話の結果を待つべきだ」との主張が出てこないとは言えない。
かつての軍事政権は1990年の総選挙でNLDが議席の8割を獲得して大勝すると、「NLDという一政党だけの国会では全国民の意見が反映されない」として国会を召集しなかった。1993年、代わりに「国民各層からの代表」による国民会議を開いて、新憲法の議論を始めた。国民会議は憲法の基本原則の策定に14年を費やした。
政治対話がそのままかつての国民会議のような道をたどるとは限らない。だが、今後政治対話が始まった場合、国会との関係がどのようになっていくか注意して見守っていく必要があるだろう。
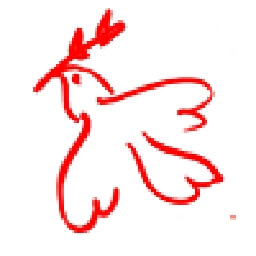

朝日新聞ヤンゴン支局長(Yangon Bureau Chief, The Asahi Shimbun)