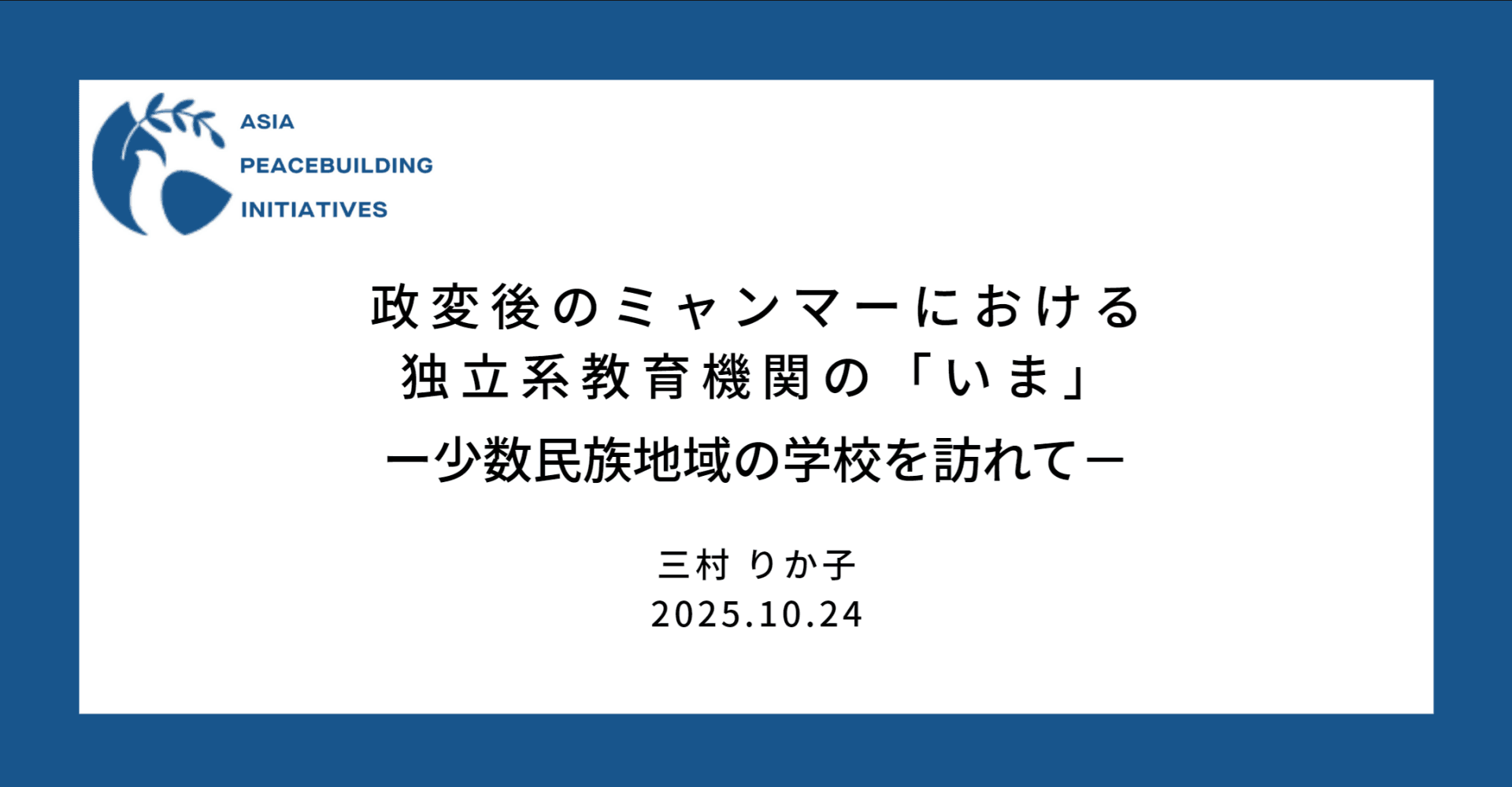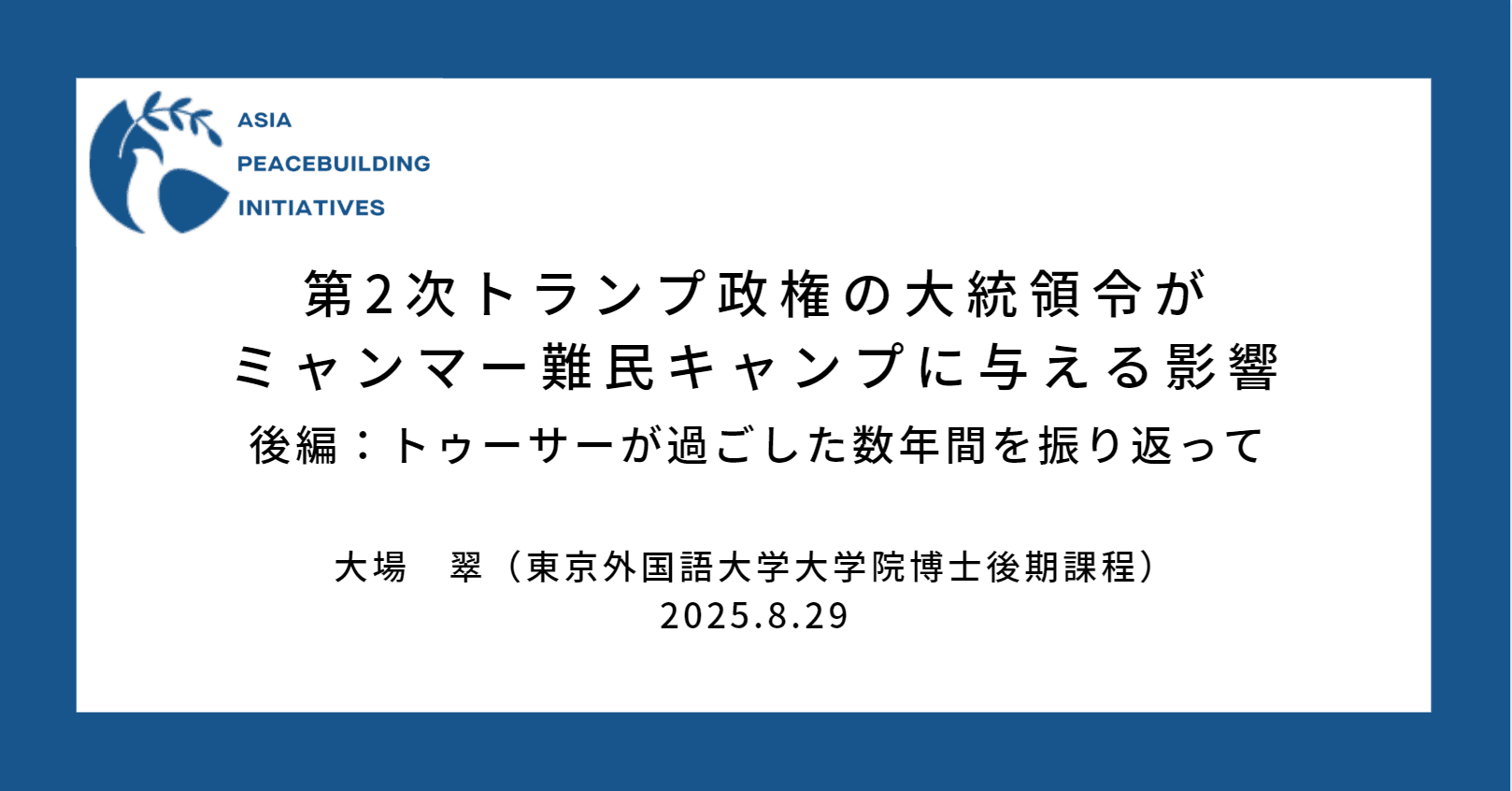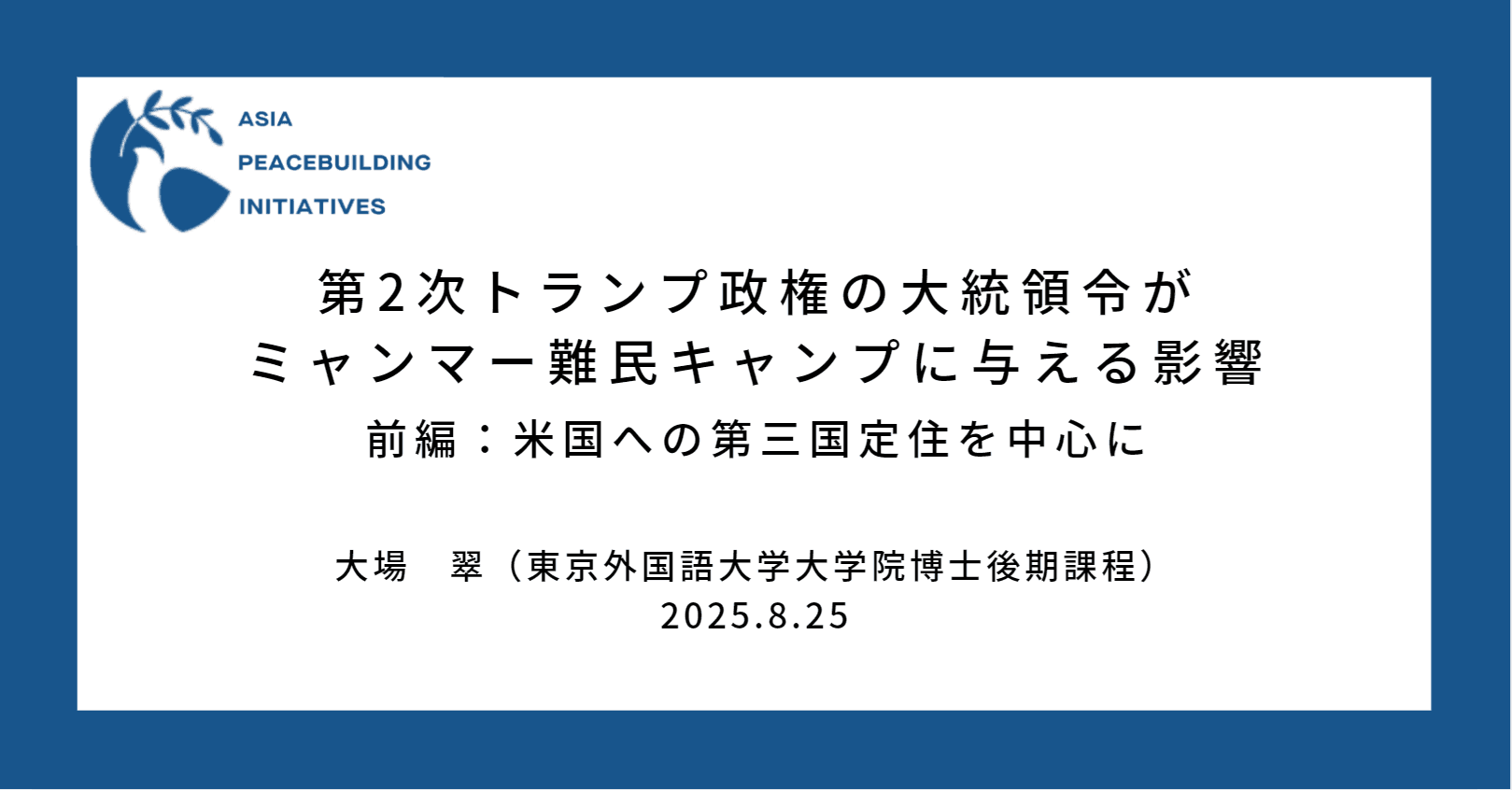- ミャンマー
カレンニーとカヤー:2つの「名」をめぐって

内戦の構図
ビルマ(ミャンマー)には4つの問題があると言われてきた。軍事政権からの民政移管、薬物の撲滅、HIV/AIDS、そして民族紛争である。前者の3つは国際社会の利害にも結びつく問題である。このため国際社会は、(その成果はともかく)軍政期という交渉が厳しい時期であっても、3つの問題に対しては様々な方策をとってきた。しかし、こと民族紛争については内政問題とされ、外部からの理解やアプローチは限られてきた。これは、紛争の現場がいわゆる「辺境地」であり、外国人のアクセスが困難であることにも起因している。
ビルマの内戦は、同国が英国から独立する1948年前後に端を発し、世界で最も長く継続している。民政移管後の現在も各地で戦闘が散発しており、現在も合計で数十万人の難民と国内避難民がいる。難民の多くは、カレン、カレンニー、カチン、モン、シャンなどの諸民族であるように、ビルマの内戦はマジョリティのビルマ族が主導する政府とマイノリティの諸民族の衝突という構図で捉えられる。ビルマ軍政は、武力で諸民族を鎮圧するだけではなく、これらの民族言語の教育を禁止するなど、その方針は「ビルマ化」として批判されてきた。
しかし現実の紛争は、ビルマ政府 vs 諸民族勢力という構図でのみでは捉えられず、さらに複雑である。というのも、それは諸民族 vs 諸民族という対立軸も内包しているからだ。数十年間の内戦の過程で、カレン民族同盟、カレンニー民族進歩党、シャン州軍、カチン独立機構をはじめとする、多くの武装組織が反政府活動を展開してきた。しかしこれらの反政府組織は方針の違いからいくつもの組織に分派していった。カレン民族同盟から民主カレン仏教徒軍が分派したことはよく知られているが、本稿で事例とするカヤー州では、カレンニー民族進歩党から離脱した共産主義者がカレンニー人民解放戦線を結党した。ポイントは、このように分派した組織のほとんどが、1990年代に政府の傘下に入った停戦組織であるということだ。
ビルマ軍の軍事作戦を遂行する上で、停戦組織は大きな役割を果たしてきた。ビルマ族が中心となる国軍に対して、停戦組織は現地の成員で構成されるので、土地勘がない国軍兵士の道先案内人として暗躍する。また停戦合意の多くは、停戦の見返りとして木材や鉱物、宝石、さらには麻薬取引などの利権が配分されることに動機づけられていると言われる。1990年代に実現した停戦合意は、地域に一時的な平和をもたらしたが、同時にビルマ軍の当該地域への介入をも容易にし、住民への迫害を助長する結果となった。ビルマ政府との取り引きでビルマ軍のプレゼンスを拡大させたことで、利害で競合する武装組織間での不信感も煽られ、結果的に民族内部の亀裂が深まることになった。政府にとってこれまでの停戦合意とは、和平のための筋道というよりも現代版の分割統治の手法と呼ぶのがふさわしい。
また、抵抗運動を続ける組織と政府間の停戦合意が難航する背景には、政府の既存の停戦組織に対する配慮があるという見方もある。つまり、既存の停戦組織にビジネスの利権が与えられているなかで、停戦を通して新たな組織をその経済システムに取り込むことは、政府が停戦組織との約束を反故にすることにもつながりかねない。
現在ビルマでは、全土停戦に向けた話し合いが進められようとしているが、1990年代に結ばれた停戦で浮き彫りになった課題を教訓として今一度学ぶ必要があろう。つまり、それはビルマ族と諸民族との関係に加えて、諸民族内部にはどのような問題があるのかを把握し、その解決のためにはいかなるアプローチが必要かという点である。本稿では、カヤー州の紛争の事例をもとに民族問題解決の方向性を考察する。
カレンニーとカヤー:2つの州名
カヤー州はタイと国境を接するビルマで最も小さい州だが、チーク材、タングステン、スズなどの天然資源が豊富である。カヤー州には、第二次世界大戦後の戦後補償として建設されたバルーチャウン水力発電所があるように、日本との関わりも深い(本紙創刊号 秋元由紀「バルーチャウン水力発電所の今:桃源郷から地雷原に―少数民族と開発の現場―」を参照)。

カヤー州の内戦には、「カレンニーとカヤー」という名前をめぐる係争という特徴がある。カレンニー州は英領期に境界線が確定した地域を指し、1948年の独立時にビルマ連邦の構成州となった。その後、1952年にビルマ政府は州名をカヤーに変更した。このためカレンニーもカヤーも地理的には同一の州を指す。両者の違いは、州名に込められた政治的な意味合いである(本稿では現行の州名であるカヤー州に表記を統一する)。
カレンニー民族進歩党(Karenni National Progressive Party、以下KNPPと表記)は、英領期にカレンニー州西部が独立の地位にあったことなどを理由にカレンニー州の分離独立を求める抵抗運動を続けてきた。KNPPは「カレンニー」という名を「州内の民族の総称」として意義付け運動を続けた(以下では総称としてのカレンニーを指す場合は「カレンニー」と表記する)。ビルマ政府がカヤーに州名を変更したのは、KNPPの政治目標と州名の一致を回避するためである。
KNPPは、他の組織(カレン民族同盟、シャン州軍・南部、カチン独立機構、新モン州党など)と同じように武装闘争をとったが、独立した「国民国家」を構築すべく、独自の文字表記を発明、採用し教育活動を行ってきたという特徴がある。KNPPは、この文字を「カレンニー」語として、支配地域やタイ側の難民キャンプを中心に普及することで「民族」の内的な統合を構築しようとした。
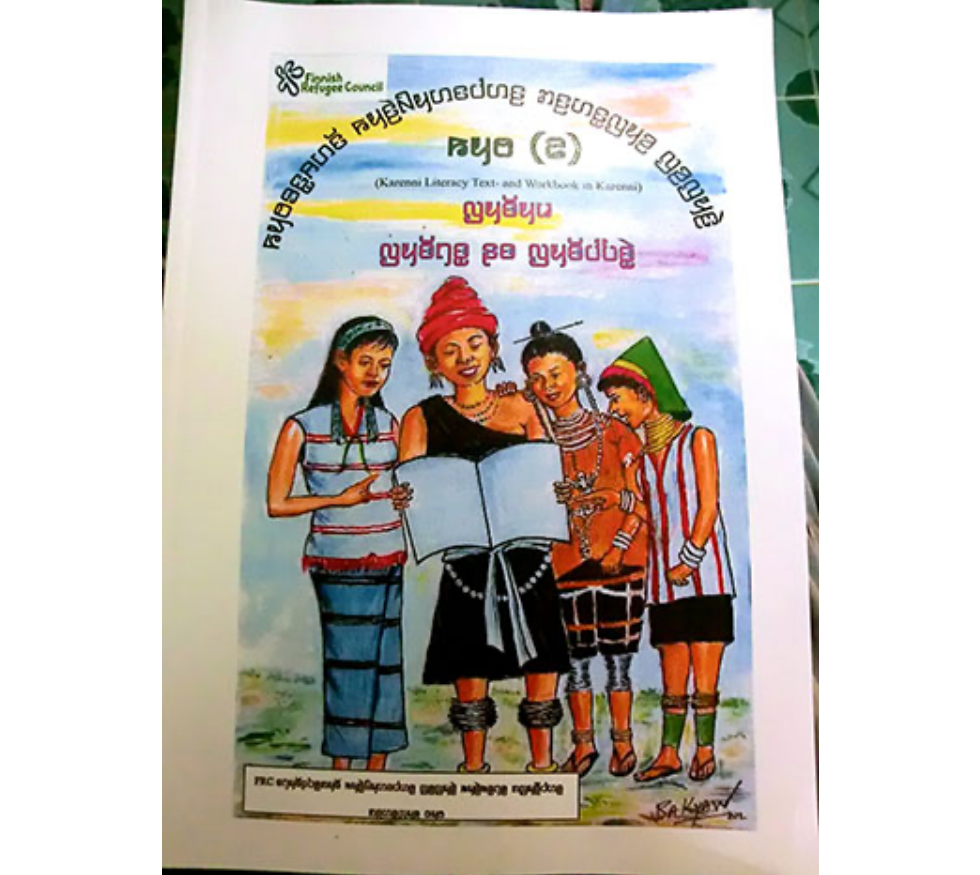
「カレンニー」文字を発案したのは、KNPPの元議長であるテーブペー(1937~2011年)である。カレンニー州には、すでにキリスト教宣教師がもたらしたアルファベット表記の文字があったが、彼は『世界の言語』(著者不明)という本を読んだことをきっかけに、アルファベット表記では自身の言葉を正しく表記できないと思うようになった。そこで彼はラングーン大学で歴史を学んでいた時代に、友人とともに文字の制作にとりかかり1963年に公表した。しかし「ビルマ式社会主義」の方針のもと民族言語教育は禁止された。その後、彼の発案した文字表記は「カレンニー」文字としてKNPPの独立運動の象徴となった。ビルマ政府は、国民に「我々の三つの責務」として、⑴ 連邦を解体しないこと、⑵ 民族の団結協力を瓦解しないこと、⑶ 主権を確保することを課しているが、KNPPの運動はこれらの「責務」を脅かす存在となった。
ナショナリズムのねじれ
カヤー州での係争は、「カヤー」として連邦に組み込みたい政府と「カレンニー」として独立を目指すKNPPとの対立である。しかしこのナショナリズムは単なる二項対立ではなく、特有のねじれが存在する。このねじれを捉えるために、カレンニーとカヤーの関係を別の側面からみてみよう。
そもそもカレンニーとは、ビルマ語の「カインニー(赤カレン)」を植民地統治に携わった英国人が「カレンニー」と呼んだことが始まりで、ビルマ語起源の他称である。他方、カヤーとは、カヤー語で「人間」を意味する自称である。カヤーリープとも自称され「赤い人」という意味になる。「赤」という色は、民族衣装の色、または肌の色であるなどの諸説があるが定かではない。さらに言語学上の分類においてもカレンニーとカヤーは同一の集団とされ、両者には自他称の違いしかない。
KNPPが他称である「カレンニー」という名を採用したのは、州内には、カヤーをはじめとする様々な民族(カヤン、カヨー、パク、ブウェなど)がいるからである。反政府側がビルマ語を起源とする他称を採用するのは、なんとも皮肉ではあるが、カヤーという自称では他民族を包摂できないと考えたのである。
ここで問題となるのは、では「カレンニー」語とは一体何語なのかという点である。「カレンニー」語は、まったく新たに発明された言語ではない。その文字を作ったテーブペーは、カヤー州西部(チェボジ)出身のカヤー民族であり、彼が考案した文字体系は「チェボジ方言のカヤー語」を表記するものであった。つまり、「カレンニー語」の表記はオリジナルだが、実際にはカヤー語なのである。このことは言語の習熟状況にあらわれている。コンソーシアム・タイランドが2001年に難民キャンプで実施した調査によると、「カレンニー」語の会話と読み書きについて、会話は容易と答えたのが81%であるのに対して、文字を全く読めない(60%)、全く書けない(62%)という結果が出ている。長年にわたって教育されているにも関わらず習熟度が低い理由として、この文字が難民キャンプだけのものでビルマ国内では教えられていないこと、さらに国内やキャンプでの共通語はビルマ語であることなどが挙げられる。
カヤー語が「カレンニー」語とされるように、KNPPの政治運動は多数派であるカヤーを中心に展開されている。かつてKNPPから分派したカレンニー人民解放戦線はカヤンを中心に構成されており、彼らはカヤー中心のKNPPを批判している。難民キャンプで「カレンニー」語教育を推進した結果、前出の調査が行われた時期に比べて、若い世代を中心に「カレンニー」語を話せる者が次第に増えてきたが、結果的に次のような事態を招いている。それは「カレンニー」を構成する諸民族のうち、「カヤー語を話す非カヤーはいるが、非カヤー語を話すカヤーはいない」ということである。「カレンニー」内部では「カヤー化」のバイアスがかかっており、「カレンニー」のなかにマジョリティ・マイノリティ関係がみられる。「カレンニー」の構成は、ビルマ族を中心とするビルマという国家の縮図である。
「カレンニー」がカヤー中心であるということに着目すると、そこには「カヤー」を連邦の構成員にするというビルマ政府と、実はカヤー・ナショナリズムに対する認識が共通しているとみることもできる。ここにカレンニーとカヤーをめぐるナショナリズムのねじれがみられる。つまりカレンニー・ナショナリズムは、カヤー・ナショナリズムに力を与える論理を内包しており、ミャンマー・ナショナリズムは、カヤーを中心とするカレンニー・ナショナリズムに力を与える論理を内包している。この「ナショナリズムそれ自体のなかに分離運動に正当性を与える」というねじれは、あくまで理念上のものではあるが、理念に曖昧さをはらむナショナリズムは、より複雑で多様な現実の前で齟齬をきたす。
カヤー州の「民族」紛争は、⑴「ビルマ化」に対抗的な「カレンニー」の運動、⑵「カレンニー」内部のマジョリティ・マイノリティの関係、⑶ ナショナリズムのねじれという3つの位相を同時に孕んでいる。
カヤー州に回帰した「カレンニー」文字
ビルマが民政移管すると、KNPPは政府と戦闘を停止することに合意し、和平に向けた交渉が続いている。それ以降、「カレンニー」文字に新たな意味が付与されるようになった。これまで反政府運動の象徴となってきた「カレンニー」文字が、カヤー州の公式の文字表記の一つとなったのである。政府関係者、教会や寺院などの宗教関係者、そしてタイ側からの代表、つまりKNPPの勢力下の代表らで組織された「カヤー民族言語文化委員会」は、2013年6月に声明を発表し、この「カレンニー」文字を公式の文字表記とすることを通知した。ただし、その位置づけは「カレンニー」文字ではなく、カヤーの「チェボジ文字」というものである。チェボジという地名がつけられたのは、文字を制作したテーブペーの出自にもとづいている。
この文字をカヤー文字と呼ぶかカレンニー文字と呼ぶかでは議論が紛糾したという。政府にとって、KNPPとはインフォーマルな集団にすぎず、「亡命政府」として存在を認めているわけではない。議論の末、カレンニーという名を用いることは認められなかったものの、両者は、州内に住む「人々の文字である」という点で合意に至った。この妥協ができたのは、「カレンニー」は州内諸民族の総称、つまり人々を指すというロジックがあったからだと考えられる。またカヤーはカヤー語で人間を意味することも想起しておこう。
他方、「カレンニー」語が「チェボジ文字」としてカヤー州の文字表記として公認されたことは、名前をめぐる係争が新たな局面を迎えたことを示す。政府は、「カヤー」の文字表記の一つとして包摂することで「カレンニー」の理念をくじき包摂することができるのか、そしてそれが和平への筋道となるか、それとも新たな係争の火種となるのだろうか。
「民族」紛争の解決に向けて
軍政期以降のビルマの歴史を紐解くと、このような形で民族言語が認可されることは異例と言ってよいだろう。社会主義時代の憲法も民族言語教育を認めていたものの、実際には有名無実で、ビルマ語教育が推進された。現在の諸民族の位置づけを考察するにあたり、もうひとつ示唆的な出来事がある。

2013年9月、「カヤンの美」という映画がビルマ全土で公開された。この映画は、隣国タイで観光業を営むカヤン(いわゆる「首長族」)は、人身売買の被害者だと訴える物語である。映画の顛末は、ビジネスマンに拉致されようとするカヤン女性を、若くてハンサムなビルマ人男性の警察官が助けるというものである。少数民族の女性をビルマ人男性が助けるという構図は、なんとも「ビルマらしい」。しかし、この映画が画期的なのは、ほぼ全編にわたりビルマ語字幕つきのカヤン語によって展開する点にある。このような諸民族の位置づけの変化は、一時的なものかもしれないが、多民族国家のあり方を模索する過程とみることもできる。
最後に強調しておきたい点は、「カレンニー」にせよ「カヤー」にせよ、人々の対応はきわめて柔軟であるという点である。状況に応じてカレンニーと自称したりカヤーと自称したりする。2014年3月から4月にかけてビルマ政府は、1983年以来行われてこなかったセンサスを実施する予定である。センサスとは、人々をビルマ政府が認可している135民族のいずれかに分類する作業だが、これが問題の解決につながるよりも新たな火種の原因となる可能性もある。そもそも人々の帰属意識やアイデンティティとは、こうした国家が規定するハードな「民族」ではなく、ソフトかつ複数であるという点に立ち返る必要がある。こうした柔軟な民族観こそ、現代版の分割統治に抗するためのよりどころになるのではないだろうか。

日本学術振興会・特別研究員