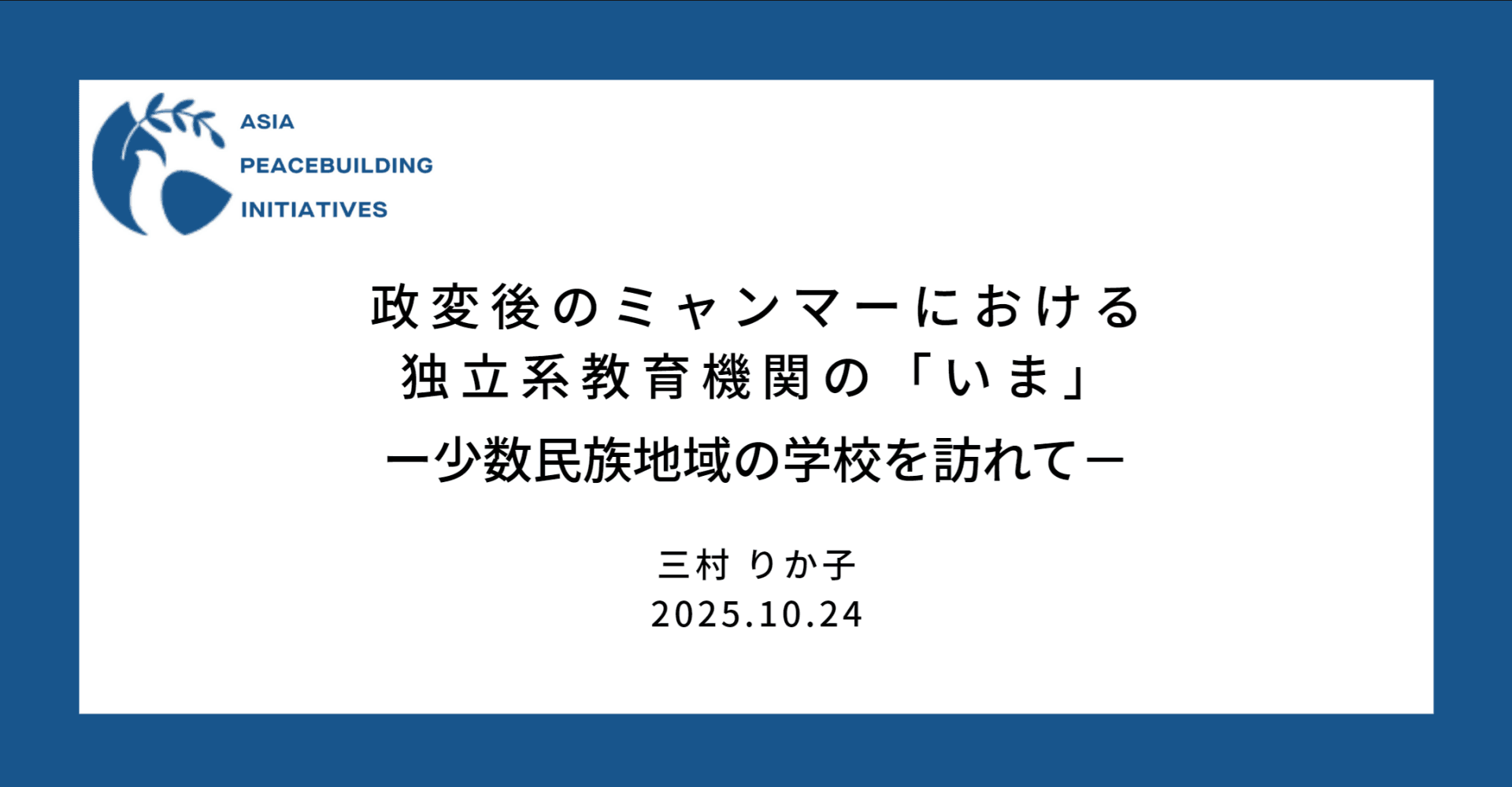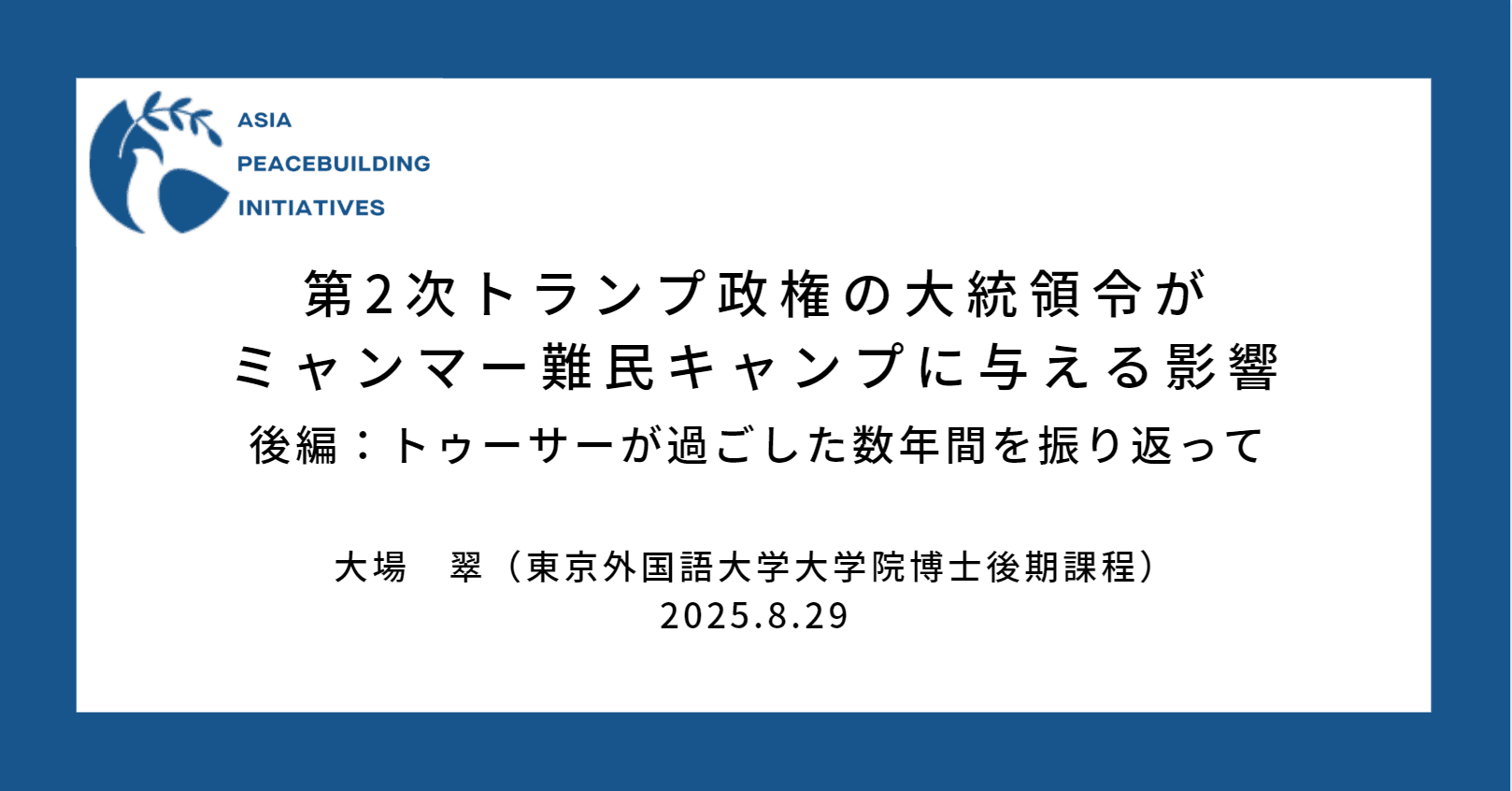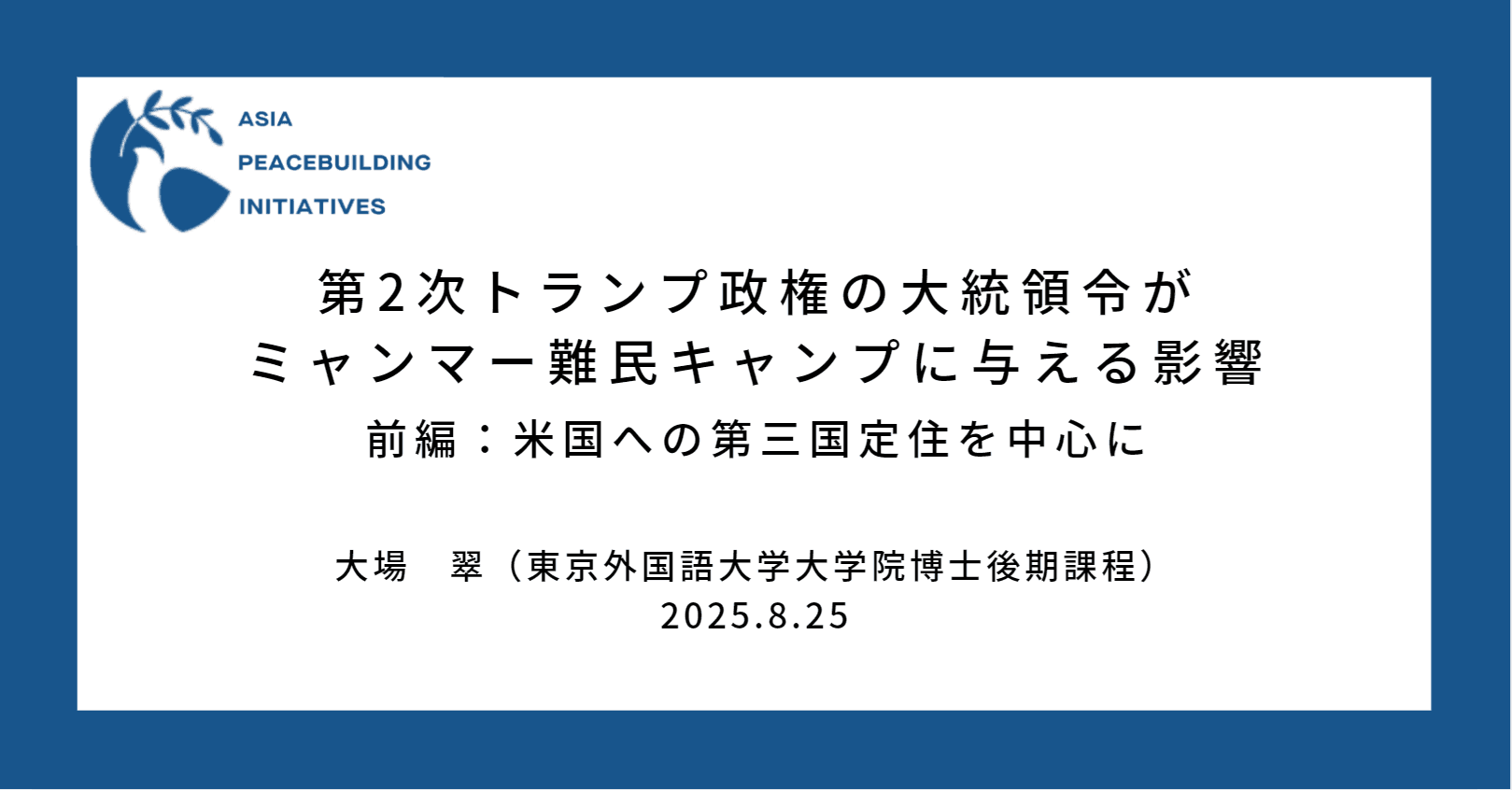- ミャンマー
国籍法に象徴されるビルマ(ミャンマー)の排他的ナショナリズム

はじめに
ビルマ(ミャンマー)では2011年後半以来、民主化や経済の自由化に向けた「上からの変化」が急速に進み、政治囚の解放や事前検閲の廃止など、国際社会が望む前向きの成果が見られる一方、いくつもの後ろ向きの現象も生じている。その中でも最も深刻な問題は、仏教徒によるムスリムへの攻撃に代表される宗教間の対立であろう。ここでは、こうした対立が生じる背景として、ビルマ国民が抱く歴史認識の問題点を、1982年に施行された現行の国籍法を通じて考えてみることしたい。そこには強度に排他的なナショナリズムが反英されているからである。
ビルマ政府による自国イメージ
1948年1月4日に英国から独立したビルマは、「上座仏教」と「ビルマ語」を強調し、さらに歴史認識としてナショナルヒストリーの叙述を通じ「イギリス帝国主義と日本ファシズムの支配を倒して独立を達成した」ことと、自分達の「歴史上の故郷が中央平野部の旧王都一帯にある」ことを力説してきた。
こうした自国像の背景には、宗主国だった英国と第二次世界大戦中の占領者である日本に対し展開した独立闘争において、その思想的基盤となったビルマ・ナショナリズムの存在がある。そこでは「(多数派の)ビルマ民族と彼らがつくりあげたビルマ文化を中心とする国家」の建国が強調された。独立達成後の国民統合過程においても、国家は公教育や政府刊行物等における記述を通じて、このビルマ・ナショナリズムに基づく自国像を徹底させることになった。
その結果、非上座仏教徒(人口の10%強)やビルマ語を母国語としない集団(同30%前後)、またビルマ中央平野部に特別な思い入れのない人々(同30%前後)は「周縁」に位置づけられることになり、これが少数民族問題と宗教問題(宗教対立)発生の一要因となった。無論、中央と地方(特に少数民族州)との経済的不平等や、中央政府による少数民族や宗教的少数者の主張を封じ込めようとする姿勢も、少数民族問題の大きな要因として指摘できる(参考までにビルマの民族別・宗教別人口比率を表1、2で示しておく)。
表1 ビルマ主要8民族の人口構成比
(Chart 1: 8 main ethnic groups in Burma)
| Bamar (Burmese) バマー(狭義のビルマ) | 69.0% |
| Shan シャン | 8.3% |
| Karen (Kayin)カレン(カイン) | 6.2% |
| Rakhine アラカン(ラカイン) | 4.5% |
| Mon モン | 2.4% |
| Chin チン | 2.2% |
| Kachin カチン | 1.4% |
| Kayah カヤー | 0.4% |
| Others その他 | 5.6% |
表2 ビルマの宗教別人口構成比
(Chart 2: Religions in Burma)
| Buddhist 上座仏教 | 8.3% |
| Christian キリスト教 | 4.94% |
| Islam イスラーム) | 3.99% |
| Animism 精霊信仰 | 1.12 |
*表1、2いずれも1983年に実施されたセンサスに基づく。ビルマでは本年(2014年)、31年ぶりに人口調査が行われる予定である。(Chart 1 and 2 are based on the 1983 census. This year (2014) a new census is due since the last one 31 years ago)

誰が土着民族か:「1823年」という幻想
ビルマでは政府公認の135民族が「土着民族」として認められ、国籍を自動的に付与されている。「土着」であるか否かは、1982年施行の国籍法(ビルマ市民権法)に基づき、第一次英緬戦争(1824-26)が始まる前年にあたる1823年以前からビルマに住んでいたかどうかで決められ、1824年以降にビルマへ移住して住みついた人々は「非土着」扱いされている。
同国籍法では、この135民族が1823年以前からビルマに住んでいる正規の「国民」とされ、独立年である1948年に施行された最初の国籍法に基づいて国籍を申請し取得した人(主にインド系や中国系の人々や英系ビルマ人)を「準国民」、法律に基づいて帰化した外国人を「帰化国民」に分類している。「準国民」と「帰化国民」は3代たてば「国民」に格上げされるが、それまでは公務員の管理職になれず、国家の教育予算が多く使われている大学の理工系・医学系学部に進学が認められないなど、不平等な扱いを受けることになる。
そうした「制限」について国籍法に規定されているわけではないが、現実に差別は発生しているため、国籍法に示された区別が「悪用」されていることは事実である。また、このことに付随して、ビルマに移民として入って以来3代以上にわたって住む人間が、「ビルマ民族(バマー)」としてのアイデンティティを主張しても、宗教がイスラームだったり、顔つきがインド系や中国系だったりすると、役所が国民登録証を発行する際に「国民」とは認めても、民族名を書き込む欄に「ビルマ民族(バマー)」と記入することを禁ずるという事態も生じている。
現在のビルマ国民の多くは、国籍法に示された「1823年」という基準に何らの疑いを抱いていない。しかし、この基準は歴史的に見た場合、ビルマ・ナショナリズムが生み出した幻想に過ぎないといえる。なぜなら、18世紀後半のビルマ王国(コンバウン朝、1752-1885)の時代から、王都には上座仏教徒を中心に、ムスリムやヒンドゥー教徒、キリスト教徒が共住し、民族的にも現在でいう中国系、インド系、アフガン系、ペルシア系、アルメニア系、ポルトガル系などが混住していたからである。それも短期滞在者としてではなく、ときの王権に公認され、保護を受け、何代にもわたって住んでいたのである。当時の王権は、被支配者を「民族」や「宗教」で分類することをせず、王権の支配が及ぶレベルの強弱で各集団の違いを認識していた。そのため、いまでいう「民族」を基準に統治対象を分類したり差別したりする発想は希薄だった。
「民族」による分類が導入されるのは19世紀後半に英国による植民地統治が始まってからである。20世紀に入ると、この国の社会のなかで、とりわけ植民地下の近代教育を受けた人々のあいだで、土着の人々を「民族」別に識別することが当然視されるようになる。その流れのなかで歴史的多数派としての自覚を深めたビルマ(バマー)民族が中心となって、植民地支配体制を打倒し、新しい独立ビルマを建国しようとするビルマ・ナショナリズムが誕生した。そこでは「ビルマ語」と共に「上座仏教」がビルマ国民の文化的核心として重視された。
ムスリムに対する「他者」意識
上述のように、ビルマのムスリムは少なくとも18世紀後半以降のビルマ王国の時代からビルマに住み着いていたことが史料で認められる。にもかかわらず、ビルマ民族を中心とする一般の仏教徒から、ムスリムはインドなどから1824年以降に入ってきた「非土着」の人々として「記憶」され、そのために「周縁」視され、「ビルマ語と上座仏教の国」におけるマイノリティ(少数派の「他者」)として「おとなしく」していることが暗に求められてきた。
ビルマ民族の中でこうした記憶がなぜ生じたのか考えてみたい。英領期には年間14万人から42万人の範囲でインド系の人々が大量に移民としてビルマに流入した。それによって1931年までにラングーンの人口の過半数はインド系で占められるに至った。また、インド系の中には金融業を営むカースト集団チェティアがいて、彼らがビルマの農民に金を貸し、返済できない場合は担保の土地を取り上げ、不在地主化していった「事実」がある。こうした要因が反インド人感情を醸成し、ビルマ・ナショナリズムが上座仏教徒のあいだで強められていったのだといえる。
1930年と1938年には大規模な反インド人暴動が国内で発生する。その際、興味深い点は、同じ反インド人感情でも、上座仏教と共通性を一部共有するヒンドゥー教の信徒に対してよりも、何ら接点のないイスラームの信徒(ムスリム)に対する反発のほうが強かったことである。英国が1937年4月に施行したビルマ統治法下で、一定の自治権を与えられた当時の英領ビルマ政府は、1938年の反インド人暴動を機に、ビルマ人政治家らの強い意向もあって、インドからの移民制限を試みる。そこではビルマ人女性とインド人移民との結婚制限まで提案されたが、その際も、ムスリムの移民に対する危機感や恐怖感が強調されている(ただし、いずれの制限も実施には至らず)。
一方、史実を冷静に見ていくと、当時のインド系移民の大半は3年ほどでインド本土へ帰る「出稼ぎ」型の短期移民であり、長期に住みついたインド系住民は数として突出していたわけではないことがわかる。またチェティアも土地を担保にした場合は年15%、無担保の場合でも年60%の利子を課していたに過ぎないので、「高利貸し」だったとはいえない。また、彼らがビルマの農村部で地主になろうとしてビルマ農民に金を貸したわけでもない。しかし、これらの史実は農民の多くが土地なしの「農業労働者」に転落していく1920年代以降、台頭するビルマ・ナショナリズムの運動が強調する「反チェティア」「反インド人」言説によって忘却されていった。
1948年の独立後、上座仏教徒とムスリムとの関係は、言語や服装を通じてビルマ化したムスリム(=バマー・ムスリム)の融合的な生き方もあって、決定的な対立に至ることなく、両者は一応共存してきた。それでもビルマ人仏教徒女性とムスリム男性との結婚は植民地期同様に敵視され、両コミュニティ間の交流が深まったわけではなかった。
こうしたなか、1990年代以降、サウジアラビアの国際的台頭に伴うワッハーブ派の影響がビルマにも及ぶようになり、ビルマ人ムスリムの若い世代の一部が、服装などを通じイスラームを強調するようになった。その結果、彼らに対する仏教徒側の「恐れ」が強まり、軍政が終わって現在の民主化に向けた「変化」が始まると、抑圧的な治安体制がゆるんだため、一部の仏教僧侶によるイスラーム批判が公然と湧きおこり、上座仏教徒のあいだで反ムスリム感情が扇動されることになった。政府は現行憲法の規定に従い、宗教の政治利用を禁ずる姿勢をとり、こうした動きに歯止めをかけようとしている。
しかし、2012年6月にラカイン州北部で生じた反ロヒンギャ・反ムスリム暴動(200人以上が死亡)や、2013年3月に中部ビルマのメイッティーラで起きた反ムスリム暴動(43人死亡)で見られたように、政府のそうした姿勢が末端まで徹底されているとはとてもいえない。警察は暴動の現場にかけつけても傍観して止めに入ることをせず、軍が投入され初めて暴徒は静まった経緯があり、また現地の行政機関は被害にあったロヒンギャやそのほかのムスリムを保護すると称して、彼らを隔離する措置を取り続けているからである。
ロヒンギャー問題
既述のように、1823年という年で「土着」と「非土着」を分ける考え方は、国家や政府だけが一方的に国民に押し付けたものとはいえず、ビルマ民族に限らず非ビルマ系少数民族も含め、土着「国民」として分類されているビルマの人々から大きな疑問もなく受け入れられている。
それを象徴するのがビルマ西部ラカイン(アラカン)州の西北部に住むムスリム集団のロヒンギャーに対するビルマ「国民」の排他的感情である。民族名としての「ロヒンギャー」の使用は文献では1950年までしかさかのぼれない。しかし、歴史的には15世紀から18世紀にこの地に栄えたアラカン王国の中にいた数多くのムスリムを基盤に、19世紀以降の英領下において現在のバングラデシュにあたるベンガル地方から入ってきたムスリム移民と、独立前後の混乱期にやはりベンガル地方から入ってきたムスリム移民が、お互いに重なり合いながら、その一部が第二次大戦後に単独の民族ロヒンギャーとして自己主張をはじめた経緯を持つ。その意味では「新しい」民族だといえるが、彼ら自身は自らの歴史を長いものとして認識している。
そのロヒンギャーに対し、現在のビルマ国民の大半は彼らを土着民族と認めず、第二次大戦後にベンガル地方から入ってきた「不法移民」としてとらえ、彼らに対する抑圧が生じ大量の難民が流出しても他人事のように考える傾向がある。「ロヒンギャー」という名称の使用すら認めず「ベンガル人」と呼ぶ人も多い。特にラカイン(アラカン)民族の多くは「ロヒンギャー」という名前に不快な表情を見せる。そこにはロヒンギャーが単に「不法移民」だからということにとどまらず、ビルマの中で最も保守的な部類のムスリムであり、容貌がほかの土着「国民」と大きく異なるという、宗教的・人種的偏見も含まれている。そしてその基本には、「彼らはそもそも1823年以前から住んでいた人々ではない」という、1982年国籍法と重なるビルマ国民の多数派の歴史認識が影響しているといえる。
アウンサンスーチーがぶつかる壁

2012年4月に下院議員となって政界入りしたアウンサンスーチーは、同年8月に発生したロヒンギャーに対する大規模な迫害に対し、暴力行為の即時停止と1982年国籍法の見直しを提言した。それに対し、彼女を強く支持する層の人々も含めて、大変なブーイングが国内で起き、海外在住ビルマ人コミュニティからも批判が沸き起こった。彼女が「ロヒンギャーの肩を持った」というのである。彼女の強調点は、1982年国籍法が有する不合理な「国民」定義(すなわち1823年という線引きのありかた)と、3つのカテゴリーに「国民」を分類する考え方への再考にあるのだが、国民はアウンサンスーチーのそうしたリベラルな考え方よりも、「1823年という幻想」にこだわる排他的ナショナリズムを優先させ、彼女を批判したのである。
こうした一連の流れを見ると、この国の未来は、自らのナショナリズムの中にある強すぎる排他性を、どこまで自覚的に制御できるかにかかっているといっても過言ではないように思われる。国籍法の再検討はそうした制御の第一歩になるはずだが、現状を見る限り、早期にそれに着手できるかどうかは甚だ微妙である。

上智大学外国語学部教授