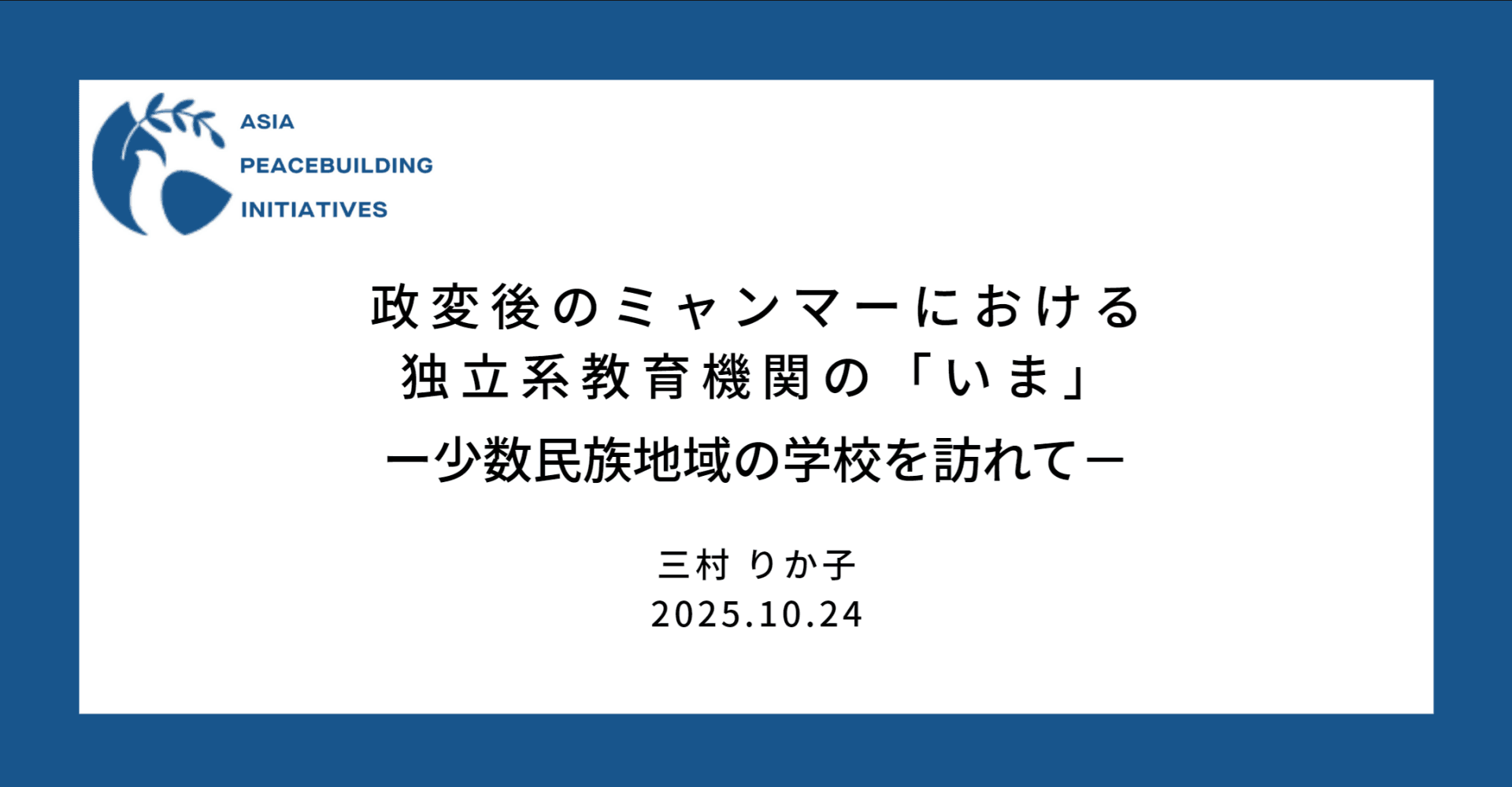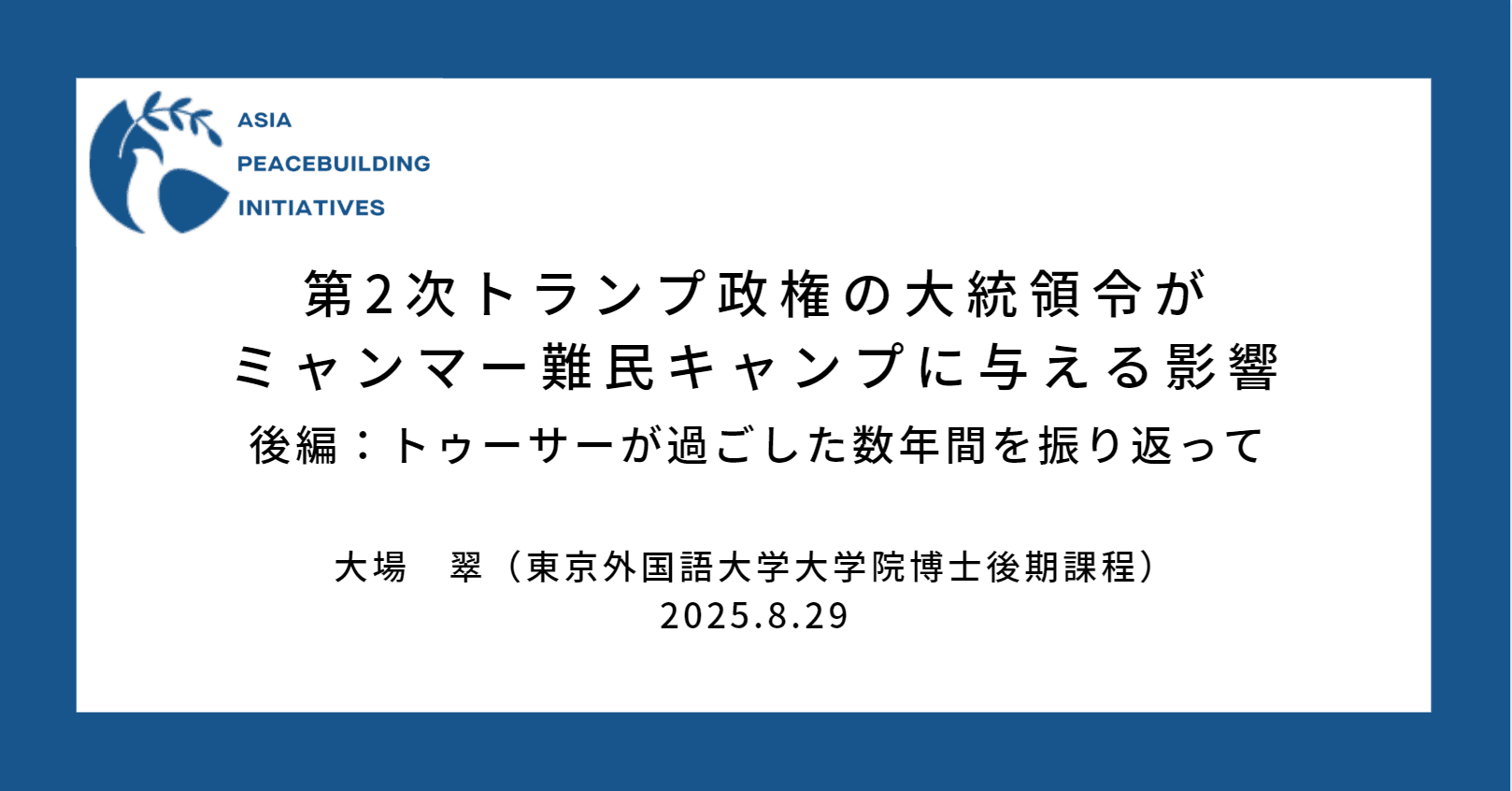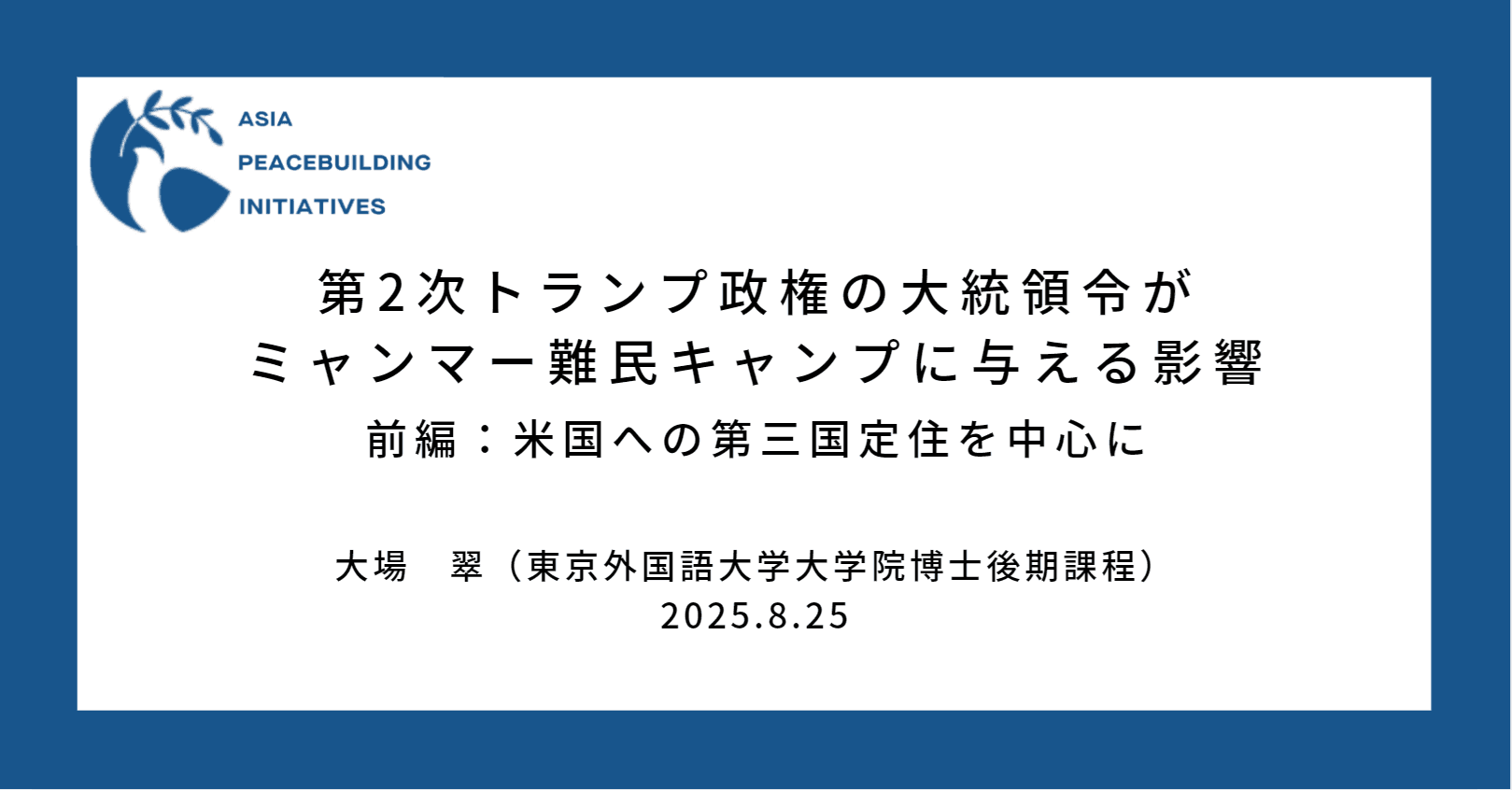- ミャンマー
王国最後の都の面影を辿る:マンダレーの町角で

豊かな食文化に多文化の歴史あり
ミャンマーの古都マンダレーが食の都であることは、あまり知られていない。
国際色豊かな現代風レストランが立ち並ぶという点では、経済改革に沸き立ち、外国人や富裕層向けの高級レストランが続々と開業するヤンゴンに見劣りするかも知れない。しかし、マンダレーに根付く食文化は、かつて王国の都であったこの町の歴史を雄弁に物語っている。マンダレーの食を丹念に味わうことで、往時のミャンマーを取り巻いていた世界の広がりに思いをはせることができる。
マンダレーの日差しは暑いというよりも痛い。ヤンゴンから離れること北へ約700キロの内陸部にあって、空気はカラカラに乾いている。太陽の光は妨げられることなく、体の芯に響くように降り注ぐ。ただでさえホコリっぽい町の空気は、夥しいバイクの排気ガスと入り混じって喉や鼻を痛めつける。町を歩くには厳しい環境だ。そのような環境下にあって癒しの場となるのは、町の至る所で見られる喫茶店や露店の類である。
喫茶店の定番は、マンダレーのみならず東南アジアのどこにでも見られる、濃厚な練乳入りの紅茶やコーヒーだ。一杯あたり30円程度。ブラックコーヒーを飲み慣れた外国人の舌には少々甘過ぎるかもしれないが、乾ききった体にはこの甘さがありがたい。ちなみに、普通のお茶ならば無料で飲み放題である。小腹が空いている時は、豊富なサイドメニューに手を伸ばすのがよい。代表的なのは肉まん・あんまんなどの饅頭類、そしてサモサなどのインド風のスナック類。あるいは茶葉のサラダ「ラペットウ」。締めて70~80円も出せば上々の一服ができる。
マンダレーの軽食に触れるならば、多彩な麺料理ははずせない。ミャンマーを代表する麺料理として、モヒンガーは有名だが、マンダレーではそれほど多く見かけない。代わってよく見かけるのが、ミーシェー、シャンカウスェ、モンティーだ。ミーシェーは中国雲南省から伝来したとされる、米の麺を使った料理。名もそのまま米線(ミーシェン)の転訛である。シャンカウスウェは、シャン族のソバ(カウスェ)の意味。モンティーはミャンマー西部ヤカイン州でもよく食される、米の麺である。ミーシェー、モンティーは40円くらい、シャンカウスェはやや高級で、一杯80~100円といったところ。
日暮れ時になると、チャパティを焼く露店も出始める。チャパティとは南アジア起源の、小麦粉で作った生地を鉄板で焼き上げたシンプルな料理である。町角の露店で1枚頼むと、ジャガイモのカレーつきで20円程と格安である。単純な料理ながら、口に含むと香ばしさが広がり味わい深い。夕食後でも「別腹」で1~2枚は平らげられる絶品だ。
しっかりした食事をするなら、マンダレーの商業中心地であるゼージョー市場の周辺を歩くとよい。シャン料理屋や雲南系華人の経営する中国料理店がこの近辺に集まっている。
このように食べ歩いてみると、様々な土地から食材や調理法がもたらされていることに気がつく。もちろんミャンマー料理の店も存在するが、より特徴的なのは中国・雲南、南アジア、シャン州からの食文化だ。さらに注意深く観察すると、町の随所に多様な出自の人々のコミュニティーが形成されていることにも気づく。シャン料理屋はシャン族のコミュニティーに隣接し、有名店がある。チャパティ露店が出る界隈はモスクの多い一帯である。
東西の文化が一同に会し、コスモポリタンな雰囲気が醸成されるのは、東南アジアの都市の特徴である。バンコクにせよ、シンガポールにせよ、東南アジアの都市は歴史的に海上交易ネットワークの結節点として成長し、その内部に多民族・多文化が共存する構造を内包している。マンダレーは内陸部にあるためか、このような観点から注目されることがあまりなかったが、マンダレーの多文化色豊かな食の世界は、マンダレーの成り立ちと深い関わりを持っている。

内陸の「港」としての繁栄
マンダレーは19世紀半ばに建設されたミャンマー王国最後の都である。町のレイアウトは日本の京都のように、碁盤目状になっている。町の中心には正方形の濠と城壁に囲まれた王宮があり、その外側に市街地が広がっている。市街地を西へ30分ほども歩むと、国内最大の河川エーヤーワディー河が滔々と流れる畔へとたどり着く。河沿いには船着き場が点在しており、国内各地へ向かう旅客船をはじめ多数の船が往来する。ミャンマーでは河川交通が今でも人々の足となり、生活を支えている。
マンダレーはミャンマーの「伝統文化」が幾つも育まれた土地だ。仏教文化の中心地として、また伝統諸工芸の集積地として、ミャンマー国内におけるマンダレーの存在感には別格なものがある。ミャンマーの国王は、仏教の護持者であることを王国支配の正当性の根拠とした。そのため、マンダレーには王族からの手厚い寄進を受けた仏教施設が多数現存している。
また、復元されたものとはいえ、王宮建築もマンダレーの景観を代表している。天に向かって聳える王宮内の七重屋根の尖塔は、王国時代のミャンマーを想起させるシンボルとして様々な場面で用いられている。金細工、木彫り、石工などの職人集団が集められ、煌びやかに荘厳された建造物の造営活動を支えた。王国、仏教という二大要素はマンダレーを語る上で最重要かつ不可欠の要素である。
とはいえ、マンダレーに息づく文化は、この二つの要素のみで説明できるものではない。この土地に往来した多様な人々の活動を視野に収めなければ、前述の食文化の豊かさは理解しにくい。そのためにも、まずはマンダレーが建設された場所を認識し、そこでどのような人々の交流があったかを把握することが肝要だ。
例えば、マンダレーの町角に立って東を望むと、彼方にシャン丘陵の山容が霞んで見える。シャンカウスェやラペットウの材料となる茶葉は、こうした「山の世界」からもたらされたものである。マンダレーが建設された当時も、茶葉は重要な交易品の一つであった。マンダレーには、今でもシャンの市場と称される区画があるが、ここはかつてシャン丘陵からの産品を運んできた、シャン族の商人が定着した場所であったと語り継がれている。また、シャンの藩王が住んでいたとされる街区もある。王国時代を通じて、シャン丘陵には地域全体を包括する単一の権力は存在しなかった。それぞれの盆地を単位に藩国が形成され、ミャンマー王国との関係を取り結んでいた。そのうちの一藩王がマンダレーを訪れた際に暮らした場所、ということらしい。
一方でマンダレーの西にはエーヤーディー河が控えている。エーヤーワディー河は、北へ遡っては雲南と、南へ下っては海を介して南アジア世界との交流を支えた。マンダレーは、そうした地域とのネットワークの結節点にあたる内陸の「港」であったと言える。
マンダレーの古い商業地には、華僑の集住によって形成された「中国人街」もある。王宮の西を南北に走る80番通りがそれだが、そこで目をひくのが雲南出身の華僑が建設した雲南会館だ。巨大な中国風の門構えを持つ、ランドマーク的な施設である。東南アジアの都市には、こうした華僑の集住区を持つものが珍しくない。しかし、雲南出身者が中核を成すコミュニティーは非常に珍しいのではないかと思われる。
この雲南会館の起源は王国時代にまで遡るが、マンダレーが位置するミャンマー中央部と雲南との交流は2000年近い歴史を有する。だが、雲南を拠点とする商人の活動がミャンマーに広がって行くのは、15世紀頃からのことであったと言われている。騰衝など雲南南西部の都市を起点とし、峻嶮な山脈を通過してエーヤーワディー河上流のバモーなどに下る。そこからは水路でミャンマー中央部に達することが可能となる。これとは別に、陸路マンダレーに到達するルートもあった。多数の馬を動員したキャラバンで、両地域を結ぶ交易が行なわれていた。
また、王国時代に商人や職人として到来し、ミャンマー国王と深く関わったムスリムが建立したモスクも多くある。とりわけ、マンダレーの商業地は、安宿が多く集まる一帯でもあるのだが、ここに宿泊すると、早朝に響くアザーンの声で目を覚ますことがよくある。中には、市場における徴税担当官だった人物のモスクなどもあり、「港」としてのマンダレーの運営にムスリムが果した役割の大きさを思わせる。
ところで、マンダレーのモスクには、その建てられ方に大きな特徴がある。それは、碁盤目に区切られたマンダレーの街区に1つずつモスクが配置されていることだ。街区の外周は、多くの場合は通りに面した商店街などになっている。そして、広大な空間を有する街区の中央部にモスクが置かれていることが多い。
これは、王国時代に国王が土地を下賜する際に、碁盤目に仕切られた1つ1つを区画の基本単位としたことと関係があるようだ。特定の有力者や、専門技能を有する集団をそれぞれの区画に割り当て、その中央部にコミュニティーの核となる施設の建設を認める。これはイスラームを信仰する人々のコミュニティーのみならず、その他のコミュニティーにも見られる特徴である。例えば、インド東北部のマニプール出身者のコミュニティーや、福建華僑のコミュニティーなどが類似した形態の街区を形成している。まさにモザイク状に多様な人間集団が共存したことが、王国時代のマンダレーの重要な特徴であったといえる。20円チャパティもまた、このような歴史を経てマンダレーの町角に定着している。そして、この町に住まう人々の生活を彩る一要素ともなっているのである。

失われつつあるものに目を向けて
さて今日、経済開放の流れを受けて、マンダレーにも変化の兆しが現れ始めている。増える一方のバイクや自動車はその象徴ともいえる。かつてこの町で、交通手段といえば馬車とサイカー(2人分の座席を据え付けた自転車)が主流だった。馬車は20世紀末までにほぼ姿を消してしまったが、サイカーはまだかろうじて生き残っている。
変化に直面する人々の受け止め方は様々だ。1970年代の旧型車から最新型のワゴンを入手できたあるドライバーは、諸手を挙げて現政権の政策に賛成していた。他方、30年以上のキャリアがあるというサイカー漕ぎは、「モータリゼーション」に伴う利用者の減少を本気で嘆いている。交差点の木陰の下にいる客待ちのサイカー漕ぎは、外国人が通るたびに必ず声をかける。必死に客を捕まえなければ、仕事がないと言う。
建設工事現場も目につくようになってきた。それまで通り沿いに整然と並んでいた2階建ての店舗兼住宅が取り壊され、5~6階建てのアパートに置き換わっている。ゼージョー市場は現代風のショッピングモールへの更新が具体化しつつあり、この開発プロジェクトの目玉である高層マンションが姿を現した。昔ながらの街区の景観は急速に失われつつある。
このような状況に対し、マンダレー在住の作家による歴史案内の本なども出版されている。そこでは、変わりゆくマンダレーへの危機感を表明しつつ、国家レベルの歴史叙述では取り上げられることがない、居住者の視点から見たマンダレーの歴史が描かれている。かつて存在した墓場、祭の風景、特徴的な商店街、そしてちょっと有名だった町角の喫茶店のことなども。
マンダレーの変化については、日本も無縁ではない。マンダレーを舞台とする新しい往来にはまぎれもなく、日本からの人とモノが含まれている。しかし、私たち日本人はここで、日本とマンダレーとの交流が今に始まったものでないことを思い返す必要がある。およそ70年前の日本とマンダレーとの出会いは、この町の徹底的な破壊を通したものであった。王宮を始めとする建造物群が戦災を被り、多くの歴史史料が永久に失われてしまった。
昨今のミャンマー・ブームの中で、「アジア最後のフロンティア」とこの土地を指して呼ぶことがある。しかし、そのような外部者の都合を一歩離れて、そこに住まう人々の生活と歴史とをまずはしっかりと理解しなければ、不毛な破壊が繰り返されるだけであろう。日本とマンダレーとの再会が、価値ある創造をもたらすものであることを切に願う。

上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科