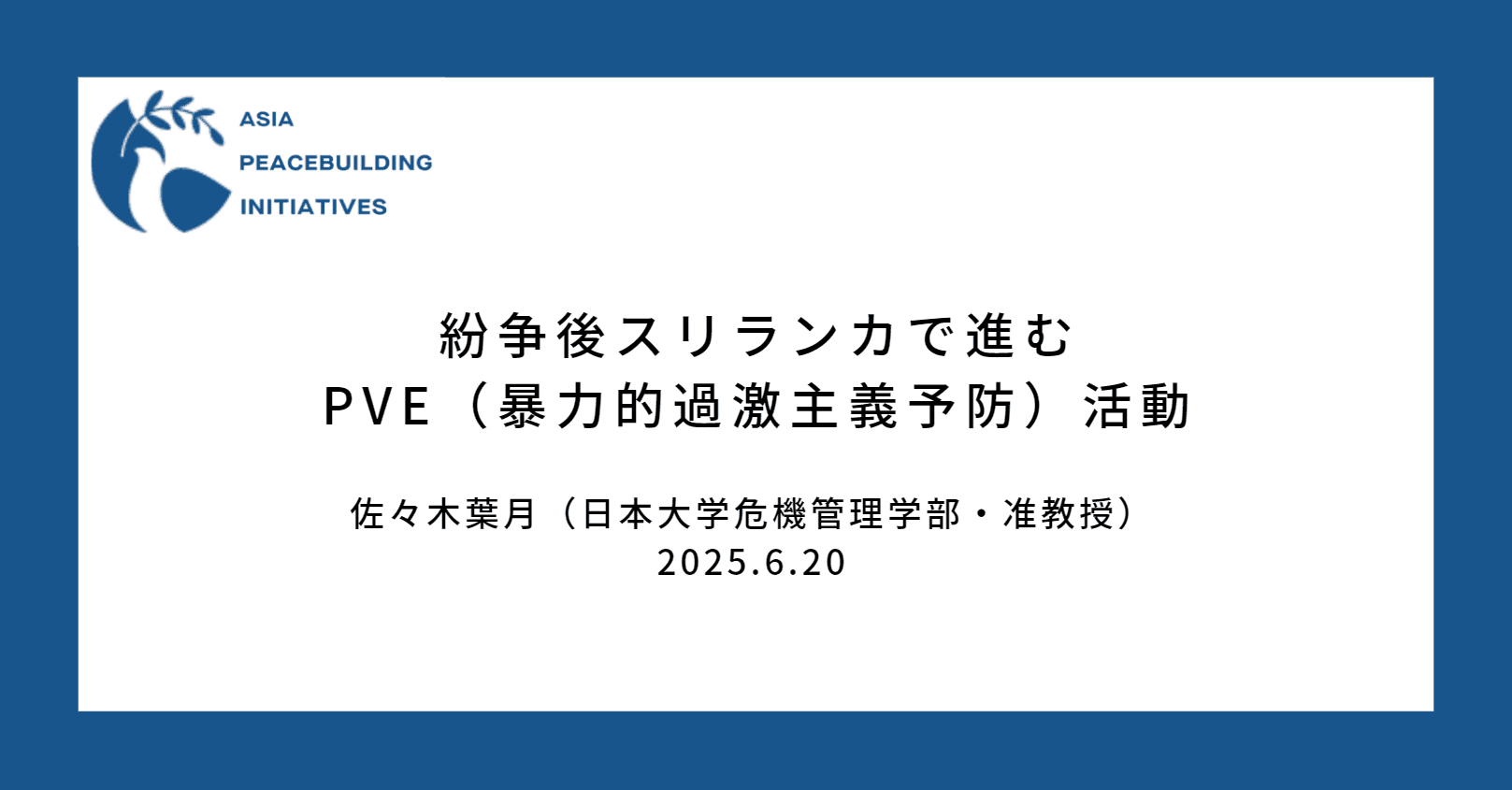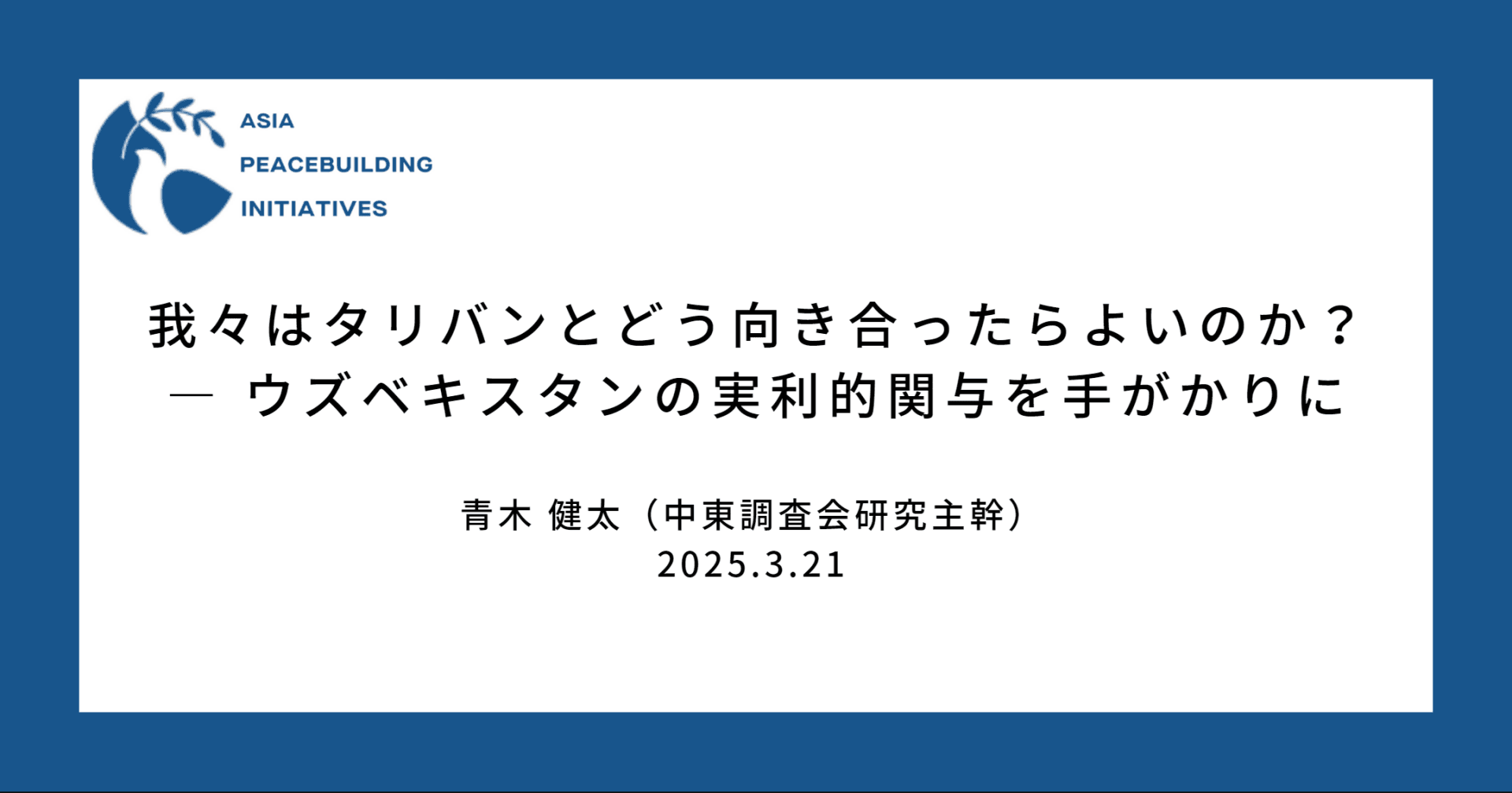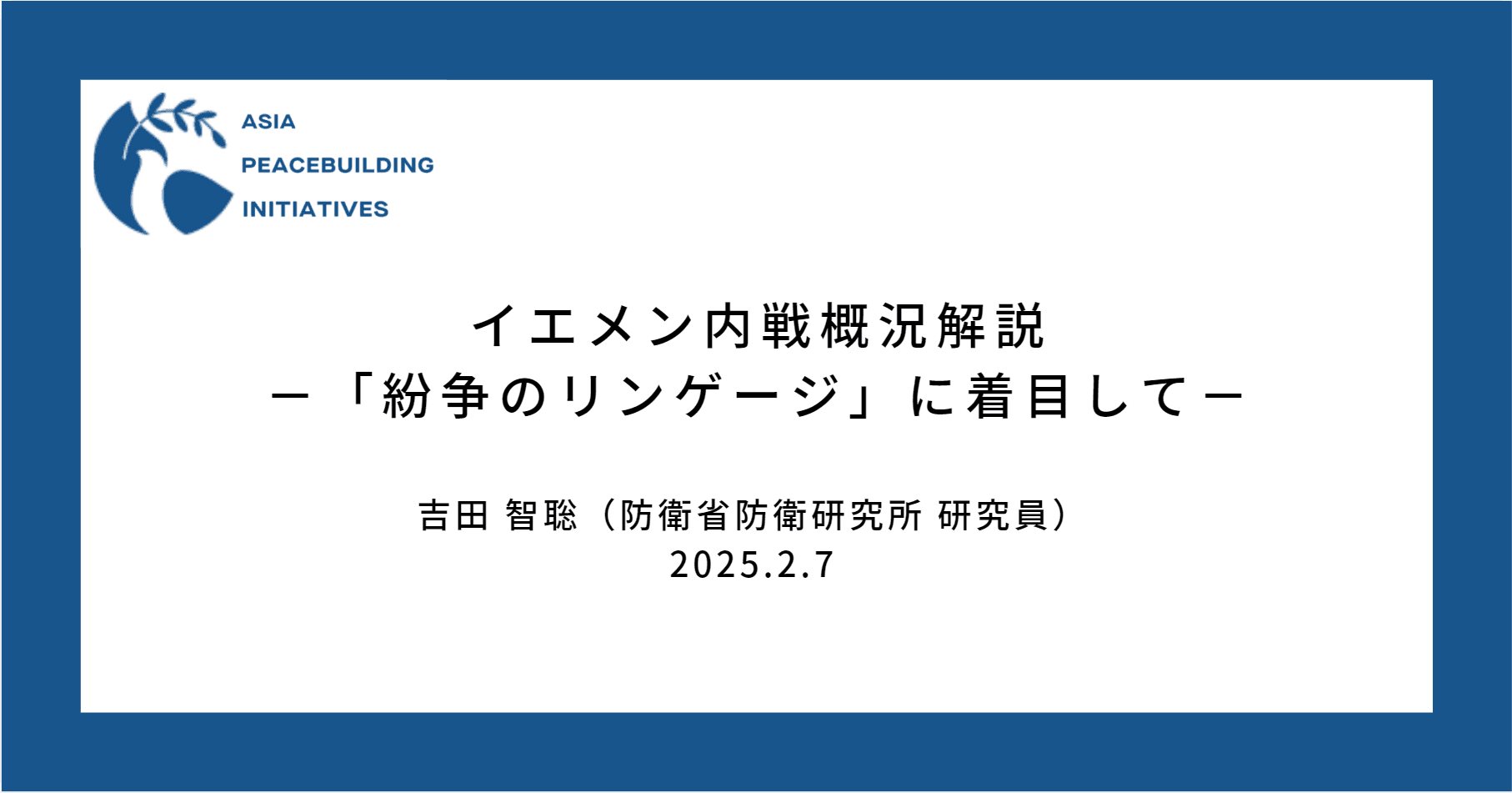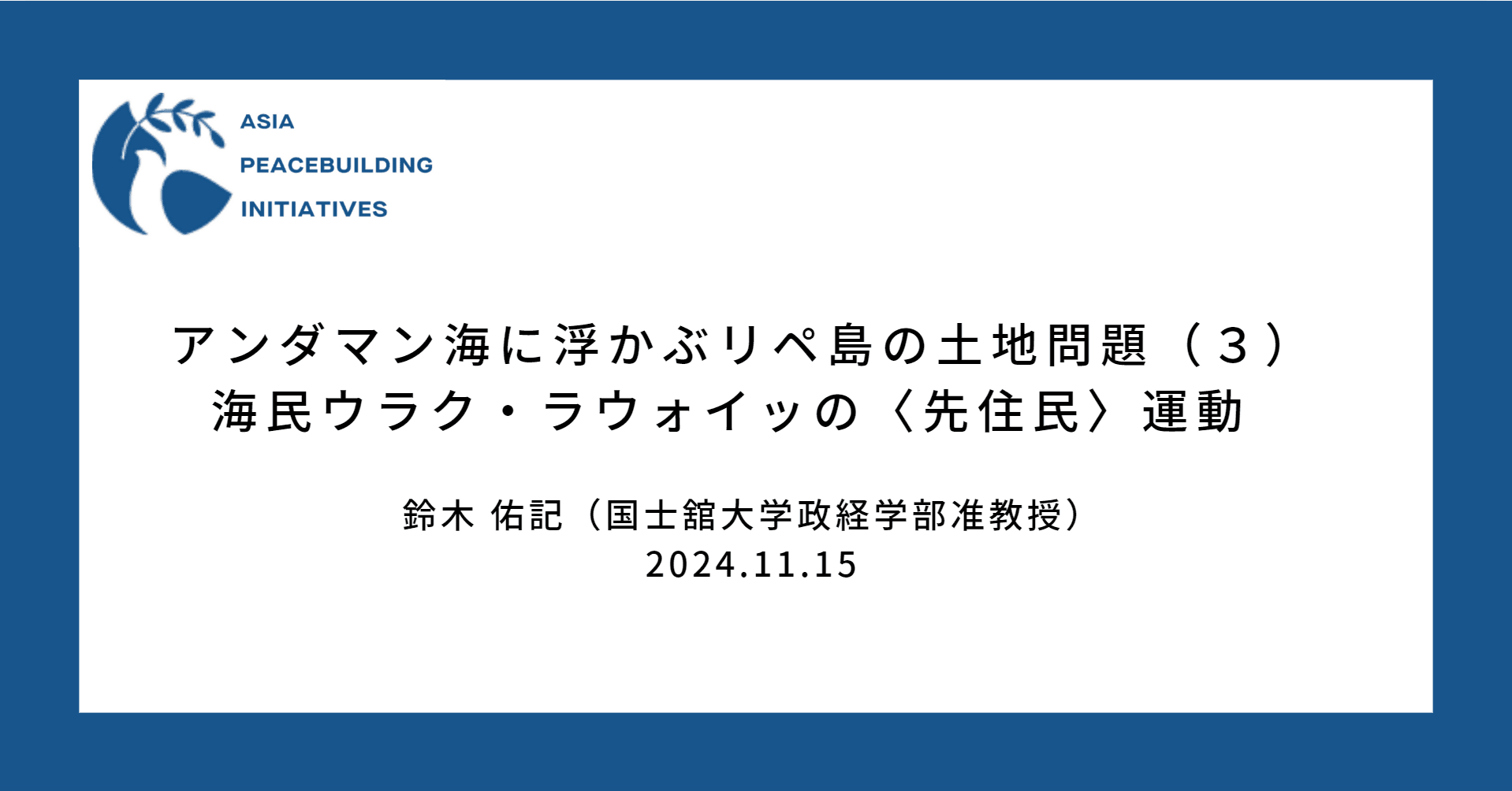- 平和構築全般
紛争再発のリスクと防止の条件: 平和構築のパラドックス

はじめに
一度、紛争を経験した地域において平和を定着させることは容易ではない。紛争後の地域は、5年以内に紛争を再発させる可能性が高いと言われ(Zürcher 2007; Collier et al. 2008)、実際に1945-96年の間に36%の事例で再発している(Walter 2004)。紛争後にいかに安定的な社会へ移行するのかという問題は、非常に大きな課題なのである。
このような紛争再発のリスクを知ることは、平和構築を行っていく上で欠かすことのできない事前作業である。なぜならば、「いかにして紛争の再発を防止し、平和を定着させていくのか」という実践的な課題に取り組むためには、「どのように紛争は再発するのか」という理解が必要不可欠だからである。
小論は、以上のような問題意識を持って、紛争後の地域が抱える紛争再発のリスクについて明らかにし、紛争の再発防止の条件についての考察を試みる。小論は、一方で現在、国際社会が取り組む平和構築の意義と必要性を再発防止の観点から認めるが、他方で国際社会の関与なき紛争には「皮肉な選択肢」が待ち受けていることを明らかにする。
すなわち、紛争研究の知見を用いて導きだされる紛争後の地域が安定をはかるための合理的方法は、「平和のための圧政」という矛盾を内包した政策にあるからである。紛争地への関与は、普遍的価値からその必要性が指摘される一方、現実には欧米諸国が意図的に関与しない、あるいは、関与できない事例がある。そのような事例において、紛争地のみで選択可能な紛争の再発防止の為の政策が、和解や共存ではなく、弾圧や排除によって実現するという平和構築のパラドックスを小論は明らかにする。
以下では、まず紛争がどのように移行するのか、紛争の変質や移行について理解し、これがどのような要因で生じるのか、主に行為主体(アクター)と彼らを取り巻く構造(紛争そのもの構造、紛争地の政治・経済・社会環境)という二つの視座から明らかにする。そして紛争再発を防止するためには、どのような政策が必要とされているのか、考察を試みる。
1.紛争の移行:プロセスとしての移行
紛争はどのように平和へと向かうのか、あるいは再発してしまうのか。この疑問に対して「紛争解決学」に取り組むラムズボサムら(Ramsbotham et al. 2011)は、プロセスとして紛争の移行を捉える必要性を指摘する。
彼らの提起する「紛争移行(Conflict Transformation)」とは、紛争が発生したり、終結・再発したりする過程の変化を捉える概念として用いられている(表1参照)。ここでいう変化とは、紛争構造が別のものに変わってしまうという大きな次元の変化から、構造を構成する諸要素が変質するという小さな次元における変化まであり、これらは相互に影響を与える。
表1:紛争移行の種類
| 移行の形態 | 説明 |
|---|---|
| 文脈的変質 | 紛争が置かれている社会的・地域的・国際的文脈が変化する事 |
| 構造的変質 | 紛争を構成する諸要素(関係者、彼らの目的や関係性)が変化する事 |
| 関係者の変質 | 紛争当事者集団がその内部にて方向性を見直したり掲げた目標を放棄・変化したりする事 |
| 争点の変質 | 紛争当事者集団が立場を変えたり、もしくは争点が顕著な特徴を失ったりするとき、あるいは新しく顕著な問題が生じるときに変化する事 |
| 個人的/集団的変質 | 紛争当事者の有力な指導者/集団が紛争に対する姿勢を大きく変化させる事 |
出典:Ramsbotham et al. (2011, pp.175-176)を参照し作成。
「文脈的変質」とは、紛争が置かれている社会的・地域的・国際的文脈が変化する事によって紛争が激化・沈静化する事を意味する。例えばラムズボサムらは、冷戦の終結という国際環境の変化によって、主に冷戦下で生じていた南部アフリカや南米での紛争が収まったと述べている。
「構造的変質」とは、紛争の構造、すなわち紛争を構成している関係者(アクター)、彼らの相容れない目的や利害(争点)、あるいはその力関係(関係性)という一式が変化する事で生じるものである。変質の形態はさまざまであるが、例えば紛争の要因が集団の関係性に依拠するものであった場合に、強者と弱者の関係に変化が生じる事で紛争が解決に至ったり、激化・再発したりする。
「関係者の変質」は、紛争当事者集団における支配的アクター(指導部)やその支持層などが変化する事を意味し、これは集団内部で新しい目標・価値・信念が採用され、紛争に対する態度が変化した際に生じる。これによって紛争を構成する集団の一方が和平を模索したり、逆に新たに強硬な目的や手段を採用したりして、紛争が沈静化/激化するというものである。
「争点の変質」とは、紛争当事者が抱える既存の争点が無用なものになったり、新しい争点が出現したりする事で生じる変化を指している。争点の変質は、紛争によって得られる利益の変化や紛争当事者の掲げる目標の変化が生じた際に生じやすいので、構造的変質と関係者の変質と平行して生じる事も多い。
「個人的/集団的変質」とは、紛争当事者における中心的な指導者の態度の変化を取り上げたものであり、具体的には勝利のためにはあらゆる手段を用いたゲリラ部隊の元司令官が和解を重視し国民を統合する指導者となる事、あるいは穏健で中立的なインテリが急進主義的で過激な民族主義指導者になる事などが考えられる。これは紛争の移行を左右する大きな問題であり、ゆえに変化の核心とも言われる。
このような紛争の変質や移行はどのような要因で生じるのであろうか。以下では、まず政治指導者というアクターの役割について理解を踏まえた上で、紛争後の地域がおかれた環境という構造的要因からの理解へと進みたい。
2)政治指導者の役割
紛争の再発は、政治指導者の決定と強く結び付いており、彼らが紛争後の状況を受入れるかどうかが重要だとされ、この判断は紛争の決着の仕方と関係があると言われている(Quinn et al. 2007, 175-176)。政治指導者が紛争の継続や再開よりも平和を求める行動に出るのは、以下のような条件が整った時だと考えられている。即ち、⑴紛争における勝利の可能性の低下、⑵勝利から得られる報酬の低下、⑶紛争のコストの増加、⑷直近の紛争期間、⑸現状を維持する報酬の高まりである。
ウォルター(Walter 2004, 373)は、戦闘員が再び戦闘に戻るか否かは、以前の紛争のコストによって左右されているとし、再発しやすくなるのは、⑴報復への支持があり、⑵戦闘員の装備も整っていて、⑶戦闘能力に関する情報が増加している状況だと述べる。続けて人々の動員は、彼らが個人的な苦難を抱え、自らがおかれた状況に強く反発し、非暴力的な手段や選択肢が欠如した場合に可能になるとして、個々人の動機だけではなく、集団間の敵対関係や指導者による動員の役割も大きいと指摘する。
マーソンら(Mason et al. 2011, 172-173)は、紛争の再発は、紛争後に「多元的な主権状態」(multiple sovereignty)が生じており、反対勢力の指導者が平和よりも紛争の再開に動機を持つ時に生じるとしている。「多元的な主権状態」とは、組織化され武装した挑戦者が政府の前に一つ以上現れ、彼らが大衆の広範な支持を得る状態を指す。
いずれの論者も紛争によって形作られた紛争後の状況が政治指導者の選択を大きく左右すると述べているが、では具体的にどのような結果が生じれば、紛争を経験した社会は平和へと移行し、あるいは再び紛争へと戻ってしまうのだろうか。以下で、計量分析の結果、指摘されている要因についてまとめる。
3)紛争終結までの形態に関わる紛争再発の構造的要因
まず、紛争の期間や犠牲、争点が紛争再発と関係しているという議論がある。このうち、紛争の期間と紛争再発の関係は、例えば長期的な紛争を経験した地域では、そのコストから再度、武力紛争を始める動機が低下するので紛争は再発しにくいとされる(Quinn et al. 2007, 185)。これは次の紛争での勝利の可能性、またそれに要する時間を紛争当事者たちが認識するためだとされる(Mason et al. 2011, 178, 185)。また、紛争が終了して1年経つごとに和平が失敗する可能性は10%ずつ低下していくという。紛争の長さは、それに耐えうる能力を持っているという意味において政府と反乱勢力 1双方の相対的な強さの指標になり得る。
紛争の犠牲に関する議論は、紛争の犠牲者が多いと、統計的には紛争後に以前の敵を脅威と感じ、戦闘が再開されやすくなるというもので、紛争後の新しい環境で人々が共存する事の難しさを示している(Quinn et al. 2007, 185; Mason et al. 2011, 186)。ただ、ウォルター(Walter 2004, 379-380)は、長期的で相対的にコストの大きい紛争は、その後に紛争が発生するリスクを軽減するという別の見解を示しながら、犠牲者の規模と紛争の発生には関係がないとした。
紛争の争点に関する議論は、統計的には紛争の再発や和平の定着との直接的な因果関係はないといわれている。それによれば、例えばイデオロギー的な革命よりも民族革命の後に再発しやすいわけでもなければ、革命的な紛争よりも分離主義的な紛争のあとに再発しやすいわけでもないという(Quinn et al. 2007, 185) 2。
次に紛争の交渉や終結の形態が紛争再発と関係しているという分析がある。交渉については、例えば権力分有(power-sharing)や自治権付与(権限委譲:devolution) 3が紛争解決に有効な政策であると指摘される事は多いが、他方でこうした合意は、紛争の合意全体の3割にも満たず(Wallensteen et al. 2011, p. 151)、権力分有や自治権付与と平和の定着の関係にも異なった二つの主張がある。
一つは、自治が争点化している紛争において、紛争後に憲法などで自治を与えないと再発のリスクは46.2%だが、与えると12.2%に減少するので、自治の与えられている状況は構造的に安全だというコリアーらの主張がある(Collier et al. 2008, 471)。但し、これは少数事例で統計的な重要性を伴わないと分析者自身も認めている事に加え、異なった分析もある。それは、政府が短期間しか紛争をせず、紛争の結果、自治権の付与などを認めた場合、新たに武装勢力から政府が挑戦を受けやすくなるというウォルターの主張である(Walter 2004, 385)。この分析によれば、紛争の解決手段として安易に自治権の付与を行えば、むしろ政府の脆弱性が高まり、新たな紛争の温床にもなりかねないという。
しかし、実際にいくつかの事例では権力分有によって和平に至っているではないかという疑問に対して、ムケルジー(Mukherjee 2006)は、軍事的膠着状態でこれが提示されるのではなく、政府軍・反乱勢力いずれかの勝利の後、提示される必要があるとした。またコール(Call 2012, 184-196)は、分有される権力の属性と合意の履行を問題にし、政治的・軍事的権力の分有を認めた場合に平和定着に寄与し、領域的権力の分有を認めた場合は再発のリスクが高まるとした上で、合意が撤回されていない事例の8割超は紛争が再発していない事例だと述べた。ただ、合意が反故にされ、紛争が再発した事例も多く、問題は権力分有合意を履行するインセンティブが当事者にあるのかという点に見出せそうである。
次に紛争終結の形態と紛争再発についての議論だが、まず交渉による和平よりも一方の側の決定的な軍事的勝利の方が統計的には紛争は再発しにくいと言われている(Walter 2004; Quinn et al. 2007; DeRouen and Bercovitch 2008; Mason et al. 2011; 大林 2013)。これは、交渉の場合、政府側も反乱勢力の側も余力を残しているので、次の紛争に突入しやすく、逆に軍事的な勝利で紛争が終わる場合、敗者は紛争再発のコストを思い知らされ、勝者の側が国家機構を通して完全なコントロールを得ようとするので、敗者は再度紛争に訴える能力も失うという理解である。
他方で、交渉による和平が失敗し、紛争再発へと向かうリスクは年を追って低下するとも言われており、特に国際的な平和維持部隊が展開し、交渉による解決が行われると、それがない場合よりも紛争は再発しにくいとされている。このように和平合意と平和維持部隊のセットが平和の定着に寄与するという議論は、現在では共有されているといえよう。
もう一つは、軍事的に勝利を治めた場合も政府軍か、反乱勢力の側かによって紛争再発のリスクは異なるという主張がある。相対的に反乱軍側の勝利は、政府による勝利よりも交渉による解決よりも紛争が再発しにくいとされているが(Quinn et al. 2007, p. 174)、1年目に限れば政府軍が勝利した場合の約2倍の再発リスクがあるという指摘もある(Mason et al. 2011, p. 184)。これによれば、実のところ反乱勢力が勝利した場合、3年以上経てば、紛争再発のリスクは政府軍が勝利した場合よりも低下するとされ、権力を得た反乱勢力が概ね4年間政権を維持できるのかによって、その後の道(安定か紛争再発か)が分かれる。
4)紛争後の形態に関わる紛争再発の構造的要因
ここまでは、紛争の終結までの形態に関わる再発要因について見て来たが、以下では、和平に至った後の紛争地が抱える紛争再発のリスクについて政治・経済・社会環境からまとめたい。
まず、紛争後には、国家運営の仕方(あるいは国家制度)と紛争再発をめぐる議論がある。一般的には民主主義が紛争の再発を防ぐという理解があるが、民主的な制度と平和定着の関係は自明ではないとされている。例えばクィンやマーソンら(Quinn et al. 2007, 85)は、紛争後2年間の民主主義の水準と紛争再発の明示的関係はないとしており、コリアーら(Collier et al. 2008, 470)は、民主主義の重要な要素の一つである選挙に対して選挙の年は再発のリスクが低下するが、その後はリスクが高まるという分析結果を提示する。
他方で、成熟した民主主義は、相対的な民主主義よりも紛争が再発しにくいという分析結果(Walter 2004, 384)もある。成熟した民主主義と同様に紛争後に安定するのは、非常に権威主義的な体制だとも指摘されている(Collier, et al. 2008, 470)。マーソンら(Mason et al. 2011, 184)の分析では、民主主義も権威主義も紛争後の和平を持続させる能力を有しているが、脆弱な民主主義や権威主義は、安定せず紛争が再発しやすいという。
経済社会水準と紛争再発の関係性も様々に指摘されている。これは、武装勢力の動員の観点から紛争後の生活水準が紛争再発と関係していると考えるもので、経済社会水準(GDP、一人当たりの所得など)が高いと紛争が再発しにくいという分析結果が出ている(Walter 2004, 380;Quinn et al. 2007, 186;Collier et al. 2008, 469;Mason et al. 2011, 186)。コリアーらは、10年間同じ条件ならば再発のリスクは42%だが、10%の成長でリスクは26.9%に低下すると述べる。紛争後の地域のみでこうした経済成長を実現する事は容易ではないので、クィンとマーソンらは国際投資が特に重要だと指摘する。なお乳児死亡率や平均寿命などの社会的指数は、紛争後に観察できる紛争による犠牲の指標であるので、これも紛争再発と一定の因果関係があると主張されている。
他にも政府軍の規模が大きいと、紛争の費用対効果が釣り合わなくなるので、反乱勢力が再び暴力に訴える可能性が低くなるとか、あるいは離散民の規模が大きいと外部地域から紛争地への支援が行われるなどの理由で紛争再発のリスクが低下するなどといわれている。また大林(2013)は、政府の側ではなく反乱勢力の軍事力や抵抗力に注目し、反乱軍の軍事力が大きければ和平が継続しやすいものの、一定領域を支配していたり、外部に安全地帯を保持していたりする場合、紛争再発のリスクが高まる事と明らかにしている。
おわりに:国際社会の対応と「皮肉な選択肢」
このような紛争再発研究の理解を踏まえると、当事者は紛争後に下表のような行動をとれば、紛争再発のリスクを低下させ、また自らの利益を確保できる可能性が高いという事になる。
表2:紛争の再発防止のための合理的政策
| 行為主体 | 政策 |
|---|---|
| 政府 | 紛争後に徹底的に反乱勢力を排除し、権限分有などの合意を締結せずに、自らの軍備を強化して、非常に権威主義的な体制を築く |
| 反乱勢力 | ⑴国際的な支援を受けて紛争に勝利し、紛争後に国際投資などを得て安定した経済成長を遂げ、成熟した民主主義体制を築く
⑵紛争に勝利した後に暴力を独占した非常に権威主義的な体制をつくり、離散民などの外部主体から支援を受ける事で、経済発展を目指す |
| 国際社会 | 交渉段階から紛争に関与し、平和維持軍を派遣する事で紛争当事者に和平合意を締結させる。紛争後は国際的な投資や支援を条件に紛争地に成熟した民主主義体制を構築させ、安定した経済成長や国家による暴力の独占を支援する |
出典:筆者作成
紛争研究の分析の結果を生かすと皮肉なのは、政府側にとっても反乱勢力の側にとっても外国の介入を求めずに自己利益を担保し、紛争後の安定を図ろうとすると、それは非常に権威主義的な体制に行き着かざるを得ないという事である。
国際社会の採り得る選択肢は、国際社会が現在取組んでいる平和構築の意義と重要性を確認する結果となっている。ただこの事は、国際社会が関与しない紛争においては結局、紛争当事者の採り得る政策が悲観的なものにならざるをえないという事実を変えるものではない。特にこの問題は、当該紛争地域が「領域をめぐる対立」を抱え、紛争後もこの問題が残り続けているような状況下では大きな課題となる(富樫 2011)。
現在の国際社会では、紛争地へ介入する際に普遍的な価値や規範が語られ、介入が国際社会の責務であるかのような論調を帯びる事さえある。他方で、現実には、欧米諸国が積極的に介入しない事例や、制約から介入できない事例も少なからずある。そのような事例において、紛争後地域の安定のための最も合理的で有効な政策が、「消滅するまで相手勢力を弾圧する」というような逆説で満ちたものである事を、まず理解する必要があろう。
参考文献
大林一広(2013)「反乱軍組織と内戦後の和平期間」『国際政治』第174号、pp. 139-152。
富樫耕介(2011)「平和構築における『未(非)承認国家』問題」『国際政治』第165号、pp. 141-155。
Call, Charles (2012) Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence, Washington DC, Georgetown University Press.
Collier, Paul and Anke Hoeffler, Mans Söderbom (2008) “Post-conflict risks,” Journal of Peace Research, 45:4, pp. 461-78.
DeRouen, Karl and Jocob Bercovitch (2008) “Ensuring internal rivalries: A new framework for study of civil war,” Journal of Peace Research, 45:1, pp. 55-74.
Fearon, James (2004) “Why do some civil war last so much longer than others,” Journal of Peace Research, 41:3, pp. 275-301.
Mason, David and Mehmet Gurses, Patrick Brandt, Jason Quinn (2011) “When civil wars recur,” International Studies Perspectives, 12, pp. 171-189.
Mukherjee, Bumba (2006) “Why political power-sharing agreements lead to enduring peaceful resolution of some civil wars, but not others,” International Studies Quarterly, 50, pp. 479-504.
Quinn, Michael, David Mason and Mehmet Gurses (2007) “Sustaining the Peace: Determinants of Civil War Recurrence,” International Interactions, 33:2, pp. 167-193.
Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse and Hugh Miall (2011) Contemporary Conflict Resolution, 3rd ed., Cambridge: Polity.
Wallensteen, Peter and Lotta Harbom, Stina Högbladh (2011) “Armed conflict and peace agreements,” Peace Research: Theory and practice, London, Routledge.Walter, Barbara (2004) “Does Conflict Beget Conflict?” Journal of Peace Research, 41:3, pp. 371-388.
Zürcher, Christoph (2007), The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus, New York: New York University Press.
Notes:
1.紛争研究では、政府に対して要求を掲げ、武力を持って現状変更を迫る勢力を反乱勢力(rebel group)と形容するが、そこには価値判断(政府=「善」、反乱勢力=「悪」)は含まれていない事を断っておく。
2.但し、紛争期間の長さの説明変数としてこの相違が重要だという指摘もある。すなわち、クーデターや大衆革命に起因した紛争は比較的すぐに終わりやすいが、民族紛争だと紛争期間が長くなるというものである(Fearon 2004)。
3.権力分有と自治権付与は、いずれも対立する勢力に政治・経済・軍事面での権力へのアクセスを認める点では同じだが、前者は既存の領域的枠組み内部での参画を認め、後者は新たな領域的枠組みや権力を付与するという点で違いがある。但し、後者も権力分有の一類型であるという議論もある。権力分有の定義及び分類については、Callを参照のこと(Call 2012 , 39-41, 186-195)。

日本学術振興会特別研究員PD (Researcher, JSPS)
(東京大学)(University of Tokyo)