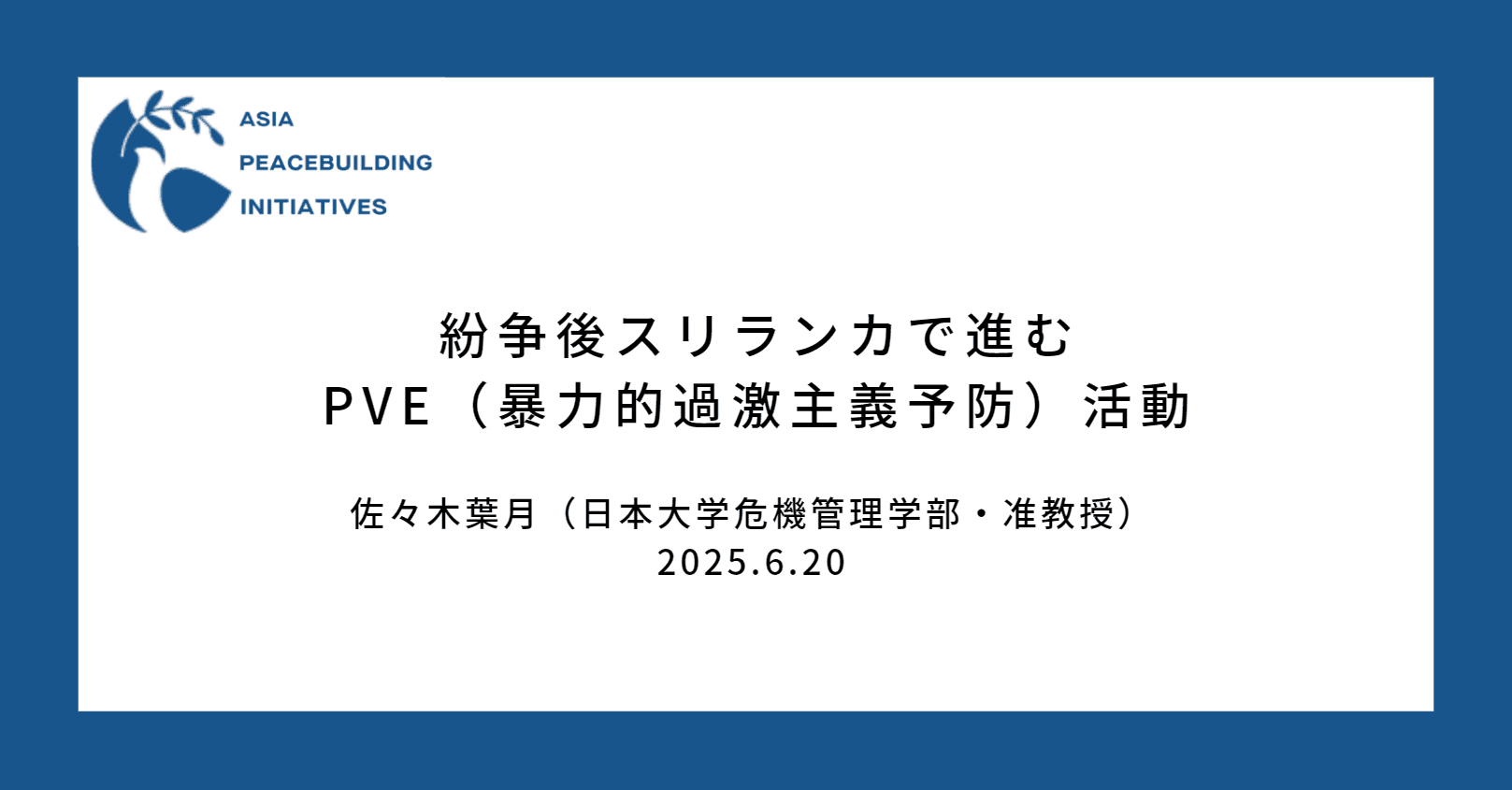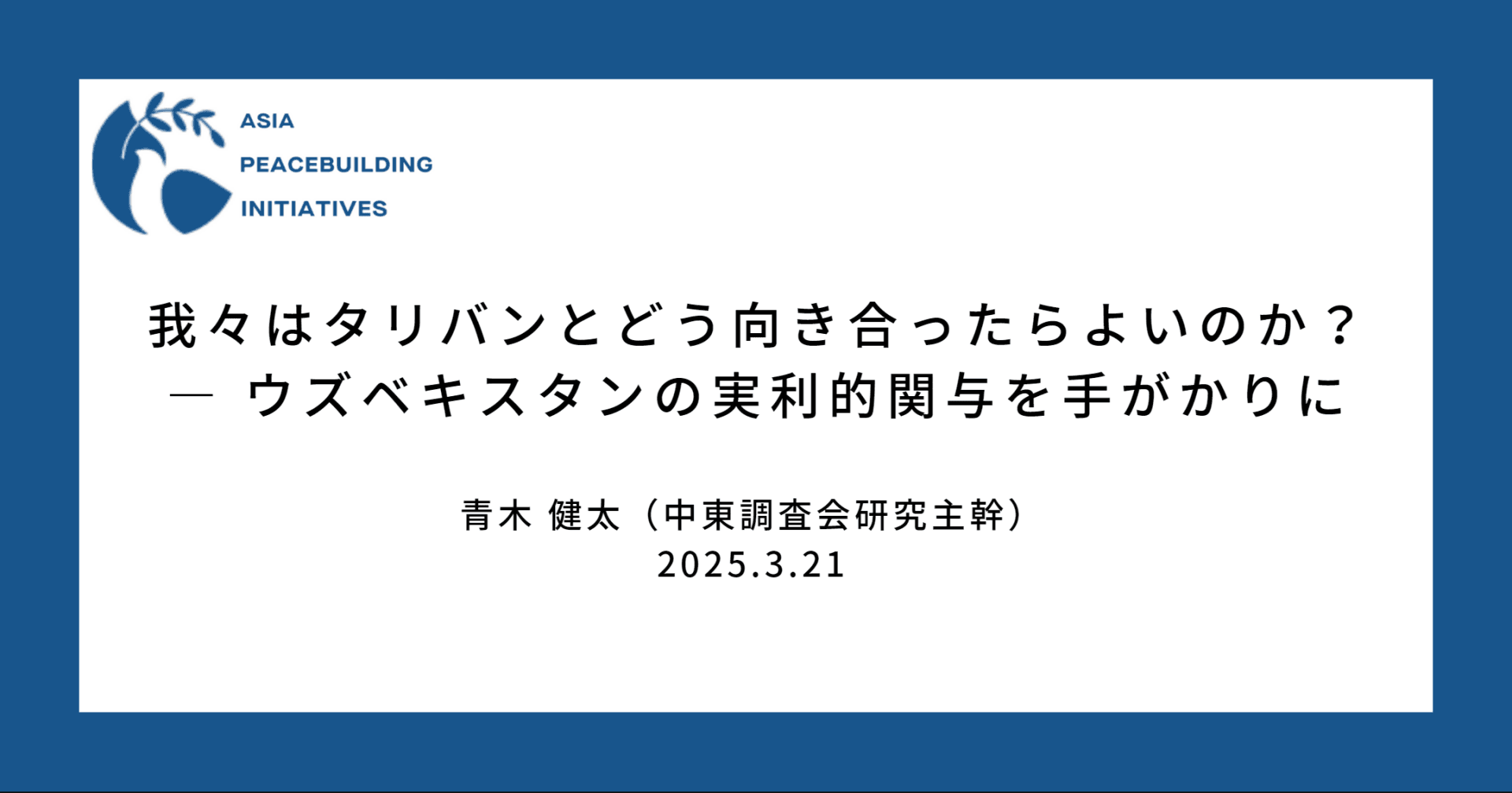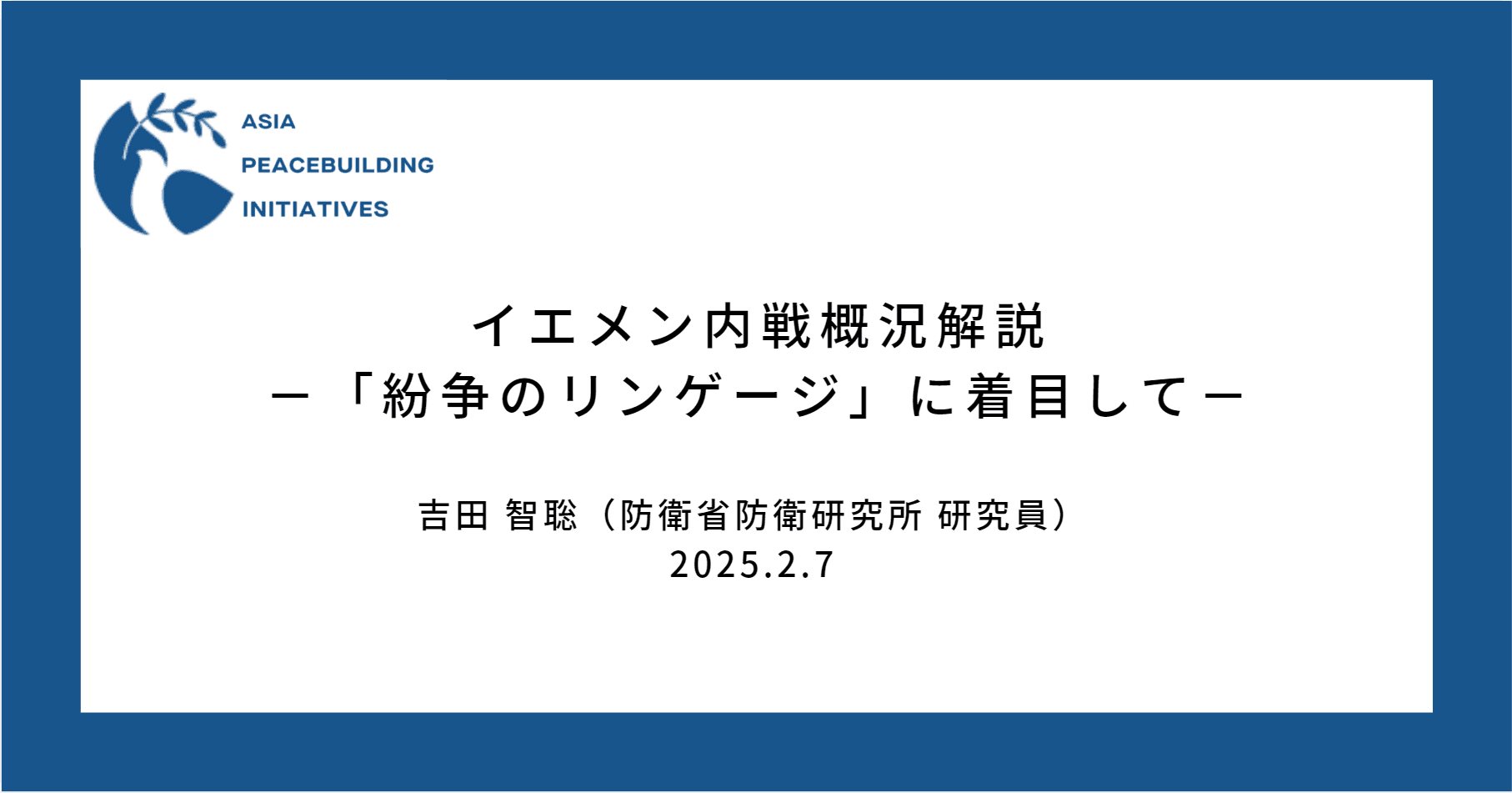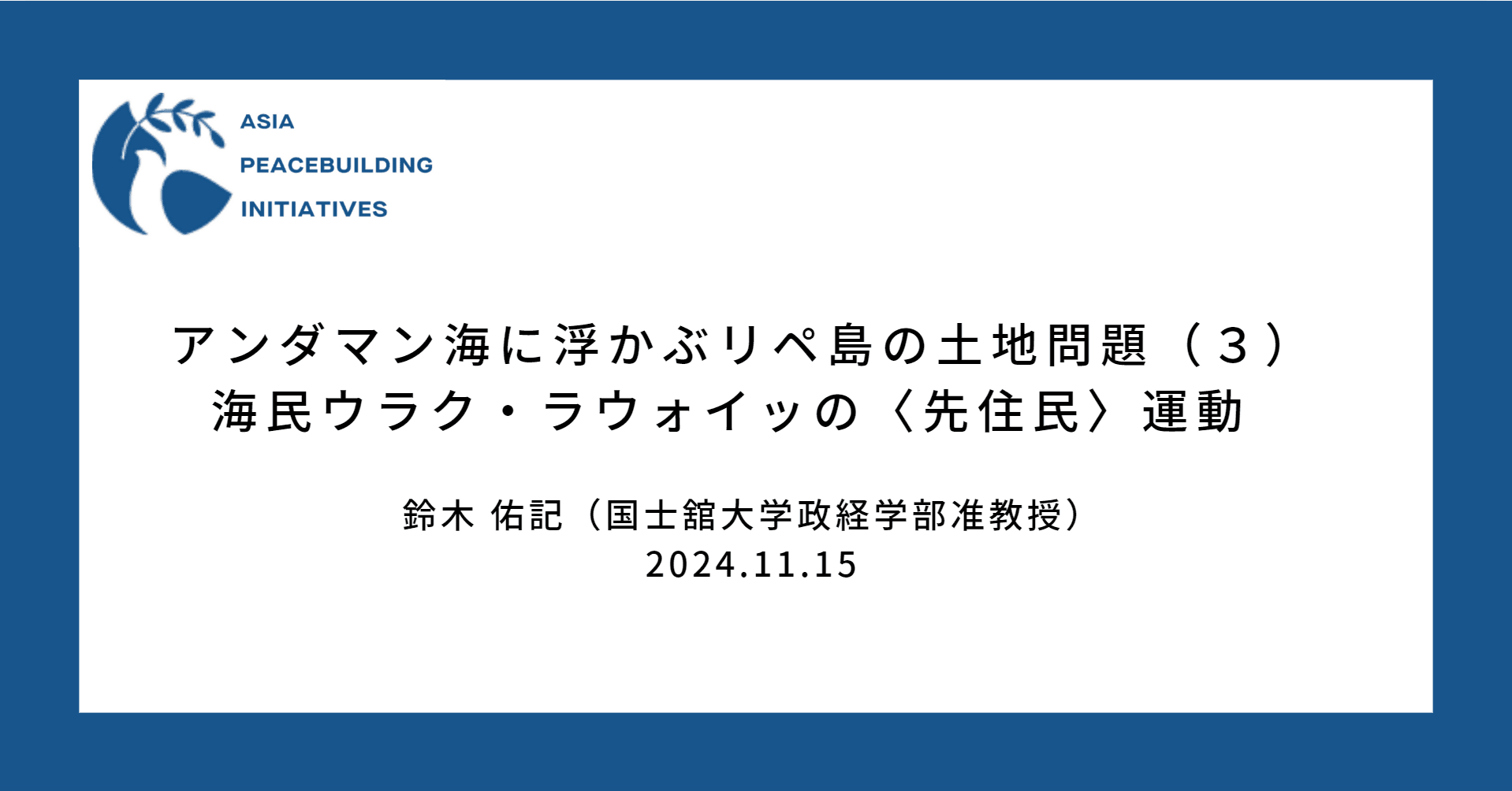- 平和構築全般
東ティモールの治安部門改革(SSR)と現地社会の主体性の課題

はじめに
本稿では、これまで私が平和構築の研究と実践や東ティモールにおける治安部門改革(Security Sector Reform: SSR)に関する研究と実践を通じて痛感した課題を「現地社会の主体性」をキーワードに論じていく。特に二大政治派閥間の対立に起因し、国軍と国家警察を巻き込んだ東ティモールにおける2006年の治安危機以降のSSRに焦点を当てて議論していきたい。
そこで、本論に入る前に、2006年の治安危機に関わった国軍と国家警察について簡単に解説しておく。インドネシアによる軍事的併合を受けた東ティモールは、国連による暫定統治を経て2002年に独立回復を果たし、新生国家として歩みだした。国軍と国家警察は憲法が制定される前に国際社会の支援を受けて新設されている。
国軍の正式名称が「ファリンティル国防軍(F−FDTL)」と言うことからもわかるように、インドネシア統治に抵抗したゲリラ組織であるファリンティルの将兵が国軍の中核に位置づけられた。他方、国家警察は創設時にインドネシア統治時代の警察官経験者を幹部として採用した。つまり、独立闘争中は反目しあっていた両勢力が、平和構築の一翼を共同で担うことになったのである。この出自の違いが、後述する国軍と国家警察との対立を招く一因となる。 なお、両組織ともに新規に要員を募り教育訓練を施すとともに、機構法の整備や組織づくりを進めた。当時は、国連が国軍創設に直接関わることは忌避されていたこともあり、東ティモールにおけるSSRでは、国軍改革はポルトガルなど二国間援助を通じて取り組まれ、国連によるSSR支援の軸足は、国家警察改革に置かれた。

理想と現実の狭間
平和構築とは、紛争後の社会において持続可能な平和を維持するための社会基盤や構造を再構築する営みである。国際社会がもたらす平和構築支援は、あくまでも一時的な側面・後方支援でしかない。したがって、平和構築を主体的に担っていく現地社会の人材や組織が欠かせない。現地社会の人材や組織を支援することで、平和構築に対する現地社会の主体性を育む。これが国際社会に求められる望ましい平和構築支援の姿である。
この理想型は、紛争後の社会の平和構築支援を担う国連や援助機関に共有されている。実際に、東ティモールに派遣された国連平和維持活動である国連東ティモール統合ミッション(United Nations Integrated Missions in Timor-Leste: UNMIT)や国連開発計画などの国連諸機関、あるいは日本の対東ティモール平和構築支援の中核を担った国際協力機構においても、現地社会の主体性の重要性は認識されていた。
しかしながら、この理想型を実際の支援として形にしていくことは容易ではない。実際には、さまざまな課題があることも事実だ。そもそも、誰が現地社会を代表するのか、新生国家の指導者たちは草の根の人々の声を代弁するのか、といった疑問が次々と浮かぶ。紛争後の選挙で選出された黎明期の政権には、必ずしも十分な正統性が備わっていないこともあれば、平和構築を担っていく実力に欠ける場合もある。現地社会には多様なニーズや異なる利害関係を持った集団や個人が存在する。例えば、紛争によって肉親を失った者、故郷を追われた者、戦後の論功行賞に与った者と溢れた者、利権を得た者と失った者。東ティモールにおいては、インドネシアの軍事侵攻後も現地に踏み止まり抵抗を続けた者から、海外に退避した者までいる。あるいは独立闘争に身を捧げた者もいれば、インドネシア軍による圧制に加担した者もいる。対立する利害関係を本来であれば現地政府が調整すべきである。だが、現地政府にその能力がない場合、多様な利害関係者の誰を現地社会の代表として国際社会は支援していけばよいのか。現地社会の主体性を尊重するという理想を唱導することと、その理想を現実の政策や行動に反映させていくことは、次元の異なる課題であることが多い。
このような課題を理想と現実のギャップとして捉えることも可能だろう。とりわけ、本稿の焦点であるSSRという主権国家の中核的な機能に対して改革のメスを振るう活動の場合には、この理想と現実のギャップは顕在化しやすい。それも単に理想と現実が異なるだけではなく、理想の実現を現実が阻むという意味でのギャップが生じる。現地社会の主体性を尊重すればするほど、SSRの中身が歪められ、必要な改革が骨抜きにされてしまう(こともある)。それによって、SSRによって守られるはずの現地の人々の安全が脅かされる。
東ティモールには、2006年の治安危機を受けて、東ティモール政府によるSSRを支援するという任務をもったUNMITが派遣されていた。しかし、改革の中身や改革への国連の関与に関して、政府側と国連側とでは思惑の違いが明らかであった。ここでは実際に表面化した相違点を4つに絞って紹介する。その前に、2006年の治安危機の概要を簡単に記しておきたい。

2006年の治安危機
事の発端は国軍内部での差別待遇の改善を要求する動きである。不満分子は「陳情兵」と呼ばれ、当初(陳情書の日付は2006年1月9日)の段階では159名の集団であった。同年2月8日の政府庁舎前でのデモ行進に参加した兵士の数は418人にまで膨れ上がっていた。その間、政府は適切な対応を怠り、3月16日にタウン・マタン・ルアク国軍司令官は、駐屯地を離れていた591名(国軍の総数の約半分)を、外遊中だったシャナナ・グスマン大統領の許可なく解雇した。外遊から戻ったグスマン大統領は、あたかも国軍内での東西出身地別の差別待遇があることを認めるような演説を3月23日にしてしまう。これが火に油を注ぐように事態の悪化を招き、東西対立の亀裂が深まる。
その後、解雇された「陳情兵」たちが4月24日〜28日に平和的なデモ行進を実施した。しかし、デモが終盤に差し掛かると非武装で行進していた「陳情兵」の集団に武装した暴徒が乱入し、事態が一気に緊迫化する。この暴動を鎮圧するために、国家警察が投入されたが、暴徒に加勢する警察官も現れたため、マリ・アルカティリ首相の命令で国軍が動員された。この間、民間人に武器が不正に供与され、国軍の一部が暴徒に加わり、国軍が警察署を襲撃して警察官を射殺するなど事態は悪化の一途を辿った。そして、暴動の鎮圧はオーストラリア軍による介入を待たなければならなかった。
政治指導者の責任問題
2006年の治安危機の真相や顛末に対する責任の所在は、いまだに明らかにされていない。もちろん、国内的には、政治的に「決着」がついているし、国連も『独立調査特別委員会報告書(Report of the Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste, S/2006/822, 17 October 2006)』を取りまとめた。結果として、当時の首相、国防大臣、内務大臣、警察長官が辞職に追い込まれ、ロジェリオ・ロバト内務大臣は民間人に武器を不正供与したとして一審で有罪判決を受けた(その後、控訴するとともに病気療養が認められ、刑が確定する前の国外療養中に「恩赦」を受けたため服役はしていない)。
しかし、東ティモール政府による真相の究明は形式的なものにとどまり、裁判には政治的介入がなされた。そして、反乱分子の問題は、2008年の大統領・首相暗殺未遂事件にて首謀者が殺害されるまで解決されなかったのである。当時のルアク国軍司令官は罪に問われず、2012年の大統領選挙に出馬するまで国軍司令官の職に就いていた。そして2012年の大統領選挙での勝利を受け、現在では大統領である。また、恩赦を受けたロバト元内務大臣は2012年に大統領選挙に出馬して16,090票(5位)を獲得した。
2006年の治安危機の背後には、アルカティリ、グスマンといった政治指導者間の権力闘争があったのではないかとする分析がある一方で、国軍と国家警察を巻き込んだ事件の真相は闇に包まれたままである。SSRには司法改革も含まれており、このような国家の屋台骨を揺るがした事件に対する公正な公判の実現が期待されていた。そして、東ティモール政府関係者が事件に関与していたとすれば、司法の中立性を担保し、正義の追求を支援するのが、国連に託された役割であったはずである。しかし、東ティモールの司法当局は真相の解明や正義の追求を十分になし得たとは言いがたい。現地社会の主体性の壁の前に、国連にできることは限られていた。
国軍と国家警察の役割分担
2006年の治安危機後に、国連は東ティモールに対するSSR支援の仕切り直しをした。憲法の規定に則り対外的な脅威への対応を主務とする国軍と国内治安・秩序維持が主務の国家警察との役割分担の明確化が重要である。国連はこう主張した。これは、単に国際的な標準の適用というだけでなく、2006年の治安危機に国軍が安易に動員されたことが事態の悪化につながったという教訓に基づいている。
ところが、東ティモール政府がとった処置は、この国連の主張に真っ向から対立するようなものだった。まず、国軍と国家警察の対立を防ぐために、それぞれを掌握する監督官庁(国防省と内務省)を統合して国防治安省を作り、グスマン首相に国防治安相を兼務させた。さらに、2006年の危機以降の国内治安上の懸案であった反乱分子の掃討作戦を国軍と国家警察の共同作戦という形で実施し、2008年の大統領・首相暗殺未遂事件を経て、この問題を解決した。グテレス治安担当国務長官は「これが東ティモール流の問題解決である」と胸を張った。
つまり、現地政府が主導したSSRは、国軍と国家警察の協力関係の強化と両者の監督機能の統合化であり、国連が思い描いた見取り図とは大きく異なっていたのである。よって、現地政府の主体性は多いに担保された。国連の助言は無視されるという代償とともに。

国家警察の脱政治化
2006年の治安危機を経て国連が学んだもう一つの教訓は、治安部門の政治からの独立を確保することの重要性であった。独立に際して国連の支援で新設された国家警察は、2006年の治安危機では政治からの独立性を確保できていないという事実を露呈した。
国軍も同様に政治の過度の介入を許していたが、国軍に対する支援はポルトガルなどが二国間援助を通じて実施しており、国連の関与は限定的であったと言える。そのため、国軍は改革のメスが十分に届かない「聖域」と化していた。このこと自体もSSRの観点からは深刻な問題であるが、ここでは国家警察に対する改革に絞って議論しよう。
すなわち、国家警察の独立性の問題は、東ティモールの警察官を「プロフェッショナル(職能)化」するという国連の取り組みを通じて解決されることが目指された。東ティモールでは、独立闘争時から連綿と続く政治的な「主従関係」が、特定の政治集団と警察官や「ベテラン」と呼ばれる退役ゲリラ兵との間に存在していた。そのため、2006年の治安危機に際して、警察官らが中立的な法執行機関としての職務を放棄し、特定の政治集団を支持する「ベテラン」組織などの利益集団に合流したことが問題視された。そこで、国連は国家警察から法執行の機能を取り上げ、自らが派遣した国連警察官によって暫定的に法執行を代行させるとともに、現役の警察官に対して一定の研修を施した後に資格審査にかけた。国連の主張は、2006年の過ちを繰り返さないためにも、不適切な警察官は罷免されるべきというものであった。
しかしながら、東ティモール政府は、この国連による努力を否定した。罷免された警察官が失職することや面子を失うことで、治安撹乱要因となることを嫌った東ティモール政府は、国連による審査の結果、不適合の烙印を押された警察官に対しても復職を許したのである。よって、現地政府の主体性は多いに担保されたが、国連の努力は水泡に帰した。東ティモール国民の国家警察に対する信頼が回復したとも言えない。
治安部門の包括的評価
国連がUNMITに与えた任務の一つに、「東ティモール政府が、その治安部門の将来像(役割とニーズ)を包括的に検討することを支援する」ことがあった(国連安保理決議1704号[2006年])。厳密に言えば、UNMITは、まず東ティモール政府による治安部門の包括的評価を支援して、治安部門の何をどのように改革すべきなのかを明らかにすべきであった。
ところが、『評価報告書(Securing the Future)』が公式に出されたのは、UNMITの活動開始から実に5年以上が経過した2011年になってからである。2012年12月にUNMITが東ティモールから撤収したことを考慮すれば、実際にUNMITや国連開発計画を通じて支援されたSSRは、包括的な検討結果に基づいたものではなかったと言っても誤りではない。つまり、国連によるSSR支援が終盤に差し掛かり、UNMITの撤収が目前に控えた時点で、ようやく東ティモール政府は、国連の支援を受けて作成した『評価報告書』の公表に合意したのである。

この『評価報告書』はグスマン首相とラモス・ホルタ大統領によって署名された東ティモール政府刊行物であるにもかかわらず、国語でも公用語でもない英語で執筆され、同時に出されたポルトガル語版とテトゥン語版は英語原本の翻訳版とされた。このことからも分かるように、包括的な検討は終始、国連主導で進められており、国連安保理決議に謳われた現地政府の主体性は形式的なものにとどまった。UNMITに課せられた任務は東ティモール政府による治安部門の包括的な検討を支援することであったため、検討対象が3つの国家治安機関(国家警察、国軍、海上保安庁)に限定されることなく、大統領府や首相府を含む17の関連省庁が検討の俎上に上った。
『評価報告書』の取りまとめを担当した東ティモール政府の省庁は、国家警察を所管とする国防治安省の治安担当国務長官室であり、同室付の顧問によれば、報告書の取りまとめが遅れたのは、国軍(国防担当国務長官の管轄)関連の情報が迅速かつ十分にもたらされなかったからである。東ティモール政府は、国軍に関しては、国連の介入や指図を受けずに独自に改革を検討し、友好国の支援を通じて実施する算段であると国防担当国務長官室付の顧問が証言している。実際に東ティモール政府は、国連が関与しないところで『2020年に向けた国防計画(Force 2020)』を策定し、『評価報告書』に先駆けて公表した。
なお、『評価報告書』遅延の理由をグテレス治安担当国務長官に聞いたところ、「包括的検討は国連の任務であって東ティモール政府の関知するところではない。遅延の理由を聞きたければ私ではなく国連を問いただすべきだ」といった返答がなされた。UNMITの関係者に確認したところ、国連側の認識では、東ティモール政府に治安部門の包括的検討を実施する意思や関心がないことが最大の要因であるとの指摘があった。このような状況に業を煮やした国連の担当官が東ティモール政府の合意を得ずに『評価報告書』を書き上げ、印刷まで手配していたことが、東ティモール政府関係者の心証を悪くして、さらに問題を拗らせた。
国連には、現地社会の主体性を重んじるという建前があるため、現地政府にその気がなければ物事は進まない。この点においても、東ティモールにおいては現地政府の主体性は発揮されたものの、国連の威信は傷つけられた。結局、『評価報告書』はSSRの指針になることは叶わなかったのである。
まとめ
もちろん、現地社会の主体性を尊重する姿勢は単なる理想ではない。実際の平和構築支援が奏功し、持続可能な平和な社会の礎が築かれるために必要な現実的な行動指針でもある。しかし、本稿で検討してきた現地社会の主体性に関わる課題は、東ティモールの政治情勢に固有の問題だとして片付けることはできない。紛争後の社会には、連綿と続く「主従関係」があり、派閥抗争や権力闘争が繰り広げられる中で、SSRを挙行しなくてはならない。本来であれば、幅広く住民の声に耳を傾け、対立する利害を調整しなければばらない現地政府は、ともすると権力闘争に絡みとられ、「主従関係」という国内政治の文脈での正統性が、国際社会が求める民主主義や正義の実現から生まれる正統性に優先されてしまう。現地社会の主体性を尊重することが、平和な社会の基盤づくりにつながるように、そして二つの正統性が重なりあうように支援をしていかなくてはならない。そのためには、「現地社会」の内実を十分に把握し、何が平和な社会の基盤づくりに資するのかを見極めていくことが大切だ。その結果として、現地の特定勢力の意向に屈することなく、粘り強く説得することが必要な場合もあるだろう。このような姿勢が平和構築を支援する外部者には求められる。
-reference 参考文献
上杉勇司・藤重博美・吉崎知典編『平和構築における治安部門改革』(国際書院、2012年)
Sukehiro Hasegawa, Primordial Leadership: Peacebuilding and National Ownership in Timor-Leste, United Nations University Press, 2013

(早稲田大学国際教養学部准教授・沖縄平和協力センター副理事長・広島平和構築人材育成センター副理事)