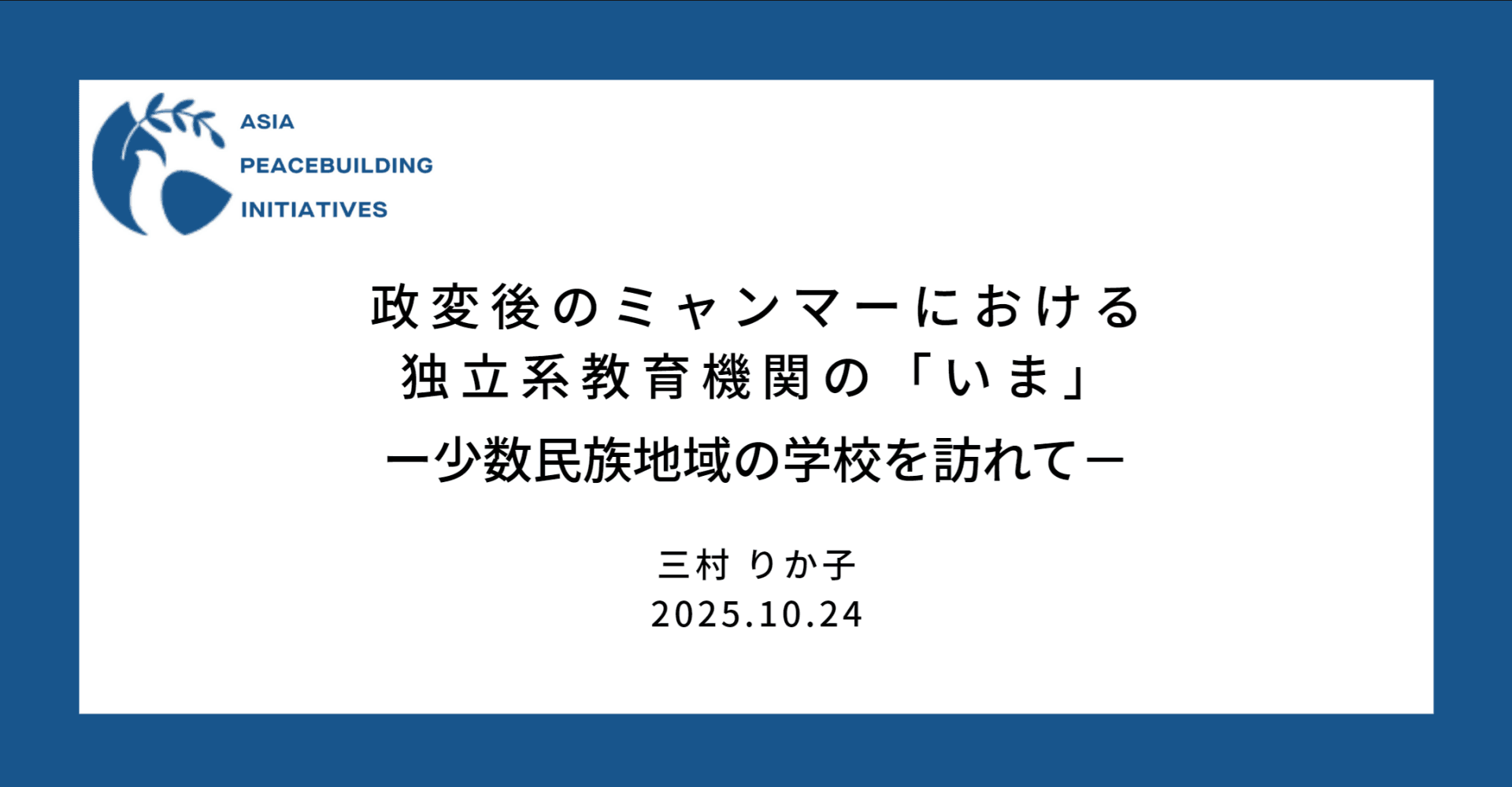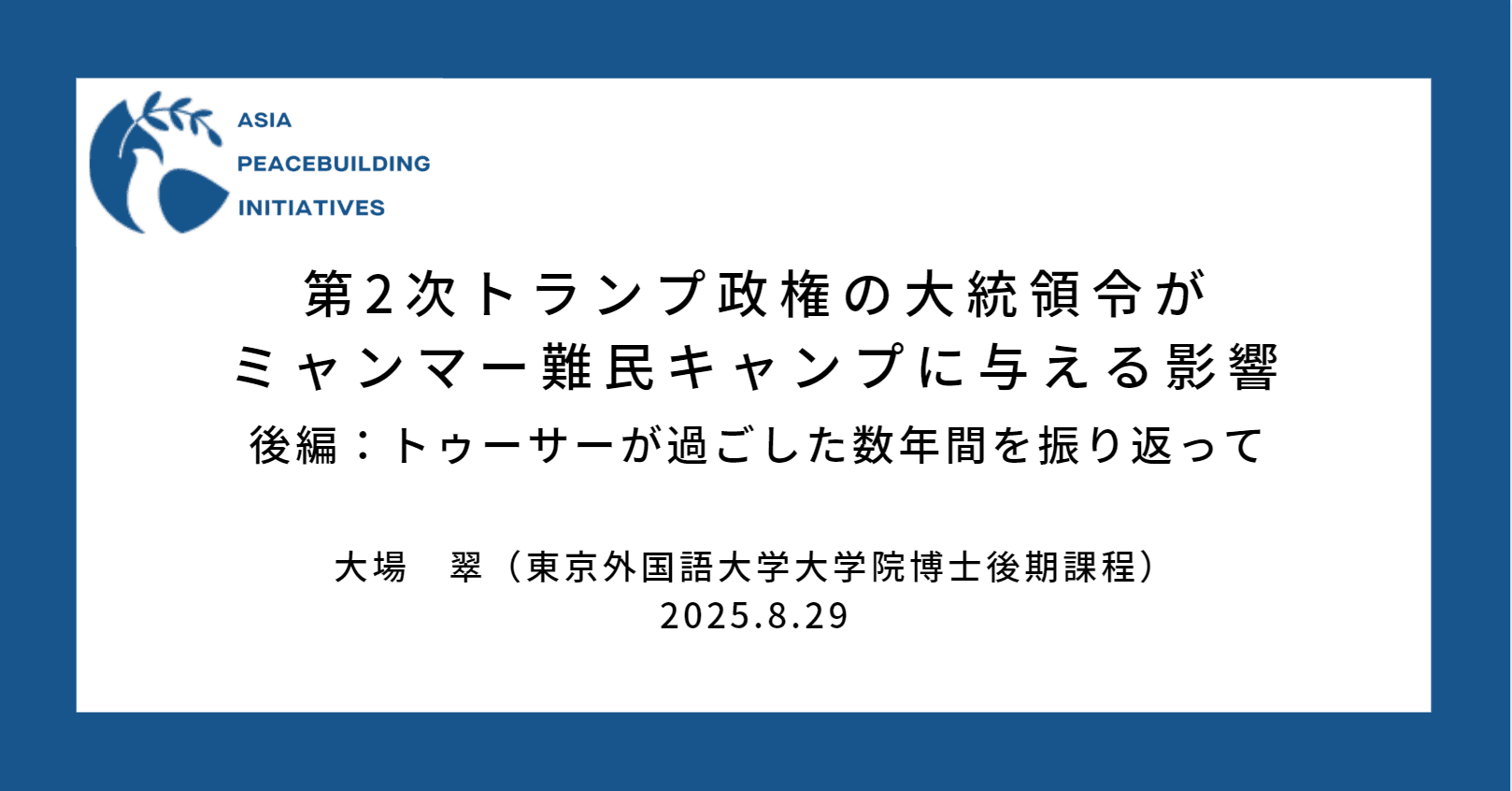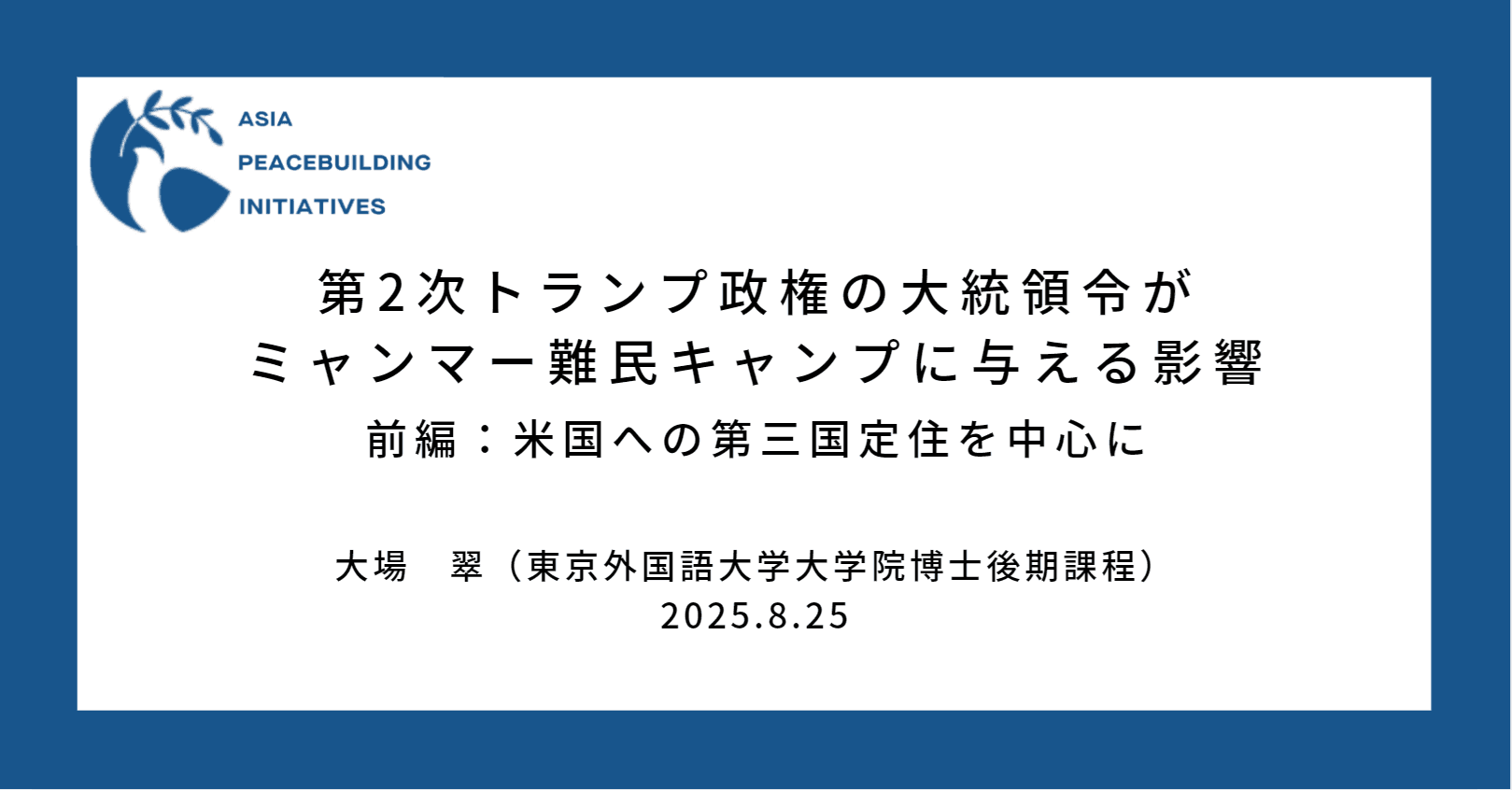- アジアのイスラーム
「デーオバンド派」とは何か-南アジアのイスラーム過激派?

1.はじめに
話題にされることは少ないものの、イスラーム世界にとって南アジアは看過できない存在である。人口で見れば、パキスタンの人口が約1億9600万人(その95%以上がムスリム)、インドのムスリム人口が約1億9000万人(インド総人口13億3800万人に2011年国勢調査の際のムスリム人口比14.2%を掛け合わせた数字)、バングラデシュの人口が約1億6400万人(その約87%がムスリム)であり(以上、各国人口は2017年の推定値)、現在の世界のムスリム総人口を18億(2015年の推定値[Pew Research Center 2015])と仮定すると、この3国だけでもそのムスリム人口の合計(約5億2100万人)は世界のムスリム人口の約3割を占めることになる。
では、その南アジアのムスリムに関して、現在最も話題になることは何だろうか。それはおそらく、パキスタンやバングラデシュで頻発するテロ事件や、かつてアル・カーイダのウサーマ・ビン・ラーディンをかくまったアフガニスタンのターリバーンにまつわるニュースではないだろうか。いずれも「イスラーム過激派」という言葉で語られることの多い問題である。
本章は、南アジアにおける「デーオバンド派」について考えることを通じて、南アジアのイスラームを再考する試みである。「デーオバンド派」という言葉を聞いてピンとくる日本人は少ないだろう。平たく言えば、「デーオバンド派」とは南アジア最大のマドラサ(イスラーム宗教学校)のネットワークを持ち、南アジアのイスラーム解釈において現在最大の影響力を誇るウラマー(イスラーム学者)の流派の名前である。したがって、「デーオバンド派」について考察することを通じて、私たちはある程度、南アジアにおけるイスラームの一般形に触れることができるはずだ。本章の第一の目的は、南アジア・イスラームの最大公約数形の概説である。
しかし残念ながら、「デーオバンド派」の考察は南アジア・イスラームの一般形の話で終わるわけには行かない。なぜなら、多くの南アジアの人々、および欧米などで南アジア政策にかかわっている安全保障の専門家たちにとって、「デーオバンド派」の名前はいわゆる「イスラーム過激派」のイメージと結びついているからである。その理由は主に、アフガニスタンのターリバーンの主要リーダーの多くがパキスタン北部のデーオバンド派マドラサで教育を受けている事実にある。今日、例えば南アジアの知識人と話していても、「デーオバンド派」の語はイスラーム過激思想の代名詞として使われることが多い。
だが、南アジアのムスリムの間で最大の影響力を誇る「デーオバンド派」が過激であるとすれば、それは必然的に南アジアのムスリムの大多数が過激であることを意味することにならないだろうか。常識的に考えるなら、全世界のムスリム人口の約3割を占める南アジア・ムスリムの大多数が過激思想に染まっているとは考えにくい。
「デーオバンド派」の「過激派」的イメージの背景にあるのは、じつは南アジアにおける歴史的過程への誤解・無理解であり、南アジアや欧米を巻き込んだグローバル規模におけるムスリムへの偏見=イスラモフォビア(イスラーム恐怖症)であると筆者は考える。したがって本章の第二の目的は、こうした誤解を解くための「デーオバンド派」をめぐる歴史的過程の概説であり、これを通じて現代世界のイスラモフォビアについて考えてみる試みである。
なお、「デーオバンド派」の名のもとになった有名なマドラサは、アフガニスタンやパキスタンではなく、インドにある。本章はインド北部ウッタル・プラデーシュ州にあるそのデーオバンド学院の訪問記を兼ねている点を、ここで付記しておきたい。

2.インドのムスリム:その多様性
デーオバンド派に触れる前に、まずインド・ムスリムの基本的な性格と多様性について述べておきたい。基本的な背景についての知識がないと、デーオバンド派の性格についても把握しにくいためである。
歴史と分布
インド亜大陸で最初にムスリムとコンタクトを持ったのは、亜大陸西海岸の人々であったと思われる。この海岸部では、アラブ世界がイスラーム化する以前から海路を通じてアラブ人と通商・交易があり、イスラーム出現後いち早くムスリムと交渉を持ったのは自然な流れだった。
インド亜大陸で最初にムスリムの支配下に入ったのは、亜大陸最西部、現パキスタン南部のスィンド地方である(8世紀初頭にアラブ人によって征服)。トルコ~アフガン系ムスリムが中央アジアから北インド各地へ侵入するようになったのは11世紀初頭以降のことで、彼らが北インドで覇権を確立したのは13世紀初頭のことだった。14世紀以降は中央~南インドでもムスリム王朝が誕生した。インド亜大陸におけるムスリム支配のピークは16~17世紀のムガル帝国最盛期であり、南インドの一部を除く亜大陸全土がその支配下に入った。
以上のような経緯から、インド亜大陸にはトルコ系、アフガン系、アラブ系、ペルシア系など数多くのムスリムが渡来・定住したわけだが、現在のムスリムの圧倒的大多数は在来インド人改宗者の子孫である。
現在のインドの中でムスリム人口が多いのは、北部(ウッタル・プラデーシュ州3848万、西ベンガル州2465万、ビハール州1756万、アッサム州1068万、ジャンムー・カシミール州857万)、中西部(マハーラーシュトラ州1297万)、南部(ケーララ州887万、アーンドラ・プラデーシュ州808万、カルナータカ州789万)である(以上、2011年国勢調査より、ムスリム人口が7百万以上の州)。やはり圧倒的に北部のムスリム人口が多いのは上述の歴史的経緯からも想像がつくところだが(インド亜大陸北部のムスリム集住地域は1947年にパキスタンとしてインドから分離独立し、東パキスタンは1971年にバングラデシュとしてパキスタンから分離独立している)、ムスリム王朝が点在していた経緯からインド中~南部にも一定のムスリム人口があり、南インドの西海岸部には古くからの海路を通じたアラブとの交流の痕跡を残すムスリム・コミュニティーが多数存在している。

スンニー派とシーア派
ここで、インドのムスリム内部における多様性に話題を移そう。
まず、よく知られているスンニー派とシーア派の区別に言及しておきたい。ご存知のように、多数派(のちにスンニー派と呼ばれる)に抗し、預言者ムハンマドの権威はムハンマドの従弟かつ娘婿のアリー(スンニー派では第4代カリフ、シーア派では初代イマーム)とその子孫に継承されるとしたのがシーア派である。
インドのムスリムの中でシーア派が占める割合についての正確なデータは存在しないが、米国のシンクタンクの推定では、インド・パキスタンともにそのムスリム人口の10~15%がシーア派に属している[Pew Research Center 2009]。この仮定に従えば、インド・パキスタンには全世界のシーア派ムスリム人口の2~3割が住んでいる計算になり、南アジアではスンニー派が主流であるとはいえ、シーア派の存在も無視できないことがわかる。
歴史的には、シーア派もペルシア文化とともに多様なかたちで南アジア各地へ流入したと考えられるが、現在のインドのシーア派に直接つながるのは、18~19世紀の北インドにシーア派を奉ずるアワド王国が存在した事実である。このため、かつてアワド王国の首都だったラクナウー(現ウッタル・プラデーシュ州都)はシーア派文化の名残りをとどめ、多数のシーア派人口を擁することで知られる。
なお、シーア派の中にもいくつか流派があり、南アジアのシーア派の主流はイランやイラクの主流と同じ十二イマーム派だが、インド・パキスタンにはシーア派の少数派であるイスマーイール派の重要なコミュニティー(ホージャー、ボーホラー等)がいくつか存在することが知られている。
ここで、南アジアにおけるシーア派文化の特殊な位置について述べておかなければならない。
シーア派においては、カルバラー(現イラク領)の戦いにおけるフサイン(アリーと預言者ムハンマドの娘ファーティマの間に生まれた次男、第3代イマーム)の殉教が大きな意味を持ち、この殉教を哀悼するためのアーシューラー祭はシーア派最大の年中行事となっている。この祭の最中、鎖などを自らの体に叩きつけ、半裸で血を流しながら哀悼の行進をするシーア派男性たちの姿については、見覚えのある読者もおられるのではないだろうか。この祭は南アジアでは、これが開催されるイスラーム暦1月の名をとって「ムハッラム」と呼ばれるが、ムハッラム祭は歴史的に南アジアでは多くのヒンドゥー教徒によっても祝われてきた。南アジアでは、ちょうど(ヒンドゥー教の神格である)ラーム神やクリシュナ神がムスリム庶民の間でも信仰されていたのと同様に、フサイン殉教の伝説はヒンドゥー教徒の間にも広く伝わっていたのである。
例えば、筆者が住んでいたインド北部ジャンムー・カシミール州のジャンムー地方には「フサイニー・ブラフマン」と呼ばれるヒンドゥー教徒のコミュニティーが存在し、その祖先がカルバラーの戦いに参加したという伝承を持っているのだが、このコミュニティーがジャンムーのヒンドゥー社会の最上位に位置付けられている事実からも、地域によってはフサイン伝説がヒンドゥー教徒にとっても大きな意味を持っていたことが窺える。
この他、パンジャーブ州を中心に広くみられる5聖者(パーンチ・ピール)のモニュメントも、その源の一つはシーア派に一般的な5聖人(預言者ムハンマド、アリー、ファーティマ、アリーとファーティマの長男ハサン、次男フサイン)の考え方にあると思われる。また、シーア派には危機に際しての信仰秘匿(タキーヤ)の伝統があるが、例えばインド北西部ラージャスターン州を中心にみられるラームデーヴ神(一般にはヒンドゥー教の神格であるとされる)の信者たちは、元来はタキーヤの状態に入ったイスマーイール派(ニザール派)の信仰結社だった可能性が指摘されている[Khan 2003]。このように、インド亜大陸の文化にはシーア派の痕跡が多様なかたちで残っている。
南アジアにおけるシーア派が現行の明確なアイデンティティーを持つようになったのは18~19世紀のアワド王国の時代だったことが近年の研究により明らかになっているが[Jones 2012]、それ以前のいわゆるシーア派が南アジアでどのようなかたちで存在したのかについては、再考の余地があると思われる。
なお、スンニー派についても一言触れておくと、スンニー派内部の区別でよく知られているのは4法学派(ハナフィー、マーリク、シャーフィイー、ハンバル)の区別だが、南アジアのスンニー派ムスリムは、アラブの影響が濃い南インド西海岸部のムスリムの一部がシャーフィイー法学派を奉じているほかはハナフィー法学派に属する。大ざっぱに、ハナフィー法学派はより柔軟に現実問題に対処する傾向を持ち、シャーフィイー法学派は(ハンバル法学派ほどではないにせよ)コーランや預言者言行録により忠実な法解釈をする傾向があると言われる。

スーフィズム
さて、スンニー派とシーア派の区別とも関係するムスリム内部の多様性の源として、スーフィズムについても述べておかなければならない。
「スーフィズム」の語はしばしば「イスラーム神秘主義」と訳されるが、その語源である「スーフィー」を一言でいえば、修行によってアッラーの神性の中へ自己が消滅する境地(ファナー)を目指すムスリム求道者のことである。南アジアの文脈でいえば、この修行の過程はヒンドゥー教の修行・瞑想の過程に類似しており、実際に両者は歴史的に互いに影響し合った部分もあったと思われる。
概してスーフィズムは、イスラーム法学の外面性に飽き足らないムスリムたちの内面的な探求にかかわっているため、イスラーム法学に依拠する権威・権力と対立する契機を秘めている。実際のスーフィズムは聖者やその墓廟(聖者廟)への庶民的な信仰を含んでいることが多いが、修行法のさまざまな道統(タリーカ)は事実上の諸教団の組織へとつながり、場合によってはこうしたスーフィー教団が強大な武力と政治力を持つこともあった。
南アジアで活動してきた主なスーフィー教団には、ラージャスターン州アジュメールにある聖者ムイーヌッディーン・チシュティー(12~13世紀)の墓廟やデリーにある聖者ニザームッディーン・アウリヤー(13~14世紀)の墓廟で知られるチシュティー教団のほか、スフラワルディー教団、カーディリー教団、ナクシュバンディー教団などがある。とくにアジュメールやデリーのチシュティー聖者廟は、ムスリムだけでなく多くのヒンドゥー教徒の信仰をも集めることで知られる。
南アジアのムスリムの多くは、外来のムスリム侵略者・支配者による強制的な改宗よりはむしろ、交易のあったムスリム商人たちの影響や、庶民から篤く信仰されたこうしたスーフィー聖者/聖者廟の影響で改宗しムスリムになったものと考えられているが、南アジアにおけるスーフィズムの歴史的役割はそれほど大きかったわけである。
注意する必要があるのは、こうしたスーフィズムの考え方は、預言者ムハンマドおよびアリーの子孫に聖性を見るシーア派の考え方や、(上述のような)ある種のヒンドゥー教の考え方と相通ずるところがあり、スーフィズム/シーア派/ヒンドゥー教の境界は南アジアにおいては歴史的に必ずしも明確ではないという事実である。

カースト制度
以上のような南アジアの土壌の上に19世紀後半、デーオバンド派をはじめとするスンニー派イスラーム内部のさまざまな流派が成立するわけだが、これについては次項で述べるとして、ここではインド/南アジアのムスリム内部の多様性を形作る要素として、最後にカーストの問題に触れておきたい。世襲の職業の区別などによって身分差別を行う、あのカースト制度である。
神の前の平等をモットーとするイスラームとカースト制度は相容れないように見えるが、実際には南アジアのムスリムの間にも、ヒンドゥー教徒の場合とほぼ同じカーストの区別が存在する(南アジアではスィク教徒やキリスト教徒の間にもカーストの区別が存在する)。
ムスリム内部のカースト大別のためのカテゴリーとしては、「アシュラーフ」(アラブ系、ペルシア系、トルコ系、アフガン系など外来ムスリムの血を引くとされる高カースト・ムスリムの総称)、「アジュラーフ」(在来インド人改宗者の子孫である低カースト・ムスリムの総称)、「アルザル」(ヒンドゥー教徒のいわゆる不可触民=ダリトに相当する最下層・被差別ムスリムの総称)の区別が知られている。ただし、この大別法は1990年代に開始された低カースト・ムスリムの運動で用いられ一定の認知を得るようになったものの、もとはインド東部ベンガル地方とその周辺のみで知られていた大別法であり、ヒンドゥー教徒の4ヴァルナ(バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ〔および不可触民〕)の大別法と同じで、必ずしも南アジアのムスリム社会の現実を正確に反映しているわけではない。
実際に機能しているのは、これもヒンドゥー教徒の場合と同じで、より小さな単位であるジャーティ(ザートもしくはビラーダリーとも呼ばれる)のほうである。ドービー(洗濯業)、ローハール(鍛冶屋)、クレーシー(肉屋、屠殺業)といった、主に伝統的に携わる職業によって区別された諸集団がこれに当たり、その多くはヒンドゥー教徒の間にも同名・同職の集団がある(この事実から、これらのムスリムは改宗後も自らのカーストの軛から逃れられなかったことが分かる)。なお、筆者がウッタル・プラデーシュ州で見聞した「シェイク・スィッディーキー」のように、表向きは「シェイク」(またはシェイフ、アラビア語のシャイフ)という外来ムスリムの血統を表す名を掲げ、都市の富裕層を含んでいるものの、同時に農村部の明らかに貧しい集団をもそのカテゴリー内に含んでいるような例もあり、各ジャーティ集団の内実は複雑である。
インドには低カースト層の状況改善のための留保制度があり、州ごとに低カーストの人々が公立機関において優先的に就職・入学できる留保枠を設けているが、ムスリムとキリスト教徒は指定カースト・指定部族(Scheduled Caste、Scheduled Tribe)の対象外であり、この優遇措置を受けることはできない。ただし、1993年から低カースト・ムスリム諸集団も「その他の後進階級」(Other Backward Classes、OBC)のカテゴリーに含まれることになり、OBC留保枠を使って各種の優遇措置を受けられるようになった。
インドで各種議員などの要職に就くムスリムの大多数はいまだに(絶対数で見れば少数派であるところの)高カースト・ムスリムであるため、1990年代に声を挙げ始めた低カースト・ムスリムたちはこの状況の是正を目指し、低カースト・ムスリムも指定カーストのカテゴリーに入れるよう要求している。
インドでは政治活動に専念するムスリム団体はほとんど存在せず、ムスリムの政治的要求はムスリム宗教団体が出すのが通例となっているが、概して高カースト・ムスリムの支配下にあるムスリム諸宗教団体は、これまでムスリム全体が貧しいことを理由に各種の政治的交渉に当たり、また利益を得てきた経緯から、当初は低カースト・ムスリムによる独自の政治活動および彼らの指定カースト要求に否定的だった。しかしこれらのムスリム宗教団体も、絶対数ではインド・ムスリムの圧倒的多数派である低カースト・ムスリムの要求を無視し続けるわけにはいかず、近年は低カースト・ムスリムの指定カースト要求を支持するようになった。

3.デーオバンド派の登場とスンニー派の諸流派
デーオバンド派の登場の背景には、19世紀後半の南アジアにおけるいわゆる「イスラームの危機」があった。
南アジアにおけるムスリムの覇権は17世紀のムガル帝国最盛期に頂点を迎えたが、18世紀に入るとムガル帝国の勢いに陰りが見え始め、19世紀には南アジアにおける実質的な権力はイギリス(東インド会社)の手に渡っていた。巻き返しを図る一部ムスリムの野望も1857年のインド大反乱の失敗で潰え、翌1858年、イギリスが東インド会社を通じた間接統治を解消しインドの直接統治に乗り出したため、それまで名目上は存続していたムガル帝国はついに完全に姿を消すこととなった。
南アジアにおけるイスラームは、このときまでは政権や法廷の運営にかかわる知識のほか、現在では「科学」の領域に入るさまざまな実用的な知識をも含む包括的な知識の体系として機能していた。しかし、イギリスに政権と法律の運用権を奪われ、知識面でも西欧自然科学の台頭をみた19世紀後半、南アジアのイスラームは「宗教」として再編することを余儀なくされた。デーオバンド派をはじめとする、「宗教としてのスンニー派イスラーム」内部の各流派が生まれたのはこのときである。
それまでは官僚養成機関だったマドラサ(イスラームの学校)はいったん機能停止し、ムスリムのアイデンティティーとしての「宗教」の知識を継承しこれを守るための「宗教学校」として再出発することとなった。運営も、それまでのように政府(ムスリム諸王朝)や封建領主などの政治権力に依存するのではなく、一般市民からの寄付金で賄う形態に移行した。
こうした変革の中心となったのが、1866年に北インド(現ウッタル・プラデーシュ州北部)の小都市デーオバンドに建設されたマドラサである(正式名称は「ダール・ウル・ウルーム・デーオバンド」、直訳すると「デーオバンド知識センター」、本稿では以下「デーオバンド学院」と略記。「ダール・ウル・ウルーム」は大学に相当する大規模なマドラサに付けられる名称)。以降、デーオバンド学院は南アジアにおける「イスラームという宗教の専門家」としてのウラマー(イスラーム〔法〕学者・知識人)養成の中心となり、その影響下にある各地のマドラサやウラマーを総称して「デーオバンド派」と呼ぶようになった。
デーオバンド学院開設の背景には当然ながら、イスラームの危機に際し、より純粋かつ正統なイスラームを継承し世に広めたいという意思が働いており、これが例えば、今日デーオバンド派の特徴の一つと考えられている聖者廟信仰否定の姿勢へとつながり、のちのピューリタン的なデーオバンド派のイメージをもたらすことになった。
なお、デーオバンド派はスーフィズムそのものを否定したわけではなく、歴史的にデーオバンド派は、師から弟子への口述直伝に依拠するスーフィズムの内面的修行を重視し、自らも優れたスーフィーだったウラマーを多数含んでいる。

デーオバンド派が登場した19世紀後半の南アジアでは、他にもいくつかのスンニー派イスラームの流派が登場した。以下、各流派についてその特徴を簡単に踏まえつつ概観してみよう。
まず、デーオバンド派とよく対置されるのが、アフマド・リザー・カーン(1856~1921)を指導者として1880年代に勃興したバレールヴィー派である。バレールヴィー派は聖者廟信仰を肯定し、預言者ムハンマドの聖性(すなわち預言者自身を信仰・崇拝の対象とすること)を認めたため、デーオバンド派と鋭く対立した。
この対立の構図がのちに「穏健で寛容な」バレールヴィー派と「過激で原理主義的な」デーオバンド派というイメージに結びついていくことになるのだが、例えば近年のパキスタンでアッラー冒瀆の嫌疑によるキリスト教徒女性の死刑に反対した世俗派政治家が暗殺された事件をめぐって、暗殺者のほうを殉教者として英雄視し擁護するデモを主に組織したのはバレールヴィー派だったりもするので、この単純なイメージは必ずしも現実に即しているわけではない。なお法学的にはバレールヴィー派もデーオバンド派同様、ハナフィー法学派に属する。
19世紀後半に登場したスンニー派のもう一つの重要な流派がアフレ・ハディースである。「アフレ・ハディース」は「ハディースの徒」の意味で、この流派/団体はスンニー派の4法学派の伝統を否定し、コーランとハディース(預言者言行録)に直接基づく法解釈を行う。この意味でアフレ・ハディースはサウジアラビアのワッハーブ主義に近く、デーオバンド派よりよほど原理主義的である。
以上が南アジアにおけるスンニー派ウラマーの3大流派だが、19世紀後半にはこの他、西欧自然科学の考え方を採り入れたイスラーム改革を目指したアリーガル運動も勃興し、南アジアのムスリム知識人に大きな影響を与えた。
現在の南アジアでは上記の諸流派に加え、20世紀に登場したイスラーム党(ジャマーアテ・イスラーミー)も大きな勢力となっているので、ここで述べておきたい。
イスラーム党は、もとはジャーナリストだったマウドゥーディー(1903~79)が1941年に結成した団体で、神を主権者とするイスラーム国家の樹立を目指すことで知られる。法学的には折衷的だが、ウラマーの権威には否定的だった。印パ分離独立後、マウドゥーディーはパキスタンに移住し、イスラーム党も印パの二つに分かれた。
イスラーム国家樹立を目指すその主張のため、独立後のインドでメディアから「イスラーム原理主義」の代名詞とみなされたのがこのイスラーム党だった。実際のインド・イスラーム党は1960年代に方向転換し、インドにおけるセキュラリズム(世俗主義)と多宗教共存を擁護するようになったのだが、それ以降も以前の強烈な主張の印象から原理主義の代表とみなされ続けた。
1990年代以降のインドでイスラーム党に代わって「イスラーム原理主義」の象徴とみなされるようになったのが、イスラーム党から派生するかたちで1977年に結成されたインド学生イスラーム運動(Students’ Islamic Movement of India、以下SIMI)である。その後イスラーム党と袂を分かったSIMIはとくに1990年代、いわゆるヒンドゥー至上主義に対するジハード(聖戦)を唱え、2001年にインド政府によって活動を禁止された。実際にSIMIがテロ行為にかかわった形跡はないにもかかわらず、インドではテロ事件が起きるたびにSIMIメンバーが逮捕され拷問を受けるという事態が続いた。
なお、イスラーム党同様20世紀の南アジアに登場し、現在グローバルにイスラーム布教活動を繰り広げるタブリーギー・ジャマーアト(直訳すると「布教組織」)は、教義的にはデーオバンド派に属し、間接的にデーオバンド派の勢力拡大に貢献している。この組織は上記の諸流派と異なり、主に布教活動のネットワークとして存在し、マドラサ運営などは行っていない。
現在筆者の手元には、インドについての資料はないものの、2002年のパキスタンにおける各流派のマドラサ数のデータがあるので、一つの目安として本節の最後にこれを提示しておこう。
デーオバンド派マドラサ:7,000
バレールヴィー派マドラサ:1,585
イスラーム党経営のマドラサ:500
シーア派のマドラサ:419
アフレ・ハディースのマドラサ:376
合計:9,880[Rahman 2008: 64]
このデータを見ると、少なくともパキスタンでは圧倒的にデーオバンド派のマドラサが多いことが分かる。

4.デーオバンド訪問
デーオバンドへの道程
デーオバンドの町はインドの首都ニューデリーから北東に約150キロの地点にある。
ウッタル・プラデーシュ州最北部のサハーランプル郡南部に位置するこの小さな町は鉄道でニューデリーとつながっている。ニューデリーから赴くには、インドには珍しく冷房とサービスの行き届いたデヘラードゥーン行特急に3時間ほど揺られてまず近郊の町ムザッファルナガルの駅まで行き、ここで各駅停車の鈍行に乗り換えて数駅でたどり着くという段取りである。
ウッタル・プラデーシュ州西部のこの一帯では商品作物としてのサトウキビの栽培が盛んで、デーオバンド駅のすぐ隣には巨大な製糖工場がそびえ立っている。なお、デーオバンドに鉄道が開通したのは、デーオバンド学院開設の翌々年(1868年)のことである。
デーオバンドの町の南西に位置する駅から、この町の中心に陣取るデーオバンド学院まで、オートリクシャで20分ほど。この古都に大きな道路は通っていないので、リクシャは曲がりくねった細い路地を、人やバイクをよけながらゆっくり進んで行く。
現在のこの町はデーオバンド学院を中心に機能しており、デーオバンド学院が存在するがゆえに、他にも多数の大小のマドラサがこの町に居を構えている。こうした状況から、イスラームを学ぶ学生が多いため、デーオバンド学院の周辺には書店が密集し、北インドでも有数のウルドゥー語書店街を形成している(むろんここではアラビア語などの書籍も多数扱っている)。2011年現在、町の人口は約9万7千で、その約71%がムスリム、約28%がヒンドゥー教徒である。

典型的なカスバ
デーオバンドの町は、典型的な北インドのカスバである。
「カスバ」(qasbah, qasba)はアラビア語起源の言葉で、一般にはアラブ圏北アフリカ(とくにアルジェリア)の城塞都市を指すことが多い。わが国の演歌の有名曲「カスバの女」(大高ひさを作詞、久我山明作曲、1955年発表、1967年にリバイバルヒット)も、フランス映画『望郷』(1937年)に登場したアルジェリアの首都アルジェのカスバを想定して作られている(アルジェの「カスバ」は、もとの城塞の周辺に形成された旧市街地全体を指す言葉となっている)。
南アジアの文脈では、「カスバ」の語の意味合いはやや異なる。アラビア語よりむしろペルシア語・トルコ語の伝統を汲む南アジアの「カスバ」はとくに城塞を含意せず、「村以上、町以下」の集落単位を表す。単に村と町の中間的集落であれば「カスバ」と呼ばれるわけではなく、文化的に「カスバ」を特徴づけているのが南アジア・ムスリム独自の伝統である。
すでに述べたように、デリーの地にムスリム王朝が誕生したのは13世紀初頭のことだが、以来19世紀まで続くことになる北インドのムスリム諸王朝にとって、行政・徴税ネットワークの末端の拠点となったのがこれらカスバだった。したがって北インド各地のカスバの起源はこの13世紀頃にさかのぼる場合が多いが、実際に「カスバ」の語が用いられ、その存在と性格が明確になって来たのはムガル帝国期(1526~1857)のことである。高カースト・ムスリムのいわゆるザミーンダール(土地所有者=地主にして帝国への納税担当者)が居住し、一定規模の市場を有し、由緒あるモスクやスーフィー聖者廟を擁し、その周囲に徴税免除地(ムスリムの知識人、官吏、スーフィーなどに対してムガル帝国が与えた土地で、これがカスバを拠点とするムスリム有力者・知識層の経済的基盤となった)が点在するというのが北インドの典型的なカスバのイメージだ。カスバはマドラサや(イギリス植民期の政府系)学校を擁することが多く、伝統的に高い知的水準を誇ったそのムスリム知識層は独自の家系譜や史書・伝記を持ち、規模の大きい町よりも緊密な人的ネットワークに支えられ、北インド・ムスリム文化の基盤を形成していたといわれる。[Rahman 2015]
デーオバンドも北インドの数あるカスバのうちの一つであり、13世紀にはすでに幾人かの著名なムスリムがここに住んでいたことが知られている。町のあちこちに点在するモスクのうち、古いものは16世紀初頭までさかのぼる。ムガル時代の史書にはデーオバンドに煉瓦造りの城塞が存在したとの記述があるが、これを彷彿とさせるような煉瓦造りの大小の建築物や廃墟が今も町のいたる所にみられ、訪れる者を歴史の夢想へといざなう。ムガル帝国の凋落とともにこの町もいったん衰退したといわれるが、1857年インド大反乱の際はこの町からも多くのムスリムが反乱に参加し、反乱鎮圧後には34名の町民が処刑された。なお、デーオバンド学院創立にかかわったウラマーの多くもこの大反乱に参戦している。

デーオバンド学院の門をたたく
典型的なカスバであるとはいえ、現在のデーオバンドの街並みとそこに集う店々は北インドの一般的なそれから大きく異なるわけではない。デーオバンド学院が近づくにつれ、周囲に書店が目につくようになり、食堂もムスリム向けの肉料理を扱う店が増えるという程度である。
現在のデーオバンド学院は500メートル四方ほどの敷地に広がっており、外側を高い建物で囲み内側にさらなる建物と中庭が広がる北インドのマドラサに典型的な様式で建てられている。デーオバンド学院の場合、敷地中央にドームを戴くメインの校舎が位置し、その周囲に他の校舎・オフィス、そして敷地を囲う外枠の建物の北半分が学生寮となっている。正門は敷地の南側中央に位置し、正門を出てさらに南へ進むと、この学院発祥の地であるチャッタ・モスクが建っている。敷地の北側にはタージマハルを模して近年建てられた壮麗なラシード・モスクがそびえ立つ(このモスクでは授業の一部も行われる)。
私がデーオバンド学院に着いたのはお昼少し前で、オフィスは休憩時間に入っていたため、正門外の南東に位置する学院付きゲストハウスにまず通された。
部屋をあてがわれ、休憩した後で昼食をゲストハウスの他の客人たちとともにいただいた。客人のほとんどは一時滞在の学生で、皆だぶだぶのズボンの上に膝まであるゆったりとした上着を羽織るシャルワール・カミーズを着ていた(シャルワール・カミーズは20世紀初頭以降の南アジアでムスリムの伝統衣装とされてきた。マドラサの学生の場合、白色の地味なものを着ることが多い)。この日はたまたま月に数回出るというビリヤーニー(肉の炊き込みご飯)の日で、広間に敷いた長い布(ダスタルカーンと呼ばれる、食事を置くための布)を皆とともに囲み、この特別メニューの恩恵に浴した。南アジアの炊き込みご飯に特有の、さまざまな香辛料に由来する芳香があたりを覆い、食欲をそそった。おかわり自由で、皆ずいぶんよく食べていた。
食事を終え、あらためて学院へ赴くと、取材するにはまず責任者の許可が必要だということで、学長のオフィスに通された。学長付秘書のオフィスは西洋式で机に椅子の様式だったが、学長のオフィスは四方にクッションが並べられた絨毯張りの床にじかに座るインド様式で、昔の日本の文人よろしく小さな書き物机を前にあぐらをかいて座った学長は、その周囲に座り込んだ訪問者集団と何やら談判中だった。その集団が立つのを待って、学長にこの学院の概要を知るために見学させてほしいと申し出ると、喜んで許可してくれた。ただし学生をはじめとする人物の写真撮影は(イスラームの教えに反するため)禁止とのことだった。
私の案内役は、初老の学院幹部らしき方が引き受けてくれた。杖をつきながら、気さくな口調で主な校舎やラシード・モスク、図書館、学院付き書店などを案内・解説してくれた。ひと通り見学し終えたところで、この先の質問や詳細についての解説は英語ができる係員(学院のウェブ担当者)にしてもらったほうが良いだろうということで、学院のウェブサイト・広報関係オフィスに連れて行ってくれた。解説はウルドゥー語でも構わなかったのだが、たしかに英語ができるような人のほうが柔軟に対応してくれる可能性が高かったので、言われるまま従うことにした。
ウェブ担当の若い係員は、この学院らしく豊かな髭を蓄えていたが、予想通り融通の利く方で、細かい質問に丁寧に答えてくれたほか、本人の写真撮影もOKしてくれた。ずいぶん垢抜けた感じの方だったが、やはりこの学院の卒業生だとのことだった。
教室については、勉強の邪魔をしてはいけないと思い、とくに見学を希望しなかったのだが、中央校舎一階の大教室で行われている授業の光景を垣間見ることが出来た。豊かな髭を蓄えた講師の口述講義を、大勢の学生が熱心に聞き入っていた。教室は一般のインドの大学におけるものと大差なく、多くの椅子付き長机が教卓前に並び、学生たちがそこにひしめくように座り、高い天井からはファンが静かに涼風を送り続けているというものだった。マドラサの授業は、より小さい教室で教師も学生も床にじかに座るかたちで行うのが常なので、この大教室の光景は、マドラサとしてはあまり一般的なものではない。さすが大学級のマドラサというべきだろう。そして、学生たちの熱気と張りつめた空気からは、デーオバンド派の最高学府で学ぶ喜びと誇りが感じられる気がした。

5.デーオバンド学院:その教育の内実
デーオバンド学院の概要
2016年8月現在、デーオバンド学院で学ぶ学生は4,704名、教員は95名(事務スタッフを除く)である。学生は外国人留学生を含み、現在は20余名のアフガニスタン人の他、ミャンマー、ネパール、スリランカ、フィジー、南アフリカ、キルギスタンなどからそれぞれ数名ずつの留学生がここで勉強している(かつてはアメリカやカナダの学生も在籍したそうである)。2014年度の予算は約2億5千万ルピー(約5億円)とのこと。
この学院は、数あるデーオバンド派マドラサの総本山としての性格も持っている。この学院の管轄下にある全インド・アラビア語マドラサ連絡会に加盟しているマドラサだけで現在2,963校を数えるが、その他の雑多な関連マドラサを含めると、この学院傘下のマドラサ数はさらに膨れ上がるだろう。以上はあくまでインド国内の話であり、これに前述パキスタンのデーオバンド派マドラサ約7千を始め、東南アジア諸国、東~南アフリカ諸国、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等のデーオバンド系マドラサを加えると、はじめてデーオバンド派のグローバルなネットワークの全容が見えてくるわけである。
この学院のメインコースは8年間のアーリム養成コースである(「アーリム」は「ウラマー」の単数形)。このコースを修了すると、大学の学士(B.A.)に相当する学位が授与される。アジア中に名声がとどろくこの学院の学位は大変権威のあるものらしく、各種マドラサなどへの就職にも大いに役立つという。
この学院では、アーリム養成コースの他に、幼少年向けのコーラン学習コースと、アーリム養成コース修了者のための各種特別コース(それぞれ1~2年間)を設けている。幼少年向けコースには、コーラン黙読、コーラン暗記の各コース(期間は生徒ごとに異なる)の他、5年間のウルドゥー語・アラビア語によるコーラン朗読コース(これを修了すると「カーリー=朗読者」の称号が与えられる)がある。(アーリム養成コース修了者のための特別コースについては後述。)
なお、以上の教育プログラムはすべて男性を対象としており、デーオバンド学院に女生徒は存在しない。女性向け教育を行うデーオバンド派マドラサもないわけではないようだが、女性教育はあきらかにデーオバンド派の今後の最大の課題の一つである。

南アジアのマドラサにおけるカリキュラム
歴史的に、南アジアのマドラサで教えられてきたのは主に次のような科目である。
文法:語源学(ṣarf)
文法:統語学(naḥv)
論理学(man t̤iq)
哲学(falsafah)
数学(riyā ẓī)
天文学(hai’at)
薬学(t̤ib)
修辞・弁論(balāghat)
文学(adab)
法学(fiqh)
法源学(u ṣūl-e-fiqh)
神学/イスラーム哲学(kalām)
コーラン読解(tafsīr)
預言者言行録(ḥadīs)
スーフィズム(ta ṣawwuf)
霊的道程学(sulūk)
これら諸科目のうちで重視される科目は、時代によって推移したことが知られている。北インドにムスリム王朝が成立した当初は法学・法源学が重視され、ムガル帝国時代になってペルシア系文化の影響が強まると論理学や哲学が重視されるといった具合である。
現在の南アジアのマドラサにおけるカリキュラムの基本を作ったのは、ラクナウーのファランギー・マハル学院で教鞭をとったムッラー・ニザームッディーン・サハールヴィー(1679~1748)である。彼が作ったカリキュラムはその名にちなんで「ニザーミー方式」(Dars-e-Ni z̤āmī、直訳すると「ニザームの授業」)と呼ばれる。その最大の特徴は、特定科目における習熟が得られない代わりに、学習者個々人が自らの志向に沿って自習することを可能にする基本的理解力を全教科にわたってまんべんなく与える点にあるといわれる。この時代のマドラサには官僚養成の目的があったことから、このカリキュラムではどちらかと言えばコーランや預言者言行録よりも論理学、哲学、数学といった実学的な教科を重視する傾向があった。なお、「ニザーミー方式」は上記諸科目のうち、薬学、文学、スーフィズム、霊的道程学を含まない。[Fyzee 2008; Malik 2008; Metcalf 2002; Rizvi 1981]
用いるテキストに違いこそあれ、デーオバンド派もバレールヴィー派も、カリキュラムの基本はこの「ニザーミー方式」なのである。次項で確認するように、デーオバンド派ではこのカリキュラムに則りつつ、預言者言行録(ハディース)に力を入れたことが知られている。とはいえ、デーオバンド学院設立直後にここを偵察したイギリス人が驚いたように[Rizvi 1980: 135-9]、デーオバンド学院をはじめとするマドラサでは数学などの実学も教えている点には留意すべきだろう。

デーオバンド学院のカリキュラム
次に、デーオバンド学院のメインコースである8年間のアーリム養成コースのシラバスをざっとチェックしてみよう。
1年目:文法(語源学)、文法(統語学)、アラブ文学、論理学、習字、朗読法
2年目:法学、文法(語源学)、文法(統語学)、アラブ文学、論理学、習字、朗読法
3年目:コーラン読解、預言者言行録、法学、文法(統語学)、アラブ文学、論理学、インド史、イスラーム史、地方自治機構、アラブ地理、世界地理
4年目:コーラン読解、預言者言行録、法学、法源学、修辞・弁論、論理学、哲学、科学(化学、物理学、動物学、植物学、衛生学)、インド憲法、経済学、現代哲学理論
5年目:法学、法源学、アラブ文学、論理学、修辞・弁論、様々な信仰
6年目:コーラン読解、コーラン読解の原理、法源学、哲学、アラブ文学
7年目:法学、様々な信仰と(イスラーム)神学、コーラン読解、預言者言行録、預言者言行録の原理、相続について、および選択科目(コーラン読解の原理、預言者言行録の原理、神学、論理学、文学――以上の科目の参考書から選択し講読)
8年目:預言者言行録(預言者言行録=ハディースの様々なエディションの学習)
[以上、Rizvi 1981: 203-7より]
そして前述の通り、アーリム養成コース修了者のためには、以下の多様なコースが用意されている。コーラン読解講座(1年)、預言者言行録特講(2年)、法学講座(1年)、法学特講(2年)、イスラーム学講座(1年)、アラブ文学講座(1年)、アラブ文学特講(2年)、教職トレーニングコース(2年)、英語と英文学の講座(2年、2002年開講)、ジャーナリズム講座(1年)、コンピューター講座(1年、1996年開講)、アフマディヤ派(異端視されているイスラームの流派)についての講座(1年)、非妥協派(アフレ・ハディース他)についての講座(1年)、キリスト教講座(1年)、比較宗教学(連続講義)、書道(カリグラフィー)講座(1年)、手工芸講座(1年)。[2015年頃発行のデーオバンド学院パンフレット; Neyazi 2014]
以上のシラバス/カリキュラムの概要で分かる通り、マドラサのカリキュラムにはもともと「宗教」以外の実学が含まれていたうえ、デーオバンド学院では必要に応じて自然科学や社会科学の科目も採り入れ、近年ではコンピューターや英語の学習にも手を広げる等、時流に遅れまいとする努力がみられる。(英語講座の導入にあたっては、学院内で激しい議論が繰り広げられたことが知られている。[Reetz 2009])
デーオバンド学院のカリキュラムがコーランやハディースといった「宗教的伝統」に重きを置いているのは事実だが、その教育姿勢は、メディアなどによって広まった「デーオバンド派」=「原理主義集団」という通俗的イメージからはほど遠い一定のバランス感覚を兼ね備えていると言えよう。また、こうした常識的なバランス感覚を備えているからこそ、デーオバンド派は南アジア・ムスリムのイスラーム解釈における主流であり続けているのである。

6.デーオバンド派の歴史的展開とターリバーンの「過激さ」の意味
ここまでの概観で、北インドにあるデーオバンド学院に「ファナティック」「狂信的」「過激派」といった形容詞が当てはまりそうにないことがお分かりいただけたのではないかと思う。しかし他方、1990年代のアフガニスタンに登場したターリバーンがかなり「過激」な集団であるのも事実である。では、なぜデーオバンド派のマドラサからターリバーンのような集団が生まれるに至ったのだろうか。この問いにある程度整合性のある回答を与えるには、南アジアにおけるデーオバンド派の複雑な歴史的展開のあらましを追う必要がある。
インドとパキスタンにおけるデーオバンド派の政治的展開:20世紀前半
すでに述べたように、デーオバンド学院は19世紀後半のインドでムスリムが政治権力を失っていく状況下、少なくとも「イスラーム」の宗教的アイデンティティーだけは死守したいとの意識から開設されたため、当初はイギリス政府の弾圧をかわすべく非政治性を保っていた。
だが、植民地支配からの解放と独立への気運がインドで高まってくると、デーオバンド学院のウラマーからもこの動きに賛同する者が現れた。その代表格がフサイン・アフマド・マダニー(Hussain Ahmad Madani、1879~1957)で、彼はガーンディーらの国民会議派と手を組み、イギリス植民政府への抵抗活動を繰り広げた。
マダニーとその同志たちは1919年、デーオバンド学院の政治部門としてインド・ウラマー協会(Jamiat Ulema-i-Hind)を立ち上げ、マダニーが会長に就任した。このインド・ウラマー協会は現在もデーオバンド学院の政治部門として活動しており、その独立運動での活躍とガーンディーらヒンドゥー教徒との協力関係などからひろく親インド的・インド愛国主義的ムスリム団体として知られ、「狂信的」「過激派」といったイメージからは限りなく縁遠い存在である。
国民会議派のヒンドゥー教徒らとの共闘の前提としてマダニーが提唱したのが「包含的ナショナリズム」(mutta ḥidah qaumiyyat)の理論だった。これはイスラーム共同体(millat)と国/国民(qaum)を区別し、かつて預言者ムハンマドがマディーナへ聖遷後、ユダヤ教徒らと共同でマディーナ国家運営を行った故事などから、ムスリムは非ムスリムと共に国/国民を形成し得るとする理論である[Madani 2005]。ただし、マダニーらは現在のインドではあたかも国民会議派的なナショナリズムのイデオローグだったかのように考えられがちだが、例えば現在のインドの国是となっているセキュラリズム(世俗主義)の概念をマダニーがとくに強調した形跡はなく、彼が国民会議派のリーダーたちに要求したのは、独立インドではウラマーがムスリム社会において伝統的な役割をきちんと果たせる体制を作ってほしいということだった。マダニーの力点はむしろ、イスラームの倫理に照らしてまず闘うべき相手はイギリスの帝国主義だという点にあり、これはアーザード(Abul Kalam Azad、1888~1958)ら他の国民会議派ムスリム・リーダーたち(非ウラマーのムスリム知識人)にも共通する姿勢だった。
一方、インドでムスリム国の分離独立を求めるパキスタン運動が勃興すると、デーオバンド学院の中にも「パキスタン建国の父」ジンナー(および彼が率いるムスリム連盟)に賛同するウラマーが現れた。彼らはインド・パキスタン分離独立前夜の1945年にインド・ウラマー協会と袂を分かち、イスラーム・ウラマー協会(Jamiat Ulema-i-Islam)を立ち上げた。以後、パキスタンにおけるデーオバンド派とその政治を率いて行ったのはこのイスラーム・ウラマー協会である。
なおここで、法学者・著述家・スーフィーとして20世紀前半のデーオバンド派ウラマーを象徴する権威だったアシュラフ・アリー・ターナウィー(Ashraf ‘Ali Thanawi、1863~1943)についても一言触れておきたい。今も新婚女性への贈り物として南アジア・ムスリムの間で重宝されている『天国の装身具』(Bihishtī Zewar、内容はムスリム女性の心得集)の著者である。
現在一般的に、ターナウィーはムスリム連盟とそのパキスタン運動を支持していたと考えられがちだが、その後の研究により、彼はムスリム連盟の運動にお墨付きを与えたわけではないことが明らかになっている。つまり彼はムスリム連盟に対し、パキスタンが実現した暁にはシャリーア(イスラーム法)を遵守する政体を作り、その政策決定過程にウラマーを正式に組み込むべきであると進言しただけであり、これに対してジンナーとムスリム連盟は確たる返答をしていない[Robb 2017]。ターナウィーとムスリム連盟の微妙な関係は、その後のパキスタン政体におけるイスラームの位置付けの難しさを予告しており、同時に、ターナウィーもマダニー同様ウラマーの地位確保を要求している事実から、基本的にイスラーム法学者の集団であるデーオバンド派の性格と関心のありようを読み取ることができる。

アフガニスタンにおけるデーオバンド派と反帝国主義ジハードの伝統
アフガニスタン、より正確に言えばデュランド線(1893年に確定したアフガニスタンと英領インドの間の国境線)を跨り、アフガニスタン南部からパキスタン北西部にかけて広がるパシュトゥーン人社会は、基本的に、①多数の部族社会、②これとは別に存在し部族社会を統括する政府/王朝、そして③この両者に依存するかたちで付属しているムスリム宗教者の三者によって構成されて来たと考えられている[Edwards 2002, 296-297; Haroon 2011, chapter 3]。
したがって、主に様々なスーフィー教団の伝統を汲むかたちで存在していたこの地域のムスリム宗教者たち(ムッラー、ピール等)が直接政治権力を握ることはなかったわけだが、他方、この地域の政府や部族にとってイスラームは権力の正統性や社会規律を保障するうえで不可欠の要素だった。
アフガニスタンにおけるデーオバンド派について考える際、避けて通れないのが、19世紀前半のいわゆるムジャーヒディーン(聖戦士)運動である。デーオバンド派が自らの思想的祖先と考えているのが、18世紀の南アジアが生んだイスラーム改革思想の大家シャー・ワリーウッラー(1703~62)だが、このワリーウッラーの息子シャー・アブドゥル・カーディルに師事したサイード・アフマド・バレールヴィー(1786~1831)が、南アジアにおけるイスラームの危機を憂え、ワリーウッラーの孫ムハンマド・イスマーイールらと共に武力による「ジハード」(聖戦)に打って出たのがムジャーヒディーン運動である。この運動は後に反英運動の性格を帯びることになるが、バレールヴィーの生前に彼がジハードの対象としたのは、当時パンジャーブ地方に一大勢力を築き、その支配地でムスリムを圧政下に置いていたスィク王国だった。
そして、このスィク王国との戦いのためにバレールヴィーらが拠点として選んだのが、スィク王国北方に位置するパシュトゥーン社会だった。バレールヴィー自身は1831年、バーラーコートの戦いにおいて殺害され生涯を終えたが、彼とその同志たちが伝えたシャー・ワリーウッラー直系のイスラーム改革思想は、当時のパシュトゥーン社会に一大宗教勢力を築いていたムッラーのアブドゥル・ガッフール(“Akhūnd” Abdul Ghaffūr、またの名をSaidū Bābā、1793~1878)とその一派によって継承され、この地域における間歇的な反英運動を支えると同時に、19世紀末以降デーオバンド派を受け入れる素地を作った。[Haroon 2011]
19世紀後半の英領インドでマドラサ教育がもはや官僚職との結びつきを失っていた点はすでに述べたが、20世紀初頭、デーオバンド派のウラマーが官僚として重用され、政治的影響力をも発揮することができた数少ない場の一つがアフガニスタンだった。このため、一部のデーオバンド派ウラマーがオットーマン帝国およびドイツと組んだ反英・インド解放のための武力闘争を画策した際、その拠点かつ最初の協力者として選んだのもアフガニスタンだった。その背景にはむろん、ときに反英に傾く当時のアフガニスタン王権の性格があった。
いずれにせよ、デーオバンド派ウラマーによるこの反英ジハードの計画は1916年に露顕し、関係者はマルタ島へ流罪となった。インド各地での参戦を呼びかける手紙が絹のハンカチに書かれ、この手紙が当局の手に渡ったため露顕したこの計画は、この手紙にちなんで「絹のハンカチ運動」(Silk Letter Movement/Te ḥrīk-e-Rēshmī Rūmāl)の名で知られている。ちなみに、前述のインド・ウラマー協会初代会長マダニーはこの運動にかかわっており、1916~20年にマルタ島で獄中生活を送っている。[山根2011; Haroon 2012; Madani 2005]
アフガニスタンにおけるデーオバンド派は、このように反英帝国主義ジハードの歴史的記憶と結びついているのであり、実際にこれら19~20世紀のジハードをめぐる文書は1980年代、アフガニスタンにおける反ソ連ジハードを鼓舞する目的で、パキスタン各地で印刷・配布されている[Haroon 2012]。

独立後のパキスタン:イスラームをめぐる政治の変化
1947年にムスリムの国としてインドから分離独立したパキスタンでは、その政体におけるイスラームの位置をめぐって独立当初から議論が絶えず、実際この国におけるイスラームの位置付けは変転を繰り返している。デーオバンド派ウラマーはこの議論において、パキスタン政体をイスラームに基づくものとするためにイスラーム党など他の面では意見を異にする宗教諸団体と手を組み、盛んに運動を繰り広げた。
その結果、1956年のパキスタン憲法では、国名がパキスタン「イスラーム共和国」(Islamic Republic of Pakistan)となり、また憲法のいかなる条項もコーランおよびスンナ(預言者の伝統)と矛盾してはならないという文言も入った。しかし、2年後の軍事クーデターでこの憲法は無効となり、1962年に新たに制定された憲法では国名から「イスラミック」の語が削除されると同時に、政府の諮問機関であるイスラミック・イデオロギー評議会(Pakistan Council on Islamic Ideology)のメンバーとして非ウラマーの知識人が登用されるなど、世俗主義的な方向への揺り戻しがあった。だが、「イスラーム社会主義」(Islamic Socialism)を掲げるブットー政権下で1973年に制定された憲法では、国名に再び「イスラミック」の語が入り、「いかなる法もイスラームに矛盾しない」規定も復活した。
この間、パキスタンのウラマー勢力の代表格であるデーオバンド派ウラマーは、パキスタンをシャリーア(イスラーム法)遵守の「イスラーム国家」(Islamic state)とすべく運動を続けた。
デーオバンド派ウラマーの主たる関心が、政治的にインド寄りであるかパキスタン寄りであるかを問わずウラマーの地位の保証にあった点はすでに述べたが、ウラマーの地位の保証とは取りも直さず、ウラマーが独占的にシャリーアを司る権限と、そのシャリーアが広く世に行われることの保証を意味する。では、そのシャリーアの施行は具体的にはどのように行われるのか。
例えば、カラーチーのデーオバンド派に属するムハンマド・タキー・ウスマーニー(Muhammad Taqī ‘Usmānī、1943~)によれば、シャリーアを実際に施行するには①ただちに施行し、細かい法解釈についてはその都度の法廷の判断に任せる、②シャリーアを全て明文化・法典化する(ただしこれには莫大な時間がかかる)、という2つの方法があり、彼自身の意見では、シャリーアはただちに施行されるべきだが、基本的にシャリーアは法典化されるべきである。
こうした見解に接して考えざるを得ないのは、第一に、歴史的にムスリム社会におけるシャリーアはその全てが明文化・法典化されることはなく、つねに法解釈についての討議を伴う「プロセス」として存在してきたという点、ひいては、「プロセス」の反対物である「法典化されたシャリーア」とはまさしく法をめぐる近代的な考え方の所産であるという点であり、第二に、近代国家システムの中でこの法典化されたシャリーアが国家権力によって運営されるという事態は、シャリーアにとっては全く新たな、しかもきわめて近代的な経験であるという点である。[Zaman 2002, chapter 4]
われわれは預言者ムハンマドと正統カリフの時代の「原理」に基づくシャリーアを施行するまでだ、とする現代ウラマーの主張は、一見すると単純で、時を超えたイスラームの基本原則を尊重しているだけのように聞こえるが、実際にその主張を施行する局面では、すでに近代化された思考回路と政治環境を経ている「原理」の姿は否応なく近代的なのであり、いくらコーランの文面をそのまま施行しようとしたところで、それは近代化の波をくぐった近代的な行為にしかならない。現代におけるイスラーム「原理」主義の根本的な問題はおそらくここに存するのであり、パキスタンのデーオバンド派の場合も例外ではないと思われる。
パキスタンのウラマー勢力は以上のような問題点をすでに抱えていたわけだが、イスラームをめぐるその後のパキスタン政治はさらに別の方向へ急展開した。ズィア・ウル・ハク軍事政権によるイスラーム化政策、ソ連のアフガニスタン侵攻に伴うジハード運動の開始、イラン革命に伴うスンニー派とシーア派の対立激化などが相乗した1970年代末から1980年代にかけての劇的な変化がそれである。
1977年の軍事クーデターでパキスタンの政権を掌握したズィア・ウル・ハク将軍は、政権の正統性を獲得する目的や彼自身の宗教的傾向などから、いわゆるイスラーム化政策に乗り出した。その内容はシャリーア法廷の設置やザカート(喜捨)の税制としての制度化など多岐にわたったが、姦通罪に対する石打ちの刑(死刑)や窃盗罪に対する手首切断の刑などを含むハッド刑(Hudood Ordinances)の導入に典型的に見られるように、象徴的な効果を狙った皮相な政策という性格は否めなかった。
とはいえこれらの政策がパキスタン社会に及ぼした影響は計り知れず、とくに表面的なシラバス改革とともにマドラサ教育における学位を公認し、ザカート税による税収をマドラサ支援に充てる教育政策は、パキスタンにおけるマドラサ数を急増させ、貧困層の子弟が大挙してマドラサに入学する事態をもたらした。
そして、この政策以上にパキスタン社会のイスラーム化に拍車をかけたのが、1979年12月のソ連によるアフガニスタン侵攻が引き起こした、アフガニスタンにおけるソ連の傀儡政権に対するジハード運動の開始である。
ソ連のこの侵攻によりアメリカはパキスタン支援に回ることになり、アメリカの後ろ盾を得たズィア政権は全面的にアフガニスタンのジハード運動を支援した。このジハードを支援する運動はパキスタンで大衆化し、宗教勢力の発言権と政治力の増大をもたらし、パキスタン社会に宗教的な空気を充満させた。
この宗教的な空気をさらに深めたのが、同じく1979年、イランにシーア派政権を誕生させたイラン革命である。つまり、この革命に危機感を抱いたスンニー派のサウジアラビアと、勢力拡充を狙うイランが競争するかたちでパキスタン国内のそれぞれスンニー派、シーア派への資金援助を増加させて行った結果、パキスタンでは両派の急進的な団体が台頭し互いに武力抗争を始めるようになり、これがパキスタン社会の宗教的な空気を増幅すると同時に急進化させた。
結果的に、これらの1980年代パキスタンの変化は、イスラームを近代的政体に取り込み内面化する(これが上述の通り、現代ウラマー勢力とイスラーム社会にとっての本来の課題であった)というより、イスラームの表面的な政治化、アイデンティティー政治としての大衆化をもたらしたのみであった。

ハッカーニヤー学院とターリバーン
1990年代のアフガニスタンに登場したターリバーン勢力は、まさにこうしたパキスタンのイスラーム化が生み出した鬼子という側面を持っている。そして、その背景にあるのが、パキスタン北部カイバル・パクトゥーンクワー州(かつての北西辺境州)のペシャーワル近郊の片田舎にあるデーオバンド派の一大マドラサ、ハッカーニヤー学院(Dar-ul-Uloom Haqqaniya)である。
それまでデーオバンド学院で学び、教鞭も執っていたアブドゥル・ハク(‘Abdul-Ḥaq、1912~88。デーオバンド学院ではマダニーに師事。イスラーム・ウラマー協会メンバー、のちパキスタン国会議員)が1947年に故郷で開設したこのマドラサは、パキスタンのデーオバンド派ウラマーの約3分の1を輩出するといわれる規模を持つ教育機関である。なお、パキスタンのイスラーム・ウラマー協会は1980年代に政治的理由から二つに分裂しているが、分裂後の一方の派閥を率いているのがアブドゥル・ハクの息子サミーウル・ハク(Samī’u’l-Ḥaq、1937~、ハッカーニヤー学院長を兼任)である事実からも、このマドラサが持つ政治的影響力の大きさを推し量ることができる。
ハッカーニヤー学院の財政規模は1980年以降、ザカート基金からの政府支援によって急増したことが知られており、同時にアフガニスタンからの留学生も急増し(同学院の学生寮におけるアフガニスタン人学生の割合は、1960年15.1%、1970年37.1%、1985年60%と漸増している)、またアフガニスタン留学生以外の学生もほとんどが地元のパシュトゥーン人であるため、アフガニスタンにおけるジハードとパキスタンを挙げてのジハード支援運動の開始後は、この学院は自らこのジハード運動に染まって行くことになった。
その刊行物でジハードの宣伝が行われたり、ジハードへ参戦する学生に休学の便宜が図られたりといった事情はあったものの、この学院がジハード運動の一大拠点となった背景には、デーオバンド派の教義というよりも、上述のパキスタン政府のイスラーム化政策やパキスタン社会のイスラーム化、あるいはこの地域における過去の反帝国主義ジハードの記憶などが大きな要因として存在していると考える方が自然だろう。[Malik 1998, 202-209]
そして、ここから生まれたのが、1989年のソ連撤退いらい派閥抗争に明け暮れ荒廃していたアフガニスタン社会にイスラームの規律と安定をもたらすべく登場し、女性の権利蹂躙やウサーマ・ビン・ラーディン擁護で悪名高いターリバーン(「学生たち」の意)である。そして、その最高指導者だったウマル師を始めとするターリバーン幹部の多くが学んだのがこのハッカーニヤー学院だった。
ターリバーンによる女性の就労権・就学権の剥奪などの現象の背景には、上述のようなパキスタン政府・社会のイスラーム化がもたらした短絡的・表面的・大衆的なイスラーム解釈があると同時に、パシュトゥーン社会が元来持っていた男尊女卑の価値観が働いているという考え方もある(この女性の権利に関する現象は、アフガニスタン農村の価値観を都市カブール等に持ち込んだために起きたという見方もある。また、ターリバーンの女性政策は多少の揺れと多様性を持っているのも事実である[遠藤 2008])。
ただ、ターリバーンには例えばアフガニスタン社会に根を張っていた少年愛(バッチャバーズィー)の習慣を根絶するなどの側面もあったことを忘れてはならないだろう。これは、結婚式などの会場で美少年を踊らせ、事後には権力者(男性)がこれを性的玩具として楽しむという慣習で、未成年児童の性的搾取であるばかりか、美少年を取り合う権力者たちの抗争に巻き込まれ命を落とす少年も多かったことが知られている[Quraishi 2010]。
ターリバーンには、1980年代パキスタン経由の現代的に劣化したイスラーム解釈の要素が入っている一方、近代以降に生まれた倫理運動という側面もあるわけで、そこにはこの少年愛の根絶に見られるように、現代の欧米とも基本的には重なり合う近代的な倫理観が存在しているのである。
ここで、デーオバンド派は「イスラーム過激派」の温床なのか?という問いに答えておきたい。
ここまでの説明でおそらくお分かりいただけたと思うが、デーオバンド派の教義とマドラサ教育自体が「過激化」をもたらしているとは考えにくい。ラフマーンが述べるように、パキスタンのマドラサにおいて「ニザーミー方式」のカリキュラムに大きな変化があったわけではなく、「過激化」したのはむしろマドラサを取り巻く環境(アフガニスタン、カシミール、パレスチナ等におけるムスリムへの弾圧、アメリカの対ムスリム政策、上述のパキスタン社会の変化など)のほうで、その影響を受けているのはマドラサの学生だけではない[Rahman 2008]。ネヤージーも述べるように、「パキスタンにおける一群のマドラサの急進化は、マドラサ教育システムに内在する要因によるものではない。それはむしろ、パキスタンという国における政治経済的な、より大きなレベルでの事態の複雑な推移の結果なのである。[Neyazi 2014: 187]」
ターリバーンによる女性の権利の蹂躙はもちろん許しがたいけれども、ではかつてのイギリス帝国主義と植民地支配、現在のアメリカの軍事政策とこれが紛争地にもたらす災禍の数々は、許してしまえるものなのだろうか? より大きく深刻な問題は何なのか、あらためて問いかけてみる必要がありそうだ。

7.結びに代えて:イスラモフォビアとデーオバンド学院の現状
このように、「デーオバンド派」をめぐる偏見ともいえるイメージ構築の陰には、現在の世界に渦巻く「イスラモフォビア」(イスラーム恐怖症)の働きと、根本的な問題の所在のすり替えがあると思われる。
このことは、ムスリム独自の教育機関である「マドラサ」のイメージについても当てはまる。マドラサにおける教育内容への想像力が働かず、マドラサ卒業生の中から反メインストリーム的=反欧米的で「過激」な政治的行為に打って出る者が多いという印象から、「あのマドラサというよく分からない教育機関の内部では「狂った」ことが行われているのではないだろうか」、ひいては「マドラサで教育を受けたムスリムという集団全体が「ちょっとおかしい」のではないだろうか」という偏見感情が生まれてしまっているのである。
ムスリムをめぐるこういった偏ったイメージ構築がなされがちな国の一つが、ヒンドゥー教徒が主体の現在のインドである。
インドにおけるムスリムの状況をインド政府の命により調査したサッチャル委員会の報告書(2006年)が述べるように、インド・ムスリムの子弟のうちマドラサで教育を受けているのは全体の約4%に過ぎず、ムスリム・コミュニティー全体がマドラサ教育により性格づけられているという仮定自体がそもそも間違っている。同報告書は、やはりインド・ムスリム子弟の約4%が通う「マクタブ」(全寮制であることが多いマドラサと異なり、一般の政府系学校などに属するムスリム生徒が主にウルドゥー語・アラビア語の知識を得るべく放課後に通う一種の塾)とマドラサが混同されていることも、こうした誤った仮定の背景にあるのではないかと指摘している[Sachar et al. 2006: 76-79]。
デーオバンド学院が今日インドで直面しているのも、ムスリムへのこういった偏見や敵対心である。現在インド中央政権を担っている与党は、しばしば「ヒンドゥー至上主義政党」の名で呼ばれるBJP(インド人民党)だが、2017年2月のウッタル・プラデーシュ州議会選挙でもBJPが大勝し、過激なヒンドゥー至上主義的活動で知られるヒンドゥー教聖職者ヨーギー・アーディティヤナートが州首相に就任した。
こうした時流を受け、2017年3月にはデーオバンドから選出されたBJP州議会議員が「デーオバンドの町名はデーオヴリンドに改めるべきだ」と発言する事態に至っている[Ali 2017]。「デーオバンド」の名はあまりにもこの有名な学院と結びついており、ムスリムやイスラームを連想させるため、ヒンドゥー教の叙事詩マハーバーラタに登場する地名「デーオヴリンド」で置き換えるべきだというのである。
デーオバンド学院の公式史書も記す通り、「デーオバンド」の「デーオ」はヒンドゥー教の女神を表す「デーヴィー」に由来しており[Rizvi 1980: 98]、そもそも「デーオバンド」自体がきわめてヒンドゥー的な名前なのだが、BJPにとってはそんな歴史的事情はどうでも良く、とにかくムスリムに大きな顔はさせないという多数派ヒンドゥー教徒側の意思がこの議員の発言に表れている。
こうしたインドの社会状況と闘わなければならないデーオバンド学院だが、じつは内部にも問題を抱えている。1982年以来、デーオバンド学院創立の立役者であるモハンマド・カーシム・ナーノータウィー(1833~80)の子孫と、前述インド・ウラマー協会初代会長マダニーの子孫がいがみ合い、分裂状態なのである[Reetz 2009]。南アジアでは、一時代を築いた政治家の子孫が世襲でそのまま政治権力を持ち続ける傾向があるが、こうした傾向がこの学院の内部にも現れたかたちである。外憂を抱えているにもかかわらず、こうした低レベルの内紛に足をすくわれている状況は、このグローバルな名声を誇る教育機関の未来にとって好ましいとは言えないだろう。

参考文献
遠藤雄介、2008、『タリバンの復活:火薬庫化するアフガニスタン』花伝社
山根聡、2011、『4億の少数派:南アジアのイスラーム』山川出版社
Ali, Mohammad. 2017. ‘Deoband will be turned into Deovrind: BJP MLA’, in The Hindu, March 17 (http://www.thehindu.com/news/national/deoband-will-be-turned-into-deovrind-bjp-mla/article17489034.ece)
Edwards, David B. 2002. Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad (Berkeley: University of California Press)
Fyzee, Asaf A.A. 2008. A Modern Approach to Islam, Second Edition (New Delhi: Oxford University Press)
Haroon, Sana. 2011. Frontier of Faith: Islam in the Indo-Afghan Borderland (London: C. Hurst & Co.)
―――. 2012. ‘Religious Revivalism across the Durand Line’, in Shahzad Bashir and Robert D. Crews (eds.), Under the Drones: Modern Lives in the Afghanistan-Pakistan Borderlands (Cambridge: Harvard University Press)
Jones, Justin. 2012. Shi‘a Islam in Colonial India: Religion, Community and Sectarianism (New Delhi: Cambridge University Press)
Khan, Dominique-Sila. 2003 [1997]. Conversions and Shifting Identities: Ramdev Pir and the Ismailis in Rajasthan (New Delhi: Manohar)
Madani, Maulana Hussain Ahmad (tr. by Mohammad Anwer Hussain and Hasan Imam; intro. by Barbara D. Metcalf). 2005. Composite Nationalism and Islam (New Delhi: Manohar)
Malik, Jamal. 1998. Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (New Delhi: Manohar)
――― (ed.). 2008. Madrasas in South Asia: Teaching Terror? (London: Routledge)
Metcalf, Barbara Daly. 2002. Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900 (New Delhi: Oxford University Press)
Neyazi, Taberez Ahmed. 2014. ‘Darul Uloom Deoband’s Approach to Social Issues: Image, Reality, and Perception’, in Robin Jeffrey and Ronojoy Sen (eds.), Being Muslim in South Asia: Diversity and Daily Life (New Delhi: Oxford University Press)
Pew Research Center. 2009. ‘Mapping the Global Muslim Population’ (October 7), http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/(2017年3月29日閲覧)
―――. 2015. ‘Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group’ (April 23), http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/(2017年12月7日閲覧)
Quraishi, Najibullah. 2010. The Dancing Boys of Afghanistan(ドキュメンタリー映画、52分)
Rahman, M. Raisur. 2015. Locale, Everyday Islam, and Modernity: Qasbah Towns and Muslim Life in Colonial India (New Delhi: Oxford University Press)
Rahman, Tariq. 2008. ‘Madrasas: The Potential for Violence in Pakistan?’, in Jamal Malik (ed.), Madrasas in South Asia: Teaching Terror? (London: Routledge)
Reetz, Dietrich. 2009. ‘Change and Stagnation in Islamic Education: The Dar al-‘Ulum of Deoband after the Split in 1982’, in Farish A. Noor, Yoginder Sikand and Martin van Bruinessen (eds.), The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages (New Delhi: Manohar)
Rizvi, Sayyid Mahboob. 1980. History of the Dar al-Ulum Deoband, Volume One (Deoband: Idara-e Ihtemam, Dar al-Ulum Deoband)(1、2巻ともにウルドゥー語の原著も適宜参照した)
―――. 1981. History of the Dar al-Ulum Deoband, Volume Two (Deoband: Idara-e Ihtemam, Dar al-Ulum Deoband)
Robb, Megan Eaton. 2017. ‘Advising the Army of Allah: Ashraf Ali Thanawi’s Critique of the Muslim League’, in Ali Usman Qasmi and Megan Eaton Robb (eds.), Muslims against the Muslim League: Critiques of the Idea of Pakistan (Cambridge: Cambridge University Press)
Sachar, Rajindar, et al. 2006. Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report (New Delhi: Prime Minister’s High Level Committee, Cabinet Secretariat, Government of India) http://minorityaffairs.gov.in/reports/sachar-committee-report
Zaman, Muhammad Qasim. 2002. The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (Princeton: Princeton University Press)

(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・客員准教授/人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター・研究員)