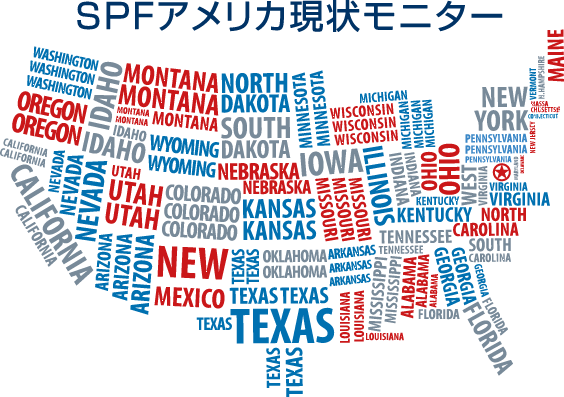米国の中東政策とミドルクラス外交

中山 俊宏
トランプ政権の4年間でアメリカから見た中東の風景は大分変わったように思われた。その集大成が「アブラハム合意(Abraham Accords)」だった。この合意によって、アラブ首長国連邦はイスラエルと国交を正常化、バーレーンもそれに続いた。背景には、長年、米国の中東外交を規定してきた中東和平の、争点としての重要性を相対化させ、イランの脅威を軸にアメリカの対中東政策を再構成しようとする発想があった。その評価は分かれるも、「アブラハム合意」は、トランプ政権が実現にこぎつけた数少ない「形のある合意」だった。その立役者である、ジャレッド・クシュナー前大統領上級顧問は、この合意の精神を維持すべく、今年5月に「アブラハム合意平和協会(Abraham Accords Institute for Peace)」の設立を発表した。
イランとの対決姿勢は強めつつも、中東全域への関与は下げていく。それが、トランプ政権の基本姿勢だった。またトランプ大統領はアフガニスタンからの米軍の撤収の道筋も明確にし、2016年の選挙の時から一貫して批判していた「永続戦争(エンドレス・ウォー)」にも終止符を打つ。こうして2001年以降、アメリカが関与を深めた「大中東圏(グレーター・ミドル・イースト)」と呼ばれる地域における「フットプリント(足あと)」を軽くするという目標に向けて着実に動いているかのように見えた。イランについては、トランプ政権からの政策的継承はなかったが、この「足あとを軽くする」という点に関しては、バイデン政権もトランプ政権の方向性を引き継いだといえる。
バイデン政権の対外政策の核には、「ミドルクラス外交」があると指摘される。それは、バイデン外交を束ねる「統合原則」のようなものだ。しかし、中東における「大きなプレゼンス」は、このミドルクラス外交という原則とは合致しない。よって、バイデン政権は、基本的にはトランプ政権の「足あとを軽くする」方向性を継承していた。しかし、アブラハム合意平和協会の設立が発表されたのとちょうど同じころ、ガザ地区でデジャヴを思わせるような衝突を我々は目にすることになった。ハマスの攻撃に対する報復でイスラエルはガザ地区への攻勢を強め、双方の側に死者が出た。死者数でいえば、パレスチナ側のそれがイスラエルのそれをはるかに上回り、バイデン外交を難しい状況に追い込んだ。バイデン政権は、「よきアメリカの大統領」ならばそうしなければならないように、イスラエルの自衛権を躊躇なく擁護する姿勢を示した。しかし、ことイスラエル案件になると、アメリカは国際社会で孤立してしまいがちだ。それは、バイデン外交の国際協調主義に抵触してしまう。それもあって、事態の収束を図るべく、バイデン政権が水面下で積極的に動いたことも伝えられている。どうにか停戦にこじつけたものの、情勢は危うい。バイデン政権を構成する面々は、外交は白紙からはデザインできないし、仮に大きな見取り図を描けたとしても、それは現実に発生する事態によって情け容赦なく妨げられるという当たり前の事実を思い知らされているにちがいない。
3月中旬からのバイデン外交のスピード感は多くの人の予想をはるかに上回るものだった。躊躇なく中国との競争を引き受け、その競争に同盟国やパートナーを動員しつつ、長期的且つ持続的な競争戦略の組み立てを企図していた。そこには、しばしば日本で懸念が表明されたように、中国に対する「微妙な姿勢」は微塵もなかった。それは、バイデン政権が大きな見取り図の中で、中国との戦略的な競争を「中心的な争点」にすると自覚的に定めたからだ。中国との戦略的な競争は実はミドルクラス外交と整合性がある。どういうことか。ミドルクラス外交は一般に、外交を通じてアメリカのミドルクラスに資するような目標を実現することと解説される場合が多い。つまり、雇用の確保や賃金の上昇、そして格差是正などを、外交を通じて実現することとしばしば説明される。こうした理解は間違ってはいないが、目的と手段が反転した説明になっている。
バイデンの外交チームが主張するミドルクラス外交は、雇用の確保や賃金の上昇それ自体を目的にしているわけでは決してない。それは次のような認識の上に立脚している。今のアメリカには、冷戦時代のようにいわばユニラテラルに、自由で開かれた国際秩序を維持・発展させる役割をアメリカが引き受けるべきだという機運はない。トランプの「アメリカ・ファースト」は、そうした傾向の露骨な表現だった。では、バイデン政権がそれはそれでもう事実として受け入れざるをえない、という諦めの境地に達しているかといえば、決してそうではない。バイデン外交チームは、大統領自身も含め、アメリカ固有のインターナショナリズムが、どういうものだったのか、まだリアルに記憶している世代だ。依然としてアメリカは大きな役割を引き受ける必要がある。しかし、単純に昔に戻れるかといえば、トランプを体験したアメリカはもはや予定調和的にそのような地点に戻ることはできない。ならばどうするべきか。それは、アメリカのミドルクラスに丹念にアメリカン・インターナショナリズムの必要性を説くことによってしか実現しないだろう。そうした発想の上に「ミドルクラス外交」は立脚している。そして、その説明にはアメリカのミドルクラスの生活の向上にも資するという説明も加えなければならない。
つまり、ミドルクラス外交は、アメリカの対外政策を、一般のアメリカ人にとっても意味をなすものとして語ること、そしてそれを通じて、ギリギリのところでどうにか国際主義を維持すること、そうした発想が核心にある。そのためには当然、広げたふろしきを畳まなければならない。アメリカはすべての問題に関与することはできないし、優先順位をつけなければならない。そうしたなかで、バイデン政権は中東からは退き、インド太平洋地域に意識を集中させるという判断を早期に下した。これはミドルクラス外交の内在的なロジックとも合致している。つまり、インド太平洋地域には米国がおそらく初めて向き合う「(潜在的に)対等な競争相手(peer competitor)」が存在している。しかし、その挑戦国と向き合おうとする時に、アメリカ単独で向き合うのではなく、共に行動してくれる同盟国やパートナーがいる。この点は重要である。ミドルクラスにとって意味をなすためには、アメリカ単独で責任を引き受けるわけではないという構図をはっきりと示すことが極めて重要になってくる。そして、事実、インド太平洋地域には、日本や豪州をはじめとして多くの「仲間」がいる。そして何よりも、インド太平洋地域は、「地域としての可能性」が間違いなく高い。この地域は、多くの問題を抱えつつも、世界経済を牽引していく地域であり、アメリカはそこに留まる必要があるというロジックだ。
しかし、このインド太平洋地域については当てはまるロジックが、中東になると空振りしてしまう。アメリカは2001年以来(もしくはそれよりも遡り湾岸戦争以来としてもいいかもしれない)の介入に疲弊しきっている。アメリカを敵対視する明白な脅威が存在してはいるものの、イスラム原理主義勢力による「カタストロフィック・テロリズム」に対する脅威認識はかなり減退しているし、あたりを見回してもインド太平洋地域のような同盟国やパートナーはあまり見当たらない。そして、何よりも地域としての可能性が高くはない。アメリカにとって、中東は問題に対処する地域だ。アメリカのエネルギー自給率が高まったことも大きく影響しているだろう。こうなると必然的に「もう退こう」という意識が先行してしまう。
しかし、バイデン政権は今、中東から去ることを思い描くことはできても、実際にはそれが極めて難しいという状況を突きつけられている。足あとを軽くしようと決断し、行動に移そうと思った瞬間に、足首を後ろから鷲掴みにされたような感覚と言ったら大袈裟だろうか。しかし、そうではあっても、バイデン外交の統合原則であるミドルクラス外交によって、中東における大きなプレゼンスを根拠づけることはできない。これによってバイデン政権のインド太平洋フォーカスが揺らぐということはないだろうが、そのフォーカスが若干ぶれることは避けられないだろう。偶然にも5月に国連安保理の議長国を務めている中国は、アメリカのせいで安保理全体としての声明が出せなくなったことを喧伝している。
こうした動きの背後で、イランとサウジアラビアが接近を模索しているとも伝えられる。イスラエルとハマスの間ではどうにか停戦合意が成立したが、ガザ地区の状況がさらに悪化していけば、イスラエルと周辺アラブ諸国との関係も悪化していかざるをえないだろう。中東和平プロセスを周縁に追いやったアブラハム合意は早くも危機を迎えている。いま事態は、あたかもトランプの4年間がなかったかのように動き始めている。
(了)