- フィリピン南部
ミンダナオ紛争と和平の行方-スールーの難民の視点から

本稿はフィリピン南部のムスリム少数民族と政府とのあいだのいわゆるミンダナオ紛争と和平プロセスに関して、とくにスールー諸島出身の難民に焦点を当てて考察を試みたい。
まずフィリピン南部におけるムスリム社会の概要について簡単に紹介する。フィリピンは総人口の約90%以上をキリスト教徒が占めるが、南部のミンダナオ(Mindanao)島やスールー諸島(Sulu Archipelago)を中心に約5%から7%前後、推定で約400万人から700万人弱前後とされるムスリムが生活している。フィリピン諸島のムスリムは、細かく分けると言語や習慣を異にする約13前後の民族集団に区分されるが、いずれもイスラームという信を共有する「モロ(Moro)」人ないし「バンサ・モロ(Bangsa Moro:モロ民族)」として総称されることが多い。こうしたフィリピン諸島南部のムスリムはスペインによる植民地支配の試みに最後まで抵抗し、19世紀末まで独立を維持してきた。この歴史的経緯や宗教的差異によって、現在でもフィリピンのムスリムは、ルソン島やビサヤ諸島などのフィリピン諸島中北部で多数派を占めるキリスト教徒(クリスチャン・フィリピノ)とは異なった独自のアイデンティティを有するマイノリティとして自他ともに区別される。また「モロ」と総称されるフィリピン南部のムスリムの内部でも、マギンダナオ(Maguindanao)人やマラナオ(Maranao)人などはミンダナオ島を中心に居住するのに対して、本稿が主な対象とするスールー諸島においてはタウスグ(Tausug)人やサマ(Sama)人などを主要な民族集団として挙げることができる(床呂 1999)。
ミンダナオ紛争の背景と現状
ここでは、現在も進行中のいわゆるミンダナオ紛争の背景と経過について触れておきたい。19世紀末までフィリピン南部のムスリムは、スールー王国など独自のイスラーム王国の下で生活を営んできた。しかし20世紀に入ると、米西戦争の結果、スペインに代わってフィリピン諸島の領有権を獲得したアメリカが、ミンダナオとスールーを含めたフィリピンの植民地化を実施することとなった。このアメリカ植民地統治時代と、それに続くフィリピン独立後には、政府の国内移住政策によって大量のキリスト教徒農民が移民としてミンダナオ島に送り込まれた。
この移住政策の結果として、ミンダナオのムスリムは、自分たちの土地を移住者のキリスト教徒農民らに奪われ、社会的に周辺化・窮乏化を強いられていった。そして1960年代後半から1970年代初頭頃にかけて、ミンダナオへ入植したキリスト教徒とムスリム住民との土地争いに端を発した紛争は、次第に武力衝突へとエスカレートしていった(床呂 2012:100、 TOKORO 2015)。
こうした状況を背景に、1970年代初頭にはスールー諸島出身のヌル・ミスアリ(Nur Misuari)を中心とするムスリム分離主義組織であるMNLF(Moro National Liberation Frontモロ民族解放戦線)が結成された。
MNLFは、リビアのカダフィ大佐やマレーシアのトゥン・ムスタファ(当時のサバ州知事)などから資金や武器の支援、あるいは訓練・出撃拠点などの提供を受けて、フィリピンからの分離独立を目指して武装闘争を開始し、1970年代前半にはフィリピン南部の各地でMNLFとフィリピン国軍との間で武力衝突が続いた。当時のマルコス大統領はMNLFの活動による政情不安を理由の一つとして1972年に戒厳令を施行したが、1974年にスールー諸島の中心地ホロの市街地が戦闘によって壊滅するなど、戦火は拡大していった。
その後、OIC(イスラーム諸国会議機構、2011年にイスラーム協力機構に改称)やインドネシアの仲介による和平交渉を経て、1996年には当時のラモス政権とMNLFは最終和平合意(FPA: Final Peace Agreement)を締結するに至った。この合意でMNLFは分離独立の放棄を再確認する代わりに、中央政府の支援を得ながら段階的にフィリピン南部の一定地域における高度な自治を確立することを骨子とするものであった(床呂 2012:101)。しかしFPAの想定していた移行期間終了後も、高度な自治区の確立という当初の合意内容は実現できず、2001年にはMNLFと政府側が再び武力衝突するなど和平プロセスは後退を余儀なくされた。
一方でMNLFから分派したMILF(Moro Islamic Liberation Frontモロ・イスラーム解放戦線)はミンダナオ島を中心に最大のムスリム分離主義組織として活動を継続した。その後、マレーシア政府などの仲介により政府側とMILFの和平プロセスも一定の進展を見せた。その結果、2012年10月にはMILFとフィリピン政府のあいだで和平の枠組み合意(FAB: Framework Agreement on the Bangsamoro)が原則として合意され、さらに2014年3月にはいわゆる包括和平合意(CAB: Comprehensive Agreement on the Bangsamoro)に両者が調印するに至った。
こうした和平プロセスの進展のいっぽう、それに逆行するような動きも持続してきた。たとえば2000年代以降も、アルカイダやJI(Jemaah Islamiya)など海外のイスラーム系テロ組織ともつながりがあるとされるアブサヤフ集団(ASG: Abu Sayyaf Group)などの武装集団がスールー諸島やバシラン島、あるいはマレーシアのサバ州東海岸各地などで人質誘拐事件や治安当局との衝突などを繰り返してきた。またMILFと政府の和平プロセスの進展の過程でいわば「梯子を外された」かたちとなったヌル・ミスアリ率いるMNLF-MG(MNLFミスアリ派)や、MILFから分派したBIFF(Bangsamoro Islamic Liberation Front)等を含む各種の武装集団による和平プロセスへの妨害活動も近年、目立つようになっている。
とくに2013年2月から3月頃に発生した「スールー王国軍(Royal Security Force of Sultanate of Sulu)」を名乗る集団のサバ侵入事件(後述)ではマレーシア政府治安部隊と同集団の衝突でサバに在住する多数のフィリピン系ムスリムが「再難民化」するという状況を招いた。さらに同年9月にミンダナオ島のサンボアンガ市で発生したMNLF-MGとフィリピン政府軍の衝突事件では11万人以上が新たに難民化するなど現地の住人には厳しい状況が続いた。

マレーシア・サバ州への国外難民の状況
概してミンダナオ紛争に伴う政府側との武力紛争によって、現在までに推定で約15万人以上の死者と、少なくとも100万人を超えると推定される大量の難民(国内避難民を含む) を出す事態となっている。そのうち海外へ脱出したムスリム住人の大半は隣国のマレーシア・サバ州へ難民として流入した。1970年代後半以降もフィリピン南部からサバへのムスリム住人の移動・移住は持続しているが、1970年代後半からは、狭義の「難民」だけではなく、むしろ経済的動機による出稼ぎ労働者の越境移動や移住という文脈で語られることが多い。ただし筆者はフィリピン南部からサバへの人のフローを「難民」と「移民」のカテゴリーに明確に峻別して考えることは必ずしも適切ではなく、現実の状況下ではある種の連続性を伴ってオーバーラップしていると考えている。
さて、フィリピン南部からマレーシア・サバ州への人のフローのうち、マレーシアにおいて狭義の「難民」(pelarian)として公的に認定されたフィリピン人は、1970年代の時点でサバ州政府は約7万人、国連は約10万人規模と推定されている。1970年代のサバへのフィリピン人難民流入に対してはこれまで国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)による難民支援事業なども行われており、サバ州東海岸の各地にUNHCRの支援の下で通称「難民村」とも呼ばれるフィリピン系難民用の簡易集落が設立されたりしたほか、コタキナバル市内の通称「フィリピノ・マーケット」と呼ばれる市場も当初はフィリピン系難民への生業支援の目的もあったとされる。
「スールー王国軍」サバ侵入事件とフィリピン系ムスリムの「再難民化」バンサモロ武装組織の誕生
本節では、サバで最近発生したとある武力衝突事件を契機として、これまで主としてフィリピン南部からサバの方向へと向かっていた人のフローが逆転するという現象を扱う。言い換えれば、これまで過去20年以上に渡ってサバに難民(ないし移民)として流入していたフィリピン出身ムスリムの人の移動のフローが逆転し、今度はサバからの(再)難民としてもともとの出身地であるフィリピン側へと還流していくという状況、いわばフィリピン出身ムスリムの「再難民化」と呼ぶべき現象を取り上げて紹介したい。
本節で述べる再難民化の状況は2013年の2月から3月にかけてサバで起きた武力衝突事件を契機としている。この事件は、ごく簡単に述べれば2013年2月前半に、フィリピン南部から出発した「スールー王国軍(RSF)」を名乗る集団(かつてスールー諸島を統治したスールー王国の末裔キラム3世の弟が率いる)が東マレーシア・サバ州東海岸のラハダト地区に上陸して同地のタンドゥオ村と呼ばれる小さな漁村を占拠した事件に始まる。事件発生当初は同村を占拠したRSFをマレーシア政府治安部隊が遠巻きに包囲して睨み合いの状況が続いていたが、その後3月1日以降は同集団とマレーシア治安部隊との武力衝突へ発展した。この事件の背後関係などにはまだ明らかになっていない点も残るが、いずれにしても武力衝突はラハダトからセンポルナなどサバ州東海岸の各地に飛び火し、この過程でマレーシア政府軍側は空爆を含む大規模な軍事行動を行うなど事態はエスカレートし、国連事務総長が停戦を呼び掛ける事態となった。
この事件では事態が概ね沈静化する3月後半までのあいだに死者70人以上を出した他、事件の背景のひとつであるサバ領土問題が政治的な論争アジェンダとして浮上し、フィリピンとマレーシアの関係に緊張を招く結果となった。本稿の文脈で重要なのは、この事件を契機としてRSFに潜在的なシンパシーを有する者が潜んでいるとマレーシア治安当局側に疑われたサバ在住フィリピン系ムスリムへの当局の取り締まり活動が激しくなり、結果的にフィリピン系ムスリムが元の出身地であるフィリピン側へ大量に脱出するという状況を招いたことである。
より具体的に述べるならば、3月のラハダトでの武力衝突以降フィリピン南部(サンボアンガ、ホロ、バシラン、ボンガオ・タウィタウィ)などに、サバ東海岸からフィリピン系の避難民(その多くはいわゆる不法移民)の大量の脱出を招いた。
これまでは1970年代から一貫して主要な人のフローはフィリピン南部からサバへと向かう方向で流れていたのが、2013年3月のラハダトでの武力衝突によって一時的にそのベクトルが逆転し、今度は戦闘やマレーシア政府による取り締まりを避けるためにサバからフィリピン側へとフィリピン系ムスリムが帰還していくという状況が発生したのである。
筆者はラハダトでの武力衝突事件の発生直後からフィリピンで二週間ほど緊急の現地調査を実施したが、以上のような「移民/難民の還流」ないし「再難民化」とでも呼ぶべき現象は、フィリピン南部のムスリム社会にも少なからぬ影響をもたらしていることが確認できた。
サバからフィリピン側に「再難民」として帰還した人の数は、フィリピン政府に登録されたものだけで2013年7月の時点で約2万人を数えた。しかし、これはフィリピン政府がスールーやミンダナオ各地に設けた避難施設で受け入れた公式登録者の数だけであり、自発的にフィリピンの村にボートなどで脱出した者は含まない。このため「再難民」の実際の規模はこの数字の少なくとも数倍、少なめに見積もっても4万~6万人規模に達していたと推定できる。
サバ在住のフィリピン系ムスリム住民の状況について補足すると、先に述べた通り3月初旬に起きた武力衝突以降、サバ東海岸各地でフィリピン系住人への取り締まりが強化され、なかでもRSFの主要な構成民族であるタウスグ人は、サバ各地の検問などで厳しいチェックの対象とされた。また武力衝突の直後に避難民の流入が顕著なマレーシアとの国境近くのフィリピン側の島では島の住人の人口より避難民の人口が多くなるような状況が続き、一時は深刻な食糧不足に見舞われるなどの影響が生じた。

こうした危機的状況に対してフィリピン政府もスールー州やタウィタウィ州、バシラン州、サンボアンガ市などフィリピン南部各地に難民向けの緊急支援施設(Evacuation Centre)を設置し、社会福祉開発省(DSWD)や各州政府、赤十字などを通じてマレーシア側から流入してくる難民に対する食糧や医療支援、また出身地の島や村への帰還のコーディネートを行うなどの支援活動を実施した。

こうした支援活動の存在にもかかわらず、避難民をとりまく状況には懸念すべき点も少なくないように筆者には感じられた。まず何より、サバから戦闘や取り締まりを避けてフィリピンに戻ってきたのは良いが、しかし故郷の村に戻ってきても仕事がない者が多く、大量にサバから避難民として帰還したフィリピン南部での経済悪化への懸念が長期的には懸念される。
また避難民のうち、とくに子供や若者など若年層の中には、実は今回のフィリピンへの脱出によって生まれて初めてフィリピンに足を踏み入れる者も少なくない。筆者がサンボアンガにおいて実施したインタビューを通じて、サバからフィリピンへ「帰還」した筈の避難民の中には、実際にはサバで生まれ育ったためにマレー語は流暢だがタガログ語は皆目分からない者がかなりの割合で存在することが確認できた。
また子供や若者のなかには先に述べたように「無国籍者」、すなわちマレーシアでもフィリピンでも出生届などを登録していないため、マレーシア市民でないのはもちろん、フィリピン人の市民権をもっていることを証明することさえ難しいという者も少なくない。こうした者がフィリピンへ帰還後に(再)就職し就業するに当たっては当然、いくつもの困難な壁に突き当たることも予想される。
まとめ
そもそもフィリピン南部のミンダナオ紛争と同紛争による難民の発生に関しては、先に述べたようにフィリピン北部から南部へのキリスト教徒の国内移民のフローが背景として存在していた。このフローは20世紀初頭以降のアメリカ植民地統治に端を発し、その後1960年代末まで入植政策として持続した。このキリスト教徒の大量の移入・入植を大きな背景として1970年代にはミンダナオ紛争が勃発し、この紛争の結果として難民として大量のフィリピン系ムスリムがサバへ渡った。すなわちフィリピンのキリスト教徒移民のミンダナオへの国内移民政策の帰結としての、ムスリム住民の強いられた脱領土化とマレーシア・サバへの難民(移民)化というのが1970年代以降の大まかなトレンドであった。
言い換えればキリスト教徒のフィリピン南部へのフローに伴って、いわば玉突きの如く、ムスリム住人が土地を追われてマレーシアへ移民/難民として数十万人規模で押し出されたのである。この「移民/難民のフローの玉突き」によるフィリピン南部からマレーシア・サバへのムスリムの難民・移民のフローは1970年代に始まり2012年まではほぼ一方向的にフローが流れていたと言える。これに対して2013年3月に起きたRSFとマレーシア治安部隊の武力衝突事件以降は、マレーシア・サバからフィリピン南部へと「再難民化」したフィリピン出身ムスリムの脱出(還流、フローの逆転)も認められた。さらにミンダナオ島のサンボアンガで2013年9月にはMNLF-MGと政府軍側の武力衝突が発生し、現地ではタウスグ人やサマ人を中心に新たに約11万人の避難民が発生する事態となった。
このようにミンダナオ紛争と和平をめぐる紆余曲折に翻弄されるかたちで、スールー諸島周辺のムスリム住民が心ならずも故郷を離れ、難民として別の土地への移動を余儀なくされるという厳しい状況が、近年においても依然として続いていると言える。
参考文献(抄)
床呂郁哉1999『越境―スールー海域世界から』岩波書店。
床呂郁哉2012 「フィリピンにおけるムスリム分離主義運動とイスラームの現在」、床呂郁哉・西井涼子・福島康博編『東南アジアのイスラーム』東京外国語大学出版会, pp.97-120。
Tokoro, Ikuya 2015 “The Re-emergence of Islam in the Context of Muslim Separatism in the Philippines.”, Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia, pp.153-174, Research Institute for languages and Cultures of Asia and Africa(ILCAA).
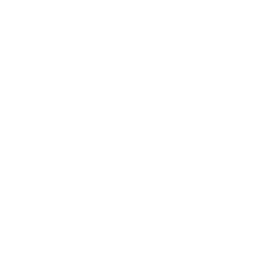
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授







