- フィリピン南部
バンサモロに関する枠組合意:その展望と課題

はじめに
フィリピン政府とモロイスラム解放戦線(Moro Islamic Liberation Front: MILF)の和平交渉は、1997年1月以来、16年間にわたって続いている。成功裏に終結するのがいったい、いつになるのか。筆者にはおよび知ることができない。成功か、失敗に終わるかは、多くの要因にかかっている。なかには紛争当事者には、どうにもできないものもある。しかし、争いを終わらせたい、という当事者の意志と責任感こそが決定的に重要である。どちらも面子を失うことなく、また損をすることもなく、和平への取り組みを成功させる方法はいくらでもあるはずだ。和平プロセスは、第三者、特に国際社会の強力なサポートを取りつけることによって、より確実に進めることができる。交渉とは結局のところ、お互いを理解しあい、見解の相違を解消することで合意に達し、当事者や他のステークホルダーらが満足する成果を生みだしたいと願う複数の人たちや集団の間で行われる対話だ。関係者全員がそのプロセスと結果に対して、当事者意識をもつことが求められる。このような取り組みにおいては、それがむずかしい課題である。
MILFのメンバーや支持者、各州や市町レベルの役人たちはもとより、一般市民の肯定的な反応から判断すると、「バンサモロにかんする枠組合意(GPH-MILF Framework Agreement on the Bangasamoro: FAB.以下、「枠組合意」)」の見通しは、きわめて明るい。以前は「先祖伝来の領域に関する合意覚書(Memorandum of Agreement on Ancestral Domain: MOA-AD)」に反対していた人たちも、今では枠組合意と和平プロセスの進展をおおむね支持している。
しかし、この前向きな姿勢はあくまで等式の一辺に過ぎない。等式にはもう一辺が存在する。以下にこの問題の両辺について述べる。そして、それに対する見解や結論については読者の判断にゆだねたい。いま事実としていえることは、枠組合意と包括的平和が達成されるか否かは、まだ決まっていない、ということだ。その成否は、和平プロセス内外のさまざまな要因や、当事者と支持者がどのように行動するかにかかっている。
交渉において失敗と成功は相対的なものだ。すなわち、和平合意に署名がされたからといって、それが成功とはかぎらない。同じように、当事者の一方または双方が、和平合意の条件の一つや二つを満たすことができないからといって、それで失敗したとはいえない。
成功と失敗は包括的に判断されるもので、そこには和平という目的もそれに向けたプロセスも含まれる。ミンダナオにおける「モロ問題」についていえば、問題の本質が提起され、互いを許すプロセスがはじまり、バンサモロで真の正常化が実現できれば、成功したといえる。反対に、失敗とは、当事者の一方が対話をやめてしまい、これまでの成果を捨て去り、和平プロセスの下地をすべて放棄し、相手に発砲しはじめるような事態をさす。こうなると、暴力が日常化する。
展望
矛盾を承知で述べると、ミンダナオにおける紛争を軍事的手段で解決することは現実的でないということにおいて、フィリピン政府とMILFは意見がほぼ一致している。紛争は人命と財産を無駄に奪う。人びとの苦しみが長引き、紛争地帯内外の発展を妨げるだけだ。戦争はこう着状態におちいり、どちらが勝者なのかすらはっきりしなくなる。
もちろん、通常戦争であればフィリピン政府軍が明らかに有利だ。しかし、戦争の勝敗は物質的、論理的な観点だけでは決まらない。戦う意志と犠牲をいとわない気持ちが軍事力と同じくらい力を発揮することも時々、いや往々にしてある。MILFはいつでも反撃できる。そして、全面的なゲリラ戦によって生き残るだろう。少数精鋭の強い意思のある兵士を使うことで、MILFはいたるところに大規模な混乱を引きおこし、破壊を行える。しかも、それをバンサモロの人びとの政治的目標と願望を損なうことなく、やってのける能力がある。だからこそ両当事者は、交渉のテーブルにつくことこそが、紛争を解決するうえで「もっとも現実的かつ文明的な方法」であると気づき、1997年1月に交渉を始めるにいたったのである。
この事実こそが、フィリピン政府とMILFの和平交渉が明るい将来にむかっていると期待できる第一の理由である。血気盛んな紛争の主唱者たちも、戦いに疲弊した人びとも、過去から脈々と受けつがれてきた争いに終止符を打つための交渉に、安らぎを覚えるにちがいない。
次に、この交渉が成功する可能性として、ベニグノ・アキノIII大統領の持ち前である誠実な人柄、人気、そしてリーダーシップがあげられる。現大統領の実母であり、フィリピンの民主化の象徴的存在である故コラソン・アキノ元大統領をのぞくと、1972年のフェルディナンド・マルコス大統領の戒厳令時代以降、これほどの強い影響力と人気を兼ね備えたフィリピン大統領はほかにいないだろう。ベニグノ・アキノIII大統領は大統領選において次点候補者に圧倒的な大差で勝利し、ジョセフ・エストラダ元大統領を退陣に追い込んだ。くわえて、アキノIII大統領の現実的な対応と政治手腕が広く国民の支持を集めている。2011年8月4日に東京近郊で行われたアルハジ・ムラド・エブラヒムMILF議長との会談については、大統領の地位をおとしめるる行為だなどとして、さまざまな方面からこの行動を非難する声があがった。しかし、これまでのところ大統領は、政府の和平交渉団を通じてMILFに伝えた約束を違えていない。考えてみてほしい。10月15日に枠組合意に調印したあと、アキノIII大統領は11月16日に行政命令(Executive Order)を発効し、移行委員会(Transitional Commission)を立ちあげた。その翌日には国会内で大統領を支持する者たちが先頭に立ち、下院・上院の両議会において、この行政命令を支持する決議案を採択した。
しかし、当事者の一方がいくら誠意をつくしても、相手がそれにこたえないと意味がない。幸いMILFは誠意を欠いていない。過去を振り返ると、停戦協定を破って血みどろの戦いを引きおこし、和平会議の行き詰まりを招いたのは、明らかにほとんどがフィリピン政府と政府軍であった。MILFはそれに応戦し、自衛したに過ぎない。思いだしてほしい。2000年にはジョセフ・エストラダ元大統領が、停戦協定と交渉の進展にもかかわらず、MILFに対して全面戦争を命じた。2003年2月11日には、グロリア・マカパガル=アロヨ元大統領が、リグアサン湿地に潜伏する身代金目的の誘拐犯を追うという口実で、またもや全面戦争を仕かけた。攻撃時、故サラマト・ハシムMILF議長はイスラム教の五行の一つ、メッカへ巡礼の成就を祝うイード・アル=アドハー(犠牲祭)の礼拝で説教をしている最中であった。2008年8月に、政府は7月27日に当事者間で仮調印したばかりの「先祖伝来の土地の領地にかんする合意書(MOA-AD)」に意図的に調印しなかった。当然ながら戦争が勃発した。
和平プロセスにとって、よいカンフル剤となっている重要なものとして、一般市民、市民社会、NGOをはじめとする社会の各セクターからの支持がある。メディア、教会関係者、研究者、女性、先住民コミュニティ、地方公務員らは、和平プロセスをおおむね支持している。一方、時々和平プロセスと枠組合意を中傷するセルソ・ロブレガット(Celso Lobregat)ザンボアンガ市長をのぞき、エマヌエル・ピニョル(Emmanuel Piñol)元北コタバト州知事やローレンス・クルス(Lawrence Cruz)イリガン市長など、かねてよりの妨害派は沈黙を守っている。枠組合意の調印によって生じた時流にそむきたくないのか、アキノIII大統領の人気に押され気味なのか。そこを判断することは難しい。
同じように、国際社会、すなわち国家と国際NGO、とりわけ国際コンタクトグループ(International Contact Group: ICG)の参加と貢献が和平プロセスの安定と促進にはたす役割は、いい表せないほど重要である。和平当事者に対して「適切な影響を与える」ことを使命とするICGの構成メンバーは、文字通りそれを十分に行っている。構成メンバーの取り組みは、当事者らの行動に影響をおよぼしている。表立って認める者はだれもいないだろうが、交渉の駆け引きは正式な当事者間だけでなく、それぞれの支援グループもふくめて行われている。そのほとんどがカメラのフラッシュや、宣伝目的の派手な演出の影でおきているのだ。
一方、和平プロセスとは直接かかわっていなくとも、自国の戦略上の権益がミンダナオにおける紛争の解決あるいは決裂とからみあい、その結果に左右される国々は、傍観席で消極的な姿勢を取るわけにはいかない。当然ながら、こうした国々は国益を優先し、それにしたがって行動するだろう。
最後に、フィリピン政府とMILFの和平プロセスでは、失敗が想定されていない。あるいは、少なくともそれが最後の手段となるよう設計されている。モロ民族解放戦線(Moro National Liberation Front: MNLF)と政府との和平協定では、署名から10年以上たったいまでも、その運用について、いい争いがつづいている。当事者たちは、その経験から多くの貴重かつ苦い教訓を学んだ。両者の和平交渉団は、1996年9月2日にフィリピン政府とMNLFとのあいだで最終和平協定が締結されると、ほどなく解散されている。いざというときの有効な監視メカニズムもなかった。MNLF指導部は競って政府内で有利な立場をえようとし、兵士らも慌てて政府軍や警察に合流していった。この2つの方法によって、バンサモロの人びとの目的は事実上挫折し、いまだに不確実な泥沼に足を取られているようだ。
フィリピン政府とMILFの和平プロセスでは、ミンダナオにICG、第三者監視団(Third Party Monitoring Team: TPMT)および国際監視団(International Monitoring Team: IMT)が展開していることにくわえ、国内外のNGOや市民社会の監視もあり、事実上いずれの当事者にも約束を破る余地は与えられていない。枠組合意の重要な責務をないがしろにしようとすれば、不利な立場におちいり、注目を浴びることとなる。自己弁護できる有効な手だてはない。ものの数秒間で地球上のあらゆるところにつながる最先端技術が現れたおかげで、合意不履行はいとも簡単に暴露され、違反した者はいい逃れをするまでもなく責苦を負う時代になった。とくに弱い者には屈辱と非難が容赦なくあびせられる。権利を侵害されたほうの当事者が、和平プロセスを回復するあらゆる手段をつくしたあとに、あえて戦争を犯してでも合意を守る義務をつらぬこうとしたら、おしまいである。事実、MILFは過去に何度かこのことを実証している。
この和平プロセスのもう一つの重要な安全装置が、当事者たちが従わなければならない移行のためのロードマップと手順を定めた「移行期の取り決めと措置(transitional arrangement and modalities)」という付属文書である。それが確実に守られるようにTPMTを結成し、バンサモロにかんする枠組合意と付属文書を中心とした、署名したすべての合意事項の実施状況について監視、点検、評価を行うのである。
その他にも以下のようなセーフティネットがある。(1)双方の和平交渉団は、未解決事項や話しあいが必要な新たな案件が生じているあいだは解散せず、協議をつづけるものとする。(2)署名したすべての協定、とくに枠組合意について、一方的な実施は認めない。(3)上述したとおり、TPMTは両当事者の誠実かつ完全な合意順守を監視するために当事者らによって結成されたものである。(4)調印されたすべての合意の履行と移行の進展について点検と評価を行うことを主な役割とするフィリピン政府、MILF和平交渉団、仲介役であるマレーシア政府ならびにTPMTから構成される正常化のための合同委員会(Joint Normalization Commission: JNC)も設置された。(5)すべての合意事項が完全に履行された場合にのみ、当事者らは和平交渉を公式に終結させるための「出口合意(Exit Agreement)」に調印できるものとする。
明るい展望を示すより具体的な例としては、2013年1月25日に両当事者はクアラルンプールにおいて第35回和平予備交渉会議を終えた。この会議では、「バンサモロにかんする枠組合意と付属文書を中心とした、署名したすべての合意事項の実施状況について監視、点検、評価を行うこと」をその役割とするTPMTへの付託条項(Term of Reference: TOR)への署名など、画期的な成果を達成した。また、権力分有(power sharing)、富の分有(wealth sharing)、暫定的な手段と措置(transitional arrangements and modalities)、正常化(normalization)にかんする4つの付属文書についての話しあいでも、大きな成果をあげた。政府側の交渉団長であるミリアム・フェレール=コロネル教授は、2013年3月にも包括的合意を実現できるとの見通しを示し、筆者もそう確信している。長く厳しい交渉を中断させる一大事がおこらないかぎり、実現可能であろう。
課題
当事者たちは、これまでさまざまな課題に直面してきた。このことは、フィリピン政府とMILF和平会談が16年にもわたっていることをみれば、明らかである。この間、4名のフィリピン大統領と11名の政府交渉団長がかかわり(MILF側の主要和平交渉団員は4名)、2000年、2003年、2008年と3つの大きな戦争が闘われた。今日にいたるまで、両者は和平プロセスをまとめようと必死の努力をつづけている。が、念願の成功はまだ手中にはない。
以下に、和平プロセスが現在直面しているむずかしさを示す例をあげる。昨年の12月12日〜15日に開催された第34回和平予備交渉会議は、TPMTへの委託事項(TOR)に署名できず、枠組合意の4つの付属文書の重要事項も解決されず、事実上行き詰ったまま終わることとなった。交渉会議の5日目には一つの公式文書に署名することなく、次回の交渉日程も定めないままに、交渉団は解散した。だが、この行き詰まりは、去る1月21〜25日に行われた交渉会議で打開することができた。

先に述べたとおり、この先の道は舗装されていない。しかも激しく曲がりくねっている。ありとあらゆる所に危険が潜んでいる。「仮に」や「もしも」が、たくさんある。「正しい法案」を可決すべき国会で、バンサモロ基本法が否決されるかもしれない。あるいは、国会では可決されても住民投票の結果、人びとに批准されなかったとしたら?新しいバンサモロ自治政府に州や市町村がほとんど加盟しないということになったら?もし最高裁判所がバンサモロ基本法を違憲だとする判決を下したら?仮に妨害派や他の抵抗勢力が武力を結集させてバンサモロ基本法に対して全面攻撃を仕掛けてきたら?
仮定や疑念はいくらでも思いつくことができる。否定的な可能性はうんざりするほど無限にあり、ともすれば絶望感に押しつぶされかねない。唯一、ポルトガルの探検家フェルディナンド・マゼランが香料をもとめてモルッカ諸島を目ざしたとき、島影一つみえない外洋にいる6ヶ月間のあいだひたすら航海をつづけ、1521年3月16日にとうとうフィリピン中部のリマサワに上陸したということに慰めを見いだすことくらいしかできない。故郷に真の平和が訪れることを切望し、悪化する状況を食い止めることを考えて、目標を達成するまでひたすら活動をつづけるのだ。今回の交渉においては、失敗を念頭におくことはしたくない。ただひたすら問題に一つずつ向きあい、解決していくだけだ。
実のところ、妨害派や他の抵抗勢力を完全に否定的な存在としてみなしているわけではない。それどころか、彼らの存在ゆえに、より一層の努力をしていく決意が固まる。こうした妨害派のおかげで、特定の問題解決に対して、クリエイティブで優れた方法や手段に気づくこともしばしばある。そして、誠実に約束を守り対話をつづけることで、妨害派の一人でも、数人でも、平和をともにつくる側につけることができれば、和平プロセス全体に対して絶大な影響をおよぼすことができる。他の妨害派を味方に引き入れたり、中立化させるためのスポークスマンとして、彼らほどの適任者はいない。あるいは、少なくとも彼らの否定的な影響力を小さくすることができる。
それでもやはり、フィリピン政府とMILFの和平交渉の成功に反対や嫌悪をむきだしにする妨害派も存在する。これまでのところ、モロ民族解放戦線(Moro National Liberation Front: MNLF)のヌル・ミスアリ(Nur Misuari)議長は和平交渉、とりわけ枠組合意をつよく非難している。彼は、和平プロセスは違憲であり、枠組合意はミンダナオでの戦争の一つのきっかけになると主張している。また、コタバト市のムスリミン・セマ(Muslimin Sema)副市長が率いるMNLFの別の派閥も、枠組合意と交渉会議でのMILFの近々の成功に不快感を隠すことができないようだ。
こうした集団は、概して枠組合意と和平プロセスの成功を妨害する。しかし、MILFではこうした一見挑発的な行為に対して冷静に対応し、逆に彼らに働きかけつづけることで、枠組合意の裏にある英知を理解してもらえることを願っている。MILFは、この枠組合意がバンサモロのすべての人びとのためであることを絶えず説明している。MILFは2期の移行期間を担うのみである。その後は、だれもが自由に政治論争に加わり、2016年に継承した者がバンサモロ政府を運営することになる。
トンネルの終わりには明るい光がみえてくるという諺がある。あえてもう一つだけ、それを妨げる要因をあげておきたい。時間的な制約である。移行委員会とバンサモロ移行局(Bangsamoro Transition Authority)という2段階の移行期間に、バンサモロ基本法を起草・実施し、国会を通過させ、採択を問う住民投票を実施する時間として、3年間が割りあてられている。そのうち、すでに2ヶ月間が費やされた。本稿執筆時点(2013年2月4日)で、当事者たちは依然として枠組合意の4つの付属文書にすら合意できていない。フィリピン政府和平交渉団が新たな団長を迎えたこともあり、さらに遅れる可能性もある。団長として彼女はまだ初心者なのである。
しかしながら、このプロセスに割りあてられた時間は、いまのところまだ決定的に足りない、というレベルには達していない。時間はまだある。努力次第でまだ間にあう。

まったくもって、和平の達成は容易なことではない。気力はくじけるし、心身はともに消耗する。天才であれ、力もちであれ、得意とする者などいない。逆にそうした者たちは、素朴で弱い者たちとの話しあいに根気が足りない傾向がある。目的と使命を背負い、忍耐力を備えた者しか、最後まで耐えぬくことはできない。結局のところ、交渉を前に進めるのは力ではない。それを動かす当事者らの共同作業なのだ。
正直なところ、和平プロセスの前途が、たとえばいまから3年後にどうなっているか、まったくわからない。課題よりも展望のほうが明るいが、私たちはまだ最終結果を知る立場にはない。相互に関連した多くの要因が、双方の前に立ちはだかるだろう。このプロセスを確実に成功させる唯一の方法は、とくに枠組合意を調印した後には、一日24時間以上働くことである。少なくともMILFは、そうするであろう。やや大げさかもしれないが、MILFが不履行をしないことを示すためには、そうするべきなのだ。
国際社会、とくに日本は、フィリピン政府とMILFの和平プロセスと枠組合意の成功を推し進める力をもっている。現在、日本が和平プロセスに対して公式、非公式に行っている援助は非常にすばらしく、おそらくはこれに匹敵する援助を提供している国はほとんどない。さらなる援助を切にお願いしたい。
From P’s Pod, vol. I, no 3. March 2013
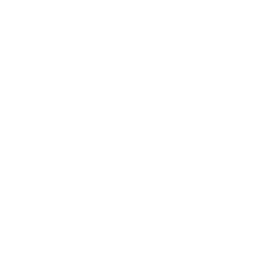
MILF和平交渉団長
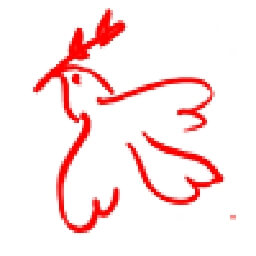
『P’s Pod(ピースポ)』に掲載されている論文・記事は、指定のない限り、著者本人の個人的な意見や見解を反映したものであり、著者の所属する役職や組織、または特定の組織、団体やグループなど(著者及び編集委員会を構成する大学等も含む)の意見や見解を反映するものではありません。







