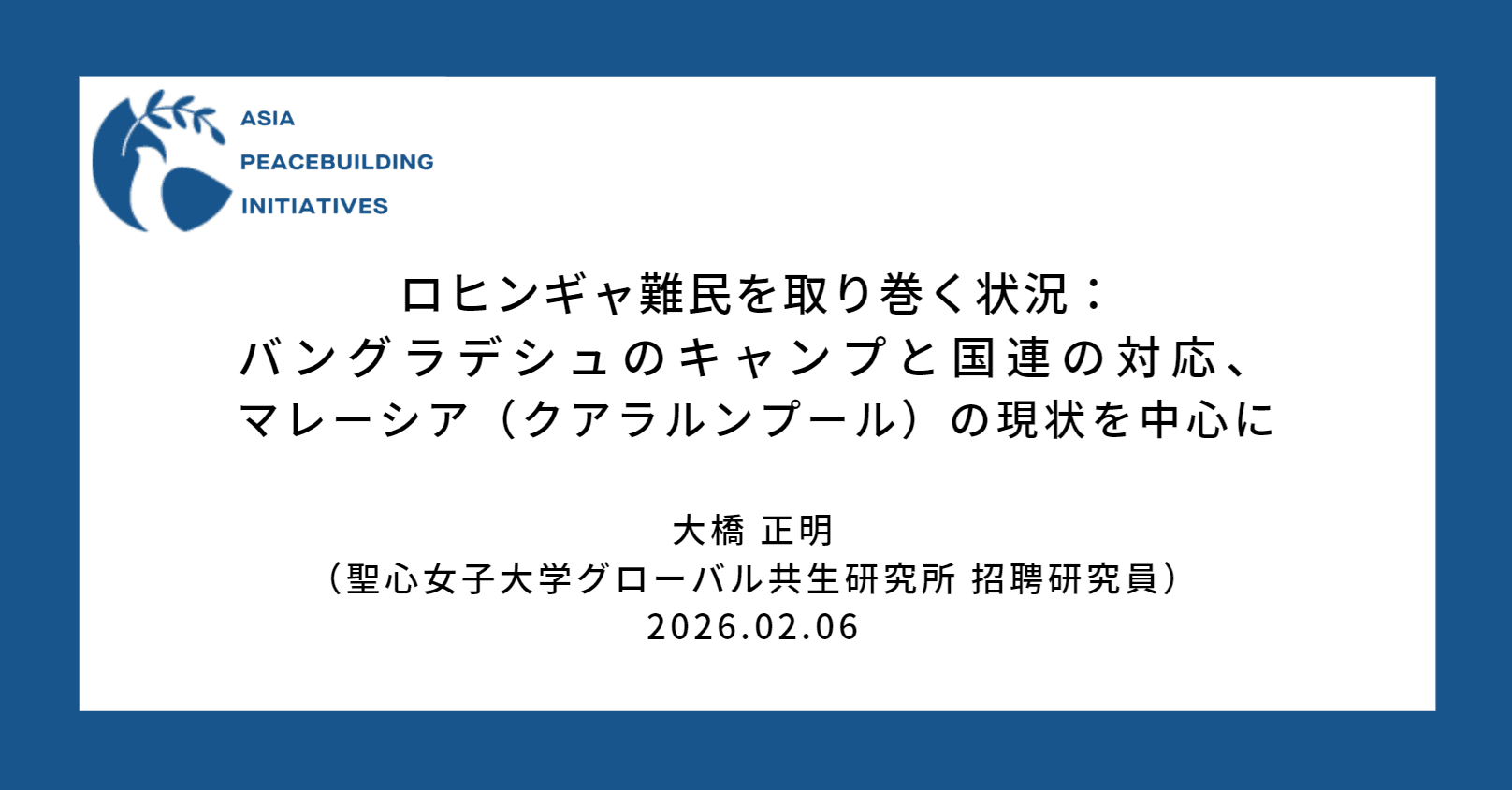- バングラデシュ
ジュマの内部組織

【入植政策、軍事化の中で】
バングラデシュ独立後のチッタゴン丘陵では、平野部からベンガル人を連れてくる入植政策と大勢の軍を配備し、軍事キャンプを建設する政策が推し進められた。ジュマ側は政府の入植政策に反対し、自決権を求め、1972年に政治組織であるチッタゴン丘陵民族統一党(PCJSS)を設立し、1973年には武装部門であるシャンティ・バヒニ(平和軍)が結成され、ゲリラ化して抵抗を始めた。1977年にはチッタゴン丘陵に駐屯する軍の司令官が、「あなたがた先住民族は必要ない。どこへでも行ってくれ。我々がほしいのはあなたがたの土地だけなのだ」と発言し[1]、その後も、土地や家の建設費用の提供、1年間の食糧配給といった支援を約束された入植者が、40万人規模でチッタゴン丘陵に入ってきた。これは当時のジュマ人口とほぼ同じ人口であった。入植政策の目的は主に2つだっただろうと、研究者であり当時を知るジュマのM氏はインタビューに「1つは、軍用地の周囲を入植者で固め、ジュマが軍を襲うときにまずは一般入植者が先に襲われる構図を作った。2つ目は、ジュマをこの地域のマイノリティにするため」と答えた。治安の維持を名目に、政府はチッタゴン丘陵に推定1万人〜3万人の軍を配備した。ジュマネットの報告書[2]によると、こうした状況は1992年まで続き、その間、13回を超えるジュマの人々に対する虐殺や暴力事件が発生した。これにより、7,000人以上の死者が発生し、6万人近い人々が難民としてインドのトリプラ州の国境沿いに避難したという。一般人やメディア関係者のチッタゴン丘陵への立ち入り制限が強化されるなか、ジュマの人々への弾圧が行われた。世界からは見えない国内での紛争であった。
【和平協定と新しい特別自治制度】
1997年12月2日、長い交渉を経てインドの仲介の下で和平協定(正式名称:Chittagong Hill Tracts Accord)が調印され、20数年続いた内戦は終結した。シャンティ・バヒニは武装解除に応じた。そのときの様子はこう語られる。
ゲリラ運動の上部組織、ジャナ・サマティ・サミティ(JSS)とバングラデシュ政府との間でチッタゴン丘陵協定が調印された。1,000人以上の平和軍は、カグラチャリ・スタジアムで2,500人の公式招待客の前で、正式に彼らの武器を放棄した。[3]
和平協定に沿って、特別な自治行政制度が導入された。1998年7月15日には新しくチッタゴン丘陵地帯省(Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs)が設立された。1989年に設置されていたランガマティ県評議会法(Rangamati Hill District Council Act)は和平協定に合わせたかたちに修正され、自治行政組織にあたる3つの県評議会ができた。また、チッタゴン丘陵地帯地域評議会法(Chittagong Hill Tracts Regional Council Act)も制定され、県評議会を統括し、一般行政、治安維持、開発に関する事項を監督・調整する地域評議会(RC:Regional Council)が創設された。和平協定の結果、ジュマの明確な自治意識と準国家的な社会システムをもつという期待が高まった。また、和平協定は各県評議会にチッタゴン丘陵地帯の行政の管轄権を与えることとなり、33分野が中央政府から県評議会へと権限移譲されることになった。権限移譲された行政分野は、以下の通りである。
土地の管理、地方の警察権、慣習法と社会規範、若者の福祉、環境保全と開発、地域観光、地方都市とユニオン評議会以外の地方行政の監督権、ローカルな取引とビジネスへの許可、小川・運河・カプタイ湖以外の湖・灌漑システムの水資源の正しい利用、死亡記録・出生記録などの統計の保存、金銭の貸し出しと取引、焼畑農業、税金、各種使用料、料金の徴収等[4]
【分裂するジュマグループと近年の動き】
この和平協定をめぐる意見の対立から、ジュマ内での「兄弟殺し」ともいわれる暴力的抗争が続いている。紛争時はゲリラとして戦い、中央政府との停戦にこぎつけたジュマの政治組織PCJSSから和平協定の内容が不十分だとし、完全自治を目指すジュマの政府組織・人民民主統一戦線(United People’s Democratic Front:以下UPDF)が決別し、対立が続く。2003〜06年の死者は推定56人、2007〜13年の死者は77人との報告がある[5]。2015年時点でも死者が出るレベルの事件やニュース[6]があった。この動きに対して、何度か対話の場を設けることを試みる外部のNGOが存在したが、両者の対立は根深く、うまく進んでいるとは言い難い。2015年8月15日には和平協定後初めて、PCJSSと政府の治安維持軍との間で死者が出る衝突が起こった。たびたび起こるジュマ同士の抗争は、バングラデシュ軍が「治安の安定のために」チッタゴン丘陵に駐屯し続ける口実を作っている。そんな中でも、近年、チッタゴン丘陵市民協議会(Chittagong Hill Tracts Citizen’s Committee)という活動家・有識者による市民グループができたり、外国に暮らすジュマの若者がチッタゴン丘陵財団(Chittagong Hill Tracts Foundation)という団体を作り、海外からのイニシアチブを高めたりする動きも出ている。PCJSSの学生組織であるPCP(チッタゴン丘陵地帯学生協議会)も、和平協定の調印記念日には毎年、完全実施を求めるPR活動を行ったり、チッタゴン丘陵でジュマへの襲撃事件や女性のレイプ事件が起こると抗議デモを招集したりしている。リーダー格の青年は「ぼくたちが声を上げ続けない限り、政府はチッタゴン丘陵の問題を覆い隠し、なかったことにしてしまう。ダッカでこうして声をかたちにしていくことが、ベンガル人社会への意識の変化になると信じている」と語る。彼らは、地域や民族に対する愛着心も大きいが、ベンガル人学生とも仲が良く、次の世代を牽引することができるかもしれない。ただ一点懸念としては、武器をもって戦うことも、彼らの選択肢には存在することである。2014年、PCJSSのリーダーであるショント・ラルマ氏が「和平協定の実施に対し政府が努力を見せないならば、武器をもっての闘いも辞さない」との声明を発表した。そのときに、普段はダッカで学んでいる若者たちが、実際にチッタゴン丘陵に大勢戻ってきたのである。政治活動に積極的ではない若者であっても、武器の輸入ルート(インド国境経由と言われる)について知っており、若いがゆえに火がついたときになにが起こるかはわからない側面もある。ジュマが武力によらない方法で団結し、声をひとつにまとめられるかが、いま問われている。

[1] Drishtipat Writers’ Collective, 2010, 『Between Ashes and Hope -Chittagong Hill Tracts in the Blind Spot of Bangladesh Nationalism』, 27頁。
[2] 下澤嶽、トム・エルキルセン、後藤光利 2007『チッタゴン丘陵白書 ~バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯の先住民族 ~ 紛争・人権・開発・土地問題2003~2006』ジュマ・ネット.50頁。
[3] アンジェラ・ジェフ(田形圭訳)「民族人権活動家、保護を求める–ジュマは丘陵地帯民族の抑圧意識を高める」1999 ジャパンタイムズ〈http://www.asahi-net.or.jp/~vi6k-mrmt/m99-bg1.htm〉2015年12月24日参照。
[4] ランガマティ県評議会資料「Transferred subject/office/department」
[5] 下澤嶽、トム・エルキルセン、日下部尚徳、木村真希子 2014『チッタゴン丘陵白書~バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯の先住民族 ~紛争・人権・開発・土地問題2007~2013』ジュマ・ネット.74頁。
[6] bd news24.com, “Five JSS activists killed during clash with security forces in Rangamati: Police” http://bdnews24.com/bangladesh/2015/08/15/five-jss-activists-killed-during-clash-with-security-forces-in-rangamati-police 2015年12月20日参照。

東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻「人間の安全保障プログラム」修士課程在籍中。大学3年時、チッタゴン丘陵地帯に出会う。教育NGO・ちぇれめいえプロジェクトを仲間と立ち上げ、NGOの駐在員として1年間先住民族の村に滞在。その後、国連開発計画(UNDP)、チッタゴン丘陵地帯開発ファシリティ(Chittagong Hill Tract Development Facility)にて半年間、平和構築のプロジェクトにインターンとして携わった。