日刊『まにら新聞』(http://www.manila-shimbun.com/)
Minda News(http://www.mindanews.com/)
Daily Inquirer(http://www.inquirer.net/)
Philippine Star(http://www.philstar.com/)
ABS-CBN News(http://www.abs-cbnnews.com/)
GMA News Online(http://www.gmanetwork.com/news/)
Manila Bulletin(http://www.mb.com.ph/)
- アーカイブ
February 2015: Southern Philippines

1) 国警長官が引責辞任
プリシマ国家警察長官(2014年12月から停職中)が6日までに、辞表を大統領に提出し、受理された。大統領が同日夕のテレビ演説で公表した。特殊部隊の警官44人ら約70人が死亡したテロリスト追跡作戦と停職原因の汚職疑惑を受けた引責辞任。
作戦を実施した国家警察特殊部隊のナペニャス前隊長は、同作戦に関する上院聴聞会などで、プリシマ長官が①停職中に同作戦の準備、実行を統括、②アキノ大統領に国軍との連携を密に取るよう指示を受けたにもかかわらず、ロハス内務自治長官や国家警察上層部、国軍に内密に準備を進めるよう指示した、と証言。同長官も大筋で認めており、行政監察院は停職命令に従わなかった同長官の再処分を検討している。
今回の事件では、連携不足による国軍の支援の遅れが被害拡大の最大の要因とされ、事前に作戦の情報を把握していた大統領の指揮、判断の責任を問う声も上がっている。
2) イクバル団長、和平プロセスの前進訴え
反政府武装勢力モロイスラム解放戦線(MILF)のイクバル和平交渉団長は12日、テロリスト追跡作戦に関する上院聴聞会に、初めて出席した。作戦実行時に発生したMILFとの交戦に遺憾の意を表明した上で、バンサモロ基本法案審議など和平プロセスを前進させるよう訴えた。
同団長は、追跡作戦と交戦について①交戦再発を防止するため、第三者機関による独立性の高い原因調査が必要、②作戦対象となった容疑者2人とMILFは無関係、③2人が潜伏していた場所はMILF支配域外、などと強調した。
また、バンサモロ基本法案の国会審議中断に関しては、17年に及ぶ交渉を経て法案策定にたどり着いた経緯を踏まえ、「和平プロセスは、次世代につなぐ希望と夢。われわれは、この機会を17年間、待ち続けた。今回の不運な出来事を理由に、和平と正義を実現するための取り組みを台無しにしないでほしい」と、早期の審議再開を訴えた。
審議を中断している上院地方自治委員会のマルコス委員長は先に、中断により当初目標だった3月20日までの法案可決は「もはや不可能」との見方を示した。住民投票やMILF構成員の武装解除など、法案可決後に始まる新自治政府創設の準備には、少なくとも1年を要するとみられ、可決時期が5月以降にずれ込めば、次期大統領選(2016年5月)と同時実施を目指す、新自治政府の議会選実施も危ぶまれる。
一部国会議員からは、法案の修正、見直しを求める声が出ているが、政府、MILF共に、和平合意に基づいて起草された原案通りの可決を強く訴えている。
3) 情報収集で米政府関係者が作戦実施に関与
コロマ大統領府報道班長は17日、マラカニアン宮殿で行った記者会見で、国家警察特殊部隊のテロリスト追跡作戦に、米政府関係者が関与したことを初めて認めた。関与の内容は、作戦実行に必要な情報の収集・共有。現地指揮所に人員を送り込み、米軍の無人偵察機で得た情報などを提供していたとみられる。外国軍の直接戦闘参加は憲法で禁じられており、今後、憲法論議に発展する可能性もある。
政府と在比米大使館は先に、死亡した警官44人らの救出・収容に限定した支援を米側が行ったことを認めた。一方で、作戦への直接的な関与は一貫して否定してきたが、一部報道などで現地指揮所に出入りする米政府関係者や無人偵察機の目撃情報が相次いで浮上。米が作戦実施にかかわったとの見方が強まっていた。
記者会見で同報道班長は、追跡作戦の対象となった容疑者2人について、比米当局が手配中の「国際テロリスト」だったことをあらためて指摘。国境を越えて活動するテロ組織に対処するためには、米国など他国との連携が必要と説明、追跡作戦への米関与の正当性を強調した。
4) MILF対BIFF交戦長期化で国軍介入へ
マギンダナオ州パガルガン町で14日、MILFとBIFFとみられる武装集団による交戦が発生。収束しないまま、隣接する同州ダトゥモンタワル、コタバト州ピキット両町などに戦闘地域が拡大している。事態の悪化を避け、国軍は介入を控えていたが、戦闘拡大で避難住民は2万人を超えており、カタパン参謀総長は19日、近く部隊を投入し、収拾を図る方針を明らかにした。
両州に点在するMILF支配地域に国軍部隊が不用意に入った場合、MILF部隊との遭遇戦が発生する恐れがある。このため、約70人が死亡したテロリスト追跡作戦の再発防止、BIFFを含めた「三つどもえ」の交戦を避けるため、MILFと連携を取りながら掃討作戦を進めるとみられる。
今回の交戦原因は、主にリドと呼ばれる異なる親族集団の間の対立、BIFF構成員によるMILF支配域通過をめぐるトラブル、の2点が指摘されている。
5) MILFとBIFFの交戦、10日ぶりに収束
6) MILF、国軍・警察からの武器横流し認める
MILFのイクバル和平交渉団長は25日、マニラ首都圏のテレビ局の取材に対し、アロヨ前政権下の2001〜2010年、国家警察と国軍から銃器類の横流しを受けたことを明らかにした。種類や数量、頻度など詳細には言及しなかった。
同団長によると、銃器類の調達先は国家警察、国軍の関係者と密輸品などを扱う武器商人。1960年代の武装蜂起当時から使い続けている武器もあるという。
マギンダナオ州内などに、武器製造所を保有していたことも認めた。しかし、現政権下で和平プロセスが進展したことに触れながら、「(MILF戦闘員が)武装解除されるので、もう武器は製造していない」と語った。
兵力1万人以上とされるMILFの保有火器数は「1万1千以下」と説明。正確な数量については「(武装解除を実施する)独立機関に通知済み」と明らかにしなかった。
Mindanao, February 2015
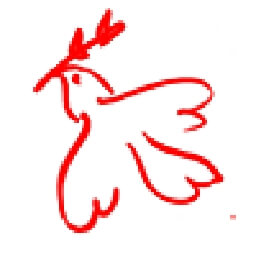
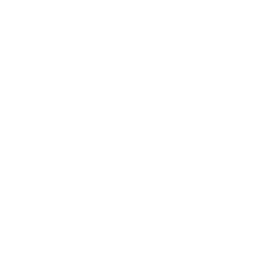
フィリピン在住







