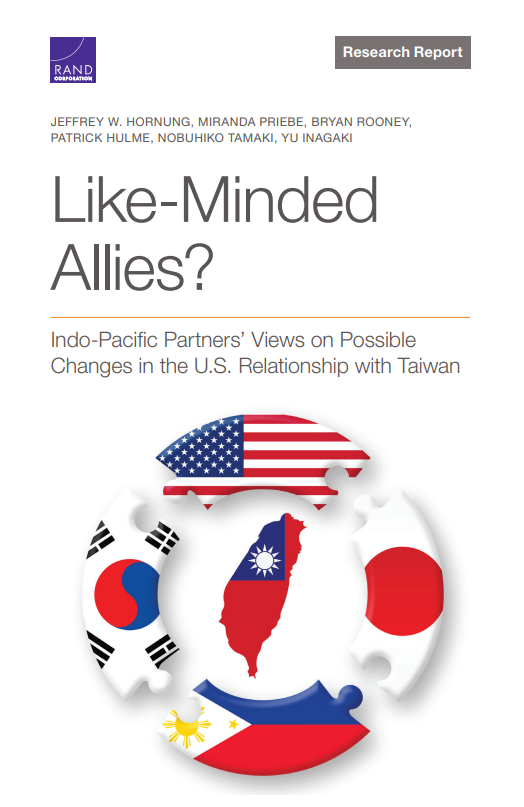【報告書】※本報告書に関するウェビナー動画を公開しました(10/17追記)
Like-Minded Allies? Indo-Pacific Partners’ Views on Possible Changes in the U.S. Relationship with Taiwan
米台関係の変化に対するインド太平洋のパートナーの見方
ジェフリー・ホーナン(ランド研究所)
ミランダ・プリーブ(ランド研究所)
ブライアン・ルーニー(ランド研究所)
パトリック・ハルム(ハーバード・ケネディ・スクール)
玉置敦彦(中央大学)
稲垣悠(笹川平和財団)
ウェビナー動画(日本語版)
| (1)収録日 | 2023年10月5日(木) |
| (2)パネリスト | ジェフリー・ホーナン氏(ランド研究所)
ミランダ・プリーブ氏(ランド研究所)
ブライアン・ルーニー氏(ランド研究所) 木場紗綾氏(神戸市外国語大学) 渡部恒雄氏(笹川平和財団) |
| (3)本動画内使用言語 | 日本語・英語(同時通訳) |
| (4)主催 | 公益財団法人 笹川平和財団 |
中国の台頭、ロシアによるウクライナ侵攻に直面する中で、台湾をめぐる議論は米国でも活発化していますが、こうした議論はもっぱら戦略的曖昧性を維持すべきなのかどうかという二者択一的な議論に終始しています。これは米国の政策が中国の台湾侵攻可能性にどう影響するかという点が中心となっています。その一方、本報告書では、米国の同盟国に着目し、米国の台湾政策の変化にこれらの国がどのように評価・反応するかを論じています。ペロシ下院議長(当時)の訪台やバイデン大統領の台湾防衛をめぐる発言といった米国の言動を同盟国は注視しています。本報告書では具体的に、①日本、②韓国、③フィリピンというの3つの同盟国を比較分析しています。
まず本報告書では、米国の台湾政策について、従来の戦略的曖昧性か否かという二分法にとらわれず、米国の政策変更を示すシグナリングの領域として外交、インテリジェンス、軍事、経済の4つを提示しています。この枠組みを踏まえたうえで、各同盟国に関して、対台関係の歴史的背景、現在の台湾に対する見方、そして米国の台湾政策の変化(外交、インテリジェンス、軍事、経済)にどう反応するかを歴史研究、関係者へのインタビューを通じて明らかにし、米国は今後の台湾政策を考えていくうえでどのような示唆が得られるか分析しています。
詳細
- 日本は、米国が外交や軍事の面で台湾への支援を強化することを歓迎し、自身も同じようなポジションをとる。
- 一方でフィリピンと韓国は、米国が目立つような形で外交・軍事における台湾支援を強化することに対して抵抗がある。
- 3か国ともに米台間の情報共有に関しては中立的で、経済関係の強化については支持している。
- 3か国ともに米国が台湾支援を低下させることは台湾海峡の不安定化につながると考え、反対している。
- 3か国ともに米国の台湾支援の低下を自分たちの安全保障へのコミットメントの低下とみている。
- 日韓は米国との同盟を重視しているため、米国の信頼性に対する懸念は、米国との距離を縮める動きにつながる。
- 過去の事例から米国の信頼性への懸念に対する反応は、誰が政権のリーダーなのかやその時の中国の行動によって変わってくる。
詳細
CHAPTER 1 Introduction/第1章 イントロダクション
- The Contemporary U.S. Debate (現在のアメリカにおける議論)
- Policy Options for Signaling a Change in the U.S. Relationship with Taiwan(米台関係の変化を示す政策オプション)
- Methodology(手法)
- Report Road Map(報告書の構成)
CHAPTER 2 History of the U.S. Security Relationship with Taiwan/第2章 米台安全保障関係の歴史
- 1949-1950: Decision Not to Defend Nationalist Forces on Taiwan (1949-1950: 国民党勢力を守らないという決断)
- 1950-1955: The United States Declares It Will Defend Taiwan (1950-1955: 台湾防衛を宣言するアメリカ)
- 1955-1979: U.S. Alliance with Taiwan(1955-1979: 米華相互防衛条約)
- 1970s-1980s: U.S.-Taiwan Relations Change; Strategic Ambiguity Is Born(1970s-1980s: 米台関係の変化、戦略的曖昧性の誕生)
- Post-Cold War Developments: Strategic Ambiguity Under Stress(冷戦後の進展:戦略的曖昧性の揺らぎ)
- Conclusion(結論)
CHAPTER 3 Japan/第3章 日本
- History of Japan’s Relations with Taiwan(日台関係の歴史)
- Relations with China and the United States: Alignment with the United States(中国、アメリカとの関係:アメリカとの同盟)
- View of Taiwan: Directly Linked to Japan’s Security(台湾に対する見方:日本の安全保障への直接的な影響)
- Japanese Views of Hypothetical Changes in U.S. Taiwan Policy (アメリカの台湾政策の変化に対する日本の見方)
- Conclusion(結論)
CHAPTER 4 The Republic of Korea/第4章 韓国
- History of South Korea’s Relations with Taiwan(韓台関係の歴史)
- Relations with China and the United States: Revolves Around North Korea(中国、アメリカとの関係:北朝鮮をめぐる問題)
- View of Taiwan: Not a Direct Priority(台湾に対する見方:高くない優先順位)
- ROK Views of Hypothetical Changes in U.S. Taiwan Policy(アメリカの台湾政策の変化に対する韓国の見方)
- Conclusion(結論)
CHAPTER 5 The Philippines/第5章 フィリピン
- History of the Philippines' Relations with Taiwan(比台関係の歴史)
- Relations with China and the United States: Balancing Between Countries(中国、アメリカとの関係:バランシング)
- View of Taiwan: Not a Primary Concern Historically(台湾に対する見方:歴史的には主要な問題ではなかった)
- Philippine Views of Hypothetical Changes in U.S. Taiwan Policy(アメリカの台湾政策の変化に対するフィリピンの見方)
- Conclusion(結論)
CHAPTER 6 Findings/第6章 結論
- Allies’ Potential Reactions to Increased U.S. Support to Taiwan(アメリカが台湾支援を強化した場合の同盟国の反応)
- Potential Responses to Reductions in U.S. Support to Taiwan(アメリカが台湾支援を弱めた場合の同盟国の反応)
- Final Thoughts(あとがき)

執筆者
Jeffrey W. Hornung(ジェフリー・ホーナン)
プロフィール
ランド研究所上級政治研究員。専門は日本の外交・安全保障政策、東アジアの安全保障問題、同盟関係を含むインド太平洋地域における米国の外交・防衛政策。
2017年4月にランド研究所に入所する以前は、2015年から2017年まで笹川平和財団米国で外交・安全保障プログラムのフェロー、2010年から2015年までは、ホノルルにある国防総省の研究機関、ダニエル・イノウエ・アジア太平洋安全保障研究センターで准教授を務めた。
日本の安全保障や外交政策、またより広範な北東アジアの安全保障問題について、Washington Quarterly、Asian Survey、Foreign Policy、New York Times、Washington Post、War on the Rocks、読売新聞、朝日新聞など数多くのメディア、政策・学術誌に寄稿している。
1991年の湾岸戦争と2003年のイラク戦争における日本の自衛隊派遣の意思決定に関する博士論文を執筆し、ジョージ・ワシントン大学より博士号を取得。2005年から2006年にかけては、フルブライト・フェローとして東京大学に客員研究員として滞在し、研究を行った。また、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)で日本研究を専攻し、国際関係学の修士号を取得した。

執筆者
Miranda Priebe(ミランダ・プリーブ)
プロフィール
ランド研究所 米国のグランド・ストラテジー研究センターディレクター兼上級政治研究員。ランド研究所では、グランド・ストラテジー、将来的な国際秩序、米軍の前方プレゼンスの効果、軍事ドクトリン、米軍事政策史、分散航空作戦、マルチドメイン指揮統制などの研究に従事。また、抑止、安心供与、脅威認識、新興国、同盟政治、米国の国防予算に関する研究も行っている。マサチューセッツ工科大学で政治学の博士号を取得。プリンストン大学ウッドロー・ウィルソンスクールで公共政策修士号、マサチューセッツ工科大学で物理学と政治学の理学士号を取得。

執筆者
Bryan Rooney(ブライアン・ルーニー)
プロフィール
ランド研究所政治研究員。ランド研究所では、ウォーゲーム、同盟国やパートナーとの協力、グランド・ストラテジー、大国間競争における抑止力とエスカレーションを中心に研究。それ以前は、国内政治と国際紛争の相互作用、民主主義国家における非常事態、独裁化、国家能力、同盟力学などを研究。2011年にボストン・カレッジで政治学の学士号を、2017年にヴァンダービルト大学政治学研究科で博士号を取得。また、マドリードのカルロス3世-フアン・マーチ研究所のジュニア・リサーチ・フェローを務めた経験もある。

執筆者
Patrick Hulme(パトリック・ハルム)
プロフィール
ハーバード大学ジョン・F・ケネディ公共政策大学院ベルファー科学・国際問題研究センターポスト・ドクトラル・フェロー。2023年5月にカリフォルニア大学サンディエゴ校で政治学の博士号を取得。2022年夏にはランド研究所米国グランドストラテジー研究センターのサマーアソシエイト、2020-2021年度にはノートルダム大学国際安全保障センターのハンス・J・モーゲンソーフェローを務めた。研究関心は、米国の外交政策における議会と行政の関係、憲法、抑止論、米中関係など。平和安全保障研究センター(cPASS)と21世紀中国センターの大学院生研究員を経て、現在はカリフォルニア大学 グローバル紛争・協力研究所(IGCC)の非駐在フェロー。研究成果は、International Studies Quarterly、The National Interest、The Diplomat、Lawfareなどに掲載されている。また、大統領、米国議会、冷戦に関する授業の講師を務めた経験もある。カリフォルニア大学デービス校で経済学の学士号(副専攻は中国語)を、カリフォルニア大学ロサアンゼルス校ロースクールで法学博士号(国際法・比較法専攻)を取得。

執筆者
玉置敦彦
プロフィール
中央大学法学部准教授。東京大学客員研究員。アジア太平洋地域における同盟政治と国際関係を研究テーマとしている。東京大学で、学士号、修士号、博士号を取得。2009年から2010年までフルブライト留学生としてボストン大学、2011年から2012年まで客員研究助手としてイェール大学に留学。近著に"Japan's Question for Rules-based International Order: The Japan-U.S. alliance and the decline of U.S. liberal hegemony," Contemporary Politics, Vol. 26, No. 4 (2020)、"Japan and International Organizations"(with Phillip Y. Lipscy)in Robert J. Pekkanen and Saadia M. Pekkanen eds., The Oxford Handbook of Japanese Politics. (Oxford University Press, 2022).

執筆者
稲垣悠
プロフィール
笹川平和財団日米グループ研究員。専門は国際秩序、国際関係理論、インド太平洋地域の安全保障など。2020年からはパシフィック・フォーラムのヤング・リーダーズ・プログラムのメンバーを務め、日米同盟などの研究に従事。2018年に学習院大学法学部政治学科で学士号、2020年にジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)で国際関係論の修士号を取得。
| (1)刊行日 | 2023年7月20日 |
|---|---|
| (2)執筆者 | ジェフリー・ホーナン氏(ランド研究所) ミランダ・プリーブ氏(ランド研究所) ブライアン・ルーニー氏(ランド研究所) パトリック・ハルム氏(ハーバード・ケネディ・スクール) 玉置敦彦氏(中央大学) 稲垣悠氏(笹川平和財団) |
| (3)言語 | 英語 |
*本報告者の内容は全て参加者個人の見解によるものであり、笹川平和財団、また執筆者の所属する機関の見解を代表するものではありません。