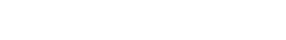論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第69回 2025/05/01
「一つの中国」からの卒業?
シンクタンクでの議論
昨年末から今年初めにかけて、民間シンクタンクによる日米豪、日豪比の三か国会合に相次いで出席する機会があった。
前者は、豪州シドニー大学米国研究センターがシドニーで開催したもので、日本からは兼原信克常務理事率いる笹川平和財団チームが参加し、上級フェローの私も加わった。後者は、私が役員を務めている豪州キャンベラのシンクタンク「地域安全保障研究所」(Institute for Regional Security)が主催してマニラで開催された会議で、日本からは岩崎茂元自衛隊統合幕僚長、三谷秀士元内閣情報官らが参加した。相対する米、豪、比各国からは、元外相、元政府高官、元駐米大使といった錚々たる面々が参加し、政府ハイレベルでの実務経験に基づいた掘り下げた議論が行われたのが印象的だった。
いずれにおいても最大の関心は、中国の攻撃的な戦狼外交と急激な軍事大国化に如何に向き合い、どのようにして台湾海峡有事を予防していくかという問題にあった。有事を防ぐための抑止力の強化、そして万が一抑止が崩れた場合の対処能力を向上させておくことに異論はなかったが、その関連で複数の論者が「一つの中国」こそを梃に使うべきとの議論を提起したことが筆者の関心を惹いた。いずれの会議もチャタムハウスルールで行われたものであり、発言者を明らかにすることはできないが、その内容は誠に興味深く、ここに共有することとしたい。
「一つの中国」の起源
むろん、「一つの中国」とは、中華人民共和国政府が中国唯一の合法政府であり、台湾は中国の領土の不可分な一部であるとする中国の立場だ。日本との国交正常化を進めるに当たって周恩来が打ち出した「復交三原則」の第一原則と第二原則にあたる。
1970年代初頭、日本やアメリカが台湾の中華民国政府との外交関係を断ち、北京の中華人民共和国政府との外交関係を開設するに当たって中国側が一番こだわったのはこの点だ。
アメリカ政府は、中国側の立場を「認める」(acknowledge)とし、日本政府は中国側の立場を「十分理解し、かつ、尊重する」とした。
日本がこうした対応を行った背景には、国際法上の理屈がある。すなわち、日本は大東亜戦争敗戦後に締結したサンフランシスコ平和条約で「台湾、澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」(第二条(b))として日本の領土権を放棄した。したがって、台湾の将来は、法的に言えば、サンフランシスコ平和条約で取り決められるべきであった。
しかるに、内戦状態が続いていた中国共産党(以下、中共)、中華民国政府のいずれの代表もサンフランシスコ講和会議に招かれなかった当時の国際情勢の下、連合国は何らの決定を行わなかった。このような状況にあっては、日本としては、台湾を中共の領土と認める立場にはないという法理論であった。
そのため、「一つの中国」について、アメリカは「認める(acknowledge)」とし、他の連合国は「留意する(take note)」 や「異を唱えない(not challenge)」といった表現も用いてきた一方で、日本は「十分理解し、尊重する」と一歩踏み込んだものの、垣根を越えることはなかったのである。当時外務省条約課長として日中共同声明の作成にあたった栗山尚一は以下のように吐露している。
「アメリカが承認していないものを日本が承認するわけにはいかないということで、承認まで行かないところで、中国と妥協できるところを探りましょうというのが、台湾の法的地位についての基本的な知恵の出しどころだったわけです」[1]
台湾問題の平和的解決
いずれにせよ大事なことは、アメリカその他の連合国、日本のいずれも「一つの中国」に同意もしていなければ、「受け入れる」ともしていないことである。そして、大事な前提は台湾問題の平和的解決であって、すべてはその前提に立った上での話であることだ。
実際、前述の栗山が北京での日中交渉用に作成した対中説明要領には、台湾は「中国の国内問題として解決されるべきもの」だが、同時に、「米中間の軍事的対決は避けられなくてはならないと言うのがすべての日本国民の念願である以上、台湾問題はあくまでも平和的に解決されなくてはならないと言うのが日本政府の基本的見解である」との記述がある。[2]
中国との関係正常化をして以降、アメリカも日本も、台湾との関係は「非政府の実務関係」ということで外交当局とは別に設置した民間機関を通じて維持してきた。かたや、「一つの中国」を金科玉条視する中国は米台、日台の関係強化に事あるたびに神経を高ぶらせて反発してきた。例えば、2022年のナンシー・ペロシ米国下院議長の台湾訪問に対しては強烈に反発し、台湾周辺で大規模な軍事演習を行い、その際、日本の排他的経済水域に5発もの弾道ミサイルを撃ち込んできたことは記憶に新しい。行政府の一員でない立法府の人間が台湾を訪問することは「非政府の実務関係」に照らして何ら問題なく、下院議長の台湾訪問の前例もあった。にもかかわらず、あれほどまでに激烈な反発を示したことは、台湾統一を宣明して止むことなく、かつ、武力の行使さえ排除しない習近平の中国が「一つの中国」を手前勝手に解釈し、その縛りを年々強化しつつあることを如実に示している。
如何に抑止力を強化するか?
上記のシンクタンクでの論者の指摘は、中国がそこまで「一つの中国」に拘泥するのであればむしろそれを逆手にとって抑止力を強めてはどうかとの発想だ。すなわち、仮に中国人民解放軍が「台湾統一」の初動として金門島や馬祖列島への侵攻など武力の行使に踏み切った場合、「一つの中国」という擬制は画餅に帰し、アメリカや日本が台湾を国家として承認し外交関係を開設する、その旨を予め宣言して中国による危険な冒険主義にブレーキをかけておいたらどうか、という問題提起だった。中国の武力行使に対する明確な「懲罰」にもなるとの発想もある。
振り返れば、「一つの中国」という擬制にニクソン&キッシンジャー、田中角栄&大平正芳が乗ってから既に半世紀余りが過ぎた。この間、何が起きたか?
台湾は中国大陸に先駆けて先進経済への発展を遂げることに成功した。今や世界の半導体は台湾無くして語れない。政治面では選挙を通じた平和裡の政権交代を幾度となく実現し、東アジアに冠たる民主主義体制として確固とした足跡を残してきた。国際社会では、APECや WTOといった国際機関・枠組みにおいて「独立の関税地域」として「中国」や「香港」と並んで貢献してきた実績がある。また、行儀の良い訪日観光客や東日本大震災の義援金をあげるまでもなく、最も親日的な「外国」であることは周知の事実だ。プレミア12での優勝は野球も日台を結ぶ大事な紐帯であることを印象付けた。
その台湾にあっても、蔣介石時代は「一つの中国」との立場に立っていたことは周知のとおりだ。
ニクソンは「自分は蔣介石、周恩来と話し合ったわけであるが、すべてについて異なるこの両人が「中国は一つ」との点については、共通の考え方を持っている。問題はどちらの中国か、ということである」と述べたと伝えられている。[3]
しかしながら、その台湾では、今や自らは中国人と捉えるよりも「台湾人」と捉えるアイデンティティーが確立してきている。
「キッシンジャー・フォーミュラ」を見直す時期が来ているのではないだろうか?