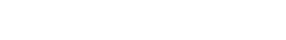論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第68回 2025/03/24
ダライ・ラマ「高齢化」問題と中国
――次のダライ・ラマ選定問題を中心に――
はじめに
昨今、いわゆるチベット亡命政府(「中央チベット政権」)[1]をはじめ、各地のチベット人コミュニティにおいて懸念されている問題がある。すなわち、チベットにおける宗教的な最高指導者であり、今年、90歳を迎えるダライ・ラマ14世の高齢化問題である。高齢化問題といっても2024年のアメリカ大統領選挙で取り沙汰された高齢化問題[2]とは意味合いが異なる。チベット人の関心事項は、その職務遂行能力ではなく、誰がダライ・ラマ15世、換言すれば次のダライ・ラマは誰なのかという問題なのである。本稿の筆者は2024年9月、ダライ・ラマの亡命先であるインドのダラムサラを訪問したが[3]、複数のチベット仏教の僧侶たちが、この点について懸念を表明した。彼らに懸念を抱かせる主な要因の一つは、中国による後継者選定への介入の可能性にほかならない。
本稿の目的は、今日的な中国・チベット問題におけるもっとも重要な問題の一つといわれる次期ダライ・ラマ選定をめぐる問題に対する理解を深めることにある。そのために、まずはチベットの最高指導者の選定方法を概観する。その後、次期ダライ・ラマ選定にあたって中国がいかなる対応をとるだろうかという問題を念頭に、ダライ・ラマに次ぐ地位にあるパンチェン・ラマ11世選定時の出来事について、そして昨今の共産党の対チベット政策について振り返る。最後に、中国の動きに対してチベットがいかなる対応を取ろうとしているのかを検討する。こうした作業は、中国共産党のとる宗教政策の限界に部分的ながら迫ることにつながる。
ダライ・ラマの選定
そもそもダライ・ラマはコンクラーベのような秘密投票、あるいは選挙や世襲によって引き継がれるものではない。「輪廻転生」[4]の考えに基づき、生まれ、死に、そしてまた生きると考えられている。つまりチベット仏教の信者にとって、次のダライ・ラマを認定するということは、現世ダライ・ラマの転生者を探し出すことにほかならないのである。転生者である以上、上述のように投票や選挙では選ぶことができないという論理である。
では、現在の14世はどのようなプロセスを経て認定されたのだろうか。1933年に先代のダライ・ラマ13世が逝去したのち、その亡骸がラサのノルブリンカ宮殿に南向きに安置されていたところ、数日後、遺体の顔が東を向いた。さらには安置されていた建物の柱の東北側に星形のキノコが生えたという。こうしたことから転生者がポタラ宮の東の方に生まれると考えられるようになった。その後、チベットの人々が聖なる湖と考え、湖面に将来を見ることができると信じられているラモイ・ラツォ湖にて13世の摂政が祈祷したところ、緑色と金色の屋根のあるお寺と青緑色の瓦葺の家をみた、と記録されている。この景色に一致する場所を探すべく高僧たちが東に向かうと、なんと同様の特徴を持つ場所と家を発見した。そこで捜索隊が目的を隠し、さらに貧しい恰好をして訪れたところ、その家の少年――ラモ少年――は、捜索隊員の高僧が身に着けていた数珠を欲しがったという。その数珠はまさしく13世が使っていたものであった。また、それとは別の複数の数珠の中から13世が使っていたものを選んだり、子供が好みそうな装飾が施された大きな太鼓と小さいが13世が使っていたが太鼓を差し出したところ、やはり遺品の方を手に取ったりと神がかり的な現象が相次ぎ、捜索隊はラモ少年が転生者であると確信を深めていった[5]。その後、いくつかのプロセスを経てラモ少年がダライ・ラマ14世と認定されるに至った。かくして1940年1月14日、ラモ少年がダライ・ラマに即位した。このプロセスをみるに、多分に恣意的な介入を許す、ある種の「あいまいさ」が介在することがわかる。複数の「転生者」が生みだされかねない余地が存在するのである。チベットにおける序列第二のパンチェン・ラマの選定プロセスも、同様に「あいまいさ」を帯びていた。次節において、その選定過程を見ることにしよう。
中国の介入
1995年、現在のパンチェン・ラマ11世の選定において、チベット側が選定した11世のほかに、中国側が選定した「11世」も存在するという事態が生じた。ことの経緯は以下のとおりである。1989年1月28日に逝去したパンチェン・ラマ10世[6]の後継として、占いに基づき、1995年5月14日、とある6歳の少年が11世と選定され、その後、ダライ・ラマの承認を受け正式にパンチェン・ラマと認定された[7]。しかし、直後、そのパンチェン・ラマは中国に拘束されてしまった。その後、中国政府によって別の少年がパンチェン・ラマ11世として「発見」され、同年12月8日に即位した[8]。この人物は現在、中国人民政治協商会議常務委員に名を連ねるほか[9]、中国仏教協会の副会長も務め[10]、中国政府や共産党の行事に参加し、中国によるチベット「解放」と統治の正当性を訴えている。例えば、2019年には、共産党によるチベットの「平和的解放」60周年に際して、「(共産党による)民主改革はチベット社会を腐敗の暗黒から勝利の光へと導いた」(括弧内筆者)と述べた[11]。これに対して、ダライ・ラマ側が選定したパンチェン・ラマは、長らくその動向が明らかにされていない。2020年5月19日の中国外交部記者会見において、彼が大学を卒業した旨、報道官から発言があったとの報道が外国メディアによってなされたものの所在は依然として不明である[12]。そのため、チベット側は引き続き彼の解放を求めているほか、2024年5月17日にはアメリカ国務省の報道官が中国に対しチベット側が選定したパンチェン・ラマの所在を明らかにするよう求めるなど[13]、本問題は今日においても耳目を集めている。
中国共産党は、次期ダライ・ラマ選定への「介入」を念頭に置いたと推定される政策的・法律的な準備を着実に進めている。例えば、1992年8月25日から28日の日程で開催された「西蔵仏教工作座談会」において、ラマの化身は政府の指導に基づくことや海外の関与を禁止する旨が確認された[14]。このほか、2007年には「蔵伝仏教活仏転生管理弁法」[15]が制定され、転生を「制度化」し、政府が管理することがより明確に定められた。こうした諸々の事実を踏まえるに、次期ダライ・ラマ選定においても中国の介入が多分に予想されるのである。これこそが、本稿冒頭で述べたチベット人たちが共有する懸案事項に他ならない。
中国への対抗策
こうした事態に直面しているダライ・ラマであるが、ただ手をこまねいているわけではない。ダライ・ラマ14世は2011年、「私が90歳くらいになったら…ダライ・ラマの化身認定制度を継続する必要があるかどうか再度検討したいと考えています」と述べている[16]。そして、2025年7月、ダライ・ラマ14世は90歳を迎える[17]。それゆえ今年、15世選定に関して何らかの決定、あるいは示唆があると考えられているのである[18]。1999年、ダライ・ラマ14世は中国からの介入を念頭に「自分の転生者がこれまでの伝統的な方法で選出されるならば、チベットや中国支配下の地域で私の生まれ変わりはありえないだろう」[19]と述べるなど、中国を牽制してきた。このほか、2011年には、自身の引退に関する講話において、そもそも指名制であったチベット亡命政府の首相を民主的に選出する制度を自ら導入したことに言及し、「亡命生活が始まって以来、私は30年以上にわたり民主的な統治制度の確立に真摯に取り組んできました」と述べた。そのうえ、「亡命地にある我々は外国に難民として留まることで、真の選挙プロセスを実現しました」と続け、こうした変化は「高まりつつあるチベット人の政治意識とチベット亡命政府の民主的プロセスにおける進展」の反映であると論じ[20]、選挙制の導入による民主化の重要性を強調した。確かに、現世ダライ・ラマは2011年に政治から引退すると表明しているものの[21]、亡命政府の首相が「(ダライ・ラマ)法王の輪廻転生に関する実際の見解については、亡命政府でも発言権を持たない」のであり、「生まれ変わりについて考えるのは法王自身で、すべて法王自身が決めることだ」[22]と述べていることや筆者が現地でおこなった聞き取り調査においても、ダライ・ラマ14世の決定が絶対であるという考えのほか意見は見られなかったことを踏まえるに、「民主的」な次期ダライ・ラマ選定が行われる可能性は否定できないだろう。
おわりに
これまで見てきた行動は、共産党の宗教政策の限界、換言すれば言葉の上では宗教信仰の自由を保障しつつも[23]、チベット仏教信仰の根幹をなす指導者選定に、その宗教儀式を逆手に取り介入しようとする共産党の姿を浮き彫りにするものである。より本質的な矛盾も指摘できる。そもそも中国共産党は革命を是とするはずである。言い換えれば、伝統的社会からの「解放」を謳っていたはずである。それに対して、ダライ・ラマは精神世界にあって、宗教的価値観に基づき伝統に倣ってチベット社会を統治してきた。本稿で概観した現状を踏まえるに、建党以来、多分に変化を遂げてきたとはいえ、あくまで「共産」党と名乗り、革命を是とし、唯物論に立脚するはずの党が、神がかり的な手法を駆使しようと試み、それに対して宗教世界にあって伝統を是とするはずのチベット側がむしろ神がかり的な習わしからの離脱を検討していることがわかる。つまり両者があべこべになっているのである。であるならば、本稿の議論は畢竟、中国革命の限界を示唆するものであると言いうる。
1 ダライ・ラマ14世は、自らの統治機構を「中央チベット政権(CTA:Central Tibetan Administration)」と呼ぶと述べている。しかし、本稿においては一般的な呼称である「チベット亡命政府」の呼称を用いることにする。なおチベット亡命政府の成り立ちは以下のとおりである。1951年に人民解放軍が本格的にラサ駐屯を開始して以降、燻り続けた反乱の火種が遂に燎原の火となり、1959年春、ラサで大暴動が生じるに至った。この暴動が引き金となり、ダライ・ラマ14世は現在のチベット自治区の省都ラサを離れ、インドのダラムサラに亡命した。亡命の道中、1959年4月29日、インドのムスーリーでチベット亡命政府が成立し、その後、ダラムサラに移り今日に至る。「ダライ・ラマ法王、引退について語る」(2011年3月19日のダラムサラでの法話会でのダライ・ラマの発話)、ダライ・ラマ法王日本代表部事務所ウェブページ、ダライ・ラマ法王14世日本公式サイト | ダライ・ラマ法王14世日本公式サイト、最終アクセス:2025年1月10日。「中央チベット政権」ダライ・ラマ法王日本代表部事務所ウェブページ、中央チベット政権 – Tibet House Japan、最終アクセス:2025年1月10日。
2 選挙の時点でバイデン前大統領は81歳であった(1942年11月20日生まれ)。なお、トランプ大統領は1946年6月14日生まれである。
3 本稿の筆者は2024年9月17日~20日の期間、公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団の助成を得て調査研究のためインドのダラムサラにあるチベット亡命政府機関などを訪問した。
4 「輪廻転生」とは、生死を繰り返し、その中で別のものに生まれ変わることを意味する。中村元、福永光司、田村芳郎、今野達、末木文美士(編)『岩波 仏教辞典』第三版、岩波書店、2023年、1096-1097頁に詳しい。
5 ダライ・ラマ、木村肥佐生(訳)『チベットわが祖国』中央公論社、1989年、39-44頁。また、以下のサイトにも詳しい。「14世ダライ・ラマ法王発見の経緯と輪廻転生制度」ダライ・ラマ法王日本代表部事務所ウェブページ、14世ダライ・ラマ法王発見の経緯と輪廻転生制度 – Tibet House Japan、最終アクセス:2025年1月10日。
6 パンチェン・ラマ10世は中華人民共和国建国前の1949年6月11日、国民党政府によって認定された。
7 この過程については紙幅の都合上、本稿で詳述することは避ける。詳しくは以下の書籍を参照されたい。Isabel Hilton, The Search for the Panchen Lama, New York: W. W. Norton & Co. Inc., 2000. 邦訳は、三浦順子(訳)『高僧の生まれ変わり チベットの少年』世界文化社、2001年。また、以下のウェブサイトにも解説がある。「パンチェン・ラマについて」ダライ・ラマ法王日本代表部事務所ウェブページ、パンチェン・ラマとは – Tibet House Japan、最終アクセス:2025年1月10日。このほか、旧来のダライ・ラマとパンチェン・ラマの関係については、青木文教『近代チベット史叢書 1 西蔵問題―青木文教外交調書』慧文社、2009年も参照。
8 前掲ウェブサイト「パンチェン・ラマについて」。
9 「中国人民政治协商会议第十四届全国委员会常务委员名单」中国人民政治協商会議全国委員会ウェブページ、2023年3月11日、最終アクセス:2025年1月10日。
10 「领导机构」中国仏教協会ウェブページ、2024年4月15日、最終アクセス:2025年1月12日。
11 「专访班禅:西藏民主改革60年,宗教信仰自由政策得到全面落实」中国新聞網、2019年6月10日、最終アクセス:2025年1月8日。
12 「パンチェン・ラマ認定の男性、大卒後『普通の生活』送る? 中国が異例発表」AFP、2020年5月20日、最終アクセス:2025年1月12日。なお、中国外交部ウェブサイトにて5月19日の定例記者会見の発言録を確認したが、当該内容は掲載されていなかった。「2020年5月19日外交部发言人赵立坚主持例行记者会」外交部ウェブページ、2020年5月19日、最終アクセス:2025年1月12日。
13 関連する内容は以下の国務省ウェブサイトで確認できたが(2024年に筆者確認済み)、2025年3月19日現在、表示されない。ただ、URLの文字から内容を読み取ることはできるだろう。
14 川田進、「毛沢東から胡錦濤時期における中国共産党の宗教政策とチベット政策」『大阪工業大学紀要』人文社会篇、2014年、39頁。
15 「藏传佛教活佛转世管理办法」(「国家宗教事务局令」第5号)中華人民共和国中央人民政府ウェブページ、2007年7月18日、国家宗教事务局令(第5号) 藏传佛教活佛转世管理办法__2008年第8号国务院公报_中国政府网、最終アクセス:2025年1月12日。
16 ダライ・ラマ14世 テンジン・ギャツォ「ダライ・ラマの化身認定制度について」ダライ・ラマ法王日本代表部事務所ウェブページ、ダライ・ラマ法王14世日本公式サイト | ダライ・ラマ法王14世日本公式サイト、最終アクセス:2025年1月10日。
17 ダライ・ラマ14世は1935年7月6日生まれ。
18 チベット亡命政府の首相も同様の見解を示している。「チベット亡命政府ペンパ・ツェリン首相インタビュー詳報」『チベット、ウイグル、香港、加害者はすべて同じだ』」、『産経新聞』2023年10月7日、チベット亡命政府ペンパ・ツェリン首相インタビュー詳報「チベット、ウイグル、香港、加害者はすべて同じだ」 - 産経ニュース、最終アクセス: 2025年2月5日。
19 「ダライ・ラマの生まれ変わりは 中国支配下の地ではないだろう」ダライ・ラマ法王日本代表部事務所ウェブページ、「ダライ・ラマの生まれ変わりは 中国支配下の地ではないだろう」 – Tibet House Japan、最終アクセス:2025年1月10日。
20 前掲ウェブサイト「ダライ・ラマ法王、引退について語る」。
21 同上。
22 「ダライ・ラマ14世の後継どうする? チベット亡命政府首相に聞いた」『朝日新聞』2025年1月27日、最終アクセス: 2025年2月5日。
23 例えば、中華人民共和国憲法36条に規定されている。