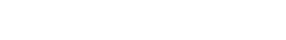論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第57回 2024/08/01
中国の核戦略(その2)
中国の核戦略と核戦力
核戦略をめぐっては、中国に限らず、主要国では、相互確証破壊や抑止というアメリカで発展した理論的な枠組みを手本としてきた。そして、これらの国々では、核戦略や核戦力に関して公式文書が刊行されてきた。しかし、数年に一度の「国防白書」を除いて、中国は核戦略をめぐる公式文書がほとんどない。日本では、独自に中国の核戦力について調査することがほとんどできないため、中国の核弾頭数や配備状況については、主にスウェーデンの有名なシンクタンクであるSIPRIやアメリカの軍やシンクタンクによる推計と分析に頼ることになる。
実は、中国の核問題専門家たちもアメリカで発展してきた核戦略理論にかなり頼って議論を展開してきた。相互確証破壊など、核戦略の基本中の基本となる概念を中国の戦略家が批判することはあっても完全に否定して使わなくなったことはない。中国軍がそれに基づいて戦力を構築してきたわけではないとしても、参考になることに間違いはない。
しかし、米中それぞれの核バランスについての見方が異なっていることを指摘しておかなければならない[1]。アメリカ側は自国の軍事的優位を前提としつつ、中国の急速な核開発が戦略的安定性を低下させているとし、安定した核バランスを保つためには、アメリカの核戦力の充実を進めなければならないとする。
一方、中国側は、中国側が不利な状況にあるとした上で、アメリカの核戦力の充実、またミサイル防衛網などの進展によって、中国の核戦力が持つ対米抑止力が弱まるため、アメリカ側による攻撃を誘発しやすくなり、戦略的安定性が失われ、核バランスが不安定になるという見方をとる。米中のバランスといっても、対称的なバランスではなく、非対称のバランスで、安定をめぐる状況の認識に違いが出るのは当然であろう。この非対称という条件下では、ロバート・ジャーヴィスの「安定―不安定のパラドックス」(核バランスの安定と通常兵器バランスの安定は一方が成り立つと他方が成り立たない)が成り立ちにくいという批判がアメリカであると同様、中国でもある。
見方が異なるとしても、ほぼ同じ結論に至ることは無視できない。同じ結論を共有するためには、見方の違いが誤解を招き、緊張を不必要に高めないようにするには、緊密なコミュニケーションによる相互理解の努力が必要となる。
この点、特に核バランスをめぐる戦略的安定性という考え方では、核戦争を避けようとする米中では両方が重視してきて、妥協点を探ってきた。戦略的安定性とは、外部からの衝撃でバランスが崩れる度合いのことを言う。この安定が脆弱である、つまりごく小さな衝撃で緊張があっという間に高まると、状況のコントロールが急激にむずかしくなり、危機に陥る。逆に、この安定が強靭、つまりごく小さな衝撃ぐらいでは緊張がすぐに急激に高まることがなければ、状況のコントロールは相対的にやさしい。したがって、この度合いを高め、脆弱さを低めて、安定を強靭にしなければならない。
中国の代表的な核戦略専門家として知られる李彬(清華大学教授)は、核の戦略的安定性を取り上げ、論じてきた。核の廃絶が予想できる将来簡単には実現せず、核兵器が存在し続ける世界では、核戦争発生の可能性を抑えることが至上命題となる。つまり、核保有国同士の緊張をコントロールし、安定を維持することが現実的な目標となった。
この戦略的安定性という概念も元はといえば、米ソの激しい対立の中でソ連側とのやり取りを重ねながら、アメリカでの議論の中から編み出され、定着したものである。冷戦期の米ソ間で行われた激しい核軍備競争が全面的な核戦争を引き起こさないよう、米ソ間で最低限の安定を実現するために精緻化された。相互の信頼が欠けても実現できた平和、いわゆる「冷たい平和」の基礎となった論理である。この理屈は、21世紀初頭の米中間にも当てはまる。
李彬もいうように、戦略安定性は、持ちうる能力や採られる政策によって変化し、戦略的安定性はダイナミックな性格を帯びる。しかし、それが大問題で、冷戦期の考え方は引き続き役立つが、工夫が必要となる。なぜなら、これまでは、戦略的安定性の評価を複雑にしたのは、すでに述べたように、MIRV化や中距離ミサイルなどの技術進歩であった。
21世紀の米中関係においても、中国側の能力の向上と、アメリカ側の改良や新戦力の開発、そしてそれらに対する迎撃網の整備が双方で進められてきた。しかし、科学技術の進歩は弾頭の改良や運搬手段の改善だけにとどまっていない。ゲーム・チェンジャー、つまり一世代前の技術を陳腐化してしまいかねない手段が登場しており、その中でも最も重要な意味を持つのがクロス・ドメインである。
クロス・ドメイン下の核戦略
クロス・ドメインは、これまでの主な戦場であった陸海空に加えて、サイバー、電磁、宇宙や脳など新しい分野での戦いも含めた領域を指す。似た表現にマルチ・ドメインがある。簡単にいえば、マルチはただいろいろなドメインをただ並べただけだが、クロスは味方の異なるドメインの間でお互いに助け合うか、逆に相手の異なるドメインの軍事システムを破壊または麻痺させる影響を与え合うことを強調する点に違いがある。難しく言えば、異なるドメインの間で相互依存と相互破壊が同時に成り立っている関係にある。力学的(kinetic)な破壊を行う兵器の数も引き続き重要だが、数の優位を発揮するには、このクロス・ドメインの関係をどう活用するかが大きく関わる。ここでは、まず宇宙から始めて、その後に核が絡んでくるが、ポイントはクロス・ドメイン間の重層的な融合である。クロス・ドメインはすでに世界的な潮流となって定着している。
宇宙での活動は、宇宙兵器も含め、人工衛星システムが作り上げた通信情報ネットワーク(コンピュータを含む)に大きく依存している。この通信情報ネットワークは、サイバーと電磁波パルスによる攻撃に脆弱である。そして、この電磁パルスは、現時点での技術では主に核爆発によって生じる。周りまわって、宇宙の安全は、サイバーと核による電磁波パルスによる脅威にさらされているということになる。そして、サイバーや電磁波パルス兵器は、通信情報ネットワークがないとできないし、そうなると宇宙の人工衛星ネットワークに依存しているとも言える。通信情報ネットワークが関わる宇宙、サイバーと電磁パルスという異なるドメイン同士の絡み合いがあり、それらの統一的な安全の確保にはクロス・ドメインの融合や統合が必要なことがわかる。ふつう、どれか一つをとって能力を突出させても、他のところで低いところがあると、その最も低いレベルで全体の能力が止まってしまう。
そして、核兵器は、たとえ直接に人命や財産を奪うことがなくとも、その爆発による電磁パルスは甚大な被害を全世界に及ぼす。地球上の通信ネットワークは、人工衛星システムに大きく依存しているので、核爆発によって生じた強烈な電磁パルスによって、多くの国々の通信ができなくなる。その損害は部分的なサイバー攻撃の比ではない。
宇宙の通信システムを混乱させれば、宇宙にとどまらず、陸海空の領域でも、相手の軍隊の偵察監視や指揮統制通信の機能は大きく低下する。今の戦争は、集中された兵力は探知されればすぐに攻撃されるので、機能が分化した兵器が分散して配置され、作戦を進める。これがいわゆるモザイク戦(mosaic warfare)で、このタイプの作戦では緊密な通信ネットワークがなければならず、その破壊や麻痺は敗北に直結する。
さらに、軍事に限らず金融や運輸を含め、全世界で経済と日常の活動に広範囲にかなり大きな支障が出る。使用が爆発的に増えているAI関連の機器ももちろん同じく核による電磁波攻撃には弱い。人によっては、通信ぐらい、と思うかもしれないが、それは大間違いである。
冷戦終了で核兵器や核戦略の役割は終わったと早合点されたことがあったが、中国はハイテク兵器の分野での遅れを補うため、核戦力を引き続き重視した。そして、21世紀初頭、このようにクロス・ドメインでの核の役割はさらに大きい。日本では、このような議論は夢物語のようにしか受け取られないことが多かったが、主要国では、クロス・ドメイン全てにおける指揮統制という概念が作られ、整備が進められている。米軍はすでにJADC2(Joint All-Domain Command and Control)という考え方に基づく指揮統制が構築されつつある。しかも、JADC2におけるAIの役割もすでに検討中である。作戦立案もAIを使えば、これまでは数ヶ月かかった作業も数分でできるようになる、と米側の予測を中国の専門家も計算に入れている。
そうなると、このような新しい状況や条件下での戦略的安定性が分析されるべき問題として登場する。これが、現代日本が直面している安全保障上の主要な問題の一つであり、しかも民間の研究者の間では、あまりよく知られていない。そこで、次に議論の基礎となるクロス・ドメインと、そこでのエスカレーションと抑止の性格について初歩的な考察を加えることとする。
クロス・ドメイン下の「複合的抑止」 とエスカレーション
クロス・ドメインという条件が、戦略的安定性に与える影響を分析には、エスカレーションが進むプロセスの中で抑止が効果的に働くかどうかを考える必要がある。また、エスカレーションが進むことが脅威と見做されれば、それは抑止として機能するのである。ここで、あらためて言えば、クロス・ドメインにおける抑止とは、核、サイバー、宇宙、脳など多くの異なる領域がクロスする、つまり影響を与え合う形での抑止である。
2024年の時点では、進行中のロシア・ウクライナ戦争で伝統的な火力戦と兵器や装備の数量が再評価されており、先端兵器への過剰な期待もあったせいで、先端兵器やクロス・ドメインに対する評価は相対的に低下した。湾岸戦争やイラク戦争での勝利はハイテク兵器によるものとされ、ロシア・ウクライナ戦争もそうなると考えられたのである。
先端兵器やクロス・ドメインの運用は大きな役割を果たしているにも関わらず、報道では火力戦の影に隠れがちであった。火力戦の重要性は間違いないが、また戦時であるため、実際には、これらの重要性が慎重に秘匿されていると見た方が良さそうである。ここでクロス・ドメインの研究をやめる理由はない。すでに述べたエスカレーションも、このクロス・ドメインと核戦略がかなり密接に絡み合っている。そこでこの側面を述べていく。
クロス・ドメインの重要性が認められるに伴い、「複合抑止」(complex deterrence)という言葉が発明されたこともあるように、概念が複雑さを増していった(なお、似た用語に「統合抑止」(integrated deterrence)があるが、こちらはアメリカが同盟国と協力してのグレーゾーン状況への対応についてのもので、異なる概念である)。この結果、複雑化が進んで事前の計算が簡単には追いつかなくなった。つまり、不確定性が増大し、緊張が適切にコントロールされていれば、政策はふつう慎重になる。しかし、影響はほとんどないと事前には考えられた小さな動きが大きな災厄をもたらす可能性がある。いわゆるバタフライエフェクトで、一見安定した状況が突然持つ敏感さや脆弱さということである。
このように、突然国際的な緊張が急激に増すことが想定されるため、クロス・ドメイン下のエスカレーションについても考察が必要となる。冷戦期の核戦略に通じるようなある程度の段階が想定できるか、それともきわめて流動的で無定形な性格を持つのか、それともこの二つの相の間を行き来するのか。核を含めクロス・ドメインの抑止やエスカレーションなど、これらの定式化は広い意味でのアルゴリズム戦で、先に定式化に成功した方が有利な安定性を確保できる。この考察は簡単ではないし、理論は完璧な処方箋でも万能薬でもない。しかし、病気は全部が治るとは限らないから、今ある病院も薬もやめてしまえという意見が通らないのと同じく、理論もないととことん困る。
限られたスペースでクロス・ドメイン戦略を包括的に議論することはできない。ここで行うのは、これからの中国の核戦略がクロス・ドメインという条件のもとでどう展開するのかを考える上での叩き台の作成である。
1 李彬によれば、米中の間で核をめぐる意思疎通は非常に難しいとされ、2011年から核保有国同士で2核戦略や核戦力をめぐる技術的な用語について専門家同士で話し合いが続けられてきた。たとえば英語の「抑止」(deterrence)は中国語では「威懾」で、米側が相手に何かをさせないという意味だけで使う一方、中国側の専門家たちは、相手に何かをさせないだけでなく、何かをさせる意味もあると解釈することが多いという。さらに問題を複雑にするのは、中国国内でも使う用語が異なり、外交部門や国防工業が「威懾」を使うが、軍事科学院や第2砲兵(現在のロケット軍)は「遏制」をもっぱら使うことであるという(『世界経済与政治』2014年第2期)。