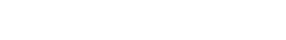論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第56回 2024/07/31
中国の核戦略(その1)
核戦略をめぐる議論では、バランスや抑止を含め、前提として、相手の認識・心理およびそのこちらとの違いを知る必要がある。しかし、安全保障はいまだ毛嫌いされがちで、特に核をめぐる議論は感情のぶつけ合いに終始することも多い。加えて、国際関係で相手の事情を理解しようとする姿勢はなぜか譲歩や媚びと見なされやすい。
しかし、孫子の言葉を使うまでもなく、相手(と自分)を知らなければどうにもならないし、特に核抑止や核の戦略安定性の議論を政策に応用する上では、一般の人間関係と同じく、相手の特徴を細かく知ることが基本中の基本である。日本がこの状況でどうしたらいいか、と政策を考えるためには、可能な限り状況の正確な把握が前提となる。目をそむけ、議論しないからといって、問題がなくなることはない。そこで、ここでは日本ではあまり知られていない中国の核戦略や核戦力、そして新たな状況におけるその変化について説明することにする。
報道に見る中国の核戦力
中国の核戦力が急ピッチで進んできたとの報道があり、この分野への関心が高まってきた。米国防総省の『中国軍事力報告書』(2023年1月)によれば、中国は運用可能な核弾頭が500基以上あり、2030年には1000発以上に達するとの見通しを示した。また、同報告書は、中国は、すでに300基のICBMサイロの建設を終え、そのいくつかは警報即発射(launch on warning: LOW)の態勢もとっていると分析している。
戦略原子力潜水艦やステルス戦略爆撃機(空中給油で米本土到達可能とされる)の増強も含め、これらはアメリカにとっても「脅威」であり、アメリカが中国に対して核攻撃をしないと中国側が自信を深めれば、台湾や日本に対して通常攻撃をする敷居が低くなるということになる[1]。
ちょうどこのころは、台湾の総統選挙を想定した人民解放軍の軍事演習が台湾付近で行われ、「台湾有事」がメディアやネットを賑わしたころであり、日本でも米からの情報を元に議論がなされた。5月の台湾の新総統就任にあたり、中国人民解放軍(中国軍)は台湾と金門島など離島の周囲の海域で軍事演習を行った。
中国は200発程度で十分なはずの「最小限核抑止」から脱却しつつあるという分析も現れた。「最小限抑止」とは、中国本土が核攻撃された場合、確実に第2撃(反撃)ができることを意味している。一方、東京大学先端技術センターと笹川財団による研究(2024年2月)[2]は、中国が「最小限核抑止」のような確固とした核戦略を持っていたというより、核戦略が変化してきたと観察している。核戦略や核戦力の分野は、きわめて高度の専門知識を必要とし、また兵器の保有はライバル国が偵察衛星などを使って見ていることを前提とするので、ダミーを作っての演出も多く、正確な状況の把握は簡単ではない。したがって、相手の戦略の骨組みを知ることは非常にむずかしい。
専門家の間でも核戦略をめぐる意見は多様であり、また一般社会でも、核戦争は切迫してはいないと考えている人は少なくない。ソ連が崩壊した後、多くの人々は、米ソ対立時のような切迫した核戦争の恐怖はもはやないと信じていた。ところが、2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争で、プーチン露大統領は核による威嚇を繰り返してきた。そのプーチンも欧米の核兵器を無視できておらず、NATO諸国との全面衝突を回避している。習近平も、2024年4月に訪中したショルツ・独首相との会談で、ウクライナにおける核兵器の使用や原子力施設への攻撃に明確に反対している。そもそも、中国は2014年のロシアによるクリミアの一方的併合も、また2022年のウクライナ東部地域の独立も認めていない。
中国はロシアと一定の距離を取る姿勢を言辞では見せる一方、二つの笹川レポート(2023年5月9日、2024年5月17日)が明らかにしてきたように、中国はロシアから高濃度濃縮ウランの輸入を増やしている。中国はこの核燃料から核兵器に転用できるプルトニウムを大量に手に入れることができ、これが中国の核弾頭急増を可能にするとも言われている。もしそうならば、急増した中国の核兵器が米中、中台や日中関係に影響を与えると考えない方がおかしい。
中国がロシア・ウクライナ戦争で必ずしもロシア一辺倒ではなくとも、中露首脳の相互訪問を繰り返してきたように、ロシアとの緊密な関係を演出するのは、外交を通しての対米抑止のためだけでなく、アメリカがロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス紛争に気を取られている間に、中国がその軍事戦略の中で核戦力の拡充を進めようとしているからということでもある。
さらに言えば、新たな国際秩序が見えてきている。中国、ロシア、北朝鮮というアメリカと対立する権威主義の核保有国同士の結びつきが強まってきており、これらの国々と西側の民主主義国家群、そして「グローバル・サウス」とまとめられているが前二者の間でそれぞれバランスをとる多種多様な国々によってできている国際秩序である。
このような核をめぐる状況は複雑で矛盾して見える。しかし、複雑だというだけでは何の答えにもならず、実際の政策になんの参考にもならない。この核をめぐる複雑な状況をどのように解釈したらよいであろうか。
核戦争が突然起こることはないとしても、緊張が高まっていくエスカレーションのプロセスでは、各国の世論も敏感に反応し、経済活動も大幅に縮小され、日常生活にも大きな影響が及び、政府にとっても大きな圧力となっていく。日本も例外ではあり得ないし、国民も政治家も核戦略や核戦力をほとんど知らないまま、どう対応しようとするのであろうか。
保有国が核の使用をちらつかせつつ進めるエスカレーションについて考える必要があるのは明らかである。言葉を変えれば、核の脅迫がある状況での交渉はどういうものか、そしてその果てに構築される新たな秩序を構想する、ということが必要になる。日本に関わるとすれば、当面は朝鮮半島、台湾、尖閣、東シナ海・南シナ海がこれに当たる。
すでに核戦力を保有している国々は、その戦略資源の有効活用のためにも、核兵器の役割を考え続けることになる。それは中国も同じで、影響を受けるのは米中、中台、そして日中関係で、例外にはなり得ない。ごく最近経験したばかりの感染症の場合と同じく、核についても、どのような状況の展開を見せるか、想定しておく必要がある。
そこで、本コラムは中国の核戦略や核戦力を扱うが、この分野はすでに筆者よりもはるかに専門的な研究者もいるので、その研究蓄積に依拠しながらも、角度を変え、特に分析する範囲を広げて議論を試みる。相互確証破壊の概念など重要な論理など、核戦略をめぐる基礎的な議論は、主に米ソ対立期に書かれた教科書に目を通すことから始まる。しかし、戦略は状況が変われば普通は変わるものであり、21世紀初頭の状況は冷戦期と同じではない。もちろん共通する部分もあり、昔の教科書は引き続き有用だが、そのままでは通用しない。あくまで叩き台として、自分の頭で考えていく必要がある。もちろん、横文字の新しい教科書は役立つが、教科書が刊行されるまで考えなくていいというわけにはいかない。
冷戦期の核戦力分析で最も重視された核弾頭や運搬手段の数は、21世紀初頭も引き続き重要で分析の基礎となるが、それだけでは核戦力の大きさの評価にはまだ十分とはいえない。冷戦期もMIRVなどが引き起こした質的な変化によって、数だけでは評価が難しくなっていた。また、1980年代には、SS-20のように欧州正面に配備されたソビエトの中距離核ミサイルは、アメリカと欧州の戦略的安定性の計算をさらに複雑にした。中距離ミサイルは米本土には届かないのでアメリカには直接の脅威にはならず、欧州だけが脅威にさらされたからである。
それだけでなく、科学技術が格段に進歩し、監視がグローバルで、攻防もミリ秒単位で行われる時代には、数とともにその使い方やそれを支えるシステムのことも含めて広く知らなければならない。数があれば有利という考えはあるが、常にそうであるわけではなく、そうなる条件を明らかにしていかなければ危なくてしょうがない。
1 この点、2024年5月には中国の戦略研究者として知られているベーツ・ギル(Bates Gill)が、アメリカのシンクタンクである全米アジア研究所(National Bureau of Asian Research)から中国の核戦略と核戦力に関する広範囲にわたる報告書をまとめ、アジアの主要国の立場からの中国の核戦力についての分析とそれに基づいた政策提言を行なっている。日本からは亜細亜大学の向和歌奈准教授が寄稿している。(”NBR Special Report No. 109, Meeting China's Nuclear and WMD Buildup Regional Threat Perceptions and Responses”)