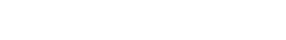論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第54回 2024/05/30
PLA核戦力の現状-ロシア「ディエスカレーション戦略」との比較
後瀉 桂太郎(海上自衛隊幹部学校 主任研究開発官/1等海佐)
ロシアの核による脅し
本論執筆時点(2024年5月)でロシアのウクライナ侵略(「ウクライナ戦争」)は勃発から2年以上が経過し、未だ終息する気配はない。この戦争において特筆すべき点の一つとして、ロシアはNATOやウクライナに対し「核の限定使用」という脅し(blackmail)を頻繁に使うことがある。クリミア併合後1年に際し2015年3月に放映されたロシア国内のテレビ番組で、ウラジーミル・プーチン露大統領はクリミア併合に伴う軍事作戦の期間中、核警戒態勢の強化、すなわち核兵器が即応態勢にあった、と発言したことは世界各国で広く報道された[1]。ロシアはウクライナ戦争でよりあからさまに核の脅しを用いている。2022年2月19日、ロシア軍はICBMと極超音速ミサイルの発射演習など「戦略抑止演習」を実施し[2]、侵攻直後の27日にプーチン露大統領は「戦略抑止部隊に特別警戒態勢をとるよう命じた」と報道された[3]。
以降2年あまり、ロシアの政治・軍事指導者は折にふれ「核の限定使用」をちらつかせ、NATOとウクライナを引き下がらせようとする。これはロシアが高烈度の通常戦争から「非戦略核」の限定使用というレベルで優位に立ち[4]、相手を脅したうえで都合の良い状況で安定させる、「ディエスカレーション」(de-escalation)戦略と呼ばれ[5]、ウクライナ戦争においてはクリミア半島やドンバス地方などをウクライナから切り取って停戦交渉を行うことが考えられる。
事態のエスカレーション・ラダー(梯子)の上下を能動的にコントロールする意図と能力を有することで競争相手に対し優位に立つことを「エスカレーション・ドミナンス」という[6]。ロシアが非戦略核兵器を含む軍事オプションによってエスカレーション・ドミナンス確保を企図するというリスクは、21世紀初頭にはごく少数の研究者によって指摘されていたものが、2014年のクリミア半島への侵攻などを契機にして徐々に認識されてきた。
このようにロシアは非戦略核によってエスカレーション・ドミナンスを確保するだけにとどまらず、抑止の破綻(ウクライナ戦争)に際し核の限定使用をほのめかしてウクライナとNATO諸国を脅し、「ディエスカレーション」を試みている。ウクライナ戦争は、核保有国が核使用の脅しをかけつつ他国を侵略した、史上類をみないケースであるが、こうしたロシアの核に依存する姿勢は、NATOに対する通常戦力での劣勢を相殺することが念頭にある[7]。
PLA核戦力増強の方向性とは
一方で中国の核戦略は情報が少なく、不明な点が多い。200ページを超える米国防省の中国軍事力に関する2023年版年次レポートでも、PLAの核戦力に関するセクションはわずか12ページ弱に過ぎない[8]。中国は1964年に最初の核実験に成功したものの、長期にわたり米ソ(露)に匹敵する核戦力の建設は経済的にも、また技術的な観点からも非現実的であった。小規模・脆弱な核戦力で戦争を核レベルへエスカレートさせることは決定的な敗北を意味する。したがって中国は核保有国となった当初から「先制不使用」(no-first-use: NFU)を宣言しており[9]、また最近まで必要最小限の報復能力をもって戦略的抑止を達成しようという最小報復戦略(minimum retaliation strategy)を採ってきた、とされる。
しかし、中国人民解放軍(PLA)ロケット軍の核戦力は近年質量ともに増強しているとみられる[10]。米国防省2023年版レポートは「2020年の段階で(米国防省は)中国の備蓄する実運用可能な核弾頭数は200発台前半から2030年に2倍(500発)以上になると見積もっていたが、2023年時点ではさらにこの増加スピードが上がり、2030年までに1000発以上に増加する」と記している[11]。加えて近年は「警報即発射(launch on warning: LOW)」と呼ばれる即応態勢の強化を進めているとされ、実戦能力向上によってより確実な核抑止の機能を企図している[12]。
一方で2021年6月以降、中国が新疆東部の砂漠地帯に120前後のICBMサイロを建設している事実が写真とともに報じられたが[13]、現在サイロ数は少なくとも300以上に達している[14]。このように増強が進む核戦力の大半はDF-31、DF-41などといった大陸間弾道ミサイル(ICBM)か、あるいは晋(Jin)級SSBNならびにこれが搭載するJL-2、JL-3潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)といった戦略核である。ロシアのように「核の限定使用」で相手を脅そうとすれば、巨大な破壊力をもって懲罰的抑止を達成する戦略核ではなく、ある程度破壊力が小さい(低出力核: low-yield nuclear weapon)、対兵力使用が可能な非戦略核が必要となるが、現時点でこうした用途に対応する運搬手段はあまり多くない。
前出米国防省2023年版レポートではこのような低出力核の運搬手段として「核搭載可能かつ精密打撃可能な最初のミサイルシステム」であるDF-26中距離弾道ミサイルを挙げる[15]。しかしストックホルム国際平和研究所(Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI)の「PLAロケット軍では2022年中に5個もしくは6個のDF-26旅団が実戦配備され、それらが有する162のミサイルランチャーのうち三分の一程度が核ミッションに従事」しており、加えて「DF-21中距離弾道ミサイルのうち24発程度が核弾頭化されている」という見積もりが示すように[16]、現在推測される非戦略核の規模はロシアと比較すれば限定的である[17]。ただし、「従来の短距離弾道ミサイルが極超音速滑空体(hypersonic glide vehicle: HGV)搭載可能なDF-17中距離弾道ミサイルに換装される」とも分析しており[18]、今後低出力核/非戦略核についても戦力が増大する可能性が高い。
おわりに
既に顕在化している欧州戦域におけるロシアの核恫喝や、今後見込まれる中国の核戦力の増強を見越したとき、洋の東西を問わず米が「非戦略核による「核の限定使用」リスク」に核レベルで対応する場合、機動性と隠密性に富む海洋核戦力はエスカレーション・ドミナンスを相手に渡さないために有用なオプションである[19]。
しかし米バイデン政権はトライデントSLBMの低出力核バージョンの運用を開始するかたわら、トランプ政権が開発に着手した潜水艦発射型核巡航ミサイル(SLCM-N)の計画をキャンセルした[20]。その理由を推測するならば、第一に欧州でNATOは通常戦力においてロシアに対し圧倒的な優位にあり、万一ロシアが核の限定使用に踏み切っても通常戦力による大規模な報復が可能と見積もられる点がある。第二にアジアを見たとき、「アクセス阻止、エリア拒否」戦略(Anti-Access/Area-Denial Strategy: A2/AD戦略)はじめ、中国の軍事戦略は基本的に通常戦力に依拠しており、ロシアのように非戦略核の使用をちらつかせて恫喝し、相手に譲歩を強いる「ディエスカレーション戦略」を採用しているわけではないことが大きい。こうした点から、現時点でバイデン政権はただちに非戦略核オプションを増やすニーズは低いとみなしているのであろう。
現時点で中国は様々な運搬手段(ミサイル・航空機・戦略原潜)を保有する一方、ロシアと異なり非戦略核を積極的に運用し、ディエスカレーション戦略を展開しているわけではない。適切に抑止を機能させつつ、同時に米国とその同盟国の側によるエスカレーションを回避するためには、「ミサイル・バランス」と「核兵器使用リスクの閾値」(nuclear threshold)を混同することなく、慎重に議論を進めることと、そして当面は通常戦力による抑止に重きをおくことが適切な戦略的方向性といえるのではないだろうか。1 “Putin was ready to put nuclear weapons on alert in Crimea crisis,” Financial Times (Online), March 16, 2015, accessed on May 18, 2024.
2 “Strategic deterrence forces exercise,” The Kremlin, February 19, 2022, accessed on May 18, 2024.
3 “Putin signals escalation as he puts Russia’s nuclear force on high alert,” The Guardian, February 28, 2022, accessed on May 18, 2024.
4 本稿で「非戦略核」とは、対兵力攻撃(counterforce)に使用される核兵器と定義する。
ところで、現在の世界において戦略核と非戦略核の区分は非常に曖昧である。かつて戦略核と非戦略核の区分は破壊力ではなく、射程によっていた。米ソ間ではINF条約で「中距離核」(射程約300~3000マイル(500~5500km))と定義されていたため、おおむね300マイル以下は戦術核、3000マイル以上の射程を持つ核兵器は戦略核となる。3000マイルとは、NATO諸国からソ連本土を直接攻撃できる、ということを意味する。
しかしながらこれはあくまで米ソ(露)間における整理の仕方であり、他国にこの定義を適用することは適切とは限らない。例えば隣接するインドとパキスタンの間では、射程500kmであっても戦略核となり得る。同じ100キロトンの核ミサイルであっても、それを都市部の大量破壊に用いる(対価値攻撃(countervalue))か、原野や洋上に展開する敵戦力のみを狙って使用する(対兵力攻撃)のか、によって意味は異なる。つまり、最終的に「これは戦略核なのか、非戦略核なのか」という命題は、使う側、使われた側の認識に帰着すると考えられる。
5 表現に正確を期するとすれば“escalate to de-escalate”、すなわち「エスカレーションを抑えるため、一度事態をエスカレートさせる」ということになる。本章では以下「ディエスカレーション戦略」と呼ぶ。Nikolai Sokov, “Why Russia Calls a Limited Nuclear Strike “de-escalation”,” Bulletin of the Atomic Scientists website, March 13, 2014.
小泉悠によれば、この概念を説明する用語には「エスカレーション抑止」、「E2DE(escalate to de-escalate)」などいくつかの種類がある。 小泉悠「ロシアの軍事戦略における中・東欧-NATO東方拡大とウクライナ危機のインパクト-」『国際安全保障』第48巻第3号、2020年12月、63頁。
6 Herman Kahn, On Escalation -Metaphors and Scenarios, Penguin Books, 1968, p.290.
7 冷戦期、米ケネディ政権は欧州戦域における通常戦力の劣勢を相殺するため「柔軟反応戦略」を採用したが、現在通常戦力で劣勢にあるロシアはこれと類似の戦略を採用している、とされる。
小泉悠「ロシアの軍事戦略における中・東欧」62頁。Tom Nichols, Douglas Stuart and Jeffery McCausland eds, Tactical Nuclear Weapons and NATO, U.S. Army War College Strategic Studies Institute, April 2012, p.158.
8 U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2023 -Annual Report to Congress, 2023, pp.103-114.
9 Ibid, p.105.
10 神保謙は20世紀末以降、中国は必要最小限の第二撃能力(second strike capability)の確保をめざす「最小限抑止」(最小報復戦略と基本的に同義)から、ICBM弾頭の複数個別目標再突入弾頭(multi independently re-entry vehicle: MIRV)化といった近代化を経て、確実な報復能力を担保し、抑止しようという「確証報復」へと変化しつつある、と論じる。神保謙「中国―「最小限抑止」から「確証報復」への変換」秋山信将・高橋杉雄編『「核の忘却」の終わり 核兵器復権の時代』第3章、勁草書房、2019年、75-85頁。
11 U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2023, p.111.
12 LOWは「早期警戒反撃態勢」(early warning counterstrike (预警反击))とも呼ばれる。 Ibid, p.112.
13 Matt Korda and Hans Kristensen, “China Is Building A Second Nuclear Missile Silo Field,” Federation of American Scientists website, July 26, 2021, accessed on May 15, 2024.
14 U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2023, p.104.
15 Ibid, pp.111-112. DF-26は通常弾頭と核弾頭の両方を運用可能な “dual capable” ミサイルシステムであるとされる。
16 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2023 -Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2023, pp.291-292.
17 2023年時点でロシアが運用する非戦略核弾頭数は1816発に達すると推定される。 Ibid, pp.262-263.
18 Ibid.
19 分析過程の詳細は下記拙稿を参照されたい。後瀉桂太郎「欧州とアジアにおける「核の閾値」-非戦略核をめぐる思考実験」岩間陽子編『核共有の現実-NATOの経験と日本』第8章、信山社、2023年。
20 U.S. Department of Defense, 2022 Nuclear Posture Review, October 27, 2022, pp.20-21.