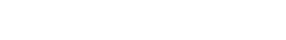論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第39回 2022/07/15
透明性なき中国の核軍拡に関する考察:NPT再検討会議を前に
1.中国の核軍拡がもたらす問題
新型コロナウイルスの感染拡大によって延期されていた核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議が、2022年8月、ニューヨークで開催される。再検討会議は5年に一度開催され、同条約の履行状況、とりわけ第6条に定められた「核軍縮交渉を誠実に行う義務[1]」について締約国間で検証する場であるが、今回は懸念事項が少なくない。2月にロシアがウクライナに軍事侵攻し、ウクライナや支援国に対し核の使用をちらつかせ、恫喝を行ったことで、二大核兵器国である米国とロシアの関係が極度に悪化している。こうした動向に加え、アジア地域、とりわけ日本にとって懸念されるのは、不透明な形で核軍拡を進める中国である。
米国防総省が毎年議会に提出している中国の軍事動向に関する報告書「MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA」2020年版においては、「現在200発台前半と見込まれる中国の核弾頭数は2030年までに少なくとも二倍に増える[2]」と分析されていた。2021年版では、この核弾頭保有数の予測が「2030年までに1000発に至る可能性」に引き上げられている[3]。
予測を上方修正した背景の一つとして、中国が民生(発電)用のプルトニウムを増産し、秘密裏に軍事転用を図ろうとしていることが指摘されている。
実際、中国は2017年、それまで毎年行ってきた国際原子力機関(IAEA)へのプルトニウム保有量の報告を突如停止し、時期を同じくして、原子力発電所の使用済み燃料からプルトニウムを分離する核燃料再処理施設2基の建設を開始していたことが、核不拡散の専門家や政策立案経験者らで組織する「Nonproliferation Policy Education Center」(NPEC)の衛星画像分析により発覚した[4]。米国防総省の報告書もこうした分析に基づいている。
不透明な形でのプルトニウム生産や核軍拡は米中間およびアジア地域の緊張を高めるばかりでなく、IAEAによる国際的な核物質の管理体制を骨抜きにする恐れがある。ひいては、NPTを基軸とする核秩序の崩壊をもたらしかねない。
本稿ではまず、今後の中国のプルトニウム製造能力を展望しながら、中国の核戦略の変化を分析する。続いて、同国の核軍拡が近隣諸国や国際社会に与える影響を分析し、影響を低減するため、日本が果たすべき役割について考察する。
2.中国のプルトニウム生産動向と予測される核弾頭保有数
(1) プルトニウム生産の歴史と今後
中国は長年、内陸部甘粛省の軍用施設でプルトニウムを生産してきたが、その施設は1987年までに閉鎖された[5]。
一方、原子力の民生利用は1980年代に本格的に開始された。2010年以降は福島第一原発事故による世界的な原子力利用の停滞とは逆に、地球温暖化対策として石炭火力発電の割合を低減するため、原発を増設している。フランスから技術移転を受けた加圧水型軽水炉(PWR[6])を中心として、2021年1月現在、日本を超える48基の原子炉が運転中で、16基が建設中である[7]。
しかし、経済発展により、2040年の電力需要は2020年の倍と見込まれ、このままPWRの増設により電力需要の増加を補うとすれば、中国は世界のウラン供給量の50%を確保する必要に迫られる[8]。核燃料の不足という状況を回避するため、中国は、PWRの使用済み燃料からプルトニウムを分離し、ウランと混ぜた混合酸化物燃料(MOX燃料)にして発電効率の良い高速増殖炉で利用する核燃料サイクル技術の確立を目指している。この技術によって中国は、2050年までに、原子力由来エネルギーのうち80%を高速増殖炉で供給することを計画している[9]。そのため、閉鎖された軍用施設に隣接する敷地に、プルトニウムを取り出す再処理施設の試験工場が新設され、2010年ごろに運転を開始したとされる。しかし、不具合が続き、同施設が通常運転に至ったのは2019年ごろと推定されている[10]。
2015年以降、この試験工場からそれほど離れていない甘粛省の砂漠地帯で、新たに二つの再処理工場の建設が開始された。中国政府、および運営主体となる中国核工業集団公司(CNNC)は、これらの再処理工場について詳細を明らかにしていないが、NPECの衛星画像分析によると、第一工場は2020年2月までに土木工事の段階を終了し、機器設置の段階に入った。工事の進捗状況から、第一工場が2025年ころ、第二工場が2030年ころに運転を開始するとみられる。
上記の再処理工場で生成されたプルトニウムの活用を見込む高速増殖炉は、運転中の核燃料の反応によってプルトニウムが新たに「生産」され、挿入した燃料以上のプルトニウム回収が可能なことから「夢の原子炉」と呼ばれてきた[11]。米国、ロシア、フランス、イギリス、日本が実用に向けた技術開発で先行し、日本では1994年から1995年にかけて「もんじゅ」とよばれる原型炉[12]が稼働していた。だが、原子炉を冷却するためのナトリウムの管理が難しく、米国は80年代に開発を中止し、英国、フランスは90年代、日本は2018年に高速増殖炉原型炉の廃炉を決めている。中国はロシアの技術支援を受けつつ高速増殖炉の開発を進め、CFR-600と呼ばれる大型の高速増殖炉(1500MW:日本で運転されているPWRの1.5倍から2倍の発電能力)2基がそれぞれ2023年、2026年ごろに運転を開始する予定である[13]。
しかしながら、高速増殖炉の開発には核物質の軍事転用の懸念が付きまとう。兵器用の超高純度プルトニウム239の取り出しが容易なためである。
PWRなど、現在、世界で運転されている発電用原子炉では純度の高いプルトニウム239の取り出しが難しい一方、高速増殖炉では、炉内で新たに生成されるプルトニウムの再処理により、兵器用プルトニウムを大量に獲得できる。そのため、IAEAは核不拡散の観点から、日本において「もんじゅ」運転中は、燃料の動向を厳しく監視していた。しかし、中国はNPTにおいて核兵器保有を認められた国であり、IAEAによる査察は義務づけられていない。同国で高速増殖炉の本格運転が始まれば、国際社会が燃料の動向を把握できない可能性が高い。
(2) 中国のプルトニウム保有の動向
IAEAによる「国際プルトニウム管理指針」において各国が報告しているプルトニウムの累積量によると、中国にとって最後の報告となった2016年は40.9キログラムとなっている(表1参照)。
表 1:国際プルトニウム管理指針(中国)
| 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積量 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 25.4 | 25.4 | 40.9 |
* IAEA「国際プルトニウム管理指針2017年版」を参照に筆者作成
今後、CFR-600(2基)が予定通り運転開始すれば、これだけで年間最大330キログラム超の兵器用プルトニウムを獲得できる。ミサイルに装填する核弾頭1発に必要なプルトニウムを3.5±0.5キログラムと換算すれば、82-110発の核弾頭に相当する。NPECは、核燃料サイクルの技術上の困難を加味し、取り出せる量に幅を持たせたうえで、すでに稼働している小型のものを加えた高速増殖炉によるプルトニウムの年間当たりの生産量と2030年時点の累積について、表2のように試算している。
表 2:高速増殖炉による中国のプルトニウム生産
| 年 | 小型増殖炉(kg) | CFR-600(2基、kg) | 累計量(kg) |
|---|---|---|---|
| 2012-2020 | 45-46 | 45-56 | |
| 2021 | 5-7 | 50-63 | |
| 2022 | 5-7 | 55-70 | |
| 2023 | 5-7 | 60-77 | |
| 2024 | 5-7 | 91-164 | 156-248 |
| 2025 | 5-7 | 91-164 | 252-419 |
| 2026 | 5-7 | 91-164 | 348-590 |
| 2027 | 5-7 | 187-337 | 540-934 |
| 2028 | 5-7 | 187-337 | 732-1278 |
| 2029 | 5-7 | 187-337 | 924-1622 |
| 2030 | 5-7 | 187-337 | 1121-1975 |
* NPEC「China’s Civil Nuclear Sector : Plowshares to Swords?」を参照に筆者作成
NPECは、表2中の2030年時点の高速増殖炉によるプルトニウム生産の累計量(太字)、現在保有しているとみられるプルトニウムと二つの再処理工場の稼働によって新たに生成される量を追加し、2030年末時点の中国の兵器用プルトニウムの推定値を2.9トン±0.6としている。核弾頭830発±210に相当する[14]。米国防総省の「2030年までに1000発の核弾頭保有の可能性」という分析が、今後の中国のプルトニウム増産見込みと合致していることがうかがえる。
3.中国の核戦略の変化
(1) 最小限抑止から相互確証破壊へ
中国によるプルトニウム増産が米国や近隣諸国の疑念を招くのは、その活動自体が不透明なうえ、中国の核戦略の変化と結びついているとみられるためである。
中国は1964年、核実験に成功して以来、核攻撃に対する最低限の報復能力を持つことで抑止力を確立する最小限抑止政策を志向してきた。具体的には、米国あるいはソ連からの第1撃に耐えて残存した核弾頭により、米ソの大都市への反撃能力を担保する。経済力で劣る当時の中国の実情に鑑み、第2撃で相手も確実に破壊できる「対称な均衡」ではなく、大都市への反撃力により、相手に核使用を思いとどまらせる「非対称な均衡」だった[15]。
しかし、冷戦終結以降、米国が核兵器の近代化を進め、2001年にはロシアとの間で締結していた弾道弾迎撃ミサイル制限条約(ABM制限条約[16])を破棄し、ミサイル防衛の強化を図ったことにより、中国が最小限抑止を維持してきた前提が崩れた。米国への都市攻撃の主力となる核弾頭ミサイル「東風5号」(射程12,000キロ)は固定式であり、米国の偵察衛星による情報収集能力により、先制攻撃に対するぜい弱性を持つ。さらに、米国本土のミサイル防衛システム配備により、第1撃で残存したミサイルも無力化される可能性があり、中国の第2撃能力の確保は容易ではなくなった[17]。
そのため、中国は核弾頭の保有数を引き上げ、運搬手段も多様化することにより、米国との間で相互に決定的な打撃を与える能力を保有し、勢力均衡を図る戦略的安定性を追求し始めた[18]。1999年、移動式のミサイル「東風31号」(射程8,000キロメートル)の実験に成功したほか、「東風5号」は複数個別目標再突入弾頭(MIRV)化を進めた。さらには、極超音速ミサイルの開発など、ミサイル防衛システムを突破できる兵器の開発を進めている[19]。
(2) 核の透明性をめぐる問題
この中国の核政策の変更もまた、不透明な形で進められている。
二大核兵器国である米国、ロシア(旧ソ連を含む)は二国間条約により、実戦配備される核弾頭数や運搬手段の保有数、場所といった定量情報を交換し、双方の検査官による検証措置を義務付けること、ミサイル発射実験を通告すること、双方の技術(主に偵察衛星)による監視を認めることで、核の「透明性」を確保し、偶発的な核戦争の防止など、核リスクの低減を図ってきた。
一方、中国は米ロ間の核の軍備管理をめぐる条約に加わっておらず、多国間条約であるNPT再検討会議の場を含め、核戦力の実態を全く公表していない。この状況に対し、中国は「核兵器に関して意思の透明性を有しており、定量情報の公開は必要ない」との立場を取っている。
「意思の透明性」とは、中国がNPTで核保有を認められた五か国(米国、ロシア、中国、イギリス、フランス)のうち唯一、無条件の核兵器の先制不使用[20]を宣言していることを指している。「いかなる場合も核兵器を先制使用しないとの国家意思は明確であり、最小限の第2撃能力しかもたないのだから、米ロと同様の基準で運搬手段の保有数や場所を明らかにすれば、国家安全保障が成り立たない」と主張している[21]。
表 3:世界の核弾頭数(2021年6月現在)
| 国名 | 全弾頭数 | 作戦配備 |
|---|---|---|
| ロシア | 6,260 | 1,600 |
| 米国 | 5,550 | 1,800 |
| 中国 | 350 | 0 |
| フランス | 290 | 280 |
| イギリス | 225 | 120 |
| パキスタン | 165 | 0 |
| インド | 160 | 0 |
| イスラエル | 90 | 0 |
| 北朝鮮 | 40 | 0 |
| 合計 | 13,130 | 3,800 |
* 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)『世界の核弾頭一覧』(2021年度版)を元に筆者作成
この主張に沿うように、先制不使用政策の下、敵の核攻撃がなされた後に報復するとの考えから、中国は核弾頭と運搬手段を分離して保管しているとみられる。新戦略兵器削減条約(新START条約[22])など、過去も含めた米ロ間の条約の定義に基づけば、中国の作戦配備の核はゼロになる(表3参照[23])。
とはいえ、核搭載ミサイルのMIRV化をはじめ、近年の中国の核戦力の整備状況は、先制不使用を中核とする核政策が維持されるのか、国際社会に疑問を抱かせている[24]。
4.中国の核戦略の変化がもたらす影響と求められる対応
(1) 中国の核軍拡の影響
中国の核戦略の変化や軍拡は、軍事的にも核不拡散の上でも、国際社会に深刻な影響を与え得る。軍事面では、中国が米国との間で「相互確証破壊」を確立できると認識すれば、アジア地域の安全保障問題に対する米国の介入を抑止できると判断し、力による現状変更を含めた高圧的な行動を引き起こす懸念がある。
核不拡散体制への影響も深刻である。NPTは第4条で、非核兵器国が核物質を民生利用することを「奪い得ない権利」と定める一方、第3条で、「核物質が核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するため、非核兵器国はIAEAの保障措置(監視、査察)を受諾する」ことを規定している。核兵器国は保障措置の対象外であり、非核兵器国側から「核兵器取得の選択肢を放棄して、NPTに加盟したにもかかわらず、非核兵器国のみに厳しい監視や査察が課せられるのは公平でない」との不満が高まっている。中国がIAEAの目が届かないところで、本来民生利用すべきプルトニウムを軍事転用すれば、イランなど核開発に意欲を見せる国が追随しかねない。
(2) 求められる対応と日本の役割
日本の新防衛大綱2019年版は、中国の核軍拡を念頭に、「核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とする米国の拡大抑止が不可欠であり、我が国は、その信頼性の維持・強化のために米国と緊密に協力していくとともに、総合ミサイル防空や国民保護を含む我が国自身による対処のための取り組みを強化する。同時に、長期的課題である核兵器のない世界の実現へ向けて、核軍縮・不拡散のための取り組みに積極的・能動的な役割を果たしていく」と表明している。短期的には両立しがたい抑止力の向上と核廃絶を追求する姿勢である。
米国の核抑止力を中心とする拡大抑止の信頼性強化のために、具体的に日本が何をなすべきかの検討は抑止の専門家に譲るが、日本にとっては、米ロ間で締結されていた中距離核戦力全廃条約(INF条約)が2019年に失効したことにより、中距離巡航ミサイルの配備を強化するロシア、核・ミサイル開発を加速させる北朝鮮にも対応する必要がある。日本は、中国の核軍拡が加わったこともあり、自国が世界で最も厳しい安全保障環境に置かれるとの認識を持つことが重要だろう[25]。
核軍縮および核不拡散への日本の貢献としては、NPT体制の信頼性を維持し、核軍備を管理していくため、多国間の枠組みで核の透明性を向上させることを提唱すべきである。
日本はオーストラリア、ドイツ、カナダなど現実的な核軍縮路線をとる10カ国で構成する国際会議「軍縮・不拡散イニシアティブ」(NPDI)の一員であり、NPDIは、核兵器国の核弾頭数や運搬手段の状況報告のための標準報告フォームを提案している[26]。中国を含めた核兵器国の配備状況について、NPT再検討会議の場で他国が理解できる仕組みを作ることは、核軍縮へ向けた具体的な議論を行う第一歩になる。
原子力の民生利用を核兵器開発にリンクさせない点でも、日本の知識や経験を生かせる。日本は核燃料サイクル施設によるプルトニウムの分離と高速増殖炉での再利用を認められた唯一の非核兵器国である。それは、日本が世界で唯一の戦争被爆国として、軍事転用可能な核物質を利用するにあたり、IAEAに全面協力し、核不拡散と原子力民生利用の両立に尽力してきた実績が認められたためである。今後、日本はNPTでIAEAによる査察を義務づけられていない核兵器国に対しても、兵器転用が可能な高濃縮ウランやプルトニウム、およびそうした物質の生成に関する施設の運営について、IAEAへの報告の義務付けなど透明性の確保を求め、非核兵器国の不満を代弁するべきである。さらには、日本が蓄積してきた技術を非核化や核軍縮検証などに活用することで、原子力民生利用の模範国、核不拡散を推進する国として国際的な信頼の向上につなげることができるだろう。
中国をNPTに引き入れたのは日本である。1989年の天安門事件により、国際的に孤立した中国に対し、円借款を再開する環境整備として、国際社会への貢献を求め、1992年に加盟を実現させた[27]。その日本外交の成果を生かすためにも、多国間の枠組みの中で、核不拡散の強化と核軍縮への道筋を示すべきだろう。
(了)
1 NPT第6条「各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する」外務省「核兵器の不拡散に関する条約」[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S51-0403.pdf]
2 Office of the Secretary of Defense, “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2020” [https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF]
3 Office of the Secretary of Defense, “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2021” [https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF]
4 Henry D. Sokolski, “China’s Civil Nuclear Sector: Plowshares to Swords?”, 2021, pp.6-22.
5 張会(Hui Zhang)「中国のプルトニウム・リサイクル計画-現状と問題点」『New Diplomacy Initiative』2022, Vol15, 1頁。
6 PWRは原子炉の中で発生した高温高圧の水を蒸気発生器に送り,そこで蒸気を発生させてタービンに送り、回転させることで発電する。日本の原子力発電所では、PWRのほかに、原子炉内で発生した蒸気を直接タービンに送る沸騰水型原子炉(BWR)がある。
7 一般社団法人原子力産業協会プレスリリース「世界の原子力発電開発の動向2021年版を刊行」2021年5月28日。
8 Mark Hibbs, “The Future of Nuclear Power in China”, 2018, p.77.
9 同上。
10 「中国のプルトニウム・リサイクル計画-現状と問題点」1頁。
11 「夢の原子炉 もんじゅ消滅で敷地片隅に新研究炉 地元は温度差」『毎日新聞』2022年4月30日(会員限定)。
12 高速炉の開発は、実験炉、原型炉、実証炉、実用炉と段階的に進められる。実験炉で技術の基礎を確認し、原型炉で発電技術を確立して、実証炉で経済性を見通した上で、商業用の実用炉に至る。
13 “China’s Civil Nuclear Sector: Plowshares to Swords?”, p. 16.
14 同上。
15 秋山信将、高橋杉雄『「核の忘却」の忘却の終わり~核兵器復権の時代』勁草書房、2019年6月、73-92頁。
16 ABM条約(Anti-Ballistic Missile Treaty)は米ソ間で1972年10月に発効した。戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイル・システムの開発、配備を厳しく制限する。双方の防御態勢を敢えてぜい弱なものに保ち、核攻撃を相互に抑止しようとする目的で締結された。『軍縮辞典』(日本軍縮学会、信山社)参照。
17 『「核の忘却」の忘却の終わり~核兵器復権の時代』78-80頁。
18 “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2020”, pp.85-86.
19 『「核の忘却」の忘却の終わり~核兵器復権の時代』81-92頁。
20 武力紛争中、相手国より先に核兵器を使用しない政策。ただし、相手国が先に核兵器を使用した場合に、核兵器で反撃する選択肢は残している。先制不使用の体制が確立されれば、核兵器の役割は他の核兵器保有国による使用抑止に限定され、核軍縮を促す効果を持つ。中国は1964年10月の核実験成功から一貫して、いかなる場合においても核兵器を先に使用しないという無条件の先制不使用を宣言してきた。『軍縮辞典』参照。
21 西田充『核の透明性』信山社、2020年11月、260-285頁。
22 新戦略兵器削減条約(New Strategic Arms Reduction Treaty)」は2009年12月に失効した「第1次戦略兵器削減条約(START1)」の後継として10年4月に米国、ロシアの間で調印され、翌11年2月に発効した。18年までに両国の戦略核弾頭の配備数を1550発以下に、ミサイルや爆撃機などの運搬手段の総数を800以下(うち配備数は700以下)に削減することなどを定めている。条約は21年2月に期限を迎えるたが、5年間の延長で両国が合意した。『軍縮辞典』など参照。
23 『核の透明性』260-285頁。
24 同上。
25 『「核の忘却」の忘却の終わり~核兵器復権の時代』235-249頁。
26 『核の透明性』169-201頁。
27 太田昌克『核の大分岐 既存秩序の溶解か新規秩序の形成か』かもがわ出版、2021年6月、146-152頁。