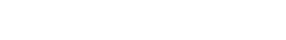論考シリーズ ※無断転載禁止
SPF China Observer
ホームへ第23回 2020/02/14
中国にとっての香港ジレンマ
はじめに
逃亡犯罪人引渡条例案の改正に端を発する香港の反政府抗議デモは、2020年に入っても元旦に実施されるなど、依然として収束にはいたっていない。2014年の雨傘運動とは異なり、今回のデモは一部の若者の抗議活動が暴力化し警察との激しい衝突が続くなど、1997年の香港の中国への返還以来、最大の抗議活動となっている。本稿においては、長期的観点から、今回のデモの背後にある中国—香港関係の構造的変化と、それが今後の中国にとって持つ意味について考えてみたい。
1. 抗議デモの特色と展開
当初香港の抗議活動は平和的に行われ、2019年6月には主催者発表で参加者が100万人を越えるなど大規模化した。しかし夏以降、一部のデモは次第に暴力化し、参加者の掲げるスローガンのなかに は「時代革命」や「自由香港」、「香港解放」など、中国との関係ではタブーとされるような表現もみられるようになった。当初の平和的なデモには多くの老若男女が参加していたが、夏以降の暴力的な活動は若い世代が中心である。民主主義の根付く市民社会の香港では、これまでもしばしば民衆の抗議デモは発生したものの、暴力行為に対しては一般に心理的抵抗があった[1]。2014年の雨傘運動の際にも、過激なデモ活動に対して批判が高まり、運動は次第に市民社会からの支持を失っていった。しかし、今回の暴力行為に参加している若者は十分な覚悟と信念をもっており、暴力がエスカレートしているにもかかわらず、市民社会も一定程度の同情と理解を示し、それを許容しているようにさえ見える。
抗議デモが一部暴徒化しつつあった夏以降、香港に隣接する大陸側の深圳で武装警察が訓練する映像が流されると、人民解放軍や武装警察の投入によるデモの鎮圧、天安門事件の再現のような事態を心配する西側メディアの報道も出始めた。しかしながら、中国の指導者は、デモに対する心理的圧力として軍や武装警察の存在をアピールすることはあっても、よほどのことがない限り、実際にそれらを香港に投入して運動を鎮圧する意図は当初からなかったといわれる[2]。
中国当局はその代わりに、香港政府や警察にその不人気で難しい役割を担わせようとした。10月末に北京で開催された中国共産党中央委員会第4回総会(四中全会)において、香港問題への対処が議論され、中央の姿勢が明確になるとともに、その後の香港政府、警察のデモへの対応は一段と厳しくなった。それまでこの問題の正面に立つことのなかった習近平は、四中全会以降、キャリー・ラム香港行政長官と11月に上海、次いで12月に北京で会見し、辞任の噂もあったラム長官を信頼し香港政府を支える姿勢を示した。更に、外遊先のブラジルから香港問題に関するメッセージを発表するなど[3]、習近平自身が香港問題に直接関与する姿勢を強め、圧力を高めた。その頃、香港に駐留している人民解放軍は、駐留地を出て路上で掃除をするパフォーマンスを見せた。また、香港警察は大学に立てこもる学生の最終的な排除に動き、激しい衝突が生じた。しかし、たとえ中国がデモの鎮圧に直接介入しなくとも、背後から香港政府を押して力で抑え込もうとする構図は、「一国二制度」への信頼を損ない、市民の反発を高める結果となった。そしてそれは、11月末に実施された香港区議会選挙において、民主派が8割以上の議席を得る圧倒的勝利を収めたことにつながったのであった[4]。
2. 中国政府の対応
今回の経緯を見ると、香港政府も中国当局も、当初反政府デモがここまで拡大するとは考えておらず、初期段階での判断ミスが後手後手の対応を生んだ。香港政府は9月に入り逃亡犯罪人条例改正案 の撤回を表明したが、もう少し決断の時期が早ければ、ここまでデモが拡大することにはならなかっただろう。また、この過程で背後にある中国指導者の香港に対する意識も、香港政府の判断に微妙な影響を与えたといえる。かつての中国の指導者は、しばしば香港問題について細やかな配慮を示してきた。返還前の1995年に、当時の李瑞環政治局常務委員は、香港は重要かつ特別であるがゆえに丁寧に扱わねばならないと強調し[5]、香港市民を安心させた。また、朱鎔基総理は、2002年11月の香港代表との会見において「返還の後、もし我々の手で香港を壊してしまえば、民族の罪人になってしまう」とまで述べた[6]。これら指導者に比べれば、今日の習近平には、かつての指導者たちのように香港人の気持ちを汲んで寄り添う姿勢や繊細な配慮がみられず、これが間接的に香港の人々の反発につながっているともいえる。
中国はパブリック・ディプロマシーの強化を図ってきているにもかかわらず、近年は失敗を続けている[7]。米国の中国政治研究者であるシャンボー(David Shambaugh)は、中国のこれまでの姿勢として、他人が自分を見るようには自分で自分を客観的かつ批判的に見ることができず、その結果、他国からは信頼を得られていないと手厳しい[8]。また、そもそも中国の政策決定者たちは、自ら民主主義を体験していないがゆえにその本質を理解できず、市民社会への対応には慣れていない。その結果、今回のデモに際しても、香港市民に対し丁寧かつ効果的なメッセージを発することができないのみならず、情勢を的確に読むことができず、台湾問題との連動さえ招いてしまった。
香港大学の中国外交研究者である胡偉星は、今後の中国の安全保障を考える際、「ソフトな脅威」すなわち文化やイデオロギー、体制に対する脅威といった問題にも着目する必要があると指摘する[9]。目下のところ香港のデモが直接中国大陸に輸出され、中国の体制を揺さぶるような事態になるようには見えない。また、中国当局もそうならないよう厳格に管理している。一方で、香港は、中国の主権下にありながら、言論の自由を含む比較的自由な体制が保障されているがゆえに、今後とも反政府活動が起きた際には、自由なメディアを通じ世界に向け中国のネガティブな情報が発信、拡散される。その結果、国際社会において、中国の対外イメージが長期的に侵食され続けることになるのである。
近年、習近平が大国外交を志向し「一帯一路」のような積極的な政策を展開する一方で、香港、台湾も含めた対外関係全般へのきめ細やかな感受性が低下しつつあるようにも見受けられる。また、習近平が自己の権威を高め、「トップダウン」の政策決定を強調するようになった結果、政権内部で異論を出しにくい、都合の悪い情報を上げにくい、その結果情勢分析にバイアスがかかるといった、これまでも指摘されてきた中国の政策決定過程の欠点が更に顕在化している。先に述べた11月の区議会選挙においても、中国側は親中派がここまで大敗するとは事前に予想していなかったようである[10]。
3. 中港間の認識のズレ
今日、GDP規模のみを見れば、香港はすでに上海のみならず深圳にも追い抜かれてしまっている[11]。返還時に香港のGDPは中国全体の1 / 5を占めたが、2018年時点で1 /37にまでその割合は低下した。しかし、今後、中国政府がいかに上海や北京の金融都市建設に力をいれたとしても、国際金融都市としての香港に取って代わらせることはできない。香港ではコモンローにもとづく「法の支配(Rule of Law)」が根付き、透明性があり予測可能性の高いビジネスが可能だからである。ここに香港と中国大陸におけるソフト面での決定的な違いがある。しかし、多くの中国人は経済のハード面、あるいは量的側面からのみ香港をとらえがちであり、今日の香港の若者の不満についても、経済格差や住宅問題に根源があるとみる傾向が強い。自由な空間が徐々に侵食されつつあるという香港人の閉塞感は、大陸からはなかなか理解されない。
返還をめぐる英国の対香港政策を研究しているライト(Dalena Wright)によれば、1984年の中英合意調印式の際に、マーガレット・サッチャーは鄧小平に、返還後の「一国二制度」の期間をどうして50年としたのかと尋ねた。これに対し鄧小平は、「その頃になれば、私たちもあなた方ともうそれほど変わらなくなっているでしょう」と答えたということである[12]。高層ビルが立ち並び経済的に豊かになった今日の中国の大都市と香港とを比べ、大陸の中国人はもう変わらなくなったと感じるかもしれない。しかし、デモに参加しているような香港の若者たちは、香港と深圳との間にある境界を越えて中国側に入ったとたん、グーグルやフェイスブック、ツイッターなど自分たちが日々スマホで慣れ親しんだSNSが遮断され、そこが自由な情報が全く入らない異世界であることを身をもって知っているのである[13]。
今日、香港社会における分断も深刻である。ある香港人の国際政治学者は、香港はサラエボのようになってしまったと筆者に述べた。歴史的に多民族で構成されるバルカン半島は、第二次大戦後チトー大統領のもと民族間で一定の融和が進み、我々はユーゴスラビア人であるというアイデンティティが徐々に形成されつつあった。しかし、ユーゴ崩壊後、それぞれの民族や宗教の「違い」をめぐって人々は再び争い始め、サラエボを首都とするボスニア・ヘルツェゴヴィナは戦場となった。その後、これは国際政治学者の間でアイデンティティをめぐる紛争の象徴的事例として扱われるようになった。同様に、香港における「香港人」と「中国人」との間にはこれまでも感情的な対立はあったものの、今回の反政府デモを通じ亀裂はさらに深まった。元来香港人は、隣接する広東省から来た人々が中心で中国にルーツを持っていた。しかし、香港生まれの若い世代は、ますます自分を中国人ではなく香港人であると認識するようになっており、世代間のアイデンティティ・ギャップが深刻化している。
4. 見えてきた2047年問題
2047年問題とは、1997年の香港返還から50年間は「一国二制度」を維持するとした中英合意のコミットメントが期限を迎えることである。一般にこれまでは、2047年以降も「一国二制度」は延長され、維持されるであろうとの楽観的な見方がむしろ支配的であった。中国にとって、自由で開かれた香港は便利な存在である。国際経済とリンクした香港の透明性の高い金融システムは、中国経済全体にとっても引き続き不可欠である。また、中国の一部エリート層、富裕層は香港に口座を有し自己の財産を送金するだけでなく、さらにはマネーロンダリングまで行う者もいるといわれる。一方で、指導者のみならず多くの中国人からみれば、今回のデモを通じ、香港人が享受する政治的な自由は、もはや過剰であるとも感じているであろう。
今回のデモにはリーダーやしっかりした組織が不在だといわれる。にもかかわらず、どうしてこのように多くの若者が自発的に立ち上がり、長期にわたって抗議活動を繰り広げているのであろうか。抗議の決意と連帯を示す「人間の鎖」には、多くの中高生までもが参加している。これら若者の間では、将来の香港の見通しはさらに悪くなるという懸念が共有されている。そして、その先に2047年問題が存在するのである。今デモに参加している若者たちは、47年以降も香港で、それぞれ自分の人生の重要な時期を生きなければならない。明確に意識しているか否かは別として、47年問題は若者たちの将来への意識にうっすらと覆いかぶさりつつあるのである。
では、47年問題は、今後どのようにして検討が開始されるのであろうか。香港は行政上、香港、九龍、新界の三つの地区に分けられる。かつての英国統治下においては、清朝から割譲された、つまり国際法上の返還義務のない香港や九龍とは異なり、新界地区は1898年の租借条約によって清朝から99年の期限で借り上げられた土地であった。99年という期間は、当時ほとんど永遠という感覚であった。ところが、その返還期限が本当に来てしまうというのが1997年の香港返還問題の起源である。実際に、返還問題が意識されるようになったのは、香港での土地リース契約のような超長期の民間契約が、97年の租借期限以降どうなるのかという実務的な関心からであった。このような議論が出発点となり、その後、中英両国間の交渉に発展した。現時点では2047年はまだまだ先であるが、もうしばらくすれば、かつてと同様に、先ずは長期の見通しが必要となる経済活動の実務において、現行の「一国二制度」がそのまま維持されるのか否か、水面下で問題意識が高まってくることになる。97年の返還以降の香港の姿は、これに先立つ1984年の中英合意と、これを踏まえて90年に成立した香港のミニ憲法ともいえる香港基本法によって形作られた。したがって、長期的なビジネスの予見可能性や社会的な安定を考えれば、47年問題についてもかなり早い時期に解決しておく必要がある。しかし、今回のデモはこのような問題を表立って提起することを当面困難にしたともいえるのである。
おわりに
これまで香港は、返還後も主権が名目上中国に移管されただけで、「一国二制度」によって、かつての英国統治下と同様の経済活動や文化、生活が維持されてきた。しかし、今日、中国の国力が向上し、また、香港に滞在する大陸出身中国人も増加し、中国の存在感が高まった。その結果、香港は「中国化」を拒絶する香港の人々の意志、更にはこれを支持する西側勢力と中国の力がぶつかり合う場所となってしまった。
過激な学生の活動は今後一時的には低調になるかもしれない。しかし、平和的なデモにあれほど多くの人々が参加したことからわかるとおり、自由の制限や中国共産党の干渉に対する香港市民の反発は根強い。2014年の雨傘運動と今回のデモが政治改革をめぐる不満で底流でつながっているように、社会全体に不満は蓄積している。したがって、今後、大幅な政治改革が実現される道筋が見えてこない限り、市民の不満を解消することはできない。一方で、デモ参加者が求める「五大要求」のうち、完全普通選挙の実現は、中国から見れば香港への統制が効かなくなる懸念が存在する以上、実現可能性は低い。中国当局と香港の人々との間の信頼が大きく損なわれているなかで、中国が関与を強めれば香港の人々の反発を招く。その一方で、香港へのこれまで以上の自由の供与は、中国自らの不安を高めることにつながる。かくして 中国の対香港政策のジレンマは当面続くことになる。
(脱稿日 2020年1月29日)
1 尖閣問題をめぐる1996年の香港での「保釣運動」の際にも、反日抗議活動が高まった。しかし、在外公館として国際法で保護される香港の日本総領事館に一部デモ隊がなだれ込んで以降、香港市民の間にやりすぎとの反省が広まり、これを一つのきっかけに抗議デモは収束していった経緯がある。
2 米国コロンビア大学の中国政治研究者であるネイサン(Andew J. Nathan)によれば、習近平が9月に中央党校で演説を行った際に、そこでのやりとりの内容の一部は報道されていないものの、解放軍の投入に否定的な発言をしたと伝えられる。“How China Sees the Hong Kong Crisis – The Real Reasons Behind Beijing’s Restraint,” Foreign Affairs, September 30, 2019 (https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-09-30/how-china-sees-hong-kong-crisis, accessed on Jan.27,2020).
3 「国務院港澳弁発言人発表談話表示 習近平主席巴西講話発出中央政府対香港止暴制乱工作的最強音 将堅決貫徹落実」『新華網』2019年11月15日、
(http://www.xinhuanet.com/gangao/2019-11/15/c_1125237646.htm、2020年1月28日最終アクセス) 。
4 もっとも香港の区議会議員選挙は、小選挙区制度の特性から勝敗がはっきりと分かれる結果となったが、実際の得票率では民主派が57%、親中派が41%であった
5 「李瑞環論香港-従実際出発做好香港工作」『中央人民政府駐香港特別行政区聯絡弁公室』1995年3月13日、
(http://www.locpg.hk/zyzc/2006-01/05/c_125991883_3.htm、2020年1月27日最終アクセス)。
6 その際の演説の動画は、香港の抗議活動が激しくなるなか、朱鎔基が10月の国慶節軍事パレードの閲兵式を欠席した直後にネット上で拡散した。(https://www.youtube.com/watch?v=JvBtPQ30WTE、2020年1月27日最終アクセス)。
7 パブリック・ディプロマシー(中国語では「公共外交」)とは、政府を相手とする通常の外交とは異なり、相手国や第三国の国民の民意に働きかけ共感を得ることにより、長期的に外交を有利に展開する外交手段をいう。
8 David Shambaugh, “U.S.-China Rivalry in Southeast Asia – Power Shift or Competitive Coexistence,” International Security, Vol.42, Issue 04, Spring 2018, p.125.
9 Weixing Hu, “Xi Jinping’s Big Power Diplomacy and China’s Central National Security Commission (CNSC),” Journal of Contemporary China, VOL. 25, NO. 98, p.168.
10 香港において中国政府を代表する駐香中央政府連絡弁公庁(中聯弁)は、現地情勢を分析して中央政府に上げる役割もあるが、その中聯弁主任の王志民は1月に入り解任された。
11 “Hong Kong economy surpassed by neighbor Shenzhen for first time in 2018 as China’s hi-tech hub soars,” South China Morning Post, February 27, 2019 (https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2187949/hong-kong-economy-surpassed-neighbour-shenzhen-first-time-2018, accessed on Jan.28,2020).
12 米国ワシントンD.C.にあるシンクタンクのスティムソン・センターで行われた香港問題に関するパネルディスカッションにおけるライトの発言。“The Reality and Future of Hong Kong Crisis,” The Stimson Center, September 25, 2019 (https://www.stimson.org/event/the-reality-and-future-of-the-hong-kong-crisis/, accessed on Jan.27, 2020) .
13 上記パネルディスカッションにパネリストとして参加した中国政治研究者ハーディング(Harry Harding)による指摘。